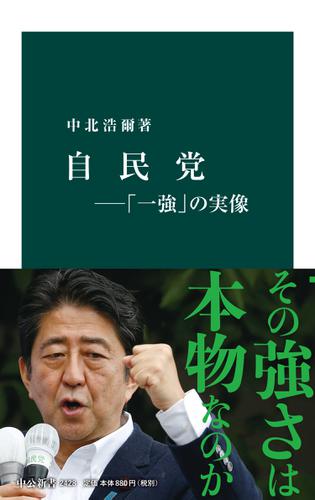
総合評価
(20件)| 6 | ||
| 10 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ自民と維新が連立で正式合意をした夜に読了。公明党が連立離脱を表明した10月10日に今こそ読んでおかなくちゃ、と図書館に申し込んで取り寄せてから速攻読書。以前同じ著者の同じ中公新書『日本共産党 「革命」を夢見た100年』を読んでから気になっていた本でした。2017年の出版なので1982年の第一次中曽根内閣から2016年に発足した第三次安倍内閣までの34年の自民党の変化を派閥、総裁選挙とポスト配分、政策決定プロセス、国政選挙、友好団体、地方組織と個人後援会という視点で詳細に分析していきます。自公連立の成立が1999年でその利害関係についての解像度も上がりました。『「自民党は自分の手足を食べさせて公明党を取り組んでいる状況にある」と自嘲気味に語る自民党本部の選対関係者…』の記述も印象的でした。また企業献金の歴史や総裁選の仕組み、世襲議員の強さの意味、宗教団体との関係など、2025年にそのまま繋がるテーマばかりで、今、起こっている現象の地下茎を垣間見たような気がしました。新しい連立はまた自民党という看板の中身を大きく変えていくと思います。中北浩爾には、ぜひ安倍退陣から2025年までの自民党の変遷を語って欲しいです。
5投稿日: 2025.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自民党の55年体制崩壊後〜安倍内閣までの分析。 2017年出版。 55年体制とその後の大勢の最も大きな変化の要因は、中選挙区制に変えて小選挙区比例代表制を衆議院に導入した1994年の政治改革にある、とする。 with chatgptでの簡単な理解 背景:なぜ「改革」が必要とされたのか 55年体制の限界:中選挙区制(1選挙区から3~5人選出)では、自民党の候補者同士が同じ区で競争する「同士討ち」が常態化。選挙は政策より「地盤・看板・カバン」(地元基盤・知名度・資金力)が重要で、派閥や企業・団体献金への依存が強まった。これが政治腐敗(リクルート事件など)や金権政治批判に直結した。 政権交代の現実化:1993年、自民党が分裂し、非自民8党派による細川護煕内閣が誕生。戦後初めて自民党が野党に転落。政権交代の正統性を担保する「公正なルール」が求められた。 改革の目的 ・「金のかからない政治」へ:中選挙区制では同じ党の候補者が競い合うために過剰な後援会活動やカネが必要だった。小選挙区制により、1区1人の原則 → 候補者同士の同党内競争をなくし、派閥・企業献金依存からの脱却をめざした。 ・政権交代の可能性を高める:中選挙区制は得票率に対して議席が分散しやすく、自民党が分裂しても「第一党」になり続けやすかった。小選挙区は「勝者総取り」の要素が強く、二大政党制や政権交代を促す仕組みになると期待された。 ・比例代表との並立:ただ小選挙区だけでは少数政党が壊滅するため、比例代表制を併用。これにより「死票」を緩和し、多様な民意も反映させるバランスを取った。 実際の政治的妥協 ・細川内閣が導入を主導し、与野党の妥協で「小選挙区300+比例200(当初案)」の形に。実際は小選挙区300+比例200→のちに小選挙区289+比例176へ微修正されて現在に至る。 「政治腐敗の温床=中選挙区制をなくす」ことが最大の大義名分だった。 結果と評価(その後) ・政権交代は実現(2009年、民主党政権成立)。ただし二大政党制は安定せず、自民党が再び一強状態に戻る。 ・金のかからない政治は十分達成されず、むしろ小選挙区で勝つための中央集権的・官邸主導の色合いが強くなった。 まずは派閥について:弱体化が進む。 経世会(田中角栄、ネットワーク強い、茂木)、宏池会(官僚系、岸田、林)、清和会(福田赳夫、森喜朗、小泉純一郎、安倍晋三、)で、清和会が強目な感じではあるが、全体的に無派閥議員が増え、3割程度に。2017年時点。 無派閥増加の経緯、2005年の小泉チルドレン、83名の新人議員は無派閥であることが推奨された。2009年政権交代での公約の派閥解消、野党転落によるポスト配分機能が意味なくなった、パーティー券の売り上げ減少、2012年公募による候補者選定。 派閥の特徴 ・非イデオロギー的:理念や政策が決定的に重要な意味を持たない。傾向はあるが。 ・制度化:メンバーの範囲が明確、会則などを持つ、選挙の際には独自の選対を持つ。 ほぼ政党であり、党中党と呼ばれるまでになる。 逆に、派閥の影響で、自民党の制度化は阻害され、自民党の運営は派閥の存在を前提とするものに。派閥均衡人事など。 これらは、党の統一を阻害する、総裁のリーダーシップを弱める、政策不在の金権・密室政治、適材適所を妨げるなど批判された。一方で、多様性の担保や擬似政権交代的に自民党の長期政権が続いた、という見方もある。 派閥の機能は大きく4つ ・総裁選挙での候補者擁立と支援 ・国政選挙での候補者擁立と支援 ・政治資金の調達と提供 ・政府・国会・党のポストの配分 総裁選でリーダーを支援する代わりに、国政選挙・お金・ポストなどを受け取るという構図。 派閥の始まりは、1956年の総裁選、それまで自由党・民主党のリーダーをそれぞれ推し、総裁が決めれてなかったが、それを決める。それまで保守政党の党首は、前党首を含む長老が話し合いで決めていたが、自民党の結成に際して、党所属の国会議員と都道府県連選出の代議員が投票権を持ち党大会で総裁が出る、ということが決まった。 そこで、誰を支持するか?で派閥ができた。 あと、中選挙区制により、各地区に複数人の自民党候補が立つ(そうしないと過半数取れないので)ことになり、そうすると選挙運動で党組織に頼れないので、派閥に支援を求めることになった。同志討も多く、そのため個人後援会(有権者を直接的に組織化するもの)を作らなければならなくなり、その際に必要な資金を捻出する上で、派閥に頼る必要性が出てきた。 →この総裁選と中選挙区制により、派閥が広まった。 総裁選での票どりのために参議院にも派閥が広まり、また田中派が主導して、派閥の組織化・機能強化が進む。 e.g. ・派閥幹部による上納金 ・幅広い分野の族議員を揃え、陳情処理能力を高める ・派閥がパーティーで政治資金を集める(企業や団体の人が参加し、政治家との人脈作りに使った) ・所属議員の秘書を、秘書軍団化する。 1980年代はさらに組織化が進み、派閥は領袖専決ではなく、機関中心主義へ また、派閥間についても、五大派閥の事務総長による会議(師走会)が毎月一回開かれ、党の重要事項の決定にあたり根回しなどするようになった。派閥間の競争も失われる。 派閥衰退のきっかけが、1988年のリクルート事件 → 小沢一郎が、腐敗防止、さらには政治的リーダーシップの強化の必要性をといた。小沢らの羽田派が自民党から離れ、細川さんを首相とする非自民連立政権ができたことで1994年に選挙改革が実現し、中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に → 派閥数の増加 五代派閥にまとまってたのは、中選挙区での最大当選者数が 5だったから。 ただ小選挙区制になり、派閥の機能が「ポスト配分」「政策勉強の場」「人脈形成」にシフトするにつれ、小規模でも独自色を出す派閥が生まれやすくなった。大派閥に集約する必然性がなくなり、リーダーごとにグループを形成するようになった。 → 選挙で重要なのは、派閥からの応援よりも党の公認、になった。資金力も下がってきて、選挙でもあまり役立たなくなって、、という感じ。 今になると、派閥との政治資金のやり取りは若手は若干プラスだが、中堅以上は負担の方が多いくらいらしい。現在の派閥の財源は、政治資金パーティ。 資金に関しては、政党助成金の分配が1994年に始まり、各政党は政党交付金への依存を強め、その配分権を有する党執行部への依存が強くなった。 また、党から派閥への資金提供も2010年には亡くなり、個人に対して党がお金を渡すようになった。 → 現在の派閥は人的ネットワークとしての役割を果たしている。 総裁選 政治改革前までは、派閥の領袖同士の派閥間の争いだったが、小泉首相の派閥を軽視しつつ、強力な政治的リーダーシップでの活躍を背景に、国民人気がある人が選ばれる方向になった。「選挙の顔」を選ぶ。 さらに、非イデオロギー的な派閥ではなく、理念グループ、の影響力が強まる。 小選挙区制では、政党の政策も重要だから。 派閥も選挙の顔になりうるような人を領袖に選ぶようになってきた。 政党内のポストの配分も、以前は派閥均衡と当選回数主義だったが、最近は民間や能力主義、女性などの抜擢人事も増え、総理総裁の人事権が強まってきている。小泉政権が決定的な変更を生んだ。今も派閥からのリストみたいなのはあるけど、その優先順位はかなり低い。 副幹事長、副政調会長、国対副委員長は、依然として派閥から送り込まれているものの、副大臣や政務官人事についても、派閥の意見は数ある重要なことのうちの一つになってきている。さらにこれらの任命が従来の幹事長から、官房長官の仕事に移ってきており、官房長官の副は別に派閥から来てるわけではないので、さらに派閥の影響力は落ちている。 今は、希望役職を議員が提出したものを見て、調整したりしてるらしい。 →結論として、人事で任命権者の決定権が自室化し、最高権力者たる総理・総裁の権力が高まっている。 例外2つ:参議院自民党と公明党 参議院改革は政治改革をよそにほとんど進んでおらず、三代派閥の優位が現在も残っている?←←これは現在においては、参議院でも派閥の力は完全に弱まっている。 公明党もポスト1つ 幹事長は、選挙の指揮、党財政の管理、国会対策、党ポストなどの人事、など幅広い仕事。総裁は首相も兼ねるので。 安倍政権の人事は絶妙で、選挙のライバルや派閥の領袖をいい感じに入れて、反発が起きないようにしていた。 政策決定プロセスについて with chatgpt 官邸主導:続いています。中枢の装置である内閣人事局は存続しており(幹部人事の一元管理)、2025年春にも運用見直しの「最終提言」は出たものの、“官邸の人事・政策統合”という骨格は維持されています。 人事院 内閣官房 事前審査制(与党の事前了承):これも続いています。内閣提出法案や予算案の閣議決定の前に、自民党の了承(政調→総務会)が事実上の提出前・成立前審査として機能しており、2024年記事や与党側の説明でも“事前に与党審査が必要”と明記されています。 ただし、様相は少し変化しています。 政権の議席状況に応じた“与党+他党”協議 2024~25年は維新・国民民主との事前調整が政策によって入り、従来の「政府・自民・公明の内側完結」だけでは収まらない局面が増えました(教育無償化や予算修正など)。=「与党事前審査」は存続しつつ、外部との事前調整が上乗せされる形です。 官邸主導への“見直し”圧力 官邸主導を強めた内閣人事局の運用については、見直し提言や改革論が相次いでいますが、制度そのものの廃止・大転換までは踏み込んでいません(=官邸主導の基盤は継続)。 人事院 リクルートワークス研究所 事前審査制の是非論が再燃 国会の形骸化を招くとの批判は強く、制度見直しを求める社説・提言や、維新などからの制度改革案も出ています。=“慣行は続くが、透明化・見直し論は強まった”。 朝日新聞 日本維新の会 令和臨調 要するに、枠組みは続いているが、運用は「連立+政策ごとの横連携」へ分散、官邸主導は「運用是正」の段階――というのが2025年現在の姿です。 自民党の事前審査:政調会の部会から始まる。部会:政府省庁及び国会の常任委員会に対応して設けられている。 部会だったという言葉が使われる通り、自民党の政策決定の中心は部会。法案の内容の修正も多くは、部会で行われる。 他にも部会に相当する機関として、調査会や特別委員会など省庁横断や、中長期的な課題に取り組む機関もある。 部会→政調審議会:部会から上がってきた政策案を審議し、承認する成長会の最高決定機関。 →総務会 党大会や両院議員総会にかわる自民党の常設的な最高議決機関。基本的にコンセンサスを重視し、誰でも参加できる上に、全会一致が慣行となっている。 総務会で可決された法案は、党議となり、閣議決定に進む一方、国会では党所属の衆参両院議員に党議拘束がかかり、造反は処分の対象。 部会→政審→総務会のプロセスが重要なのは、それを通じて重層的な調整がされているから。 部会:関連省庁との間の調整が行われる。内閣提出法案のキアンは基本的に官僚が行うが、部会での説明・答弁で、議員の発言を受けて官僚が字句を修正する。族議員の意向を聞きつつ作業を進める。ここで、自民党の議員は、部会を通じて法案や予算案に影響力を行使し、業界の意向を反映させるように努めている。 自民党政権は当初、官僚優位の政策決定を行なっていたが、1960年代後半から自民党の優位が強まり、1970年代末には決定的となった。なぜならば、議院内閣制を採用していることにくわえ、自民党政権が長期化したことにより、数年でポストが変わる官僚に対して、専門知識を豊富に蓄積した族議員が台頭したため。また、議員の方が官僚に比べて分業していないため、調整力があることも起因する。 なぜここまで合議が優先される中でも官邸がリーダーシップ取れるかというと、部会・総務会でも、挙手などの採決ではなく、議長が「こういうことになりました」と発言することで決められる、で、どうしても決まらない場合には、偉い人に判断を一任する、という形で通ることもある。だからトップダウンも行けてしまう 政府の政策決定のトップダウン化の数population目方 橋本行政改革(1990年代後半) ・省庁再編 ・内閣機能の強化:重要政策の方針について首相が閣議で発議権を持つ、内閣官房の強化、内閣府の設置(特命担当大臣が置かれる、経済財政諮問会議など重要会議の設置) 経済財政諮問会議では、骨太の方針(経済財政運営と、構造改革に関する基本方針)で予算編成がされるように。 従来は財務省が概算要求基準を作成して閣議をかけ、各省庁が概算要求を提出して始まった。
0投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ『日本共産党』に続き読んでみた。 良し悪しはわからないけれどどの党にも偏らず新書の範囲にあり得ない濃さをコンパクトにまとめていると思う
0投稿日: 2022.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ『日本共産党』の著者が描く、自民党の強さの正体。 組織内部、選挙戦略、支持団体との関係などから、自民党を支えるものの正体に迫る。 『日本共産党』に比して、私のような素人にはやや込み入った記載が多かった印象で、読み進めるには少し時間がかかった。それでも読後は、テレビややかましい街頭演説でしか知ることのなかったかの党がすこし立体的に見えるようになった。 時候がら、白眉と思われるのは支持団体との関係について書かれた部分。その中では宗教団体との関係にも触れられている。それを読んでわかったことといえば、特定の集団が自民党の政策を大きく揺るがすことはなく、影響力も限定されているということ。しかもその結びつきは緩やかなものであるということである。 私は自民党員でも支持者でもない”無党派層”だが、いたずらに特定団体との過去の関係ばかり取り上げる野党やメディアは、一回この本を読んだ方がいい。 無論、宗教2世の問題や霊感商法の問題に改めてスポットがあてられ、それに苦しむ人(もしくは自分が苦しんでいるということに気づけてすらいない人)の救済につながることには一定の意味があることは否定しない。
1投稿日: 2022.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自民党の歴史と勢力図を理解するための「派閥」、近年の総裁および幹事長ポストの権力増大を理解するための「総選挙とポスト配分」、支持の源泉がどこにあるかを見るための「友好団体」「地方組織と個人後援会」といった具合に、複眼的に自民党の正体に迫ろうとしている。〈現在の自民党は、政治改革への対応を経て、民主党に対抗するなかで形作られてきたといってよい〉という結論にいたる道筋は、本書のなかでおおむね裏打ちされていると思う。野党勢力が民主党政権「失敗」の痛手から立ち直りきらず、低い投票率が続いているなか、相対的に多い固定票を持つうえに公明党と選挙協力ができる自民党が有利に国政選挙を戦っているという分析も、うなずける。すごく面白いかというとそういう本ではないが、自民党の現在地点を理解するという意味で、非常によくまとまった一冊。
0投稿日: 2021.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ派閥の性格の変化、事前審査制度の変化などから自民党の政治的強さを論じている。中北さんの政治史系の本は読んだことあったが、現代の政権を分析している本は読んだことなかった。しかし、非常に緻密な分析をしており読みごたえがある。
0投稿日: 2021.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
綿密なデータに基づいて分析されている。 自民党総裁が長続きするようになった背景には、総裁選挙への一般党員の投票を重要視した事にもある。
0投稿日: 2019.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ参院選に読了が間に合わず! それにしても、今回の参院選は事前の想定通りで、与党の勝利という結果となった。この本に書かれている通り、しぶとい強さを発揮している。 それにしても、下野した時に対民主党戦略として、右傾化した政策を打ち出したとは知らなかった。その後の民主党及びその成れの果ての政党の状況を見るにつけ、何のための政権交代だったのか、さらに自民の右傾化まで招いたとしたら返って状況を悪化させただけとも思える。 若い世代の自民支持率が高いことも理解できないが、ちゃんと政治に向き合ってこなかった我々世代の責任なのだろうと感じる。
0投稿日: 2019.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ結論は穏当ながら説得力に富んでいる。 友好団体の章の経団連と宗教団体、そして、地方組織と後援会の章は知らないことが多く、興味深い。 #整理 ・中選挙区制度は派閥を必要としたが、金権体質を産み、小選挙区制度が求められ、首相の権限の強化と相まって、派閥の弱体化に繋がった。 ・選挙においては、1.無党派層獲得のための強い党首、2.固定票としての自公連携
0投稿日: 2019.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1章 派閥―弱体化する「党中党」 第2章 総裁選挙とポスト配分―総裁権力の増大 第3章 政策決定プロセス―事前審査制と官邸主導 第4章 国政選挙―伏在する二重構造 第5章 友好団体―減少する票とカネ 第6章 地方組織と個人後援会―強さの源泉の行方 終章 自民党の現在―変化する組織と理念 著者:中北浩爾(1968-、三重県、政治学)
0投稿日: 2019.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在、圧倒的な強さを示している自民党について、その組織がどのように動いているのかという点から理解できるように書かれています。歴史的な成り立ちについても書かれていますが、それよりも、いまの戦い方(直近の戦い方)に重点が置かれていると思います。派閥とは何なのか。派閥政治からの脱却がもたらしたものは何か。そこから最近の自民党の強さと、脆さを知ることができます。これからの日本政治を知るために。一党独裁になるにしても、二大政党制になるにしても。この自民党という戦後政治を作ってきた存在を学ぶことは避けられないと感じました。
0投稿日: 2019.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ平成31年現在、一強状態にあるとされる自民党について、党の文書や機関紙・一般紙の記述や数量的なデータ、そして関係者へのインタビューなどを駆使し、派閥、総裁選挙とポスト配分、政策決定プロセス、国政選挙、友好団体、地方組織と個人後援会、理念といった多様な視覚から、包括的に分析、その実像に迫ろうと試みている。 本書では、1980年代半ばを55年体制下の自民党の完成期と位置づけ、それとの対比で現在の自民党を捉えており、衆議院での小選挙区比例代表並立制の導入をはじめとした1990年代の一連の政治改革及び民主党の台頭を要因として、自民党は組織や理念の点で大きな変貌を遂げたと分析している。自民党の強みであった派閥や友好団体による固定票、地域組織等は弱体化しつつも、連立を組む公明党の存在を含め、自民党が保持するリソースは他党を圧倒し、それらを安倍政権も活用しており、長年にわたって築かれた自民党の優位は、簡単には覆らないだろうと結論づけている。 本書により、過去及び現在の自民党の姿を、包括的に理解することができた。特に、衆議院の選挙制度について、中選挙区制から小選挙区比例代表並立制へと変更した政治改革の、自民党の在り方への影響の大きさを認識した。また、現在、「一強」といわれる、自民党、そして安倍政権であるが、近年の自民党の絶対得票率の低迷や政治的リソースの弱体化に鑑みると、必ずしも盤石とはいえないということも感じた。 本書について欲を言えば、他の政党よりも充実していると思われる自民党の事務組織についても、言及してほしかったと思う。しかし、現時点での自民党の全体像を捉えるのに、最良の一冊であると感じた。
0投稿日: 2019.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ①1994年の政治改革②民主党への政権交代 が今の自民党を形成していく上で大きなインパクトを与えたというのが印象的。特に①に関して、今まで自分は「ふーん、小選挙区比例代表並立制にこの時に変わったのね」というくらいの認識だったが、自民党・派閥に対して大きな変化だったことを知る。 政治学ちゃんとやるべきだった…真面目に勉強しよう…
0投稿日: 2018.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んで思ったのは、安倍ちゃんが卑怯で弱虫なのが奇跡的に功を奏して選挙に勝ち続けているということ。しかも、利益誘導型の政治を行うために組織化されていない国民を低賃金で働かせ、増税して、年金の原資などの財産にまで手を付けている。そりゃあ緊急事態条項が必要になる日が来るわ。もちろん海外からの攻撃ではなくて、大規模なデモや市民運動に対してなんだから。国民はそうなって初めて自らの政治問題として事態を受け止めることになるのか。あるいは、北朝鮮のように闇市を立てて生き延びるかだろう。
0投稿日: 2017.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いが内容は小難しい。以下に詳しい感想が有ります。http://takeshi3017.chu.jp/file6/naiyou24001.html
0投稿日: 2017.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近の自民党はごたごたしていますが、その強さの秘密がわかったような気がしました。一方、派閥政治から官邸主導への転換は必然とはいえ、それによって、自民党にはいろいろな意見を持った政治家がいる、それが強みという見方も過去のものになりつつある。 全く知らない世界ですが、面白かったです。
2投稿日: 2017.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ実証的研究としては、よく調べており、なるほどと思いましたけどね。著者の結論、そうだろうなと思うけど、やっぱり悲しい。
1投稿日: 2017.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは非常によくまとまってる良書ですよ。さすが中公。章の間にやや重複は見られるものの。財界はその他業界団体と異なる位置付けという認識はなかった。発見であった。
1投稿日: 2017.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ中北浩爾『自民党 「一強」の実像」』(中公新書、2017年4月)税別880円 一橋大学大学院社会学研究科教授の中北浩爾(1968-)による55年体制以降の自民党論。 【構成】 第1章 派閥 弱体化する「党中党」 1 衰退への道のり 2 派閥とは何だったのか 3 失われた機能 4 残存する役割と上意下達機関化 第2章 総裁選挙とポスト配分 総裁権力の増大 1 脱派閥かする総裁選出プロセス 2 揺らぐ人事慣行 3 ポストはどう配分されるのか 4 強まる総裁の権力 第3章 政策決定プロセス 事前審査制と官邸主導 1 事前審査制とは何か 2 小泉政権という危機 3 安倍政権の官邸主導 4 事前審査制の持続力 第4章 国政選挙 伏在する二重構造 1 減少しつつも優位にある固定票 2 公明党との選挙協力 3 公募による候補者選定 4 二重構造化する国会議員 第5章 友好団体 減少する票とカネ 1 団体における自民党の優位 2 加入率の低下と影響力の後退 3 データでみる友好団体の変化 4 経団連と献金システム 第6章 地方組織と個人後援会 強さの源泉の行方 1 強固な自民党の地域支配 2 地域回帰への道 3 末端組織としての個人後援会 4 変わる国会議員と地方議員の関係 終章 自民党の現在 変化する組織と理念 1993年の55年体制崩壊とともに、長らく衆議院議員選挙として定着していた中選挙区制から小選挙区制と比例代表制へと転換された。20世紀末の政治改革であった。 本書の導入は、55年体制下の自民党、とくに1970年代に全盛を極めた派閥政治の解体過程である。 総裁選への出馬ハードルの低下、政治資金規正法改正によりその求心力が低下し、特に当選回数を重ねた議員には派閥加入のメリットが低減したと分析する。 さらに、橋本内閣以来の首相・首相官邸権限の強化により、派閥の最大の強みであった閣僚はじめ各種ポストへの配分もままならなくなった。特に小泉政権以降、当選回数が少ない議員からも抜擢し、派閥所属のベテラン議員の人事が頭打ちになるケースが増えた。おそらくここまでは、従来の自民党分析・平成政局分析の中でも言及されてきた。 本書の政治学的分析は第3章以降が本題となってくる。 第3章は、首相権限の強化を国会提出法案の事前審査制を取り上げる。この点、竹中治堅『首相支配』でも簡単に触れているが、これを自民党の党運営の伝統と位置づけて一章を使って論じるところに本書のユニークさがある。本来自民党はボトムアップの政策立案を行ってきたと本社は前提する。自民党の伝統的な事前審査は、部会-政調審議会-総務会の各レベルで議論され、全会一致(総務会長に一任)されることで法案提出となる。これに風穴をあけた2例を比較し、首相(総裁)-党の間の力関係の変化を示すのが狙いである。具体的には、党内で強力な異論が噴出した小泉政権の郵政民営化法案、第二次安倍政権の農協改革法案が俎上になる。党の合意形成を無視し中央突破を図った小泉政権に比べ、安倍政権は族議員を取り込んだり、農協からの要求に譲歩を見せるなどして円滑に事を運んだ(この点、農協改革が微温的になったという批判もできると思うが、それは本書の議論とは直接関係ない)。 第4章以降は、ポスト55年体制下においても自民党が国政選挙での得票が続いていることについての分析である。公明党との選挙協力の深化、民主党への政権委譲後の新人候補増加など、目につきやすい点である。世襲議員と3バンを持たない非世襲議員との二極化はわかりやすいところ。一方、非世襲議員の立候補に際して、公募でのリクルートが活発化しているという指摘は面白い。政党のオープン化と清新さをPRすることで、選挙対策として活用できるという思惑。欲を言えば、選挙の鍵を握る無党派層から自民党への投票傾向にもう少し説明や分析がほしいところ。 第5章、第6章はいわゆる業界団体と地方の後援会組織と党中央との関わりの分析である。政治資金規正の強化により、企業からの献金は減少傾向ながらも経団連は21世紀に入ってなお自民党への献金を継続している。とはいえ、野党の集金力に比して、自民党の力は一段も二段も上であり、第4章の冒頭で言及されている「絶対的に減少しているが、相対的には固い票田」が自民党にはしっかり残っている。 地方組織との関係性への言及の中で、特に面白いと感じたのは、市町村議会・府県議会の議員と国会議員との力関係の変化である。つまり、中選挙区制時代は、同一選挙区に自民党候補者がいれば、候補者は自らの選挙応援をしてくれる地方議会議員との関係性を重要視せざるを得ない(そうしなければ、他の自民党候補にその地方議会議員がコントロールできる票をもっていかれる)。しかし、小選挙区制になれば、国会議員と地方議会議員の関係も一対一対応となり、殊更関係を強化しなくとも惰性となる。 総じて、中選挙区制時代(55年体制下)と小選挙区時代(55年体制以降)を、党内の派閥構造の変化、法案審議・閣僚&幹部人事、支持基盤に分けて明快に分析がされている。派閥構造の変化、首相権限の拡大などは、すでに小泉政権期に関する先行研究で示されていたところではあるが、安倍政権まで尺をのばしてみると余計にその変化が小泉政権の一過性のものでないことがわかる。1990年代の政治改革とその後の野党の不振が、自民党一強の現状をつくりだしたことが構造的に理解できる。 これで著者の守備範囲は ①占領期の中道政権樹立(『経済復興と戦後政治』) ②保守合同・左右社会党再統一による55年体制成立(『一九五五年体制の成立』) ③自社の55年体制の固定化(『日本労働政治の国際関係史』) までの従来の研究に加え、 ④55年体制崩壊期(『自民党政治の変容』) ⑤55年体制崩壊以降の自民党政権(本書) も加わったことになる。 1980年代終わりから1998年の橋下政権までの期間については、 同じ著者の『自民党政治の変容』(NHKブックス、2014年5月)で政局も含めて記述されており、本書の前編にあたると言える。著者は後書きで佐藤・松崎『自民党政権』を55年体制自民党分析のスタンダードとしているが、著者の二書はあわせて平成自民党分析のスタンダードとなるのだろう。 ところで、著者とほぼ同門と言える政治史・政治学出身の北岡伸一(無論北岡氏の方が年長)が手がけた『自民党』は、一般向けながら55年体制下の自民党分析としてはそれなりに定評はあったと思うが、本文でも脚注でも、言及がない。アプローチも政権への評価も相当違うだろうが、同じ書名を使うからには、何かしらの対抗意識はあったのではと想像してしまう。
1投稿日: 2017.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ自民党は結党以来38年間にわたり政権を担い、2度「下野」したが、2012年に政権に復帰。一強状態にある。その間、自民党は大きな変貌を遂げた。本書は、関係者へのインタビューや数量的なデータなどを駆使し、派閥、総裁選挙、ポスト配分、政策決定プロセス、国政選挙、友好団体、地方組織、個人後援会、理念といった多様な視角から、包括的に分析。政権復帰後の自民党の特異な強さと脆さを徹底的に明らかにする。
2投稿日: 2017.04.26
