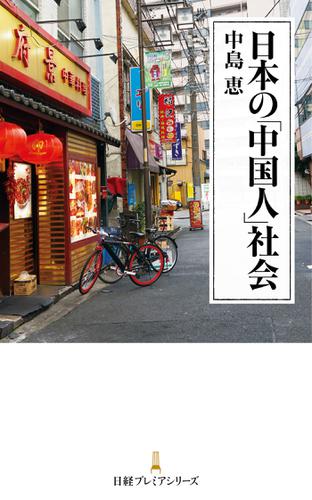
総合評価
(18件)| 3 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本に住む73万人の中国人の実態を インタビューや個人の視点から記したもの。 総じてミクロの視点からの記述の割にはルポタージュとしての面白みに欠ける。 ・日本人に有名な中華料理店と中国人のそれは違う ・今(2018年)日本に来る中国人は昔に比べて金持ちで優秀の人が多い ・中国人は大人でも よく勉強する。ビジネススクール(2年350万円)、学習アプリ(得到)はやってみたい。
0投稿日: 2022.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なんとなく日本にいる中国人をサポートしたいと思っていたけど、在日中国人が具体的に何に困っているのか、どういう側面からサポートできるのか知ることができた。 心理的なサポートもある。 親が積極的にPTAに立候補するっていうのは面白いなと思った。 「中国リテラシー」が低い日本 初めて聞いた表現で印象に残った 「サラダボウルと同じで、野菜同士は同じボウルの中にあっても、ドレッシングがなければ交わらない」 「中国に帰っていたら、自分の伸びしろは大きかったかもしれない。でもその分競争が激しいから失敗していた可能性もある。日本は中国ほどの伸びしろはないかもしれないけど、公平な社会だから努力次第で成功できる」 「中国人のゴミ出しマナーは・・」の「中国人」を個人の名前に置き換えてみる。「〇〇人は」と一括にする視点を捨てることが開かれた社会につながっていくのでは。
1投稿日: 2021.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や私たち日本人にとって、中国の存在は良くも悪くも切り離せないものです。特に、新型コロナウイルス流行の際には、マスクの不足などでそのことを改めて思い知らされたような気がします。メディアの報じ方などにより、中国人に対する悪い偏見が多いことも事実ですが、中国とうまく付き合っていくことは、その影響力を考えるととても重要です。これからは多様な情報の中から正しい情報を見極め、偏った感情的な見方を改め、将来に向けて正しい行動を選択するように心がけることが大事である、と教えてくれた1冊だと感じています。 【気づき】 ・中国人への偏見は多い。特に、テレビやインターネットで得る情報には、目を引くために偏ったものが多い可能性が高いことを頭に置く必要がある。 ・正しい情報を得る努力をして、真正面から中国と向き合う。中国は広く、国の中でも多様性があることに注意する。 ・良いものは受け入れていくことで、日本人にとっても大きなメリットを得られる。ただし、経済面だけを考えて依存度を高めてしまうと、今回のコロナウイルス流行時のようなリスクを負うことには注意すべきかもしれない。 【本のハイライト】 ・人口14億人の中国はあまりにも巨大で、多様で、奥が深い。社会の変化も尋常ではなく速く、人々が常に流動している。 ・人口減少、少子高齢化、外国人労働者受け入れなどの課題がある日本人にとって、70万人以上になった在日中国人の存在は無視できないほど大きくなった。「中国の縮図」が在日中国人社会ならば、そこから理解の糸口をたどることが中国を理解する第一歩かもしれない。 ・距離が近づけば傷つけあったり、摩擦も避けられないが、無闇に恐れたり、お互いに遠くから眺めているだけでは何も始まらない。今こそ真正面からしっかりと向き合いたい。 〇日本に持ち込まれた「コミュニティ」の構造 ・「ゆるいつながり」だから伝えられることもある。SNSだけのつながりだから、遠慮なく聞けることがある。うまく商売に活用できることもある。 ・海外では母国語で入ってくる情報と現地語で入ってくる情報に大きな格差がある。そこに住むからこその出会いもある。 ・コミュニケーションの主なツールはSNSへ変化しているが、基本的に人間のコミュニティは昔からほとんど変わっていないのではないか。中国人は人数が爆発的に増加しているので、その多様化が進んでいる。 〇勉強に駆り立てられる人々 ・日本の経営者はひとつの分野を突き進み、そのクオリティを高めていこうとするところがあるが、中国人経営者はいろいろなことに挑戦して動き回るタイプが多い。それが新たなエネルギーを生み出す。変化に追いつくためには、できるだけ違う業界の方と接触し、自分の頭を柔軟にしておく。幅広い知識や教養を身につけることが重要。 ・今の中国人は日々洪水のように大量の情報を浴びている。その情報をきちんと精査し取捨選択する、的確な情報に自らアクセスする、有益な情報をキャッチするためには自身の審美眼を磨かなくてはいけない。そのためにみんな努力している。変化の激しい中国では、過去に貴重な経験や栄光があっても、それが通用しない。多くの人は自覚し、危機感を抱いている。中高年が20代の若者から真摯に学ばなければいけない時代となっている。 ・中国では何か問題が生じれば、法をかいくぐってでも「解決策」講じようとする人が必ず現れる。違法やグレーゾーンは珍しくない。学歴が重要で、実利があるなら国籍を変えてもいいと考えて大金を支払う人がいても不思議ではない。 〇日本に住むことの利点と難点 ・日本市場が縮小し、中国人観光客によく売れる商品を販売するメーカーなどにとっては、越境ECを手掛ける在日中国人と手を組んで、自ら中国進出するリスクを回避して中国人に直接販売が可能に。中国の国産品のレベルも上がっているが、消費者は依然海外製品に憧れがある。地理的な距離、中国国内の物価高騰もあって、今後も日本製品の需要はある。 ・今後の日本を支える産業は消費財、観光、医療、ファッション、文化、教養、伝統になっていくのではないか。 ・中国人は中国人なりの「バイアス」をかけて、その地域や人々を見てしまう面があることに注意。「中国人」同士でも、あまりに国土が広く、お互いによく知らないからこそ、ステレオタイプで相手を見る傾向がある。見えないライバル意識的なものも存在する。 ・ささいなやりとりの中にある小さな問題や誤解の積み重ね、思い込みが、日本人の中国に対する大きな誤解やギャップにつながる。日本人は「中国リテラシー」が総じて低く、身近な中国人を通して見た中国を「正しい」と思いこむ。お互いに根本的なところで、まだ知らないこと、誤解していることは多い。 ・中国では魅力的な投資先がなかなか見つからない、もう投資が終わったという理由で日本に目が行く。余剰資金があり、地理的事情、技術力を魅力に感じ投資する。後継者がいない企業の買収や業務提携、不動産投資が増加。 ・中国企業に多いパターンは、とりあえず欲しいものは手中に収め、短期間に大儲けするもの。技術をコツコツ積み上げる発想があまりない。日本が受け入れがたい理由でもある。双方の置かれた状況やお国柄の理解が大切。 〇私たちは「違う世界」に生きている ・身近な中国人との間に「かなり情報のバックグラウンドに違いがある」「全く違う情報網持っている」と認識している人は少ない。同じ東アジアということだけで、欧米人と比べて違いを意識しにくい。本当はかなり違いは多く、気がつかないと深刻なコミュニケーションギャップにつながることもある。 ・SNSで物理的につながることはできても、情報を共有するかは別。成長して生活環境や内面が変わるにつれ、付き合いが変化し、自分に合ったコミュニティが完成されていく。 〇彼らがこの国に住み続ける理由 ・最近では中国人のマナーは劇的に向上している。かえって日本でサービスの低下が見られることもある。 ・日本人にとっても、中国人と同様、外国人と共生していくことは言葉で言うより難しい。自分が当事者にならないと関心は持てないかもしれないが、日本が彼らをどう受け入れていくのか、それにより日本社会がどう変わるかは私たち一人ひとりの問題でもある。
0投稿日: 2021.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国人と一括りにすると大きな間違いを犯すことになることがよく分かる話が満載だった。人種に限らず同じ人間として、同じようなところで悩み、考え、その日を暮らしていっているんだと感じた。外国に出ている人の方が、国内だけで暮らしている人に比べて自分の人生についてより深く考えている人が多いと感じるのは、人種を問わないことだろう。日本人は外に出て、もう少し自分のことについて、日本のことについて考えるべきだと考えさせられた。
0投稿日: 2020.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ・プロローグ →昔とは違う現状の日本における中国人の在り方。 ・第一章 なぜ、この街にばかり集まるのか →一定の地区に集中して住む中国人とまたそこに住む日本人との在り方。 ・第二章 日本に持ち込まれたコミュニティの構造 →日本において中国人が各々のコミュニティをつくり集まり互いに情報網をつくりあげている。またそれの土台となる中国ならではのSNSの使用。 ・第三章 勉強に駆り立てられる人々 →日本とは違い目まぐるしいスピードで変化している中国。子供から大人まで常に変化に追いついていかなければという危機感。また日本と中国の教育環境を上手く利用した親の子供への教育機会。 ・第四章 日本の教育はゆるすぎる →子供と親が絡んだ中国での受験戦争。 ・第五章 日本に住むこと、その利点と難点 →中国人による日本を経由した中国へのビジネス。 第六章 私たちは違う世界に生きている →食文化、コミュニケーションといった同じアジア人でも異なる見方、考え方。同じ中国料理でも日本の中国料理とはかなり差異がある。 第七章 彼らがこの国に住み続ける理由 →日本に住む中国人それぞれが思う考える日本における理由。 →今後における〇〇人は〜という一括りの考え方からの脱出の必要性。 日本に中国人が増えてきているのは肌で感じていたが、当事者達の現状までは知る由がなかった。この本を通して日本で彼らがどういった目的または理由で生きているのかを知ることができ、またその反面『中国社会を理解する』という点においてもとても勉強になりました。 私が精読できていないのかもしれませんが、比較的エリート、富裕層の方々の証言が多々描かれていると思ったので、より一般層の方に焦点を当てた現状も知り得てみたいと思いました。
0投稿日: 2020.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
比較的最近の日本にいる中国人のお話。 日本にはすでに70万人以上の中国人がおり、短期・公務、さらに帰化した中国系を含めると100万人もいるらしい。 西川口といったすでに中国人が多いことで有名になった場所、そのほか中華街とは別に中華学校の存在等の理由で中国人が集まっている横浜市南区の話とか興味深い。 筆者が言うようにSNSの発達等で本国と瞬時に繋がりを持ち続ける分、今の中国人は日本人化しなくともやっていけるところはあるのだろうなと思う。 また筆者は日本人の中国・中国人に対する理解力の低さについて書いているが、それはつまり中国人が日本人を理解することも難しいということなのではないか?とも思う。自分自身中国に関わってみて、確かに大きく違うと思うし、根本的に相容れない考え方を持っている人も多い。だが中国人も違う考え方を尊重できるほど視野が広くもないという印象だ。 これだけ物理的にも文化的にも近い日本が、彼らを理解できないのであれば、では世界で誰が理解できているのだろうか?という気もする。
0投稿日: 2020.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ<目次> プロローグ日本の中国人は、高地県民とほぼ同数 第1章なぜ、この街ばかりに集まるのか 第2章日本に持ち込まれたコミュニティの構造 第3章勉強に駆り立てられる人々 第4章日本の教育はゆるすぎる! 第5章日本に住むこと、その利点と難点 第6章私たちは違う世界に生きている 第7章彼らが、この国に住み続ける理由 エピローグ黄さんが日本で送った日々 あとがき 2018/12/10 初版 みんながんばってるよ 中国人コミュニティに入っていろいろ知りたいなあ
0投稿日: 2020.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル通り。 シナ人の努力の仕方は本当に凄いと思うが、それがもちろんシナ人全体ではないはずで。 ムッチャ、シナ人側からの視点でそれは新鮮な感覚ではあるが、危機感の薄さも気になる。 共産党についてあまりにもさらっと触れてるだけだったり。 この本だけ読んでいてはダメな気がする。
0投稿日: 2019.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本にいらっしゃる中国人の方の現状。自分も数年に一度中国に行く機会がありますが、特にここ5年くらいでの発展は目覚ましく、日本はいろんな面で本当に抜かれていると実感しました。この差はこれからさらに広がってしまうようにも思われます。さらに日本に滞在されている中国人の方の意識の高さもよくわかりました。ただ、本著は富裕層の方のお話に特化している部分もあると思われ、そうでない方の現状ももう少し知りたかったです。
0投稿日: 2019.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ国慶節休暇の移動の車内にて。 日本にいる中国人がメインのテーマだけど、中国にいる中国人の気質についても書かれていて勉強になる。 中国の「日本人」社会についても、似たようなことが言えるかなと思いながら読んだ。
0投稿日: 2019.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本に住む中国人は急増し、その総数は17年末で100万に迫るという。果たしてそれは脅威ではないのか?中国人は日本社会に溶け込めるのか?しかしながら、本書はそれらの関心をはぐらかし、日本での暮らし、仕事、育児、進学などの悩みを描き、等身大の姿として伝えている。一定の教養ある中国人が持つ悩みである。ただ、私たちの関心事はその水準に達しない多数の人々の動向にある。北京オリンピックの時に起こった多拠点での過激なデモを忘れてはいない。本国共産党との繋がり、地域コミュニティでの非協調性、犯罪などの数がもたらす社会的影響、共存のあり方に触れて欲しかった。
3投稿日: 2019.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の中に、「小さな中国社会」ができていた!住民の大半が中国人の団地、人気殺到の中華学校、あえて帰化しないビジネス上の理由、グルメ中国人に不評な人気中華料理店―。70万人時代に突入した日本に住む中国人の日常に潜入したルポルタージュ。
0投稿日: 2019.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国本土の中国人はどんどん変わっている。 日本に住む中国人も一枚岩ではない。 同じ国に住んでいても、中国人は日本人とは異なる情報の世界に生きている。
0投稿日: 2019.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログアラフィフ以上の日本人は、中国というと、どうしても人民服を着た自転車の大群のイメージを捨てきれないのではないだろうか。今やGDPは日本の3倍、眠れる獅子は超大国の座を取り戻した。 日本に住む中国人は高知県の人口に匹敵するが、日本の社会に溶け込むというよりは、自分達のコミュニティをどんどん拡大して、あちこちにリトルチャイナが構築されている感がある。 いつか日本は中国に乗っ取られてしまうのでは?と驚異に感じる日本人もいるだろう。しかし、この本を読むと、あまりにも変化の激しい中国の現状や中国人(と言っても様々な階層があり一括りにはできないが)の考え方、受け入れる日本側の問題にも触れることができる。 メディアによる断片的な情報を鵜呑みにせず、隣人としてお互いに生身の人間として理解し合おうとする姿勢が求められている。 日本と中国の差はまだ広がるだろう。しかし経済的繁栄だけが全てではない、日本の若い世代は多様な価値観を持つ、経済力でもう一度世界に存在感を示したいのはシニア世代だけではないだろうか。日本は違う道筋を見つけることも出来ると思う。2019.5.30
1投稿日: 2019.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
組織力の話はなんか納得いく。アメリカに暮らす日本人の話と比べると国民性っていうのは確かにあると思った。 中で分断されたグループごとでキッチリつながっている、のは結構アメリカ的な気がする。
1投稿日: 2019.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログショックを受けた。日本に住む70万人の中国人について書かれた本だが、変化が激し過ぎる本国の情報を常に日本で掴むために、中国人達がどうやって情報を集めているか書いてあった。ショクだったのは、中国に住んでいるのに知らない情報を1年遅れで日本語媒体から入手する自分の時間の遅さに。。。学習app得到とか、罗振宇とか、全然知らんかった。
0投稿日: 2019.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ軽い読み物としては、自分の興味を引き付けるものだった。まず、中国人に対する認識について、日本人が広く持っているものが適切なのかどうか、ここから始めなければ読み進めないところがある。 中国は現在進行形で駆け足で進んでいる場所である。今年も去年と同じような一年だったと感じる日本とは比較の対象にならないのである。 改革開放以後我們中国的高速発展、、、如何? これまで中国人と多少とも交流してきた自分自身として、またそうではない人にとっても、中国と日本との関係、現状を振り返ってみる気軽な一冊である。
0投稿日: 2019.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1/30読了。19年8冊目。7.0/10点。 タイトル通り「日本に住んでいる中国人」にフォーカスしている、なかなかニッチなところに切り込んでいる本。日本には合計73万人の中国人がいて、彼らがどのように生活をしているか、どう考えているかという点について掘り下げられていく。 中国人への悪い偏見を持っている人にはお勧めしておきたい本。目から鱗な部分がチラホラ目についた。 一番印象的だったのは、「中国人は総じて勉強家」という事。本当に日本ヤバいんじゃないかと思えたのはここ周辺。意識がちゃうわ、と感じた。「最低でも早慶」とかね。 もっと世界がグローバル化すると、国の境目ってどんどんなくなっていくようになると思うので、そういう時に考えるべき課題のいくつかを示唆していると思う。中国人は中国人だけのコミュニティを持っている、とか、その中国人コミュニティの詳細はほとんどの日本人は知らない、とかはどうなのかなぁ、もっとオープンにならんのかなぁと思った。 この本を読みながら明らかに自分の中で変化した部分として、電車内で話している中国人に目が行くようになったこと。何気ない会話をしている彼らを見て、裏に色々あるのだろうなぁと想像するようになった。この「色々ある」は当然、中国人だけでなく他の外国の人たちも同様だろう。 日本はまだ全然海外勢を呼び込む準備が出来ていないと思うが、特に欠落しているのは「彼らに目を向ける意識」なのではないかなぁ、などと思った。 扱っている内容がニッチである、という時点でまず面白い。それに加えて、「へー」と思えた箇所がいくつかあったので、7.0点に落ち着いた。
2投稿日: 2019.01.30
