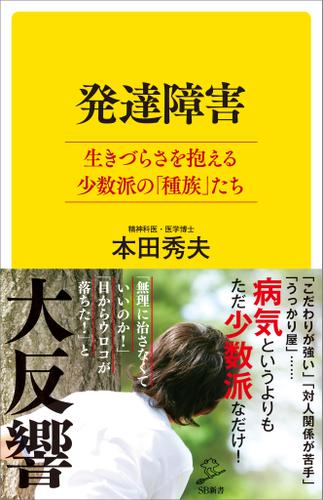
総合評価
(35件)| 13 | ||
| 12 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ発達障害は多くの特性が混在して表れるということがよくわかった。障害についての知識が殆ど無かったが、簡潔な文章と図のおかげで読みやすかった。学術書のような内容ではなく、様々な発達障害の基本的な説明と、グレーゾーンにある人の見分け方、生き方が書かれていた。
10投稿日: 2025.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
特性は選好性という表現が特徴的でした。できないのではなく、好みが違うという考え方が、柔和で良いと思いました。生きづらいと感じることも捉え方を変えれば長所になる、その長所を活かすことが環境調整というふうにおっしゃっていて、勉強になりました。
0投稿日: 2024.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ440 本田秀夫(ほんだ・ひでお) ◎信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授・同附属病院子どものこころ診療部長。特定非営利活動法人ネスト・ジャパン代表理事 ◎精神科医師。医学博士。1988年、東京大学医学部医学科を卒業。東京大学附属病院、国立精神・神経センター武蔵病院を経て、横浜市総合リハビリテーションセンターで20年にわたり発達障害の臨床と研究に従事。発達障害に関する学術論文多数。英国で発行されている自閉症の学術専門誌『Autism』の編集委員。2011年、山梨県立こころの発達総合支援センターの初代所長に就任。2014年、信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部長。2018年より現職。日本自閉症スペクトラム学会常任理事、日本児童青年精神医学会代議員、日本自閉症協会理事。 ◎2013年刊の『自閉症スペクトラム』(小社刊)は12刷5万部のロングセラー。 発達障害 生きづらさを抱える少数派の「種族」たち (SB新書) by 本田 秀夫 ASの特性というのは、たとえば以下のようなものです。 □喜びや悲しみ、興味、達成感などの感情を人と分かち合うのが苦手。 □ひとりでいることを好む場合が多い。人と交流する場合でも、受け身的になったり、自分ばかり積極的で一方的な関わりになったりする。 □独り言が多い、抑揚が不自然、敬語がうまく使えない、皮肉が通じないといった形で、会話がかみ合わないことがある。 □表情や姿勢、身振り、指差し、視線などによる「非言語的なコミュニケーション」が上手にできない。 □ 特定のものごとに強い興味をもつ。 そして、それ以外のことにはほとんど興味や関心をもたない。 □特定の手順や配置、スケジュール、行動パターンなどに強くこだわる。相手や場所に応じて行動パターンを決めている場合もある。 □幾何学的な図形やデジタルな情報、機械的な記憶、 特定分野のマニアックな知識 に強い関心をもつことがある。 □他者の気持ちを動かすことには、基本的に興味をもたない。たとえば、目的もなく人が嫌がるようなことはしない。 □視覚的な情報に注意が引かれやすいなど、特定の感覚に過敏や鈍麻がみられる。特定の音やにおい、触感などを極端に嫌がることなどがある。 いえ、そんなことはありません。もしも、 楽しみ方に優劣があると考える人がいるとすれば、それは多数派のおごり でしょう。 ASの人たちの楽しみ方は、ただ少数派だというだけ です。人種や民族、性的志向などのマイノリティが直面する問題点──そこには、マイノリティの人たちがマジョリティを知るほどには、マジョリティの人たちはマイノリティのことを知らないという共通点があるのです。 ところが、ASの特性がある人がこのようなおしゃべりに参加していた場合には、さまざまな点で違いが現れます。 まず、ASの特性がある人は、自分の好きな話題についてはとことん語りたがるところがあります。そのため、大勢でおしゃべりをしているときに、ひとりでしゃべりすぎてしまったり、自分だけ極端にマニアックな話をしたりします。 また、もしもおしゃべりの結論が「今度食べてみよう」ということになったにもかかわらず、それを誰も実践しない場合には、ASの特性がある人は違和感を抱くでしょう。マニアックな情報をいろいろと交換しあったのに、それを実生活に生かさないのはおかしいと感じるのです。「あとで役に立てる気がないのであれば、なんのためにケーキの話をしたのか」というのが、このタイプの人たちの感じ方 です。あるいは、こう考えることもあるかもしれません。「そこまでマニアックにケーキのことを調べたり考えたりするのなら、もっとのめりこんでいこうよ」と。ASの特性がある人の多くは、マニアックな知識をさらに掘り下げていこうとしたがります。 大人で、文字を書くことが苦手だという人もいます。ほとんど判読不能な文字を書く人、独特のクセ字を書く人、書類を作るのが極端に遅い人、記入欄から文字がいつもはみ出してしまう人など、大人の社会にもさまざまな形で「読み書きの苦手」がみられます。そのような例のなかにはLDの特性がある人もいるかもしれませんが、多くの人はLDには該当しません。 感覚面の異常というのは、とても微妙な問題です。たとえば猫舌というのも一種の異常ですが、たいていの人に理解も配慮もしてもらえます。 しかし、たとえば「水玉模様を見ると吐きそうになる」 という視覚的な異常があった場合には、どうでしょうか。これも実際にある例なのですが、この感覚をもつ人はあまり共感してもらえないそうです。 つまり、 感覚面の異常には共感されやすいものと、そうではないものがある ということです。そしてその違いは、多数派か少数派かということだけなのです。味覚でいえば、猫舌や、激辛料理が苦手だという感覚はけっして珍しくありませんので、比較的共感を得やすいでしょう。しかし、これもまた実例ですが、白米以外になにも食べたがらないという感覚は、ほとんど共感を得られません。 ADHの特性で、ひとことでいえば「うっかりミスが多い」ということです。 ものごとに対して適度に注意を向けることや、注意を向け続けることが苦手 です。そのため、人の話を聞きもらすことや、ものをなくすことがよくあります。また、作業をやり切ることや、順序立てて進めていくことが得意ではありません。勉強や仕事をするときに「要領が悪い」「段取りが悪い」などといわれがちです。 この特性が目立つのは、主に子どもの頃です。 大人になるにつれて、急に立ち歩くようなことは減り、多動性・衝動性がもう少し目立たない形に 変わっていきます。たとえば、仕事中に指をトントンと鳴らす、思いつきの発言がときおりみられる、レストランなどで時間をつぶすことを嫌がるといった行動になるのです。 LDの特性です。これも背景はさまざまですが、表面的には、簡単な計算も苦手という状態になります。具体的には、 数字の大小や関係などの理解が難しく、数を数えるときに指を折って読み上げたり します。また、数学的な視点からものごとを考えることが困難で、たとえば、あるものと別のものの数量を比較するようなことが、直感的にはできない場合があります。 計算に関することが基本的なところから理解しにくいという状態です。 DCDの特性です。運動が苦手という特性は生活面では、 走る姿がぎこちなく見える、球技が極端に苦手、逆上がりができない、自転車に乗れない といった特徴としてみられます。 目安として、同じ年齢の人の大半がそれほど苦労せずに身につけられることを、いくら練習しても習得できないということが多ければ、この特性の可能性があります。 たとえば、幼児であれば自転車に乗れなくても当たり前ですが、小学校中学年くらいになってくると、乗れない子のほうが珍しくなります。逆上がりも同様で、小学校低学年であれば、まだできない子もたくさんいますが、高学年になると、できる子のほうが多くなってきます。 とくに 発達の特性がある人は「やりたいこと」を大切に してください。なぜかというと、発達の特性がある人は一般の人に比べて「やるべきこと」が多くなりがちで、そのために「やりたいこと」を我慢させられてしまうことがよくあるからです。 ここで、私が最近よく使っている「『やりたいこと』と『やるべきこと』を考える図」を見ていただきましょう。 その場合、問題がないようにみえても無理をしているので、いずれ燃え尽きます。そうすると、本人は「なんのために生きているのかわからなくなった」などと言って、勉強や仕事などのやるべきことを急にやめてしまいます。 このような問題を私は、 発達の特性がある人の「過剰適応」 と呼んでいます。発達の特性がある人が、世間から求められている社会規範をその人なりに理解して、 苦手だと感じながらもそれに適応しようと努力した結果、かなり無理をして「過剰」に「適応」する形になってしまう という問題です。 対人関係が苦手な人は、人に合わせることがうまくできないため、まわりの人から「空気を読めない」などと言われます。そして、それが大きな欠点のように指摘されるわけですが、本当にそうでしょうか。 人は空気が読めなくても、別に死にはしません。私は 空気を読めないということを、そもそも致命的な弱点ではない と考えています。察しが悪いことをなまじ気にするから、それを弱点のように感じたり、困ったりするわけで、そんなことを気にしなければよいと思うのです。 空気が読めないというのは、裏を返せば、人からなにをいわれても動じない ということでもあります。それは、自分の考えをもっていてブレないという長所でもあるわけです。そして、自分を強くもっている人は、大勢とそつなくつき合うことは苦手かもしれませんが、 気の合う少数の仲間とは、うまくやっていける ことがあります。 また、このタイプの人は会話をするとき、相手との関係作りよりも、話の内容そのものを重視します。相手の反応をみて話を調整したりせず、大事なことはそのまま伝えようとします。そういうところを「空気が読めない」と言われるわけですが、そうして愛想やお世辞でごまかさず、きちんと内容のある話ができるということも、ひとつの長所といってよいのではないでしょうか。 ですから、環境調整や世渡り術を考えるときには、その「ブレない強さや内容重視の考え方を生かすこと」、そして「無理に誰とでもつき合おうとするのではなく、少数の仲間と交流すること」 を心がけていただければと思います。 こだわりが強い人は、自分の興味があることや納得できることに関しては、かなり強い集中力を発揮 します。ほかの人が休憩しながら1時間かけてこなす作業を、休憩せずに 30 分で仕上げてしまえるようなところがあるのです。そのために別の仕事を追加されるなど、結果として要領が悪くなる面もあるのですが、それは勤勉性でもあります。一度これだと決めたことには、真面目に突き進むことができるわけです。 ですから、その「手を抜かない勤勉性」や「定められた規則を守り、初志貫徹できるところ」を生かして環境調整をすると、うまくいきます。その強みを十分に生かすためには、 ルールを決めるときや、状況が変わって方針を見直すときに、まわりの人とよく相談することが重要 です。そういう 相談相手を身近に得ることができれば、やるべきことを見失わずに、自分の役割に邁進 できます。そのような世渡り術をぜひ身につけていきましょう。 いっぽう、ASの特性がある人は基本的に、そのような対人関係の微妙なかけひきを楽しみません。そのため、会話などでかけひきをして人と親しくなっていくというよりは、 共通の趣味などを通じて誰かと意気投合し、そのような出会いのなかで恋愛・結婚する ということのほうが多くなります。 また、ASの特性がある人の場合、かけひきを楽しもうとしない分、恋愛・結婚のプロセスが早くなる傾向があるといえるかもしれません。気になる相手には最初から強くアピールしてしまうという例や、相手からアプローチを受けると比較的早く相手を信じてしまうというような例があります。恋愛・結婚に関してはやや性急なところがみられるため、その点を自覚し、心配なときには家族や友人などに相談するようにしてもよいでしょう。 いまは生活していてとくに困ることがなく、自分には発達障害はないと感じているという人のなかにも、発達の特性がある人はいます。この本を読んで、自分に(家族や友人に)当てはまる部分があったという方は、具体的にはどんな特性があり、生活を今後どのように調整していくのがよいのか、この機会に考えてみてください。それは将来の困難を予防するための一手になるかもしれません。
0投稿日: 2024.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ主治医より、初診の際に勧めていただいた本です。 色々と違和感を覚えていたことが全てこの本を読んで腑に落ちました。
0投稿日: 2024.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ診断に至らないグレーゾーンの場合や、グレーゾーンにも入らないが、発達障害の特性がある場合を記述しようと工夫されているのが印象的でした。
0投稿日: 2023.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ発達障害と言う言葉がしっくりこない。 障害でなく特性であり、障害になるかどうかは、理解があるかないか、協力があるかないかが大きく影響するって考えて、人とも自分とも付き合っていきたい。
0投稿日: 2023.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自律スキルを持って自分ができることは実践し、その点では社会に貢献する。苦手な面では無理をせず、ソーシャルスキルを使って人に相談しながらやっていく。著者が他の本でも繰り返し述べている「自律とソーシャルスキル」これに尽きるな、と感じた。つまりは勉強よりも身辺自律や周りに頼る力を育てていくことに注力すればよいったことかな。
0投稿日: 2023.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者本人も発達障害当事者であり、平易で寄り添うような文体とともに、ASDとADHDは混ざり合う例が多く、なおかつ普通の人と地続きだ、という解釈はまさにその通りで目から鱗でした。
0投稿日: 2023.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ読前は、発達障害(ADHD注意欠陥多動性障害)(ASD自閉症スペクラム障害)という文字通りの意味を知識として知っているだけでした。 また「人間はどちらかの傾向がある」ぐらいの浅い知識で、「自分はADHD傾向だから!」深く考えず、30年以上過ごして来ました。 しかし読後は、「発達の特性を〇〇が苦手、という形で、機能の欠損として捉えるのでなく、〇〇よりも〇〇を優先する、という生来の志向性の偏りと捉える」という筆者の主張が、実際に困った時に役立つ知恵なのだと気がつきました。 まさに「白か黒かではなく、グレー」で、グレーの色も濃いグレーか、薄いグレーか、どちらかの傾向ではなく、両方「重複」しているのか?どの程度ななか?の視点が重要だと、目から鱗でした。 自分の特性に照らし合わせて考えると、例えば、雑談が苦手で、自然に相手の話を聞き出すのが苦手でも自分と相手の興味のある話題に絞って、話をするなど、無理の無い範囲内で調整をする事が出来ると感じました。少しでも、生きづらさを抱えている方は、オススメです。
1投稿日: 2023.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこの書籍も発達障害グレーゾーンから派生して読み始めた1冊。 発刊当時(2018年)から考えると、グレーゾーンの概念を理解したうえで読み進めた方が理解しやすいように思えた。 また、著者自らがうまく図解として落とし込んで説明しているため、どこに自分自身が当てはまるか?とイメージしながら読みす進めることも出来る。 定型発達かそうでないか。 でも、ここまで疲弊するのはどうしてだったのか? そういったもどかしい部分の回答なども、本書に提示されていたので(発達の特性がある人が社会規範に適応しようと無理をして「過剰適応」する形になってしまう p178)、グレーゾーンに当てはまる自分自身としては、この1冊も思いのほか読了して良かった内容だった。
1投稿日: 2023.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ重複する発達障害の特徴とその対処法について分かりやすくまとめられている。 ちなみにASDやADHDの最後のDは障害という意味であり、本書では特性の程度という概念を重視するため初めにAS、ADHについての考え方を紹介していた。 発達障害が重複することでそれぞれの特性が弱くなることがあり、それによって発達障害の診断がつけられないケースが少なくない。しかし当人は生きづらさを抱えているにも関わらず環境調整されないまま過ごしているうちに、うつや不安障害などの二次障害を引き起こされる。そのため、診断にとらわれず個々の特性の程度に合わせて生きづらさを予防していくことが重要となる。 また、発達の特性を「 ~が苦手」という形で、なんらかの機能の欠損としてとらえるのではなく、「 ~よりも ~を優先する」という「選好性の偏り」としてとらえる方が好ましい。そしてそれが少数派の選好性であるが故に生きづらさを感じるわけだが、ふつう(多数派)との間に優劣の差はなく、お互いがお互いの生きやすいようにやっていけば良いのである。 自分はADHDの不注意、ASDのこだわりの強さがあると思っている。(一つの物事に過集中するのはADHDの特性だと思っていたが、本書によるとADHDのみの場合興味のある物事に対しても注意散漫になることが多く、ADHDの過集中とされているのはASDのこだわりの強さによるものではないか、とのことだった。興味のある場面では落ち着いてるのに興味が無くなった途端ソワソワするのもASDの特徴とのことで、これも当てはまっている気がする) 不注意によって落ち込んだりすることもあるけれど、こうした本に救われるのも事実で、児童精神科医によって心が救われる人は世の中に絶対いるんだと思う。 たまにSNSで発達障害と診断された人が"本当の発達障害は自分で気づけません。気づいてる時点で発達障害ではありません"と言っているのを見るけど、医者でもないのにその発言をするのはは随分と傲慢だよね。生きづらさを身をもって知っているのにどうして他人の生きづらさを無い物にしたがるのだろう。 ところで本書ではDCD(発達性協調運動障害)も取り上げられてたけど、走る姿がぎごちない、逆上がりができない、球技が極端に苦手、歩いたり作業してるときに体の一部をよくぶつけるなど、出てきた特性にほとんど当てはまっててびっくりした。まあ生活する上で困ってないから良いのだけど…。とはいえ学生時代に体育で皆と同じことを強要されるのは正直辛かったなあ。 ✏研究によって「この支援法がよい」というふうに書かれたことは、だいたい、 ASDやADHDなどいずれかの障害に特化した内容になっています。 ✏ASの特性がある人は、こだわりと対人関係を天秤にかけたとき、こだわりを優先する。 ✏内容が変わることはあっても、こだわる対象がどんどん増えていくわけではなく、こだわりの総量は変わらない。 ✏LDの特性があるのか、それとも学ぶ機会が少なかったのか判断が難しい。 ✏発達の特性がある人(とくに自閉スペクトラムの特性がある人)は、基本的には自分のやりたいことを大事にする人たちです。自分のやりたいことに「これ以上は減らせない」という最低ラインがあります。 ✏発達の特性がある人は、一般の人とは違って、仕事が忙しい時期でも、やりたいことへの情熱がおさえられなくなることがよくあります。食事や入浴、睡眠の時間を削ってでも、やりたいことをしたくなり、しかも、ストレスがたまればたまるほど、そういう思いが爆発しやすくなります。それが、発達の特性がある人の特徴です。
6投稿日: 2022.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと自閉症、ちょっと注意欠如多動性障害 以下AS.ADH という解釈は新鮮だった。 診断名に囚われないという話は良く聞くが、なぜかという理由がよく分かった。 1つはAS.ADHが重複しているということ。 2つはそれらの程度に強弱があるということ。 要は人それぞれに違った特性、段階があるということで、一般的に障害の無い人と呼ばれる中にも生きづらさを感じている人は多いのではないかと思う。 私自身は人はみな発達障害を抱えているのではないかと思う。強弱はあるにしろ、人間社会にいる中で何かしらの生きづらさを感じていると思う。人の悩みの殆どは人間関係にあると言われているように。 だから、その生きづらさを解消できるように周りからの合理的配慮、自分では相談できる力、自分の特性を話せる力が大切なのではないかと思った。 支援が必要な人達と関わる機会が多い私にとって、目から鱗の話ばかりだった。 自分自身も支援が必要だと感じた…。
0投稿日: 2022.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログおわりに、が心に響いた。この本を読んで、今は自分には関係がないと思ったとしても、世の中にはこういう特性を持っている人もいると認識しておくことで、自分も生活しやすくなる、と理解した。この本を読んだきっかけは、発達障害ではないかと思う人と接し、その人の発した言葉に傷ついたことである。その人とは関係を絶ち、二度と会うことはないが、未だにその言葉は自分を傷つける。その自分を受け入れ、乗り越えるために、発達障害について知ることにした。この著者の他の本もまた今度、読みたい。
0投稿日: 2022.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、発達障害と診断されてはいないものの生きづらさを感じている大人向けに書かれています。 著者の、発達障害を「〜が苦手」ではなく、「〜よりも〜を好む志向性」という考え方が、他の書籍と比べて、しっくり来ました。 1点、学習障害の以下の部分についても、上記の著者の「〜よりも〜を好む志向性」を当てはめることができると私は思います。アメリカのテンプル・グランディンさんの一例があるからです。 ▶学習障害(以下LD)の「読むのが苦手」「書くのが苦手」「計算が苦手」という特性も、基本的にはネガティブな概念です。ある特定の学び方が苦手で、その部分は育ちにくいということですから、特性そのものを長所として生活にとり入れることは難しいでしょう。 発達障害については、時代とともに分かってきたことがかなり変わるので、なるべく最新のものを、複数冊またいで調べることが重要だと感じます。
0投稿日: 2022.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ『発達障害』について分析した一冊。 著者自身発達障害の傾向があるとのこと。 具体的な事例が豊富でわかりやすかった。 印象的なのは、「こだわりが強い特性はあるけど、こだわりの総量自体は変わらない」という一節。 つまり、興味の対象が別のことに向いたら、前のことに対するこだわりは半減するということ。 当事者だからこそわかり得ることだと感じた。
0投稿日: 2022.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ不安や心配を解消するにはネットで調べるよりその道のプロの人が書いた本を読む方が私には合ってる。 一つだけ気になったのは苦手なことを周りの人に伝えるってとこ。 例えば職場で上司に「私はうっかりミスが多いので一緒に確認をしてください」と言って「わかりました」ってなる? 「忙しいのにそんなこといちいちやってられるか!」「何回も聞くな!」ってならない? そうなったら気にせず別の手伝ってくれる人を探せばいいってこと? 職場で怒られる想像しかできなくて辛い。
0投稿日: 2022.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27462019
0投稿日: 2021.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本の主張は「発達障害(ADHD、ASD、LDなど)は高確率で併発する」というものであり、その一点に尽きる。 個人的にはそれは当然のことという実感があり、特に目新しいものではなかった。 しかし社会に向けてはもっとこういうことを啓発していく必要があるのかもしれない。その点にこの本の価値はあるのだろう。いつ社会が変わるのかはわからないが…
0投稿日: 2021.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んで、自分が発達障害という診断を受ける前からずっと感じていた「居心地の悪さ」について納得がいく説明を受けたような、モヤモヤしていたものがすっきり晴れたような気分になりました。 明日から、もう少しだけ頑張れるかな。「少数派」の一人として。
0投稿日: 2021.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ30年以上臨床の現場で患者を診てきた筆者の言葉には説得力がある。何より自身の経験を元に書かれているからだ。 そして明瞭で分かりやすい文章。まず冒頭の「この本は、『発達障害とは何か』『発達障害の人が他の多数の人と違うのはどのような点か』を解説した本です。」という一文が良い。ここで読者が自分の知りたい内容と合っているかが確認できる。 次にこの人は発達障害か?というケースが3例。結論は、「ちょっとAS」。ASDのD(Disorder ; 障害)がない状態。日常生活の障害にはなっていないが、その症状はあるということ。 ここは我が子にも当てはまるのではないかと思った。 次にASの特性。 ・喜びや悲しみ、興味、達成感などの感情を人と分かち合うことが苦手 ・一人でいることを好む。人と関わる場面でも受け身になったり、自分ばかり積極的で一方的な関わりになる ・独り言、敬語が上手く使えない、皮肉が通じないといった形で、会話が噛み合わないことがある ・表情や姿勢、身振り、視線などによる非言語的なコミュニケーションが苦手 ・特定の物事に強い興味をもつ ・他者の気持ちを動かすことには、基本的に興味を持たない等 これは教科書的な説明だが、筆者はここからさらに具体的な例を挙げてくれるのでより理解が進む。例えば黒ひげ危機一髪。 多くの人は、みんなで一人ずつ剣を刺していきドキドキ感を共有することを楽しむ。しかしASの人達は、一人が剣を刺し続け、人形が飛び出すまでの回数の多さを競って楽しむ。自分の番でないときは、各々読書など好きなことをしていたそう。これは子供でも大人でも同じ。 筆者が言いたいのは、楽しみ方に優劣はないということ。ただ、ASの人の楽しみ方は少数派だということ。日常では、通常のやり方の方が楽しいと信じて疑わない人達が多数派なので居心地が悪い。
0投稿日: 2021.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ本田先生の説明はとてもわかりやすい。発達障害を抱える人たちはただ少数派なだけ。それぞれが心地よく感じられる場があることが大切だと感じた。得意な面を活かして生活していく、、、このことを知っているだけでも生きづらさから解放されていくのではないかと思った。
0投稿日: 2021.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々に読んだ発達障害の本。ASDとかADHDとかLDとか、用語が分かりづらいなと前から思っていたが、これらの特徴が重複しやすく、グレーゾーンにあたるであろう人が多いとのことで、そりゃあ分かりにくい。 後半では、「生活面の「環境調整」(本人なりの世渡り術も含む)」と題し、 ①ボトムダウン式 発達の特性があって苦手なところを少しでも「ふつう」に近付ける ②トップダウン式 発達の特性があって苦手なところについて、それを補完する手段を考える。現状を把握し、そのなかでできること・できないことを検討する。 ……の2つの方法に分類する。①はわかりやすいが、障害は努力だけではどうにもならないものであり、環境調整には②のアプローチが重要だとする。 実際にどんな手段があるか、という段になると、やはり「周囲の理解」という言葉が頻発して、やっぱりそこに行き着くんだよなぁと思ってしまった。 でも、それだけではなく、発達の特性がある人が「やるべきこと」が多くなりがち(対人関係や段取りなど苦手なことを社会においてこなすためにエネルギーが必要ということ)なことに注目し、特性に合った環境調整を行い、「やるべきこと」減らし、「やりたいこと」をする時間を増やすことが大切だという。 また、特に大人になってから発達の特性について悩みが発生している場合、環境よりも自分の希望を優先しがちになる。これは人間の特性だから当然のことだが、基本的には特性に合った生活がよいことも念頭に置きつつ、自分のやりたいことと環境調整の実現性について考え、バランスよくやっていくのが大切なのだとか。 発達障害を「発達の特性」と表現し、あくまで少数派なだけだよという著者は優しいが、もし当事者が「ふつう」に憧れているとするならば、なかなか根の深い問題なのかなと思う。「ふつう」とそれ以外に優劣の差はない、誰もが自分を理解しそれが自分の「ふつう」だと思って生きていける社会が素晴らしい、そのとおりだろう。 でも、自分が目指していたものや強く憧れていたものが、従来型の「ふつう」であり、そこは自分が行きつくことのできない場所だとするならば、その人は再び別の山に登る気持ちを奮い立たせることができるのだろうか。
0投稿日: 2021.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ発達障害の特性が重複する事はどの本にも書かれているのに、医療の世界ではそれに対する処方が確立されていないことに驚いた。 複数の特性を合わせ持つ事で、どちらの特性が出る訳ではなく、むしろ一部は抑えられて見つけづらくなることが具体的に書かれており、とても納得したのと同時にわざわざ言わなくてはいけないことが衝撃的だった。 発達障害を持つ本人もそのご家族も、読んでおくべき一冊です。
0投稿日: 2020.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ発達障害に関する本は数多く出ているが、この本はリブートというか、2周めというか。重複とグラデーションというキーワードを駆使して、発達障害とは一般に思われているよりも微妙で複雑な問題ですよ、ということを訴える。いわば概論的な内容で、総花的な印象を受ける。章立てに沿って内容を埋めましたよ、的な。この分野の第一人者の著作だから、ためになる情報は少なくないが、個人的には前作(『自閉症スペクトラム』)のほうが胸に響いた。
0投稿日: 2020.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ発達障害を少数派の特性だと捉え直すことによって考え方や生き方が前向きになれると思った。 AS、Adの発達傾向を見て自分には発達障害の傾向は薄いように感じた。仕事の離転職の多さは偏った性格が原因のようだ。しかしASのこだわりの強さの特徴と似ている部分はあったので総量不変の法則【こだわる物の総量は変わらない】に則ってこだわるものが生活の質を向上させるものにするように意識的にしていきたい。
0投稿日: 2020.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ微妙なケースを多く挙げているので、これは、、どうなんだ? 特別に支援が必要なのか? と考えさせられる。「ふつう」に合わせるんじゃなくて、行動の原因を探って、その人ごとに支援のあり方を考えよう、という話。理屈はわかるがなかなか大変。様々な特性と環境調整の考え方、例は参考になる。 個人的に、不注意な人は失敗にめげない(なので不注意がなくならないともぃえる)がツボ。
5投稿日: 2020.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ASという診断がつく、うっかりミスも程度問題。 とても役立った。 『自分のやりたい事を最優先させる。』 一種の自己啓発本のように読めた。
0投稿日: 2020.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が発達障害かもって思っている人に読んで欲しい。 障害には強弱があることや、ADHDとAS両方を持ち合わせている人の存在についての章は大変興味深かった。
0投稿日: 2020.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ元々気になっていた先生の著作。 発達特性のある人も個性的な人もそれぞれが自分の事を理解し、自分の「普通」を生きていける社会になるといい。 自分の「やりたいこと」を生活の中心にして人生設計ができていればそれでいい。 やりたいことをして失敗するのと、やりたいことを我慢して失敗するのでは後悔の仕方が違う。 ボトムアップとトップダウン 苦手なことを克服するよりできることとできないことを検討し、補完する手段を考える方が生きやすい。 空気が読めない→気の合う少数の仲間とは上手くやっていける。ブレない強さや内容重視の考え方を生かす。「自分は主張が強いので、言い過ぎだと感じたら教えてください」とあらかじめ伝えておくのもいい。
0投稿日: 2019.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「重複」や「強弱」など、なるほどと思った。「この症状、言動があるから発達障害」と一概にいえないのが難しいところなので定型発達からのグラデーションであり、更に発達障害の中でもこの特性があるからこの障害と明確に区分できるものではないという考え方はそこからこぼれ落ちている生きづらい人達にとって救われるものではないだろうか。
0投稿日: 2019.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ色々な特徴が重複している例があって、その場合、症状が複雑で適切に対応されてないケースがある。 そういう例がある、という事実を紹介してあるだけで救われる安心する人もいるんじゃないだろうか。
0投稿日: 2019.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ11/15 ネット上で話題の一冊! 発達障害の「わかりにくさ」の理由を解説しつつ、 発達障害を直さなくてもいい、と語る一冊
0投稿日: 2019.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ発達障害関連の本をいろいろ新書でよみましたが 内容としては、一番かもしれません。 途中までは、内容的にもそんなに新しいことや、発見や 納得などもなかったのですが、後半からどんどん引き込まれるように有用な内容が書かれてあると思いました。 第4章の『やりたいことを優先する!』からどんどん 引き込まれました。 環境調整を有用に実施すること。 やりたいこととやるべきことの図 それぞれの特性ごとの調整方法 など。特に著者が書いた独自の各種図表が非常にわかりやすく、前記のやりたいこととやるべきことのバランスの図は 非常にわかりやすいものでした。 さらに5章の”自分が『発達障害かもしれない』と思ったらとあとがきは非常にいい内容だと思いました。感動すらするような内容だと思います。 そういう特性を持っている息子にも読んでほしいとおもいました。
3投稿日: 2019.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ発達障害と呼ばれる障害についての画期的な提言だと思う。主に二つ。 ①発達障害にはASD/ADHD/LDの側面があり、それは従来言われてきたのよりもっと頻繁に混在していることを理論と豊富な症例で示している。 ②「障害」は周りとの関係である。同じ行動でも周りの理解とサポートがあり生活できているならそれは障害ではない、として障害DisorderのDを除いたASやADHという考え方を使っている。 また、単なるオタク(マニア)と障害レベルのこだわりの違いを手を替え品を替え説明してくれる。 ウチは、父がAS、母がADH、息子が両方という傾向があり、息子の症状についてよくわからないまま(親が)混乱していた。本書のおかげでADH優位なASということがすっと腑に落ちた。 あと、贅沢を言えば、日々の生活の中での対策が欲しかった。 人生レベルでどう考えていけば良いのかは明確に書いてある(長所を伸ばす、活かすべき)のだけど、その考えに基づいて「ゲームに熱中しすぎて他のことを全部忘れてしまう」といった日常の困りごととどう向き合うかのヒントがもう少し欲しかった。 「黒板に爪を立ててキーッと鳴らす音には何度繰り返されても慣れないでしょ?」は、確かにその通りなんだけど、それでは日常の困りごとが積み上がって障害レベルになってしまいそうなのでガミガミ叱ってしまう、、、という悩みの解決にはあと一歩届かないのです。 追記:ちゃんと「日常生活の中での対策」がありました。 本田秀夫『ADHDの子の育て方がわかる本』 こちらと一緒に読むべきですね。
0投稿日: 2019.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログカテゴライズせずに発達の特性を“強弱”や“濃淡”という捉え方をすることにとても共感できた。 「~ができないのではなくて、~よりも~を優先する」という選好性という考え方にもとても共感。
0投稿日: 2019.01.01
