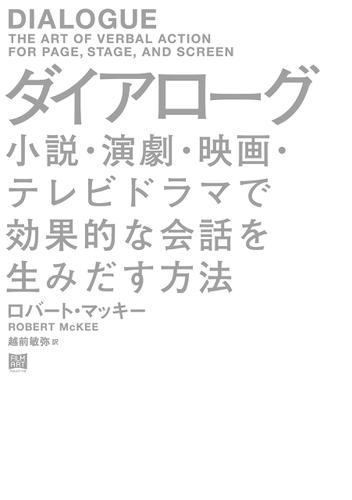
総合評価
(3件)| 0 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「語らず見せろ」という格言は、ダイアローグが力強いドラマを生まず、受け身の説明に終始してしまうことへの警告だ。「見せる」とは、真実味のある登場人物達が願望を満たそうと苦心し、その場にふさわしい行動をとりながら適切な会話を交わすという、現実さながらのシーンを提示することだ。「語る」とは、登場人物にそれぞれの探究を中断させ、そのシーンや人々にとって必要でもないのに、生い立ちや考えや感情、好きなことやきらいなこと、過去や現在などを長々と説明させることだ。ストーリーは人生の隠喩であり、心理学や環境破壊や社会的不平等に関する論文でも、登場人物の生き方とは無縁の主張を論じるものでもない。 このような語りは、行動を起こす登場人物にとっての強い必要性ではなく、そこにいる読者や観客の耳に作家が意見を吹き込むためだけの弱い必要性を満たすものになりがちだ。さらに悪いことに、そういう語りはサブテクスト(言外の意味)を消し去ってしまう。登場人物がさまざまな障害に立ち向かい、目標を達成しようとするとき、そこで口にすることばや行動によって、読者や観客はその人物の内なる思考や感情を感じとるものだ。しかし、作家が登場人物の口を借りて、たいした動機のない明瞭化をおこなうと、読者や観客はつまらないセリフを口にした人物の内面へ通じる道をふさがれる。また、その登場人物が作者の考えを述べる代弁者になり果てれば、興味がしぼんでしまう。 そして、見せることは感情移入を促してペースを速めるのに対して、語ることは好奇心を削いでペースを落とす。見せることは読者や観客を大人として扱って、ストーリーへ誘い込み、作者の築いた世界で感情を解放させたり、さまざまな物事の核心を見せたりしたあと、先々の事柄へと進ませる。語ることは読者や観客を子供として扱い、親が膝を突いてわかり切ったことを説明してやるのと同じだ。 人間の性質は、大きくふたつの側面に分けることができる――外見(その人がどのように見えるか)と実体(その人の本当の性質)だ。したがって作家は、実像と性格描写というふたつの側面に応じて登場人物を造形していく。 実像とは、そのことばどおり、人物の深層心理や倫理観を示すもので、人生が窮地に陥って、選択と行動を迫られるときにはじめて明るみに出る真実の姿だ。〝選択の原則〟は、フィクションであれノンフィクションであれ、すべてのストーリーテリングの基本である。真の人物像は、欲望を追い求めて危険だらけの行動を選んだときにのみ表現することができる。 性格描写とは、人物の総合的な外見、つまり表面上の特徴と行動の総体を表す。これは、好奇心を刺激する、説得力を与える、個性を持たせるという三つの役割を果たす。 (1)好奇心を刺激する。読者や観客は、登場人物の表向きの顔がほんとうのものではないことを知っている。その顔はペルソナと呼ばれ、表の世界と真の性質のあいだにはさまれた人格の仮面だ。独特な登場人物に出くわすと、読者や観客はその人物のことばに耳を傾け、こんなふうに考えをめぐらす。「この人はこう見えるけど、ほんとうはどうなんだろう。正直者か、嘘つきか、やさしいのか、残酷なのか、賢いのか。冷静なのか、せっかちなのか。強いのか、弱いのか。善なのか、悪なのか。興味深い人物像の奥にどんな個性が潜んでいるんだろう。いったい、本当の姿は?」 (2)説得力を与える。想像力をよく働かせて巧みに設計した人物像は、観客や読者が架空の人物の存在を信じたくなるほどの精神や肉体、感情や言語を具え、現実にいるかのように感じさせる。二世紀前の詩人サミュエル・テイラー・コールリッジも言ったとおり、読者や観客はストーリーと登場人物が存在しないと知っているものだ。けれども同時に、物語に没頭するためには一時的に信じなくてはいけないこと、あるいはもっと正確に言うと、みずから不信感を捨てて、疑念や批判なしに登場人物の行動や反応を受け入れなくてはいけないことも知っている。 読者や観客がある登場人物のことを嘘つきだと感じて、「こいつの言うことはひとことも信じられない」と考えるなら、それは真の姿の発見にもなりうる。だが、同じように考えたとしても、単にありそうもない人物像と思っただけなら、そこは書き直したほうがよい。 (3)個性を持たせる。想像力をよく働かせ、しっかり調査して生み出した人物像は、多くの要素を組み合わせてできた独特のものである。遺伝、幼少時の環境、身体的な特徴、知性、感受性、教育、経験、物腰、価値観、嗜好、そしてその人物に個性を与えてきたありとあらゆる文化的影響が混じり合う。日々の暮らしをつづけ、仕事、交友、性、健康、幸福などを追い求めるなかで、さまざまなふるまいが独自の人格を形作っていく。 そして何よりも重要な特徴は、発することばだ。これまでだれも出会ったことがないような話し方をさせるとよい。その語りは登場人物のなかで際立つばかりか、秀逸な技巧を凝らせば、どんな架空の人物とも異なることになる。最近の例では、ウデイ・アレン監督『ブルー・ジャスミン』(13)のジャネット・〝ジャスミン〟・フランス(ケイト・ブランシェット)がそうだ(性格描写のためのダイアローグは、第十章と第十一章でくわしく解説する)。 登場人物の行動に対するわれわれの信頼の基準は、発言に対してもそのままあてはまる。テレビや映画や演劇向けに書かれたダイアローグは、俳優に信用できる演技をさせなくてはならない。そのため、登場人物がどれほど複雑で魅力ある性格の持ち主だとしても、ストーリーの構想がどれほど感情に訴え、意義深いものだとしても、その人物の内面に忠実に、また設定やジャンルにも忠実に話さなければ、読者や観客は不信をいだくだろう。納得のいかないダイアローグは、調子はずれな音がコンサートをぶち壊すよりも早く興味を失わせる。 だからと言って、空疎なまやかしのダイアローグをただ自然にすればいいというわけではない。飛行機や列車やバスのなかで同乗者たちの会話に耳をそばだててみれば、そのような噂話だらけのつまらない会話をそのまま演劇や映画や小説で使うわけにはいかないことに、すぐさま気づくはずだ。現実の雑談は、バスケットボールのドリブルのように反復をつづける。日常会話には鮮明さや響きのよさや表現力が欠けていて、何より重要なことに、意味が欠けている。たとえば、ビジネスの会議は、比喩や修辞などの最小限の表現の綾すら感じさせないまま、何時間も延々と続くことが多い。 日常会話とダイアローグの決定的な相違は、ことばの数でも選び方でも組み合わせ方でもない。ちがうのは内容だ。ダイアローグは意味を凝縮するが、日常会話は薄める。だから、たとえ実世界にきわめて近い設定やジャンルだとしても、信頼できるダイアローグは現実を模倣しない。 それどころか、現実とまったく関係がないのに信頼できる場合もある。アリスの不思議の国のようなありえない世界に住む生き物たちは、生身の人間がけっして口にしない台詞を話すが、自らに忠実であり、設定にも忠実だ。 日常そのままから非現実までどんな設定であれ、戦争ものからミュージカルまでどんなジャンルであれ、不明瞭な一音節から叙情豊かな韻文までどんな形式であれ、ダイアローグは登場人物がおのずと語るような印象を与えなくてはならない。したがって、われわれは厳密に現実どおりかどうかではなく、作中世界での信憑性に基づいてダイアローグのよしあしを判断する。登場人物のことばの選択や語り方を忠実に現実世界に近づけすぎると、日常の凡庸な会話を引き写すことになってしまう。必要なのは、ストーリーの世界とジャンルのなかで、説得力があって自然だと感じさせることだ。 「メロドラマ的な」という形容詞は、やりすぎを非難するものだ。金切り声、恐ろしげな暴力描写、お涙頂戴の感傷、ポルノまがいの濡れ場などなど、一方、シェイクスピアの『オセロ』は殺意に満ちた憤怒を表現し、サム・ペキンパーの『ワイルド・バンチ』(69)は暴力を映像詩へ転換し、スティーヴン・ソンドハイムの戯曲『リトル・ナイト・ミュージック』は深く悲痛な感傷を探り、大島渚の傑作『愛のコリーダ』(76)はあからさまに性行為に耽溺するが、どの作品もメロドラマではない。 オイディプスが自らの目をえぐり出すはるか以前から、偉大な語り部たちは人間の体験の限界を探ってきた。二十一世紀になってもこの探求はつづいているが、それは芸術家たちが人間の内面の深さと幅には限界がないと感じているからだ。登場人物にどんなことさせると思いついても、どこかでだれかが、想像の上を行く方法ですでにおこなっている。 だから、メロドラマの問題は、誇張表現ではなく動機不足に基づく。 興奮状態を鬼気迫るものにしようと、大袈裟なしぐさを連発したり、失敗を悲劇にできないものかと、登場人物の頬に滝のような涙を伝わせたり、その人物の日常に訪れた実際の危機をしのぐ過剰な反応をさせたりすれば、その作品はメロドラマとして片づけられる。 つまり、メロドラマ的なダイアローグはことばの選択によるものではない。人間はなんでもやりかねないし、その際になんでも言いかねない。登場人物が情熱的に語ったり、懇願したり、下品に語ったり、口汚く罵ったりするさまを想像できるなら、それに見合う動機を用意することだ。ふるまいと欲望の釣り合いがとれたら、さらに一歩踏み込んで、「この登場人物は自分の行動についてはっきり語るだろうか、控えめに語るだろうか」と自問するといい。 人物造形の諸要素――服装、身ぶり、年齢、性的傾向、気質、表情など――のなかで、話し方は群を抜いて不信の種になりやすい。おかしなことばづかい、奇怪な表現、そして不自然な間さえもへたな演技――見せかけの感情、浅い考え、空っぽの心――のにおいを漂わせる。だからこそ、書き手はダイアローグの一行一行で苦心して信頼の絆を保とうとする。 作家は感覚を研ぎ澄まし、表現の豊かさが露出過多へと変わる境目に気づかなくてはならない。そのためにはまず、自分の表現手段における言語の限界を見きわめるべきだ。紙の上では非常に説得力のあることばも、舞台で話すにはぎこちないかもしれない。真実味があるかないかを見分ける目安は慣習としてかなり決まっているから、手がけるジャンルをまず見きわめたら、その伝統を学ぶべきだ。最後は「自分がこの登場人物なら、こんなときなんと言うだろう」と自問して最良の判断をくだすといい。仰々しさを抑えるのは、生まれつき具わった感覚と鍛えられた判断力だけだ。そして自分の内なる判断力に従い、疑わしいときは控えめにしなくてはならない。 ごみとは、たとえば「やあ、元気かい」「おかげさまで」「お子さんたちは?」「みんな元気よ」「いい天気だね」「ええ、やっとね。先週は雨ばかりだったけど」といったやりとりのことだ。何もない棚に小間物を並べるように、無能な書き手は退屈なシーンをがらくたで飾り立て、世間話でリアリズムの雰囲気を出そうとする。だが、ただ雑談をさせても登場人物には血がかよわないし、ただスウェットパンツを穿かせてもアスリートにはならない。さらに悪いことに、よけいなおしゃべりは人物とシーンをしぼませ、読者や観客に勘ちがいをさせる。 ダンスがただの動きではなく、音楽がただの音ではなく、絵画がただの模写ではないように、ダイアローグはただのおしゃべりではない。芸術作品は部分の寄せ集め以上の意味を持ち、作品のどの部分もただの部分以上の意味を持つ。 へたくそな会話は、とかく字句どおりになる。つまり、口にしたままで、それ以上の何もない。一方、すぐれたダイアローグは口にした以上の内容をにじませ、すべてのテクストの下にサブテクストがある。リアリズムの伝統に慣れた読者や観客は、あらゆるセリフには言外の意があり、そうでなければそもそも書かれなかったはずだと思っている。そのため、ごみの山に埋もれたものを探し、表面の意味しかないことばから含意を見つけようとする。見つからなければ困惑し、腹を立て、興味を失う。 もし会話の裏にこれといった考えや感情がないのなら、その箇所の内容を濃くするか、さもなければ切り捨てるべきだ。 非リアリズムでは、登場人物は紋切型で立体感がない場合が少なくない。空想上の誇張された世界を舞台にするストーリーは、寓話のような筋をたどる。たとえば、ピクサー・アニメーション・スタジオが制作した『インサイド・ヘッド』(15)がそうだ。その結果、会話が単純で説明的でわかりやすくなるにつれ、サブテクストは退化する傾向がある。『ロード・オブ・ザ・リング』のような作品で、たとえば「危険を冒してかの地へ赴く者は、ひとりとして帰らない」という台詞に、隠された意味や別の含みはない。俳優が皮肉を込めてこれを言ったら、笑われて台なしだろう。 フィクションを書く過程のどこかで、どんな作家も厄介な疑問に突きあたる。自分はそもそもどういう種類のストーリーを書いているのか。リアリティへ向けての作家の姿勢は大きく分けてふたつある。それは模倣型と象徴型だ。 模倣型のストーリーはありのままの姿を写したり似せたりしたもので、リアリズムのさまざまなジャンルがこれだ。象徴型のストーリーは現実の姿を誇張するか抽象化したもので、非リアリズムの数多いジャンルのどれかだ。真実に対してどちらが忠実であるか、一概には言えない。すべてのストーリーは現に存在するものの隠喩であり、リアリズムと非リアリズムのどちらに寄るかは、作家が自分の世界を表現するときに、読者や観客を引き込むための方便にすぎない。 それでも、非リアリズムとリアリズムを大きく分けるもののひとつはサブテクストである。非リアリズムはそれを弱めたり消したりするが、リアリズムはそれなしではありえない。 なぜか。 非リアリズムの作品では、登場人物を象徴する性質――美徳、悪徳、愛情、貪欲、純真――などを際立たせて純度をあげるために、無意識が切り捨てられ、そのため複雑な心理が表現されない。 一方、リアリズムの大前提は、人が考えたり感じたりすることの大半は自覚されないというものだから、登場人物の思考や感情のすべてが直接そのまま表現されてはいけない。そこで、模倣型のジャンルの作品では、心理を多面的に、複雑に、皮肉を交えて描くために、無意識から浮かび上がった欲望を自覚的な意志と対立させる。 複雑な心理や社会を描写するリアリズムでは、ほぼすべての台詞でサブテクストが必要となる。非リアリズムでは、そうした細部に気を散らされないために、サブテクストを削ぎ落とす。 現実の会話もそうだと言い張って、冗長さを肯定しようとする書き手もいる。たしかに一理ある。人は何度も同じことを言うものだ。ただ、単調さは現実どおりだが……つまらない。わたしの美意識が求めるのは生き生きとした語りだ。ストーリーとは、つまるところ隠喩であり、コピーではない。現実らしさ、いわゆる〝細部の反映〟は、信頼性を高めるための様式上の戦略であって、創造的考察の代用品ではない。 ストーリーテリングにおける究極の罪は退屈であること――つまり、収穫逓減の法則を無視することである。この法則では、同じ経験が反復されるほど効果が薄くなる。コーンに載ったアイスクリームは、ひとつ目はすばらしくおいしいが、ふたつ目は香りがなくなり、三つ目は胸焼けを起こす。実のところ、同じ主張が立て続けに繰り返されると、効果を失うばかりか、やがて正反対の結果をもたらす。 少ない台詞で多くを表現する技術を身につけるには、まず、周囲の人たちの〝言わないこと〟と〝言えないこと〟を見きわめる目を養い、それから〝言うこと〟を聞く耳を鍛えることだ。脚本家のウィリアム・ゴールドマンは、おそらく映画史上最もすぐれたダイアローグの書き手で、しばしば〝ハリウッド一の耳〟の持ち主と評される。だが、それを言うなら、ダイアローグ向けの耳というのはどういうものだろうか。 印象としては、記者や速記者のような技能に長け、たとえばバスに乗ったときに、まわりの人の会話を聞いて内容をすばやく正確に書き留められるということだろう。わたしはゴールドマン本人をよく知っているが、彼がニューヨークでバスに乗っていたのはずいぶん前の話だ。しかしどこにいようと、ゴールドマンは作家の耳で深く傾聴し、聞こえてくる言葉よりはるかに多くのものを聞き取る。 語りも行動である。だからゴールドマンのように、人の話をふたつのレベルに分けて聞く必要がある。テクストとサブテクスト。言うことと、すること。語るにあたっての言葉の選び方と文法。人が自分の行為を隠そうとするときに、どんな言葉を使うのかに耳を澄ますといい。〝言わないこと〟を感じると、語り手の巧妙な戦術に気づくだろう。そこからさらに〝言えないこと〟、つまり意識の下で働いて行動を起こさせる衝動と欲求を聞き取ろう。社交場の技術としての語りにも気をつけよう。人はどんなことばを使って他人を動かし、自分の望みをかなえてくれそうな反応を引き出すのだろうか。 <中略> それから、よいものを読み、悪いものを書きなおすことだ。勤勉な作家は、書いていないときはほとんど、熱心に何かを読んでいる。小説や戯曲を読み、映画やテレビドラマの台本に目を通す。劇場や映画館の大小を問わず、そこで演じられるダイアローグをよく見て、よく聞いている。彼らはこれまでに読んだり見たりしたすべてのストーリーに、ふだんの生活で耳にした生の会話を加え、それらの副産物として、ダイアローグ向けの耳を養ってきた。 クエンティン・タランティーノのダイアローグは、自然な響きと高度な表現性をみごとに両立させている。タランティーノの作品の登場人物のように早口でまくし立てる人間は現実にはいないのに、観客はそれが街角で撮られたものであるかのように感じる。テネシー・ウィリアムズの生き生きとしたダイアローグは、デカンターから注がれるワインのようによどみなく流れる。裏社会のごろつきたちの軽妙で粋なダイアローグを書くことに関しては、エルモア・レナードに敵う者はいない。これらの定評ある作家たちの作るダイアローグは、日常会話のように耳になじむ一方で、立体感のある登場人物に独自の声を与えている。 逆に、出来のよくない脚本や小説を読むことになったとしても、作者を見捨てて本を投げ出してはいけない。そういう場合は、もう一度読んで、書きなおすといい。作者のことばを消して、自分のことばに変える。悪いダイアローグを書きなおすことは、才能を鍛錬するもっとも効果的な手立てだ。 作家が外から内へ向かって書くときは、登場人物が出演する劇を前から十列目の真ん中の席で見る客になったつもりで、自分の想像したものが動くのをながめ、シーンを観察し、ダイアローグを聞く。この方法だと、その場でどんな風にも調整できるので、なんにでも使えるし、さまざまな変形が無限に生まれる。作家はそのひとつひとつを吟味し、試行錯誤を繰り返すうちに、理想のビートの組み合わせを見つけて、転換点に至るまでそのシーンを作っていけばいい。 この方法は客観的で受け入れやすく、融通がきくが、ともすると深みに欠ける危険もある。作家がいつも外にいて、遠くから湧き上がる感情がなければ、行動を起こしたり語りはじめたりする意欲が生まれない。そのため、内容と形式に欠陥が生じ、ダイアローグもその犠牲になってしまう。 だから、内から外へ向かっても書かなくてはならない。登場人物の中心に〝わたし〟という名の絶対の核を置き、登場人物の視点で物事を見て、想像上の出来事を体験するというわけだ。 言い換えると、作者はその登場人物を最初に演じることになる。男であれ、女であれ、子供であれ、野獣であれ、中へはいりこんで、即興で演じ、その登場人物を内面からつくり上げていく。その人物となって、いまを生き、さまざまな感情や衝動がこみあげるなかで、求めるものを手にしようと苦悶し、望みを妨げるものを取り払おうと奮闘する。その人物が感じるとおりに感じ、鼓動までも合わせていく。この主観的なダイアローグの作り方を、わたしは内面からの造形と呼んでいる。 内面から書くには、伝説的な演技指導者コンスタンチン・スタニスラフスキーの〝魔法のもしも〟理論を用いるとよい。その際、〝もしもこの登場人物が、こういう状況にいたら、どうするだろうか〟と考えてはいけない。これでは、その人物を外からながめることになるからだ。〝もしもわたしが、こういう状況にいたら、どうするだろうか〟と考えてもいけない。あなたはその登場人物ではないからだ。あなたがそのような状況で感じたり、行動したり、言ったりするであろうことは、その登場人物のふるまいにはほとんど関係ない。だから、〝もしもわたしがこの登場人物で、こういう状況にいたら、どうするだろうか〟と考えるべきだ。あなた自身をもとにしてつくるのだが、あなた自身としてではなく、あなたが作り出した人物として考えるということだ。 有名な劇作家の経歴を調べると、アリストファネスもシェイクスピアもモリエールもハロルド・ピンターも、みな出発点は舞台俳優だったことがわかる。小説家にとってさえも、演じることはダイアローグを書くうえでとても役立つはずだ。 登場人物に合ったダイアローグを作るには、周囲の人々をよく観察し、フィクションもノンフィクションもたくさん読んで、人間の行動に関する知識を身につけることだ。しかし、総じて、すぐれた人物造形の源は自分自身をしっかりみつめることである。アントン・チェーホフも「わたしは人間の本質についてのすべてを、自分自身から学んだ」と言っている。 結局のところ、あなたの生み出す登場人物を駆使することだ。〝魔法のもしも〟で考えよう。もしも自分がこの登場人物で、このような状況にいたら、どうするだろうか。なんと言うだろうか。その正直な答えに耳を澄ますことで、それはいつでも正しい。あなたは人間らしくふるまい、人間らしく話すのだから。 自分自身の姿を知るにつれ、ほかの人間の本質も、それを表現する独自の形もわかるようになる。そして自分を知れば知るほど、より多くの人になれることに気づく。人物を造形し、演じ、彼らのことばで語ろう。 私はここできみを見守っている――きみの瞳に乾杯。
0投稿日: 2025.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ創作に関する会話についての創作論。言葉にして伝えること、言葉にはしないこと。その行動の背景となるサブテキスト。物語を別の方向から楽しむことができそう。ただ、中身が難しくて理解できたかははっきり言えないのが残念。もう少し勉強してからもう一度読みたいかな。
0投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログダイアローグの主原則 ①ダイアローグがかわされるたびに、シーンを進展させる行動(アクション)や反応(リアクション)が生まれること ②そうした行動は語りの表層で具現するが、登場人物の行動の水脈はサブテクスト(言外の意味)から目に見えぬ形で流れている 潜在的欲求 欲求の対象 究極課題 シーンの課題 動機 シーンの支配者 敵対する力 シーンの価値設定 サブテクスト ビート 進展 駆け引き 転換点 真の姿 真の進展 テクスト 明瞭化 性格描写
0投稿日: 2018.01.20
