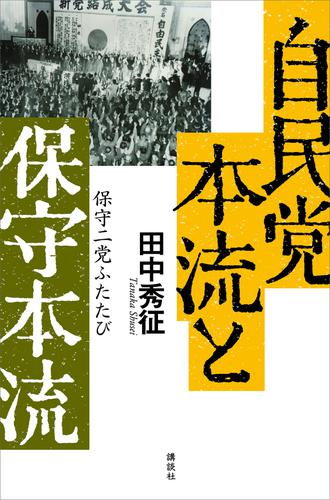
総合評価
(5件)| 3 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ一寸した切っ掛けで興味を覚えた一冊であったが、出会って読了して善かったと思う。 基本的には昭和20年代辺りから近年迄の日本の政治という内容だが、凄く興味深い。 本書の著者が参加した対談を読む機会が在った。その中で“自民党本流”、“保守本流”という表現を用いていた。それがそのまま題名になっている本に出会い、是非読みたいと思ったのだった。 「保守」とでも言えば、自民党に所属、自民党の流れを汲むグループに所属という政治家を想い起す。としても、「保守?」という感がしないでもない。本書はその「保守?」という問いへの一定の回答めいたモノを提示しているようにも思った。そういうことを説きながら、「保守」と呼ぶべきモノ、呼ばれているモノに大きく2つの潮流が在るとしている。その大きな2つの潮流が、昭和20年代以降の様子の中では、石橋湛山を始祖とするように見受けられる「保守本流」と、岸信介を始祖とするように見受けられる「自民党本流」とであるとしている。 大政党の「自民党」には、色々な考え方の人達が在って、目指したいと主張する事柄も似ているようで意外に幅が在る。著者が「保守本流」、「自民党本流」と大別している2つの潮流の間では「歴史観」、「憲法観」というようなモノが大きく違うということが指摘されている。近年の政権は、「自民党本流」の側の「歴史観」、「憲法観」を示しているようであるという。 こうした「現代史」を考える材料になる一冊だが、1990年代に選挙制度を換えて、何か「人」が政治の世界に輩出され悪くなってしまったというような話題も在る。そういう中で「行詰っている?」という雰囲気も色濃いような気がする。そういう辺りも「考える材料」として有益だ。そういうような内容に関しては、1990年代に政治の世界に在った著者が語る内容なので、真に迫る。 本書は2018年に登場していて、それ位の時期の話題迄は入っている。そこから数年経ているが、それでも尚、本書は有益だと思った。政治が揺れているような感、または何か大きく変わろうとしているかのような感が否めない昨今であるからこそ、「少し前迄を遡りながら、色々と知って考えてみる」というようなことが有効なのかもしれないと感じるのだ。 なかなかに有益な一冊で、1990年代頃等の記憶にも残る様々な経過等を詳しく解説している感で面白い。御薦めしたい。
1投稿日: 2024.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ選択肢の無い選挙は、辛い。 ダイナミックさが薄れてしまった政治の世界。 そういう閉塞感を見つめ直す。
0投稿日: 2019.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ自民党所属の元衆議院議員である著者が、1955年に設立された自民党の歴史の本質を、「岸信介に代表される自民党本流」と「石橋湛山に代表される保守本流」という2つの政治思想を背景とするダイナミズムにある、という観点からまとめ上げた労作。 著者の問題意識は、太平洋戦争を招いた日本の植民地政策等の対外膨張を批判し、「小日本」とも呼べる国家観をベースとして現在のリベラル勢力をも一部包含していた自民党の保守本流の流れが、”ニューレフト”と評された宮澤喜一を最後に潰えてしまい、岸信介を信奉する安倍晋三の政権下において、かつての自民党が持っていた2つの政治思想のダイナミックな政治論争とそこから生まれる多様性が消失してしまった、という点にある。 本書を読むと、いわゆるハト派の保守というものが、リベラルの一部の政治思想を包含するものであり、ハト派の復権こそが日本の政治において求められているのではないか、という感覚を新たにした。
0投稿日: 2019.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ自民党史の流れを理解するのに参考になった。これまで何が保守でリベラルなのか、その軸が全くと言っていいほど理解できず混乱していたが、野党も保守を名乗るようになっている現在、本書の自民党本流と保守本流という流れで考えると現状の整理がしやすく、今後の政治の動きへの見方が深まるように感じる。著者の議員時代の直接の経験をベースに書かれており、それぞれのキーパーソンに対する印象、評価、その変遷等についても興味深く読んだ。
0投稿日: 2019.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ自民党総裁選の動きが地味に始まっている。でも、「どうせ安倍さん続投でしょ」という、諦めムードなのか全然盛り上がる感じがない。(対抗馬いないというのが大きいところか?) 一昔前なら自民党総裁選となれば、個性派の候補者が出てきて「次はどうなるのか?」という期待感があったような気がするが、最近は気が付いたら終わっていたなんてこともざら。 なんでそんなことが起きるんだろう? そもそも「自民党」ってなんだろう?とニュースを見ていて気になったので早速本屋に行ってみた。気になったことは関連する書籍を「5冊」読むのが近藤の鉄則。一冊だけだと思想などに偏りが生まれるので必ずしも正しい情報ではないことが多い。 久しぶりに「政治」関連の書籍を手にしてみる。こういうときはまずは知っている著者から入るのがいい。時間があれば日曜日朝にTBSで放送されている「サンデーモーニング」という関口宏が司会をしているニュース番組が好きで見ている。 そこに今回の著者田中さんがコメンテーターとして出てくる。地元「福山大学」の教授だったことは知っていたが、経歴を見て元衆議院議員だったなど新たな発見があって読む前から気になるポイント満載。笑 90年代ころまでは自民党も「保守本流」と「自民党本流」と二つの勢力が拮抗していた。簡単に書くと改憲消極派の「保守本流」と改憲積極派の「自民党本流」。ひと時代前までは「保守本流」が中心勢力だったのが、今は「自民党本流」が主流。(つまり、安倍総理は「自民党本流」) 細かい違いや歴史的背景については是非、本著を手にして詳細を確認して欲しい。でも、その中でその流れが大きく変わった背景には「選挙制度」が大きく起因していることが分かった。 細川政権下で「中選挙区制」から「小選挙区制」になったことが一番の原因だと締めくくっている。(この理由についても本著で!)しかし、政治って改めて知ると面白いものだ。 追伸: 私はノンポリなので別に自民党を擁護しようとかは全然考えてないけど、今のほうが意識はあるはずなのに、中高生だった90年代のほうがよほど印象に残っている政治家がたくさんいたような気がする。。。。何だか個人的には淋しい。(その原因こそが、選挙制度なのだということが分かったのが収穫!
0投稿日: 2018.08.22
