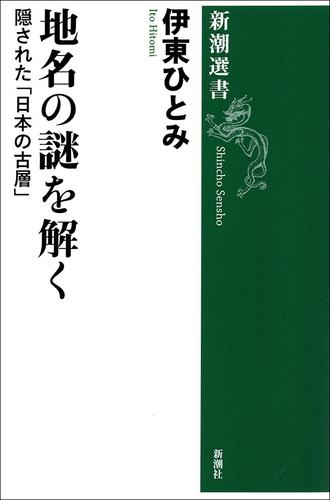
総合評価
(3件)| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ各地に散らばる個々の地名について述べることが横糸だとするならば、本書は日本の太古からの歴史・信仰・コトバをめぐる縦糸だと言えよう。もし読者の関心が身近な地名の由来を表面的に知りたいだけだとしたら退屈な遠回りのように思えるかもしれないが、参考文献が多く載せられているので、本書を足掛かりにしてほかの文献へと地名の探求を広げていくとよいのではないだろうか。
0投稿日: 2020.10.28地名は、縄文人が使用していた言葉
人々に使用されていた地名が、律令国家の確立の一部として、字数や使用文字の制限を課せられ、漢字で表記されるようになる。これが明治維新での中央集権体制の確立のために、再整理される。さらに、昭和の大合併、平成の大合併などで再整理されるといった、地名がたどった歴史的運命の解説です。何気なく使用していた地名について、新たな視点を与えてくれました。
0投稿日: 2018.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ●→本文引用 ●ともあれ縄文人は「よくもの言う」自然と対峙しながら、生活圏にある川や野原、山、谷、沢、浜、岬、さらには巨木や岩などにそれぞれ名前をつけていった。それは、「そうした自然を自分たちの息がかかった味方に引きずり込んでいく」ことだった。と小林氏は言う。ソトの世界に存在するよそよそしい場所も、名前をつける(あるいは、名前を知る)ことで、たちまち関係を取り結んで自分たち人間側の世界に所属させることができる。名づけというのは、所有すること、占有することでもあるのだ。(略)太古、人々は場所に名前という言葉を貼りつけることで、人知の及ばない力をもつ土地の精霊をその名で縛って言向け和し、ハラの場所一つひとつを自分たちの生活空間にマッピングしていった。西田氏の「定住革命」論にからめるならば、土地への名づけは定住生活を成り立たせるために必要な観念操作だった、とも言えそうだ。 ●おそらく常陸地方に暮らしていた縄文人にとって、谷間の低湿地を表す「ヤト」という地名は、そのまま、その土地に宿る精霊の名前でもあった。そして、その「ヤト」という地名=神名は、精霊のカミとしての霊力や性格を背負うものだったのではあるまいか。よく「名は体を表す」と言われるが、「草木よくもの言う」時代にあっては、名前(目に見えない世界)と実体(目に見える世界)はぴったり一致していて、まさに名実一体。目の前に広がる大地につけられた地名は、ムラの人々が代々カミなる自然と真剣勝負の交渉をして獲得してきた認識のすべてを背負ったものだったに違いない。
0投稿日: 2018.01.20
