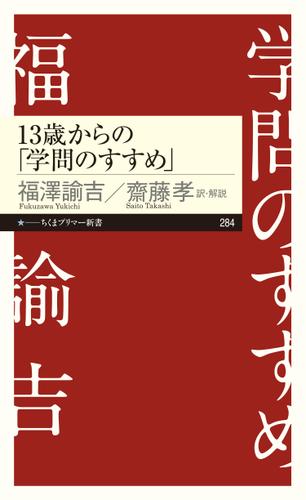
総合評価
(9件)| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
福沢諭吉の学問のすすめがわかりやすく要約・解説してある本。 国民のあるべき姿・政府のあるべき姿がとてもわかりやすく書いてあった。 要はどっちが上とか下とか作らず、偉ぶったり依存したりせず、各々が自分の仕事を全うし自律・共創を目指そうということだと理解した。 福沢諭吉は明治時代の丁度開国した時代に生きた人なので、西洋の文化や技術・軍事力に圧倒され、日本もこのままでは植民地にされる!西側の仲間入りをせねば!って必死だったんだろうな 個人的には、個人の自由を侵してくるものには卑屈になるのではなく、論理と道義を持って抗議しよう。 という内容が印象的だった。 「自分が我慢したらいいかな、、」と思いがちだが、その判断が自律から遠ざかる一つの原因なんだろうなと思った。学問にはげみ自律を目指そうと思った。
0投稿日: 2025.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ学問のすすめを読んで見たかったのですが、難しそうだったので、齋藤孝先生解説の本を読んで見ました。 中学生向けの本だけあって、とてもわかりやすく理解できました。 日本人なら一度は読んでもらいたい学問のすすめ。 この本ならわかりやすいので是非。
0投稿日: 2022.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ気にはなるがなかなか手に取らない書だったが、 子供に読んでもらうのに読んでみた。 訳者の言葉になってるなと感じるところはあるが、 中学生が読むのには丁度いいのでは。 解説も分かりやすい。 「学問のすすめ」 これが、100年前に書かれたのかと言う驚きと 新しい時代の始まりに道を示した書と納得。 当時20万部出版されたらしいが、 読んだ人はそれ以上になるだろう。 今一度、現代に生きる者が読んでも良い書だと思う。
1投稿日: 2021.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「DJ日本史」で学問のすすめが特集されて、かなり気になったので読んでみました。13歳からって書いてあるから、私にも読めるかなぁと、図書館で借りました。 期待通り、学問をなぜするのか説得力のある答えが書かれています。幼稚園児の子供にも教えたいけど、ちょっと難しいので、絵本とかにして読み聞かせしたいです。 絵が苦手ですけど、、どうしても子供にも伝えたいです。 私自身も、使う予定はないけど英語を勉強しようと思いました。
0投稿日: 2021.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
賢い政府は賢い国民を作り、良い社会を作る。 そのためには一人一人が独立する気概を持つ。 それには皆が学ぶことが必要。という軸の元 学問の大切さ、それをどう生かすか、どう生きるかが イラストを交えながら分かりやすく書かれています。 本などで学び、それを深め深化させ(考え・議論し更に学ぶ)、実際に活用する。 学ぶだけではなく、人と交流し社会的に活きる。 自分のために学ぶだけでなく、社会の為、後世に残すために学ぶ。 学問をするのは良い社会をつくるため。 13歳のうちにこうした視点を持つと持たないでは その後の人生に大きな差が出ると思います。 大人にも気づきを得られる1冊です。 イラストもあり分かりやすい。
0投稿日: 2021.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
Q、妬みがなぜ生まれてくるのか? →A、自由に行動できないから。 自分に不自由があると、人を妬んでしまう。
0投稿日: 2019.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ福澤先生の文をわかり易く書いてあるというより 訳者の言葉に直してあります。 13才はもう文章を子ども向けにする必要はないのではないかな、と思うので、中学生以上なら、同じ訳者の普通の現代語訳の方がいいのではと思う。
0投稿日: 2017.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読了】 平成の世を痛烈に皮肉っているような感じがしました。 ニュースを賑わす政治家やぼくたちを。 福沢諭吉が現在に生きていたとしたら、きっと嘆くのだろうな。 タイトルに偽りなし。 読みやすい文章だったので、学生時代に読んでおいて損はない一冊でしょう。
0投稿日: 2017.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ齋藤先生は以前から福沢諭吉の「学問のすすめ」をものすごく押しています。日本人の必読書ナンバーワンとまでいっています。私も早く読まないとと思いながら手が付けられていませんでした。そんなところへ、本書が登場し、雰囲気だけでもつかめるかと思って読み始めました。うまくすれば、来年1年間で「『学問のすすめ』のすすめ」が書けるのではないかと思ったりしながら。ところがです。あにはからんや。あまりおもしろくないのです。それはちがうだろう、と思うようなこともあるのです。時代が違うといってしまえばそれまでなのですが、少し根本的に私がなじんできた考え方とは違うものがあるようです。福沢諭吉自身は西欧諸国からの遅れを感じて焦っていたのかもしれません。そんな中の最終編。「人望と人づきあい」の中で、見た目の印象が大事といいます。生涯両親の喪に服しているかのようにしているのは大変よくないといいます。そうか、私自身がそうだったかもしれない。なんか、かたくて、ものわかりが悪そうで、気難しそうで・・・そう思われていたとしたらごめんなさい。あらためます。といいつつ、きっとこれって父親からの遺伝なんだろうな、なんて思っています。
0投稿日: 2017.09.17
