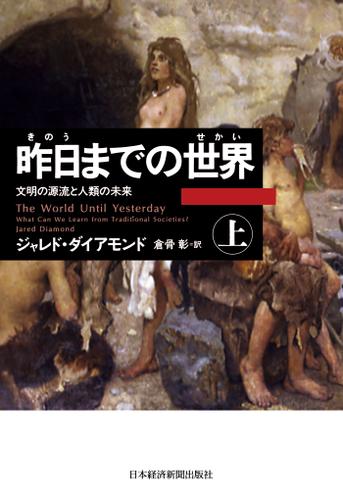
総合評価
(47件)| 10 | ||
| 19 | ||
| 10 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
昨日までの世界(上)(下)―文明の源流と人類の未来 「銃・鉄・病原菌」のダイアモンド博士の最新翻訳本です。 今回のテーマは、国家を持つに至る前の部族の段階の社会と国家社会との差異を考察することによって、違いを明確にし、部族社会の特長を国家社会に応用する術を学ぶというもの。 「見知らぬ人との関わり方」「戦争と平和」「子育て方法」「老人への接し方」「危険への対処方法」「宗教」「多言語」「非感染性疾患」など様々なテーマを扱っています。 具体的な事例の記載も豊富に収録されています。 博士らしい、客観的な比較と違いの要因の分析など、安心して読める内容です。 今の安心・安全暮らしの中で、改めて人類史の特異な時代・環境に生かしてもらっていることの感謝すると共に、更に今の社会をより暮らし易いものにしていくかのヒントもいろいろと提案されています。 ただ、トータルで800ページは中々骨の折れる読書ですが、時間を使うだけの知見を得ることができると思います。 竹蔵
1投稿日: 2025.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が持っているあらゆる価値観が絶対的ではないと知る。とはいえ、その価値観はその文化を育んできた背景の中で、より平和で幸福な方向へと向かってかなり合理的に決定されてきているのだと考える。わたしはいまの世界の価値観を受け入れつつ、変えるべきことを変えていきたい。 ——- ・伝統的社会 社会的ネットワークが強調される。同じコミュニティでは勝ちも負けもない。 ・現代国家社会。特にアメリカ 個人の重要性が強調される。自己利益最大化、自分本位の個人主義、個人間の優劣 ▲子供に優劣、競争させ、のべつまくなしに指示を与える→子供の発達を阻害 ○人と会話して過ごす。受け身ではなく能動的に遊ぶ。社会性を身につける。 【現代国家と違う】 ・放任主義の子育て。幼くても自分の行動に責任を持つべき。火のすぐそばで子どもが遊ぶ、火傷をすることも、ナイフを握ったり口に入れたり振り回すことも許容 ・介添なしの出産=人間は強くあるべきで、自力で困難に向かうべき ★アロペアレンティング=アカビグミー族では1時間に平均8回いろいろな人に手渡される 【背景となる合理性】 ・国家社会 VS 非国家社会 ・国家社会は子供に利害をもっている。有能で従順な市民、労働者、兵士にする必要。 ・中央集権的に決められ、道徳の範囲が決められる。 ・狩猟民族では、食糧確保における女性の貢献度が高いと、父親の子育てへの貢献度が高い ・ニューギニア高地では男性は戦うもの、家族を守るもの、と考える ・狩猟民族は所有物が少ない=体罰が少ない ・農耕民族や牧畜民は所有物や財産が多い。=家族や集団全体に被害を与えるようなことを子供がしないように体罰。 ・狩猟採取民族は徹底した平等主義。 ・子供の発達が親の責任とは考えない ・狩猟採取民族は高齢者や病人を帯同できない。よって遺棄、殺害する。 ・現代国家高齢者は社会的に孤立する傾向。利用価値が昔より低い。 ★子ども夫婦の子育てを助ける ★加齢とともに向上する心身の属性を生かす=専門分野にかかわる知見や経験、人間や人間関係についての理解力、自分のエゴを抑えて他人を助ける力、多面的知識データベースが関与する複雑な問題の学際的思考の組み合わせ力 ★管理、監督、教育、助言、戦略立案、取りまとめ ★高齢者が得意とし、かつ、やりたいことを任せる
0投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログダイアモンド氏 3編目。 伝統的社会と現代社会を比較しながら、様々な考察を行う。相変わらず膨大な知識に基く検証は凄いの一言。 上巻では語られるのは商売などに代表される取引の実情、戦争、子育て、高齢者など。 取引と言っても現代では通貨があるが、伝統的社会では主に物々交換。地域や民族によって生産される物も違い、暗黙の了解で助け合っている。そんな人達が争いを起こしたりと、規模こそ違えども現代も変わらないなと感じた。 高齢者の章は初版から10年経っておりさらに深刻。価値が下がっている、というのは凄く納得出来た。
0投稿日: 2023.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ600万年の人類史。1万1000年前に農耕民族になり、5400年前に国家が成立し文字が生まれた。 大きく4つの社会形態 1. バンド (小規模血族集団) - 数十人だけ。平等で1万1000年前まで存在。 2. トライブ (部族社会) - 数百人規模。みな知り合い。政治的指導者の存在が希薄で専門家は進んでない。1万3000年前から存在? 3. チーフダム (首長制社会) - 人口が増加して経済活動が専門化しはじめる。見知らぬ人と会っても同領内いることによる安心感で紛争が減る。首長の神権的地位から派生した共通の政治的宗教的アイデンティティあり。また経済的な再分配。貢物と分配。政治的経済的イノベーションが生まれたが、制度的な不平等が生まれた。7000年前までには存在? 4. ステート (国家) - 人口規模の増加、政治の組織化、食糧生産の集約化。 世界中に多様な社会が存在しているのか。 x - 知能の差、生物学的な差、労働倫理の差、 o - 環境による違い。政治の集権化が進み、社会清掃が増えたのは、人口の稠密になったためであり、それは農耕と牧畜により食糧生産の増加と集約化のである。栽培化や家畜化ができる野生の動植物の種類は地域によって異なる。 第二章 国家社会における司法の欠点は、制度の趣旨が、民事の場合は損害を賠償する責任の所在を判断すること、刑事の場合は加害者に賠償させることとされ、感情的な対立の終息や和解をはかるという事が二の次にされ、ほとんど目的にもされないということ。 - 実験的に修復的司法が取り入れられている。 非国家社会では、人間関係を含むさまざまな関係を紛争前の状態にまで回復し、感情面での対立を終結させる 国会社会の紛争解決システムの利点は、1) 報復抑止の効果、2) 紛争解決の判断が当事者間の力関係の外側でなされ、3) 刑事民事上の罪を明確にすることで再犯や一般の人の犯罪抑制効果。 第4章 人間が生得的に暴力的かあるいは協調的かの議論は無益。どちらでもありうる。どの形質が特徴として際立つかは外部環境の影響に左右される
0投稿日: 2021.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログダイアモンド博士の本業だったニューギニアでのフィールドワークを多く読ませてくれる。伝統的社会と比較することで、現代社会がどういうものか、我々が常識としている価値観がどういうものか、客観的に考えさせてくれる点が最も有意義な点となっている。ほんの数万年前までは誰しもがこういった生活を送っていたと想像させてくれる。 伝統的社会では幼児が母親と一緒にいる時間が高割合との記述があったが、その後、祖父母や親戚などコミュニティで子育てして両親は食物採取に行ける、という記述もあり、内容的に混乱してしまった…
0投稿日: 2020.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者のニューギニアでの体験を通じて伝統的社会のあり方を振り返るとともに、現代社会との対比を説明した書籍。切り口は、戦争、子供、高齢者。(生活への余裕が生まれ)文明の成熟とともに司法が発達し、当事者間に委ねない仲裁手段が発達した。高齢者は経験、知識、技術が若年者より優れていたため重宝されていた。子供・高齢者ともに、集団にとって負担になる場合口減らしをすることもあった。 伝統的社会は、生きることが最重要課題であり、食糧に余裕が無い時代のことである。人間も生物として、種の存続に必至であった時代のことだ。意図的な口減らし、当事者による報復合戦など、現代社会と比較して、酷な一面もある。一方で、現代社会は、食糧供給安定、文明の発達、平均寿命向上・技術革新を経て、資産を持たない高齢者への社会の関与の仕方、環境汚染などの別の面で問題が発生している。総じて、社会は改善してきているが、何をするにも副次的な影響があり、そこから発生する課題を予見しながら対処することが望まれるのは、これまでも、これからも変わらないのであろう。この普遍的な考え方を理解出来た点はよかった。 現代の高齢者の価値が、保有資産に比例するのは些か寂しい面があり、著者提示の、孫世代の育児への参加、知識経験の若年層への提供、管理者監督者としての指導は高齢者とともにある有用な選択肢であろう。
0投稿日: 2020.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界的大ベストセラー『銃・病原菌・鉄』の著者、ジャレド・ダイアモンドによる本書。 この『昨日までの世界』は、文明社会が興る前の人類の伝統的狩猟採取社会ではどのような生活が行われていたかを、最近まで、あるいは現在もこの伝統的狩猟採取社会を営んでいるニューギニア奥地の少数狩猟民族やアマゾン奥地に住む狩猟採取民族らの調査を通じて解き明かしていく学術書である。 人類が現在のような中央集権的国家社会を営むようになったのは、およそ5000年ほど前だ。人類誕生が約600万年前、つまり人類歴史のほとんどの期間は伝統的狩猟採取生活による社会で人類は生きてきたのだ。 現代社会に生きる我々は、現在の生活様式が一番優れていると勝手に思っている。 例えば、国家や軍隊を作り、法律を整備して警察を作り、争いごとが起きれば裁判によって解決されるという社会だ。 しかし、このような社会的生活は歴史的にみればほんの最近始めたことに過ぎない。 果たして本当にこれが正しい人間の生活なのだろうか? それ以前の人類の歴史のほとんどを占めている狩猟採取生活にメリットは全くないのだろうか? 本書は、非常に分かりやすく記されており、歴史初学者であっても容易に理解することが可能だ。ちなみに僕がこの上巻を読んで一番驚いたのはヨーロッパ人と初めて遭遇(ファーストコンタクト)したニューギニア奥地に住んでいた伝統的狩猟部族達の回顧録だ。 彼らは、1900年代に入るまでまったく他部族との接触はなく、同じ部族だけで暮らしてきた。他の人種の存在などまるで知らなかった彼らが、肌の色の白い、人に似た形をした生き物と突然出会うことになったのだ。 その部族の人たちは、肌の色の白い人間は死んだ人間であると思い(人は死ぬと腐敗し、色素が白っぽくなるからだろう)、この白人達は自分たちの死んだ先祖が蘇ってきたものだと考えたのだという。 もちろん言葉は通じず、同じ人間であるかも疑問だった。 そこで彼らはこの白人達が自分たちと同じ人間であるかどうかを調べる為、こっそり白人達の使っていたトイレに忍び込み、白人達の排泄物が自分たちと同じような排泄物であるかを調べ、さらに自分たち部族の若い女性を白人の男達の元へわざと行かせ、彼らと性行為をさせ、白人の男が自分たちと同じ性器を持ち、同じ性行為をするかどうか調べさせたのだ。 なんという勇気だろうか。 逆の立場になって考えてみて欲しい。 もし自分達の前に、謎の飛行物体が降り立ち、その中から 形は人間の女性のように見えるが、言葉は通じず、髪の毛の色は真っ赤で、しかも肌の色が真緑の生き物 が出てきたとしよう。 自分の部族の長老から、 あの生き物が人間の女かどうか調べろ。とりあえずお前、アレとちょっとヤッてこい。 と命令されたらどうだろうか。 は?いやいやいや、あれ、どう見ても人間と違うでしょ!?肌緑色だし・・・ え?ちょ、ちょ、ちょ、おま、ま、待って、絶対、無理無理無理無理無理無理~~~!!!! となるだろう。 このような命を受けたニューギニアの少数部族の若い女性も同じように感じたのではないだろうか。 それでも彼女は使命を果たしたのだ。まさにヤマタノオロチの生け贄にされた乙女の心境だったに違いない。もの凄い勇気だ。まさに尊敬に値する。 まあ、冗談はさておき、本書の上巻では、『部族同士の抗争』、『子育て』、『高齢者への対応』の三つがメインテーマとして描かれている。 『部族同士の抗争』については、我々が思い描く銃と大砲を駆使した『戦争』とはかけ離れており、弓矢と槍での戦闘が行われていた。死者数も当然微々たるものである。 しかしながら、彼らにとって抗争は自分たち部族の生存と滅亡を左右する最大の凶事だった。 本書のなかに記されたデータは驚くべきものであった。 少し詳しく書くと、100年間の平均で最も戦争による死亡率が高かった国家は20世紀のドイツとロシアであった。 この両国は第一次世界大戦と第二次世界大戦という二つの大戦争によって国土の大半が戦場と化し、多くの死亡者をだした。その戦死者指数はドイツ0.16(人口1万人あたりで年間16人が死亡するという意味)、ロシアは0.15(人口1万人あたりで年間15人の死亡)となっている。 ちなみに同時期の日本は原子爆弾の投下や沖縄戦の惨禍などがあったにもかかわらず0.03(人口1万人あたりで年間3人の死亡)という数字だ。 しかし、伝統的狩猟採取民族の戦争死亡率は0.25(人口1万人あたりで年間25人の死亡)に跳ね上がる。これは弓矢と槍での戦闘で、一回の死亡者数が少ないといえども常に隣接する部族と抗争を行い、酷いときには片方の部族が女子供も含め皆殺しになるという状況では、世界大戦を上回る数の割合での犠牲者が常時発生していたのだ。 ニューギニアの少数狩猟民族が中央国家により、抗争を禁じられた時、少数狩猟民族の男達は反対するかと思ったら、誰一人それに異論を唱えなかったという。 なぜなら、彼らは一様に 「終わりのない戦いは怖かった。何処にいても油断が出来なかった。人を殺すのも殺されるのも嫌だった」 と話し、中央国家による部族への介入を喜んだという。 また『子育て』の章も非常に興味深いものだった。 伝統的狩猟民族の子育てはまさに『子供ファースト』の社会だった。 体罰や厳しいしつけなどは全く無く、赤ん坊の乳離れの平均は3歳になるまでだという。 もはや信じがたい事実だが、考えてみると狩猟民族の食生活には僕たちが普通に利用する赤ちゃん用の離乳食や牛乳などは当然なく3歳になるまでの子供に与えられる『食事』は母乳が一番安全で効果的で効率的だったのだ。 その為、3歳までの子供がいる母親が再び妊娠し、出産してしまうと二人の乳幼児に十分な母乳を与えることができず、やむを得ず、新しく生まれた嬰児を遺棄する(殺害する)という嬰児殺しも発生する。しかし、この可能性は非常に低いらしい。なぜなら授乳中の母親の妊娠率は非常に低いためだという。 ただ、この『授乳中の母親は妊娠しない』というのは現代社会に生きる女性にはあまり適応できないそうだ。それは伝統的狩猟民族の母親と現代の母親の授乳をする頻度が全く違うからだという。 伝統的狩猟民族の母親はひっきりなしに乳児に授乳している。眠るときも赤ん坊と添い寝をし、日中も乳児を抱きかかえて、ぐずればすぐに授乳するのだという。 ちなみに『赤ん坊が泣いたり、だっこを求めたりする時にすぐに対応してはいけない。すぐには対応すると赤ん坊がわがままな子供に育つ』と僕などは子供の頃、そう教えられたのだが、これは全く根拠のないことらしい。 伝統的狩猟民族の赤ん坊は泣けばすぐに周りの大人が対応する。 伝統的狩猟民族の赤ん坊の泣いている時間と現代の文明社会で暮らす赤ん坊の泣いている時間を比べたら、伝統的狩猟民族の赤ん坊はほとんど泣いたまま放置されるということはないという。 その結果、伝統的狩猟民族の子供はみなわがままに育ったかというとそうではない。もちろん、同一環境による比較実験が出来る訳ではないのでこの結果はなんとも言いがたいが、僕らが教わった子育てが一番正しいという思い込みはもしかしたらあまり根拠のないものなのかもしれない。 さらに『高齢者への対応』についても非常に興味深いものがあった。 伝統的狩猟民族において高齢者はいうなれば『外部記録媒体』なのだ。 つまり、文字や紙のない部族においては、『知識や経験』は高齢者の専売特許であり、日常生活に役立つこと(どの植物が食べられるか、どの植物に毒があるか等)から緊急事態(過去の台風や災害などの生き残り方法)への対応方法など、高齢者がいなければその部族が生き残れないという状況だった。 現代の文明社会においては、この高齢者のメリットはどんどん減っている。 過去の出来事がすべて紙や電磁的媒体に記録され、実際に経験をしなくても誰でもその情報を得ることができるからだ。 伝統的狩猟民族でも当然、このようなメリットを提供できなくなった高齢者は部族のお荷物となる。伝統的狩猟民族の移動について行けなくなった高齢者は遺棄され、殺害されることもある。 これに対する伝統的狩猟民族の高齢者の防御策もなるほどとうなずけるものであった。 例えば「所有権を死ぬまで若者に譲り渡さないこと」や「男性の結婚は40歳を超えた者にしか認めない」などといった僕たちには信じがたい掟を作っている部族もある。 『所有権を譲り渡さない』というのは、家畜や土地などの所有権は全て父親に所属し、息子達はそれを父親からの直接の相続によってしか得ることができない。つまり、年老いた父親は相続権を餌に息子達に死ぬまで自分の面倒をしっかりとみさせることができるのだ。 『40歳を超えなければ男性は結婚できない』というのは、文字どおりそのままの意味であり、40歳を超えて初めて部族の若い娘と結婚をすることができる。 40歳という年齢は平均寿命が50歳代の伝統的狩猟民族とってはかなりの高齢であり、ほぼ『高齢者』と言っていいだろう。 これは、部族を維持していくには『高齢者』を大切にしなければならないというルールを若者にたたき込むという意味があるのだ。 なぜ若者はこのような、ある意味、合理的でない掟に従うのか? これは、自分の番がいつか回ってくると分かっているからだろう。 今我慢すれば、自分が年をとった時にいい目をみることができる。この一念だけで、若者は我慢をすることができるのだ。 『昨日までの世界』この上巻を読んだだけでも目から鱗が落ちる体験を何度もすることができた。 我々人類は、そのほとんどの期間を過ごしてきた伝統的狩猟民族としての生活をほぼ全て捨ててしまっているが、こうしてみると有利な面もいくらでもあったのだと気がつかせてくれるのだ。下巻も楽しんで読んでいきたい。
30投稿日: 2019.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで読んだダイアモンドの作品とは一線を画している様な気がする。 この作者がずっと研究してきた伝統的社会との比較を通じて、現代社会への問題提起をしている。 どれが正しいとか間違っているとかの判断を下そうというものではなく、哲学的な色が強いかな。 恐らく晩年に達している作者は、自分の研究から得た考えを集大成的する意味合いで作ったと思う。それだけに作者の強い思いが伝わってくる。 自分と他者とを区別する境界線から始まって、「平和と戦争」・「子育てと高齢者」についての考察が上巻の内容。 作者のいうところの工業化社会に属している自分にとって、全く別の価値観(伝統的社会の価値観)を提示することで、自分たちの考えを俯瞰して冷静に見ることができる。 こういう風に自分の価値観をひっくり返す作業は、頭を柔らかくするには一番な気がする。 個人的に面白かったのは終盤の高齢者の位置づけと価値の話。 特に高齢化社会が今後も進んでいく日本としては、作者が提示する高齢者の価値(子育て・経験の共有・高齢だからこそできる仕事)は暗い問題に対する希望になり得るんじゃないだろうか。 下巻への期待も込めて星四つで。
1投稿日: 2019.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ狩猟採取社会や首長部族社会などの伝統的社会と現代の国家的社会を比較する。狩猟採取社会は人間が現代のような社会を形作る以前の何万年と進化してきたものだ。その社会で採用されている風習は進化の波に洗われてきたものといえる。伝統的社会との比較による知見をこれからのわれわれの政策に生かすことを目的にしたという。
0投稿日: 2018.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ『文明崩壊』『銃・病原菌・鉄』のジャレド・ダイヤモンドの最新著書。自らの経験と幅広い分野の研究結果を積み上げて持論を展開する。これまで自分が知らなかった事柄が多く語られているが、数々の事例によって検証されていて非常に説得力がある。ただ、前著と比較して、事例が多すぎてかえって読みにくくなっているような気がする。 本書は西洋社会と伝統的社会の比較。伝統的社会のいいところと悪いところを検証することで、現在の社会(西洋社会)をよりよくするための参考にする、というのが本書の目的。
0投稿日: 2018.10.06シリーズ完結編かつ入門編
『銃・病原菌・鉄』、『文明崩壊』に続く三部作?完結編です。 ニューギニアの回想から始まった『銃・病原菌・鉄』のように、本作もまた著者の原点であるニューギニアから始まります。フィールドワークの体験談が多く、読み物としてもなかなか面白くなっていますが、後半の、宗教の機能と発達への文化人類学的アプローチやニューギニアで急増する成人病に対する生理学的な説明などに広範な専門知識を持つドクター・ダイアモンドらしい非凡さが顕れています。 全体的な構造としては、1931年のニューギニア人「発見」当時と現在を対比させ、「昨日までの世界」と「今日」を比較していますが、これは前著『文明崩壊』において「過去の社会」、「現代の社会」として提示されていた(それぞれ前掲書第二部、第三部のタイトルです)見方をそのまま引き継いだものとなります。両方を取り上げた前作とは異なり、本作では「過去の社会」であるところの「昨日までの世界」を主に取り上げています。『銃・病原菌・鉄』においても「部族社会」として取り上げられていたあたり(前掲書下巻14章)ともリンクする内容であり、著者が度々取り上げてきたメインテーマの一つだということが分かります。 とはいえ、前作、前々作とくらべるとかなり取っつき易い内容となっており、本書から入ってもまったく問題はありません。シリーズ未読・既読を問わずお勧めできます。 一点、ご注意を。本書はハードカバー版を底本としているのですが、物理書籍版では文庫本が既に出ているため、電子版も遠からず文庫版ベースのものに切り替わるのではないかと思います。念のため。
0投稿日: 2017.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「銃・病原菌・鉄」では、人類の文明が発達したのかを説明した著者が文明化した社会と未開社会(この本では伝統的社会)を比較を論じたもの。 前著が文明社会が伝統社会に対して優越していることを前提で書かれていたのに対して、この本では文明社会の抱える問題に対する解決策のヒントが伝統的社会にあるのではないかという視点で書かれている。上巻は紛争、育児、老人について、述べられている。
0投稿日: 2017.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ201701/ グドールが観察したのは、子供たちにバナナを与える遊びである。その遊びでは、まず、子供たちの前に、一房のバナナがおかれる。その房には、ひとり一本のバナナがいきわたるように、十分な数のバナナがついている。この遊びでは、子供たちが一番大きなバナナを取り合うということはしない。それぞれの子供が自分のバナナをふたつに切って、一切れを自分で食べ、残りの一切れを別の子供に差出し、その子供から一切れをもらう、ということをするのである。そして、最初の半分の一切れを食べ終わると、残りの半分をまた二つに切って、その一切れを自分で食べ、残りの一切れを別の子供に差出し、その子供から一切れをもらう。子供たちはこのやりとりを五回繰り返すので、バナナの大きさは八分の一、十六分の一とだんだん小さくなっていき、最後の最後には、三十二分の一という小さな切れ端になる。そして、最後にそうなったとき、子供は三十二分の一切れを自分で食べ、残りの一切れを別の子供に差出し、その子供がその三十二分の一切れを受け取って食べるのである。つまり、この、儀式ごっこの遊びは全て子供の教育と訓練の一環だった。ニューギニアの子供たちは、この儀式ごっこの遊びから、自分が得することではなく、みなで分け合うことを学ぶのである。/
0投稿日: 2017.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログニューギニアなどの伝統的社会のあり方を類例に、現代社会の価値判断を問いかけていく。 「文明崩壊」「銃・病原菌・鉄」に比べると落ちるが、それなり以上に面白い。 上巻のラストは高齢者が大切にされない米国社会への愚痴で締め。ウザい。
0投稿日: 2015.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「銃・病原菌・鉄」で著名な生物学者が、研究のために定期的に訪れるニューギニアでの生活をもとに、伝統的社会と工業化社会との広範囲かつ詳細な比較を通して、現代社会が抱える課題と解決策を提示した大作。 著者は、我々が常識として受け容れている文化や生活様式が、実は人類の長い歴史からすれば「つい最近」作られたものであり、 人類が圧倒的に長い時間を過ごしてきた「昨日までの世界」における人間関係、紛争解決、リスク回避、宗教、子育て、高齢者対策の中に、「今日の世界」が物質的豊かさと引き換えに抱えた新たな社会問題を解決するためのヒントがあると主張する。 ともすれば産業化が遅れた「未開の地」として片付けられがちな伝統的社会に光を当てつつ、それらを手放しで賞賛するような単なる懐古主義に終わらない点は、著者の非常に幅広く学際的な研究領域によるところが大きいと思われる。やや冗長な表現も多いが、時空を超えて視野を広げることができるスケールの大きな作品。
0投稿日: 2015.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ銃・病原菌・鉄 の作者 ジァレド・ダイアモンド の新作 ニューギニアを調査し、文明の源流と人類の未来を考える 子育て、高齢者への対応 嬰児殺し、敬うか、遺棄するか、殺すか? 伝統的戦争と国家戦争
0投稿日: 2015.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり内容の濃い本だった。筆者の基本的なスタンスとして、とことんまで事実を調べて、それと比較が出来る別の事象までも集めてきて、細かすぎるまでに徹底的に論理的に検証を進めている、ということが伝わってきて、どの話も、とても説得力が有る。 扱っているトピックも、戦争や、子殺し、賠償、などどんな小さな村や社会にもあるような普遍的で、かつ生々しい、根源的な事柄を取り扱っていて、どれも人間の本性について考えさせられる興味深い内容ばかりだった。 いかに自分が、自分の育ってきた世界の価値観に染まりきっているかということがよくわかる。 世界には様々な価値観があって、その間に優劣はないし、どれが絶対的に正しい常識ということもない。 自分がもし、日本とは違う国や、今とは違う時代に生まれ育っていたら、まったく違う常識や判断基準を持ち、したがって、今の自分とはまるっきり違う人間になっていただろう。 たとえばもし自分が「子供への体罰は良くないことだ」という価値観を持っていて、それに絶対の自信を持っていたとしても、それは自分が熟考を末によってそういう価値観にたどりついたわけではなく、前提として、自分が育った環境の価値観をストレートに受け継いでいる。 【興味深かった話し】 ピマ族やナウル島人には飛び抜けて糖尿病の人が多い。 肥満になりやすい体というのは、エネルギーである脂肪を体に蓄積出来るということで、飢餓の状況での生存に有利なので、周期的な飢餓にさらされていたピマ族では、そういう体質の人が多く生き残った。皮肉なことに、それらの人が急速に文明化して、日々の食べ物に困らなくなった途端に、一気に糖尿病によって死ぬ人が激増してしまった。
0投稿日: 2015.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
さすがジャレド・ダイアモンド…と、唸らせる内容。 伝統文化と近代文化の対比による、現代社会の問題点への指摘と対策、決してユートピアではない伝統文化の在り方を、滑らかな筆致で読ませる。下巻を読むのが楽しみ。
0投稿日: 2015.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもと高齢者だけじっくり読み。今の生活に生かす気づきを得られたかっていうと微妙だけども、子育てについて、直感も大事にしよう、と感じた。情報に振り回されやすいけど、親子ともに、心穏やかに安らかに過ごしたいし、そのためには常識と思われることでも息苦しそうだったらとっぱらっていいんだな、と。本の感想なのか、って感じだが。
0投稿日: 2014.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味深かったのは、ニューギニアで交通事故を起こした場合の調停の部分。 使用人として事故を起こした場合は会社が責を負い、すべて対応するのは当たり前ですが、報復殺人を避けるために代理人を置いてわずか5日程度で調停が終了する。代理人は被害者・加害者とは別の部族のものが行い、ほぼ1回の調停で賠償額(Sorry Money)を決め、報復殺人が行われないと確信した時点で被害者・加害者ともに葬式が行われた。もし個人で起こしてしまった場合には、加害者の村・親類縁者が賠償することになる。 このような状態になっているのは、現代社会において事故など発生しても当事者同士がかかわることはまずないが、ニューギニアでは反対に一生関係を持ち続ける可能性があるからだ。 マオリ族の遠隔地戦争を支えたのが、従来栽培されてきたサツマイモではなくて、ヨーロッパからもたらされたジャガイモで、それは生産性が高かったから。 マオリ族の一部の部族がマスケット銃を得て、ほかの部族を滅ぼしていったが、ほかの部族にもマスケット中が行き渡った結果、武力紛争は終結した。現代もあまり変わらない。
0投稿日: 2014.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ高知大学OPAC⇒ http://opac.iic.kochi-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?isbn_issn=9784532168605
0投稿日: 2014.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者のフィールドであるニューギニアの暮らしはいわゆる「未開」の社会(伝統的社会)ではあるが、我々が暮らす現代社会は10万年近い人類史から見るとほんの一瞬に過ぎない。農耕が始まる1万1000年前までは狩猟採取の生活であったし、国家の成立もたかだか5400年前。必ずしも伝統的社会はよいことばかりではないが、と断りつつも全体に伝統的社会に対するノスタルジアを感じさせる内容。 ・西洋社会は個人主義であり、他人との競争が中心になっている。伝統的社会は個よりも集団としての振る舞いが重要になる。個人がおこした不祥事の後始末もコミュニティ全体でけりをつけるし、その際はこれまでのコミュニティ同士の貸し借りの精算も行なわれる。 ・食料などが十分にはない社会では高齢者の口減らしが行なわれることも多い。口伝に頼らなくとも知識が伝えられるようになった現代社会でも「老人の知恵」はさほど必要とされてはいないが孫を育てる手伝いなどをする。 ・子育てなどは親以外の人々(アロペアレント)が介入し、子育ての責任は社会全般で共有される。 体罰はしない社会とする社会とがある。一般的に、狩猟民族は子供に対する体罰を行わないが、牧畜民族などでは行なわれる。これは家畜のように希少な共有在を持つ社会では子供の間違った行動によって大きな損失を招く可能性があるからなのだろう。 授乳期は長く、両親と行動を共にすることも多く、アロペアレントによって多くの社会モデルを目にし、スキンシップも多い。こうしたことがよりよい人間に育つ原因である、とややノスタルジックな見方がされる 復讐心や戦争は人類のDNAに刻み込まれているのだろう
0投稿日: 2014.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログジャレド・ダイアモンド「昨日までの世界(原題:The World until Yesterday~What can we learn from Traditional Societies?)」の上巻を、やっと、本当にやっと読み終わる。 この人の本は、「銃・病原菌・鉄」、「文明崩壊-滅亡と存続の命運を分けるもの」に続く三回目、それぞれ上下巻二冊で、どれも、もぉぉ~本当に分厚くて長い。小さい活字で頁にびっしりというのが定番だ。なぜこんなに長いのか? それは彼が実際に見聞きした事実を隠さずに克明に書こうとしているからだ、ということになるだろう。今回はインドネシアのニューギニア島でのフィールドワークで見聞し体験したことをベースとしたものだが、伝統的社会(要するに西洋文明に染まっていない現地人の社会)にどっぷりと浸かって調査するといういつものパターン。よくぞここまでするものだと感心させられるのだが、そんな中での具体的な見聞記だから、それは実に興味深く面白くないわけがない。ボリュームにうんざりしながらもつい読み進むというわけだ。 現地人の生活ぶりを様々な視点から分析してゆく中で、やはり切実なのが「高齢者への対応」。伝統的社会では、高齢者はどのような扱いを受けるのか。かつて日本でも姨捨山の例があったようだが、ニューギニア高地人でも事情は同じ、いやむしろ遥かに厳しいと云えるのかも知れない。要はただお荷物になってしまった老人はもはや生きる道がない。一方で、貴重な知識や技能をもつ、役に立つ老人のみが尊重されるという事実。ギリギリの食料事情の中では当然のことなのかも知れない。生きることを許されなくなった老人には、部族によって異なるものの、①完全に無視され食事は与えられず放置される、②移動の途中で置き去りにされる、③自殺を求められる、そして④我が子によって殺される(殺し方も衝撃的なものが多い)、というパターンに分かれるよう。それにしても現代の我々から見ると想像を絶する酷い扱いとしか云いようがない。しかし食物が十分ではない極限に近い状態で生活している人間にとっては、生き延びるためには止むを得ないことでもある。 文明社会に生きる我々は、今、世界に食料が絶対的に不足しているとは云えない(偏りはあるが)中で、何も役に立たずともこのような酷い扱いを受けることはありえない。社会保障制度の恩恵でもってそれなりには生きてゆけるわけだが、果たしてこれが永続できるのかという疑問。どういう形にせよ老人がどのように社会に貢献すべきか、ということがこれからの大きな課題になるのは必至だろうし、そしてまた究極の問題にはなるのだが、最近話題になりつつある安楽死というテーマも避けては通れないのに違いない。我が身の処しかたも含めて大きな課題というべきだろう。実に厳しいことだが。
0投稿日: 2014.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ今回も膨大なページ数。 「内容紹介からの引用」 600 万年におよぶ人類の進化の歴史のなかで、国家が成立し、 文字が出現したのはわずか5400 年前のことであり、 狩猟採集社会が農耕社会に移行したのもわずか1 万 1000 年前のことである。 長大な人類史から考えればこの時間はほんの一瞬にすぎない。 では、それ以前の社会、つまり「昨日までの世界」の人類は何をしてきたのだろうか? 領土問題、戦争、子育て、高齢者介護、宗教、多言語教育 ……人類が数万年にわたり実践してきた問題解決法とは何か?
0投稿日: 2014.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代国家社会と伝統的社会を人間関係、戦争、子育て、高齢者といった現代社会がまさに抱える誰もが直面する問題を切り口に比較した本でした。この視点が面白かったです。人類学のような民族学のような、それでいて社会学のような。でも専門知識を必要としない分かりやすい内容です。 「昨日までの世界」は著者のニューギニアでの経験から始まります。1930年代にはまだ伝統的な生活を営んでいたニューギニア人が数多くいました。しかしこの数十年間でもう現代人のような生活を手に入れます。人間が数万年かけ現代的な生活様式に変化してきたことをたった数十年で。それは長い地球の歴史からみれば、伝統的社会であった時代の方が現代化して以降の時間よりはるかに長い時間を人類が過ごしてきたという歴史を、数十年間に早送りして見ているような感覚であると表現しています。しかしその昨日までの世界は新しい世界に置き換わったわけでもなんでもなく、いまも現代人の中に受け継がれているし、そこから学ぶべきこともあるとして伝統的社会の様々な生活を分析し、現代の問題の解決になる糸口を見つけようと試みています。 なぜ国家が誕生したのか。戦争がどのようにして始まりどのようにして終わるのか。子どもに対する体罰のあり方、高齢者に対する扱い、などの考察は非常に斬新な視点で、しかも身近な問題で参考にできそうな内容です。
0投稿日: 2014.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代社会の1つ前の世界として、独立した生活様式を維持していたニューギニア高地人との比較を通して、戦争・宗教・社会的つながりについて考察した本
0投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ上下巻まとめて。 主にニューギニアにみる、現代に残る「昨日までの世界」と、西欧的な現代の社会をどうすり合わせようか、ということか。 昨日までの世界にある危険と、現代の社会にある危険はさっぱり一致しない。だが昨日までの世界に見られる建設的なパラノイアは、人が人たるためのものであったのではないか、と強く思う。 短い時間で一気に昨日までの世界から現代の社会に放り出されると、人は大変な変貌を遂げてしまう。 上巻の印象は、濃密な関係のある世界と、これっきり会うことがないであろう人々の利害でできた世界の対比。下巻は宗教や言語、食事などに期待された役割とその変貌。他にも多くのトピックがあるのだが、似た話の繰り返し、という気もしなくもない。 やはり隣人とは争うものなのだなあ、などと、きっとテーマとは異なる印象を強くした。
0投稿日: 2013.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在田舎に引越して半年。噂が重要なコミュニケーションツールで、性的に寛容、というあたりがこの町とニューギニアを結びつける…
0投稿日: 2013.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界的ベストセラーを生み出し続ける著者の最近作です。『文明崩壊』では,環境保護の必要性を説得的に描き出しましたが,それでは豊かな環境に生きる先住民の暮らし方や思考法は,現代文明社会で暮らす人々に意味があるのか?まったく新しい観点から論じられた文明論です。私は多くのことを本書から学びました。皆さんは? *推薦者 (国教)S.T. *所蔵情報 http://opac.lib.utsunomiya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=BB00330989&initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
0投稿日: 2013.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝統的社会と現代社会の比較。 思考の流れ、仮説が多く、冒頭か章末に結論、まとめを書いて欲しい。 ニューギニア伝統的社会の事情には相当お詳しいが、近代日本の事情には疎いようだ。
0投稿日: 2013.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ジャレド・ダイアモンド執筆時、75歳 現代へのまなざし 【ニューギニア人】p19 2006年の人々と1931年の人々の間にこれほどの違いがあった理由は、世界の大半の人々が数千年かけて辿った変化の過程を、ニューギニア高地人たちが直近の75年で駆け抜けたためだといえる。 【国家の誕生】p29 紀元前9000年頃ようやく始まった食料生産以前には国家は存在し得ず、その後、食料生産が数千年にわたって続けられて国家政府を必要とするほど稠密で膨大な人口が形成されるまで、国家は存在しなかった。初めて国家が成立したのは紀元前3400年前後の肥沃三日月地帯で、それに続いて中国、メキシコ、アンデス、マダガスカルで国家が成立し、続く1000年の間にそのほかの地域にも広がり、ついに今日では地球全体で描かれた地図を広げると、南極大陸以外の土地は全て国家に分割されるという状況にまでなった。 【エルマン・サービスの4つのカテゴリー】p31 人口規模の拡大、政治の中央集権化、社会成層の進度によって分類。 ①小規模血縁集団(バンド) ②部族社会(トライブ) ③首長制社会(チーフダム) 「再分配」 ④国家(ステート) List of wars and anthropogenic disasters by death toll http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_and_anthropogenic_disasters_by_death_toll 【「ファースト・コンタクト」直近の事例】p97 1938年6月23日、ニューギニア高地人の発見。 NYアメリカ自然史博物館とオランダ植民地政府との共同探検隊。 バリエム渓谷。 Cf. ボブ・コノリー、ロビン・アンダーソン共著『First Contact』 <メモ> ウルルン滞在記の日本逆訪問 Cf. 「無限なようでいて、無限でない想像力について」 アメリカにおける「自警主義(ヴィジランティズム)」:頼れるものは法より自分が持っている銃という考え方。 Cf. エリー・ネスラー事件 「修復的司法」:犯罪を、法律に対する違法行為として捉えるだけではなく、個人や社会全体に被害をもたらす行為として捉える。p193 【戦争の定義】p228 「戦争とは、敵対する異なる政治集団にそれぞれ属するグループの間で繰り返される暴力行為のうち、当該集団全体の一般意志として容認、発動される暴力行為である」 ハイゼンベルクの「不確定性原理」の人類学の野外観測調査の文脈への応用。p232 個人間の自然発生的な争いが軍事的および組織的な戦争へとエスカレートした事例として、1969年6月から7月にかけてエルサルバドルとホンジュラスとの間で行われた「サッカー戦争」である。p240 http://en.wikipedia.org/wiki/Football_War <メモ>ホッブズがいう「自然状態」の中で、つい最近まで生きていた人々。 【体罰をする社会、しない社会】p330 ドイツ帝国の宰相ビスマルクは、同じ一家でも体罰を受けた世代の次には、体罰を受けたことのない世代が現れるというように、被大別経験の有無が世代ごとに入れ替わるといっている。 サミュエル・バトラー「鞭を惜しめば子どもは駄目になる」 lifehacker:人類はこのまま進化したらどうなるか? 10パターンの大胆予想 http://www.lifehacker.jp/2012/12/121230kotaku_evolution_of_humanity.html <メモ>小規模部族社会において、高齢者は現代のGoogleに代わる生き字引なのである。p374
0投稿日: 2013.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ西洋社会との接触が限定的な工業化されていない小集団社会は、人類600万年の歴史の中で、そのほとんどを過ごしてきた社会である。 改めて、短期間での変化の大きさに気づく。前著作の存在意義がわかる。
0投稿日: 2013.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろい! 部族間で争っていた時代には敵を殺すことは称賛に値していたんだ。なんで殺してはいけないかといえば、めぐって自分も殺されたらいやだから。殺してはいけない。命を長らえることはよいこと。食糧の確保、危険の回避、医療の進歩。人類は命を長らえるすべを手に入れてきた。ちっぽけなようでやっぱり凄いな。そうして地球上にひしめき合っている命。今のテーマは欲望をどのようにコントロールするか。人間が頭でっかちになると結局自分を滅ぼしてしまう。70億の人口は多いようにも思うけど、実際のところ母なる地球にとってはどうなのだろう。自分と、隣の人と、母なる地球を大事にしたくなる。
0投稿日: 2013.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1.ジャレド・ダイアモンド『昨日までの世界 文明の源流と人類の未来』日本経済新聞出版、読了。『銃・病原菌・鉄』の著者による新著。「今日の世界」とはヨーロッパ化された世界。前著でその経緯を辿った。本書では工業化以前の「昨日までの世界」と対比する中で、文明の危機への処方箋を提供する。 2.J・ダイアモンド『昨日までの世界』日本経済新聞出版。「今日の世界」の根幹は国家の成立だ。しかし600万年に及ぶ人類の歴史の中で、国家の成立は5400年ほど前に過ぎないし、ここ百年で「今日の世界」となった事例も数多くある。歴史的にも人類は「昨日までの世界」で長時間過ごしてきた。 3.J・ダイアモンド『昨日までの世界』日本経済新聞出版。豊富なフィールドワークと人類学的調査から著者は、子育てや介護といった現代社会の岐路となる問題のヒントを「昨日までの世界」に求めるが、その論証は説得力に富んでいる。しかし、著者は同時に「過去への憧憬」も手厳しく否定する。 4.J・ダイアモンド『昨日までの世界』日本経済新聞出版。ヨーロッパ文明のおごりも否定する。成功は文化的に優れていたからではない。安易なイデオロギー批判とロマン主義趣味を柔軟に退け、叡智を学び未来へ開くこと。著者の文明論の集大成の本書は柔軟な思考と公平さの指標となるだろう。 5.J・ダイアモンド『昨日までの世界』日本経済新聞出版。なお9章は「デンキウナギが教える宗教の発展」(下巻所収)。文化人類学的宗教の役割変遷論のまとめ。7つの項目で検証した図表があるので紹介しておきます。 https://twitter.com/ujikenorio/status/340477492215291906/photo/1
0投稿日: 2013.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝統的な社会(西欧的の反対)と、我々の社会(西欧的)を、その良いところ悪いところを比較しています。伝統的な社会も、我々が通ってきた世界で、タイトル通り「昨日までの世界」。現代の我々が、何を得て、何を失ったのか、冷静に見ることができます。 上巻は、自分以外の他人への対応、戦争、子育て、高齢者への対応について。 今までの著作よりも、冷静な視点から書かれているのを感じました。
1投稿日: 2013.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ『文明崩壊』、『銃・病原菌・鉄』の著者ということで期待したが・・・これはあまりお勧めではありませんね。 下巻を読んでいないので、評価が変わるかもしれませんが・・・
0投稿日: 2013.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻を読んだだけでの感想は、文明崩壊や、銃・病原菌・鉄に比べると駄作では?というもの。退屈なお説教話という感じ。 下巻は未購入だが、どうしようか?と迷う。
0投稿日: 2013.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログパプアニューギニアでの伝統社会を主とはしているが、まだ首長制の名残が残っているアフリカやアジアの国々はもちろん、かつての日本における社会の成り立ちを考える意味でも面白かった。特に自然が豊かで狩猟採集から始まった社会では、同じような成り立ちから現代に至っているのではないか。伝統社会やコミュニティがまだしっかり残っている社会に急激な貨幣経済や資本主義が流入している中で、今後の地域や精神社会にどのような影響を来すのか、非常に興味深いところである。
0投稿日: 2013.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログUCLA医学部生理学教授を経て、主に生物学畑を修めるも、その後鳥類学、人類生態学へと研究領域が多岐に渡った著者による一冊。 タイトルの通り昨日までの世界すなわち、著者が主なフィールドとして再三渡っているニューギニアの文化をはじめ、オーストラリア周辺からはクナイ族、ヨルング族、ユーラシア大陸からはアイヌ民族、キルギス族、アフリカ大陸からはクン族、ピグミー族、北アメリカからチュマシュ族、カルーサ族、南アメリカ大陸からはヤマノミ族、シリオノ族などを「伝統的社会」として主にアメリカ文明との違いについて展開されている。 特に、印象深かったのが、ニューギニアの紛争解決と、所謂アメリカ等の国家が提供する民事司法の差異についてだった。 子供を轢き殺してしまったという痛ましい事件において、ニューギニアでは被害者家族の葬儀に加害者が参加し、葬儀に食物を提供し、弔辞を述べる。こうした儀式が目指すところは「許す」というプロセスを社会的に支援しているというところだとして紹介されている。一方、民事司法の目指すところは、私的な暴力をやめさせる国家の権威とされている。 こうした紛争解決プロセスの他に高齢者社会との付き合い方、組織知の形勢プロセス等のテーマが展開されている。 どちらがいい悪いではないのだろうが「昨日までの世界」には、今日我々がぶかっているテーマに対する解答例が存分に詰まっている、と感じさせる一冊。
0投稿日: 2013.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ文明社会の今日に至るまでの流れを、伝統的社会の生活・経済・法・諍いなどの例を多く挙げ、広く人類としての未来を計るという壮大な一冊。 「銃・病原菌・鉄」の時に感じた震えるような衝撃は味わえなかった。 口絵もまとまってしまっていたので、見にくいし。○○族の顔といった画一的な案内では膨れ上がる知的好奇心は満たされない。 手元に 下 は無いけれど、内容によっては斜め読みになってしまうかも。 星四つをつけたのは第3部の「子どもと高齢者」が興味深い内容でぐぃと引きつけられたから。逆ピラミッドの年齢構造の今、考えなければならない内容だ。
0投稿日: 2013.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ニューギニアの空港で、チェックインを待つ著者の視線から、長い人類史への旅が始まります。ほんの数十年前までそこに存在していた〜現在は失われつつある〜「伝統的社会」を通じて、文明がどのように始まったのか、人間の社会はどのように進化してきたのかを広く、深く考察するのは「銃・病原菌・鉄」で知られるジャレド・ダイアモンド。もともとは鳥類の研究のためにニューギニアの奥地に通っていたそうです。そこにあった先住民たちの風俗習慣は、我々の住む世界のそれとは全く違うものでした。 本書では大きく「空間の概念」「戦争」「子供と高齢者」「危険に対する対応」「宗教、言語、健康」という章立てとなっていますが、もっとも重要なのは「戦争」についての考察でしょうか。 数十人から数千人規模の小さな集団の間での関係は、国家という概念が出来る以前の文明の姿を我々に教えてくれます。敵と味方という概念が生まれ、あるいは交易が始まり、そして戦争が起こります。少なくともニューギニアにおいては小規模な戦争は日常的に起きていたようで、死因の大きなパーセンテージを戦争が占めていました。「野蛮な文明人と平和を愛する原住民」というケースはここには当てはまらなかったようです。隣接する部族の間では常に戦闘と報復が繰り返され、戦士だけでなく女性や子供もその対象になっていました。その一方でより遠方の相手とは平和的に交易が行われたりもしています。これはどういうことなのでしょうか。戦争の原因は様々で、食料や水、あるいは生活空間そのものといった「資源」の奪い合いなどが考えられます。しかし最も多いのは「報復」だといいます。個人間の揉め事、女性や奴隷の収奪、家畜の盗難、偶発的な殺人などに対する報復です。当然隣り合って接触する頻度が高い地点でそれは起こりがちです。そのあたりは現代の国家間の関係でもあまり変わっていません。著者は「パールハーバーを忘れる」という項を立てて、人間が復讐心をコントロールすることで戦争を防ぐことが必要だと説きます。ここに通底しているのは「被害者意識」なのでしょう。人間は自分が被害者である、虐げられている、と思うときに最も攻撃的になるし、残酷になれるという一面があるのです。 伝統的社会から、文明を発達させてきたはずの我々ですが、世界中で続く戦争や暴力の連鎖を観るに付け、まだまだ成長していないのではないかと思うのです。果たして人類の未来は明るいものに見えるのでしょうか?どこかに希望を見つけたいと願います。
1投稿日: 2013.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みながら脳裏に浮かんでいたのは、時代も文脈も違えど悲しき熱帯だった 数千年の人類史に匹敵する数十年のパプアニューギニアの数十年に立ち会った著者の稀有で数奇な体験の書
0投稿日: 2013.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ『銃・病原菌・鉄』、『文明崩壊』のジャレット・ダイヤモンドの新作。 著者が文化人類学者として実地でのフィールドワークをしていたことを初めて知った。特に鳥類学者でもあったとは。本書は、クロード・レヴィ・ストロースにとっての『悲しき南回帰線』と同じような位置付けなのだろうか。前二著とは趣がやや違い、特徴であった壮大な論理的な推定はやや影をひそめ、その代わりに著者の実体験のエピソードが出てくる。もちろん「昨日までの世界」についての文献を広く確認し、単なるエッセイではない。『銃・病原菌・鉄』の重要な結論 ― 文明の発展は地理的な条件がたまたまそのように恵まれていたから ― の元になる経験はここにあったのかと知ることができた。 タイトルにもなっている「昨日までの世界」とは、いわゆる伝統的社会 ― 人口が疎密で、数十人から数千人の小集団で構成される ー のことである。紀元前9000年ごろになって始まった食料生産以前には国家は成立しえなかった。初めて国家らしきものが成立したのは紀元前3400年前後で、それまで少なくとも人類は「昨日までの世界」を生きていた。どちらかといえばそちらの方が本来的なものである。WEIRD = Western, Educated, Industrial, Rich, Democraticな社会は人類の歴史の中では奇妙(weird)なものなのである。「昨日までの世界」のことを知ることで、現代の世界でも役に立つことが出てくるのではないのか、というのが著者も目的のひとつでもある。 社会は、その規模により、「小規模血縁集団(Band)」、「部族社会(Tribe)」、「首長制社会(Chiefdom)」、「国家(State)」に分けられる。この分類は学術的にも一般的らしい。この社会構造の中で、他人は、「友人」、「敵」、「見知らぬ他人」に分類されるが、この中で見知らぬ他人に対する態度が伝統的社会と現代社会の大きな違いだという。また、もちろん食料調達と分業にも違いが生じる。"Size does matter"なのだ。これにより、紛争解決の方法、戦争、子供、高齢者、危険(リスク)、宗教、言語、健康、などが異なってくる。現代の司法制度と刑罰というものが特殊なものであることもわかる。本書では、それらの違い、「優劣」ではない、を丁寧に解説している。 --- 昨日までの世界が一世代も経たないうちに現代化され、ほぼ世界中からなくなっていこうとしている。このことは、近代化の時期が早かった地域は、その土地形状と生息生物にたまたま恵まれていただけである、という著者の『銃・病原菌・鉄』での主張につながっているように思う。また、現代化が非可逆的な過程であることも結果的に示されてもいる。 上巻は、紛争解決、戦争、子供、高齢者、まで。どれも現代社会でも重要な問題である。もちろん、昔はよかったなんてことにはならないので、安心を。
0投稿日: 2013.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ鉄病原体銃はクソだけど、これはすごく面白かった。 昨日までの世界 •平均寿命短い –そもそも平均寿命が短く、現代の定義での高齢者に達する人はほとんどいなかったし、当時の定義での高齢者になる人も少なかった。 •高齢者殺し –資源が限られ、頻繁な移動を伴う生活において、食べるだけの人間を養う余裕があるとは限らない。放置して死に追いやる、自殺の手伝いをする、積極的に殺す、など部族により差があるが、高齢者殺しは広く行われていた。 •高齢者尊重 –一方で高齢者を尊ぶ部族もある。食料に禁忌をもうけ、高齢者しか食べられないということにしたり、中には食べ物を噛み砕いてあげてから食べさせるような部族もある。
0投稿日: 2013.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝統的社会と近代国家社会という二つの軸に照らして育児、家族、教育、戦争などについて論じてる本。 戦争ってそもそもなんなのかとか、社会ごと子育ての差異とかすごく詳しく書いてあって非常に興味深い。 高齢者の扱いが近代→伝統へ回帰してく想定とかもかなり頷ける。 下巻も楽しみ。
0投稿日: 2013.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログダイアモンド先生はおもしろいなあ。 しかし「なのである」「食する」とかが多くてなんか違和感。 倉骨先生ってこんな訳文つくる人だっけか。 短期間で翻訳するために下請け変えたのかな。
0投稿日: 2013.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ西洋型の現代社会と、国家成立前の「昨日までの」社会を比較して、その得失を考察する。 『銃・病原菌・鉄』のような目を瞠るほどの驚きはなかったが、それでも著者のニューギニアでの実体験も含めた豊富な事例で、一つ一つ確かめていくように論を進めていくのが面白い。 とくに多言語文化の利点と失われつつある言語の保存を訴えた第10章。この部分だけやけに熱がこもっているように感じたのだが。
0投稿日: 2013.03.16
