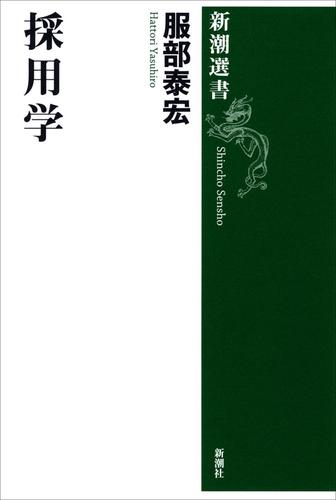
総合評価
(30件)| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ採用というものの奥深さを感じだ。実務とアカデミアを繋ぐ本でありどの立場の人が読んでも学びが大きいと感じだ。服部先生凄い。
0投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ採用に携わる人なら一度目を通すべき一冊。採用とは何たるかを基礎から学べる。2025年の今となってはもはや過去の話も多いが参考になるはず。多くはそうそう!って内容かな。 採用を長年やってきた私としてはまさに感覚的にやっていることも多く、経験者なりのバイアスがかかっているのは事実で、耳の痛いところとあったので、それを意識しながらこれからも仕事しようと思った。
2投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ・母集団 エントリー求職者数? ・優秀者の言語化 ・アトラクト、選抜基準、選抜手法、最終選択 ・変わりにくいスキル 知能、創造性、概念的能力、鼓舞、エネルギー、情熱、野心、粘り強さ ・可変的だが変わりにくいスキル 判断能力、戦略、ストレスマネジメント、適応力、傾聴、チーム力
0投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ旧日本型の新卒・中途採用の学術的説明書. . ## 面白かったところ. . * 人材補充以外の、企業の採用に対する目的がわかる. * 採用活動を通じた企業からの暗黙的なメッセージを知れること. . ## 微妙だったところ. . * どちらかというと、旧日本型で新卒一括採用のイメージは湧くが、ジョブ型の採用に関してはイメージしづらい. . * ベンチャーの採用の話も出てくるが、厳密に言うと `メガベンチャー` の採用なので、シード期真っ只中のベンチャーの採用に関する話ではない. . * `ブランド` という話が出てくるが、 `採用` というよりも採用活動を通じた `広告` やイメージ戦略の話のような気がして論点がズレている印象.
0投稿日: 2023.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ・自社における「優秀さ」をつくりだす ・採用力=採用リソース × 採用デザイン力 など、これから採用をスタート、改善する組織や人にとって、前提として押さえておきたい枠組みを分かりやすく提示してくれています。
0投稿日: 2023.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログよかった!もっとはやくよむべきだった。色々目からウロコ。母集団は多ければ多いほどいいのか?など。課内で展開したい。
0投稿日: 2021.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在利用されている様々な採用手段の有効性を、主にアメリカのデータに基づいて論じている。日本で、それが当てはまるのかどうかは不明。 企業側が積極的にネガティブ情報を流すことによって、ミスマッチによる早期退職を減らすことができる。
0投稿日: 2019.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ学術的な知見に基づく、採用のあるべき論。 求職者として、人事の懐のどこが痛いのか知るために手に取った本。 ---- ・新しいメンバーを入れることで「同質化圧力」「慣れ」「硬直化」「閉塞感」を打ち破りたいが、実際には、面接を通じて企業の体質・面接者の気質に似通った人が選ばれる。 ・口づてのように非公式のルートから得た情報に基づいて採用された人材は、企業に長期間とどまる可能性が高い。 ・開始4分くらいの間に、採用/不採用を決めていることが多い。外見の良さ、コミュニケーションの上手さは有利 ・どんなに優れた選抜ツールを使ったとしても、将来の業績の半分も説明できない。 ・日本の人事は、誤って好ましくない人を採用するリスクを最も恐れる。減点方式。 ・「事実に基づく経営」デニス・ルソー等 =経営の現場に、入手しうる最高の科学的知識を用いる =自社の問題について考えるためのデータを集める =知っていることに謙虚になる --- ・高い成果を出す優秀な人材は他社への転職機会も恵まれているし、本人にその自覚がある ・内定前後の認知的不協和 1)「自分は極めて大きな決断をしようとしている」 2)「この決断が正しいのか確信が持てない」
0投稿日: 2019.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログロジックとエビデンスに基づいた科学的な観点からの「採用学」を確立する宣言の書。書名は『採用学宣言』が妥当かな。 志はよいけれど、実践的な知識という面では物足りない。あらゆる企業に当てはまる「普遍解」がないとしても、研究成果として明らかになった原則とかもあまり書かれていない。 それは必ずしも筆者の責任ではなく、産業心理学の現状なのかもしれないが。
0投稿日: 2018.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016年5月刊。2017年度採用で、スケジュールが再度変更になったことには触れていないが、2016年度の大幅な変更は考察されている。 最適な採用の「解」は、結局その企業が自分自身で導くしかない、と書かれている。しかし、このような学問が成立し、本が多数出版されていること自体、皆が「解」を求めていることの表れか。
0投稿日: 2018.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書では、経営学から分化させ体系化しようとしている「採用学」を提起している。社会や企業からのニーズから生まれたこのディシプリンは、おそらく今後多くの研究が生産されていくものと感じた。膨大な研究をレビューした著者はまさにこの学の先がけなのだろう。留意したい箇所を以下に引用した。また蓄積された各知見を総動員して、各組織自身が問いと解を導き出すことが肝要という旨も、再三述べられている。 採用学は、採用という実務を、改めて募集、選抜、定着のプロセスに分けて求職者と企業側に分ける検討することが、基本的な出発点となる。そして曖昧な期待と魅力的な情報の交錯が現実の採用を複雑なものとしている。さらに採用後の「育成」もかかわってくるので、なかなか最適・最善な解は見つけにくい。 私たちのコミュニティでも話題になる研究と実践の関連について、著者は次のように述べている。「研究者としては理論の構築や検証だけでなく、良質のエビデンスの提供とその蓄積を、ビジネスパーソンとしてはそうしたエビデンス、そして自らが有するデータの分析に基づく経営を行う必要がある。」(p.226)一つの理想形として覚えておきたい。また、「経験豊富で、優れた勘を持ったビジネスパーソンと出会うことで、科学的なエビデンスの方も相対化され、洗練される可能性が十運にある。事実に基づく経営とは、科学者が提示するエビデンスと、ビジネスパーソンが持つ経験・勘と平等な立場に置くことを主張しているのだ。」とも主張されており、重要な指摘といえる。 最後に些末なことであるが一つふれておく。113頁に「ピアノの『ド』の鍵盤と『ラ』の鍵盤を同時にたたくと不協和音が鳴る」という記述がある。楽典では、普通に3度ないし6度の協和音程と習うはずであり、グレゴリア聖歌の時代ならまだしも、現代においてドとラを不協和音といえるかは疑問である。
1投稿日: 2018.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【214冊目】電子書籍にて購入。経営学修士で横浜国立大学准教授の服部泰宏氏の著作。日本で「採用学」を掲げて研究する学者がなかなかいないことから注目。既婚だけど、スポーツマンでイケメンだから、今後マスメディアの露出も増えそう。 まず冒頭の映画「マネーボール」の逸話が興味深い。確かに企業は採用において「優秀な人材」が欲しいという。しかし、では「優秀」とはどういうことなのか。それをそもそも採用する側がきちんと認識していないんじゃないかという反省を促す逸話である。 そして、日本における採用の歴史、採用という営みに対する科学的視座の提示、日本における最新の新卒採用の動向を概観するという構成。さすがに経営学なだけあって、様々な新規概念や定式が示されていて勉強になる。幾つかの例を下に記す。 ◯ 採用基準の(意図しない)拡張 ◯ 大規模候補者群仮説 ◯ 優秀さを「変わりやすい能力」と「変わりにくい能力」に分ける ◯ 評価する、ということには、「何かを計る」ことと「価値を創り出す」ことという2つの側面がある ◯ 採用力=採用のリソース×採用デザイン力 <採用のリソース…有形/無形> (有形…動員できるスタッフ、予算、企業の立地など) (無形…採用担当者の人脈/採用ブランド) ・採用担当者の人脈…人材にリーチするための人脈/社内の支援集団とのつながり ・採用ブランド…企業・業界のブランド/採用自体のブランド 筆者は「採用自体のブランド」が今後の日本の採用を考える上で極めて重要と述べている。確かに採用そのもののみを考えれば済む採用学者にとってはこれが重要かもしれないが、採用実務者及びビジネスパーソンからするとこれはさほど重要とは思えない。なぜなら、企業にとっては、採用は経営手段の一つに過ぎず、採用自体のブランドに惹かれて求職してくるような応募者は、就職後に期待と現実のミスマッチに陥りやすいと思えるからだ。
0投稿日: 2017.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ2017/8読了。 既知の情報が多かった&新卒メインの本だったので、ふーんという感じ。 新卒採用が日本独自のものであるが故だろうが、中途採用も学問として組み立ててほしい。
0投稿日: 2017.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ属人的かつ主観的になりがちな採用を科学的手法を用いて分析した本。 実体験と合わせて考えてみると、やはり多くの企業では自社にとっての「優秀な人材」の具体化ができていないのではないかと思う。そのため、求める人材の欄には「コミュニケーション力」などのいわゆるビッグワードが並び、結局曖昧で属人的な採用となることが多いだろう。 こうした現状を考えれば、本書のタイトルである「採用学」は、企業の採用を大きく変えていく可能性のある学問だと感じた。
0投稿日: 2017.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ採用のコンピテンシーについて、感覚値ではなく形式知の科学的観点から書かれている。 新卒一括採用の課題を忠実に研究している。 疑問としては、統一した指標が果たして採用に必要かどうかであり、企業がいまもなお、ひとを人とはさて見ず、ただのツールとしている現れともとれる。かならず、少しのズレや感覚の違いはあるが、その差を教育や経験によって補い合うことも採用なのではないか? 人は得意不得意があり、男女で脳の構造が異なる。 採用時にこの2点も加味した内容が含まれることを切に願う。
0投稿日: 2017.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
若手の研究者が採用を科学的に調査した本。 人事担当経験の長い人が自分の勘と経験だけで書いたものとは違い、統計や他の文献なども参照していることから非常に説得力がある。 以下ためになったところ。 良い採用とは「求職者をランダムに採用したときに比べて、より高い業績を収められる、または企業へとより強くコミットし、中長期的に企業にとどまるか人材を獲得できること」 コミュニケーション能力に代表されるようなあいまいで多義的な「能力」の測定や判定は難しい 日本の採用の問題点はリソースに頼った人海戦術と能力や期待があいまいなこと マイナスの情報を与えることでかえって無駄な募集者を減らし、正常な期待値を保たせることができる 採用チャネルごとのメリット・デメリットを考えること 優秀さの定義と明確にすることと可変的なものかどうかを考慮すること(何を見ないかが重要) 選抜ツールに必要なことは妥当性(測りたいものを測れているか)、信頼性(再現性)、納得感 採用力=採用リソース(資金など有形なもの&ブランド力などの無形なもの)×採用デザイン力(採用を設計する力) 勘と経験だけの採用はあやうい。科学の知見を有効に活用する必要がある 正しい採用自体の回答は企業自体が試行錯誤し取り組んでいくしかない 以前人材紹介会社で勤務していて採用に関して非常に疑問に思っていたので、読後非常にすっきりした。 人間が人間をフィーリングでみることは不可能だということが再認識できた。
0投稿日: 2017.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2017年6冊目。 人事担当者の勘に依存せず、科学的に採用すべきという主張。非常にユニークな採用が挙げられているが、体感できる採用方法か多くなってきているような感じる。同じ場を共有することがお互いの理解に有効だという考え方に基づいていると思うが、そこは共感。面接を受ける側が場所や時間を全て設定する代わりに全員面接できるというものがある…これはやってみたい!!
0投稿日: 2017.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くのデータと先行研究をベースに、採用を具体的にどう考えたら良いか、のヒントが散りばめられている。文章が分かりやすく、また、興味深いエピソードやコラムがあり、読み物としても素晴らしい。今の当社にとって必要な考え方や情報が、集められていた。ありがたい。
0投稿日: 2017.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ丁寧にこれまでがまとまっていて良かった。 採用に正解は無いが、やはりどんな人物を採りたいのかという作戦を練るという当たり前が肝要。
0投稿日: 2016.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ新規採用にかかる考え方を変えさせてくれる。採用におけるいわゆる「母集団」を広げて、絞り込むことに警鐘を鳴らすことは非常に意義深い。
0投稿日: 2016.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ採用の今がとてもわかりやすい。 まさに、今困っていることがありのまま綴られている。 様々な企業内で採用のカタチがあるが、採用活動とは他企業の真似ができるものではないと痛感した。
0投稿日: 2016.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ・主観や慣習、勘を排した視点に立てば最適な人材を確保でき、企業イメージのアップにもつながる。 ・コミュニケーション能力は重視するな、人は見た目じゃない。 ・減点方式で採れるのはそこそこの人。 ・面接の常識を疑い、採用と育成のつながりを重視することで新しい地平が見えてくる。
0投稿日: 2016.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織と人はどのように関わるべきなのか、その入口から携わる事に。エライコッチャ!と様々な知見に触れる中で出会った一冊。企業はもっとこうした研究者に対するフォローを増やすべき。
0投稿日: 2016.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ採用の過程を科学的に分析し,それぞれの企業がより良い採用ができるようにするためのエビデンスの提示を試みる本と言える。 採用における期待の曖昧化と能力の曖昧化が入社後のミスマッチの原因となる。さらにフィーリングのマッチングも加わるという。 能力の曖昧化やフィーリングのマッチングに関しては,日本の職務を限定しない雇用と大きく関連すると思った。そうすると,面接等の選抜方法を改善するだけでは限界があり,能力の曖昧化やフィーリングのマッチングを回避するためには,職務を限定した雇用にしていくことが大事になってくるのだろうか。。。 あと,後半部分では,日本の企業の新しい採用方法の事例が紹介されている。その多くあげられていた事例が良い採用方法なのかどうなのかというのが実証されていないのではないか,と思った。今後の研究成果が期待されるところである。 日本の採用について色々と学べる本だと思う。
0投稿日: 2016.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログマジ就活ってクソゲーだよな。二度とやりたくねぇ。 と、リーマンショックをまともに食らった2011年卒が抜かしております。 日本の就職活動はなぜそんなにクソゲーなのか。 ライバル社は有能揃えているのに、どうして弊社はゆとりばかりなのか。 採用を学問する採用学を筆者は提唱する。 読んでみたけど面白くねーな。 結局、新卒一括採用が楽なんだよ。採る側も学生側も。という低みの見物。
0投稿日: 2016.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ160806 中央図書館 採用をマッチングの問題として捉えるのは、そのとおりだと思うが、内容としてはあまり大したことが書いてないように感じた。コラムだけが、なんとか面白く読める。
0投稿日: 2016.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の仕事柄、役に立ちそうだと思い、読んでみました。 うちの会社の採用試験には、まだまだ改良の余地があると思った一方で、うちの会社に合った形で、かなりまともな方法で採用を行っている、とも思いました。 ただ、この本にもあるように、採用が良ければO.K.ではなく、その後の教育も大切なので、今後も、採用・教育ついて、トータルで考えていきたいと思います。
0投稿日: 2016.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ尊敬する同業者に薦められ読んでみる。大変読みやすく、また、採用の基本的な考えから最新の潮流まできれいにまとめあげている本。仕事関連の本はほとんど読まない(変な思想に犯されたくないので)が、これは客観的な事実をしっかりと伝えよう、そして採用について世の中に考えてもらおうという作者の心意気も感じられて大変好感が持てるものだった。仕事場の夏の課題図書に認定したくなる。
1投稿日: 2016.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ待ちに待った、服部先生の著書、採用学です。共感するところ大です。採用は企業のマーケティング活動の一環なのです。だからこそ、科学的なアプローチが必須です。
1投稿日: 2016.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学的な採用に関わる研究の知見だけでなく、社会科学としての本質的な意義と、事実に基づいた科学的経営(EBM)の知見について豊富に記載されている。特にアメリカ経営学会における実践(現場)と研究のすれ違いの理由について「HOW」と「WHY」の相互の異なる視点が生み出しているという記載に、大学経営においても同じことが当て嵌まると感じた。本書は社会科学系学問を先行する学生にも読んでほしいと感じ、また大学経営に関わるところでは、大学職員で研究を志す、又は社会人院生として研究に触れた人たちにぜひ読んで欲しい願う。
1投稿日: 2016.06.09
