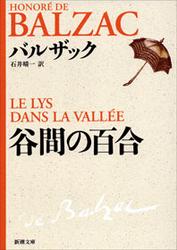
総合評価
(24件)| 8 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ475P バルザック良いんだけど段落の長さは異常 ゴリオ爺さん→谷間の百合でバルザックの魅力が分かった。まだヴィクトル・ユーゴーの良さは分からない。 #読書 失われた時を求めてとかバルザックの谷間の百合とかフランス文学の何の意味もない団長な情景描写みたいなのほんと好き。これこそフランスの一見余計なもの(お菓子とか、サーカスとか映画みたいな文化的なもの)に命かけてるお洒落さの象徴だと思う。 #読書 「洒落(しゃれ)」には「気の利いた」「粋な」という意味があり、そこに接頭語「お」をつけて丁寧にした言葉が「お洒落」です。江戸時代から使われていた言葉で、当初は服装に限らず「言動が洗練されてること」も含んでいました。 『谷間の百合』というタイトルは、「人目につかない静けさの中に咲く、清らかで高潔な存在」を象徴します。 これは作中で主人公フェリックスが恋する女性「アンリエット夫人」を指していると解釈できます。 •アンリエットは人妻でありながら、純潔を守り、精神的な愛に徹する女性です。 •彼女の存在は、世俗の愛欲から離れた高潔な愛、つまり「谷間にひっそりと咲く百合」にたとえられるのです。 私の中で、ザ・フランス文学といえば、これ この冗長で緩慢なストーリー展開…美しいけど、甘ったるい表現の連続…これを淡々と読み進めていくことこそ、純文学を愛してしまう人間の浪漫というか宿命ってやつだよね。 バルザック「谷間の百合」#読書 「あまりうちとけ過ぎる人間は尊敬を失いますし、気やすい人間はバカにされますし、むやみに熱意を見せる人間はいい食い物にされます。 」 バルザック「谷間の百合」 バルザック全集26巻をすべて読むのが今年前半期の読書の目標です。「谷間の百合」は二回読んだか。「幻滅」は近年読んで、まだ記憶に残っているので、いいか。「ゴリオ爺さん」はどうせならば新訳で読み返そう、とか計画をたてています。 バルザックの代表作「谷間の百合」の全文朗読というありがたい労作。18時間もあるが聴く価値のある物語。まぁ前半はだるくて退屈な面がかなり強いが後半の綺麗な関係が荒み汚れ人間の真実をさらけ出してくるシーンは心に永遠の傷痕が残ること必至。 バルザックの「谷間の百合」然り、今読んでいるサンドの「笛師のむれ」然り、昔のフランスの小説は心情描写に加えくどいぐらい情景描写が多いと思ったら、よく考えると写真の無い時代だったからだと気づく。 そう考えるとものすごく緻密な文章ではないかと感心に変わってくる。 バルザックはゴリオ爺さんよりも谷間の百合の方が爽快感があって好きでした。ただ、どうでもよさそうな描写が長いので飽きるのはわかります。 受け売りですが、短編がおすすめらしいですよ。光文社古典新訳文庫の『グランド・ブルテーシュ奇譚』や『ラブイユーズ』はわたしも読みたいと思っています。 バルザックの谷間の百合を読んでるが、流石に胸焼けするな。 20歳前後であれば、清らかな恋慕とままならないことへの憎悪に心を動かされもしただろうが。 病院でお昼ご飯屋で待っている間、昨日から読み始めたバルザックの谷間の百合読んでたんですが私は今までなんでこれを読んでいなかったんでしょうかね、てなってる大好きなねちねち感情&情景・光景描写系なんですけどいまんとこ好き好き大好き青年の春なんでこの季節にあってていいです。春にベルンハルトなんて読むもんじゃネェ セラフィタ も面白そうですね(メモメモ) 中学生の時、谷間の百合を読み始めて挫折しました バルザックって面白いですよね 中学生で谷間の百合は無理だった ゴリオじいさんくらいだったら、、 やっぱり読めなかったでしょうか? 「夕食は、私にとっては内心の歓びのうちに過ぎました。いま自分は彼女の家にいるのだと思うと、私は彼女の現実の冷淡さにも、伯爵の礼儀正しい態度の蔭に隠された無頓着さにも、思いをおよぼすことができませんでした。人生と同じく、恋愛にも恋愛だけに自足していられる思春期というものがあります。私は、情熱のひそかなざわめきに即応するへまな返事を幾度かやってしまいましたが、しかし誰一人として、彼女さえそれを見ぬくことができませんでした。もっとも、彼女は恋愛についてはなにも知らなかったのですが。そのほかの時間はまるで夢のようでした。この美しい夢がさめたとき、私は月光を浴びて、芳香にみちた暖かい夜のなかを、牧場や川岸や丘々を飾る白い幻のような夜景につつまれながら、アンドル川を渡っていました。そのとき、一匹の雨蛙が一定の間を置いて間断なく投げかけてくる哀愁にみちた澄んだ鳴声が、静寂のなかに響くたった一つの音色として、私の耳にはいってきました。その雨蛙の学術上の名称はなんというのか知りませんが、この厳粛な日以来、その声を聞きとめると、私の心にはかならず無限の歓喜がこみあげてくるのです。それからしばらくすると、ほかの場合と同じように、それまで自分の感覚を鈍磨しつづけてきた、例の大理石のような無感動の状態にぶつかっていることに、私は気がつきました。自分はいつまでもこうなのだろうか、と私は考えこみました。自分はどうにもならぬ宿命的な力に支配されているのだ、と考えました。そして過去のいまわしいできごとが、いましがた味わってきた純粋に自分一個の歓びと争いあうのでした。フラペールに帰りつく前に、クロシュグールドのほうをふりかえると、その下のところに、トゥーレーヌではトゥーと呼ばれている小さな艀が一艘、トネリコの木につながれて、川の流れにゆられているのが見えました。このトゥーはモルソーフ氏の所有になるもので、彼はそれを釣りに使うのです。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「「女というやつは、いつでも自分が正しいと思いたがるものなんですな!」私のほうを見ながら彼はそう言いました。 彼の言葉に目顔で賛意を示したり、あるいは反対をとなえたりするのを避けようとして、私はじっとジャックのようすを見ていましたが、彼はしきりにのどが痛いと苦しがり、とうとう夫人がむこうへ連れていきました。私たちのそばを離れる前に、夫のこんな言葉が彼女の耳にも達したはずです。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「「美しい夜ですこと!」「女性のように美しいですね、奥さま」「なんて静かなのかしら」「そうですね、ここにいたら、完全に不幸になるはずはありませんね」 この答えを聞くと、彼女はまた刺繍の仕事にもどりました。私はとうとう、彼女の心のなかに、みずからの場所を求めている愛情からわきおこる、真情のうごめきを聞きつけるようにまでなっていたのです。だが、金がなくなれば、こうした夜の時間ともおさらばです。私は母に手紙を書いて、金を送ってくれと頼みました。母は私を叱りつけ、一週間分の金もくれませんでした。では、いったい誰に頼めばよいのか? しかも、ことは私の生命にもかかわっているというのに! こうして、私は自分の最初の大きな幸福のさなかで、かつていたるところで悩みの種となったあの苦痛に、ふたたび出会うことになったのです。けれども、パリでも、中学校でも、私塾でも、私は思索的な禁欲によってそれをくぐりぬけたわけであり、私の不幸はいわば消極的なものでした。が、フラペールでは、それは積極的なものに一変したのです。そのとき、私ははじめて盗みの欲望を知りました、魂に深い痕跡を残し、それを押し殺さなければ自分自身への尊敬を失ってしまうような犯罪の夢想や、凶暴な憤激というものを知りました。母の吝嗇のために、私に無理強いされたあの痛々しい瞑想や不安のことを思いだすと、私の心には青年たちにたいする聖者のごとき寛大さ、自分は落ちこんだことがなくても、あたかもその深さを測ろうとでもするように深淵の縁まで達したことのある人々がそなえている、あの聖者のごとき寛大さがわいてくるのです。私の清廉潔白さは冷たい汗を糧として育ったので、人生の表面が左右に割れて、その河床の荒涼たる砂礫がさらけだされたこの時期にますます強められたわけですけれども、それにもかかわらず、人間の行なうおぞましい裁判が一人の男の首に剣を突きたてるたびに、私はひそかにこうつぶやいたものでした、「刑法というものは、不幸を経験したことのない人間たちによってつくられたのだな」と。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「でも、まず第一の問題として、わたくしの気にいる家庭教師がいったいどこでみつかるでしょうかしら? それにこれからさき、あの恐ろしいパリで、あらゆるものが魂にとっての罠となり、肉体にとっての危険となるあのパリで、いったいどんなお友だちに、あの子を保護していただけるでしょう? あなたの」彼女はしみじみした声でそう言いました。「あなたのお顔や目を拝見すれば、いまにきっと高い地位にお就きになるはずの方だということは、誰だって見ぬけますわ。どうか高々と飛躍なさって、わたくしどものいとしい子供の保護者になってやってくださいませ。どうか、パリへお出になってくださいませ。お父さまやお兄さまが援助してくださらないようでしたら、わたくしたちの家族の者が、とりわけ母などはそういうことにかけては達者ですから、かならずお力になれると存じます。どうぞ、わたくしども一家の勢力をご利用なさってください! そうすれば、どんな道を選ばれても、まちがいなくお力添えもご援助もできるはずですわ! ですから、その余っていらっしゃる力を、気高い大望のほうに注いでくださいませ」」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「彼女が前に言ったとおり、クロシュグールドの秘密に通じているのは私一人だけでした。この谷間の澄んだ空気や青い空が、気分のいらだちやつらい病苦をどれほど鎮めてくれるか、そしてクロシュグールドの住居が子供たちの健康にどんな影響をおよぼすか、それを経験によって確かめた上で、彼女は充分理由のある断わりかたをしたのですが、他人のことに侵入しがちな女性で、娘の不運な結婚を悲しむというよりむしろ屈辱に感じている公爵夫人は、しきりに反対を言いたてていました。アンリエットは、母親がジャックやマドレーヌのことなどほとんど気にかけてないのに気づきましたが、これはまたなんという恐ろしい発見でしょう! 娘がまだ若い頃に押しつけていた圧制を、相手が結婚してからも依然として加えつづけることに慣れているすべての母親と同じく、公爵夫人は、反駁をまるで認めぬ論法で押し通すのでした。彼女はあるときは自分の意見にたいする同意を無理強いするために、詭弁まじりの親身そうな態度を装うかと思うと、またあるときは甘言で獲得できぬものを畏敬で手にいれようとして、手きびしい冷酷な態度を装ったりするのです。やがて、その努力も無駄だと見てとると、今度は私がかねがね母親のなかに見ぬいていたのと同じ皮肉な気質を、あからさまにむきだしにするのでした。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「優しみがなく、冷淡で、打算的で、野心の強い婦人と、けっして涸れることのない穏やかですがすがしい善良さにあふれたその娘とのあいだに起こったこの争いのことを、はっきり思い描いていただくためには、ゆりの花、私はいつも心ひそかに彼女をゆりの花になぞらえていたのですが、ゆりの花が磨きたてられた鋼鉄の機械の歯車にこなごなにされるところでも、想像していただかねばなりますまい。この母親には、娘とつながりあうところなどまるでありませんでした。ですから、娘に王政復古の利益を利用することをはばみ、依然として孤独な生活をつづけることを余儀なくしている真の障害を、彼女は見ぬくことができませんでした。娘と私とのあいだに、なにか恋愛遊戯でもあるのだろうと彼女は思いこみました。彼女は疑念を表明するに当たって、はっきりとこの恋愛遊戯という言葉を使ったのですが、まさにこの一語のために、二人の女性のあいだには、それ以来どうにも埋めようのない深淵がひろがるようになってしまったのです。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「恋とは、恋でないものをことごとく嫌悪するものなのです。それから、公爵夫人は宮廷の豪華な生活にひたるべく出立していき、クロシュグールドではすべてがもとどおりの秩序を回復しました。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「そうです、もっと年をとると、私たち男性は女性のなかの女性らしさを愛するようになります。それに反して、最初に愛した女性については、私たちはそのすべてを愛するものなのです。彼女の子供は私たちの子供であり、彼女の家は私たちの家であり、彼女の利害は私たちの利害であり、彼女の不幸は私たちの最大の不幸であり、私たちは、彼女の衣裳も家具も愛します。彼女の小麦畑が風に吹き倒されるのを見れば、私たち自身の金が失われたのを知ったとき以上に悲しみにくれます。暖炉の上に置かれた私たちの骨董品を散らかす客は、叱りつけてやりたい気持ちになります。この聖なる愛情によって、私たちはまったく別の人間となって生きていくわけなのですが、それにひきかえ、もっと年をとると、悲しいことに、私たちは別の一つの生活を自分のなかにひきいれて、その相手の女性が若々しい感情でもって、私たちの乏しくなった能力を豊かにしてくれることを求めるのです。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「この鮮やかな布地の上には、矢車菊、忘れな草、シャゼンムラサキなどありとあらゆる青い花が輝き、空の色からとってきたようなその濃淡さまざまな青の色調は、白い色とじつにしっくり調和しているのです。これはすなわち二つの汚れのなさ、なにも知らぬ汚れのなさとすべてを知りつくしている汚れのなさ、子供の心と殉教者の心ではありますまいか?」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「はるがやのなかに隠されたアプロディーテ〔ギリシャ神話の愛と美と豊穣の女神〕の香りに陶然とさせられたら、はたしてどんな女性が、この心に秘めたもろもろの想念の豪華な饗宴を、このやむにやまれぬ衝動にかき乱された純白の愛情を、そしてじっとおさえつけられた倦むことを知らぬ永遠の情熱が、幾度となく繰りかえしてきた争闘のなかで、ついに拒まれ通しだった幸福をなおも求めつづけるこの赤い恋の欲求を、理解せずにいられるでしょうか? この愛を語る花束のみずみずしい細部や、微妙な対比や、唐草模様がはっきり見えるようにするために、また心を動かされた最愛の女性の目に、ひとしお咲き匂った花から涙がこぼれてくるさまが見えるようにするために、それを十字窓の光線のなかに置いてごらんなさい。彼女はいまにも身を任せそうになるでしょう。天使か、さもなければ子供の声が、深淵のふちで彼女をひきとめねばならなくなるでしょう。そもそも人間は神に何をさしだすのでしょう? 芳香と光と歌、つまり私たちの天性のもっとも純化された表現を、です。だとすれば、人間が神に捧げるあらゆるものが、この光にあふれた花々の詩のなかでは、愛に捧げられていたのではありますまいか? 隠された官能の喜びとか、語られぬ希望とか、暖かい夜のかげろうのように燃えあがったり消えうせたりする幻影などを優しく愛撫しながら、その旋律をたえず心にささやきかけるこの花々の詩のなかでは。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 https://a.co/eZDCexw 「「人生をつまらないと言うのはいけませんよ」と私は言いました、「あなたはまだ恋をご存じありませんが、恋というものには天にまで輝く楽しさがあるのですからね」「おやめになって」と彼女は言いました、「わたくしはそんなものは知りたいと思いませんわ。グリーンランドの人間が、イタリアへいったら死んでしまいます。あなたのおそばにいれば、わたくしは静かな幸せな気持ちになれますし、あなたには自分の考えをなにからなにまで、すっかりお話しすることもできます。どうぞ、わたくしの信頼をこわさないでくださいませ。神父さまのような美徳をそなえながら、いっぽうでは自由な人間として魅力をおもちになることが、なぜできないのでしょうかしら?」」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「とくにあまり人を信用しすぎたり、俗っぽくなりすぎたり、お節介を焼きすぎたりしないでくださいね、なにしろそれが三つの暗礁なのですから。人を信用しすぎると尊敬されなくなりますし、俗っぽくなりすぎると軽蔑を買いますし、お節介を焼きすぎると利用しやすい人間と見られてしまいます。そしてなによりもまず大切なこととして、生涯を通じて二人か三人以上のお友だちをおつくりになってはいけません、あなたの全面的な信頼がその方々の財産になるわけです。ですから、それをたくさんの人にあたえたら、そういうお友だちを裏切ることになりはしませんかしら? 二人か三人の方々と、他の人々よりもとくに親密に交際なさる場合にも、ご自分のことに関しては慎重にふるまい、いつも控え目になさってくださいませ。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「たしかに、誰でもみんな、善良そうな利己主義の蔭にそっと隠されたこのうえなく激しい軽蔑の念よりも、美徳の滑稽さのほうに共感を感じやすいかもしれません。けれども、そう感ずる人でも、その両者を警戒する術を覚えなければならないでしょう。つぎに俗っぽさということについてですが、もしもその俗っぽさのおかげで、ある愚かしい人たちから感じのいい男だなどと言われようものなら、人間の才腕を測定したり評価したりすることに慣れている人は、すぐあなたの欠陥を推察して、あなたはたちまち悪評を受けることになりましょう。なにしろ、俗っぽさというものは弱者の使う手段なのですから。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「そして、不幸なことには、弱者というものは、各々の成員を機関としかみなさない社会から軽蔑の的にされるのです。もっとも、たぶん社会のほうが正しいのでしょうし、不完全な存在にたいしては、自然が死を宣告するわけなのです。ですから、女のいじらしい保護ぶりにしても、ある盲目的な力と戦って、情愛の知恵でもって物質の凶暴さを打ち負かすところに女が見いだす喜び、そういう喜びによって生みだされるものなのです。けれども、社会は母親というよりはむしろ継母のようなもので、自分の虚栄心におもねる子供をいつくしむのです。それから、熱意にみちたお節介ということですけれども、これは若い時代、若さの力を発揮することに現実的な満足をみつけだし、他人にだまされる以前に自分自身にだまされる若い時代の、最初に犯しがちな最大の誤りなのですが、この熱意は心をともに分かちあえる女のために、女性と神のために大切にしまっておいてくださいませ。世間という市場も政治という投機の場も、この宝とひきかえにガラス細工を返してくれるだけですから、こういう大切な宝をそんな場所へおもちこみにならないでくださいませ。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「女というものは、どんなにずるさのない女でも、無数の罠をもっているものなのです。どんなに愚かしい女でも、相手に疑う必要もあるまいと思いこませ、それにつけこんで勝利を占めるものなのです。いちばん危険でない女といえば、べつに理由もなくあなたを愛するようになったり、これという動機もなくあなたを捨てたり、かと思うと虚栄心であなたにまた近づいてきたりするような、そんな浮気な女ということになりましょう。とにかく、どんな女性もすべて、現在のあなたに、あるいはまた将来のあなたに害をおよぼすことになるでしょう。社交界へ出かけていって、楽しみと虚栄心の満足とで生きている若い女性は、一人残らずなかば堕落した女であり、やがてはあなたを堕落させるでしょう。」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「女性とのおつきあいについてのわたくしの考えも、この騎士道の言葉のなかに言いあらわされています。『すべての女性に奉仕せよ、されどただ一人の女性のみを愛せよ』」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「「アンリエット、あなたという偶像にぼくは神にもまさる崇拝をささげていいいます、あなたはぼくのゆりであり、ぼくの生命の花なのです、そのあなたにどうしてわかっていただけないのですか、ぼくはあなたの心とまったく一体になっているので、身はパリにいるときでも魂はここにあるのだということが、ぼくの良心であるあなたにどうしてわかっていただけないのですか? ぼくがたった十七時間でここへやってきたこと、馬車の車輪が一まわりまわるたびに数限りない思念や欲望が運ばれ、あなたの姿を目にしたとたんに、それが嵐のようにあふれでたのだということを、あなたにいまさらお話ししなければいけないのでしょうか?……」」 —『谷間のゆり(上)』バルザック著 「ここで自分の罪を弁明しようなどとは思いませんが、ナタリーよ、こういうことだけはどうか心にとめていただきたいと思います。それは、あなたがた女性が男性の求愛から逃れるときにくらべると、男性が女性の誘惑に抵抗する場合には、ずっと方策にめぐまれていないということです。世間一般の風習として、手きびしいはねつけかたをすることは、私たち男性には禁じられていますが、それがあなたがた女性にあっては、かえって恋する男にたいする誘いの餌となりますし、さらには礼儀の上からしても、義務として定められたものでもあるわけなのです。ところが、われわれ男性の場合には、男のうぬぼれにもとづくおかしな法規があって、慎しみぶかい態度は笑いものにされてしまいます。われわれ男性は、つつましさというものをあなたがたの独占に委ねて、ひそかに好意をよせるという特権が、あなたがたのものになるようにしているのです。ところが、そういう役割を逆転させようものなら、男性はよってたかって嘲罵の的にされます。恋の情熱にまもられてはいましたけれども、私にしたところで、誇り高さ、惜しみない熱愛、美貌という三重の誘惑に無関心でいられる年齢ではありませんでした。自分が女王としてふるまっていたある舞踏会の席上、アラベル夫人が、人々からよせられた賛美の言葉をそのまま私の足下に捧げたとき、そして私の視線をさぐって、自分の衣裳が私の好みにかなうかどうかを知ろうとし、それが私の気にいったとわかると、それこそ喜びに身をふるわせたとき、私もその彼女の感動ぶりに心を動かされたのでした。その上にまた、彼女は、私としては逃げようもない地帯にたちはだかっていたのです。外交界のある種の会合の招待をことわることは、私にはむずかしいことでした。彼女の身分からすれば、どんなサロンの扉でも自由にひらかせることができましたし、それにお望みのものを手にいれるときに女性が発揮するあの独特の巧妙さでもって、彼女は家の女主人に頼みこんで、食卓では私の隣りに坐るようにしてもらった上で、私の耳もとにこんなふうにささやきかけるのでした。「モルソーフ夫人のように愛していただけたら」と彼女は言いました。「わたくし、あなたのために、なにもかも犠牲にいたしましてよ」」 —『谷間のゆり(下)』バルザック著 「伯爵夫人は広間にいて、マドレーヌに刺繍の網目を見せてやりながら、ドミニス神父がジャックに数学の授業をするかたわらにつきそっていました。以前ならば、私の到着の日には、彼女はもっぱら私のことに打ちこんで、自分の仕事など延期することもあえて辞さなかったはずです。しかし私の恋はあくまで真実そのものでしたから、過去と現在とのこのいちじるしい対照からひきおこされた悲しみを、私は心のなかで押し殺しました。それというのも、藁のように黄色い顔色が、この天上的な容貌の上にただようと、さながらイタリアの画家たちが聖女の顔の上に描きだした聖なる微光の反映そっくりにみえたからです。そのとき、私は死の冷たい風が心のなかを吹きすぎるのを感じました。それから、かつてそのまなざしにただよっていた澄みきった水のような輝きを失った眼光が、ふと私の上に落ちかかってきたとき、私は思わず身ぶるいしました。そのときはじめて、彼女のなかには悲しみが原因となった変化が起こっていること、そして戸外ではその変化が目にとまらなかったことに、私は気がつきました。この前の訪問のときには、額にほんのかすかに刻みこまれているにすぎなかった細かな皺は、ずっと深くほりこまれていました。青ずんだこめかみは熱を帯びたようになり、窪んでいました。目は優しくうるんだ眉毛の下で落ちくぼんで、その周囲は黒ずんでいました。あたかも表面には疵があらわれはじめ、内側に巣くう虫のために早くも黄色っぽくなってきた果実のごとくに、彼女は腐りかかっていたのです。私が、望みといえば一にかかって彼女の魂になみなみと幸福を注ぐことしかないこの私が、そうするどころか、逆に彼女の生命がたえず新しくよみがえり、彼女の気力がたえず新しく力を獲得する泉に、苦々しいものを投じてしまったのでなかろうか? 私は彼女のかたわらに腰をおろして、後悔の涙にくれる声でこう言いました。」 —『谷間のゆり(下)』バルザック著 「悲しいことには、わたくしは前ほど子供を愛さないようになってしまいましたの、それというのも、すべての激しい愛情は正当な愛情を奪いとってしまうものだからですわ。ほんとにそうですのよ、フェリックス、どんな苦しみにもそれなりの意味があるものなのです。どうかわたくしを苦しめてくださいませ、モルソーフや子供たちがやる以上に苦しめてくださいませ。あの女性は神さまのお怒りの媒介者なのですわ、わたくしは憎しみをもたずにそばに近より、こちらから笑いかけていくつもりですわ。もしもそうしなければ、信者でもなくなり、妻でも母でもなくなるわけなのですから、わたくしは、どうしてもあの方を愛さなければなりませんの。もしもあなたがおっしゃるように、わたくしもいくぶんかお役に立つことができて、それであなたのお心が美しさを汚すようなものと接触せずにすんだのだとしたら、そのイギリスの女性も、わたくしをお嫌いになるわけはありませんわ。」 —『谷間のゆり(下)』バルザック著 「フランスの女性は、恋をすると一変してしまいます。あまねく賛美の的となっているその独特の媚態を、彼女は恋を飾るために使い、その危険きわまる虚栄心は犠牲にして、いっさいの意図をふかく愛することにむけるようになります。恋人の利害、憎悪、友情をすっかり背負いこみます。」 —『谷間のゆり(下)』バルザック著
0投稿日: 2025.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ美しい文章で、プラトニックだが狂わしい恋愛が語られる。 情景、心情描写がとにかく美しく、バルザックの原文は勿論、日本語訳としての完成度も高いと思われる。(原文で読んでいないので、なんとも言えないけど、、) 時代背景やフランスの小説であるので、現代の恋愛とはかけ離れた価値観(男女観、キリスト教的バックグラウンド)があったり、フランス人女性への盲目的な賛美があるきらいもあるけど、内容、読後感は素晴らしいので、是非読んでおくべき一冊。 自分の置かれた状況に限らず、周りの人へ優しさを振り撒く美しい生き方をしていきたい、という考え方を持つ契機になり得る。 最後に、個人的に特に印象に残った一節を紹介。 「たしかに私はしばしばつまずきました。でも一度たりとも地にたおれたことはございません。」
2投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024年12月5日、YouTubeで横山英俊さんとデヴィ夫人のコラボ動画「戦後の幼少期に一大決心!スカルノ元大統領との結婚生活の裏に秘められたバイブルの一節とは」のなかで、デヴィ夫人が子供時代に読んでた本として紹介されたうちの一冊。 「アンリエットになりきってた」 https://youtu.be/cNsU4-PHicw?si=cGHyoTM12U0hmEyF
1投稿日: 2024.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログナタリー非常に正しい このヴァンドネス君は自分の身をとくと省みるのがよろしい 度を超えた我慢は禁欲は身を滅ぼす モルソフ夫人。。。 残念だ。。。 気持ち次第で人生は良いものにも悪いものにも変えられようと思う、難しいけれど。
1投稿日: 2024.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログバルザック著、谷間の百合。とにかく文章が美しい。プラトニックさも相まってまさに流麗な文体で谷間の百合たる夫人との会話、心理劇が展開される。実際にフランスの田舎はとにかく美しいので、地図や写真をみながら登場人物たちを想像することができる。 細かい描写にも思いを誘うところがあるのでしばらくしたら再読したい一冊。
2投稿日: 2024.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ自伝的要素が強く、独白調で書かれているため、個人的に期待していたバルザック的喜劇とは程遠く、読むのに難儀した一冊。 好みだと思うが、独白体はちょっと苦手。。。
1投稿日: 2024.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
主人公フェリックスは人妻モルソフ夫人に恋をしてしまう。ただ、相手は夫にも家庭にも何も不満を持っていない素晴らしい女性。いくらフェリックスが愛の言葉を伝えようとも、常に年上の人妻女性として彼と対応し、彼の母親であるかのように接してくる。というかフェリックスに恋しないように自分に言い聞かせているようである。 フェリックスの一途な恋はすごいが、それを毎回ひらりとかわさなければならない夫人の苦労を考えると、ただ自分の本能に従って人妻に言い寄るフェリックスにイライラさえしてくる。 最後の夫人の手紙が非常に良い。正直、読者なら気づいていたであろう夫人の本当の気持ちが美しい文体で表現されている。
2投稿日: 2023.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
純真な青年が貞淑な伯爵夫人に魅了され近づくが……。恋愛感情の機微と葛藤を描いた『人間喜劇』に連なる傑作。 うーむ、これはツラい。伯爵夫人の捧げ尽くす愛は美しいが、非常にもどかしくもある。男性側としては、主人公を責められないのだが。二十歳そこそこの男子の性的衝動を軽く考えられてもな〜。後に明かされる夫人の本心を考えると、アンリエットとしての身勝手さ、モルソフ伯爵夫人としての貞淑さで二つに割れている彼女の心も悲劇の要因なわけで。マドレーヌさん、カンベンしてくださいよ……。 しかし、ケチョンケチョンにこき下ろすナタリーの返事は、感傷に対する客観として、いっぱしの紳士となっているはずのフェリックスにはいい薬かも。男女の視点の違いが浮き彫りになる指摘など、皮肉的なラストではあるがどこかコミカルにもみえる。
1投稿日: 2022.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ナタリーというこの作品では登場しない人間喜劇の人物に向けてフェリックスという男性が自分の半生を綴る物語。 前3分の2のフェリックスが恋した人妻アンリエットとの仲良くなる過程は冗長に感じられたものの風景描写や感情の揺れ動きが丁寧に描かれ綺麗でそれを楽しむ作家かと勘違いしていた。後ろ3分の1になってようやく主人公のクズさが分かり恋敵のダドレー夫人が登場し物語が動いた時になって、この作者の会話の巧妙さを知った。ダドレー夫人との一件以降はアンリエットに対して言い訳ばかりする主人公がおり、そのことや後に続く死に対してのことを見るに、結局この主人公は寄宿舎時代やアンリエットに不意にキスしたときから根本的には何も変わっておらずマドレーヌやナタリーが言うように自分のことばかりで成長していなかったということが最後には分かった。アンリエットとの約束もついには守られなかったし。最後まで快く思っていなかったモルソフと最終的には主人公が同じ構造だと分かったところも面白かった。 アンリエットの死の描写は言い方はあれだがとても繊細で衝撃を受けた。思うにこれはフェリックスの物語ではなくアンリエットの物語だった。ただ前3分の2が本当に長く何度も挫折しそうになった。読むのに十ヶ月ほど用し再び読み返そうとはもう思わない。最後の最後まで読むまでは星3だと思っていたが、意味は理解できたので四捨五入したら4になるくらいの点数だと思う。
5投稿日: 2022.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ美しい翻訳は、充分たのしめる。 内容は究極のマゾヒスト同士のストイックな恋愛に サディストガ乱入し、常人が退却宣言をするという物語。 それぞれの心の逡巡がこれでもかと語られ、手紙に綴られ、ある意味自己主張のぶつけ合い試合の様相。 こんなにくねくねものを考えられるのかと感心してしまった。 古今の名作は、膨大な言葉を作家が使い倒して産まれると言うわけだ。 言葉好きには欲求に答えてくれる。 読み応えとはこのことと感じられる。 バルザック、初めて読んだけれど まさにフランス人。 昔の翻訳もなかなか。
1投稿日: 2021.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログカテゴリ:図書館企画展示 2020年度第3回図書館企画展示 「大学生に読んでほしい本」 第2弾! 本学教員から本学学生の皆さんに「ぜひ学生時代に読んでほしい!」という図書の推薦に係る展示です。 川津誠教授(日本語日本文学科)からのおすすめ図書を展示しています。 展示中の図書は借りることができますので、どうぞお早めにご来館ください。
0投稿日: 2021.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログドストルストイの御二大作品は キリスト教及び欧州歴史が成す知識を前提としているかんじで 現在日本でのほほんとしている身には 板書している言語はしれても その説明するところが皆目見当つかない心地だが 同じ人間喜劇でもこちらは修辞が比較わかりやすい気がする 訳者の手腕が並外れているだけかもしれないけれども 日本語ででも音読したくなるような素敵な文 恋愛とその周囲の夫婦や家族や宗教を題材にして 人間とその関係を描いている作品は 「教養」や「青春」というような「小説」の分類は 小説(登場人物と筋書きの結構)だけが 文による表現ではないことを思い出させてくれる 詩歌による表現はおそらく「知識という前提」がないのでわかりづらいのであり ならば多彩な修辞であればわかりやすいのでもないのだ 彫り削ぎ落として本質を得ることもまた表現の手段であるなら そのとき足元に散らばる削り屑も見えていないのでなくそこにあるのだ
1投稿日: 2018.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
初心な青年フィリックスと、人妻であるモルソフ伯爵夫人の恋について、ひたすらその心理のみをつぶさに描いた究極の恋愛小説。自己犠牲を美徳としたとき、恋は不幸に終わります。
1投稿日: 2016.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
550ページ。長かった。 最後はナタリー夫人によるフェリックスに対する批判で終わった。びっくりした。 この話をひどく簡単にまとめてみると次ような流れである。 青年が恋した人妻はキリスト教徒で操を立てて深く愛しあおうとしない。そのことに欲求不満が高まり続け、妖艶で活動的なイギリス女性に恋をして肉欲に溺れた。それを知った人妻は嫉妬の炎で命まで燃やしてしまい死んでしまった。死の間際に渡された手紙にはどれほど青年を愛していたかが綴られていた。青年はその後女性と関わることをやめようと決意したが、ナタリー夫人に出会い恋をした。これが私の過去です。知って欲しかったので手紙に書きました。 という体裁で540ページ近くの手紙をナタリー夫人に送る。ナタリー夫人の回答は「昔の女の話はやめてくれ。あなたはもう愛せない。亡霊と愛しあっていてくれ」というようなもの。 ここで終わる。 最後の最後にモルソフ夫人の手紙、ナタリー夫人の手紙と2度の転換が訪れる。後半ダドレー夫人と出会ってからモルソフ夫人との仲の雲行きが怪しくなるにつれてどんどんおもしろくなっていくが、それまでは退屈極まりない話だった。 官能と自然描写が非常に長く描写されているが、最も記憶に残ったのはモルソフ伯爵の人間描写である。この自己中心的で自分が一番誰よりも傷ついていると思い込んで周囲を傷つけていく人の実在するかのようなリアリティはすさまじく、モルソフ夫人に同情せざるをえない気持ちなる。同時に胸糞悪いモルソフ伯爵がいなくなる気配が全くない序盤はページを捲る手が進まなかった。 恋だの愛だのに興味がない私にはゴリオ爺さんの方が大傑作でおもろかったがバルザックの人間観察と心理観察の鋭さがよく分かった1冊。
1投稿日: 2016.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログアンリエットからフェリックスに宛てた最後の手紙、これを読むまでは、なぜアンリエットが悲しみのために死ななければならないのか、理解できなかった。自らプラトニックで肉親的な愛を求めておきながら、フェリックスの恋愛にショックを受けるいわれがないように思えたから。 しかし死後に読んでくれと手渡した手紙により、アンリエットの心理も理解できた。 原文を読めないのでなんとも言えないが、非常に緻密で練られた文章であることが、優れた翻訳からも伝わってくる。 (2016.3)
1投稿日: 2016.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「人生の門出」が読み進めるのに苦労したので どうかと思ったけど「谷間の百合」はとても読みやすかった。 文体が(とてもとてもとても長い)手紙だったからだろう。 話の筋は単純だけど(ごめんねバルザック…自伝的要素もあるのに) 流麗華麗綺麗な文章がこれでもかと畳みかける。 でも「ああなんて重い愛情…」と思いつつ最後に 「…ですよねー。」とうなずいてしまった。 女性からするとナタリー嬢による主人公への手紙のお返事は至極当然。 こんな手紙を書いてあげるなんてナタリーはとても優しい。
1投稿日: 2015.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
第一部は主人公とヒロイン(モルソフ夫人)の淡い恋愛関係が続く。しかし、一変して第二部では主人公が彼女の傍を離れ、第三部ではヒロインが死に至り、登場人物たちがこぞって主人公を冷笑する。 訳者あとがきによると「谷間の百合」はバルザックの自伝的要素を含む小説らしい。そして、比較的早い時期に完成していたと思われるが、出版まで時間の間隔があったとか。 思うに、第一部は若い時に書かれていて、それを年数経ってバルザックが読み返し、自分の分身である主人公に辟易して第二部以降を付け加えたのでは。(夜中に書いたラブレターに後悔するみたいに。) 個人的に最後のナタリーの手記は不要と思う。終盤の主人公はたしかに女性に理想像を押し付け、そのわりに自分からは行動しないというつまらない人間に成り下がっているし、それを一刀両断する手記にスッキリしたのも事実。でも、第一部の主人公とヒロインの淡い真綿につつまれたような関係や、一貫して守り通されたヒロインの悲しい一途さにまで、良くない後味を残してしまう。 裏表紙のあらすじでは宗教的永遠を描くと書かれていたけれど、話の展開や主人公らの心変わりと言い、むしろ不変なものはないと思えてしまった。 作品を一貫して、モルソフ夫人の主人公への言付けは素敵だった。でも一番好きなのは、主人公の心変わりに冷たく変貌するシーン。それまで完璧だった夫人にはじめて人間らしい弱さが見える。
1投稿日: 2014.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログやはり物語というものは悲劇であるべき。ハッピーエンドには美しさがない。個人的にはゴリオ爺さんの方が好み。
2投稿日: 2013.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
モルソフ夫人が死んだ後、マドレーヌに対して話すときの自己憐憫がしつこくてちょっと苛々しました。 文章は全体的に綺麗な比喩が多くてとても綺麗な文章で、描写のこういう濃さとても好みです。
0投稿日: 2012.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校三年生の夏の読書感想文で読ませられました。 私にはまったく理解不可能な世界でした。 主人公たちは恋に恋している模様。 結局あんたら何したいわけ?とツッコミながら読んでおりました。 500ページも読ませた揚句、あの結末はないよな、と思いました。 痛快と言えば痛快なのですが、そこまでのくだりが長い……。 比喩表現の勉強になるのかな……?と、苦痛を伴う抒情的文章(笑) 読むの、疲れました。 むしろ消化不良の感。 「こんな図書推薦しやがってふざけんな」という思いを胸に秘めつつ、6000字の小論文を書きました。 屁理屈でもこねないと、この物語は楽しめない。 この作品自体では楽しめない。 でも妙に惹かれる作品でもある。
1投稿日: 2011.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
図書館で借りてきた(2011/6/13)。まだ読んでる途中です。 しかし、素晴らしく書いてある箇所があったので引用。 「丸い身体つきは力の証拠です。しかしそうした女性は、勝気で、我が強く、情があるというよりもむしろ官能的です。それに反して、平たい身体つきの持主は、献身的で、こまやかな心づかいにあふれ、ともすれば優秀にとらわれがちです。前者よりも後者の方がより女であると言えましょう。平たい身体つきは、しなやかで柔軟さに満ち、丸い身体つきは柔軟さに欠け、嫉妬深いのです。(Pp.49-50)」
1投稿日: 2011.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログゴリオ爺さんのような滑稽な人間描写が主かと思ったバルザック作品だったが、本作は実に情緒的な恋愛の姿が描かれている。文描写の圧倒的な実力も流石だなという印象。 古典的でベタな物語でもこれだけの質感に導きく実力は物凄い。本作が傑作と云われる所以とバルザックの本質的な実力がよくわかる。
1投稿日: 2010.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校の頃、一度読みました。 最近は外国文学はあまり読まないのですが、急に思い立って購入。 折り重なる言葉のひだの多さに圧倒される。 最近読んでいた本とのあまりの違いに、同じ文章でこんなにも違うものかと。 登場人物の手紙の長いことと言ったら・・・作者はフランス革命時代の人ですが、その時代には、教養ある人々は、こんな長い手紙を書いていたんでしょうか? 人物の、揺れる心理描写もすごい。 でも、これ、覚えある。 日本文学にもある。 それは源氏物語。 特に、宇治十帖と・・・ 自分でも認めたくない嫉妬で弱って死んでいく紫の上、かな。 男女の機微に洋の東西はないのかもしれない。
2投稿日: 2009.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ充たされない結婚生活を送るモルソフ伯爵夫人の心に忍びこむ純真な青年フェリックスの存在。彼女は凄じい内心の葛藤に悩むが……。
0投稿日: 2007.05.27
