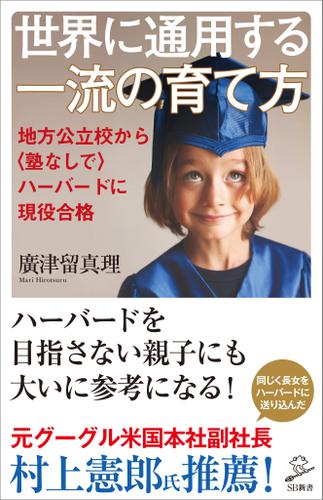
総合評価
(17件)| 1 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ備忘録 ・子供の勉強を学校に丸投げしない 小学校~高校まで、公立に通うとかかる学費は、43万円 ・親と子供は、別人格と認識する ・親が子供の可能性に関して、勝手に判断しない ・習い事は、真剣にやる ・出来る子供は、筋肉がしっかりとしている。体格が引き締まっている。 ・子供をほめてやる気と自信を伸ばす ・子供とToDoリストを作成する ・親が読まない本を子供に読ませてはいけない ・体調の悪化は、首から上にかけて起こる ・模試は、受けない ・宿題の学習効果は、ゼロ。デューク大学 ハリスクーパー ・丸暗記学習は、現代では無価値 ・ハーバード大学の費用は、特段高いわけではない ・英語学習に関して、とりあえず定型文をたくさん覚える ・SIJ サマーインジャパンでハーバード大学生との交流を主催
1投稿日: 2024.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログん〜あまり参考にならなかった。 アメリカ様の言うことは全て正しい、的なある意味盲目。 確かにハーバード現役合格は凄いけど、大学合格で誇ってる時点で日本的だよな。入学してからが大事なのでは? もちろん参考になる部分も多々ありますが、その部分は他の本と同じです。
1投稿日: 2022.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ廣津留すみれさんの本と続けて読みました。小さい頃からの、それも家庭学習って本当に大切なんだなと改めて思い知りました。こちらも読みやすく書かれていましたが、私としてはすみれさんの「超・独学術」の方が面白かった。
0投稿日: 2021.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ常識にとらわれない独自の家庭教育がすごい。でも、なかなか普通の家庭では真似できないかな。「文化資本」という言葉を初めて知りました。 地方の公立高校からハーバード大学へ合格し世界に羽ばたいた娘さん、素直に応援したいです。彼女のTo Do リストを参考に見たかった。
0投稿日: 2021.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ”子供は親の背を見て育つ”ということを実感しました。子供は未来から来た未来人である。旧人類である親の物差しで、子供の振る舞いを測ってはいけない。
2投稿日: 2019.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ平日は勉強、土日は課外活動。 学校での評価にしばられず、子どもの将来や人間性を長期的に考える姿勢は真似したい。
0投稿日: 2019.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ家庭学習✨ 外注に丸投げしない。 長文をなんとなくでも読んで、 勉強以外の時間、見せる場での 度胸付け、平常心。 ToDoタスク。 未来人の子供へ 親が出来ることも色々ある。
0投稿日: 2019.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「なかなかこうは出来ないだろうな〜」 というのが、読み終わっての感想。 筆者(親)自身が早稲田大を出ていて、英語と音楽が得意で、一人娘で・・・と高い能力や環境を備えた上で、必死に教育を施した結果なので、スゴイな〜とは思っても、これを同じように実行出来る家庭は少ないんじゃないかと思う。 終始、家庭教育の重要性と、海外へ目を向けた教育を訴えているが、それも普通はなかなか・・・ なので、一般家庭ではあまり参考にはならないかも。 子供を海外で活躍する人材に育てたい方は一読の価値あり⁈
0投稿日: 2017.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 ハーバード云々ではなく、本来あるべき教育とはこういうことだな、と共感。 子どもにとって、本当に必要なこと、不要なこと、しっかり見極めたい。
0投稿日: 2017.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞広告を見て、本屋でも気になり購入。 息子の子育てで参考になるところも多少ありますが なかなか実践するのは難しいこともあり やはり家庭学習が重要なのかなと考えることもありました。 親も教養身につけて子どもと一緒に頑張らないとな~~。
0投稿日: 2017.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ母親がすごい 塾なしでハーバードへ 育児書読んだり、 幼稚園に通わせるつもりないとか、修学旅行より歌舞伎とか。。外国人とホムパとか ちょっと普通にできないことも多々あり そもそも語学も堪能だから、子供に英語の読み聞かせもできたのだろう。 でも参考になることも以下あった 得意なことを教え、不得意は一緒に勉強 四季や行事を大切に Todoリスト 教育は家庭から 勉強の価値教える 教育コストを抑える リビング勉強
0投稿日: 2017.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ只々、圧巻。一般的な親御さんがやるように、他の親御さんがその子供さんにさせているやり方に盲従するのではなく、自ら本当に子供のためになることを考えられています。日本には留まれない、良い意味で規格外の親子さんたちです。
0投稿日: 2017.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ・常に親と子どもは別人格と意識しておくこと。これが家庭学習の大前提。仮にわが子が勉強や習い事てま成果を上げたとしても、それは親ではなく子どもが成し遂げたこと。親の成果のように錯覚してしまうケースがとても多い。自分とわが子を同一視せてしまうと家庭学習の土台が揺らいでしまう。わが子に対してもいつも謙虚でいる心を持ち続けることが大切。 ・義務教育以外は外注、それ以外は家庭学習。家庭学習を重視した方が学校や塾に丸投げするより、子どもの将来に役立つ。 ・6歳までの親子の時間は一生の財産。 ・母国語(第一言語)で語彙が豊富な子どもは、外国語(第二言語)でも語彙が豊富になり、母国語に引っ張られる形で外国語も得意になる傾向がある。読める漢字が増えて語彙が広がってくると、幼少期の英語学習にも好影響が出てくる。 ・子育ての基本の一つに「大きくなったら誰でもできるようになることを焦って早くからさせない。書くことは筆圧が上がるにつれて上達するし、小学生になったら嫌でもアルファベットや英単語を書かされるから焦らなくてもよい。それと対照的に子どもは読むことが得意。読むたびに「よく読めたね!」と褒めてあげると、それが成功体験となって難しいものほど張り切って読もうとする。計算については「まだ幼いから無理だろう」と親が勝手に判断しないことが大切。一般常識はいったん脇に置き、親の思い込みで子どもの可能性の芽を摘むようなことをしないで、能力を伸ばしてあげるべき。 ・Actions speaks louder than words.言葉よりも行動で示す。これは私が家庭学習で大切にしてきたこと。幼い頃から私が本を読んでいると、いつの間にか近くによってきて横に座っていた。私が楽しそうに本を読んでいる姿を見て、子どもも同じように自分の本を開いて読むようになった。 ・一個人として節度を持って接する、親子といってと、たまたま何かの縁でそうなっただけ。同じ家に住んでいるからといって、子どもにいちいち干渉すりは権利はない。赤の他人に見られて恥ずかしい姿はわが子にも見せない。そう心がけてきた。子どもの反抗期は、家庭内の価値観と学校などの価値観との違いに対する葛藤から生じる。我が家にはそうしたダブルスタンダードがなかったから反抗期がなかった。 ・子どもは未来から来た人と思えば腹も立たない。子どもは未来人。親が知っているこの世界に馴染んでおらず、知らないことがたくさんあって当然だということになる。 ・何が何でも学校の行事を優先させなくてはならないとは思わない。学校は外注先。発注者である親が責任と節度を持ち、何を優先にするかを主体的に判断すべき。 ・親が読まないような本は子どもに読ませない。親自身が興味のないような本を買ってきて「この本はためになるから読みなさい」と子どもに接しても、読まないと思ったほうがよい。 ・わが子はハーバード大に現役合格したが高校の成績は学年1番だったわけではない。そもそも最初から1番を目指していなかった。学校の勉強で学年1番になる程度のことは、広い視野からするとたいした評価にはならない。ハーバード大の入試ガイダンスも「地域の最もよい学校でトップ3〜5%に入ってください」と書いていただけで「1番になってください」とは書いていない。2016年のガイダンスには「地域の最もよい学校で」という文もなくなった。最高に成績がよくてもトップになる必要はなく、他のことに時間を使ったほうが将来への投資になる。 ・「教育は家庭から」という信念。2020入試変革に備えるうえで忘れてはいけないのは、子どもの勉強を学校や塾に丸投げ・外注してはいけないということ。有名な学校や塾に外注することが、必ずしも子どもの将来の成功や幸せを約束しない。 ・ハーバードに限らず、海外のトップ大学はじこせが基本。子どもの頃から自分で決めるのが当たり前だという傾向がとても強い。 ・中高6年間でNYタイムズ1日分の文章しか読まない、これで英語が読めるようになるわけがない。日本の英語教育はリーディングに重きが置かれてきたわけだが、それさえ不十分。そもそも読む量が圧倒的に少ない。 ・ハーバード生は笑顔を忘れない。円滑な社会生活を営むベース。 ・ハーバード生に何か頼むと5分くらいで必ず何かのアウトプットがある。さすがのハーバード生でも5分では80%程度の完成度だが、それでも頼んだ側としては作業がしやすくなる。 ・ハーバード生は否定形ではなく肯定形で話す。ネガティブなことは口にしない。日本では廊下は走らない とあるが「廊下は歩こう」の方が行動しやすい。否定形で注意されるより、ポジティブに行動を導いてあげるほうが、「そうしよう!」と思えるもの。
0投稿日: 2016.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ父が買ってきてくれて読んだ本ですが、著者であるこのお母さん自体がすごすぎます! 英語教育に関する筆者のご意見も、傾聴に値しますね。 私個人的には、ハーバード生の特徴の中に、「笑顔」と「発言がポジティブ」という、日ごろ私が感じている2つのキーワードが入っていたのが、印象的でした。
0投稿日: 2016.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ一人娘が現役でハーバード大に合格。その子育て方が書かれている。 私はこんなやり方をしました、こんな方法をとりました、みんな真似するがいい!!といったドヤ感がすごい。 全体的になんだかとても偉そうな印象を受けた。こうすべきといった決めつけも感じられる。そもそも大学が最終目標ではないと言っているが、どんな人間になって欲しくて1歳の頃から教育をしてきたのかが、よくわからなかった。 得意なことを伸ばした結果なのだろうが、学歴に直結しているのはほんとにただの結果論なのだろうか。 家庭教育の大切さについて、日本の英語教育の酷さについて、ハーバード大生の性質については面白かった。 気になったのは、家庭教育の重要さを言っておきながら、父親の話がまったくでてこないこと。家庭教育である以上、父親も重要な役割があると思うのだが。ここの父上は何を考えていたのだろう。口をだすことすらはばかられるほど妻が強いのかと勘ぐってしまった。
1投稿日: 2016.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ英語教室を運営するお母さんが、どのように娘さんを日本の公立高校からハーバード大に合格させたかを説明している本。小学生から英語の長文に慣れさせるのが大事というのは納得ができた。 一般化しにくい内容だと思うが、塾に頼らず家庭学習の重要性を説いている点は、子どもを持つ親には示唆に富んだ内容だと思った。
0投稿日: 2016.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
英語塾を主宰している著者が娘の教育について語った本。 トップクラスの子たちは東大よりもハーバードやスタンフォードを目指す時代なのかなぁと考えさせられるところはあったが、内容的にはハーバード大生の姿勢がいかに素晴らしいか、娘がいかに自分の教えを守ったかという自慢話が長々と続くだけで得るとことはない。目次だけでも見ていれば買わなかったのに、、、とちょっと後悔
0投稿日: 2016.09.27
