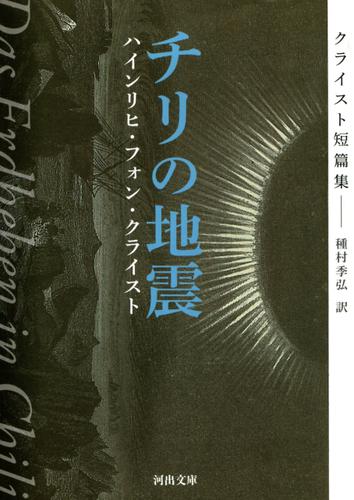
総合評価
(14件)| 1 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイ以外の短篇6本を読んだ。うまくいきそうでそうはならない、という話が多かった。「チリの地震」は、そこには行くな!と止めたかった。「聖ドミンゴ島の婚約」は、すれ違いの悲劇。
0投稿日: 2025.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログドイツの小説家・劇作家ハインリヒ・フォン・クライスト(1777-1811)の 掌短編小説6編+エッセイ2編を収録した作品集。 文筆で身を立てるべく奮闘しながら挫折を味わいもし、 最期は交際していた女性と心中――という、 短くも過激な生涯を送った人物による、 ヨーロッパと南米を舞台にした 風変わりな味付けの人間ドラマが並んでいる。 内容もさることながら、 発表時は宗教界の力が強かったため、 当時の社会通念に照らして、 けしからん内容だと一蹴された小説が、時代が下るにつれ、 価値観の変化に伴って評価が高まっていったという事実が 胸を打つ。 ■チリの地震(Das Erdbeben in Chili,1807) 1647年、チリの首都サンティアゴ。 ジェローニモ・ルグェーラ青年は 家庭教師を務めていた貴族の娘ジョセフェと 恋仲になったことが露見し、クビになった。 ジョセフェは修道院へ送られたが、 ジェローニモは彼女との逢引に成功し、結果、 修道女の妊娠が発覚するというスキャンダルに。 神への冒瀆とて各々投獄されたが、 ジェローニモが絶望して自殺を図ろうとした瞬間、 大地震が発生した――。 * 災害文学の古典であり、 非常時における共助と信仰の問題が俎上に。 体面や家名を重んじ、 自由を抑圧するのが普通だった 古い時代の常識に異を唱える若者の悲劇が、 発表から長い時間を経て、時代が下るにつれて 高く評価されるようになっていったことが興味深い。 反逆児クライストは天国で笑っているだろうか。 ■聖ドミンゴ島の婚約(Die Verlobung in St. Domingo,1811) 19世紀初頭、ハイチでの黒人による暴動と 白人虐殺の最中に出会った可憐な混血の少女トーニと スイス人でフランス軍将校の青年 グスタフ・フォン・リートの恋。 * 後年、合意の上で恋人を射殺して すぐさま後を追ったという作者クライスト自身の姿が 二重写しになる。 ■ロカルノの女乞食(Das Bettelweib von Locarno,1810) スイス南部ロカルノにて、さる侯爵の古城に現れた、 年老いて松葉杖を突いた病身の女。 侯爵夫人は彼女を憐れに思い、一室を宛がったが、 侯爵はそれをよしとせず、追い立てた。 彼女は命じられたとおり暖炉の後ろに移動したものの 息絶えてしまい……。 * 短くて味わい深い恐怖譚。 侯爵の愛犬が見えない幽霊の存在を感じ取って吠えると、 それに合わせたように松葉杖を床に突く風な音が響いた という条が白眉。 ■拾い子(Der Findling,1811) ローマの豪商アントーニオ・ピアキは 息子を伴なってラグーザへ。 そこで疫禍に見舞われ愛息を失ったが、 偶然出会った孤児ニコロを代わりに家へ連れ帰って 育てることにした。 アントーニオの若い後妻エルヴィーレは ニコロを歓迎し、 家族は幸福に暮らしていくと思われたが……。 ■聖ツェツィーリエ或いは音楽の魔力~ある聖者伝説 (Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik,1810) 16世紀オランダ(ネーデルラント)に 偶像破壊騒動が巻き起こっていた頃、 ドイツ・アーヘンの学生四兄弟が感化され、 聖ツェツィーリエ修道院を襲撃しようと目論んだが――。 ■決闘(Der Zweikampf,1811) 14世紀末、ヴィルヘルム・フォン・ブライザハ大公が 早暁、矢で射られて暗殺された。 華奢で優雅な装飾が施された、その持ち主は誰なのか。 二転三転、激しいセリフの応酬が舞台劇の趣きを醸すところは 戯曲をも物した作者の面目躍如か。 ■話をしながらだんだんに考えを仕上げてゆくこと (Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden,1878) 未完のエッセイ。 他者とのコミュニケーションを介して 連想的に思考を取りまとめていくことの面白さと 大切さについて。 ■マリオネット芝居について(Über das Marionettentheaterr,1810) 1801年、著者は舞踏家の男性と偶然出会い、 その人が参加している人形芝居について話を聞いた。 マリオネットに命を吹き込む使い手の技術について “話をしながらだんだんに考えを仕上げて”いったこと。 ※もう少し詳しいことは後程ブログで。 https://fukagawa-natsumi.hatenablog.com/
0投稿日: 2022.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ1755年にリスボンを襲った大地震は神への信仰を揺るがす大事件だった。舞台をチリのサンチャゴに移し、大地震によって死を免れた愛し合う男女が天災と人災のなかで破滅する様を描く絶後の名作。
0投稿日: 2019.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ訳:種村季弘、原書名:Das Erdbeben in Chili(Kleist,Heinrich von) チリの地震◆聖ドミンゴ島の婚約◆ロカルノの女乞食◆拾い子◆聖ツェツィーリエあるいは音楽の魔力◆決闘◆話をしながらだんだんに考えを仕上げてゆくこと◆マリオネット芝居について
0投稿日: 2019.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まであまり読んだことのなかった系統ですが、新しいものを読んでみたくて手に取りました。 素直に素晴らしいと思える作品ばかりです。 しかし、ところどころ翻訳が怪しいところがあるようで……それも話の筋に関わるレベルみたいです。 全集なんかと読み比べもしてみたいところです。
0投稿日: 2015.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 十七世紀、チリの首都サンチャゴで引き裂かれたままそれぞれ最後の時をむかえようとしていた男女がいた…絶後の名品「チリの地震」他、天災/人災を背景にした完璧な文体と構成による鏤骨の作品群、復活。 [ 目次 ] [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
0投稿日: 2014.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
河出文庫。種村季弘の編訳。 多少編成は違いますが、岩波文庫版より読みやすいような。 読みやすけりゃいいってもんじゃないだろーがって 話も巷間にはありますが、それはおいといて。 いやあ、中世って、さすが「暗黒」呼ばわりされるだけあって、 怖いわあ・・・・・・・・・現代人から見れば、ってことですが。 なにが怖いって、中庸もなければ戸惑いも迷いもなく、 過激に極端から極端へ疾走して、完結しちゃうとこ。 信仰に振り回される世界って、その渦中にいれば 案外に幸福だったりするのか??? 現代人の複雑系やらモラトリアムやら、鼻で笑われそうです。 ・チリの地震 ・聖ドミンゴ島の婚約 ・ロカルノの女乞食 ・拾い子 ・聖ツェツィーリエあるいは音楽の魔力 ・決闘 ・話をしながらだんだん考えを仕上げてゆくこと ・マリオネット芝居について
0投稿日: 2014.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学のころ、独文の講義をとった。いくつかの短編小説(時代はバラバラ)を読んでいき、そのうち一つについてレポートを提出するという形式だったのだが、それら短編のうちの一つが、この本所収の聖ツァツィーリエだった。その講義は結局出席しなくなり(たぶん面倒だったんだろう)単位を落とした。もったいないことをしたものだ。
0投稿日: 2014.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章が読みにくい。 他、難しい熟語、雅語などが出てくる。 『エンデの読んだ本』より「マリオネット芝居について」で興味を持ち購入。 この評論の切れ味が良すぎて、ほかの短編作品もいいのだが、それを読んだ時ほどの衝撃は得られなかった。
0投稿日: 2013.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「チリの地震」 首都サンチャゴで、何千という人間が落命した1647年のあの大地震のまさにその瞬間、さる犯罪のために告訴された、その名もジェローニモ・ルグェーラという一人の若いスペイン人が、監禁されていた牢獄の柱の下に立っていましも自ら首をくびろうとしていた。(p11) どよめきの中に投げ込まれたあの衝撃からこの方、人々は皆許し合っている、とでもいうかのようなのだ。人々の記憶はもうあの衝撃の瞬間までしか立ち戻れなかった。 (P22) 最初の大揺れの直後、市内は男たちの目の前で分娩する女どもであふれ返ったということであり、修道僧たちがそのなかを手に十字架を持って走り回って、世界の終りがきた、と叫び狂い、衛兵が副王の命により教会を明け渡すよう要求すると、チリの副王はもういない、と応じた事、その副王はあの恐怖の極地の瞬間に略奪行為をやめさせる為に絞首台をたてさせざるを得なかった事、火に包まれた家をようやく抜けて助かった男が、何もしていないのに立ち回りが早すぎるというので家主に捕まって、あまつさえち首をくくられ (P23) 人々の地上の戝がことごとく潰滅し自然が丸ごと滅亡してしまいかねなかったあの恐ろしい瞬間の只中にこそ、人間の精神そのものがあたかも美しい花のように花開いたかのようだった。あたかおあの共通の不幸がそこから逃れ出た人々全てを苦痛はどの人の心の中でもこよなく甘い喜びと混じり合い、エルヴィーレの思うに、ために幸福全体の総計は、それが一つの面から出てくれば、その分もう一つの面から取り除けられる、とは必ずしも申せないほどだったのである。 (P24) 生まれからすればついぞ仏人なんかじゃなくて、スイス人とこちらに判っているお方が、強盗まがいに襲いかかって殺して身ぐるみ剥ぎたくなる程の、どんな悪を私達に働いたというの? (P65) 植民者達に対してここでならした不平が、島のあの人がやってきた地方にも同じ様に通用するのかしら? (P65) 「話をしながら段々に考えを仕上げてゆくこと」 フランス人の言うには「食欲は食べているうちにわいてくる」のだそうだが、この経験命題をパロディ化して「考えは話をしているうちにわいてくる」といっても、事実であることに変わりはない。 (P206) 自分の求めているものとあらかじめ若干の関係のあるなにやら模糊とした観念を私は持っており、(略)これを携えて臆面もなく一歩を踏み出しさえすれば、はじまったからには結末もあるはずという必然性に導かれて、話の進むうちに、(略)情念がその錯綜した観念に完全に明白な刻印を与えてくれる (P207) モリエールみずからの言うところによれば、モリエールは彼自身の判断を語る術を心得ているこの女中の判断を頼りにしていたという。 (P207) 7月23日、国王が諸身分代表に討議を命じていた国王最後の君主制議会終了の後、諸身分代表がまだ席を去らずにいた議会にとって返して彼らに王命を承ったかと尋ねに来た式部官を、ミラボーはあの「電撃」で片づけたのだ。 (P208) ミラボーの答えるには、「我々、王のご命令を承りました」-思うにミラボーは、このおとなしやかな発端では締め括りの言葉にした銃剣のことは念頭になかった。「さよう、閣下」とミラボーは繰り返した、「承りましたとも」-御覧のようにミラボーは、自分が何を言いたいのかサッパリ判っていない。ミラボーは続けた、「ここで王名をめかされるいかなる権利がおありかな?我々は国民の代表なのだ」-これこそミラボーの必要とした言葉だったのである。「国民こそが命令を与えるのであり、国民は如何なる命令も受けはしない」ミラボーは、いまや魂が武装蜂起の構えで待機している反抗を表現する言葉を、ようやく見出すのだ。「それゆえ、どうか国王陛下に申し上げて頂きたい、我々に議席を去らせる者があるとすれば、それは銃剣の暴力を措いて他にはございません」 (P209) 相互作用によってそれ自体に内在する電気―度が再強化されるのであるが、それと同様にわが弁論家の勇気は的を壊滅させながら大胆極まりない精神抑揚へと移行していく。 (P209) この種の話し方こそが真の声高らかな思考である。表象の列と表象の記号の列とがならび会って同時進行してゆき、その両者にも情念が呼応する。 (P212) ある表象が支離滅裂に表現されたからといって、そこからただちに、当の表象が支離滅裂に思考されもしたという帰結は出てこない。 (P212) 思考から表現への精神の移行という突然の業務交替が、考えたことを口に出すのに必要でもあれば、考えたことを固定するのにもなくてはならない精神の刺激を、再びすっかり解除してしまったのだ。 (P213) 実は、解っていない、のではなくて、それが私たちのある種の解っている状態なのである。むしろ凡庸そのものの精神、昨日暗記したばかりで明日は綺麗さっぱり忘れてしまう人間の方が、こういう場合には打てば響くように回答しかねない (P214)
0投稿日: 2012.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ発表当時はすでに200年前。 今読めば、まるで現代文学のよう。 現代にも通じる、切り裂くような痛烈な文体と構成。
0投稿日: 2012.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ【チリの地震】 処刑という絶望の中、起こった大地震。そして、地震は離れ離れになっていた男と女と二人の子どもを再会させる。一瞬、希望が彼らを包む。まるで、それはユートピア。 しかし、たくさんの人々の「犠牲」の上に成り立つ再会と幸せなど長続きすることはない。 一組の男女を生かすのも、許すのも、裁くのも、殺すのも、それらは決して神が行うのではない。すべては、人間が行うことなのだ。 この作品が、3.11後に再び出版された意味とは一体何なのだろうか。わたしたちは、400年以上前のチリで起こった地震をテーマにした作品から何を感じ取るべきなのだろうか。
0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「チリの地震」息が止まる衝撃。 今まで読んだ短編の中で、一番の傑作。 救われた喜び、再会の喜び、困難な中での一体感、待ち受けていたかのような人間の醜悪さ、夫婦に託された微かな希望。
0投稿日: 2011.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ起承転結のしっかりした、王道の短編集といった印象。 「チリの地震」 天災が人間の心の中に、ある種逆説的に平穏さをもたらす場面の描写が凄く上手。★★★ 「聖ドミンゴ島の婚約」 分かりやすい悲劇。起承転結がハッキリしていて短編のお手本といった観あり。ベタだけど普通に面白い。★★★★ 「ロカルノの女乞食」 いや、流石にそこまではいかないんじゃないか。と思ってしまう幽霊の影響力の強さ。★★★ 「拾い子」 シンプルな構成ながらも、怒り心頭のピアキの迫力はなかなかのもの。★★★ 「聖ツェツィーリアあるいは音楽の魔力」 これは奇蹟と言えばいいのか何なのか。神の配剤は少なくとも俺の理解を超えている。★★★ 「決闘」 これも王道と言いたくなるような起承転結のハッキリした構成が読みやすい。正義は勝つ。★★★★ 「話をしながらだんだんに考えを仕上げていくこと」 これは小説ではなくエッセーの類かな。タイトル通りのことが書いてある。まずは話題にして口に出してみると、もやもやしてた考えがしっかりした輪郭をとる、というのは仕事の上でもよく使う手段。★★★ 「マリオネット芝居について」 エッセーのような小説のような。認識力が自然の動きを阻害するという論旨は結構面白かった。★★★
0投稿日: 2011.08.20
