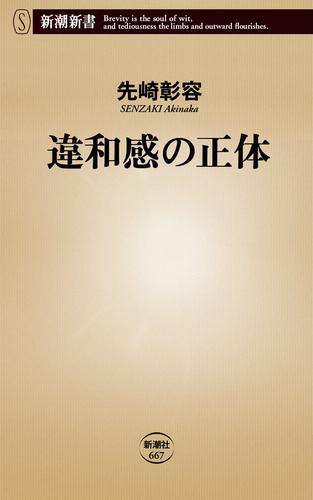
総合評価
(16件)| 1 | ||
| 8 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「ものさしの不在」「処方箋を焦る社会」をキーワードに、二項対立や型にはまった価値観に対して筆者が覚えた違和感について、歴史や思想家のことばを参照しながら考える。 現代日本は「普遍的な価値や真理」が存在しない相対主義の時代、各人バラバラに正解を導き出す必要がある。その困難と不安に耐えきれず、「反原発」や「アメリカ批判」といったわかりやすいスローガンについ飛びついてしまう。そして、友と敵を明確に分け、敵対する勢力を排除することで友=つながりを強固にしようとする。しかし、自分の考える「正義」を声高に叫ぶのではなく、微妙な均衡点を探りだし新たな秩序をつくりあげるために、理解困難な他者と粘り強く交渉を続けなければならない。 本書で紹介されている思想家のなかで、「自分の価値観の主張はエゴイズムである」と自己の限界を意識した「現実主義者」高坂正曉、自分の正義感を自問し続けた吉本隆明、日々の生活のなかで問題を解決し続けること、秩序を維持し続けることこそが「政治」であると考えた江藤淳に興味を覚えた。
0投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ2023/10/12読了 正しい言説正しい情愛といえども、笑いを失えば不正となる。 自らの正義に疑問を持たない人を啓蒙することは極めて難しい。 知性は必ず弾力性を失い、自分を信じすぎてしまう。そうなるとイデオロギーになる。知性主義となる。
0投稿日: 2023.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ論説とか、解説ではありません。 エッセイ。 それも、酔っ払った文学青年が、多少シニカルに学のない友達を睥睨する、そんな感じの本。 著者が現代社会で感じる違和感に、過去の思想家の思想も紹介しながら、「説明」をつけていく。自分の設定したスキーマの土俵に理論を構築して、論じるのは、ストローマン論法とさほど変わりはない。 「物差しのない時代」とか、自分の中の正義を振り翳すみたいな、肯首できるところもあるのだが、大半は飲み会でハミゴにされてるのに気づかず、一人で喋り続けてる感じかなあ、という論。 文字面だけ追って、読み飛ばした。
0投稿日: 2023.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ神が土台となっている欧州の思想を神なしで日本に持って来たため土台が根腐れしている、と言ったところか。最単純に言うと二項対立はそれ自体が何も考えていないから起こるので、それに絡め取られてる時点で問題解決には程遠くなると言うこと。 本来なら江戸までの日本的価値観を土台に据えなければいけないのに旧弊と切り捨てた所から間違えている訳だ。これは他の思想家の方々も各自の方法でたどり着いた答えと同じですね。 いつ日本人は過去の遺産を取り戻す気になるのだろう。
0投稿日: 2022.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ日々をぼんやりと生きている自分には、難しく理解できない箇所も多い。 読んだ時には、なるほどと思うがすぐにわからなくなる。要再読。
0投稿日: 2022.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ神武(岩戸、いざなぎ)景気 ⇔2020 相対主義 村上裕一「セカイ系決断主義」 ロマン主義的政治のheroism→ポピュリズム? サングラスの橋本は屈折した自己表現、政治の場に立ち外したときは社会を直視できるようになった? 戦後日本の自由主義教育 教師の権威性 政治と日常の区別の必要性 与那覇の新しい歴史観 中国を中心とする新・帝国主義の時代 あぶれ者たちの感覚を掴みきれないとき、彼らは暴走しはじめた が制御不能→国家の危機
0投稿日: 2022.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ多様な意見が認められて少数派も尊重されるという風潮の中で、旧態依然とした思考の人たちが振りかざす「物差しのない正義」。感覚的気分的な尺度で激昂して身勝手な殺人を起こす犯罪者も方向は同じだと思った。ダイバーシティが進むにつれて言わないでもわかる常識的なことが消えていき、わからない者同士が互いに信用できる新ルールを作るにはロジカルに進めないと理解し合えない。しかしこのロジカルは個人の経験則や感情的に大切にしたいこととは逆行する場合がある。そしてそのストレスが更に間違えた正義となって発散される悪循環を招くのだろう。大変面白く読んだ。
0投稿日: 2022.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ものさし不在」で、さまざまな「正義」が跋扈し、騒々しいまでに「処方箋を焦る社会」に対する違和感を先崎先生が斬る。 東日本大地震後の原発反対運動、安保法制反対デモ等が激しかった頃、著者が感じた違和感をベースに論じられる日本の姿は、驚くまでに今、コロナ禍で感じられる違和感とも相似している。 自らの正義を疑わず、「〜であるべき!」「反◯◯」を唱える人々。権力を持つものは悪で、民衆は善であるという決めつけ。 我が正義こそが普遍的であると押し付け、人の意見に聞く耳を持たない人たち。相手の尊厳をも尊重しない言葉の暴力が溢れた社会に疲れ果てている私に、この著書は静かに語りかけてくれる。 この本に引用されている、敗戦時、寄るべきものを失った時代に江藤淳や吉本隆明らが著した本を是非読んでみたくなった。 今こそ、文学(言葉)の力が必要だという著者の言葉に納得。
1投稿日: 2021.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近夜はBSフジのprimenewsにハマっているのだが、先日登場されていた日大の先崎教授の著作。 日頃ビジネス界隈の本ばっか読む中、ひっさびさに思想、社会学系の本に触れたのもあり、初っ端から『ああ文系の論考ってこうだよなぁ〜』感を痛烈に感じた! 物事を、ファクトベースではあるんだけど、そこに個人の知識や知見、過去の思想家などの思考をふんだんに絡めて、独自の視点で喝破する。それはとてもブレもなくなるほどなぁと思わされるのも多いが、極めて分かりづらい...。論点や論拠があっち行ったりこっち行ったり、着いてくのがしんどい。 primenews登場時の論説は極めて分かりやすかったのだが、著作はむずかった。が、たまにはこういうものも読まねばと思った。 あと冒頭、なぜブラピの名作『リバーランズスルーイット』が“反知性主義”とされるのか、という問いがあり、その答えが本章で描かれてて、なるほどなぁと思った次第。深い。
0投稿日: 2020.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログまだ中途半端です。 違和感を自分で感じました。よくわからんちんでしたもんで。 賢い御仁であろうし好感持って新聞コラム読んでいますが。 俺が阿呆なんでしょう・・・残念なおっさんと呼んでください・・
0投稿日: 2018.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログテレビなどのメディアで流れている「主張」ってだいたい二元論でどっちかの立場の者が声高にしゃべってる図で、違和感がなくもなかった。 わかりやすいから流しやすいのかもしれないけど、それじゃ批判される方はビクともしないですねたしかに
0投稿日: 2017.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「躊躇い」と「躓き」。 様々な知識人を取り上げ、その言動の解説が冷静かつ秀逸だと思います。 「どれだけ正しく見えても、簡単に信じないようにするにはどうすればよいか」(P157)、「自分の想像力と実際とはどれくらい違うか」(P189)、吉本隆明の言葉に、物事の本質を追及する深みを感じました。
0投稿日: 2016.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ものさし不在」と「処方箋を焦る社会」という2つのキーワードで現代社会を理解するという切り口は悪くないと思うのだが、著者独特の文体が非常に読み難くて分かり難い。結果、何がいいたいのかよくわからない。もうちょっとスッキリ書けないのだろうか。
0投稿日: 2016.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログマイノリティーが"差別撲滅"等のイデオロギーを振りかざすのは自意識過剰の表れである。 マイノリティーならマイノリティーであることの誇りを持つこと。
0投稿日: 2016.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書だから気楽に読めるかな、と思ったけど、3回読んでようやく大まかな内容が理解できた。 この本をなぜ読もうと思ったかは言うまでもない。安保法制をめぐる国会前のデモや、沖縄の基地移転をめぐる知事の発言、在特会などのヘイトスピーチ、いじめ自殺やモンスターペアレンツによる教育現場の疲弊。報道に接していて常々思っていたことは、なんでそんなに簡単にレッテルを貼って、事を単純にしようとするんだ、ということ。 これらの事象を読み解くカギとして著者はふたつのキーワードをあげる。ひとつは「ものさしの不在」もうひとつは「処方箋を煽る社会」 「ものさしの不在」というのは、以前は信頼するに足る権威や情報というものがあったが、いまはその信頼性が大きく揺らいでいるため、自分自身でなにが正しいのかということを考えなくてはいけない、ということ。 昔は先生のいうことを聞いていれば良かった。マスコミの情報は的確だった。経済は右肩上がりで、真面目に働いていれば生活に困らなかった。それらが現在は頼りない、神話となってしまった。 「処方箋を煽る社会」というのは、上記のような病理を治す特効薬を望む人が多くなったということ。そんなに簡単に解決策があるわけではないし、あったとしても時間がかかるものなのに、即効即決を望む。そうなると耳当たりのいい極論に飛びつく人も出てくる。(トランプ現象なんてその顕著な例かもしれない) 個人的に最近の報道で感じた違和感は沖縄だ。 軍属の男が女性を殺した事件だが、すぐに米軍出ていけの集会になって、辺野古反対になって、知事はその論陣の先頭に立った。被害女性の死を悼むのそっちのけにして、事件を政治利用してないか? 構図的には戦争で死んだ兵士を戦争の英雄に祭り上げて自軍を鼓舞するのと一緒だじゃないのか。(※著者は上記のようなことは言ってません) たぶんこんな意見を有名人がSNSで拡散したら炎上する。罵詈雑言が飛び交うことだろう。沖縄の心がわからない奴は死ね!とか。 実はこんな言葉をすぐに吐ける人が「違和感」をつくりだしている人で、「正体」だ。本書を読めばその意味が汲み取れるだろう。
0投稿日: 2016.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆2 最近世間でいろんな場面で語られる「正義」や「ただしさ」に関する「違和感」がどこから来ているのかという主題について,過去の思想家の試作や作品を元に考察されています。 書き出しにおいて,基準となる「ものさしの不在」となっていること,そして答えを早期に求める「処方せんを焦る社会」というのは,至近の多数の課題に対するマスコミや世間の動きを見ていると,なるほどとは思ったのですが,そこから後の論の展開は,あまり腑に落ちるところがありませんでした。 ところどころ,「こういう話も切り口によってはわかる」と思うようなところもあるのですが,それは一部で,その後の論の展開には,あまり納得することができませんでした。新書で扱うにはテーマが大きく,あれこれ幅広く語れているからかもしれません。 冒頭の考え方の基準となる「ものさしが不在」であることと,そこから答えを急ぐ傾向というのは,もっともな指摘だと思います。そのような世の中でも,自分なりの基準をきっちりと持ち,判断できるようにするためには,情報をきちんと仕入れてそれを咀嚼するというインプットともに,自ら納得をして態度を決め,意見が違う人とも適切に理解をしあうというアウトプットが,今の時代ほど求められているのだと思います。そのベースとなるのは,子供の頃の学校や,それ以外の実地での教育なんだろうなという思いを,最近,いろんな場面で持ちますが,その思いをこの本の冒頭を読んだときに思い起こしました。
0投稿日: 2016.06.12
