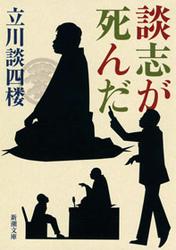
総合評価
(13件)| 1 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ一気に読ませる。 談春の『赤めだか』が出てベストセラーになったのが2008年。談四楼が書評で褒めたら、談志が激怒し、おまえは破門だという。還暦近くになって破門されるとは。なにが悪かったのか、理由がわからない。この時、談志72歳、亡くなる3年前のことだ。 最初は家元の怒りにまともにとりあっていたが、しかし少しずつ異変に気がつき始める。書いてあるエピソードを読むかぎりでは、強迫的嫉妬、記憶障害や相貌失認の症状。病気なのだ。 小説風の展開で、モノローグが随所にあり、回想シーンも頻出する。なまなましすぎて、多少脚色しないと書けなかったということなのかもしれない。 (蛇足。「談志が死んだ」という回文は生前からあった。談志がぴんぴんしている時に、同名の本も出ていた。あえてこの書名にしたのは、談志の死を知った直後のことを冒頭に据えているからか。)
0投稿日: 2025.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ談志の懐古本。書かれているエピソードはどれも面白い。しかし談志と談四楼の結びつきがどのようなものであったかはいまいちわからない。 談志がそれほど凄い落語家であったのか、どんな無理難題をふっかけられても、弟子が何も言えないような、それほどのものであったのか。 学生時代(浪人時代?)、後楽園ホールの公開録画に行って談志が司会の「笑点」を見た。たしかにものすごく面白かった、ハチャメチャと言っていい面白さだった。当時の落語もスピード感あふれるハチャメチャだったと記憶している。ただしこの頃は寄席へは行っていない。 このとき「マカオのおかま」という回文が出てきたように記憶している。本の表題になっている「談志が死んだ」もこのとき出てきたような気もするがこちらは確言はできない。 この本によれば談志はピカソのように何度も変わったとのことだが、継続して談志を見ていないのでそれはわからない。 最後に見たのは横浜であった談志の会で、もう病気になってからだった。澤田隆三がプロデュースしていて、志の輔が談志が来るまでのつなぎをやっていた。志の輔が前座をやるくらい談志はえらいんだと思った。 しかし談志の演目は柳亭痴楽の綴り方教室? みたいなもので、朝鮮語なまりでしゃべってみせてもほとんど笑えないものだった。何をやっているのかとがっかりした記憶がある。
1投稿日: 2023.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020.7.13.読了 2.5〜3かな… 一番好きな落語家ではないけど、好きな落語家の一人。 生前に残った破天荒?の話がとても多い落語家でもある。 生前から亡くなったあとまで、またまつわる話を古株弟子の一人を元に語られている。 良いことも悪いことも、語られる事は興味があり、面白くもあるけど、正直、個人的には談四郎さんの語り口がどうしても引っかかってしまう。 談志師匠が落語家としてはもちろん、特殊なカリスマ性を持ってるからこそある事ではあるとおもうけど、憧れ、尊敬、羨望、嫉妬、愛憎、独占欲の様なものを感じてしまい、ネガティブな要素も感じてしまい、気持ちよく読む。という事が難しかった。 最後の親と子。という部分も、それを踏まえた形に感じてしまう… うーん。 一人の近い人間から語られる事だから、これで良いのかもしれないけど。 同時に、それを感じさせるくらいの、筆者の強い想い。がある事も伝わる。 もちろん、筆者だけではなく、多くの人がさまざまな形で強い想いを抱く人。 落語家にも力があり、生き方にも力と己の道を進み、カリスマ性がある談志師匠だからこそ、多くの人が惹きつけられ、様々な反応がでる。という意味では興味深い。 一度生で高座を見たかった。
1投稿日: 2020.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ一つではなく そのほかにも 秀でているモノを 持っておられる人のモノは やはり面白い 談四楼さんの この「小説」には そのことを強く感じた 立川談志さん 確かに稀有なる噺家のお一人だったろう 古今亭志ん朝さんが亡くなられた時に 「寄席の灯が消えた」などという常套句が 新聞、雑誌に載せられた時 「けっ 何を言ってやがる 俺(談志)がいる!」 と言われたとか、言われなかったとか、 そんなエピソードを 彷彿とさせられる一冊です
1投稿日: 2019.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは本の雑誌ランキングから、だったかな?落語のことを殆ど知らず、談志といえば第1回M-1での辛辣コメントしか思い浮かばないんだけど、ランキング上位に選ばれる以上、門外漢でもいけるのかな、と思って入手。偏ってはいるけど基本的にはお笑い好きだし、立川一門のことなら意外に楽しめるかも、っていう思いも抱えつつ。とはいえ、そもそも本著者のことも知らないし、出てくる名前も殆ど初めて聞く人ばかりとなると、さすがにハードル高めだった(苦笑)。とはいえ、巨星が墜ちたときの一門の混乱とか、だいぶ頭が怪しくなってきていた最後の日々とかは、かなり楽しく読めました。
0投稿日: 2019.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ師匠 談志の死と、かつて同じ師匠の下で修行しながらも袂を分かれることになった同期 小談志の死。 師匠 談志の陰陽を虚実合わせて紡ぐストーリーに引き込まれた。 あくまで、ノンフィクションではなく長編小説という形にしているのが粋。
0投稿日: 2017.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ物書きでもある落語家が描く、稀代の落語家の晩年の日々。師匠の心身の異常による理不尽な仕打ちへの恐怖と悩み、自分も年齢を重ね、かつての師匠が通った道程と照らし合わせたときの思いなどが軽快なリズムの文体から体験できます。 談志はピカソ、と称する山藤さんの言葉が、その生涯を表すのにぴったりだと感じられました。
0投稿日: 2016.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
立川談四楼『談志が死んだ』(新潮文庫、2015年11月)読了。 立川談志は好きではない。(笑) とはいえ気になる落語家であったことは間違いない。とくに1999年の第50回紅白歌合戦に飛び入りした姿が忘れられない。 そんな談志を巡る「裏側」を小説風に綴ったのが本書。 立川流の落語家は文章がうまいというのは以前から知ってたが、今回談四楼の文章を読んで、「うまいなあ」とそれを実感。 小説の体裁を取っているとはいえ、ほとんどが実話なのでしょう。晩年から亡くなるまで、弟子として仕えてきた談四楼ならではのエピソードがよどみなく綴られている。 個人的興味からいえば、落語協会の分裂騒動のくだりが面白かった。振り返ってみれば1978年の出来事というから、恐ろしく古い。 しかし当時から少しだけ落語に興味があった小生。この騒動で圓生が協会から脱退したことは衝撃的だったし、小さんが嫌いになったりした(あまり意味が分かってなかったのだけれど)。 分裂騒動は大量の二つ目を真打ちに昇進させようとした小さんに反旗を翻した圓生が協会を離脱したことに起因する。真打ち昇進試験を実施して二つ目を真打ちに昇進させる策を取る落語協会。 1983年の真打ち昇進試験は10名が受験し、2名が不合格となる。2名とも談志の弟子で、そのうちの一人が談四楼だった。その談四楼がこの出来事を書いているだから詰まらないはずがない。『うーん、そうだったのか』と事の真相が明らかになる。まさにドラマ。 師匠と弟子。どこぞの世界にも通じる何かがある。 そういえば、本書で、談四楼は談志の「お別れ会」の場面を詳細に書いている。その中にこんな場面がある。司会は談笑。 続いて談笑は、大スクリーン前へと移動するように客を促す。映し出されたのは談志生前の高座、それも2007年、読売ホールにおける伝説の『芝浜』であった。「登場人物が勝手に喋り出しゃがった」と談志が言い、そこに居合わせたファンは「神が降りた」と賞賛し、談志も楽屋で更に「技(ぎ)、神(しん)に入る」と胸を張ったのが、この『芝浜』なのだ。[p.198] 『そんなにすごいのか』と聴きたくなるような書きっぷり。 でも芝浜、あんまり好きではない。あんまり好きではない落語家の、あんまり好きではない演目。(苦笑) そうそう、お分かりのように、このタイトル、回文。 談四楼によれば、スポーツ紙の見出しだったようだ。
1投稿日: 2016.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログまさに虚実皮膜の間。どこまでが実話でどこからが創作なのか判然としない。 ただ、孤高の天才が直面する老いの問題を巧みに救いとっていると感じた。
0投稿日: 2016.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ噺家さんが書く文章にはずれはない、まして直弟子がその師匠について記した本書は外しようがない。そこに著されるのは「ここまで書いていいのか」と思うような故人の陰鬱たる面が多いのだが、それが結果的に陽の部分を浮かび上がらせる絶妙な効果になっている。
1投稿日: 2015.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ立川談春が抜群に面白かったのでこちらも読んでみる。立川流最古参の弟子の回顧録。なんか、文句が多いように感じてしまい、作者の視点が最後まで好きになれなかった。この人の落語はどんな感じ何だろう?落語は人柄が出る気がするけどもしこの本から感じ取れる人なら見たいとは思わない。
0投稿日: 2015.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ噺家さんとは、虚と実の合間を歩くものなのだろうか。 噺とは、命や老いや浮世の義理やら、何やらを描いたものなのだろうか。 そして、その噺の中には、笑いとともに哀しさや軽みがあるものだろうか。 軽さじゃなくて、軽み。ほんとは、ずっしりと重いもののはずなのに、ふっとぬけてくような軽み・・・。
1投稿日: 2015.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ実は立川談志についてはあまり関心がなかったため名前しか知らない。そんな私が読んでもおもしろい小説(ほぼドキュメンタリーと言っていいと思うが…)だった。どこが創作部分なのだろうか、一門にくわしくないためそこのところがわからないのが残念だけれど、わからないなりにぐいぐい引き込まれてしまう読み応えのある作品だった。 理不尽なほど独裁者であった家元の死をどううけとめたのか、晩年から死後にかけての古弟子である著者の行動と頭を去来する数々の思い出話をベースに一門の動きを描きつつ、落語協会をとびだして立川流として独立した経緯から談志の人となりまで詳しく知ることができる談志&立川流入門と言っていい内容。と同時に、親や師匠のような存在が老いて壊れていく容赦無い現実をいかに受け止め向き合っていけばいいのか、きれいごとでは済まぬきつい現実と、それを乗り越えた先にある心境を疑似体験させてくれる稀有な作品だった。 こう書くと深刻な作品としかみえないが、実際には落語的な文体(文中に落語そのものも折りこまれているし、噺家同士の会話もほとんど落語そのものだし)のおかげでおもしろくどんどん読めてしまった。
1投稿日: 2015.11.30
