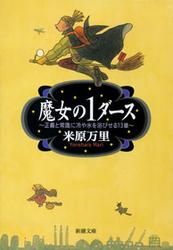
総合評価
(91件)| 22 | ||
| 39 | ||
| 17 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白い! "常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションでしかない" アインシュタインの言を腹落ちさせてくれる一冊。男、女、キリスト教徒、イスラム教徒、先進国、発展途上国、戦勝国、敗戦国、私たちはあまりに違うのに、気を抜くと、正義も真実もたった一つしかないように思ってしまう。 20年以上前の本だけど、 snsの台頭でますますその傾向が強まり分断がうまれている現代にこそもっと読まれて欲しい本だと思います。
3投稿日: 2025.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的で話し上手で、胆力があり、お茶目。通訳やロシア(ソ連)で生まれ育った経験を通じて、私たちのもつ社会通念に「冷や水を浴びせる」ような、米原万里の魅力が詰まった本だった。これも自分で買った本ではなく、身内の本棚にあった本で旅中の出会い。 アネクドートとは、特にロシア語圏で広まった風刺やジョークを指す小話。これと、シモネタを自由自在に駆使するのが米原万里。シモネタも教養がベースにあるから下品な感じがしない。 本書で取り上げられる、私の好きな話。米原万里の創作ではなく、ロシアのアネクドートだと思うが、彼女の雰囲気によく合う気がした。 ー まずイギリス人が、「エデンの園は、絶対にイギリス以外に考えられない」と言い張る。曰く「イギリスは紳士の国だ。林檎が一つしかないとき、何はさておき、まずレディーに譲りするとは、これぞジェントルマンシップ。アダムはイギリス紳士だったはずです」フランスの学者も、一歩も退かぬ構えである。「いや、二人はフランス人に相違ない」「たかが林檎一個で男に身体をまかせる女なんてフランス人くらいしかいないはずだ」となかなか説得力のある発言。ところが、そのときまで黙って話に耳を傾けてきたソ連の学者が、やおら立ち上がると、自信たっぷりに言い切ったのだった。「議論に決着をつけてさしあげましょう。アダムとイブはわが同胞であったに違いありません。ろくに着るものもなく裸同然の暮らしをしていながら、食い物ときたら林檎一個 … そこを楽園だと信じていたアダムとイブは、共産主義下のソ連人に違いない!という自虐ネタだ。 アクネドートは「性的、自虐的、平和、多様性」を織り混ぜて形成されている事が多いので、人を和やかに楽しませる事ができる。これが著者の教養の真髄にあるのだろう。本書は、冷や水どころか、そんな安らぎのシャワーを浴びられるようなエッセイ集。
82投稿日: 2025.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ各章の冒頭、「パリのアメリカ人」のように「異郷のなんとか人」ネタで、読者の関心を鷲摑みにする。しかしその先がどういう展開になるかは、ほとんど予測がつかない。なにしろ書き手は米原万里、使えるリソースは無尽蔵にあるからだ。たとえば、モスクワのベトナム人で始まる章は、ロシアの小噺につながり、それが三権分立の話につながってゆく。シベリアの日本人で始まる章は、純粋概念の話につながり、それがオウム真理教の話で終わる。 こういった章が13。この数なのは、魔女にとっての1ダースが13個だからという。もしかして、下ネタの多さも魔女のなせるわざか。 巻末の解説を書いているのは、同時通訳の「師匠」と仰ぐ徳永晴美。弟子以上にパンチの効いた文章。驚いたことに、師匠は米原万里と3歳しか違わなかった。
0投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ国際問題・近現代史の話七割、下ネタ二割、その他異文化交流小咄一割、といった感じのエッセイ。 米原万里さんの本、過去にブクログに「読んだ」と登録していたのは一冊だけだった(『旅行者の朝食』)。もう少し読んでいたような気がしたのは、他の方のレビューや家族の所有本などでよく見かけるから、勝手に顔見知り気分になっている著書が多かったせいかもしれない。 『旅行者の〜』の洒脱さに比べると、本書はちょっとギトついた印象。でもタイトル→裏表紙の紹介文→まえがきの導入がうまく、あとがき→解説も軽やかで、焼き肉をくるむサンチュのように(ロシア料理で例えられなくて申し訳ない)、ともすると胃もたれを引き起こしそうな本編の重みを和らげてくれた。 以下、備忘メモ。 ・中ソ関係が最悪だった六〇年代、七〇年代を通しても、一九四五年に中国東北地域に初めてソ連軍が進行してきた(ソ連による日ソ中立条約の一方的破棄ということになる)ときの戦車や戦闘機が、神聖なものとして維持されていた。ソ連軍は、日本の中国支配からの解放軍として記憶されている。
13投稿日: 2024.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ【感想】 本書は、日露の同時通訳の第一人者である米原万里さんが、通訳業の中で感じた異文化の「非常識」を綴ったエッセイである。「非常識」という感覚は、その前提に規範化された「常識」がある。常識から逸脱した際に感じる違和を「非常識」と呼んでいるのだが、しかし、異文化という枠の中では、その「常識」がそもそも形を成していない。日本人から感じてみれば素っ頓狂な行動が、実はその国の中で標準的、ということは往々にしてあり得る。そうした非常識さを列挙し、私たちが当然のように感じているアタリマエに「冷や水」を浴びせてみよう、というのが本書の趣旨である。 数々のエピソードのうち私が一番印象に残ったのは、7章「○○のひとつ覚え」での日露米のシンポジウムの話だ。 モスクワでのロシア経済改革に関するシンポジウムの打ち合わせでは、シンポジウムに参加した日本側の学者や専門家は皆英語の優れた理解力を持ち、大多数はロシア語の文献の読解力も持っていた。ロシア側から参加した学者や専門家も皆英語をものし、多数の者が日本語堪能であったという。ところが、アメリカ側からの参加者は、『ジャパンアズナンバーワン』の著者エズラ・ボーゲルを除いて、ロシア語も日本語もかじったことさえない様子なのだった。しかも、それを恥じ入るどころか、他国からの参加者が英語ができて当たり前という態度だった。 筆者はこれを見て、「彼ら(アメリカ側の参加者)は精神的に不幸である」と述べている。 外国語を学ぶということは、単に新しい語彙を増やすだけの作業ではない。その言語が話されている国の文化を学ぶことである。だとすれば、英語の話者はマジョリティであるがゆえに、他国の言語=文化を知ろうとせず、想像力が貧しいままになってしまう。 そして、これは現代の日本にも同じことが言えると思う。日本の文化が発掘され世界での影響力が大きくなるにつれ、日本人は「やっぱり日本の文化が一番面白い」と思うようになり、他国の文化に目を向けなくなっている。これでは、国際語すら学んでいない貧しい民になってしまう。他言語を学ぶ意義を忘れず、日本の娯楽の豊富さに慢心しないようになろう。あらためてそう思える一冊だった。 ――しかし、「国際語」を母語とする国民は、その分外国語を学ぼうとするインセンティブが弱く、実際、かなりの知識層の人々でさえ、外国語を学ばない人が多い。学ぶとしても、同格の「国際語」をかじる。ところが、「国際語」は、前世紀の帝国主義的世界分割にいち早く参加した同じキリスト教文明圏の国々の言語なのだ。地球上の多様な文明を反映するものになっていない。これは、彼らの精神を、とくに異なる発想法や常識に対する想像力を貧しくしている、という意味で不幸でもある。その不幸が彼らだけにとどまっていないのが、もっと大きな不幸である。 ――――――――――――――――――――――――――――― 【メモ】 ・ある国や、ある文化圏で絶対的と思われてきた「正義」や「常識」が、異文化の発想法や価値観の光を当てられた途端に、あるいは時間的経過とともにその文化圏そのものが変容をとげたせいで、もろくも崩れさる現場に何度立ち会ってきたことだろう。一方で人間は常に飽くことなく絶対的価値を求めてやまない動物なのだから困ったものである。 ・時折したたかな商人たちのとんでもない眼のつけどころには心底驚かされてしまう。異文化の人々の中に分け入り、潜在的需要や潜在的供給力を発見する精神の自由で逞しい、それでいて敏感なあり方にほとほと感心させられるのだ。未知のものに対する好奇心と同時に、時代と場所が変わろうとも人間の本質はそう変わるものではない、という人類の普遍性に対する信頼が根底にあるような気がしてならない。 ・どうも気を抜くと、意識という代物は、それも年をとるほどにそうなのだが、ついつい馴染みの可能性に飛びついて、未知の可能性を排除してしまう傾向がある。そして、この人間の意識の保守的特性が、もっとも著しくあらわれるのが言葉なのではないだろうか。 言葉そのものが、そもそも保守的であることを宿命付けられた存在である。われわれが過去だけでなく現在と将来について語るときに用いる言葉は、その語彙も文体も文法も、遠い遠い過去にできたものなのである。だから事物を命名した時点の言語共同体の価値観をいやがおうでも引きずっているのである。 そのうえ言葉は、誕生した遠い過去から現在に至るまでの間に、その言葉の担い手である言語共同体によって蓄積されてきた、その言葉にまつわる諸々の経験に基づくイメージや観念を張り付かせてしまっている。というのも言葉は事物そのものではなく、あくまでも事物を表す記号に過ぎない。だから、われわれは言葉を読み取ったり、聞き取ったりするときに、意識のほうは、その言葉が表そうとする概念やイメージを喚起するようになっている。その喚起されるイメージが習慣化してしまうのである。 ・思えば、この商売を始めて以来、100回以上も崩壊前のソ連邦を訪れている。通訳として、実に様々な思想、信条、党派の人々に同行した。そして面白いことに、共産党系や社会党系の人々の多くは、ソ連を訪れて失望し、自民党系の多くの人々が、「なんだ、それほどひどい国じゃあないではないか」と結構ソ連を見直したりしたのである。奇妙だが、当然といえば当然のパラドックス。 人間の判断が、いかに事前に形成されたイメージに左右されるかを物語る好例ではないだろうか。事前のイメージに縛られて、それを裏切る現象が眼に入らなくなるという弊害もあるが、逆に、事前のイメージとの食い違いが、大きなインパクトとなって、実際以上に印象に刻まれてしまうという傾向を、われわれの心は持っている。 ・どの言語においても、他言語に訳される情報は、その言語によって担われている情報の数百分の、いや数千分の一にも満たない。つまり、ひとつの言語を知るか知らないかによって、その人の情報地図は全く異なる様相を呈すのである。 そのうえ、どの言語も、その言語特有の発想法とか、世界観を内包しているものだ。 英語やフランス語などの「国際語」を母語とする人々は、その言語が「国際語」になっていく背景に、多くの植民地を有していたという血生臭い過去を引きずっているにせよ、その通用範囲が広いという意味で、幸福である。 しかし、「国際語」を母語とする国民は、その分外国語を学ぼうとするインセンティブが弱く、実際、かなりの知識層の人々でさえ、外国語を学ばない人が多い。学ぶとしても、同格の「国際語」をかじる。ところが、「国際語」は、前世紀の帝国主義的世界分割にいち早く参加した同じキリスト教文明圏の国々の言語なのだ。地球上の多様な文明を反映するものになっていない。これは、彼らの精神を、とくに異なる発想法や常識に対する想像力を貧しくしている、という意味で不幸でもある。その不幸が彼らだけにとどまっていないのが、もっと大きな不幸である。 ・どうやら、初級を徹底的に身につけること、これが言語を身につける基本のようだ。ところが、人間の脳味噌にはなるべくサボろうとする機能が自動的に備わっている。あるパターンを新たに習得する労を惜しんで出来合いの類似パターンで間に合わせてしまう機能がオートマチックに作動してしまうのだ。近接する言語の学習においてはこれがしじゅう作動する。主観的にどんなに頑張って抵抗しても、この機能を停止させるのはほとんど無理。自動制御モードになっているから、そのモード自体をプログラムし直さなくては不可能なのだ。そして、その言語との姻戚関係が遠ければ遠いほど、手元に類似パターンがないため、この省力装置は作動しない。つまり、脳はより謙虚にその言語に接し、新鮮な発見をし、その言語を突き放して、根源的に構造的に究明しようとする無意識の意志が生まれやすいのではないのだろうか。要するに、言語間の距離が遠ければ遠いほど、言語間干渉は起こりにくいのである。
33投稿日: 2024.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログロシアを中心とする当時の世界情勢の中で、筆者の価値観や感覚を感じられる一冊。文字が多くやや古い言い回しが多いので読み進めるのは大変だったが、古本屋でたまたま手に取った一冊との出会いもいいものだなと感じた。
0投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログモスクワで「魔法使いの集会」に参加した。 全く魔力もないし占いも当たらない微笑ましきニセモノばかりだったが、筆者だけがロシア語ができたせいか『悪魔と魔女の辞典』という小さな本をくれた。 人間界の常識とは色々逆さの意味になっている。 一例としては(割と知られたフレーズではあるが)「1ダース」を表す数字は、人間界では「12」だが、魔界では「13」だという。 米原万里は、ロシア語の通訳として、異文化の仲介役を仕事としていたから、文化と文化を見比べなくてはならない場面に多く立ち会ってきた。 本書の中では、異端人が別の目で世界を見た時、常識がくつがえる、そんな瞬間が紹介されている。 下ネタ多く公共交通機関の中で読むのは危険だが(笑いが止まらなくなる)、ソ連が崩壊する激動の時期に多くの仕事をして来た筆者の、政治的視点、歴史的視点も真剣に書かれている。 なるほど、戦争がどうしても起こってしまうのは、人間のこういった性(さが)とか業(ごう)のなせる技なのだろうなとも実感した。 「汝の隣人を愛せよ」は、なかなか実行が難しい。 (ちなみに現在、『世界くらべてみれば』というテレビ番組が放送されていて、これがとても面白い) 第1章 文化の差異は価値を生む トルコへ旅行した日本人女性が乗り合わせた、髭面の男性ばかりの「水着女を見に行くツアー」 イスラム圏では、水着はおろか、女性の顔さえも拝めない。 「希少価値」は商売になる。 第2章 言葉が先か概念が先か 言葉を「概念」に直し、それを別の国の「概念」を通してその国の言葉に訳するという手法の自動翻訳機が開発されている。 「概念」は文化によって違うし、その微妙な違いを介して訳すのは無理ではないかと著者は思う。 第3章 言葉の呪縛力 「販売元:福島県」と記載されていたから、産地も福島県だと勝手に思っていたら・・・ 第4章 人類共通の価値 ベトナム語は、鳥の名前には前に必ず「チム」と冠する。 鳩は「チム・ボコ」 あなたも気付かぬうちに、ある国での下ネタを口走っているかも。 第5章 天動説の盲点 大多数の人々にとって、世界は自己や自民族中心に回っている。 相手の身になって考えることには限界がある。 第6章 評価の方程式 期待が大きいと、失望も大きい。 上昇志向の強い人間は、なかなか幸せになりにくい。 第7章 ○○のひとつ覚え ロシア経済改革のシンポジウムに参加した学者たちを見て、 アメリカ側だけがロシア語も日本語もかじったことさえ無い人物ばかりだった。 「国際語」を母国とするアメリカ人は、外国語を学ぼうとしない。 それは、異なる発想法や常識に対する想像力を貧しくしている。 第8章 美味という名の偏見 「星は輝き、花は咲き、イタリア人は歌い、ロシア人は踊る」という名文句があったが、「中国人は料理する」と加えたい。砂漠のど真ん中にあっても、皮から餃子を作る。 第9章 悲劇が喜劇に転じる瞬間 モスクワの空港での、爆買いベトナム人と空港税関職員たちの熾烈な攻防戦。 待たされてイライラしてしまうが、視線をズームアウトして、「木を見て、森を見る」と悲劇が喜劇に転じる。 それは「第三の目」の効用で、昔からの政治の「三権分立」がこれに当たる。 スターリンが失敗したのは、権力を一つに集めたから。 第10章 遠いほど近くなる 外国語を習う場合、近い言語系の人が最初の上達は早いが、いつまで経っても母国語訛りが抜けない。系統が近いゆえ、干渉が起こってしまう。 逆に、全く関係のない言葉の国から来た人の方が、最初こそ苦労するが、最後はきれいに話せるようになる。 第11章 悪女の深情け 振り向いてくれない高嶺の花ほど追いたくなり、女が自分に夢中になってくると飽きてくる、追われるようになると逃げたくなる、そんな男性心理はよく小説にも描かれている。 この心理は男性に限らない。 (「蛙化現象」も似てるかな?) 第12章 人間が残酷になるとき 戦争を防止する最良の手段は、なるべく多くの異なる国の人たちが直接知り合うことだとも思える。 人間は人間を一番愛しているかと問われれば、そんなことはない。 見知らぬ人の訃報より、自分のペットの死の方が悲しい。 また、動物を愛する人は心が優しいなどと言うのも一般的ではなく、600万人ものユダヤ人を死に追いやったヒットラーは犬が大好きだった。 権力者の行う「観念操作」で最も頻繁に用いられるのが、国とか民族への「愛国心」なるもの。 点火しやすくすぐ燃え上がるから「異なるもの」への憎しみを焚き付けやすい。 第13章 強みは弱みともなる 塩野七生氏の歴史観。 ヴェネツィアは、外からの人の受け入れを拒否することで大を為したが、その方針を貫き通したため衰退せざるをえなかった。 古代ローマは、門戸を開いたことで大国となったが、衰退も同じ要因で起こった。 エピローグ 物は考えよう⇒別の視点から見る 異端との出会いこそが、自身の立っている場所を明確にする。 解説 徳永晴美 米原万里の視点は、帰国子女ならではのもの。それも、社会主義国からの再突入による摩擦熱の大きさによる。 それはほとんど、異星人としての体験だったのではなかったか。
2投稿日: 2024.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル買いしたので中身分かってなかったけど、メルヘンじゃなくて辛口だった!でも全然良き裏切りで、ものの考え方がこうも違うし、でも同じところもあることもある、と言うことが面白おかしく時にシビアに読めました。
1投稿日: 2023.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ国際問題に絡んだ話が多め 文字が多く読みにくい部分がちょこちょこあったから斜め読みしたり飛ばし飛ばし読んだ ほ〜!と思う話も多かった 欧米諸国13は不吉な数字 13回や13号を設けない習慣が根付いてる 日本や中国では4 発売元福島、生産地中国の山菜 虫、ゴミたくさん入った状態でドラム缶で買ってそれを取り除いて販売してる この本の作者の米原万里の本初めて読んだけどロシア語の翻訳者なのもすごいし本の内容も頭いい人が書いてる!って感じだった
0投稿日: 2023.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」に次ぐ同著者の二冊目の本。 副題が「正義と常識に水を浴びせる13章」。文化の差異が異なる価値観を産み、異なる文化が異なる言語を産み、美味の評価も変わったり、異文化の交差でそれぞれの文化が際立ったり、また、それが異文化の排斥に繋がったり、文化と言語の違い等で愛国心が芽生えたり、その愛国心を手玉に政治家に馬鹿みたいに騙されたりもする。 文化の多様性の裏表を同時通訳者の著者が下ネタを随所に散りばめながらの実話の数々面白く読みました。 正義と常識は、絶対でないも、それぞれの正義と常識を認め合うことや理解することが大事であり、またその為にも知識や経験を広げることでその一助になるのではないかと思いました。
0投稿日: 2022.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「そういう考え方もできるのか」とか「そんな事情があったのか」など、新たな発見に満ちた一冊だった。 何より、これまでの経験や見聞きした情報から一冊の本にまとめ上げる著者の能力に脱帽。 アメリカに批判的な部分も個人的には好感。
0投稿日: 2021.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログチェコで学生時代を過ご、ロシア語通訳者として働く著者が、世界の様々な文化や考え方の違いと、そんな中でもみんな共通する特性などを面白く書いている。歴史や政治など固めの話や、ゴシップやしもねたなど軽い?話も織り交ぜてあって、楽しく読める。自分や自国の文化を絶対と思わず、何事も相対的でいろんな考え方がある、という大らかなスタンスが好き。
0投稿日: 2019.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア語の通訳を勤めてきた著者が、これまでに体験したさまざまなエピソードを織り交ぜながら、文化の違いが生み出す悲劇と喜劇について考えたことを綴ったエッセイ集です。 ところどころに下ネタもさしはさまれており、けっして身構えて読むような本ではありませんが、文化の相対性について考えるきっかけになるような視点が随所に含まれています。
1投稿日: 2019.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア語通訳者の著者が「所変われば常識も変わる」ということをメインテーマに 様々な具象について語る面白エッセイ。 発刊から20年経っていますが、今もって魅力的です。 通訳という職業柄、異文化のぶつかり合いは日常茶飯事であるでしょうが、 それをここまで上手く論じ、ユーモアをたっぷりからめることができるのは 米原女史の優れた技ではないでしょうか。 職業柄、知人友人からもれ聞く話も大変面白いものが多いのでしょうね。 文化的なお話もたくさんですが、言語学的な話も交えて色々語っていらっしゃいます。 自身の経験を踏まえた、言語取得に関する話が印象的でした。 とっつきやすい似ている言語を取得している者よりも、 (スラブ語圏学習者がロシア語を学ぶ) かえって言語体系が似通っていない学習者の方が (日本語母語の著者がロシア語を学ぶ) 疑問だらけのまま基礎からしっかり取り組むので、 最終的にその言語に精通する可能性があるのではないか、という指摘です。 しかし皆レビューで下ネタ下ネタ言い過ぎやない、と思ってましたが 自分がこの本で一番印象に残ったくだりが 「嘘か本当か、モスクワの一等地に日本大使館を移転しないかと 打診を受けた日本政府が、好条件にも関わらずその話を断った… 何故か?……住所がヤキ××コ通りだったから」 なので、やっぱりそれなりに耐性のある方お読み下さい。
0投稿日: 2019.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ魔女の1ダースは「13」だそうな。 幼少を東欧で過ごし、ロシア語の通訳を生業としていた著者が、いろいろな国の常識の違いについて面白く綴っています。 日本と外国の常識の違いだけでなく、同じ日本の中にも常識の違いが往々にしてあります。育った環境によるものなのでしょう。 頭を柔らかくして、自分の常識に固執しない。いろんな常識を面白く捉えられる余裕を持つことが大事ですね。
0投稿日: 2019.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア語同時通訳者ということは存じ上げていたが、それ以外はさぱりな米原万里さんだったが、ユーモアあふれた気取りのないさっぱりとしたおばさまがいらっしゃった。通訳者として、文化の異なる人と人をつなぐお仕事。中にはとんでもなく不愉快なこともあれば、政治がらみの言うに言えない経験もされたことが文章からにじみでていて、その中でもお披露目できる面白いことを茶目っ気たっぷりに書かれていて、見果てぬ土地に興味を持った。「期待の地平はなるべく低いほうがよい。」
0投稿日: 2019.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア語通訳者としての経験談かと思ったら、テーマはあれど話題は絞らないでどんどんと広がっていくエッセイだった。 政治、経済の話かと思ったら食事情が語られ、言語間を橋渡しする感覚を述べた流れで意図せぬ下ネタ通訳の話になったり。 古今東西大小上下と視点の固定を許さない快作。 そして、めっちゃ中華料理食べたくなる。 脳と思考に不意打ちの刺激をガツガツ与え、ついでに食欲も刺激される不思議な一冊。
0投稿日: 2018.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「常識」というある種の「先入観」に凝り固まった「大人」に思いっきり冷や水を浴びせかける軽妙なエッセイ「13」章。 私たちの「常識」では1ダースといえば12。ところが、魔女の世界では「13」が1ダースなんだそうな。そう、この広い世界には、あなたの常識を超えた別の常識がまだまだあるんです。異文化間の橋渡し役、ロシア語通訳をなりわいとする米原女史が、そんな超・常識の世界への水先案内をつとめるのがこの本。 全編を貫くのは、世の中に絶対というものはないという警鐘。いわゆる常識、先入観、思いこみがどれほど当てにならず誤解のもとになるか。例えば体型に関する意識調査では、80%もの日本人女性が自分の体型に不満という結果が。悲しいかなマスメディアもファッション誌もブティックのマネキン人形も、こぞって八頭身欧米人型体型を「理想」として日本人の脳味噌にインプットし続けた結果だと著者は喝破しています。その考えに触れるだけで、ふっと心が軽くなる。 どんなお偉方も権威も、下ネタも、米原女史の手にかかれば相対的に描かれて唸ります。米原氏が師匠と慕う徳永晴美氏に言わせればそこは「宝石箱と汲み取り式便槽の中身を一挙にブチマケタような、おぞましい知の万華鏡の世界。だが、恐れてはならない」。飛び込めば、実に爽快な世界です。
4投稿日: 2018.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し昔の本ですが、筆者の米原万里さんの魅力的なこと。 ロシア語の同時通訳として活躍された方で、様々な人々が共存していくことへの鋭い洞察力を感じます。 既にお亡くなりとのこと、今の世を見たら、どんなことを語ってくださるのか、聞いてみたいものです。 常識というのは、属する世間での勝利の方程式みたいなもので、世間が変われば、その方程式は通用しなくなるのでしょうね。いつの間にか、それを絶対視してしまうのは、愚かなだけでなく、恐ろしいことだと感じました。
1投稿日: 2018.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読中。自分の常識は世界の非常識、ものの見方が変わる警句にあふれたエッセイ集。あらためて読むと、のちの創作活動の芽というか種のようなものもそこここに。何年たっても変わりない真理ばかりなのでエピソードはなつかしいものでも内容が古びることもなく、定期的に読み返したほうがいい本の一つかもしれない。 ひさびさに読み返して、仮名ででてくる須藤某て佐藤優じゃないの?と思い当たったりもして…
0投稿日: 2017.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ万里さんがトランプがアメリカの政権握っていること知ったら何ていうかなぁ。 各国政治からシモネタ、小咄、守備範囲が広すぎる。 徳永氏のエピローグもさすが万里さんの師匠...男だったとは。
0投稿日: 2017.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ目次からたいへん興味深い。 「無知の傲慢。経験主義の狭量」 メモ 「努力しだいで改善が見込める分野にはどんどん理想パターンを取り入れ、容貌とか年齢とか努力の余地のない分野にはゆめゆめ理想パターンを描かないこと。これが幸せになるコツ。」 「弱みとは、その人間が弱みと思いこんだ時点から弱みとなる」
0投稿日: 2016.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本で暮らしているとどうしても物事を日本人の基準で考えてしまう。そして普段はそのことに気づくこともない。しかし著者のこの本を読むと当たり前だと思っていたことが実は世界の非常識かもしれないことが分かる。特に特に先の大戦についての話で、被害者側の視点に立つことがいかに難しいかを考えさせられる。また先進国の傲慢さの指摘など、メディアが口を噤む話題にも鋭く切り込んでいる。 ソ連などの東側に精通していながら染まらず、相対的に物事を捉える著者の見識は示唆に富んでいる。そして毎回下ネタが上手い(笑)。
0投稿日: 2016.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ文化違えば、立場違えば、考え方次第で、物事の捉え方はこんなにも違う。それを面白がれる余裕があれば人生楽しくなりそう。
0投稿日: 2016.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「相手の気持ちになって考える」はよく聞くが、国際交流には「第三者視点で考える」という事も大切だと分かりました。 『人類の半分の価値』に大爆笑。
0投稿日: 2016.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ同時通訳家であった彼女の言葉のセンスが光る一冊。そのリズムは軽快で、どこまでも言葉は美しい。 いろいろな国のお国事情や小噺がいっぱいで楽しい。イスタンブールの海峡の眺められるホテルのバルコニーなんかで、ビールでも飲みながら読めたらすごく素敵なのにな。
0投稿日: 2016.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ変にアカデミックっぽい分析を加えなくても、おもしろエピソード、エッセイでよかったのではという気がする。
0投稿日: 2016.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ下ネタから高度な異文化理解、マスコミ批判まで、なんとも振れ幅の大きな内容。 とっつきやすい一面、「経験主義の狭量、無知の傲慢」とか、はっとさせられる言葉がたくさんある。 もう二十年も前に出た本だそうだが、今読んでも価値のある一冊ではないだろうか。 グローバリズムの名のもとに、特定の価値観が、無根拠に「常識」化している今、この人がいてくれたら...と思う。
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログマリさんの本を読むと、言葉のセンス、世の中のや人に対する見方にとても感心します。多分彼女の人生経験と読書体験の凄さ、仕事で培ってきたであろう人脈と言葉の感覚、多角的なものの見方・・・もっと話を聞きたい!と思わせてくれます。いくらなんでも魔女の集会に参加した日本人ってそうそういないだろうなあ。 本書は、自分が常識だと思っていることが、場所が変われば非常識、文化や言葉の違いを面白おかしく書いている本です。 個人的には、第7章の「⚪︎⚪︎のひとつ覚え」、第10章の「遠いほど近くなる」が興味深かったです。第3の視点を持つ。面白かった。
0投稿日: 2014.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
少女時代からチェコでロシア語で学んだ経験から、ロシア語通訳になった米原氏の、一見不真面目で実はまじめな比較文化論といえるだろう。海外経験豊富で、異文化や歴史的背景からくるいろいろなエピソードとそれから学ぶものを提示している。著者の偏らない博識には舌を巻く。忘れていた近代世界史・世界勢力地図の復習にもってこいだ。 下ネタが多く、笑える箇所がたくさんある。下ネタは万国共通、コミュニケーションの潤滑油なようだ。個人的に面白いと思った箇所を抽出してみる。 「あくまでも仮説に過ぎないが、美味美食が盛んな国、一般国民が料理に多大な関心をはらい、膨大なエネルギーを費やすのは、封建制度が比較的長く続いた国々である。中国、フランス、イタリア、日本…いずれもそれに当てはまる。そして逆に、一般的に「料理がまずい」といわれている国々、すなわちイギリス、オランダ、スイスなどは、いずれも資本主義が他国に先駆けて芽生え、発展した国々である。」なるほど! また、ロシアの大学や大学院での学位授与の審査が、裁判方式というのも面白いと思った。一般傍聴者の前でオブジェクションを唱える立場がいて、それを論理で打ち負かせないと学位がもらえないという。 将来引用したいと思える小話がちりばめられていて、海外で生活する私にはとても参考になった。"
0投稿日: 2014.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ米原さんと同年齢。同じ時代と世界を生きてきたはずだが、自分の世界の狭さに落胆。のほほんと世界のこともよく知らずに日本で生きてきた。1999年に書かれたものだが、今も同じようなことが繰り返され続いている。正義と常識に冷や水を浴びせられて、みんなシャンとすればいい。
0投稿日: 2014.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014.9.19 am1:21 読了。小説以外で、時間を忘れてのめり込んだのは久しぶり。くすっと笑って、うーむと唸りえーっと声を上げたくなる本書。物事に対する複眼的な見方や、各国の文化的背景などをもとに、ちょくちょく入ってくる下ネタ混じりのジョークがかなり面白かった。様々な分野から引用される本の多さに驚く。読みたい本が鰻登りに増加。どうしてくれる。異文化というとっつきにくいイメージのあるテーマを面白おかしく、かつ明快に記してある。ロシア文学に興味が湧いた。とりあえず何事も体験してみないとわからないということか。「冷や水」たっぷり浴びました。今年私のベストに入ること間違いなし。早くに亡くなったのが本当に悔やまれる。
0投稿日: 2014.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ【本の内容】 私たちの常識では1ダースといえば12。 ところが、魔女の世界では「13」が1ダースなんだそうな。 そう、この広い世界には、あなたの常識を超えた別の常識がまだまだあるんです。 異文化間の橋渡し役、通訳をなりわいとする米原女史が、そんな超・常識の世界への水先案内をつとめるのがこの本です。 大笑いしつつ読むうちに、言葉や文化というものの不思議さ、奥深さがよーくわかりますよ。 [ 目次 ] [ POP ] 人間界では12、でも魔女界では13が1ダース。 常識だと思っていることも、時代や言語や文化が違えば、「経験則絶対化病」にしか過ぎないこともある。 博覧強記の著者に、思い込みをひっくり返される快感がたまらない。 自分を突き放して第三の目で見ることの大切さも身につく。 [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
1投稿日: 2014.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の思考や視点が如何に凝り固まっているかを発見できる.また,様々な国の文化にも触れることができ,異国への興味が湧いてくる. しかしながら,著者の思想と自己顕示が(当然自覚的だろうが)露骨なため,なにやら調味料と油を大量に投入した料理を食べたような気分になることが否めない.
0投稿日: 2014.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ違う文化圏の人たちの同じ言葉や事柄に対する,理解の違いについてのエピソードをちりばめたエッセイ。一つ一つが笑えたり,考えさせられたりして,面白かったです。 普段日本で暮らしていると気づかないことも満載で,日本を相対的にみる視点への入り口になれそうな1冊でした。
0投稿日: 2014.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ同一の事物や現象が、視点を違えるだけで全く別な物に見えてきたり、同一の単語や語句が、文化的歴史的背景や身分階級時代など、置かれた文脈によって思いがけない意味をおびたり....これは何も米原万里さまレベルの通訳だけに言えることではない。
0投稿日: 2013.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ魔女の世界では1ダースが”13”であるように、我々の常識とはいかに狭く不安定な世界でしか通用しないものだと思い知らされる一冊です。ロシア語通訳ならではのエピソードが面白くて腹がよじれます。 九州大学 ニックネーム:山本五朗
0投稿日: 2013.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ頭の回転が速く、仕事に有能であること。 歴史、政治、宗教に理性的で不偏であること。 2つは両立、相関しそうで意外としない。逆相関があるんじゃないか、と思うこともある。
0投稿日: 2013.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルからして真面目な本かと思いましたがそんなことはなかった。 確かにインターナショナルで新たな物の見方は与えてくれるかもしれないが、「正義と常識に冷や水を浴びせる」と豪語するほどのものではない。 米原さんお得意の下ネタが割と幅を利かせているので、苦手な人はご注意。 著者の体験というよりも、見聞きした異文化エピソードをふんだんに盛り込んだ本、という感じ。 なので面白いといえば面白いのだが、通訳業に追い詰められた鬼気迫る感じはなく、客観的なこともあって、少し冗談の切れ味が鈍いような気がする。 もちろん有益で真面目な内容もあるが、純粋に異言語間交流を解説した本としては「不実な美女か貞淑な醜女か」のほうが上だと感じる。 なので、未読な人は先にそちらをオススメする。ただしこちらは内容が抽象的なのでとっつきにくい人もあるかもしれない。
0投稿日: 2013.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログすげーよくわかったw。 別の視点から見ること。そして解説がうまくまとめられていて、これまたすごい(^^)
0投稿日: 2013.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログもともと作家で選んで本を読むことをあまりしないが、米原さんの書く文章に惚れ込んでしまったので、せっせと米原作品を読むことに励んでいる。 通訳の経験がなければ書けない話がてんこ盛りで、あっという間に読了した。
0投稿日: 2013.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ米原万理という人は、不思議な人である。 実にあっけらかんとしているが、 その中に手品師のような仕掛けを作ってある。 チェコスロバキアのプラハで、ソビエト語を学んで、成長した。 1950年生まれというから、ちょうど同じ時代の女性である。 なくなられたのは、実に残念である。 ちょっと、シモネタが多いが、 翻訳の際には、そのようなシモネタが、 知らず知らずに出てくるのだろう。 通訳という仕事をやることによって、 文化の違いをうまくすくい上げる。 悪魔と魔女の辞典から 愛ー相手から無料で利益を引き出すのに、 相手が対価以上のものをこちらから獲得したと錯覚し、 得したと思わせるための呪文の一種。 ただし、呪文を唱える当人の方が錯覚し、 自分の方が損していると思いこむ場合も多い。 「無償の愛」などとわざわざ定語を つけたりすることがあるように、 本来は有償なものと考えられている。 希望ー絶望を味わうための必需品 思いやりー弱者に対しては示さず、 強者に対して示す恭順の印。 謙遜ー自慢したいことを 他人にいわせるための1種の方法 希少価値というなの価値 供給過剰で、いつでも手に入るものの価値を 人間はなかなか認めたがらない。 異文化の人の中に分け入り、 潜在的需要や潜在的供給力を発見する精神の自由で逞しい、 それでいて敏感なあり方にはほとほと感心する。
0投稿日: 2013.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ米原さんのエッセイは素晴らしいので沢山の人に読んでほしい。どうしてもアメリカ視点になってしまう日本人には東欧の視点が必要かもしれない。東欧は共産主義の崩落、その後の民族闘争、国家建設をし、変動を遂げた国。学ぶところが多い。物事に絶対ということはない。絶対だと思われていた正義や常識が、異文化の光にあたれてもろくも崩れ去る様を目撃した米原さんのことばには説得力がある。 オウムがロシアで信者を増やしその後大事件を起こした頃、その頃に書かれた本だけど時間差を感じさせない。オウムに対しての見解も正しいもので安心して読める。 ロシア語の通訳ならではの話に考えさせられた。有識者会議などで英語圏以外の国の人々は母国語以外の語学を学んでいるが、英語圏の国は他言語を学んでいない。通訳が話す内容は要約された内容。数千分の一の内容。やはり相手の言葉を直接理解する方がいいに決まっている。 この本の解説は米原さんが師と仰ぐ徳永晴美さんがされている。この方の文章も面白く、そしてオチもあるなんて。最後まで読み応えのある本だった。 図書館で借りたけど、何回でも読みたいので購入検討。
0投稿日: 2013.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で。 世界各国を比べてみるとこちらが美しい言葉と思っている言葉がどこかの国では下品な言葉だったり、こちらの常識が非常識だったり絶対と言うものは確かに絶対ではないのだなあと言うことがしみじみよくわかります。それを面白おかしく読んでいるうちになるほどなあと思わさせられるのだからたいしたものだと思うのです。それにしても日本人はお国のことをジョークに出来るほど心に余裕のある人が居ないんだなあとつくづく思いました。その辺りエスプリやウィットが無いと言われる原因なんだろうなあ、きっと。 面白かったのですがちょっと尾篭なお話が多いので少し辟易しました。好きな人は好きですよね、こういうネタ。別に上品ぶっているわけではないのですがちょっと多すぎるような気がしました…
0投稿日: 2013.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ博覧強記。古今東西、上から下まで、かた~い話から、やわらか~い話まで。 テンポもよく、間のとり方も面白い。 読みましょう。新たな視点がいくつも加えられるでしょう。
0投稿日: 2012.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログロシアの話を中心に、様々な国の話が出てきて面白い。結構、下ネタ系も多い。電車の中で噴き出してしまって、困った。
0投稿日: 2012.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ロシアは今日も荒れ放題」の解説と本書の解説を比較するととてもおもしろい。著者が師匠と呼んでいる正反対の2人の好対照が楽しめる。
0投稿日: 2012.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ米原万里「魔女の1ダース」読了。面白い。頭の柔軟体操になる。そして彼女の素晴らしい毒舌ぶり。我々が抱く正義や常識をものの見事にぶっ壊していく。解説者さんがおっしゃる通り,まさに彼女の話はおぞましい知の万華鏡。 宇宙飛行士の秋山さんのエピソードは思わず笑った。というか,終始笑いが止まらなかったw
0投稿日: 2012.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「豊か」ということを感じる。知識がひろく、懐が深く。異文化を知り、正義や常識は同一でも不変でもないことを知っていることにも拠るのだろうか。 自分を知るためには、他者を知らなければならないのだな、と反省。
1投稿日: 2012.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ私たちの常識では1ダースといえば12。ところが、魔女の世界では「13」が1ダースなんだそうです。こういう話を皮切りに私たちが日ごろ思っている事を超えた別な常識があることをこの本では教えてくれます。 故米原万里女史のエッセイです。彼女の綴る異文化論は下ネタも交えつつ、物事の本質を鋭くついてくるので、読んでいてアハハハハと笑いながら、最後にはしみじみと『そういうことなのか』とうなづく自分がおりました。 例えばキルギスの中華料理はどれもこれも羊の脂まみれで閉口した米原女史が厨房に講義に行くといきまいたところで、食席をともにしていた大統領最高顧問は腹を抱えて笑いながらキルギスの銀行家と日本の中華料理店に入ったときチャーハンというのはもっとひたひたの脂の中に入っていなければならない、俺が今から厨房に抗議に言ってくる。とまったく同じことを言っていたときのエピソードや、 「ロシアのベトナム人」という箇所では、空港で、たくさんの荷物を持ち込もうとしてロシア兵に後ろから首根っこを捕まれて引きずりまわされるベトナム人がいる中で、その隙間を別のベトナム人がすり抜けようとし、またロシア兵がそれを捕まえるという光景が空港中で繰り広げられ、まるでドリフのコントのような世界になっている中で一人のロシア人がそれを見ながら 「イヤー、ベトナム人ってのは、大したもんだぜ。あれじゃ、アメリカが負けるわけだよなぁ」 とつぶやき、米原女史がまず大笑いをし、それを同行している日本人のスタッフに通訳してあげると、彼らもたちまち笑いの渦に巻き込まれたのだそうです。 こういう状況になっても、それを笑い飛ばせるのは、やはり強さがないとできないことなので、その辺は僕も見入ってしまいました。ここで取り上げているほかにも、言語の習得に関する考察や、彼女が通訳の傍らやっていた添乗員でオペラ劇場でのお話も非常に面白かったので、ぜひ一読をしていただけたら、と思っております。
1投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ常識、先入観を覆す、ってこういうことを言うのかなー、とぼんやり思う。それにしても面白い。興奮し、時には声を出して笑いながら読んだ。ありきたりの日常が少し楽しいものに変わる一冊。
0投稿日: 2012.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の常識を世界の常識と思っちゃいけないということを再認識。目から鱗。でも感情的になっている文章が鼻につく部分があったのでその分☆1個減点した。
0投稿日: 2011.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ異文化との接点。 ロシア語翻訳の第一人者として名高い著者のエッセイ。 世の中を風刺し、その中から何かしらの普遍や本質をかぎ分けようとしている。 シモネタから激しい意見まで、著者のカラーが強いため好き嫌いが分かれるかも。 翻訳を生業としているためか、言語や文化についての言明は面白い。 例えば、概念は液体のようで、それをロシア語という器から日本語という器へと移し変える。という件は納得できる。話す言葉によって性格が変わってくる、というのもその一例だろうか。 そして、異端との出会いが自分自身を自覚し、豊かにしてくれるという件も面白い。 自分らしさは他人との違いから生まれるように思う。それならば、自分を知るために他人を知る、というのは自明のように思える。
0投稿日: 2011.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人バザーで購入。米原万里のエッセイは1冊過去に挑戦。その時はあまり乗れない文章だったのだけれど、このエッセイは共感することも多くてあっという間に読破。
0投稿日: 2011.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ通訳者として日本とロシアの橋渡しにたずさわった著者は、きっと中世における魔女に似ていると感じておられたと思う。グローバルな時代となった現代は、あまりにも安易な物語を必要としている。マスコミや権力から与えられる知識や宣伝を、簡単に真実であると信じてしまう。それに対して、立ち止り、自分自身の感性を見つめ直すために、著者のような発言は貴重でした。十数年前に発行されている本書は、少しもその貴重さを失っていません。
0投稿日: 2011.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこの人の本ピカイチだなぁ。どの話も当たり前だと思っていたことを覆され、新しい視点から人間の本質を見ることができた。あと、本当に世界は広いし知らないことがたくさんだとも気づかされた。シンポジウムに参加した、日本、ロシア、アメリカの学者の話が1番のお気に入り。
1投稿日: 2011.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ米原万里は、東ドイツに向かう飛行機で日本に住む在日北朝鮮人、金氏と隣り合う。WW2後、世界には3つの分断国家が生まれた。南北ベトナム、東西ドイツ、そして、韓国と北朝鮮。「この国(ドイツ)は、お国と運命を同じくする国ですね」と米原万里が言うと、彼は顔を真っ赤にして必死に否定する。ドイツは分断される責任の一端を自らが負っているが、朝鮮半島は違う、と。 米原万里は、「本来引き裂かれるべき責任を負っていたのは、日本だった。ドイツが受けた罰を、日本が逃れたのは、それを朝鮮・韓国に肩代わりさせる結果になったからだ」と金氏が暗に言っているように感じたという。 2003年の冬、私はイタリアのアッシジからナポリへ向かう列車の中で、同じような経験をした。ペルージャ辺りで乗ってきて、列車の一番前の座席に座っていた私に話しかけたのは、30台半ばの韓国人だった。彼女は流暢な日本語を話し、私を自分の席の隣に案内してくれた。京都で大学に通う彼女は、日本に来る前、日本がとても嫌いだった。でも、ある時京都に訪れた彼女は、涙を流した。失われてしまったアジアの文化を、ここまで大切に、日本はpreserveしていてくれた、と。日本を別の視点から見るようになった彼女は、京都の大学に留学するまでになった。日本での生活や、恋人の話をしてくれる彼女だったが、突然戦争の話になると、表情が一変した。日本が大嫌いだった昔を垣間見たような気がするほどだった。 米原万里が、金氏に対して感じたように、彼女も案に同じことを言いたかったのかもしれない。
0投稿日: 2011.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア語通訳者である米原さんによる、常識を覆すエッセイ。 米原さんは通訳者としてさまざまな国を訪れているし、さまざまな人々と交流を持っていて、その経験からご本人が思わず「ほほー」と唸ったエピソードがたくさん載せられている。 常識というのは環境によって作られた幻なんだなあと痛感する1冊。 作中におもしろいなぞなぞがあったので引用します。 『サウジ・アラビアの王子様の一人が日本を訪れ、たまたま目にした車に心底惚れ込んでしまった。 「豪奢で華やかで気品があて威厳がある。これぜ余が捜し求めていた理想の車じゃ」 というわけで、さっそく買い求め、今も国で愛用しているという。たしかに一切の先入観なしにみるならば、王子様の用いた形容詞はこの車を描写するのにピッタリかもしれない。でも、おそらく日本人には、この車を毎日乗り回す気は絶対におこらないだろうと思う。さて、この車は何でしょう。』
0投稿日: 2011.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会にとらわれる常識と非常識について綴られている。 ちょっと難しい部分もあったけどこういう視野を広げさせてくれるエッセイは好き。 モテ猫からみえる日米関係についての話とかなるほどなーと思った。
0投稿日: 2011.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア語通訳者として活躍していた米原万里さんのエッセイ。自分の常識がいかに常識ではないか、ということを異文化コミュニケーションから語る。
0投稿日: 2011.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「終生ヒトのオスは飼わず」を読んだ後、米原万里の本を、さらに2冊続けて読んだ。「パンツの面目 ふんどしの沽券」と、この「魔女の1ダース」。実際、「パンツ..」は、米原万里のパンツ/ふんどしに対する探究心と、題材を求める対象の広さに驚き感心した。しかし、いかんせん、私にはテーマに興味が持てなかったので、楽しんで読んだとは言えない。「魔女の1ダース」は、広く世界を知っていて、通訳をやっている彼女ならではの著書だと思う。私自身も海外で外国人といっしょに仕事をしているので何となく分かるのだけれども、日本で普通に暮らしていれば決して味わえないような、異なった文化や習慣や考え方というものが存在して、それは明らかに違いが分かる場合もあるのだけれども、時に説明のし難い感覚的な違和感みたいな微妙なものもある。後者は本当にどう説明すれば良いのか分からないのだけれども、この本の中で米原は、ぴったりとしたエピソードを引きながら、それを表現できているように感じる。これはなかなかすごいな、と思った次第だ。
0投稿日: 2010.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ真面目な話あり下ネタあり。全編通して笑えてかつ知的好奇心も満たせて自己啓発にもなる。 もっと早くに出会いたかったけど、出会えて良かった米原万里さん。
0投稿日: 2010.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨年、『オリガ~』を読んでからとても気になっていた米原万里さん。 ようやくエッセイを手に取れました。 いや~、面白かったよぅ!!何度吹き出したことか。 そして目からウロコがぽろぽろ落ちました。 さすが、同時通訳者として「ナマの言葉」に触れられてきただけあって、言葉とその背後にある文化・習慣に対するまなざしがとても厳しく温かい。 亡くなられたのが本当に残念です。 本プロで検索したところ、女性の読者が多いように感じましたが、男性とくに米原さんと同年代の方の御感想を聞いてみたい気がしました。 何冊か借りているので、しばらくは米原ワールドにハマることにします。
0投稿日: 2010.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で借りて読了。 ロシア語通訳者の筆者による言葉や文化についてのエッセイ。 読むのに時間がかかった。 というのも、無知ゆえ、自分が知らないことが多過ぎて、「こういうことがあって、それについてこう」のそもそも「こういうこと」について調べたり考えたりしながら読むと少しずつしか読めなかった…。 「日本の日本人」である私には色々とカルチャーショックで興味深い。海外の文化だけでなく、言葉、言語、それ自体についても。 普段気にも留めず頭から信じて行動している事柄が、他国では全く違う視点をもって受け止められるという事実。「事実」ってとこが重要だと思う。 世界は広いのだなぁ。
0投稿日: 2010.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
図書館の本 内容(「BOOK」データベースより) 私たちの常識では1ダースといえば12。ところが、魔女の世界では「13」が1ダースなんだそうな。そう、この広い世界には、あなたの常識を超えた別の常識がまだまだあるんです。異文化間の橋渡し役、通訳をなりわいとする米原女史が、そんな超・常識の世界への水先案内をつとめるのがこの本です。大笑いしつつ読むうちに、言葉や文化というものの不思議さ、奥深さがよーくわかりますよ。 翻訳ものはたくさん読んでいるほうだと思うのですが、ロシア側からの視点で書かれたものはほとんど読んでいなかったんだなぁ、と今更ながらに思うエッセイ。 そうか、最初の印象ね。 チェコとスロバキア、とかチェチェンとかもうちょっと世界情勢を知りたい視点も増えました。
0投稿日: 2010.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者はロシア語同時通訳をやっていらした米原万里さん。 日本、東欧、中国との交流や仕事からの体験を、歴史的、民族的に分かり易く説明。ときに下ネタも混ざっていてとても読み易い。 私がもう少し歴史や戦争に詳しかったらこの本をもっと楽しめたのに、と悔しい。
0投稿日: 2010.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア語通訳第一人者による、異文化論エッセイ。 と書くと堅そうですが、毒舌系で実におもろい! 特にタイムリーに挿入されるロシア小話が最高だw しかも、笑いながら読み進めていくと、時々「ほおーっ」「そうだよな~」と目ウロコな意見に出会うのです。 例えば、 「弱みとは、その人間が弱みと思いこんだ時点から弱みとなる。」 とかね。これはスカルノ元大統領(デヴィ夫人の旦那ね)の逸話から導き出されてる警句なのですが、どんな逸話かは、読んでのお楽しみ♪ 実は、バイオリニスト・エッセイストの鶴我裕子さんが著書内でエッセイの師匠と崇めてらしたので読んでみたのです。 なるほど~崇めたくなるね~。
0投稿日: 2010.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログあたためて、あたためて、かなり時間をかけて読み終えた一作。 いや、決して面白くないからではなくて、書いてあることが興味深くて考え×考えしていたらすっごく時間がかかってしまったのです。。。 マダムの紹介でオリガ・モリソヴナ~を読んで以来、米原女史のエッセイにも手を出し、すっかり虜に。帰国子女であるがゆえの着眼点なのか、読んでいるとそりゃビックリ!の色々な事象に驚きます。 実は読みながら面白い!ところに付箋を貼っていたのですが、多すぎて(爆)紹介しきれなくなりました。 これがスタンダード!だとおもっている事が、実は別の文化によれば全く違っていたりしてとても面白く勉強になります。 難しいことばかりじゃなく、さすが「シモネッタ」の異名をとる米原女史、異文化にわたる下ネタも満載(笑) 楽しみながら様々な文化を知ることができる至極の一冊です。 シ 「ガセネッタ&シモネッタ」も是非とも入手して読まなければ♪ ゆっくりじっくり、心の活力剤に。
0投稿日: 2010.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ【あらすじ】 私たちの常識では1ダースといえば12。ところが、魔女の世界では「13」が1ダースなんだそうな。そう、この広い世界には、あなたの常識を超えた別の常識がまだまだあるんです。異文化間の橋渡し役、通訳をなりわいとする米原女史が、そんな超・常識の世界への水先案内をつとめるのがこの本です。大笑いしつつ読むうちに、言葉や文化というものの不思議さ、奥深さがよーくわかりますよ。 【感想】
0投稿日: 2010.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ついつい馴染みの可能性に飛びついて未知の可能性を排除してしまう傾向がある」 こういうことは当たり前の様であり、 なかなか言い当てることは難しい。 あまりに日常で普通はわかったつもりになって流してしまうから。 こんなにシモネタが多く、 バッサバッサと世間、他国、政府を切り刻むのに 決して下品でなくむしろ爽快な読了感を与えてくれるのは 疑いようもなく著者の暖かい人格と知性のなせる業だ。 点と点が結びついた感動に目頭が熱くなることも 1度や2度ではない。
0投稿日: 2009.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「世間一般の常識では、1ダースの鉛筆は12本だが、魔女の世界では13本」 見慣れた風景の中に異分子が混じることで、見えなかったものが見えてくる。常日頃、当然視している正義や常識に冷や水を浴びせるエッセイ集。 *************************** 米原さんの本は2冊目。 前回同様、知的な話と柔らか〜い話のバランスが絶妙!軽い大爆笑は無いけれど、読み終わったときには数段脳の展開力が早くなっている感じ。誰にでもオススメしたい1冊。
0投稿日: 2009.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、にわか仕込みで佐藤優を読んでいると友人に語ったら、うれしそうな口調でこの本を薦めてくれた。私と違ってロシア文学もちゃんと読んでいる彼のことだから、そうそう詰まらないモノを薦めてくるはずもないが、それにしてもこのエッセイは予想以上だった。米原万里は、幼少期をチェコスロバキアで過ごし、帰国したのちはロシア語の同時通訳者として活躍した。その極めて稀有な経歴から察するに、幾度となく価値観の転換を余儀なくされてきたのだろう。彼女の視座は徹底的に相対化されている。多少の事実誤認があるとか、そういう甘っちょろい指摘では、このエッセイの肝は全く揺るがない。本書との出会いがもっと若いうちだったなら、私の大学生活は少し違ったものになっていただろうな、と思わざるを得ない一冊。ただし、ところどころに覗く彼女自身の政治的スタンスは相対化しながら読む必要がある……かな。尤も、彼女自身は自分の政治スタンスの相対化なんてとっくに済ませてるだろうけれど。☆の数は、いろいろ迷ったけど、5で。
0投稿日: 2009.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ職業柄世界中を飛び回っているので、ある国の常識が他の国の非常識である事を熟知している。そんな著者が世の中の相対性を中心に様々なエピソードをユーモアを交えて語ったエッセイ。 題名は魔女の世界では1ダースは13を意味するという事から取ったもの。 大笑いしつつ読むうちに、言葉や文化というものの不思議さ、奥深さがよーくわかりますよ。
0投稿日: 2008.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこれを読んで、カルチャーショックってどんなものかわかりました。 いろんな角度からの見方があるのだと、改めて気付かされます。
0投稿日: 2008.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ故・米原万里さんのエッセイ。 なんともパワフルであり、あたたかい方だなぁ、と文中の至る所で感じさせられます。 山菜の話・・・強烈だったなぁ(笑
0投稿日: 2008.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア語通訳の仕事をしてる人が、今までの経験にもとづいて文化間の摩擦・誤解・混乱の面白い話を語ってます。経済の重要な会合の通訳を務めてるだけあって、歴史の裏話みたいなのもかなりあった。気がする(w 個人的に中国と他の地域の料理の違いの考察みたいなのが面白かった。こういう"文化の違い"を扱った本は好き。ちょっと文がクドくて読みにくかったけど。
0投稿日: 2008.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログあなたの常識、わたしの非常識。日本の常識、世界の非常識。 異文化交流の経験のある人ならだれでもうなずいてしまうエピソードが満載。 もちろん、米原万里本ならではの下ネタもそこここに…
0投稿日: 2008.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ通訳のお仕事をなさっている米原さん。異文化?エッセイ。 いろいろな小話が載ってるんだけど、ひとつひとつギュッとつまって濃い感じです。 もちろん落ちあり、笑いあり、下ネタまで網羅しております。 世界は広いゼイ☆としみじみ。海外で生活してたい、とは思わないが、絶対海外旅行にいってみせる!今年の野望!!(笑)
0投稿日: 2008.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログやけにオウム事件が出てくるな、と思ったら文庫初版が平成12年。 そこに古さはあるけれど、言われてることは今でも課題として残ってる。 ちょっと下品な例が多いけど、そこも不変な「笑い」なんだろうな…。
0投稿日: 2008.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本では常識でも、他の国では常識ではないことの多さにびっくり。自国の論理を振り回すことの愚かしさがよくわかります。難しい言葉ではなく、ユーモアたっぷりに異文化について書かれていて、納得でした。いろいろ引用したい文章があったのだけど、すっかり忘れてしまった。自分のボケが憎い。もしかしたら、また書き足すかもしれません。
0投稿日: 2007.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア語の通訳者の筆者が見聞きした様々な国のいろんな目線とその違いで起こる出来事をまとめたエッセイ。日本のとある言葉が、違う国ではシモネタになってしまうなどという笑える話から、韓国とドイツを同列化して烈火のごとく韓国人に怒られた、という真面目な話まで、興味深く読めました。自分の中で常識と思っていることは、本当に他の人もそう思っているか?というところに気づかせてくれます。
0投稿日: 2007.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログあまり目にすることのないロシアのジョークをちりばめた米原氏独特のエッセイ集。政治色が強すぎてくどすぎる嫌いがある。
0投稿日: 2007.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログシモネタだと眉をひそめちゃう我々は常識をわきまえた人間だろうか?正義と常識が崩壊した明日は怖いけど、まあうまくやっていける、そういう気楽さも教えてくれる。
0投稿日: 2006.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログシモネタだと眉をひそめちゃう我々は常識をわきまえた人間だろうか?正義と常識が崩壊した明日は怖いけど、まあうまくやっていける、そういう気楽さも教えてくれる。
0投稿日: 2006.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ彼女の本を読むといつも、今住むところに自分がいる意味、というのを考えさせられる。 文化的許容範囲を広げようと言うのは簡単、でも実際は… 精進します。
0投稿日: 2006.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日亡くなった米原万里さんの傑作エッセイ。自分が生まれ育った国の文化と習慣に基く直観がいかに誤謬に満ちたものであるか、そして外国語と外国の文化を学ぶことがいかに楽しく、大切なことであるかを、抱腹絶倒のエピソードで説く、彼女の代表作。
0投稿日: 2006.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ【私たちの常識では1ダースといえば12。ところが、魔女の世界では「13」が1ダースなんだそうな。そう、この広い世界には、あなたの常識を超えた別の常識がまだまだあるんです。異文化間の橋渡し役、通訳をなりわいとする米原女史が、そんな超・常識の世界への水先案内をつとめるのがこの本です。大笑いしつつ読むうちに、言葉や文化というものの不思議さ、奥深さがよーくわかりますよ。】
0投稿日: 2006.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ通訳、という仕事柄見えてきた言葉や文化、常識・・・そんな堅苦しいことは考えずともおもしろく読めます。
0投稿日: 2006.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ米原万里さん、大好きです。世界は自分のモノサシだけでは計れないことがたくさんある。それをわかりやすくおもしろく著されています。
1投稿日: 2005.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いことを、ただ面白いだけですませるのではなく、どこまでも深く深く追って分析してゆくその姿勢が、素晴らしい。常に目からうろこです。いかに自分の目が曇っているかを実感させられます。[2004.10.19]
0投稿日: 2004.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度読んでも、「自文化」のなかでしか通用しないモノの見方・考え方をしている自分に気付かされる。これまで「常識」だと信じてきたのもが、ぐらぐらと揺らぎ、音を立てて崩れ去る衝撃とおかしさを味わいたいなら、是非。私ももっと自分の頭で判断する訓練をしなきゃなー
0投稿日: 2004.10.11
