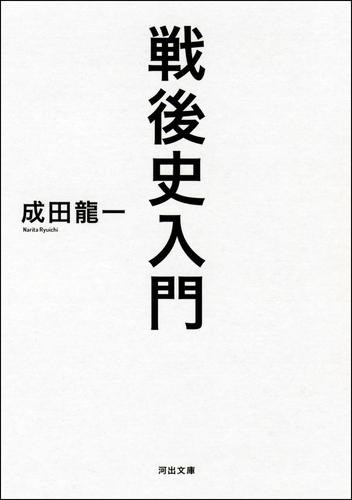
総合評価
(10件)| 1 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ【琉大OPACリンク】 https://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19058233
0投稿日: 2023.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ歴史は歴史と言われるのか、その年代項目は重要とされているのか、そう考えるきっかけになる良書だと思った。
0投稿日: 2021.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログただ学校で習ってきた”歴史”だったけど、私たちは聖徳太子が居る前提で習った。 だが今聖徳太子はいなかったなど私たちが学んだ事とは違う歴史を現代の子は習っている。 どういう事なのか理解できなかった。 だが、この本を読んで日本史は一つではないことがわかる。 その人その人の視点で歴史が変わる。 聖徳太子が居ないと言われ始めたのもそういう事かと思った。 戦後にはとても興味があったが、時代の渦にいた登場人物もたくさん出てきてその度にその時の作品も紹介していて分かりやすく作品も興味が湧く。 中田敦彦が歴史を語るのは難しいとYouTubeで言っていたが確かに年表での出来事だけが歴史ではないため難しいなと感じた。 あとそれぞれの歴史家で語る内容も目線も違うからそりゃ難しいよなと。 改めて感じ方を見直せる作品だった。
0投稿日: 2020.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ若い読者に向けて、戦後の日本の歩みを語りかけた本です。とくに歴史のさまざまな見方があることを、ていねいに解説していることが印象的です。 沖縄や女性、在日コリアンなどの視点によって、一枚岩のように見なされている戦後史が、じつは一定の解釈の視点にもとづいて構築されたものであることを読者に気づかせるような工夫がなされています。映画『ALWAYS 三丁目の夕日』にえがかれた「古き良き時代」の裏で起こっていた事実に目を向けることで相対化を試みるなど、興味深い切り口から歴史について学ぶことの意義を考えさせる入門書だと思います。
0投稿日: 2019.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史とは何か。多面的なものの見方を示す4章以降の女性に視点から、在日朝鮮人の目から、沖縄の目から などが学ぶところ多い。
0投稿日: 2019.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学の学部を選ぶ際に読むべしと息子に紹介された本を親が読む。「歴史とは何か」「歴史は記憶をまとめたもの、まとめ方、まとめた時代によって視点が変わる」「歴史の幅」など当たり前だけど分かり易く丁寧に描かれていて日常的な人間関係にも活用できる考え方。冷戦が終わった1989年。湾岸戦争が1991年から。冷戦終わってすかさず中東問題が浮き出てくる歴史の動きを実感して震える
0投稿日: 2018.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生向けに書かれた戦後史の本。わかりやすいが、最近戦後史(昭和史)に興味を持っているためか、あらかたの知識がすでにあり、新鮮みはなかった。良い復習はできた気がする。
0投稿日: 2017.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学生の時に、二年の研究室に入った時の最初の演習がE・H・カーの「歴史とは何か」を読むことだった。国史をやりたくて落とされて、日本思想史という第二希望でがっかりしているところで読まされたこの本は、日本史についての記述は一行もなくて、歴史的な記述は、その時代や思想によって変わってきている、という言わば「当たり前そうな」事が延々と書かれている退屈な本だった。しかし、曖昧な認識でそうだと思うことと、根拠を持って「当たり前」だと思う事には天地ほどの開きがあるのである。特に昨今のような、ポピュリズムや反知性主義が大手を振るような時代ではなおさらだ。私は歴史書を読むたびに、この本を、この本を選んでくれた指導教授を、ふと思い出す事が多い。 E.H.カーもいろんな言い方で「歴史とは何か」を語っているけれども、成田氏も、教科書ではおざなりにしか書かれていない戦後史の「歴史的事実」を切り取り、何故切り取ったのかを説明して「歴史とは何か」を繰り返し説明する。 高度成長期の集団就職の子供たちを描くのでも、「ALWAYS 三丁目の夕日」の六子の人生よりも、死刑囚永山則夫の人生から説明した方が歴史がよく見えてくる、と著者は説明する。 在日朝鮮人や沖縄の立場から見ると、戦後史はまた違った様相を見せる。沖縄の瀬長亀次郎や阿波根昌鴻の名前は教科書に載らないけれど、沖縄の歴史を語る時には忘れてはならない人たちだと著者はいう。 「事実と事実の結びつけ方、出来事と出来事との説明のしかたこそが歴史なのだ」 若者向きに書かれた本である。しかし若者のみに必要な本というわけでは無い。さらにいえば、この本を読んだあとはぜひともカーの「歴史とは何か」を紐解いて欲しい。 2017年3月7日読了
2投稿日: 2017.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年2015年は、戦後70年のせいか、戦後史をあつかった本をよく目にする。成田さんの本書は2年前に出たものの文庫化である。歴史とは歴史家によって異なるというのはE.Hカーの有名なことばであるが、成田さんは一つではないがなんでもありというわけではないという。それは人々によって共感され、確認されるものでなければいけないのだそうだ。ぼくも昔歴史学を志したことがあったから、これはよくわかる。しかし、最初は事実を集めていけば歴史ができあがると単純に考えた時代もあった。恥ずかしい限りだ。さて、本書でぼくが面白いと思ったのは、やはり書かれることと書かれないことの差である。これは新聞が典型だ。ある出来事についての、各新聞の取り上げ方、採不採はみごとにリアルな現代史となっている。本書から例を拾えば、『ALWAYS 三丁目の夕日』が取り上げられている。ぼくはすべてを見たわけではないが、堀北真希の六ちゃんは覚えているし、昭和を牧歌的にとりあげたという感じはしていた。しかし、そこには60年安保につながる政治の季節や、三池炭鉱の労働争議は描かれていない。六ちゃんは集団就職で田舎から町へやってきて町工場で働き、3作目では結婚までするという幸せな生涯を送っているが、実は当時の集団就職した者のうち半分強が3年以内に転職しているという。歴史はなにを描くかがここには現れている。
0投稿日: 2015.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「戦後」を学ぶには、まずこの一冊から! 占領、55年体制、高度経済成長、バブル、沖縄や在日コリアンから見た戦後、そして今——これだけは知っておきたい重要ポイントがわかる新しい歴史入門。
0投稿日: 2015.07.08
