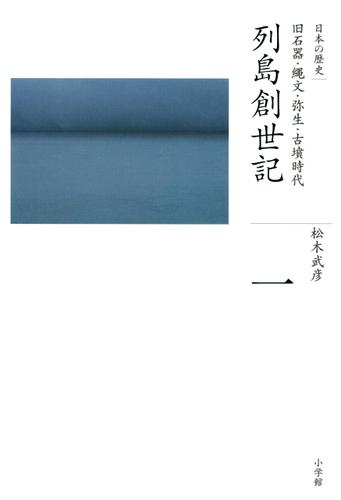
総合評価
(15件)| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・700万年前に猿人が出て、15万年前に新人が出る ・旧石器時代にも農業をする動きはあったが、定着しなかった ・2万年前は寒冷化のどん底。瀬戸内海は陸地となり、日本海は対馬と津軽で外海とつながる内海となった。狩猟・解体・加工に特化したナイフ形石器の登場。 ・1万5000年頃に温暖化していくと、ナウマンゾウやオオツノジカといった大型の動物は消滅。ナイフ形石器から実用性にこだわったフットワーク重視の社会orデザインに拘ったネットワーク重視の社会の登場。 ・結局、縄文時代はネットワーク重視の時代となった。 ・各地域、とりわけ東日本では獲得・加工・貯蔵の技術が個別化。共有された知が目に見える形となって現れる文化となる。物資流通ネットワークが形成される中で、デザインに凝った土器の登場。無文字社会において、デザインこそがアイデンティティーの表明となる。 ・「凝り」は個々人感の差異を助長する方向に働く一方、環状のモニュメントは平等志向。 ・BC3000〜2000年頃、再び寒冷化。これが内からの弥生化と外からの弥生化をもたらす。前者では、集団よりも個々人のイニシアティブが重視されるように。後者は、四大河地域に端を発する、自然と人を支配する文明型文化である。北九州や北海道・東北北部では外からの弥生化が早くから進んだのに対し、中部・関東での進みは遅かった。 ・農耕は人口の増加をもたらす。北九州では資源を巡る争いが増え、人々が互いに寄り合うことでムラ→クニの動き(強い集団が弱い集団を征服していく説に否定的) ・BC300〜100年頃の弥生中期には、温暖化。北九州で大酋長、北海道で副葬のピーク、近畿・東海で環壕集落が大型化。 ・紀元前後から弥生後期、古墳時代にかけて寒冷化。鉄器を取り入れることで、農業生産の衰退に対応。世界的に見るとゲルマンの大移動の時代。 ・鉄を軸とした流通経済のシステムへ。大酋長は遠距離交渉の窓口となる。同列的なムラから、鉄の流通拠点となる大きなムラを頂点に、階層的なクニへ。 ・まとめると、弥生後期にかけての寒冷化でムラからクニへ、石から鉄へ、墳丘墓の出現、青銅器の大型化と消滅。 ・3c半ば、箸墓古墳の登場。鉄を軸とする外部物資の交易圏をめぐり、大酋長同士の利益を調整する人物(=倭王)が共同で擁立される。 ・5c半ば頃には列島の鉄需要が満たされる。倭王や大酋長の権威が低下。古墳の衰退。この支配体制の再編成を経て、律令社会へ。
0投稿日: 2024.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ旧石器時代・縄文時代・弥生時代・古墳時代それぞれにおける、人々の思想的な営みがよく理解できた。本書で扱う原始時代という時代は、文献資料がない時代ということで、古代以降の歴史と比べて当時の人々の理性的・人間的な部分を軽視してしまいがちな時代であると思う。しかし、そこには人間の理性の萌芽ともいえる「文明」が存在していたということを本書を通じて実感した。 原始時代人の理性のどのような部分が、今を生きる現代人と共通しているのかに注目していきたい。
3投稿日: 2021.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この書籍は、日本列島の歴史と言いますが、日本史の創造期の旧石器時代から古墳時代までの長い期間を2007年まで解っている範囲までを解説されています。 未だに謎多き「旧石器時代」。ちょっと解り易くなった「縄文時代」を前後。「弥生時代」も前後。「古墳時代」は全期にして、縄文と弥生は近年の研究で繋がりがあるのでつながるようになっています。
0投稿日: 2019.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
☆縄文遺跡での小グループは出自別ではないかとのこと。古墳の埋葬品から、被埋葬者は神格化されていたとする。
0投稿日: 2018.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本列島の旧石器時代から縄文、弥生時代までを認知考古学という新しい手法で述べた試みである。認知考古学では、当時の人々の考え方から考古資料を読み解く。例えば、縄文時代は平等ではなく競争社会だったが、それを合理化するための儀式として土偶や祭具が使用されたという。
0投稿日: 2017.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ考古学者である著者が、ヒトの確かな足跡が発見される旧石器時代から、巨大古墳が築かれる5世紀までの4万年の日本列島の歴史を文字の記録に頼らず、物質資料のみで描いた大作。 何より新鮮だったのが、歴史科学の再生において「認知科学(ヒューマンサイエンス)」をベースにし、人の心の普遍的特質から人の行動を考古学的に説明しようとした点。文字のない「物質」と「人の心」から読み解く考古学の世界は、自分が想像していた以上に惹かれるものであった。 無文字社会の人、もの、心のあり方とは?そもそも宗教というものはあったのか?日本という国はどうやって形成されていったのか? こういった素朴な疑問に対し、なんらかの新しい発見がきっと見つかるはずである。 架空の存在への信仰、美、芸術に満ちた世界。 5万年前も今も変わらない、人間の本質というものに気づかされる。 <以下引用> 考古学研究者が「画期」「革新」などと呼ぶような変革の多くは、実際には何十年も、何世代もかけて徐々に進んだ小さな変化の積み重ねであることが少なくない。このような小さな変化の積み重ねこそ、歴史が動くメカニズムであり、そこに人類史の本質がある。
0投稿日: 2017.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ文字による記録がほとんどない5世紀までの日本古代史について書かれた本。 文字資料がない、つまり物質資料しかない時代における社会のあり方や人々の心を読み解こうというのが、本書の趣旨となる。認知考古学という学問があるというのを初めて知った。読み物として非常に面白い。まさにこんな本を読みたかった。 たとえば。地球が寒冷化した時期には無個性なツルンとした土器が増える。なぜか?寒くなると食料が得にくくなるため、同じ場所に定住するのが難しくなる。結果、人の移動が増え、文化の交流が生まれる。これが土器の無個性化に繋がった。。。 面白いけど、推理ゲームの感はある。その説の裏づけとなる証拠を見つけるのは難しそうだ。同じ物的資料からでも、研究者ごとにバラバラな結論が出そうな気がする。
0投稿日: 2015.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014.2.10 新しい日本史 非文字社会を解いていく方法が示されている 何度もまとめてくれるので、読みやすい。まだ理解はできていないので、折った部分を読んで整理する必要がある。あとがきを読んでから、再読。 このシリーズは面白そう。
0投稿日: 2014.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ縄文中期の信州・諏訪のあたりがとても気になっている。 当時の日本全体の人口が仮に(通説で)26万人ほどだったとして、諏訪、茅野周辺から関東にかけて多くの縄文人が暮らしていた。縄文銀座のようだったのではないか。 黒曜石の採取地、それと気候、このあたりの謎を解く鍵がある。
0投稿日: 2012.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ松木先生の書く文書はほんとにおもしろいです。 大学入学直前に読んで夢をふくらませた一冊。 しかしいざ発掘・整理作業・卒論等をやっていくと、なんだかこの本のイメージからかけ離れてしまっているのが現状 笑 もう一度読みたい。
0投稿日: 2011.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ旧石器から古墳時代にかけての数万年を一人の著者が述べるという野心的な歴史書。まだ文字をあまり使わない時代であるため歴史の詳しい部分を語ることができないのはもどかしいが、異物や遺跡を通して断片的ながらと応じの状況を垣間見えることができる
0投稿日: 2011.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 四万年の歩みを一気に描く新しい列島史。 [ 目次 ] 第1章 森と草原の狩人―旧石器時代 第2章 海と森の一万年―縄文時代前半 第3章 西へ東へ―縄文時代後半 第4章 崇める人、戦う人―弥生時代前半 第5章 海を越えた交流―弥生時代後半 第6章 石と土の造形―古墳時代 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2010.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ2008.01.11 結構なボリュームで、ところどころ難解だった……。何年か考古学をやってた私ですらそう思うのだから、基礎知識がない人がいきなり読むときついかもしれない。 でも、この本は、これまでにない新しい切り口で書いていて面白い。考古学はどうしてもミクロな視点で物事を考えがちだけど(なにせ、土器の縄文文様の縄目の組み方がどうなってるかが時には重要だったりする)、著者の松木氏は意図的にマクロな視点で見ようとしている。東アジアの中の「列島」という位置づけであって、これまでにありがちな「日本」というくくりでないところに好感を持った。図や写真も豊富で説得力がある。 私が大学で教わった先生や、発掘でお世話になった先生や、卒論で真っ向から反対意見を書かせてもらった他大の先生(笑)等、懐かしい名前がたくさん出てきて、もう随分時間が経ったんだなあと思った(^^; それと自分でも意外だったのは、遺跡の名前とその特徴をまだ自分がしっかり覚えてたこと! 遺跡名が出てくると、ああここは有名な絵画土器が出たところだ、高地性集落の代表例だ、でっかい掘立柱建物が出てる遺跡だ、甕棺が有名だ、水田跡が見つかったところだ、等々……。 もうすっかり考古学からは離れたつもりでいたけれど、根っこのどこかに残ってるんだなあと、少しばかりくすぐったいような気持ちにもなったのでした。
0投稿日: 2010.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ旧石器時代から古墳時代までの約4万年が対象。 当時の気候や土器、墓等の出土品から人々がどのように歩んで行ったかを検証していく。 なによりこの本が特徴的なのが、上記要素に加えて「心の科学」認知科学を用いて既成の解釈に囚われずに、新たなアプローチでこの時代を検証しているところ。 文字による記録がないこの時代のことを、日本列島の形や気候、土器の形状等の証拠と、人間の普遍的な行動を説明している認知科学とを用いて、さながら事件のプロファイリングをしていくように、その時々を推理していく過程はかなり分かりやすく、且つ刺激的だった。 そしてなにより、土器や古墳程度の認識しかなかったのが、本書のおかげで当時を生きていた人々がぐっと人間味が増して身近になった。 そして今後綿々と続いていく日本の歴史の最初のご先祖様としての認識が深まったように思う。 今後のこのシリーズを楽しみさせるに十分の要素をもった第1巻です。
0投稿日: 2008.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の松木武彦さんは1961年生まれ。 つまり、2008年現在段階でまだ47歳。 この若さで『日本の歴史』を執筆するとは、おそれいります。 さて、ページを開くと、まず文字が大きいですね〜(笑)。 少し大きすぎるとも思いますが、これは編集の方針なので仕方ないです。 内容的には結構、斬新で、歴史と気候の変化を絡ませる点は結構参考になりました。 ですが、旧石器〜古墳時代の事象を解くのに「凝り」だけでは、説明が付かないと思います。 そのほかにも、今までの自分の説を白紙にするような言説など、いろいろ問題が多いのですが、考古学が専門に分かれる傾向にある中、一人で旧石器〜古墳時代まで纏め上げることは並大抵の苦労ではなかったと思います。 あと、比較的文章が平易で読みやすいですね。 一般の歴史好きの方には良いのではないでしょうか? 値段も手ごろで購入しやすいしね(・∀・)。 この本を読んで、考古学を好きになる人もいるかもしれません。 というか いてほしいな (*´・д・)(・д・`*)ネー
0投稿日: 2008.01.01
