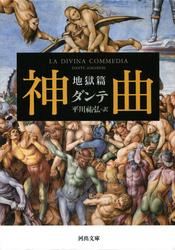
総合評価
(66件)| 20 | ||
| 18 | ||
| 13 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ平川祐弘 訳(河出文庫) 全3巻(地獄・煉獄・天国) - 各巻 約400~450ページ 合計 約1,200~1,300ページ 『神曲』(しんきょく、伊: La Divina Commedia)は、13世紀から14世紀にかけてのイタリアの詩人・政治家、ダンテ・アリギエーリの代表作である。 地獄篇、煉獄篇、天国篇の3部から成る[1]、全14,233行の韻文による長編叙事詩であり、聖なる数「3」を基調とした極めて均整のとれた構成から、しばしばゴシック様式の大聖堂にたとえられる。イタリア文学最大の古典とされ、世界文学史上でも極めて重きをなしている。当時の作品としては珍しく、ラテン語ではなくトスカーナ方言で書かれていることが特徴である。 『神曲』は、 地獄篇 (Inferno) 煉獄篇 (Purgatorio) 天国篇 (Paradiso) の三部から構成されており、各篇はそれぞれ34歌、33歌、33歌の計100歌から成る。このうち地獄篇の最初の第一歌は、これから歌う三界全体の構想をあらわした、いわば総序となっているので、各篇は3の倍数である33歌から構成されていることになる。 イタリア国内 編集 トスカーナ方言で書かれた『神曲』の文体が、現代のイタリア語の基礎となった。方言問題や、俗語と文語について説いたダンテの『俗語論』の影響も大きい。 イタリアにおいてダンテは国民的詩人とされ、イタリア文学の基となるとも言われる。また、高等教育において、全歌、深く突き詰めて学習する。 欧州連合の共通通貨ユーロは、片面に各国ごとの独自デザインがなされているが、イタリアの最高額2ユーロ硬貨には、ダンテの肖像(ラファエロ原画)が採用されている。 数々の芸術作品に『神曲』のイメージが多用された。ミケランジェロは、『神曲』地獄篇に霊感を得て、ヴァティカンのシスティーナ礼拝堂に、大作「最後の審判」の地獄風景を描いている。オーギュスト・ロダンの有名な彫刻「考える人」も、そもそもは地獄篇第三歌より着想された「地獄の門」を構成する群像の一人(恐らくはダンテ自身)として作られたものである。 ボッティチェッリ、ウィリアム・ブレイク、サルバドール・ダリ、ギュスターヴ・ドレら高名な芸術家が、『神曲』の挿絵を描いている。 チャイコフスキーは、『神曲』中の絶唱とされる地獄篇第五歌に歌われた、フランチェスカとパオロの悲恋を題材として、幻想曲『フランチェスカ・ダ・リミニ』を作曲した。 フランツ・リストは、『神曲』の構想をもとに『ダンテ交響曲』を作曲した。ただし、天国を描写するのは不可能ではないか、とのリヒャルト・ワーグナーの意見に従い、煉獄を描いた第2楽章の終結部で天国を象徴する「讃歌」を置くに留めている。ピアノ曲としては『神曲』の地獄篇におけるすさまじい情景を描写した『ソナタ風幻想曲「ダンテを読んで」』(『巡礼の年 第2年』)を作曲している。 ジャコモ・プッチーニの3つの一幕物のオペラ三部作より第3部「ジャンニ・スキッキ」は、『神曲』の地獄篇でほんの数行程度で語られるに過ぎないが、その一節に登場する同名の人物を題材にしている。 1911年、イタリアで Giuseppe de Liguoro 監督によって地獄篇が『L'Inferono』として映画化(無声映画)されている。同映画は2004年にドイツの音楽グループ・タンジェリン・ドリーム(Tangerine Dream) の制作した音楽をのせる企画でDVD『L'Inferono』として発売されている。 ポルトガルの映画監督マノエル・デ・オリヴェイラの映画作品に、精神病院を舞台にした『神曲』 (1991年) がある。聖書やドストエフスキー作品の作中人物になりきった人々が各々の妄想の中に生き、西洋における「罪の意識」を明らかにする。 ボッカッチョはダンテに傾倒し、『神曲』の注釈書やダンテの評伝を残している。のちにはフィレンツェで『神曲』の講義を開いたこともある。彼がもともと『喜劇』と題された作品に『神聖なる』の形容を冠したことから、『神曲』の書名が始まった。また、代表作『デカメロン』は人間模様を赤裸々に描写したことから、『神曲』ならぬ『人曲』とも呼ばれる。 T・S・エリオット、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、ジェイムズ・ジョイス、ヘンリー・W・ロングフェローら世界中の文学者にも影響を及ぼし、ロングフェローのように自ら翻訳を発表した者もいる。 ドイツの古典主義作家ゲーテの代表作『ファウスト』の世界観も『神曲』の影響を色濃く受けているといわれている。また、『ファウスト第2部』第1幕における主人公ファウストの独白部分は『神曲』と同じTerzineの韻律であり、ゲーテが『神曲』を意識して書いたことが見てとれる。しかしゲーテ自身は1826年にダンテについての小論を書いているが、「ダンテの地獄に生える青カビを諸君の世界から遠くに追い払い、澄み切った泉に恵まれたる天性と勤勉を招け」と批判しており、偉大さは理解しつつも限定的な評価を下している。[7] アレクサンドル・デュマは『モンテ・クリスト伯』の主人公の名字をダンテスにしたが、これはダンテに由来するとされる。また、当時『神曲』の特に地獄篇がフランスで流行っていた (Wordsworth Classics 版モンテ・クリスト伯より)。 夏目漱石は、短編『倫敦塔』で、貴人が幽閉され消えていった倫敦塔と重ねて、地獄の門に刻まれた銘を引用している。 大江健三郎は中期の作品である『懐かしい年への手紙』において故郷でダンテの研究を行う”ギー兄さん”を登場人物としている。またこのギー兄さんについて大江は「自分がそう生きるべきだった理想像」として語っている[8]。 中原中也は『神曲』を愛読しており、彼の詩に『神曲』の影響を見て取る者もいる。 大西巨人の代表作『神聖喜劇』の題は『神曲』の原題を意識した命名。また、オノレ・ド・バルザックは、自らの作品集を『人間喜劇』(La Comédie humaine)と名づけたが、これもダンテの“神聖喜劇”に対するもの。 アニメーション映画監督の宮崎駿は『神曲』をオマージュした、『君たちはどう生きるか』を制作した。 BBC Radio4が実施した世界の名著ランキングでシェイクスピア、トルストイをおさえて1位を獲得。[要出典] ジャン=リュック・ゴダールの映画作品「アワーミュージック」の構成は、『神曲』に倣い地獄、煉獄、天国の3部構成をとっている。 アメリカの作曲家R.W.スミスが作曲した吹奏楽曲『神曲』 (The Divine Comedy) は、地獄編、煉獄編、昇天、天国編の4楽章にて構成されている。概ね原典の構成に沿って作曲されており、現代的な作曲手法を取り入れながら聴き手にも伝わりやすい内容となっている。 アレクサンドル・ソルジェニーツィンの『煉獄の中で』(原題は『第一圏の中で』)は、舞台となった合同国家政治局 (OGPU) 管轄の特殊研究収容所をリンボになぞらえて名付けられた。 イタリアの音楽グループ・メタモルフォシは『神曲』に想を得た『Inferno』と『Paradiso』という組曲を発表している。 エンターテインメント 編集 トマス・ハリスの著による『ハンニバル』シリーズの登場人物であるハンニバル・レクターも、ダンテに対して類稀な興味を寄せる。 アメリカの作家マシュー・パールは、19世紀アメリカを舞台として、ダンテの地獄篇に描かれた劫罰を再現したかのような殺人事件を描いた推理小説『ダンテ・クラブ』を著している。 山田正紀のミステリ『神曲法廷』、山田風太郎の『神曲崩壊』、ラリー・ニーヴン & ジェリー・パーネルの SF 『インフェルノ―SF地獄篇』など、数々の小説の題材となった。 永井豪のバイオレンス漫画『魔王ダンテ』『デビルマン』などの世界観は、彼が幼少期に読んだ子供向けの『ダンテの神曲物語』の影響を受けたものである。この本に掲載されたギュスターヴ・ドレの挿絵に衝撃を受けたという。また、永井は『神曲』三篇を漫画化している。 車田正美の漫画『聖闘士星矢』冥王ハーデス冥界編の舞台はダンテの地獄をほぼそのままなぞっており、独自の解釈による地獄の情景が描かれている。 コーエーの『魂の門 ダンテ-神曲』 07th Expansionのゲーム『うみねこのなく頃に』のストーリーや主要人物の一部のモチーフとなっている。 CAPCOMのデビルメイクライシリーズに登場するキャラクター名の一部が、神曲を元に名付けられている。 「ダンテは、これからの苦難の多い地獄めぐりをするだけの力が、自分にあるかどうかに、危惧をもっている。ウェルギリウスは彼を元気づけて、自分がここへ来たのは、地獄の辺獄から、天上の三人の淑女――聖マリアと聖ルチーアとベアトリーチェの頼みで、ダンテの危急を救うために遣わされたからだという。そのいきさつをきいて、ダンテは決然として師にしたがって苛烈な道にわけ入ることになる。時は四月八日の聖金曜日の暮れがたである。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 ダンテ・アリギエーリ(イタリア) ルネサンスの先駆けとも言われる詩人、哲学者、政治家 叙事詩『神曲(ラ・ディヴィナ・コレディア)』は「地獄篇」「煉獄篇」「天国篇」から成る代表作 ロダンは神曲に着想を得て『地獄の門』を創り、門上のかの「考える人」はダンテという説もある 前提はダンテの『神曲』の地獄編で、地獄に落ちた者たちを上から見ている審判官が「考える人」なんだけど、 背景や前提条件をいっさい切り取って全く同じものを借りてきて、人が考えてる様を作品にしたんだとさ。 同じ事実(作品)を見ても、意味ってガラっと変わるんだね。 ダンテの神曲はオッサンがオッサンに導かれて地獄と煉獄と天国を旅する大古典だ。 ダンテ 神曲 地獄篇 ダンテは、現世は地獄であり 地獄にも階層がある。 私達は、現世は地獄であり、地獄の中を生きていると考えたら、私自身スッキリとした気持ちに。 この世は地獄。 だからこそ、体当たりで生きなきゃ。 「〔水がひいて〕大地のように固くなった川をよぎって、この賢者たちといっしょに 七つの門〔七という数字は神秘的な数字として、よく使われる〕をくぐり、緑したたる曠野へ わたしはたどりついた。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 今日の雑学 考える人っていう像を知ってるかな? トイレで寛いでるポーズの人だね あれはオーギュストロダンがダンテの「神曲」という叙事詩の地獄篇(煉獄篇、天国篇の三部作)に着想を得て作った「地獄の門」という像の一部で「地獄の門の上で熟考するダンテを表そうとしたもの」という説があるよ 「ダンテが意識をとりもどしたところは、第三の圏谷だ。そこは貪食の徒のいるところで、彼らは滝のように降るよごれた雨と雹にたたかれて、ケルベロスという怪物にさいなまれている。ダンテはここで、陽気なフィレンツェ人のチャッコに呼びとめられる。そして、地獄の魂たちのもつ将来を予見する力によって、チャッコから、フィレンツェの黒党・白党の運命を知り、ダンテ自身の追放のことも予言される。その男から、最近死んだファリナータなどのフィレンツェの名士たちが、その地獄の下層で罪の重い魂といることを教えられる。ダンテは師と、第四の圏谷へ下りていく。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 https://a.co/ekbm4Uo 1304~21【ダンテが「神曲」を著す】 フィレンツェの詩人。地獄篇、煉獄篇、天国篇の3部から成る黙示録的幻想長編叙事詩。ヴェルギリウス他古今の実在人物が多数登場。文語のラテン語ではなく口語のトスカーナ方言で書かれた。世界の文学・芸術に多大な影響。 #購入本 『神曲【完全版】』ダンテ 個人的に死ぬまでに読みたい未読の古典ベスト3のうち1冊をついにお迎え ボルヘスが「最高峰の連なり」と表現した『神曲』 悩んだ末にドレの挿画完全収録の河出書房さんの完全版を 次の夜な夜な読書の1冊にしようかなぁ イタリアの生んだ最高の詩人ダンテが14世紀に著した『神曲』は、キリスト教文学の最高峰とされる叙事詩です。東海大学准教授の原基晶さんが、地獄篇、煉獄編、天国編を各回ごと解説するオンライン講座が開講します。 ダンテの神曲の「地獄編」を読むと、地獄に落ちるのは「悪いことをした人」じゃないんです。地獄に落ちるのは「ただボンヤリと生きちゃった人」なんですね。ダンテからすると、それは積極的に悪事をなすよりもっと悪いことだ、というんです。放っておいてくれ、と言いたくもなりますけどね。 「神曲 地獄篇」 ダンテ=アリギエーリ著 中世イタリア詩人 TIME誌で世界文学史上最高傑作に戴く 全ルネサンスの嚆矢 驚異の想像力で地獄を組み立てる イスラムでは悪書 西洋では聖書に次ぐ聖典 案内役はヴェルギリウス ダンテの偏見で地獄に送られたムハンマドやブルートゥスが荼毘を纏い糞の河に沈む 今週末「キリスト教」をテーマにした読書会に参加するにあたってダンテの『神曲』の地獄篇を読了したが、キリスト教やそもそもの世界史の基礎知識に乏しい事を再確認。 ロダンの地獄の門はダンテの神曲が元ネタです。 当時のキリスト教の「地獄」は、意外にも具体化されていなかったそうです。ダンテの詩の内容が地獄のイメージを具体化したんです。 西洋の名作にはダンテの詩の影響が見られるものが多くあります! 「二人が門の外にいる間、地獄の三人の復讐の女神が塔の上にあらわれて、メドーゥサを呼ぶといっておどす。師はダンテの目をふさいだ。ほどなく、天上の使いが沼をわたってあらわれ、その命令でディーテの城門は開かれて二人は門を入るが、そこにはいたるところに墓があって焔を噴きあげている。そのなかでは異端異教の者が、その派ごとに埋められて焼かれている。そこは第六の圏谷である。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 ダンテの神曲を軽く読んだ。神曲ってダンテの境遇話だったのかという発見と、ベアトリーチェのことがとにかく大好きで大切であるがとても伝わってきた。今度は別の方の訳文の神曲が読んでみたい 大学生の夏休みが暇すぎて、ダンテの『神曲』を読んで過ごしたことを思いだす。ほかに読んだのは『グイン・サーガ』。あんな長い休みは二度と訪れないので、いつもなら読めない超長編シリーズをもっと読破しておけばよかった。『ローダン』はぜったいあの時に読むべきだったなあ 「「うしろを向いて 目をつむるのだ。ゴルゴン〔メドゥーサの首〕があらわれて目にふれようものなら、おまえは絶対に地上へはもどれないだろう」こういって師は、自分でわたしにうしろを向かせ、わたしの手だけでなく、そのうえに、自分の手でわたしの目をおおい隠してくれた。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 「また人は、こころに神を否定し 譏り、自然にさからって〔同性愛、男色など不自然なことをして〕神の善意をあなどれば、神に暴力をはたらかすことになる。だからこそ、〔第三の〕いちばん狭い環のなかには、ソドマ〔男色者〕、カオルサ〔高利貸〕、それに心に神をあなどって口で涜す者どもを、神の印で封じこめてあるのだ。人をだませば良心の呵責をうけるものだが、」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 「そこでだ、〔城内の〕第二の圏谷〔第八圏にあたるマーレボルジェ〕に巣くうている者は、偽善者、おべっか使い、魔術師、まじない師、うそつき、大泥棒、聖物売り、女をとりもつ者、涜職者、その他の 同じように汚れた奴らばかりだ。そこで、さきの〔人をだます〕場合では、人は、本性となる愛と あとから加わって特別な信頼をめばえさす愛とを おろそかにするものだ。(六三)」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 「第七の圏谷にいよいよ入るのだが、そこには生前に暴力をふるった魂たちがいる。嶮しい崖を下りると、牛頭人身のミノタウロスがいたが、その憤怒のすきにダンテたちは岩のくずれた間を駆け下りる。崖の下には、広い濠が平野を輪のようにとり巻いていて、暴君どもが赤い血の川で熱湯攻めにあっている。ウェルギリウスは、そこの半人半馬の群れのなかのネッソスという一頭に案内してもらって、その煮えたぎる川岸へダンテをみちびく。世にときめいた暴君どもが、そこでひどい責苦をうけている。第七の圏谷の最初の環でのことである。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 https://a.co/dnklL1r 「第十三歌ダンテは第七の圏谷のなかの第二の環に入る。そこには自分の肉体に暴力を加えた自殺者と、自分の財産を湯水のように蕩尽した浪費者がいる。自殺者は節くれだった棘のある樹に変わり、凄惨な自殺者の森となって、怪鳥ハルピュイアイが棲んでいる。浪費者は茨のなかを駆けまわり、牝犬に追われてからだを引き裂かれている。樹が物をいい、枝を折れば血がでてきて、ダンテの象徴的な手法が、怪奇なまでに陰惨なイメージをただよわす。それぞれにその身の上を物語るが、フィレンツェのひとりの市民は府の不吉な将来を予言する。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 https://a.co/6BmuKp6 「第九の圏谷へ向かおうとすると、するどい角笛のひびきが高らかに鳴った。その昼とも夜ともつかぬ無明のなかで、ダンテは塔のようなものが屹立しているのを見た。そのくらがりに立っているのは、実はその圏谷の坎に突っ立っている巨人たちで、腰から下は坎の中にあって、鎖で手や胸をきびしくゆわかれている。その巨人のひとりで、手をゆわかれていない巨人アンテオが、師とダンテを坎の底に下ろしてくれる。すでに、地獄もせばまっていて、さいはての地底に近づいている。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 叙事詩の特徴 •神や英雄、国家の運命といった壮大な主題 •詩の形式で綴られる(韻律、比喩、定型句が多用される) •文化のアイデンティティや歴史観を強く反映 「第九の圏谷は、コキュトスという堅い氷の獄で、罪の魂たちが氷づめになっている。四つの環嚢になっていて、ここではそのうちの、肉親を裏切った者の墜ちる第一の円カイーナと、国や府に弓をひいた者の墜ちる第二円アンテノーラとの出来事が扱われている。第一円では、ダンテはカミシオン・デ・パッツィから氷づめの魂たちのことをきいた。第二円では、ダンテは氷づめになった頭につまずくが、それがフィレンツェ軍を裏切ったアバーティとわかる。とくに、ある坎ではひとりの男が相手に食らいついたまま氷漬けになってるのを見るが、そこにまで憎悪を曳きずっているのは、ウゴリーノ伯とルッジェーリ大司教のいきさつがあるからである。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 https://a.co/86nTj3J 「第九の圏谷のどんづまりの第四の円は、地獄の底で、地球の中心点だからひどく狭い。ユダの国ジュデッカと呼ばれて、恩義ある人を裏切った者が、全身さかさまになって氷づめにされている。その中心に怪物ルチフェロが、三つの顔と六枚の翼をもって、口々に罪人をくわえて噛みくだき、風をまき起こしている。キリストを裏切ったユダと、カエサルを裏切ったブルートゥスとカシウスが食われている。ダンテは師の首にしがみついて、怪物の脇腹の毛をつたって、頭と足の位置をさかさまにして下りていく。地球の中心だからそうしたので、北半球から南半球にでたことになる。その暗い孔をのぼって、南半球のそとにでて、ふたたび天上の星を仰ぐ。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 「ダンテの家系であるアリギエーリ家については、ダンテがその四代前の先祖にあたるカッチャグイーダがイスラム教徒とたたかって戦死したことを『神曲』の「天国」(十五歌、十六歌)のなかで述べているだけで、くわしいことはわからない。しかし、家紋がのこっていたことからみても、名門というほどではなくても、貴族の家柄だったことはたしかだ。あるいは武将の家だったかもしれない。父の職業は公証人ともいい、あきらかでないが、いくらかの不動産収入のほかに、金融のようなことで生活を立てていたらしい。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 https://a.co/5J1dOc7 「一三〇〇年、ダンテは他の五名とともに、フィレンツェ市のプリオーレ(統領)の一人に選ばれる。ダンテが、フィレンツェ市の内紛を調停するために、法王がシャルル・ドゥ・ヴァロア軍をフィレンツェヘさし向けようとする意図をさとって、法王に謁見するため使節としてローマヘ赴いたのが一三〇一年だが、この年にヴァロア軍はフィレンツェに入り、黒党のクーデターにあって、彼はローマに滞留しなけれぱならなかった。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 「ダンテの思想は反教会的か ここで、こういうフィレンツェという社会を背景として、ダンテの思想的な問題を考えてみたい。すでにその府では、商工業の繁栄で、唯物的な主知的な思想がたかまっていたらしい。それには、一三〇九年に法王クレメンス五世が法王庁をフランスのアヴィニョンへ移したのがもとで、それのローマ復帰問題がおこっていて、法王がフランスとイタリアで並立するという騒ぎになっていて、教会の権威が地におちたことも、底流になっている。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 「そこでは、ダンテを「彼は教会の子だが、反法王庁の思想家だ」という妙な論理で推す人もいた。これが後の、アルビ派やフリーメーソン、宗教改革運動者、ひろい意味のプロテスタントが、ダンテを同志とし先覚者として見ることになるのである。 しからば、ダンテははたして反教会的であったのか。さいわいにして、スカルタッツィーニが、その問題について、「べつのことだが同じこと」というエッセイで論じている。ダンテは教会から離れたようでも、信仰の点では同じだといっているのだ。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 「このことは、いまではアナクロニズムとして一顧もされないことだ。それは、ダンテが信仰のあついカトリックだったか、また全霊を教会に捧げていたのか、もしくは、それに敵対する立場にいたのかという問題である。それが、秘密結社のメンバーとして、アルビ派、フリーメーソン、社会主義者などとして、彼に烙印を押す人の夢をもってすることは、我々のとりあげる問題ではない。問題として、より重要なことは、ダンテの深い魂のなかでは、ローマ教会の組織、その良心的、非良心的な改革者と相争っていたのではないか、ということである。このことは、とくにプロテスタントの神学者によって、しばしば想像されてきたことである。その人たちはのちの十六世紀の宗教改革運動の基本理念を擁護した人たちである。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 https://a.co/4oEyKUp 「十九世紀のヨーロッパにおける国民主義の運動は、『神曲』をロマン主義的に読むことを教えた。ドイツを主とする国民的民族的な伝統文化の再吟味につれて、ドイツの学者は、ダンテの仕事にイタリア的な範疇を越えた、ひろい人間的な価値を認めて、古語の分析と資料の発掘を手がかりに、実証的に『神曲』を研究しはじめた。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 「一九三〇年以後は、ダンテ研究は解釈学の全盛で、それも文学の実証性を追求する手がかりとして、証明として、ダンテをとりあげている。エリオット、ファガーソン、アウエルバッハ、セイアなどが、それを代表している。 ダンテ評価の流れを歴史的に見ると、近代までは写本の収集とその校訂などの文献的書誌的研究が主で、十九世紀末から本文批評の実証的研究と、分科的証明を与えるための科学研究に入った。現代では、ダンテの創作体験に立つ認識といい、部とテーマによる構造的なつかみ方といい、より実在的に深まる一方、現代の人間性の証人としてダンテをとりあげるなど、その評価の意味と方向はこれまでとは変わっている。 しかし、七世紀にわたる評価の対象として、ダンテの著作は、全人類の世界性をもった永遠の文化財として、いまなお無限の傾域を残していることはいうまでもない。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 https://a.co/1x5g8kf 「ダンテが地獄をあまり正確に描きすぎたので、古くから注疏者の間で、その距離や大きさなどが計算されている。それによると、地獄の穴の深さは、三二五〇マイルと計算されている。それはダンテが『饗宴』のなかで、地球の直径を六五〇〇マイルと算定しているから、その半分は三二五〇マイルとなる。しかし、この地獄の空洞は地殻で蓋をせられているが、エルサレムとフィレンツェの間を地底の中心から四五度の角度とすると、地表にもっとも近い地獄前庭の周囲は一万マイルとなり、かりに前庭を入れて圏谷を十の等分のものとして計算すると、フィレンツェから地軸までの地球の半径までの圏谷の周囲は、平均して三二五マイルということになっている。もちろん広狭の差はひどいが、だいたい地獄の幅の見当はつく。〔シュナイダーの『神曲釈義上巻』〕したがって、下の方のマーレボルジェ(悪の環嚢)になると、ずっと狭くなって、ウェルギリウスは周囲を二二マイルだといっている。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 「第一圏谷〔辺獄〕 罪はないが神を敬わない者、洗礼をうけない者。第二圏谷 好色者の獄第三圏谷 貪食する者の獄第四圏谷 吝薔者と浪費者の獄第五圏谷 激怒者と怠惰者の獄第六圏谷 異教徒の獄第七圏谷 暴力を加えた者の獄 第一円 近親者に対する暴力者 第二円 自己に加えた暴力者 第三円 紳に対する暴力者第八圏谷 欺瞞者の獄 第一嚢 人を誘惑した者 第二嚢 阿諛へつらいをした者 第三嚢 聖職聖物を売買した者 第四嚢 占い師 第五嚢 詐欺をした者 第六嚢 偽善者 第七嚢 偸盗 第八嚢 欺瞞をそそのかした者 第九嚢 不和の種をまいた者 第十嚢 貨幣偽造者第九圏谷 裏切者の獄 第一円(カイナ) 近親を裏切った者 第二円(アンテノーラ) 祖国を裏切った者 第三円(トロメア) 客人を裏切った者 第四円(ジュデッカ) 主を裏切った者地の中心 堕天使の魔王ルチフェロ」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 https://a.co/1iPMzlQ 「一九三〇年以後は、ダンテ研究は解釈学の全盛で、それも文学の実証性を追求する手がかりとして、証明として、ダンテをとりあげている。エリオット、ファガーソン、アウエルバッハ、セイアなどが、それを代表している。 ダンテ評価の流れを歴史的に見ると、近代までは写本の収集とその校訂などの文献的書誌的研究が主で、十九世紀末から本文批評の実証的研究と、分科的証明を与えるための科学研究に入った。現代では、ダンテの創作体験に立つ認識といい、部とテーマによる構造的なつかみ方といい、より実在的に深まる一方、現代の人間性の証人としてダンテをとりあげるなど、その評価の意味と方向はこれまでとは変わっている。 しかし、七世紀にわたる評価の対象として、ダンテの著作は、全人類の世界性をもった永遠の文化財として、いまなお無限の傾域を残していることはいうまでもない。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著 https://a.co/1x5g8kf 「こういうわけで、ダンテが地獄にいたのは正味二日で、オーア夫人はその正確な時間を、ダンテの詩にある星の位置から計算して割りだしている。もっとも、彼女によるとダンテが地獄に入ったのは、天文学的には四月八日でなくて、三月二十五日だと論証して、ムーアの説を否定しており、天体のあり方から、その年も一三〇〇年ではなくて、一三〇一年だともいう。そう主張するだけの科学的な十分な根拠がある。」 —『神曲・地獄篇』ダンテ・アルギエーリ著
0投稿日: 2025.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
地獄に住む魂たちの中にも、ダンテが共感や尊敬を抱いている人物たちが、幾人か登場します。 第5歌のパオロとフランチェスカ、第10歌のファリナータ、第15歌のブルネット、第26歌のオデュセウス、等。 そして誰より、ダンテを導いてくれる準主役のウェルギリウスがそうです。 彼らが当時のキリスト教会の価値観では、天国に行けないという事に、必ずしもダンテは納得してなかったのではないでしょうか。 ウェルギリウスは、天国に座を占めるベアトリーチェから頼まれて、ダンテを救済することになりました。 しかし、地獄にいる魂は、神に見棄てられ、天国からその存在自体を完全否定されている者たちです。 キリスト来臨という例外は有りましたが。 ですから、ダンテを救済するために、地獄の住人にそれを依頼することなど、本来はあり得ないでしょう。 それでもウェルギリウスは、こうして天国のベアトリーチェと接点を持ち、地獄のみならず煉獄をも旅をし、地上楽園までたどり着いています。 『神曲』全体の約3分の2の間ダンテを導き、「天国篇」の導き手であるベアトリーチェの約2倍の出番が、ウェルギリウスに与えられているのです。 こういったところに、ダンテなりの、当時のキリスト教会の偏狭さに対する、アンチテーゼが込められている気がします。 つまり、キリスト教会の定義を越えて、ウェルギリウスたちをも神の愛は包み込んでいる、というダンテの願いが見出だせる気がするのです。 以上はあくまで私の、推察とすら言えない、妄想にすぎません。 ですが『神曲 地獄篇』には、直接には表現できなかったダンテの本当の想いが、比喩的に描写されていると思っています。
0投稿日: 2025.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログずーっと読みたかったもの。難解なのかなと思っていたけれど、翻訳が良いのか面白い読み物として読めた。(叙事詩なので小説扱いではないと思う)続きがとても気になる。地獄は七つの大罪に関するもの。
0投稿日: 2024.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
私が『神曲』を初めて読んだのは大学三年生の頃でした。今から10年以上も前です。ですがこの地獄の最下層の氷漬けの世界を初めて目にした時の衝撃は今でも忘れられません。 「キリスト教の地獄の一番底は氷の世界なのか!仏教と真逆じゃないか!」と私は仰天したのです。
0投稿日: 2024.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ何回も挫折しながら半年くらい時間掛かって読み終わった。それでもこの本の面白さの全てをわかった気が全くしない。絶対リベンジする。
0投稿日: 2023.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的に思うこの本のすごいところは映像がありありと目に浮かんでくるところ。描写が丁寧で細かい作品は数あれどここまで映像的にみせれるのはこの作品以外しらない。アンソニー・ドーアのシェル・コレクターという作品も情景の描写がとても上手だったな
0投稿日: 2023.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ『神曲』である。『神曲』といえば『神曲』なのであって、傑作の誉れ高いということは、十代の頃から知っている。 で。岩波文庫である。上巻だけ買うと挫折しても「数百円だから、ま、いっか」となりやすく、それでは最初から挫折するために買うようなものだから、上中下巻をまとめ買いしたわけだ。奥付には1988年発行とあるから、小生22歳くらいである。そして予想どおり、上巻の十数ページで挫折すること数度。 その間、30年以上、古本屋行きの段ボール箱に入れては「ううむ。やっぱ、とっておこう。いずれ読めるかもしれないし」と、往生際悪く箱から取り出すということを何度やったことか。 で、今回。 数年前に逝った父の本棚に河出文庫版があったのを発見、パラパラめくって「こりゃ読めそうだ」と思って持ってきた。ちなみに親父は一度も開いていないらしく、ページをめくるとパリパリ音がする。アマゾンでポチったものの、おそらく読んでいないと思われる。さすがは親子である。 それはさておき、ようやく読めたよ、『神曲』(まだ地獄篇だけだけど)。 岩波版は原著の詩の雰囲気を文語体で表現しているため、現代人には難解だ(『南総里見八犬伝』を読了した自分でも、この訳はしんどい)。やはり翻訳の読みやすさは重要だ。河出版の奥付は2008年初版で、小生が読んだ文庫は2012年の発行。 岩波の場合、注は最後にまとめて掲載されているので行き来が面倒だが、河出は各歌が終わるごとに注が掲載されているので、たいへんわかりやすい。 それから、なんといってもギュスターヴ・ドレの挿画がたくさん載っていること。これでだいぶイメージしやすい。 さまざまな映画や小説はもちろん、『デビルマン』『進撃の巨人』などのコミックもインスパイアされていることがわかった(悪魔の描写など)のは僥倖である。アーティストの想像力を刺激するのが『神曲』。 イタリア関係の知識がないのでまるでちんぷんかんぷんな話題もあるが、ギリシア神話の知識が少しあるのでそっちはよかった。 まるで歯が立たなかった岩波文庫だが、よい点が1つ。それは「地獄の図版」が巻末にあること。これは河出版を読みながらも役に立った。あと2冊、行けそうである。
2投稿日: 2023.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ・「心配するな。私たちの行手は誰も遮ることはできぬ。これはその筋の思召しだ。ここで私を待っていろ。精神が疲労困憊したようだが望みは確かだ。元気を出すがいい。私はおまえをこの下界に置きざりにはせぬ」
0投稿日: 2023.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログひとまず地獄編を一通り読み終えた。まだまだ知識不足なのか、人生の経験不足なのか、物語の面白さを感じるに至らない。読みやすい訳と解説だからひとまず読み進められた感じではあった。 現実の世界で目に見えない地獄にて人々が罰せられる様子をリアルに描くダンテの表現力は圧倒的だった。とてもグロテスク。中には、挿絵なしでは想像もつかない描写もいくつかあった。 ぜひ煉獄編、天国編も読んでいきたい!年内に読むのが目標。
4投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログようやく読み終えたという感じ。 かなり読みにくい印象。 キリストを裏切ったユダや、カエサルを暗殺したブルータスやカシウスが地獄の底にいるのはわかるが、マホメットさえも地獄にいるのには驚き。 ローマカトリックのようなキリスト教の立場からすれば異教徒であるマホメットは大罪なようである。 善悪で人を捌くこの本だが、個人的には好き嫌いで物事を見る方が好きだ。 しかし、地獄の様はなかなかに激しい。 天国を見る前に、しばらく地獄篇で休暇になりそうだ。笑
0投稿日: 2022.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史に名を残すダンテの文学作品、「神曲」です。政治活動に深く関わっていたダンテが政変に巻き込まれてそこから永久追放された後に綴った文学作品であり、まずこの地獄編は人間省察の本であるとも言えるでしょう。人間が地上でどのような悪行を重ねるとどのような地獄に落ちるのかと言うことを詩的に文学的にこれでもかと言うほどの文章では表現できないような恐怖や狂おしいほどの苦悩の様の有り様を生生と活写している本です。 ダンテがこの本を通して一貫して訴えたいことは因果応報と言う理念のもと、現実に名誉を得て現世では有名だった方などが地獄で生々しく激しい責め苦を受けている姿を描写している様は非常に面白いものがあり、何故そのような責め苦を受けているのかの理由なども記載しており、因果応報とはこのような事かと理解されます。 一生の間に1度は読んで起きて本であると言えるでしょう。
0投稿日: 2022.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログよくぞここまで....というほどの、(当時の時点で)ありとあらゆる想像しうる責苦が、生きている中で犯した罪の応報として描かれていて興味深い。 宗教・歴史上、差別的な思考や記述というのもあるし、作者の偏っているように思える思想も捉えられるが、作者含めた登場人物の強い個性や信念としての印象を残しているような感じ。 よく「崇高な思想」とか「敬虔さ」みたいな表現を見ることがあるが、本書を読んでいると、それはどれほど窮屈なのだろうかと思ってしまった。
0投稿日: 2021.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史や宗教の背景がないので、注釈を頼りに読み進めることに。 上方落語の『地獄八景亡者戯』だ!と理解してから、読みやすくなった。歴史的にはもちろんダンテが先。
0投稿日: 2021.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ学術文庫の原訳から平川訳へ 読みやすさという点では断然平川訳なのだけれど、 叙事詩の訳文であることや背景の理解など総合すると断然原訳だなぁ。 全体像をすっきり見通すため補完的な役割として、平川訳は非常にありがたい本です 『神曲』への取っつきやすさをぐっと縮めたという点でも。
0投稿日: 2021.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと難しく読みにくいものかとおもっていたら、註釈や挿絵がかなり多かったおかげもあり、わかりやすく面白く読めた。 もっと抽象的な話かとおもっていたら、結構ダンテの私情や私怨が多かったようにおもう。
0投稿日: 2020.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ一日一歌読み進めたが、その一時一時は非常に贅沢な時間だった。 序盤は舞台設定の目新しさに惹かれるものの、半ばこれが不朽の名著たる所以ってなんだ?と悶々とし、終盤になってようやく朧げにその輪郭が見えてきた。 とは言え、原語(トスカーナ語)の詩的な情緒だったり、ウェルギリウスやホラティウス等の詩を味わうことなしに僕の中で名著だと断言はできない。んー歯痒い。 そんな中でも、確実に言えるのはダンテの想像力と描写力、教養の深さは並大抵ではないこと。恐らくそれが名著たらしめている大きな要因だと個人的に思う。 ダンテは実際に見たことのない地獄の世界を行ったかのようにありありと描写する。絶妙な比喩もその一助になっている気もする。そこに人文学、物理学、歴史学などあらゆる学問の教養がスパイスのような役割を果たす。 注釈も詳しく、文庫で手軽に買えることに感謝! さて、煉獄編へ〜
4投稿日: 2020.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ西洋古典として名高い『神曲』。 格式高いイメージでしたが、全部で100歌に分かれていて、それぞれのボリュームは大きくないので、割と読みやすかったです。 地獄篇は、詩人ウェルギリウスをお供にダンテが地獄を巡ります。キリスト教社会の死生観や当時のイタリア国内の状況が垣間見ることができます。地獄で刑を受けている人物にダンテの知り合いが多数おり、中には師匠までが責め苦を受けています。特に、ダンテの政敵が出てくるあたり、ダンテの怨念というか私情が感じられて面白いです。 また、世界史上で見知った偉人が出でくる辺りも、当時の価値観が見えて面白いです。サラディンが出てきて驚いた。とはいえ、皆地獄行きとして書かれていますが。 また、ケロベロスやベルゼブブ等、西洋の地獄や魔界の生き物達も一通り出てきます。 非常に深く解読できる名古典ですが、軽い気持ちで一歌ずつ読んでいっても十分楽しめる作品です。
0投稿日: 2020.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ挿し絵豊富だし注釈も親切で宗教・歴史的教養の無い私にも優しい・・・ 平川先生訳の神曲、訳文も読みやすいし文章の固さがちょうど良くて(これは人によって好みありそう)理屈的に「?」てなるところは注釈で他の文献からも引いて来つつ解説されてるから痒いところに手が届きますありがてぇ~賢い人の教養お裾分けありがてぇ~ イスカンダルも地獄の下層で人の血を流し産を掠めた暴君として赤々と煮えたぎる血の川で煮られていますからね…所変わればですね 宗教、自殺者に厳しいよね。。。 最後の審判の日に己の亡骸を探しに行くも自分で捨てたものを再び身につけることは許されず地獄の森で自らの魂の茨の木にその肉体が吊るされる。。。
0投稿日: 2019.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ地獄篇読了 まぁ、もはや、読んだ、というだけで、何か残ったかと言われると、、、 何回か読まないと把握できない複雑構造 ゴシック建築みたいなもの、とはよくいったもので、ほんとそうです ぽかーんとアホのよう
0投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログダンテ著、平川祐弘訳『神曲 地獄篇』河出文庫 読了。まさしく過去千年の最高傑作。まるで夢の世界だが、具象的で実にリアル。邦訳としても秀逸で、言葉が非常に美しく、何度再読しても飽きの来ない名作。キリスト教世界観に精通していれば楽しい地獄旅行になったはずなのに。煉獄篇も既に準備済みw 2010/11/19
0投稿日: 2018.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ地獄篇、煉獄篇、天国篇の3篇。壮大な構想と、綿密な構成、そして巧みな表現ということで文学史上に屹立する作品(だそうである)。 ダンテの生きた時代への理解が不十分なので読みづらくはあったが、読み応えは確かにある。ダンテが、キリスト者として当時の世界観のなかで、あらん限りの要素をこの詩の中にぶち込んでいる所が凄みか。書いている者の思いも、読む者の受け止め方も、今日とはまた違うものであったろう。また、神の世界を描いてもあくまで世俗的なところから離れていないのも魅力だ。 最近読んだ「ディアスポラ」にちょっと近いところを感じる。変な比較か?
0投稿日: 2018.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ"この本に興味を持ったのは、松岡正剛さんの書評を読んだため。是非読んでみたくなった。神戸への出張の車中で地獄篇を読んだ。平川?弘さんの訳、河出書房のものだ。 キリスト教とギリシャ神話がベースに組み立てられている。この後の、煉獄篇、天国篇を読むと印象が変わるかもしれない。 古典の名作といわれている本。注釈が丁寧に記載されているので、背景や人間関係などもわかりやすい。"
1投稿日: 2018.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2009年1月16日~17日。 右のほほを打たれたら相手の左のほほを殴り返せ! というキリスト教の教えの本(キリストはそんなことはもちろん説いていないが)。 自意識過剰男ダンテ(作者が作中の登場人物)が自分の気に入らない人間を地獄に落として呵責に苦しませている。 そんな感じ。 つまらなかったか? いやいや、物凄く面白かった。 詩的な文章はそれこそ「文学!」って感じがするし、なによりもダンテ(作者としても、登場人物としても)が人間臭くて。 それにしても、キリスト教ってのも自己中心的な教えだなぁとも感じた。 洗礼を受けなかっただけで地獄(ま、辺獄ではあるが)に落ちてしまうんだから。 「信じる者は救われる」=「信じない者は救わないもんね」 西洋、特にキリスト教圏の国々の人たちはまた違った見方をするんだろうな。 イスラム教圏の国々では「悪魔の書」と言われているらしい。 なにしろマホメット(ムハンマド)を地獄に落として真っ二つにしちゃってるんだから。 翻訳、および解説を書いておられる平川氏の「ダンテは良心的な詩人か」も良かった。 この解説は西洋人には書けないものかも知れない。
1投稿日: 2018.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ最良の翻訳といっていいと思う。岩波版とか講談社学術文庫版とか集英社文庫版とかいろいろあるけれども(読んだことないんだけど)。
0投稿日: 2017.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ご存知でしたか? これは詩なんです。 一応ダンテが実体験したことになっていますが、生きたまま地獄を巡るわけです。 当時はキリスト教が法王派と教皇派に分かれて争い、法王派であったダンテは政争に敗れて追放されていました。 そんな失意のダンテの前に、古代ローマの詩人ウェルギリウスが現われ、神が創りたもうたこの世界を見て、この世の人たちに正しく伝えるように言うのです。 で、まず地獄から。 文字を読める人が少なかった中世の頃、夜、薄暗いろうそくの明かりの下で武器や農具の手入れ、織物などの手作業をしながら誰かに読んでもらって聞く地獄の様子は、それはそれは恐ろしく感じられたと思います。 死ぬほど地獄に行きたくない→神様の教えに従って、善い人生(正しい人生)を送らなければならないと思うのは、自然な流れでしょう。 そういう意図をもって書かれたのが、この神曲。 だから地獄の住人たちは歴史的に有名な悪人だったり、個人的にダンテが気にくわないヤツだったりとかなり恣意的。 もちろんキリスト教ができる以前にお亡くなりになった人は天国へ行けません。 でも、地獄にはいますけれども罰は受けていません。善い人は。 天国へ行くための第一歩は善い人であることではなく、洗礼を受けることなのです。 小難しい理屈もありますが、詩なのでテンポがいいです。 そしてダンテは、庶民に受け入れられやすいようにラテン語ではなくトスカーナ地方の方言で書いたそうなので、余計に耳から入りやすかったのではないかと思います。 “ゲルマン人のゲーテの『ファウスト』と異なって、ラテンの人ダンテの『神曲』は非常に緻密に構成された芸術作品で前後照応する場合が多く、それが精読の興味にたえる理由の一つともなっている。”(訳者あとがき) ゲーテ、ディスられてる。 目に浮かぶような描写で地獄の様子を、罰を受けている人々の様子を、延々と語ります。 キリスト教の教義では魂は不滅です。 生まれ変わることもありません。 だから永久に罰を受け続けなければならないのです。 反省したから許されるとか、水に流すなんてことは一切ないのです。 泣いて罪を悔いても、一度やっちゃったことは取り返しがつきません。 最後の審判の日まで、地獄に落ちた亡者は苦しみ続けます。(地獄に落ちちゃった人が最後の審判の日に救われるとは思えないのですが、そこのところはどうなんでしょう。とても気になります) この容赦のなさが、私には何より恐ろしかったです。 「罪を犯したことのない人だけが罪びとに石を投げてよい」とイエスは言ったのじゃないの? なぜ許さん? 一章ごとに一編の詩。 詩の前にまず内容が書いてあって、全体像を念頭に置きながら詩を読み進めます。 その後には詳しい訳注。 何行目の○○について、一編につき20~30ほどの注。 それが34章。 あちらを読んだりこちらを確認したりと、思いのほか時間のかかる読書でした。 ダンテが付けたタイトルは『喜劇』 後の人たちはこれを『神聖喜劇』と呼びました。 日本語タイトルの『神曲』は、森鷗外がつけたらしいです。 キリスト教にほぼ初めて触れたであろう明治の文人たちは、この作品のどこに心を打たれたのでしょう。 作品の文学的な部分なのか、信教の厳しさなのか。 私はこの本を読んで、どうせ落ちるなら仏教の地獄に落ちたいものだと思いました。 とりあえず蜘蛛には親切にしておきます。 そして、糸が切れそうになっても皆を励ましながら、心をひとつにして極楽をめざそうと思います。←お釈迦さま、その際はよろしくお願いします
2投稿日: 2017.01.20数ある翻訳の中でももっとも平易かと
”神曲”は青空文庫で無料で読めますが、あちらは文語的で現代人な私には難しすぎました。 どの訳が良いかネットなどで情報を集めるうち、河出の平川訳がよさそうだと以前から考えていたところ、こちらのストアでそのものを見つけ(逆にそれ以外は無い)一気に三冊購入しました。 原作はそもそもイタリアの平民が使っていた言葉で書かれた作品のようですし、おそらく高尚に考える必要はありません。ただ欧米においてはシェイクスピアに並ぶ知識人の文学であり、キリスト教が栄えたヨーロッパ人の思想を知る上で大変参考になると思います。
0投稿日: 2015.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
左手の堤へ鬼たちは向かったが 出かける前にみな自分たちの隊長に向かって 合図にしたでべえをして見せた。 すると隊長の方は尻からラッパをぷっと鳴らした。 時代を超えて読まれる名著中の名著。お堅いのかと思いきや、放屁場面が出てきた…。ルネッサンスの時期に、キリスト教の世界がどのように思われていたかがよくわかる本。口語訳である上に、背景が注に書かれているので分かりやすい。地獄、煉獄、天国編があるのだが、登場人物が実話や神話に基づいているのに驚いた。つまり、ダンテが地獄に落としたいと思っていた人は見事に地獄でお会いすることになる。マホメットはキリスト教を信じていたが、そこから分裂してイスラム教を作ったなど、古代の常識や慣習を知ることができるのも魅力の一つ。相当の知識がないと読み砕けないので、博学になってから読むのでも遅くはないと思った。
0投稿日: 2015.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
インフェルノの読後手に取る。ダンテの生きた時代、キリスト教の影響が色濃く反映されているのか?割と読みやすかった。
0投稿日: 2015.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログまぁ…どちらにしてもダンテさんの頭のなかはこうだったんだということが出ているんでしょう。西洋の人の極端さが認められてん〜んって感じ。 日本にも地獄思想があったので、人間ってそんなものなのかとちょっと落胆しましたが、脳は変われますから希望は持ちましょう。 個人的にはギリシャ神話やローマの英雄なんかがちょくちょく出てきて楽しめました。 乗りかかった船なので仕方がないから、気は進まないけど煉獄篇、天国篇も一応読んでみます。 訳者の平川先生のボッカチョ作の「デカメロン」はきっと池田先生テイストなんじゃないかと読んでみたくなりました。 Mahalo
0投稿日: 2014.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ崇高すぎて敷居が高く敬遠していたが、ドラマ「BORDER」の謎解きに出てきたので読んでみた。ダンテがラテン語ではなくトスカーナ方言で書いたのは、より多くの人に読んでもらいたかった故だろうし、分かりやすい平川訳で読んで正解だろう。 「神曲」というタイトルは森鷗外の紹介文からきていて、原題は「喜劇」という意味の「Commedia」だそうだ。当時の人物名をバンバン出し、地獄で大変な目に遭わせ糾弾するというジャーナリズム的な意味もあったらしい。知識があればもっと面白く読めたろうに残念。 大食らい、吝嗇、浪費、異教異端、暴君、自殺、男色、女衒、阿諛追従、聖職売買、魔術魔法、汚職収賄、偽善、窃盗、権謀術策、裏切、何でもかんでも地獄行き。心して生きよう。 漆黒の六枚羽の意味がやっと分かった。
0投稿日: 2014.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかく古典なのにさくさく読める。しかも注釈が熱い!詳しい!わかりやすいとAmazonのレビューで好評だったがその通りだった。 古典への扉を開いてくれた翻訳に感謝の一冊。
0投稿日: 2014.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語はダンテが幼年の頃より、深く愛していた美しき女性:ベアトリーチェが夭逝するところから始まります。 時は1300年4月7日、深い絶望の淵に立たされた若きダンテは、生きる道を失い彷徨い歩くうち暗い森のなかへ迷い込んでしまいます。 そこに現れる3匹の猛獣!絶対絶命のダンテの前に、古代の大詩人であるウェルギリウスが現れ「道を見失った君が無事に現世に戻るには「死後の世界」(生前罪を犯した者が裁かれる地獄、生前の罪を償い浄めるための煉獄、そして幸福な魂だけが行ける天国)において死者の魂の声を聞き、自分の進むべき道を自身で見つける他ない。私は天上にいるベアトリーチェから頼まれて救いに現れたのだ」と告げます。 この言葉に動かされ、ダンテは地獄へ下る決意をします。 二詩人が行きつくと、地獄の門があり「汝ら、われをくぐる者、一切の望みを捨てよ」と銘文が刻まれています。その先は河があり、地獄の渡し守カロンが二人を運びます。その先は辺獄(リンボ)と呼ばれる、善良であるにもかかわらず、洗礼を受けなかった人々が集まる獄。その先で二人を待ち受けるのは、尻尾を巻きつけて、その巻きついた数で堕ちる地獄を決める地獄の裁判官ミノスが待ち受けます。そこを抜けると本当の地獄が始まります。 愛欲ゆえに災いを招いた者たちは白骨を晒し黒い風に吹かれ、貪欲に耽った者は地獄の番犬ケルベロスに何度も喰われ、自殺者は森の木となり蠢き身体を怪鳥に啄ばまれる。 地獄は下へ行けば行くほど、重い罪の魂たちが裁かれる構造となっています。 たとえば神話と呼ばれる時代に、自らの力を過信し神々に戦いを挑んだ巨人族は下層で、足を地に着けて大地から力を得ないよう井戸に浸され苦しみ続けています。 そして氷漬け地獄(コキュートス)の果てにある地獄の最下層では全ての悪の根源ー神に背き、神の怒りに触れ、地獄の底に閉じ込められた地獄の王ー堕天使ルチフルが、キリストを裏切ったユダ・イスカリオテらを噛み砕きながら醜い姿で永遠の責苦に遭っています。 ルチフルの脇腹から、二詩人は地球の反対側に抜け煉獄へ入ります。
0投稿日: 2014.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなく読み始めたら、面白くてついつい読み切ってしまった。想像力をかき立てる描写もすごいけど、何より凄いのは人々を一元的に断罪するキリスト者の狂気だと思う。まだキリスト教が宗教としての意義を持っていた時代の、だからこそ垣間見せる狂気には現代の新宗教と共通するものがある。
2投稿日: 2014.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ事前の知識も全くないまま興味と勢いだけで購入。当初は本の厚みにビビリましたが、読み始めると意外とさくさく大変興味深く読み進めることが出来ました。地獄巡りの旅の描写には想像力をかき立てる凄みがあって、思わず自分はどの地獄に落とされるのか・・・なんて考えちゃったりしました(笑)
0投稿日: 2014.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なんかもっと深遠な、とてつもない哲学が語られるのかと思っていたが、何のことはない、上方落語にもある地獄めぐりの物語だ。それに付け加えるものがあるとすれば、ふんだんに登場する実在の人物たち。彼らの生前の所業を断罪するその手際が当時の人々の目からすればジャーナリスティックに映ったのかもしれない。 ただ、ディティールの表現は確かに秀逸。蛇が人間に、人間が蛇になる描写など、さしずめSF映画のようにビジュアルに訴えかける。想像力をかきたてる描写は圧倒的。
0投稿日: 2013.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ有名な作品なので、一度は読んでおこうと思い読んでいる。 歴史的背景や、宗教的背景もあまり知識がないので理解がなかなか難しい。 詩の訳というのは原文のニュアンスとかを正しく伝えるのは難しそうであるが、表現が独特で面白い。 視覚的なイメージはゲーム「デモンズソウル」が近いのではないかと思う。
0投稿日: 2013.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログいやあ楽しかった!ーー 目の前に現れるリアルな地獄の凄絶なこと! おびただしい罪人がさまざまな苦行を強いられて、苦しんでいる。 それをただただ目にし、目的地へそぞろ歩いていく。 ダンテのおののきがこちらまで伝わってくる。 読む前はもっと抽象的で難解な作品だと思っていた。 それぞれの歌の前に訳者による「内容紹介」と、本文あとの注解により理解が進む。 とにかく情景が具体的で生々しい!その情景を見るだけで読書の醍醐味を与えてくれる。 おびただしい人名は読み飛ばして、ひと息に目を通しながら文章を味わうだけで大きく満足できる作品。 よーし、煉獄篇天国篇もサクッと読んでいくぞ!!
0投稿日: 2013.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕の予想に反し、結構わずかな時間で読み終えた。面白かったというのもあるし、訳がよかったのも大きいと思う。地獄で苦しんでいる人の描写が、人間的で生き生きしてるのが楽しい。煉獄編もこの勢いで読めてしまうかも。
0投稿日: 2013.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ2000年のロンドンの「タイムズ」紙で「過去千年間の最高傑作は何か」というアンケートで選ばれた、700年以上も前の作品。 ダンテがウェルギリウスの案内によって地獄・煉獄・天国への旅に出る。そこで様々な地獄絵図に遭遇する。 蛇に巻かれた男が出てきたり、自分で自分の首を取って手で持ち歩く男がでてきたり・・・日本では出てこないような地獄の発想ばかり。
0投稿日: 2013.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログダンテの想像力、構成力に脱帽。それを大変解りやすく訳し、そして注釈をつけている、平川氏に感謝です。 当時のイタリアで、l知りうる限りの歴史、自然、天文、数学などをふんだんに散りばめて死後の世界を描いてあり、おどろおどろしい場面がたくさんありながらも、楽しんで読めた。 注釈のなかに『往生要集』がでてきたが、仏教の地獄絵巻とかなり重なる部分もあり、比べながらでも面白いかもしれない。 先達のウェルギリウスが知的で包容力があって、素敵すぎます。 続いて煉獄編を読みます。
0投稿日: 2013.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログすいぶんかかって読破。 地獄篇~煉獄篇~天国篇と、あわせて1000ページを軽く越えるボリューム。 ちなみに、宗教的な興味がとくにあったわけではない。 「分かりやすい」と好評の訳だけあって、さながらダンテと旅する気分。地獄篇では、さまざまな罪によって罰を受ける人々を見て、ちょっぴり自分の罪を悔いてみたりもした。 煉獄から徐々に抽象的になっていき、天国はまったく理解を越えていた。まだ私の魂はそこに到達できないらしい。(笑)
0投稿日: 2013.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ難解として知られるダンテの『神曲』だが、地獄篇は様々な作品の引用元として使われているためか多少冗長に感じつつも楽しむことができた。興味深いのは『ニコマコス倫理学』からの引用がさらりと出てくること。アリストテレス哲学は十字軍遠征時にイスラム圏から逆輸入された思想であり、『神学大全』でそれがキリスト教内に体系化されてからまだ数十年しか経っていないはず。またギリシャ・ローマ時代の偉人達がイエス以前に生まれていたという理由だけで地獄の第一層に落とされている描写は、中世におけるキリスト教の絶対性を物語っている。
0投稿日: 2013.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ想像よりもずっと読みやすい。近所のに住む嫌いな人に対して、地獄に落ちているという描写をしてしまう、なんとも俗な感じがたまらん。面白い。
0投稿日: 2012.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログダンテが実際に体験したこととして描かれた地獄をダンテの驚異的な想像力と知識の深さでディティールにまで緻密に描いている。かなり構えて読む類いのものと思っていたけれど、そんなことはなく軽い興味だけでも楽しめる。地獄を見たい人、旅してみたい人にオススメ。案内人は詩人ウェルギリウス。現実にいた人物や神話の人物が現在伝えられている現世での罪を償うため地獄で罰を受ける描写もあり、意外なほどリアルだった。詩だが、詩の形をした物語。感じたことはレビューだけには書ききれない。比喩など修辞的な部分が多いため、この本は訳者による解説が細かく、そちらもよかった。
0投稿日: 2012.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログほんとに読んだのはこれではなく、山田慶児の『ダンテは世界をどう描いたか 新訳「神曲地獄篇」と、その解説』(編集グループSURE発行)。なので河出文庫版を読む方は参考にしないでください(Amazonで売ってないものも自分で登録ができるように早くしてほしいよ)。 で、SURE発行の本はどれも装丁がうつくしいのですが、これも装丁にひかれて購入したもの。イラストに口語訳でたいへん読みやすく、敬遠してた古典もこれなら読めそう、と思ったのですが、本文への注がまったく不親切なのに、がっかり。地獄の構造が図解されてるのはおもしろかったけど、解説も自己満足くさくて読者のことは考えてませんね。 しかし見てきたように地獄のさまを語って自分の思想を語るこの本が名作とされてきたゆえんが理解できません。キリスト教道徳+自分の政治的価値観で勝手に地獄におとされたことにされた人たちも迷惑しちゃうよなあ。地獄がこんな感じだと、天国はよほど退屈なところなんじゃないかって思う。
0投稿日: 2012.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ□『神曲』全体について イタリアの詩人であり政治家でもあったダンテ(1265-1321)のキリスト教叙事詩、1304年頃から死の直前1321年の間に地獄篇・煉獄連・天国篇の全三部を完成させたという。原題は『La Divina Commedia 神聖喜劇』、ミルトン『失楽園』ゲーテ『ファウスト』へと連なっていくキリスト教文学の、則ち「西欧世界」文学の最高峰といわれる(ただし本作を「世界」文学の傑作と呼ぶのは、西欧キリスト教中心主義の誹りを免れ得まい。「元来キリスト教徒だったマホメットがそこから分裂してイスラム教を創始した」という当時の支配的な考えに則り、ダンテは作中にてマホメットを地獄に堕とし、分裂分派の罪で肉体を真っ二つにされる罰を永劫に与え続け、その裂け目から臓物がはみ出ている様を生々しく描写している。アラビア語訳の『神曲』では、その場面に該当する地獄篇第二十八歌は削除されているという)。 執筆背景について。当時ダンテはフィレンツェの政争に破れ国外追放に遭い、放浪生活を続ける中で『神曲』は執筆された。『神曲』各篇には、古典古代の哲学者や詩人だけでなく、当時の政治家や聖職者を実名で登場させ、自らを失脚させた者は地獄へと堕とし、殆ど私怨と見紛うほどの宗教的・政治的義憤をぶつけているのは、我が身の不遇に対するダンテの私的な情念が垣間見えるようで興味深い。 文化史的意義について。ダンテは『神曲』に於いて、ギリシア・ローマの古典古代文化(叙事詩や悲劇・喜劇)を摂り込みつつ、それをキリスト教中世の世界観へと組み換えていくことで、ルネサンスの先駆をなした。また本作は、当時の知識層の共通の"国際語"であったラテン語ではなく、彼の出身地でもあるトスカーナ地方の方言則ち"俗語"で書かれており、これが現代イタリア語の基盤になったと云われる。 なお本書では、19世紀の版画家ギュスターヴ・ドレの挿絵が多数挟まれ、ダンテの詩句に独特なイメージを与え、その情景を忘れ難いものにしてくれる(岩波文庫版ミルトン『失楽園』にも彼の挿絵が入っている)。訳文も現代語として読み易く、同時に決して作品の持つ威容を損なうことがない。また訳註は、本書を読む上で必要な補足を通してキリスト教や古典古代についての様々な知識が得られるに加え、近代日本における『神曲』受容の挿話も多く挟まれ森鴎外・上田敏・正宗白鳥・与謝野晶子などが引用されており、読書の奥行きが広がる。 キリスト教という世界観を知る上で大変貴重な読書体験を与えてくれる作品と云える。 □『地獄篇 Inferno』について 阿鼻叫喚、酸鼻を極める地獄絵図。この『地獄篇』では「全体について」でも述べたとおり、キリスト教的世界観とりわけその凄まじいまでの「想像力」「体系的構想力」やキリスト教徒の「信仰への感性」を窺い知ることが出来る。そして、キリスト教がその信徒の内面に対して如何に峻厳苛烈なまでに抑圧的に作用してきたか、外部者にとっては想像の域を出るものでないとは云え、その絶大な力の片鱗は充分に体感として味わうことができる。 日常、信徒たちは、現世で果たせなかった復讐心を抱えながら、復讐の代理人たる神(「ああ神の力よ、何という厳しさだ、/このような痛撃を復讐として下すとは!」第二十四歌)とその舞台である地獄という観念で内面を凝固させていくことによって、辛うじて俗世を生きていたのか。神へ向かおうとする自らの良心に対する自己束縛的とも云うべき厳格さ(「ただ良心だけが私の支えだ、/良心というのは人間の良き伴侶で、/自己の潔白の自覚が人に強みを与えてくれる。」第二十八歌)、「目には目を、歯には歯を」の talio 同害刑法 の延長である神の復讐という教えに対する厳粛な畏怖(「神の裁きに対して憐愍の情を抱く者は/不逞の輩の最たるものだ。」第二十歌)、キリスト教が信徒に与える内的抑圧の強さを感じずにはおれない。日本近代の基督信徒たる内村鑑三は、神ひいては地獄の実在を信じるがゆえに、『地獄篇』の凄惨な描写に亡者の叫喚を聞き取り、身を慄え戦かせたという。 その存在が精神を介してありありと感得される絶対的な存在としての神への信仰に対する倫理的厳格性と、その神の言葉として壮大な神学体系を支えているロゴスの論理的厳密性。更にそこに必然的に備わる抽象性・普遍性への志向。キリスト教の、そんな凡ゆる局面に向けられる「徹底性」が、随所に垣間見える。そしてこの徹底した抽象性・普遍性・絶対性への傾向、その極端への傾向は、ひいては暴力性を志向することにならないか。 文化史的には、そうした傾向こそ西欧に於いて緻密な近代自然科学が誕生した要因ということになる。しかし同時に、キリスト教のこの厳格な抑圧性こそが、ヨーロッパ世界に於ける被虐嗜好・加虐嗜好(マゾヒズム・サディズム)の内面的母胎となったのではないかとすら想像したくなる。 思想史的には、キリスト教世界に於ける無神論・唯物論的自然科学(神の摂理ではなく飽くまで自然法則として追求する)・自由主義思想・啓蒙思想の主張が、自己の内面に対してもまた同時に外なるキリスト教社会に対しても如何に命懸けの行為であるか、その重みが多少とも実感できたように思う。しかし、これら近代を特徴づける思潮に見られる激越な「宗教からの自由」の熱望が、逆説的にもキリスト教に見られる絶対性への志向に由来しているならば、近代思想とは、キリスト教的絶対性を無意識の骨格として残しながらもキリスト教自体を内破しようとしたものと云えないか。その後、ヨーロッパ世界に放たれたニーチェのキリスト教批判の矢が、如何に思想上の衝撃を与えるものであったか、窺うことができる。 一方で資本主義と官僚制の巨大な機構として極度に抽象化された近代社会は、ブレーキの無い動力のように留まることなく極端へと走り続ける。上述したキリスト教の背後にある、非妥協的で殆ど機械的とすら云える非人間的なまでの厳格主義・純粋主義・絶対主義・独善的自己中心主義が、のちの植民地暴力による西欧の世界支配、ひいてはアウシュビッツという極端にまでその運動を加速させていったのではないか。 この一篇からここまで想像を走らせるのは、或いは分を超えているのかもしれない。 なお、『地獄篇』には、近代的自我の先駆とも云えるような、何人かの印象的な罪人が登場するのを紹介しておく。第五歌、フランチェスカ。不実の結婚に抗して、恋人パオロとの真実の愛によって現世を逐われた。パオロと真情が結ばれた日の回想は美しく、あの瞬間に神も俗世も消えて世界は二人だけのものになったに違いない。第二十六歌、オデュセウス。「この世界を知り尽くしたい、人の悪も人の価値も知りたい」という激情に駆られて大海原に乗り出す彼は、短くも雄大な叙事詩を語る英雄そのものだ。自らの眼で世界と人間の謎を探求しようとする彼の姿は、ファウストにも重なる。第三十二歌、ボッカ。作者ダンテが実生活に於ける不遇の私怨を晴らさんばかりに、作中のダンテは復讐者たる神の代理人の如き狂態で亡者の首を掴んで脅しあげ名前を聞き出そうとしても、相手は口を割らぬ。ダンテが怒りの余り男の髪を束にして引き抜き続けても、敢然と目を伏せたまま。この男に、神に傲然と反抗する人間精神の自由の萌芽を見るのは、後世の贔屓目か。 その他、本篇には、一読忘れ難い罪人や情景が幾多も描かれ、読む者を飽きさせない。 最後に、『地獄篇』を読み終えた与謝野晶子の歌を。 一人居てほと息つきぬ神曲の地獄の巻に我を見出でず
1投稿日: 2012.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログそういえば読んでました 初読は小学生の時だったけれど、地獄編の挿絵のグロさに戦々恐々としていた記憶しかない… 最近になってやっとこの本の書かれた背景諸々を知ったので機会があったら読み直したい!
0投稿日: 2012.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログダンテがこの小説を書いてから推定七百年は立つ。当時西欧はルネサンスに沸き、モンゴルやイスラームという他者に怯え、国の中に市民という概念がようやく根付き始めたころだった。そんな時期に鬼子のように産み落とされたこの小説が、当時をして正当な評価を下されたか否かは判然としない。しかしこの小説、いや小説と呼ぶにはあまりに巨大な三遍の叙事詩は、七百年を経ても尚、キリスト者ですらない一人の東洋人の心を打つほどに壮大な世界を打ち立てている。 この作品の中で語られる世界、地獄は読む者は誰もがそこにだけは身を置きたくないと思わせるような陰惨で無情極まるものだ。各層で営まれる罪に対する贖罪は痛ましく、歴史の中で名を馳せた英雄達ですら断罪されている。それは現世的な栄誉も神の前では全て虚栄であるという無慈悲な宣告である。我々からしたらそれは人の抗えない業であると感じられるような責めようのない罪(食の為の殺し、愛憎の果ての自殺)を糾弾され、むごたらしく責められ続ける人々の姿を読むキリスト者は誰もが善行を積んで天国に至らずとも地獄行きだけはなんとか免れようと思ったのではないだろうか。そのような意味でこの作品は警句としても働くのだが、純粋な芸術としてもこの作品が構築した世界図は驚嘆に値する。一人の中にこれだけの世界が内包されていたとは、ルネサンスの本質たる人間賛美の意味を改めて認識してしまう。 しかもこれはまだ3分の一でしかない。ダンテがこれから見るであろう世界を想像すると胸が震えるばかりだ。
0投稿日: 2012.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際を率直に言えば、これは「詩人が神の名を盾として用意した、私憤を晴らす為の公開処刑の場」である。 そこで筆者の人格や教典の真理を云々するのは、それぞれの筋に任せれば良いのであって、「これらの天才が気狂いじみていたとも考えられないことはない。彼等を手離しで感心して好きになるためには、こちらも少し狂う必要がある。いずれにしろ、批判的であるよりは僕のように熱中した方がましだ」と云うGoghの言葉に従うのが、詩篇そのものを愉しむには一番の姿勢と思われる。 私自身は、西洋絵画の更なる堪能の為、屡々題材に採られる処を元の形:文学にて体験しておく、という立場で進めた。確かに、剰りに自己へ都合良しな設定の中を、時に媚態さえ呈しながら先達に依存しきって巡る詩人の姿は、全き人格者のものとは言えないかも知れない。けれどそれを臆面もなく晒しつつ、既に七世紀もを人類規模でウケ続けてしまっている辺り、とても子供らしく天真爛漫と、或いはそれこそは天に近き魂のあり様のようにも思える。 そのような詩人と、父母の両性兼ねた大詩人と共に往く、地獄の旅路。雄大なる想像力、緻密な構成力、屈強なる筆力、(私憤にも又燃えるのだろう)情熱と志とで絢爛に組み上げられた、それは詩人最大の建築物を訪ねるかの如き道程だった。もし、科学と技術との発達で心の視力は逆に衰退したのだとすれば、その渦中を眼前にまざまざと想い描いて慄くこと難しい現代に在るのは、至極残念なことに違いない。
1投稿日: 2012.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白い!難しそうで敬遠していたけど、河出版は読みやすいと聞いて読みました。注釈が分かりやすく、訳も現代語だからサクサク読み進めました。まるでダンテと共に地獄巡りをしているような臨場感はすごい!ヴェルギリウスの優しさが身に染みます。キリスト教の概念の勉強にもなるし、とても面白かったです◎続いて煉獄篇も読みたいです。
0投稿日: 2011.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ1300年春、人生の道の半ば、35歳のダンテは古代ローマの大詩人ウェルギリウスの導きをえて、生き身のまま地獄・煉獄・天国をめぐる旅に出る。地獄の門をくぐり、永劫の呵責をうける亡者たちと出会いながら二人は地獄の谷を降りて行く。世界文学の最高傑作、第一部地獄篇。
0投稿日: 2011.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
持ってるのはこの表紙ではないけどまぁ、気にしない この中世における思想というのだろうか?良く表現されているのではないかと思っている。友人は何故か、地獄篇しか知らなかったが、私は煉獄篇が最も好きだったりする。
0投稿日: 2011.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログトスカーナ出身のダンテは、古代ギリシャの詩人ヴェルギリウスとともに、地獄を下に下に降っていく。イスラム教の始祖ムハンマドも罰を与えられている。文学の世界的最高傑作とは、キリスト教に準じたものか。
0投稿日: 2011.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011.3.24 図書館 ちょっと教養を深めようかと…おもったんだけど読み切れるかしら 追記:読み切ったよ!
0投稿日: 2011.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ宗教書の形を借りた、自己の正当化かつ、政敵への恨み辛みの超大作って感じでした。 でも、その情熱に拍手
0投稿日: 2011.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なんでこんなにおもしろいんだろ。当時のナポリやフィレンツェの状況、政治的背景なんて、全然知らないのに。地獄をめぐる描写の鮮やかさが、そうさせるのかなあ。
0投稿日: 2011.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく詳細な地獄の描写 挿絵はむしろいらん!ぐらいの作品 歌とあるだけあって意味のとりづらい部分も
0投稿日: 2011.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ購入してから1年寝かした、いや挫折した本を読み終えたが、確かに読み易いのだがなんとも難しい。出直しです
0投稿日: 2011.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログダンテはこの一冊を通して、自分は気に入らない人間を容赦なく妄想の中で地獄に落として嘲笑する男なのだという自己主張をしていることに気づいていたのかな?
0投稿日: 2010.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋で見かけた頃からすごく読みたいなぁ、と思っておりまして。 友人が「すごく長いよ」と言っていましたが、長さがともあれ、内容が長さに相応しいのならそれでいいです。
0投稿日: 2010.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ平川訳は平明な現代語でかつ詩情も損なわれていない(たぶん)。他の訳はあまりにも難解で読む気になれなかった。
0投稿日: 2010.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初、なんだなんだこれは、わけわかんない?!って思いますが、だんだんわかってきます。cocoiは、これで、政治学のレポート書いて好評だったといってたけど、、、どんな?ちょっと興味あり。
0投稿日: 2010.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログそう言っちゃなんだけど(ひょっとしたら不謹慎?)、面白かったぁ!!!! 「神曲」というタイトルからして「どこか説教じみた抹香くさい話なんじゃないか?」と思ったり、これまでにチャレンジした難解な文語調翻訳で「う~ん、よっぽど余裕がないとこれは読み終えることができない・・・・・(溜息)」という先入観があったりで、興味を持ちつつもどうしても読み進めることができなかった作品だけど、この平川版の「神曲」は「読み易い」「面白い」「翻訳日本語が美しい」の3拍子 + ギュスターヴ・ドレの挿絵のインパクトであっという間に地獄篇を読み終えてしまいました。 以前にチャレンジした時はほとんど進まなかったせいもあって全く気がつかなかったんですけど、「神曲」ってコテコテ・キリスト教文学かっていうとそんなことはなくて、KiKi の大好きな「ギリシャ神話」とか「英雄叙事詩」とか「歴史モノ」と親和性の高い作品だったんですねぇ。 ま、そんなこともあり、やはりこの作品を本気で楽しもうと思ったら最低限 「聖書」、「ギリシャ神話」、「ホメロス;イリアス & オデュッセイア」、「古代ローマ史」の基本的知識は必須でしょうねぇ。 ま、これに追加でダンテの生きた時代のイタリア情勢も知っていればさらに面白いのかも!! もっとも KiKi は凡そそのあたり(ダンテの生きた時代のイタリア情勢)の知識には疎いのですが、それでも微に入り細に入り付してくれている「注釈」のおかげで、とりあえず一読するには何ら不都合は感じませんでした。 (全文はブログにて)
0投稿日: 2010.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログダンテの代表作を3分冊にしたものの1冊目、地獄篇です。3冊まとめて購入してその厚さに驚き、げんなりしたものですが、実際に開いてみると意外と楽に読み進めることができました。 この詩の主人公にして語り手であるダンテ(作者であるダンテが旅をしているという設定なのでしょう)が地獄、煉獄、天国の三界を廻るというあらすじはとても有名ですが、主人公と語り手が同一であるという設定はこの時代には例がない、という平川氏の指摘にはいささか驚きました。こうした物語手法は現代ではそれほど珍しくないと思いますが(さすがに作者を主人公と語り手に据えるというのは現代でも珍しい部類に入るでしょうが)、もしそれが当時斬新な手法だったとすると、あえてダンテが3つのの視点を重ねたその意図はどこにあるか。私は、理由は詩の内容にあるのだと思います。 地獄篇では過酷な罰を受ける人物が数多登場しますが、そのほとんどが実在の人物で、ダンテの政敵であったり教皇であったりするという、なんとも狭い世界だけで物語が進んでいる感があります。世間では「世界的な傑作」という高評価が当たり前の本書も、こと地獄篇に描かれた彼らの姿からはとてもそうは思えませんでした。言ってしまえば、政争に加担して敗れたダンテが、作中の地獄に仮託して政敵たちを懲らしめているだけの話です。こんなばかばかしい話をキリスト教神学の仮面をかぶせて大仰に描き切った本書は、まさに喜劇だとしか思えません。この詩の題名に「Commedia」とだけ題したダンテ自身も、もしかしたらそう考えていたのかもしれません。しかし、もちろんこれは世代と地域とを隔てた私の感想であって、同時代・同地域の人々には、「実在するダンテがやはり実在する政治家の地獄に落とされる姿を見て回る」というこの詩に触れたときどう感じたでしょうか。そう考えるとき、私はダンテという人に底知れぬ恐ろしさすら感じてしまいます。 とはいえ、物語という視点からこの詩をみるとやはり面白いのも事実です。展開の進め方も巧みだと思いますし、読者にその情景を想像させ、また作品世界に引き込ませる力は圧倒的ですらあります。生々しい地獄の描写などは、我が国の往生要集や日本霊異記にも劣らないでしょう。日本語訳も全く気になららず、とても読みやすいものに感じられました。平川氏による解説「ダンテは良心的な詩人か」も収められており、本編後にこれを読ませるとは見事、の一言に尽きます。平川祐弘訳。 (2009年7月入手・2010年9月読了)
1投稿日: 2010.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ大作だけどあっさり読み進められるのは平易な現代語訳と詳細な解説の賜物。 訳注もふつうは巻末についていて行ったり戻ったりが面倒だけど、 歌(章)ごとにまとめてあるので読みやすい。 父なる神と子なるキリストと精霊の三位一体の神聖意外を認めないはずなのに、ゼウスや運命の女神たちなどギリシア・ローマ神話の神が出てくるのはどうかと。 でも関連するギリシア神話をいっしょに読むと知識も増えてなお楽しめる。 訳注で正宗白鳥が、今の政治家や軍人や有名人を使って書いたらどうなるかと書いてたけど今の日本で書いてみてもおもしろいかも。 もちろん仏教地獄の話で。
0投稿日: 2010.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ダンテ『神曲』地獄編,河出書房,2008(初版1966) 再読(2009/8/12)。基本的にはウェリギリウスに導かれて、ダンテが地獄を旅する話である(ちょっと『西遊記』みたいだ)。 ダンテ(1265-1321)はフィレンツェに生まれ、法王党として政治にかかわり、1302年、故郷を永久追放された。『神曲』は1300年頃の設定で書かれており、ダンテの敵が地獄で手ひどく罰せられ、大便のなかでのたうちまわっていたり、自分の首を提灯のようにさげて彷徨っていたりする。師匠がじつは男色の罪を犯していて、引かれていく途中だったり、亡者が地獄の鬼(悪魔?)に鞭打たれていたり、貪欲な亡者がぐるぐる回って、ぶつかって罵りあったりと、地獄はまあそんな所である。冷たい雨が降ったり、火の粉が絶えず降ってきたり、空気がくさっていたり、ときどき、ケルベロスだのミノスだのミノタウロスなどの怪物や、巨人がでてきて、悪態をついたり、予言をしたりする。キリスト教徒じゃなかったホメロスは辺獄(リンボ)の片隅で淋しくしている。マホメットやアリーは二つに裂けている。キリスト教を分離させた者に応報の罰らしい。 たぶん、現代の映画なんかで消費しつくされたイメージだからだろうか、偉大な作品ではあるんだろうが、内村鑑三のように身の毛がよだつこともなく、こんな所かと読んでいる。地獄編が面白くないのは、ダンテが敵をいじわるく痛めつけているからもあるけど、そこには人間の「生活」がないからだと思う。ちなみに地獄でも、派手に痛めつけられている「主人公」は大悪人で、凡人は地獄に落ちても脇役である。悪人としては、恋に身を忘れた者から、偽金作り、裏切り者までたくさんいて、みな因果応報の罰をうけている。貪欲なものは生前自分がサイフにつめこんだように、地獄では自分が穴に詰め込まれていて、足だけでていたりする。 ウェルギリウスとダンテは地獄を底まで下りていき、地球の重力があつまるところで、悪魔大王(ルシファーとかベルゼブルとよばれる)をみる。大王はキリストを裏切ったユダと、カエサルを殺したブルータスとカシウスを三つの首でかみ砕いている。彼らは悪魔大王の毛をつたって、南半球にでていくのであった。 「神曲」の「神」は形容詞で、「神のごとき」の意味で、後に冠せられた。もともとの名称は「コンメーディア」とのこと、「ハッピーエンドの話」の意味だったが、のちに転じて、「喜劇」の意味になった。「光も黙る」とか「年老いた裁縫師が針に糸を通すような目つき」とか、うまいなと思う比喩はある。 『神曲』はイスラム圏では悪魔の著らしい。平川祐弘(『マテオ・リッチ伝』の著者)による注釈は詳細、カーライルやブルクハルト、正宗白鳥や内村鑑三、与謝野晶子などの意見を事細かく、引いてくれている。訳としてもよみやすい。『神曲』はその後の地獄のイメージなどに影響を与えた作品で、中国に宣教したイエズス会士などの頭にもあった作品だろうと思う。
0投稿日: 2009.08.12
