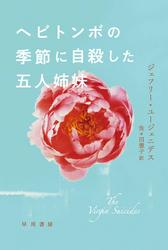
総合評価
(52件)| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 3 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
登場人物の名前を覚えるのが大変。 というのは5人姉妹の名前以外に、近所の人や学校の人、メディア関係者など誰が一体重要人物なのか読んでいてわからないので名前をいちいち覚えていられない。 映画「ヴァージン・スーサイズ」が素晴らしかったのと、メインキャラクターが女性のストーリーを男性作家が書いているのに興味を惹かれて購入。 オチがタイトルに書いてあるし、映画も見ているからどこに向かっているのかわかるのに、読み応えあり。
0投稿日: 2025.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログさっぱりわからない。うちのばあちゃんがアメリカでどうしても理解できないところは、なぜ、みんないつも幸せそうなふりをしてるかってことなんだ。 フォーマルドレスを着た女の子たちは、どことなく怪物めいて見えた。頭の上には髪が うずたかく、しっかりと結い上げられていた。酒を飲んだり、キスしたり、あるいは椅子の中で酔いつぶれている彼女たちの向こうには、実はもう、カレッジが、夫が、子育てが、 ぼんやりとしか感じられない不幸が待っているのだ――いいかえれば、人生が待っているのだ。
0投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログソフィアコッポラの映画から原作に入ったけど、あんまり面白さがわからなかった 主人公たち、というか、作者が女の子にだいぶ夢を見ている気がする。理想化してるというか。
0投稿日: 2023.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読むのは2度目だけれど映画は未鑑賞。 両親、特に母親からの抑圧がとてもあるのに加えて、姉妹を外から眺めて賞賛する「僕ら」にも失望してたんじゃないかと思いました。セシリアの未遂の時点ならもしかすると留められたかもしれないのになぁ。 男子側の視点過ぎました。この年齢の男子だったことがないのでちょっとわからない。。姉妹のこと何でも知ろうとするけど、直接向き合ってた人はあまり居ない。僕らのうちの誰も、姉妹を本気でこの環境から連れ出そうとする気概がない。ミセズ・リスボンの妨害なんてなんのそのでは…と思うけど、この時代の保守的な街では仕方ないかとも思いました。学生だし親の言う事は聞いとかないと。。 映画はソフィア・コッポラ監督で女性目線での制作だから原作より寄り添えるかも…と、ますます観たくなりました。
5投稿日: 2022.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
出版当時のアメリカの雰囲気や流行、母国の人が持つ感情をもう少しでも知識があればもっと楽しめた気がする。5人の少女たちの不安定さや独自さが魅力となり、触れたいのに触れられない気持ち。自殺によりそれが強化され調査に乗り出す「ぼくら」が成長し続ける中で、彼女たちを忘れたら青春が無くなってしまうような感覚が切なくて温かい気持ちになる。少女たちの自殺に向かう生命力や不潔さ、そして清楚さの同居に、人って複雑で理解なんてできっこないんだって思わせてくれる文章がすごい。
1投稿日: 2022.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
狂ってるけど、綺麗。映画も見たけど、本の方が印象に残ってる。いつだって狂った親の犠牲になるのは子どもたち。狂った親が綺麗な娘たちの心を握りつぶしちゃったって感じ。
0投稿日: 2022.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ1970年代、デトロイト。リスボン家五人姉妹の末っ子セシリアが、パーティー中に二階の窓から飛び降りて死んだ。町の人びとの好奇と憐憫の目に晒され、のこされた一家は少しずつ壊れていく。遂に五人姉妹の全員が死にゆくまでを執拗に見つめていた〈ぼくら〉は、中年になり青春の思い出として彼女たちを語りだす。回顧録を模して書かれた、歪んだ青春小説。 とにかく〈ぼくら〉の語り口と行動原理がキッツい!最初から最後まで「キッツ……いやキッッッツいわ……」と思いながら読み終えたのに、解説の巽孝之が語り手のヤバさに一切触れていなかったのでびっくりしてしまった。だが、「〈ぼくら〉の目を通して見たリスボン家事件の顛末」だということこそ、本作の肝じゃないのか。自殺した少女たちの心理に迫ることが目的の小説ではなく、ストーキングの加害者心理を描いた秀逸な小説として私は読んだ。 〈ぼくら〉の仲間は異常である。リスボン家に招き入れられるや否や姉妹の部屋を覗き見、トイレを物色し使用済み生理ナプキンを持ち帰ろうとするヤツ。下水道からリズボン家の地下室に潜入し、奇しくも風呂場で1回目の自殺を図ったセシリアの発見者になったヤツ。〈ぼくら〉はいつも双眼鏡で、あるいはこっそり窓の下に潜んでリスボン家を覗き込んでいる。終盤にはなんと、もっと幼い頃からリズボン家を監視するための秘密基地を木の上に作っていたと明かされる。〈ぼくら〉と一人称複数を名乗るのもセシリアの日記に基づくのだが、その日記をはじめとして姉妹にまつわるあらゆるものを蒐集し、「資料」と称して見せびらかそうとする。 五人姉妹を執拗に見つめていた〈ぼくら〉だが、当然姉妹からも見返されていたとのちにわかる。それでもなお自分たちの窃視症を棚に上げて駆け落ちの相手に選ばれたのかと勘違いする救いようのない能天気さ。彼らに対する姉妹たちの復讐は強烈だ。そして復讐の相手は〈ぼくら〉だけにとどまらないだろう。関係者のインタビューから片鱗が見ているにもかかわらず〈ぼくら〉が直視しようとしないところにこそ事の本質がある。 姉妹たちの死亡報告書を書いたホーニッカー医師は、さらりと「家族に対するいじめ」という言葉を使っている。これはセシリアの自殺のあと、野次馬たちに囲まれた日々を指しているとも考えられるが、リスボン一家がこの町に移住してきた新参者だったことを考慮するとまた異なる角度の景色が見えてくる。越してきたのは11年前、既に末のセシリアも生まれ、五人の女の子がいる家は目立ったろう。しかも父親は地元の学校の新任教師として子どもたちとその親の噂の的だったはずだ。幼い〈ぼくら〉が基地を作ってまでリスボン家を覗こうとした好奇心はそこに端を発すると思われる。 〈ぼくら〉の町デトロイトが移住者にどう接するかは、黒人やヨーロッパからの移民の扱いを通して間接的に描写している。こういう情報の出し方がとても上手い。ある意味では、リスボン夫妻はわざわざ越してきて11年かけて町に全てを奪われ、デトロイトに棄てられたのだとも言える。かつてラックスの恋人だったトリップの落ちぶれた中年の姿からしても、これはホワイト・トラッシュ的なものの考え方が醸造されていく町の空気感を書き写した小説なのだと思う。 とにかく、自分たちに責任の一端があるなどとは微塵も思わず、けれども姉妹の心理を"分析"する資格はあると考えている人間の視点を貫いて書かれている。姉妹の一挙手一投足を凝視していたことの免罪符のように自分たちがまだ童貞だったこと、そして自分たちの思いを姉妹が"わかろうとしなかった"ことを強調して怒りだす〈ぼくら〉は、今で言えば完全にインセルの仲間ということになるだろう。公民権運動後のデトロイトという舞台設定を最大限に活かしながら、現代でも変わらぬ搾取構造の強烈な痛みが体に突き刺さる、完成度の高い作品だった。
1投稿日: 2021.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ末娘セシリアの自殺から始まる5人姉妹の集団自殺が描かれている。預言的と書かれてあるがそこに現実批判(吟味)による倫理を読み解かなければならない。 集団自殺だからといってタブーにすることは当然意味がない。ただ未来に向かって現実を批判する時この集団自殺を突き放して見る視点があればいいのだろうと思いました。そういう視点を得ることがこの本の良さだろうと思います。坂口安吾で言えば故郷(ふるさと)かなって、没落していく雰囲気は一瞬フォークナーっぽく感じたけど、男の子の視点というところが自己批判の甘さがあると思う。そういう設定だから別にかまわないけど。お互いに循環論証になっていて止揚できないというか批判できない部分があると思います。そこが世界文学になれるかどうかの瀬戸際のような気がします。
0投稿日: 2020.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ暗すぎる話で我に帰るのに時間がかかった。 ヘビトンボの幼虫は川に網を入れて掬うとヤゴなどと一緒に捕まえられたが、見るからに気持ち悪く、羽化するとますます胴長で嫌な感じになる、さすが昆虫に強くても余り好きな虫ではなく、これを題名に使った作品は想像どおりだった。 ちょっとひるんだが図書館にあるし、予約してみたら、折り返し来たのでビックリ、やっぱり読む人は少ないのかと思いつつ、図書館本優先で読んた。 手首をきったが見つかって、一命を取りとめていたリズボン家の13歳の末娘が窓からとびおりた、塀の上に落ちて助からなかった。 5人の娘はみな年子だった、こういう家庭は珍しいが、ない事もないだろう。両親は厳格過ぎるほどだったが、5人いれば自分たちだけの世界が作れる。それぞれの性格にあった暮らし方で、貧しいながら学校にも通っていた。 美人ぞろいで、近所の男の子の関心の的だったが、ひとり目が自殺した後、一時残りの娘たちは、自分たちだけの世界の閉じこもってしまった。次第に落ち着き周りには正常に見えてきた。だが母親は何もしなくなった、茫然自失というふうで、数学教師の父親も勤めには行くが次第に奇矯な振る舞いが多くなってクビになる。その頃は、姉妹も家庭の鎖からは解かれたようだったが、それぞれの輪の中からは出てこなくなった。家は荒れ、姉妹は閉じこもってしまった。 関心を持った記者は姉妹の心理を想像してあれこれと書きたてたが、噂も次第に静まっていった。 20年後、この騒ぎを見続けた近所に住んでいた男の子たちは、そのとき姉妹を助けようとした、いざ出発というとき、残りの娘たちもそれぞれの方法で自殺していた。 なぜなのか、助けようと努力した男の子たちはいつになっても衝撃から抜けきれない。 ありそうもない美人五人姉妹の自殺が、最後のシーンだった。そこに至るまでには、穏やかに見える日もあった、だが様子を窺っているとひとりの娘の奔放な生活が見え、中には信仰に生きている娘も見える、また自分の美しさに酔っているようでもある。性格は違うが、閉ざされた中で、異常なことを異常だと感じない、もう学校にも行かず家の中の暮らしがたまらなく暗い。 娘たちの青春、それを見続けた男の子たちの青春は、最初の末娘の自殺から宙に浮いてしまった。 中に入れば姉妹の日々はそれなりに過ぎていったのだ。外の生活を知ってはいるがいざ外に向かって拓かれるときが来ると、明るいものよりも妹が飛び込んだ闇の中がふさわしく思えたのかもしれない。 死者は残されたものに悲嘆と諦めを残して去っていける、だが若い姉妹にとって末娘の死にざま、痛ましさ、醜さに出逢った衝撃は、既に一部が壊れるのに十分だっただろう。時がたてばそれは美しい死に変われるものだろうか、成熟過程の不安定なとき、それを青春物語にして、成長過程の不安定さに持ってくるのはいい、死に憧れたのか?それも間違いではない、事件があった家で残りの年子たちが一塊になって身を守ることは十分考えられる。両親も生きることを放棄して娘たちにも関心がなく、何くれとなく世話を焼いた近隣の人々も、リスボン家はそういうものだと見慣れてしまう。 作者は何を言いたかったのか分からないが、残酷で惨めで恐ろしい。青春の痛み?厳格な両親に対する反抗?これを読みとれというのだろうか、こうした結末にいたったという物語は十分に書きつくされているとは思うが。
0投稿日: 2019.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
昔購読していたファッション誌のモデルさんがおすすめしていたのを見て以来、ずっと読みたかった作品。姉妹の部屋に吊り下げられた十二宮のモビール、ブラジャーの引っ掛けられた十字架といった印象的なモチーフが次々登場し、読んでいるこちらも段々と幻惑されられていく。最初の自殺の日から放置されたままのパーティー会場で、ピニャータのように吊り下がった死体を発見するシーンは鳥肌。ぜひ映画でその映像映えを堪能したいところ。70年代アメリカのティーンエイジャーの鬱屈した生活の中で、ひたすら死に引き寄せられる姉妹と彼女らに性欲を抱きつつ助け出したいと望む「ぼくら」の対比が美しい。
0投稿日: 2019.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ次々と、そして淡々と死んでいく姉妹。そんな姉妹を崇拝しながら、どうすることもできなかった少年たち。掴みどころがなくて儚くて幻想的。
0投稿日: 2017.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ雲霞に似た昆虫、蛇蜻蛉が湖から湧き上がって町を埋め尽くす初夏に自殺した リズボン家の五人姉妹について、後年、大人になった「ぼく」たちが回想し、 それぞれが知るエピソードを繋ぎ合わせて彼女らの死の謎に迫ろうとする。 舞台は明示されていないが、作者の故郷ミシガン州の町で、 彼が思春期の真っ只中にいた1970年代半ば頃の設定と思われる。 金銭トラブルや痴情の縺れによる殺人はどんな場所でも起こり得るが、 犯人が語る動機が他人には釈然としない、不条理かつ凄惨な事件は ゴミゴミした場所より整然とした小ぎれいなベッドタウンで発生しやすい ……と述べたのは誰だったろうか。 この小説の中では他者への暴力は描かれないが、そんな、 岡崎京子「GIRL OF THE YEAR」(角川書店『チワワちゃん』収録)の 主人公のモノローグで > そこにはショートケーキのようなウソくさい家がラブリーに建ち並んでいる と称されたような郊外の住宅地で、 十代にして人生に行き詰まりを感じた少女たちが自殺していく暗澹たる物語。 「ぼく」らは彼女らを救いたいと思い、不器用ながら手を差し伸べようとしたが、 彼女らはそれを恐らく理解しつつ、 「ぼく」らの手を握り返すことなく旅立ってしまった。 「ぼく」らも彼女らと同年代の、まだ子供で、 彼女らの苦悩を受け止めきれないことを承知していたからだろう。 少年たちでもなく、きれいごとや理想論しか言わない大人でもなく、 彼女らと同じ「生きづらさ」を感じながら抜け道を見つけて生き延びた、 若干知恵をつけた少し年上の「おにいさん」「おねえさん」が近くにいて 支えてくれていたら、こんな悲惨な事態にならずに済んだかもしれない。 「死」以外に脱出口が見出せないほど現状が辛いなら、 死なずにその場から逃げ出すのがベストな選択だと思うが、 少女たちには逃亡を図ることもできなかった。 痛ましい。 ところで、長い時間が経って、すっかりおじさんになった「ぼく」らだが、 思い出の中の、 性衝動をどうにか抑えて日々を過ごしていた青臭かった時代の行動は なかなか気持ちが悪い(笑)。 リズボン姉妹が使っていたバスソープの銘柄を知るや、 同じものを買ってきて香りを確かめた(p.66)だとか、 女の立場で言わせてもらうと「豆腐の角に頭をぶつけて××!」 といったところ。 五人姉妹それぞれに独立した美点を認めて好きだと思っている、というより、 彼女らを一塊の「女(になろうとする生き物)」なるオブジェと捉えている風で、 「十三歳の女の子だった」ことがある身として生理的に許し難い。 現実には、こうした男子のバカさ加減と女子の頑なさが、 ある時点で互いに軟化し、折り合って、自然な恋愛感情として発酵していくのだが。 原題は The Virgin Suiside で、ソフィア・コッポラによって映画化された。 機会があったら観てみたい。 しかし、この邦題は長いが見事。
7投稿日: 2017.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ想いや感情を記すには言葉が少なすぎる、を地でいった作品。映画と小説の、それぞれ優れた部分があるけれど、少年達の心情の吐露に関しては小説の方が上だろうな。
0投稿日: 2016.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログものすごく退屈でつまらなかった。それはもうものすごく。単純に好みの問題なんだけども。自殺した五人姉妹について<回想する近所の(元)少年の視点と内面>というのが駄目だった。姉妹たちの内面が描かれるものかと期待した私が完全に勘違いで間違いだったんだけど。村上春樹を読まされてる感じ(読んだの10冊もないけど)。苛々したけど、でも読み切った…。こんなに向いてない本を手に取ってしまったのは久しぶりだ…。
0投稿日: 2014.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいるうちにどんどん息苦しくなってきて、どうしても長時間通しで読むことができませんでした。 細切れに読んでは休み、読んでは休み。 次々に自殺したというわけではなく、最初に末の妹が自殺し、その後残された姉妹たちが何とか自分たちの置かれた状況を打破しようとしたけれどそれはならず、最後に手段は別々でも同時に自殺したんだと思う。 環境に適応できなかったのは五人姉妹ではなく、親のほうだったのだと思うのだが、危険の多い世の中に子どもを送り出す不安は私にもわかる。 できることならば目の届くところにずっと子どもをおいておきたい。 でもそれはできないことでしょう? 出来ないことと、普通はあきらめるでしょう? 必要最低限の人間関係しか認めない。 家族のなかだけで完結しようとする両親。特に母親。 ボーイフレンドどころか、女の子の友だちもいない娘たち。 男の子に対する興味はあるけれど、デートの仕方も分からない、お洒落の仕方も分からない。 とりあえず家にいさえすればいいのか、家でお酒を飲みタバコを吸う少女たち。 そして外の世界に憧れる。 最初は見知らぬ世間に対する恐怖と嫌悪だったのかもしれない。 内側に内側にと向かう母の心は、最後は生きることへの無気力?無関心?あきらめ?みたいな感じになっていって、父親は職を失い、子どもたちは学校をやめさせられ、買い物に行くことも家のなかを片付けることも食事を作ることもしなくなる家族。 物はくさり家具は焚きつけになり。 「ここから連れ出して」というSOSは、結局自分たちの絶望に踏みにじられたのだろう。 少女たちは彼女たちを連れ出しに来た近所の少年たちの気配を感じながら死んでいったのだから。 世の中に希望を持てない、そういう時代だったのかもしれない。 親の束縛が堪えられない、そういう年頃だったのは確かにそうだ。 だけど、ではそういう子どもたちがみな自殺を企てるかというと、もちろんそんなわけはなく。 私はただ、リズボン家の孤立した、廃頽した家の空気がたまらなく堪えがたかった。
0投稿日: 2014.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を10代の時に読めて良かったと思う。 小説の後に映画を観たが、小説の場面をたどたどしくなぞっているだけ、という印象で、小説を読まずにこの映画を見た人はどんな話か理解できるのか?と疑問だった。 少女たちに音楽をプレゼントしてあげる場面で、一番重要な「明日に架ける橋」をカットしたのも意味不明。 映画でなくて、この原作の魅力がもっと広まってほしい。
0投稿日: 2014.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログバージンスーサイズとしてコッポラの映画を見たのが先だった。 素晴らしく幻想的でガーリーでその自殺さえもフリルにある刺繍のひとつであるかのように描かれていて、小説はどうだったんだろうかと。 コッポラは女性で、この小説を書いたのジェフリーは男性だった。 アプローチとしてもそのようになっていた。 つまるところ、これには近くとも深い断絶があり そのひとつが女の子と男の子のあいだにあるものだった。 ただそれに仮託されたのが社会の断絶でもあったので コッポラとジェフリーが対岸から書いてもいまだ同じ作品であった。 自殺と対極にあるのはカトリックなんだが、これはやや日本人としては捉え損なうかもしれない。 ただ、心性として僕らも一神教的な世界に近づいているとすればこの世界における自殺と同じようにそのおぞましい求心力を感じることだろう。ただそれ自体としては潔癖であるにもかかわらず。
1投稿日: 2013.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ヴァージンスーサイズを見てから読んだので、おおざっぱな話や登場人物はだいたい頭に入った状態で読みました。映画のほうは女の子たちのほうにクローズアップがされていましたが、こちらは語り手である男の子たちや、映画で拾いきれなかった細かい事柄がきちんと説明されていたので個人的には原作のほうが好きです。特にクライマックス~エピローグに至るまでは小説のほうが密で、いくつもの絶望(年月の経過、街の退廃など)が重なっていき少女たちの死が覆い隠されてしまう過程がわかります。あと、映画のタイトルが何故「ヴァージンスーサイズ」であるか、ということは原作のほうが分かりやすいです。
0投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この手の翻訳は苦手。 青春小説だった。 もっと暗くて、 ドロドロしたものかと思って読み始め、 どちらかというと、 彼女たちに恋をした男の子たちの目線で、 彼らの青春に、五人姉妹の 自殺が入り込んだようだった。 本当に人一人がはなしの中で 死んだのか分からないくらい、 周りの心理描写が薄く、衝撃もない。 彼らが序盤で言っていたように、 彼女たちは一つだったのかもしれない。
0投稿日: 2013.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「マリッジ・プロット」がおもしろかったので、古本屋で購入以来、放置してあった同じ著者のこちらも読んでみた。一見エキセントリックな10代の五人姉妹(とその両親)を描きつつ、彼らを取り巻く地元コミュニティの人々の様子も描き、当時のアメリカ郊外の閉塞的な雰囲気がとても伝わってくる。巽孝之氏の解説がまたおもしろい。著者はデトロイト郊外出身とのことだが、映画監督のマイケル・ムーアも同じミシガン州の郊外出身で同世代だな〜などと思ったりした。映画は未見だが巽先生がぜひ見るようにとおっしゃっているので見ようと思います。
0投稿日: 2013.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログリズボン家の5人の姉妹が自ら命をたつ1年間の物語です。20年後に、彼女らの友人のひとりが過去を振り返っていく筋立てになっています。少女たちの死を扱っていながらも不思議と深刻さが希薄で、絵画的かつ寓話的な作品です。
0投稿日: 2013.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ淡々とした語り口が逆にリズボン家が崩壊して行く様を生々しく見せている。 訳文は硬質で、その分、客観性や語り手の無力さが際だっているように思えた。
0投稿日: 2013.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ話が横道にそれて読みずらい。あとよくわからない登場人物が多すぎる。映画化されてるそうだけどそっちのほうが良さそう。
0投稿日: 2012.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近は、登場人物が死ぬ、もしくは死んだあとが描かれている小説が読みたい。 人生を感情に納得させるために小説がある。 どれだけ読めば納得できるだろう。 優れてはいるけど、最低な気分になる小説だ。リズボン家には一筋の光も届かない。 解説によると、自殺小説というジャンルがあるらしい。どうかしてる。 でも救いのまるでない話を読むのもいいかもしれない。救いが提示されないから、自分でどうすればいいか考えなくちゃならない。 両親がいつでも背中の上にのしかかっているように感じる。彼らの重みを常に感じて、時には一歩も動けなくなる。立ち尽くして、途方にくれて、泣き叫びたいけど声も出ない。助けを求めたいけれど、通じ合う人はどこにもいない。 自分で作り出した怪物にとらわれているだけなのかもしれない。 ここから出たい。誰かじゃなくて、自分の力で出たい。 押しつぶされて死ぬのを待つのは嫌だ。重荷を誰かに押し付けて知らないふりをするのも嫌だ。 終わったことは終わったこととして、限られた人生を精一杯生きたい。それだけなのに。それだけのことが途方も無く難しい。 ともかく、リズボン家の五人姉妹よりはマシなことをしたいんだ。
3投稿日: 2012.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログバージンスーサイドの原作ぽいあなと思いつつ読み終わり、後書きでやっぱりと思いました。映画だとなんで自殺したか分からなかったけど、小説の方が自殺に至る経緯が分かりやすい。
0投稿日: 2012.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログリズボン家の最後に残った娘がとうとう自殺を図った朝もー今度はメアリイで、テレーズのときと同じ睡眠薬だったー二人の救急隊員が家に駆けつけた。その家のことなら、ナイフの入った引き出し、ガスオーブン、ロープを吊るすことのできる地下室の梁、もうどれも知り尽くしていた。
0投稿日: 2012.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ姉妹たちの生活についての描写がなかなか生々しい。 誰かにずっと覚えてもらえる、気にかけてもらえるというのは非常に羨ましいことだなと感じた。 最後の部分で作者が、自殺者は「自分が世界で一番かわいそうと思っていて、誰も自分を助けてくれようとしない」という一種の自己愛から自殺するのでは、というようなことを書いていてそこに共感するものがあった。 解説者が、この姉妹は70年代のアメリカの凋落を予言している、という点を強調していてなえる。それは、姉妹について作中の誤った理解を持つグループのうちの一つに与していることになるのではないのか。 電話越しに音楽でやり取りする場面が好き。 トリップ・フォンテインは最低。
0投稿日: 2012.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ヘビトンボが飛ぶ季節に末娘のセシリアを筆頭に次々と自殺していくリスボン家の姉妹たち。 その時のことを当時少年だった「僕ら」の視点から振り返る。 彼女たちの自殺の原因は書かれてなく、読み手も「僕ら」と一緒になって推測するしかない。 リスボン家は躾に厳しく、学校外で他人と接する機会がないため姉妹たちは周りからミステリアスで憧れの存在だった。 しかし本当は彼女たちも普通の私たちと変わらない子たち。 最初は家が厳しすぎることで将来を悲観しての自殺かと思ったが、それ以上に根本的なことかもしれない。 この世界そのものが彼女たちと合わなかったのではないだろうか? 不思議な感じで始まり、不思議な感じで終わる、とてもミステリアスだけど穏やかな話。
0投稿日: 2012.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
つかみどころがない。雰囲気とか煙みたいなものだけが漂ってる。 「生活」を感じさせない女の子たちがただ、淡々と死んでく。 触れんし、呼び戻すこともできんし、最初から会話できてたのかも怪しい。 自分らには見えんものを見て、聞こえんものが聞こえてる人らに「生活」を求められん。相手してもらえない。せいぜい、終わってから気付く。 原題は「The Virgine Suicides」やのに、ヴァージンじゃない子がでてくるけど、それが大したことではない。
1投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ権力(古くからの慣習)に抑圧される青春の脆さと美しさと、思春期特有のあいまいに漂う性に満ちている小説。権力に対する自由を描いた点でアメリカ青春小説の傑作「ライ麦畑」と共通する。だが、「ヘビトンボ」にしかないサスペンスと幻想的な香り、きっとまた、嗅ぎたくなる。
0投稿日: 2012.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者が悪いのか訳し方が悪いのかわからないが、とにかく文章が読みづらい アメリカの文化をこちらが知らないから想像できないというのもあるけれど、無意味な説明が長々と続く箇所が多く、読んでいて退屈極まりなかった この物語は小説ではなく映画向き 映画を観て原作も読んでみたいと思い手に取ったが、読まなくて良かったな 良い音楽が出てくる物語は、映画で表現されるべきなのかも
0投稿日: 2012.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルから(『ヴァージン・スーサイズ』の原作だ)と気がついて、読んでみました。 原文タイトルは、やはり映画同様に(The Virgin Suicides)とのこと。 ぼんやりと、『ヘビイチゴの季節に自殺した五人姉妹』だと勘違いして、季節は春かと思っていましたが、ヘビトンボなんですね。 ということは、晩夏の話ということでしょう。 前に映画を観た気がしますが、かなりおぼろな記憶しか残っていません。 とにかく謎だらけだったため、原作を読んで多少なりとも理解を深めようと思いました。 ただ、読めども読めども、記憶に触れないストーリーが展開します。 最後まで読んで、(やっぱりおかしい。確か、舞台はオーストラリアで、白い服の少女たちが山登りをして行方不明になる実話だったはず)と、確認してみました。 すると、それは『ピクニック・アット・ハンギングロック』(ピーター・ウィアー監督)でした。 すっかり勘違いをして読んだというわけです。少女たちが若くしてこの世を去る、という設定だけ共通していました。 結局この映画の方は、観ていなかったとわかりました。 昔ながらの、行間の少ない文庫本は、読みにくさがあり、物語世界にもあまり入り込めませんでしたが、発刊当初、アメリカでは大きな話題になった作品だとのこと。 実話を元にしたものでもなさそうです。 少年の目を通して描かれる、美しい少女たちの自殺は、なんとなく美しい印象を残すものとなっていますが、実際に考えると、相当いたましい事件。 実際に、教職についていた父親は、資格なしと見做されて、解雇されます。 社会的にも大問題となりそうですが、そういったリアルな側面にさほど触れられないため、青春物語のカテゴリーに入ると見做してよいのでしょう。 末娘がまず命を絶ちます。 初めは風呂場で手首を切り、一命を取り留めたのちには、今度は飛び降り自殺をして。 それから、残された姉たちは、一人ずつ命を落としていくのかと思いましたが、まさか全員が一度に自殺をするとは思いませんでした。 それも、末娘の自殺したちょうど1年後に、一人は首を吊り、一人は多量に睡眠薬を飲み、一人はオーブンに顔を突っ込み、一人は車の中で首にベルトを巻きつけるという、めいめいの方法で。 ショッキングです。主人公は、その光景を目の当たりにしているはずなのに、恐怖もトラウマもなく、淡々と描写しており、完全に観察者役に徹している点が、やけに非現実的です。 それほど両親に問題があったとも思えず、彼女たちの自殺の動機もはっきり明かされないままに終わる物語。 やはり謎に満ちています。 思春期の少年の語りということもあり、かなり性的にどぎつい描写もありました。 後味が悪いというよりは、結局よくわからないまま、消化不良で終わった感じ。 それは、主人公が彼女たちに対してなにもアクションを起こせないまま、悲劇を見つめていることしかできなかったからに違いありません。 無力な少年少女たち。死を選んだか選ばなかったかだけの違いで、未来に希望を抱いていないのは一緒だったようです。 主人公はすでに中年になっており、過去を思い返す形でこの物語を語っていますが、現在の生活が充実しているとはあまり思えません。 アメリカ文壇では、これが刺激的な作品と受け入れられたのでしょう。 もしかしたら、これは文章よりも、映像化されたものの方が、作品の世界観を伝えやすいものかもしれません。 内容的にあまり好みではありませんが、機会があったらソフィア・コッポラの初監督作品となる映画版の方も観てみようと思います。
0投稿日: 2012.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕たちは彼女たちをずっと知りたいと思い、彼女たちの姿・形を追っていた。 しかし、彼女たちは僕たちにそぶりを見せることなく、ただただ笑っていた。 結局、彼女たちの自殺の理由は分からない。いくら僕たちが彼女たちの記憶をたどり彼女たちに近づこうとしたところで、彼女たちの心の奥に潜むはかない感情にたどり着くことはできないのだ。
0投稿日: 2011.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ5人姉妹が次々と自殺していく。そこに隠された秘密…そんなものはない。将来への不安、理想と現実の不一致。。アメリカの歴史になぞらえた小説。でも読んでると現実に起きた話なんじゃないかという錯覚におちいる。
0投稿日: 2011.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ語り手になる少年達(もうオッサン?)の姉妹に対する視線はまさに愛です。 少年たちが持つ青春のみずみずしさ、少女たちが抱える十代の苦悩が上手いこと描かれています。 僕の場合先に映画を見てるから本を読みながら映画のシーンや音楽がフラッシュバックしてどっぷり世界に浸る事ができました。 映画では「おしいっ!」って思っていた部分も原作を読んで痒いところに手が届きました。
0投稿日: 2011.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ修飾語の多い回りくどい表現が多用されているのがいけなかったのか、説明不足で突然現れる人名がいけなかったのか、翻訳が今ひとつこなれていない感じがするのがいけなかったのか、とにかく内容が頭に流れ込んでこない本だった。一文一文理解しながら読み進めて行くことにつかれ、物語の雰囲気を感じ取ることができなかったのが残念。
0投稿日: 2010.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログもう何年も前に読んだ。 この話を知ったのは映画が先だったはず。 この本を読んでかなり映画は忠実だな…と思った記憶が。 古くさく頭の硬い親たちの子育てに犠牲になったのか… 表面的にはきっと幸せに見えていたはずだが。 窮屈な生活の中でほんの小さな喜びを見つけたり こそこそ悪いことをする女の子達は ごくごく普通なのだ。
0投稿日: 2010.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ印象的な題名を覚えていていつか読もうと思っていた本。映画化されているというのは本のカバー写真を見て知った。 70年代のアメリカの田舎町に住んでいたリズボン家の五人の姉妹。厳格なカトリック教徒の両親の下で育った彼女達は「ぼくら」の憧れの的だった。 末娘のセシリアの自殺からリズボン家は徐々に崩壊し始め、姉妹の全員が自殺という形でこの世を去ってしまう。 どうして彼女達は自殺したのかを探ろうと、大人になった「ぼくら」が回想する形で綴られた物語。少女達のことを語ってはいるが、実質のところは少年達の青春の物語だと思った。五人姉妹の中で、セシリアとラックス以外の三人の印象が薄いのが残念。
0投稿日: 2010.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画が思いのほか良かったので読んでみました。 映画は女性監督だけあって、映像美というか、小物のかわいさとかも際立ってましたが、 小説はまたガラっと雰囲気が変わって、完全男の子達の物語 最初は「なんじゃい、この邦題。失敗したかな。」と思ってたけど、 読んでみると分からなくもない。 むしろ、直訳するよりも断然良かったかも。 ただ、翻訳が全体的にあと一歩感があるかな。 内容としては只今消化中(笑)
1投稿日: 2010.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初に逝ってしまったのは、末妹の13歳のセシリア。 それから1年足らずの内に、残る姉妹も次々と自らの命を散らしていった。 美しく個性的で、秘密に満ちた彼女達に、あの頃のぼくらはみな心を奪われ夢中だった。 言葉を交わし、膚に触れ、あんなにも近くにいたのに、姉妹に差し伸べたぼくらの手は永遠に届くことはない。 ヘビトンボの飛び交う季節に、静かな謎だけを残して羽根のように淡々と死んでいった五人姉妹。 彼女等を愛した少年たちによる回想録。 ソフィア・コッポラ監督により「ヴァージン・スーサイズ」というタイトルで映画化。
0投稿日: 2010.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2007.08.07読了)(2007.07.29購入) (「BOOK」データベースより)amazon リズボン家の姉妹が自殺した。何に取り憑かれてか、ヘビトンボの季節に次々と命を散らしていったのだった。美しく、個性的で、秘密めいた彼女たちに、あの頃、ぼくらはみな心を奪われ、姉妹のことなら何でも知ろうとした。だがある事件で厳格な両親の怒りを買った姉妹は、自由を奪われてしまった。ぼくらは姉妹を救い出そうとしたが、その想いが彼女たちに伝わることは永遠になかった…甘美で残酷な、異色の青春小説。
0投稿日: 2010.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ別の本の検索をしたら少女つながりで出てきたんです。映画のタイトルだけは知ってたんだけど。 姉妹の自殺はあくまでマクガフィンで、ぼくらの街のお話だった気が。(…と思いながら読んでたら解説にもやっぱりそうやって書いてました) でも映画は機会があれば見てみたくなりました。
0投稿日: 2010.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ手を伸ばしても届かない五人姉妹と閉ざされたリスボン家の断片を集めては想いを馳せる男の子達。姉妹が選んだ自己愛と孤独と憂鬱と拒絶。そのにおいは私を包み、いつまでも捕らえて離さない。
0投稿日: 2010.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログソフィア・コッポラの映画「バージンスーサイズ」原作。 末娘の自殺をきっかけにして、伝染病のように「死」は5人姉妹の間に広がっていく。 苦しい物語。読むのが辛かった。
0投稿日: 2010.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ70年代前半、米国ミシガン州の郊外の住宅街に、五人姉妹が住んでいました。年齢は13才から17歳。厳格なカソリックの家庭に育った彼女らは、美しく謎めいていて、少年たちの憧れの的でした。 しかし、末娘のセシリアが自殺した初夏のある日を皮切りに、一家は崩壊の一途をたどり始めます。若く可憐な姉妹たちが、次々自ら命を絶っていったのです。 二十数年後、当時彼女らの近所に住み、同じ学校に通っていた少年の回想という形で物語は進んでいきます。 この小説は、フランシス・フォード・コッポラの愛娘であるソフィア・コッポラの初監督作品〝The Virgin Suicides〟として、1999年に映画化されたそうです。 ティーンエイジャーの悲しく甘美な揺らぎを綴った、すばらしい青春小説でした。
0投稿日: 2009.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画にもなった 「ヴァージンスーサイス」。 ストーリーについては、わりと 皆さんがレビューしているので割愛。 それよりも僕にとって 「映画の聴こえる音楽」。 と、カッコよく言ってみたものの 講演で話していた柴田元幸さんの 受け売りなんだけど。 リズボン家の少女達と 男の子達がお互いに 電話で自分の 「お気に入りの曲」 を流す場面がある。 ギルバートオサリヴァン「アローンアゲイン」 に始まり キャロルキング「去りゆく恋人」まで 交互に受話器にレコードの音を近づけて 相手に贈る。 僕の一番好きな場面。 こういう事なんだよなぁ、と思う。
0投稿日: 2009.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログなんでおっさんがこんなに女の子の気持ちがわかったのか教えて欲しい すごく悲しい すごくすごく悲しい 「さぁ、入れて。もうちょっとよ。それで気持ちがぴったり合わさるから」
0投稿日: 2008.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログthe virgin suicidesの元ネタです 男の人にこんなに少女の気持ちが分かるんだ、くらい細かい。
0投稿日: 2007.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログThe Virgin Suicides 甘美で残酷な響き。 痛い程の少女性を70年代アメリカの文化に併せて書き出した一冊。 終始記録的な客観視点で書かれ、ノルまでに少し時間がかかったもの、一気に読破。 映画の方も見てみようと思った。
0投稿日: 2007.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画が面白そうだったので文章から入ってみた作品。 でも文章がわかりにくい部分が多々あって難しかった。
0投稿日: 2006.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ末娘の自殺によって死に魅入られたかのように崩壊する家族の物語。エロスとタナトスが一緒くたになった暗く不安な小説。
0投稿日: 2006.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画を見てから買った作品です。かなり昔に買って読んだので、あんまり覚えてないですが、映画の衝撃が忘れられていない気がする。
0投稿日: 2006.02.12
