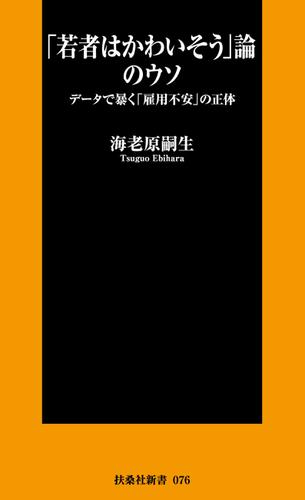
総合評価
(29件)| 2 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 fukui"powered by"
fukui"powered by"
「大卒はなぜ職にあぶれるのか」 https://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51465063.html
0投稿日: 2025.06.14 quazism"powered by"
quazism"powered by"
若者を取り巻く労働環境に関するいくつかの本を取り上げ、それぞれのデータの読み方の間違いを指摘、さらにそれらの書籍内容の一部を取り上げ、拡大解釈するマスコミの罪について書かれている。 著者の指摘は「なるほど」と思うところもたくさんあったが、いくつか「どうなの?」という箇所も。 例えば外国人労働者の25年期限付き受け入れって、普通、25年も住み着いたら帰りたくない人が多いのでは? 強制送還ってわけにもいかないでしょうし・・・ それに、世界中からまんべんなく集まればいいけど、実際は中国から来る人が多数でしょう。 湯浅さんとの会談を載せることには著者の許容範囲の広さを演出されたのでしょうか? 読むほうからすると、湯浅さんの発言のほうが説得力あるように感じました。
0投稿日: 2019.08.12 p206cc02"powered by"
p206cc02"powered by"
数字のトリックを丁寧に追う事でベストセラーの穴を追求する姿勢はカウンターとして必要だし良いことだと思うが、結論として若者は「かわいそう」ではないのか?というと、高度成長期やバブル期に若者だった世代と比較すると圧倒的に恵まれていない状況にあるという事をむしろ補完している論考になっている。
0投稿日: 2018.10.31 nikuatsu-shoten"powered by"
nikuatsu-shoten"powered by"
メディアリテラシーをつけるための本です。統計的なデータを見るときの注意事項等、勉強になります。でも、この本についても疑って読むのが正し読み方でしょうか。
0投稿日: 2017.09.23 成蹊大学図書館"powered by"
成蹊大学図書館"powered by"
「大学卒業後の将来」「働くこと」「就職」について、今だからこそ、自由に考えてみよう。タイトルは衝撃的ですが、じっくり読んでみてください。 [配架場所]2F展示 [請求記号]366.21/E14 [資料番号]2010107783
0投稿日: 2014.04.12 shiosaitoneko"powered by"
shiosaitoneko"powered by"
このレビューはネタバレを含みます。
世の中に流布するデータを再検証し、今の若者は本当に「かわいそう」な状態にあるのかを論じ、就職難やニート・フリーターの増加の本当の原因を追究する一冊。 「派遣労働者の増加により大学生の新卒採用が減少している」というのは、著者の「派遣労働者は主にブルーカラーであり、大学生の新卒採用には影響はない」という立証によって否定される。この他にも、著者は若者の雇用にかんする様々な言説に論理的に反論している。 単に「若者かわいそう」論を否定するだけではなく、きちんと自身の考えも論じているところが著者のすごいところ。ニートーやフリーターの増加については、産業構造の変化により、人とコミュニケーションをとる必要があまりない仕事(農業・漁業・林業・工場労働など)が大幅に減り、コミュニケーションが苦手な人が働ける場所がなくなったことが原因だと主張する。著者が出会ったフリーターのほとんどは、コミュニケーションが苦手そうだったという。 フランクな文章で書いているけど、けっこう読みごたえがあるし、なかなか深いところまで論じている本だと思う。
0投稿日: 2014.01.08 kurarix"powered by"
kurarix"powered by"
若者の就職/雇用に問題がないというのではなく、むしろもっと大きな問題を認識して対処すべき、とデータを使って検証。 80年代以降の地殻変動によってもたらされたブルーカラー職の減少や、サービス業による雇用代替が対人折衝業務を増やしたが、これに適応できない人が多いと筆者は指摘します。 雇用を巡る議論の背景については概ね同意なのですが、実はあまり崩れていないと本書中でも説明される日本型雇用(長期雇用、年功序列)が、サービス業と相性が良くないことの考慮が必要と評者は思うのです。 最終章の湯浅氏との対談においても、反貧困論の主眼は長期雇用確保のようであり、雇用の入り口を重視する筆者と微妙なズレが見られます。 プレゼンスを増すサービス業(筆者のいう対人折衝業務)における長期雇用への期待が裏切られ本書発行の2010年以降にブラック企業問題に発展していくとすれば、改めてブラック企業問題を踏まえた筆者の見解を読みたいところ。 筆者であれば、世代間論争や特定企業の経営問題のみに帰することなく読み解いてくれると期待します。
0投稿日: 2013.12.22 情報ドカタ"powered by"
情報ドカタ"powered by"
単純なので、この本読んで、大企業を一社も受けなかった、上場企業の内定を蹴った自分を呪ったものだ。まぁ、大企業で働けるほど社会性はないのだが。
0投稿日: 2013.10.04 komoda"powered by"
komoda"powered by"
データで暴く「雇用不安」の正体 ― http://www.fusosha.co.jp/book/2010/06216.php
0投稿日: 2013.09.21 りとる"powered by"
りとる"powered by"
グッド Raw dataに当たる重要性を再認識。 ま、世の中印象論で語る輩が何と多いことか。 某欧米礼賛の某科学者とか。
0投稿日: 2013.04.14 komaki-n"powered by"
komaki-n"powered by"
雇用の常識ででてくる数字がもう一度ってな感じで最近のニュースでお決まりの若者論や非正規雇用に対する反論が数字を交えて展開されている。主張も雇用の常識とほぼ変わらない印象もあるけれど最後の湯浅さんとの対談がおもしろい。数字のプロ・雇用主や転職者(いわば勝ち組)を知っている著者VSNPO法人貧乏人の見方って感じ(笑)
0投稿日: 2013.04.09 daisukeuchida"powered by"
daisukeuchida"powered by"
「エンゼルバンク」のモデルにもなった転職業界のカリスマによる一冊。 自身の過去の著作を宣伝している箇所が食傷気味、かつ、類似本の否定で一章を割いているのには辟易するが(だったら読むなという感じだが)、数値データのからくりなんかをうまく論破し、マスコミの取材不足や表面的な部分しか取り上げていないところをぐっと指摘している点は痛快。ここまであからさまに書いて、敵をだいぶ作ってしまわないか、こっちの方が心配になってしまうが、まぁ、余計なお世話であろう。 学歴が高い人には第二新卒もセカンドチャンスも手厚く、そうでない人にはそれなり、とか、中小企業はどこも人手不足、とか、本当か?と思わせつつも、そうだろうなぁと思う説得力があるのは、著者が現場を大事にしていて、いつも情報に敏感であるから故であろう。 すべてを真に受けるというよりは、必要な情報を選んで自分で活かす、という点では非常に価値が高い一冊になるのではないかと思う。
0投稿日: 2012.08.14 marshmallow-b"powered by"
marshmallow-b"powered by"
勉強会の課題図書として読みました。 雇用に関する様々なデータが、メディアを通して発表されています。 しかし私たちはそれに何となく目を通すだけで、どこから持って来たものなのか調べたりどんな解釈のもと報道されたのか考えたりすることは…なかなかありませんよね。 全部が全部じゃありませんが、実はとんでもない使い方をされているデータもある。鵜呑みにするのは危険だよ!自分の物差しを持とうね!ということを教えてくれる本です。
0投稿日: 2012.03.23 ayuki"powered by"
ayuki"powered by"
(2011/10/22読了)大卒の就職氷河期は、めくらましで、実際におきていることは、昭和の時代に高卒・短大卒の就職口だった仕事がなくなっているor非正規になっているということ。いやその通りでしょう。そして、製造業や建設業で減った現場仕事分の求人需要は、今や外食小売サービス業になったので、「対人折衝が不可避な仕事」が苦手な人には受難の時代、と。うん、まあそうだよね。
0投稿日: 2011.11.13 yasz"powered by"
yasz"powered by"
私はバブル世代だと認識していますが、最近の若者は就職を見つけるにしても大変だなと思っていますし、マスコミもそのような論調で報道していると思っています。そのような中で、データで裏付けられた「雇用不安」の正体を示して、「必ずしも若者は可哀相ではない」と主張している本には興味をもちました。 新規採用者数はこの20年間で変化していないこと、就職氷河期は大学数が増えたこと(p115)というのは目からウロコでした。確かに私の若かった頃と比べてみると、携帯電話があり、インターネットがあるので恵まれている面も多くあると思いますし、私の時代にも不遇な思いをしている人達はいたと思います。 なんとなく若者は可哀想という雰囲気を、このような本がデータでその根拠を示してくれるのは、私の仕事を進める上でも役に立つと思いました。 私も何となく感じていたのですが、20年以上前から年功序列や終身雇用制は崩壊したと言われていますが、転職する人は私も含めて少しずつ増えているようですが、昔ながらの制度は、この本に書いてある通り未だに残っていると思います。 また、言い難いことである、いまだに高学歴で大企業に勤めることは安定であるという、世の中で言われていることと逆行する事実をデータを持って証明している(p71)点は認識を改にしました。また正社員の定義は昔と今とでは異なる(p101)という点も同感でした。 以下は気になったポイントです。 ・日本型雇用の崩壊の間違いとして、1)昔からそれほど終身雇用でなく、現在でも昔程度には終身雇用、2)大学新卒者の正社員採用も減っていない、である(p28) ・自己信託型の給料後払いと、海外におけるピラミッドは、大学卒ホワイトカラーの雇用においてのみ適用、高卒ブルーカラーは海外移転により崩壊した(p31) ・賃金データを調査する場合、所得別の実人数を調べるならば「民間給与の実態調査」、世帯別収入なら「国民生活基礎調査」、雇用形態別の構成員数ならば「労働力調査」がある、門倉氏は世帯構成や人数把握が難しい「賃金構造基本統計調査」を使用(p34) ・若年離職率の高さは下位高卒層に起因する、上位校×大企業という、いわゆる「エリート」的組み合わせでは、今でも3年転職率は1割程度、5年後には更に下がる(p71) ・かつての正社員には、事務職での一般採用、今ならば派遣に該当するような事務請負、構内製造協力会社(非系列下請)も含まれていた(p101) ・1985年から2008年の、4年制大学・新規卒業者の正社員就職数は減っていないどころか、バブル期(87~91年)の平均31万人を下回っていない、製造・事務・販売スタッフは非正規にシフトしている可能性は十分ある(p105) ・就職氷河期になったのは、企業が新規採用を減らしたのではなく、大学をつくりすぎたことにある(p115) ・正社員を非正規に変えたという表現は、詳しく言うと、高卒もしくは女子短大卒の受け皿を非正規に変えた、ということ(p120) ・卒業後3年間での転職率は、中卒(60%以上)>高卒(40%以上)>大卒(30%程度)であり、1987年から2005年まであまり変わらない(p125) ・2008年の生産年齢人口は、1984年とほぼ同一の8178万人、正社員数は、1984年が3333万人、2008年は3441万人で増加している(p138) ・現在の非正規社員総数は約1760万人、派遣数で考えると、一般派遣(常用:84+登録:281)+特定派遣(33)=398万人、常用就労者数だと(84+80+33=198万人)で非正規全体の1割程度となる(p144) ・派遣解禁により72万人も非正規が増えたことに対して、製造業の一般派遣就労者:48万人のうち30万人程度は、解禁以前は「構内請負企業で正社員」扱いであった、これを除くと解禁で増えたのは20万人程度(p144) ・正社員と派遣社員の人件費を比較すると、34職種中31職種において平均で21%高い、それでも企業が派遣を使うのは「解雇が容易だから」(p155) ・若者を取り巻く本質的な地殻変動とは、1)85~95年にかけておきた為替レートの大変化、2)85年から続く大学進学率上昇、3)80年以降、低下した出生率、である(p205) 2010/09/05作成
0投稿日: 2011.10.19 柏葉"powered by"
柏葉"powered by"
珍しく新書などを手に取ってみたり。一~二章は「若者はかわいそう」論を流行らせた本3冊やニュースなどへの反駁。三章は対談。四章が解決策の主張。最終章は対談。 一章はベストセラー本3冊への論駁なので、対象となる本を読んでからの方が理解できそう。という訳で1.門倉貴史「ワーキングプア」、2.玄田有史「仕事のなかの曖昧な不安」、3.城繁幸「若者はなぜ3年で辞めるのか?」を読んでみる。就活も数年前に過ぎてるし、雇用問題にあまり興味がないので3冊とも読み通せるか不安だけど。とりあえず手に入れてきたい。 一~二章は「こうなっているからデータを鵜呑みにしちゃ駄目ですよ!」って感じの解説なんだけど、筆者にも騙されている気がする。四章が勢いがあって面白かった。期間限定の外国人労働者の受け入れ等は夢物語だと思うが。 本の内容より、本に対する色んな人の感想を見ている方が面白いかも。
0投稿日: 2011.10.15 tomitaro"powered by"
tomitaro"powered by"
日本だけではなく世界中で新卒者の就職難が深刻化しているが、「大学出て就職できる人の総数は減ってない。大学卒業する人がいくらなんでも増えすぎた。そもそも大学行けない人がいっているのか問題だ!」といった作者独特の説得力のある社会論。賛否両論あると思うが、大いに説得力ある。 原発問題でも同様だが、マスコミとそれに迎合して、ただただセンセーショナルにあおる連中は確かにいる。裏にあるトリックを見逃して、右往左往してはいけないねぇ。
0投稿日: 2011.09.12 深川ふらふら遊覧記"powered by"
深川ふらふら遊覧記"powered by"
ケバケバしい題名にもかかわらず、今の日本社会を正確に分析しようとしている真面目な本です。そのうえで、じゃあどうするんだよ、という問いかけにも著者独特の提案を行っている。賛否様々に意見は分かれると思うが、雇用・労働問題を真剣に議論するためのたたき台として使える本です。
0投稿日: 2011.09.01 ucchi-chiba"powered by"
ucchi-chiba"powered by"
P34 所得別の実人数を調べるなら「民間給与の実態調査」、世帯別収入なら「国民生活基礎調査」、雇用形態別の構成員数を調べるなら「労働力調査」があるはずだ。なぜ門倉本は、人数把握に適さず、世帯構成もわからない「賃金構造基本統計調査’を使って話をここまで進めるのか。それに無理がある。「すぐそこにある正解データをあえて使わない」という得意技が、根底に流れていると感じてしまう。 「日本の労働者の4人に1人がワーキングプアで、その数546万人」つまり、割り返せば「日本の労働者は2184万人?」というアラアラな数字に、なぜ誰も疑問を持たなかったのだろう。 →本や雑誌に書かれているからと言ってすべて鵜呑みにしてはいけない。そして、それらデータを、自分にとって都合のいいもの、耳ざわりのいいものだけ選んでしまっていないだろうかと不安になる。 P42表より 91年から98年にかけて大学生・大学院生は54.3万人も増えている。91年から98年にかけて常用雇用は55万人減っていると言われているが、その分大学生・大学院生が増えている、これでほとんど説明可能だ。 →都合のいいデータを利用して恐怖心を煽り立てる手法の典型例ではないだろうか。 P80 市場価値、の4文字に悩むことになる。商社マンとして4つの重要な要素は下記の通り。今の自分に当てはまるものは結構あるのではないだろうか。 ・経理、会計がわかる ・海外文化に通じ、現地での人脈もある ・小さいながらも会社の経営層を経験 ・実務にプラスして、後輩指導、リーダーシップなどの経験がある 大手のスローライフは、いつしか「とんでもない能力」を体に蓄えさせてくれる。大手のスローライフはけっこういいものだ。 だから、むやみに転職するのはやめよう。 唯一つ。転職をするとするならば、それは、社風や周囲と合わないと思った時。仕事内容ではなく、社風のほうを、意思決定の軸にすべきだ。 →自社の良さを自分自身理解しているだろうか、それを意識しているだろうか。考えているだろうか、目先の仕事内容に囚われていないだろうか。まずは、うちの良さを認識しなければ。 P105 大学新卒で正社員就職する人の数は、バブル期よりも就職氷河期の現在のほうが2割近く多くなっている。さらに、女子の数字も上がってきており、近年では2008年が女子就職者数のピークであった。(80年代後半、正社員就職者数は29.4万人、現在は37万人ほど) P109 直近10年の大手企業の採用総数は、不況期に4万人程度、好況時に10万人弱といったところ。採用総数は不況の2010年が33万人、好況の2008年入社が38.8万人、好景気だろうと不景気だろうと、大手企業に入れない人たちは中堅中小に25~30万人毎年変わらず就職している。つまり、中位校以下の学生が、「大手」を意識したら毎年「学生の超過剰」状態となるのは恒例行事なのだ。 大学が増えすぎていること、中小企業は受け皿となっていることは重要な要素点だ。 大学全入、高校全入、誰でも進学できる。入れて当たり前が常識となっているから、入社できない場合、落選時のショックも大きいのだろう。 P118 現在、大学新規卒業生の求人倍率(学生1人あたりにつき、何件の求人があるか)は従業員数1000人以上の大手企業で0.5倍程度。しかし、1000人未満の企業では3.63倍と、非常に高率となる。 →このようなデータがあると、本当に、何をもって”氷河期”と呼ぶのかとても疑問に思えてくる。 P122 一括採用のメリット ①初期マネジメント教育 毎年後輩が入社してくるため、2年目から先輩として後進の指導に当たることになる。そのため、先輩社員に指導・育成というスキルが培われる。 ②暗黙知や意思決定スタイルなどDNAが伝承 ホワイトカラー(営業や企画などは特に)製造工やエンジニアと異なり、習うより慣れろ形式で覚えて行くことが多い。これらが伝承されていく。 ③全社視点・顧客視点の養成 管理職になるまでの期間が非常に長いため、現場社員として、数多くの部署を経験できる。 ④リクルーター経験による理念浸透 P139 生産年齢人口が減れば、正社員数は減る。この当たり前のロジックを忘れていると、大変なことになる。「若者はかわいそう」論もいいが、そろそろこのことに目を向けるべきだ。 P201 「就社ではなく、就職だ」仕事が辛くても、気の合う仲間がいて、会社のスタイルも自分とあっていれば心地よいからやめはしません。規模とかブランドではなく、そんないい組み合わせが、本当は必要。 P210 決して大企業は採用を減らしてはいない。就職氷河期の内実は、大学生が増えすぎたことが第1の問題であり、第2の問題は、中堅中小企業や販売・サービス業を志望しない、という嗜好の問題がある。そして、第3の問題は大学無試験化により、小中学校の基礎知識さえ身につけていない社会人不適格な大学生の増加といったところだろう。 P216 期限付き外国人労働者受け入れ施作について →外国人受け入れ及び、25年での帰国の提案はとても充実したものであるように感じる。最終的には出生率を上げるということが何より重要なゴールだ。 P270 ほとんどの人って、高校でも大学でもクラスでチヤホヤされたり、表彰されたりしたことってないでしょう?ところが、会社に入ると仕事をあてがわれて、生まれて初めて陽が当たって、熱中しちゃうところがある。 →必要とされることにはまってしまい、会社命になってしまう人のことを表しているのだと思う。かつての自分もそうだったが、必要とされていると勘違いを起こし、自分のすべきことを見失い、楽な道を選んでいた様に思う。 常に心の片隅に自分は勘違いを起こしていないか、気をつける様習慣づけなくてはならないか。 毎年の様に繰り返される就職特集。マスコミはこぞって今の学生の就活がどれくらい”悲惨”で”大変”かを騒ぎ立てるが、一体これらの報道がどれだけ正しいのだろうか、本書を読んでそういった騒ぎに腹を立てるとともに心底呆れ返った。 種々の聞こえの良い慰めのデータ、論に頼るのではなく、真実を見据え自分を磨いていくことこそが大切。 本書からは虚構を用いて恐怖を煽ることの卑怯、自分の頭で考え、行動することの大切さを大いに学ぶことができた。
0投稿日: 2011.07.29 kamikami3594"powered by"
kamikami3594"powered by"
このレビューはネタバレを含みます。
世代間不平等、新卒一括採用、非正規雇用、ワーキングプアなどにまつわる「若者はかわいそう」という論調をさまざまなデータによって論駁した本。 確かに実情を顧みず、安易なムードで若者が語られることは多いと思います。マスコミは「新卒学生の就職率が史上最低だ!」などと他人事のように語るが、「で?それがどうした?」としか言いようがない。情報の精度もあてにならないものばかり。不安と悲惨さを煽るだけ煽って、あとは野となれ山となれ状態。 ですが、やはりこの本の総論には賛成しかねる。「本当に悲惨なのは若者よりも中高年」、「新卒で失敗しても第二新卒があるから大丈夫!」なんて論調で語られても… マスコミの語り口よりはマシなものの、あまり変わり映えはしない。 読んでおいて損はない。
0投稿日: 2011.06.18 maaizawa"powered by"
maaizawa"powered by"
世間の「若者はかわいそう」を打ち崩す論が展開されている。 若者を巡る状況に昔と今でそう大差は無い。 確かに日本の労働環境は昔とは変わっている。 しかし、メディアが大きな声を出していることで、本当に見るべき構造の変化を見逃していると指摘する。 データについては、世間に使われているものよりも信頼出来るものを出しているとしている。 が、自分で検証していないためわからない。 ただ、データの嘘の様々な方法については本書も疑いの対象としながらも学ばなければいけないだろう。 また、本書中で述べられている「期限付き移民政策」は現実的で非常に良いと感じる。 詳しくはぜひ読んでほしい。
0投稿日: 2011.06.12 bax"powered by"
bax"powered by"
このレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 就職難・派遣叩き・ロスジェネ・貧困etc.はやりの俗説は間違いだらけ! 『エンゼルバンク』のモデルとなった雇用のカリスマが解決策を大胆に提言する。 [ 目次 ] 第1章 「若者かわいそう」ベストセラーを論駁する(論駁1『ワーキングプア』(門倉貴史著) 論駁2『仕事のなかの曖昧な不安』(玄田有史著) ほか) 第2章 流布された「怪しいデータ」を検証する(「貧困率」をめぐるOECDのミスリード;多発するトンデモ「若者かわいそう数字」 ほか) 第3章 対談・教育と雇用の現場から(vs私立4大学キャリアセンター職員―就活の最前線に立つ4人に聞く、就職氷河の本当の理由;vs鈴木寛参議院議員(文部科学副大臣)―文部科学行政のキーマンに聞く、大学問題への処方箋 ほか) 第4章 問題の本丸は何か?3つの地殻変動をどう吸収するか(80年代と現在の間にある3つの断裂;地殻変動に対応するための暴論) 最終章 錯綜した社会問題に解を!(vs湯浅誠・反貧困ネットワーク事務局長) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.06.08 雀歩"powered by"
雀歩"powered by"
「若者の貧困はウソで貧困なんてない」ではなく、「若者の貧困という偏った問題意識では、より大きな貧困問題を見過ごしてしまう」という話。筆者も文中で「タイトルが誤解を生むかもしれない」と述べているが、そう思うなら副題で分かるようにすればいい。というか、主題である「ウソ」として挙げている統計のごまかし等は、本書発行時点でもよく指摘されている内容で、特に目新しい感じはなかった。 筆者の主張では正社員を幹部候補と実務職員とに分けて採用、処遇するべきというのには同感。また、公的派遣という提案はありかなと思った。最終章での、筆者の持論を湯浅さんにぶつけた対談が一番面白かったが、終わりがずいぶん尻切れトンボで残念。
0投稿日: 2011.05.26 公認会計士 日根野健"powered by"
公認会計士 日根野健"powered by"
本質的な地殻変動(社会の変化)として、 A.1985年~1995年の10年間にわたって起きた、為替レートの著しい変化 B.1985年から続く大学進学率の急上昇 C.1980年以降、急低下を始めた出生率 を指摘し、これを原因として次の7つの問題が発生したとする。 1.円高による国内製造業の空洞化→非正規社員の増加 2.サービス業(対人折衝業務)の増大→引きこもり増 3.大学進学率アップによる大学生余り・学力低下→就職氷河期 4.大卒比率アップによるブルーカラー職への志望減少 5大卒比率アップによる中小企業への志望減少 6.人口減による内需産業のマイナス成長 7.大学の破綻 である。 これを解決するための策として「教育安保政策~期限付き外国人就労者受け入れ~」という持論を展開する。 労働問題から今の日本の問題点を把握し、解決策を提示する独自の切り口が面白い。
1投稿日: 2011.03.08 koichn"powered by"
koichn"powered by"
タイトルが煽り気味なので引いてしまうが、中身はまじめな一冊。一方的な「若者はかわいそう」が空虚なウソだ、と著者は(かなり明白に)言っているのだが、きっと誤解される。
0投稿日: 2011.03.01 kofsan"powered by"
kofsan"powered by"
いつもの明快な海老原節 大卒の就職氷河期の主たる原因は、大学生の増えすぎと人間関係を要しない職業(製造業、自営業、農林漁業など)の減少
0投稿日: 2010.11.14 ejun"powered by"
ejun"powered by"
若年層の非正規社員の増加、正社員の減少、就職氷河期・・・などさまざまな切り口で語られる、若者が搾取の対象になっているという論を、一般に公開されているデータをもとにひとつひとつ論破していった上で、それら、表層的な見えている問題の奥に、もっと大きな問題があるという内容。 上記の論にはおおむね共感できた。
0投稿日: 2010.10.11 ライオン"powered by"
ライオン"powered by"
日本型雇用なんて、終身雇用なんて崩壊した。と聞いて久しいけど まだまだ世の中、新卒一括採用。著者がどんな切り口で労働市場を 眺めているか要注目の一冊です。
0投稿日: 2010.09.16 amano225"powered by"
amano225"powered by"
「若者はかわいそう」論のウソ 若者批判ではなく、若者でも大丈夫という本。城繁幸さんについて批判てきだと思ったら、ほとんど言ってることが同じだった。日本の会社がもっと流動的になればいいんですけどね。 http://amzn.to/9AZm0F
0投稿日: 2010.07.09
