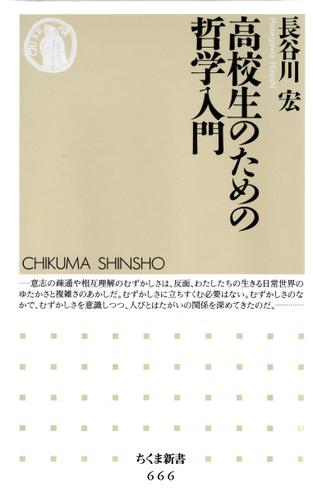
総合評価
(15件)| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
高校生のための哲学入門 どこで薦められていたかもう忘れてしまいましたが、とにかく手元にあったので読んでみました。 あまり多くは書きませんが(書く価値がない)、題名が内容と合致していません。 もし、竹蔵が編集者なら「老人の独り言」とでもします。 内容的には著者の人生や読書体験の基づいて、生きることに関してのいろいろなことを書いています。考えることがが哲学というのであれば、一応哲学はしています。しかし、あくまでも著者の思い描くことができる狭い範囲の思考です。もっと残念なのが、論理展開が強引すぎて何故こういう結論になるのか?が不明なことが多々あります。おそらく著者の中では論理的に完結しているのでしょうが、読んでいてさっぱりわかりません。 もう一つ批判したいのは、編集者や出版社の方針です。この出版社では広告を見ると”高校生の・・・”というシリーズをやっているみたいですが、そうであればはじめて手に取る高校生の真の入門書であって欲しいです。著者の主張は抑えて、哲学の歴史、重要な思想史、参考文献の解説をふまえて今をどう哲学すべきかが語られて欲しいです。老人の繰り言のような本が入門では、哲学に少しでも興味をもった若い人がかわいそうです。新書は文庫やハードカバーに比べて儲かるのはわかります。でも、シリーズ化するのであれば、内容や著者の選択などはシリーズの方針に合致した選択をして欲しいと思います。 なんか、非常に辛口の書評になってしまいましたが、出版不況といわれ多くの頑張って良書を出版している出版社が倒産するような業界にしないように、読者の期待を裏切らない本を出して欲しいと本好きの竹蔵は切に希望します。 竹蔵
1投稿日: 2024.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ2007年第一版 塾講師でありながら哲学者という変わった経歴を持つ著者。 「哲学」の入門書であり、「哲学学」の入門書ではない。 (「哲学学」の入門書は例えば「ソフィーの世界」) 世界と自分との対峙、人間存在への関心、生と死、自分とは何か? 人が生きていく上で向き合う疑問→哲学
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ長谷川さんの良心を感じた。市井の学者っているんだな。感慨深い。学問的な意味での哲学ではない。最初はなんだかなぁ、と思いながら読んでいたが(我見に過ぎないのではないかとの疑念ありつつ)、読み終えてみると、よい意味で裏切られた感じ。こころが暖まるエッセイだった。 ・平等と対等。 ・人柄への関心。 ・共同精神と死。個の精神と死。 ・死者と精神的につながることによって共同の世界が深みのあるゆたかさを獲得しえているとすれば、そのゆたかさは死の悲しさと寂しさをくぐりぬけ、悲しさと寂しさを包みこんではじめて可能となるゆたかさだ。 ・芸術的な美を楽しむには、いったんは信仰心や知識に背を向けるようにして自分の感覚に磨きをかけなければならない。 ・容易に答えの得られぬ問いをかかえつつ、現実肯定と現実否定のはざまをいきることは、精神の強さのあかしなのだ。 ・子どもとの意志の疎通がうまくいかないとき、ことばづかいを分かりやすくしたり論理を緻密にしただけではどうにもならない。子どもの日常世界をなにほどか共有し、子どもの知と思考を、観念的にもせよ、自分のうちに取りこまねばならない。
0投稿日: 2013.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「自分と向き合う」「人と交わる」「社会の目」「老いと死」 といった、人生におけるテーマ8つについて論じた本。 哲学というほど大げさなものではなく、もっととっつきやすい 人生論的な内容です。 高校生でも十分読めるけど、この本の内容を真に実感するのは もっと後になってからだろうな。 誰もが漠然と感じていることをよくここまでわかりやすく 日本語に落とし込んで表現したもんだと感心しました。 普段の生活をゆっくり振り返るきっかけともなる良書。
0投稿日: 2013.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログほとんど術語なしに書かれた高校生向けの本。あlくまでも入門書なので、ありふれた結論に陥っている感もあるが、在野の哲学者としての論考をじっくりたどるのは楽しかった。
0投稿日: 2012.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者は学習塾の講師という立場に身をおく在野の哲学者である。哲学という自由度の高い学問と、極めて実用的な学習塾での授業という両方をこなしていること自体が私にとっては興味深いものであるが、そのほかにも様々な行動を通して知の実践をおこなっている方のようである。 タイトルにあるように高校生に向けられた本書では、難しい哲学用語を極力避ける方針が貫かれている。引かれている例文も読者を煙に巻くという類のものはほとんどない。ただし、述べられていることはいずれも哲学の基本的課題というべきものばかりであった。 私は最終章の「知と思考の力」に注目をした。学ぶとはどういうことなのか、私たちは日常の学習に対して無関心であることを痛感させられたのである。学習には大学受験とか就職とか資格取得とか目的があっておこなうものがある。これがいま私たちが考える学習の大半のイメージである。しかし、利害とは無関係に純粋に学びたいことを学ぶという学習が別にある。それを追求するためには場合によっては既存の枠組みの中では難しいこともあるというわけだ。 筆者は大学からはなれ市井に身をおくことによって、周囲の人々の中に潜在的に存在する普遍的な知と思考を感じ取る。こうした謙虚さとでもいうべき態度が学ぶものには必要であることを気づかされるのだ。
0投稿日: 2012.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「自分」とは、「社会」とは。私たちの「生きにくさ」はどこから来ているのか。難解な語を排し、日常の言葉で綴る待望の哲学入門。(「BOOK」データベースより)
0投稿日: 2012.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「哲学」とは便利なことばで、何か小難しいことがあれば、何でもかんでもそれで済まされてしまうという風潮がある。 以前、友人が言っていたことだけれど「趣味で、哲学を勉強しています」というのは更に便利なことばだ。それを言うと、相手は「スゴイ!」とか「頭良さそう!」とかなるわけで。 でも、その実、そこで勉強している「哲学」というのは、昔誰かが言っていたことを暗記しているに過ぎなかったりする。ドヤ顔で「哲学では~」とかのたまっている人に限って、そういう傾向が強い。それ、別にアナタの凄さじゃないですから。 さて、そんなこんなで「哲学」の意味というのは、結局よくわからないのだけれど、本書は様々なことを考えさせてくれる。「高校生のための」と題されているが、長谷川さん自身が述べているように、別にその点に力が入れられているわけではない。もちろん、中には高校生の頭をこねくり回すような記述もあって小気味良いのだけれど。 そして、生きていく上で避けられない事々に、長谷川さんなりの見解を示していただけたということには、素直に「ありがとう」と言いたい気もする。散々悩んだ挙句、答えが出なかったようなことにも回答していただけているので、長谷川さんの見解に納得できれば、それは自分の中の一つの結論ともなる。ただ、やっぱり本書の正しい使い方は、長谷川さんの見解にナニクソと思って、自分なりの見解を築き上げることだとも思うんだ。 ところで、高校生が本書を読んで、もし楽しめなかったとしたら、それは国語教育、あるいはその指導にも責任があるのかもしれないと思ったり思わなかったり。 【目次】 はじめに 第1章 自分と向き合う 第2章 人と交わる 第3章 社会の目 第4章 遊ぶ 第5章 老いと死 第6章 芸術を楽しむ 第7章 宗教の遠さと近さ 第8章 知と思考の力
1投稿日: 2011.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「高校生のための」とタイトルにはあるが、著者も“はじめに”で書いているように、誰が読んでもいい内容です。哲学というと言葉遊びのような文章をこねくり回したり、やたらと小難しいイメージがあるけれど、この本は入門というだけあってとっつきやすい。第1章の「自分と向き合う」思春期にかけて、それまで外に向かっていた意識が押し返されて自分へと還ってくる。そこが哲学のはじまりなのかな?第6章の「芸術を楽しむ」もこれまで自分が考えていたような芸術を楽しむには知識が必要だという思い込みをバッサリ否定していて新鮮だった。
1投稿日: 2011.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ年末にふらふらして電車のったりミスド行ったりして読んでた。高校生じゃないですが。 哲学っていうと人の名前や考え方の名前から入っていきそうだけどこれにはそういうの全然出てこないです。すごい根本的なことを書いてるだけです。解決ではないし。まあそういうことを考えるのが哲学なんだよってことですね。 考えるための橋渡しにはなるかもしれないけど、ちゃんと哲学の勉強をしたい人は別の本を手に取った方がいいと思います。
1投稿日: 2011.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ著書は、「哲学」や「思想」は「個人の人生」と、どのように関わるのかを記す。答えは、「人生を楽しむ」ためというのが本書の主張である。 著者は、塾に通う子供たちと山奥の合宿や演劇祭を行い、その子供の親たちと付き合い、PTAや地域の活動など、ながい模索を経て、「まわりに気兼ねしないで自分の考えをきちんと提示する魅力的な人物」や「一人の人間の個性的な生き方を支えるに足る透明な知と思考」に出合う(p208参照)。「人生を楽しむ」哲学者・長谷川宏とその人の魅力を髣髴とさせる一節。
1投稿日: 2011.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生向きというので読んでみました。でも私にはちょっと難しくて分かりづらいところもありましたが、哲学って深いんだと思えるようになりました。
1投稿日: 2010.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 「自分」とは、「社会」とは。 私たちの「生きにくさ」はどこから来ているのか。 難解な語を排し、日常の言葉で綴る待望の哲学入門。 [ 目次 ] 第1章 自分と向き合う 第2章 人と交わる 第3章 社会の目 第4章 遊ぶ 第5章 老いと死 第6章 芸術を楽しむ 第7章 宗教の遠さと近さ 第8章 知と思考の力 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
1投稿日: 2010.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「高校生のための」と前書きしてありますが、アイデンティティーに揺れる青年期の人たちだけでなく、或る程度事故を確立したと考えて日々を淡々と営んでいる人も揺るがせる、貴重な著作だと思います。 抽象的な知と思考の在り方をどう具体化し、現実世界に生かしていくかを追求し続ける著者の姿は、宮城谷昌光作品の主人公たちの生き様を思い出させました。そのときそのとき、一瞬一瞬をどう生きるのかという問いに全身で答え(応え)ようとする身の処し方だと思います。
1投稿日: 2010.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ『自分と向き合う』 ・思春期の不安と孤独は,同時に,世界とずれた自分と向き合い,自分らしい生き方への模索と向かう第一歩だ. ・世界と自分とのあいだのずれを自覚したとき,世界に帰一するのではなく自分と向き合うことで世界との関係をいっそうの深みにおいてとらえようとするのがデカルト哲学. ・このように切実に自分の生き方を模索することこそ,人間らしい生き方なのである. 『人と交わる』 ・他人の人となりに目がいくとき,いやでもその他人と自分との違いを意識せざるをえない.自分と他人の違いと共通性をともども意識しつつ,深め,おもしろがる.それが,人となりへの興味を軸とする交わりの基本だ. 『社会の目』 ・人間は,社会的存在の不可欠の一要素として,社会の目を意識して生きていく,生きていかねばならないという事実がある. ・社会の目に従って生きる生き方と,抗って生きる生き方.前者は,社会の目がよしとする生き方と,個々人がみずから生きたいと思う生き方の間の葛藤を,社会の目のほうに力点を置いて解決しようとする生き方.後者は,個人を個として独自の価値を持つ存在ととらえる個人主義であり,近代的な考え.社会にゆとりが生まれた証拠. 『遊ぶ』 ・遊びの世界の楽しさとは何か?人は,みずから緊張状態を作り出そうとし,そのなかに自ら溶け込もうとしている.そういう気分の高揚が遊びの基本要素の一つだ.不確定の状況に身を置く不安と,自他の工夫によって不確定を確定へともたらす主体性の発現とがからまりあって生み出されるのだ. 『老いと死』 『芸術を楽しむ』 『宗教の遠さと近さ』 ・しあわせな毎日を送っている人は宗教とは縁が薄い.生きることを苦しく思っている人こそ宗教に近い人だ. ・「信じる」とは何か.日常生活では,不確かだな,という思いを抱きつつ,とりあえずこうだと決めること.宗教では,疑いのあるものを信の力によって疑いなきものたらしめる. ----------以下感想---------- こういう本を読むと,自分の感情がどこから生まれてきていたのかがよくわかる. 哲学もいいもんだ.
1投稿日: 2010.02.13
