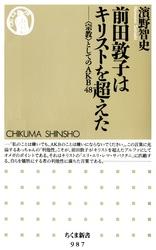
総合評価
(48件)| 1 | ||
| 7 | ||
| 18 | ||
| 7 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024年の今、私がこの本を読む必然性は全くない。しかしおもしろかった。 全体的に気が狂っているし、何を言っているのかよくわからない。ゴルゴダの丘がどうのこうのとか。何を言っているんだおまえは? しかし狂った熱量によって著者の脳が高速回転しているのはよくわかる。その結果、膨大な知識と教養が、前田敦子(と島崎遥香)及びAKB48と接続してしまっている。著者は分かってしまった。それを確信してしまった。それを書かずにはいられなかったのだ。 やはりアイドルにハマっておかしくなっている人の様子はおもしろい。
0投稿日: 2024.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ一世を風靡したAKBというグループの特異点をあげて、それが社会にどのような影響を与えるかを考察する本。著者は「近接性」と「偶然」の2つが、従来のアイドルグループと異なる点であり、それらが独特の関係性、共同体、利他性を生むのだという。今回この本を読んで、柄谷行人が唱える「交換様式」と似たものを感じ取った。資本主義社会のなかで、資本主義を真っ向から否定するのではなく、それに乗っかったうえで多くの人々(国境を越えて)に贈与する。これは数々のソフトパワーを有する日本にとって、ある種の国防戦略として取るべきかもしれないと思った。
0投稿日: 2023.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ近接性→超越性 近代 社会システムが複雑性を縮減されたうえで作動可能 独裁体制に対する民主化としての総選挙 吉本 マチウ書 ネットの匿名アンチ⇔実際に会いにくる現場でのオタクたちによる承認 貨幣→商品→貨幣 草貨幣→劇場→草貨幣
1投稿日: 2022.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2021年7月12日読了。「私のことは嫌いでも、AKBのことは嫌いにならないでください」という有名な前田敦子の、2011年総選挙でのスピーチに象徴されるAKBの「宗教性」・アイドルを超えた何かについて「近接性」「偶発性」のキーワードをもとに読み解こうとする本。「空虚な中心」ということ?圧倒的に優れたものがセンターになるわけではない運営が「アンチ」も取り込みうること、それぞれ異なる「推し」を持つファンもアンチも巻き込むシステムが「総選挙」であること、など…。ガチのAKBヲタが書いているだけあり、特に後半・ぱるる推しをカミングアウトしてからの章はキモくて読んでいられないが、筆者の主張自体は興味深く読んだ。現在の〇〇坂などのグループも、AKBシステムの発展形として考えてよいのだろうか?
2投稿日: 2021.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ2021年4月27日、記入。 前田敦子さんと勝地涼さん、離婚を発表した、とのこと。 ウィキペディアでは、前田敦子さんは、次のように紹介されている。 前田 敦子(まえだ あつこ、1991年〈平成3年〉7月10日 - )は、日本の女優、歌手。愛称はあっちゃん。 元既婚者で1子の母。 女性アイドルグループ・AKB48の元メンバー。 千葉県市川市出身。 2020年12月31日まで太田プロダクションに在籍し、2021年1月1日より、フリーで活動中。 元夫は俳優の勝地涼。 ●2023年7月13日、追記。 AKB48の第1期生として、2012年まで活動していたとのこと。
2投稿日: 2021.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ宗教というよりはリーダー論バージョンⅡって感じでしょうか...。プロダクトライフサイクルとロングテールの違いに改めて気づく...。
0投稿日: 2018.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ前田敦子はキリストを超えた・・・知らんけど、 「私の事は嫌いでも、AKBの事は嫌いにならないでください」 人類の罪を背負って磔刑に処せられたキリストにちなんで、 「ゴルゴタの丘のあっちゃん」という著者の的確な例えのセンスすごい。 AKB総選挙の始まりについてを知り、 とても興味深く、社会史との近似性を感じた。 秋元康独裁政権 → デモクラシー → 総選挙 これは学校教育に取り入れてもいいくらいの 社会学のモデルケースではなかろうか。 理屈っぽい語りによるオタ心理も読めておもしろかった。
0投稿日: 2018.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ前田敦子も卒業しているし、そのライバルの大島優子も卒業し、そのブームも一段落した現在、読むにしては完全に時期を逸したけれど読んだ。志向性を持った集団やムーブメントとしてAKB48を宗教として読み解くという試み。宗教者からは冗談じゃない。ということになるかもしれないけれど、当時の情報の中にいれば、こういう読み解きを有効にするだけの熱量があったようにも思う。あまりに難しく語りにくい事柄としての宗教をポップ・アイドルを使って客観的になぞらえて考えるのはきっかけとしては悪くない気がする。
0投稿日: 2017.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本が出たのは五年前。あまり深く考えずに手に取ったのですが、この時差がけっこう面白いかも。私はアイドル界のことはよく知りませんが、当時は的を射ていた分析も、年月が経つとまた違って感じられるかもね。前田敦子さんも結局は消費されていく芸能人の一人だったのかなあと思ったり、頂点を極めたらあとは落ちていくのが自然の理なのかなと思ったり、いろいろ感慨深かったです。
0投稿日: 2017.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのヲタぶり凄いとしかいいようがない。 アンチの存在が、スターを創るという考えは鋭い。そしてアンチに耐えられるのがヲタとメンの近接性にあるというのも納得できる。 それにしてもこの人をヲタを夢中にするシステムを考えた秋元氏の才能は恐るべし。 このシステムから外れた途端にこれまで神の存在だったものがまったく普通の人になることから考えてもシステムの巧妙さがわかる。 ヲタもメンバーもそのシステムの中で踊っているだけなのだが、両者とも幸せならばそれでよいというのがこのシステムの巧みなところ。 願わくば、システム内で踊らされる側よりもシステムを作る側になりたいものだ。
0投稿日: 2015.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ題名からして、トンデモ本であることは間違いなし。狂気の渦の中にいる人のナマの声を出版したものとしか言いようがない。
0投稿日: 2015.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルからしてブッ飛んでいる本ですが、内容には一部共感できるのは、私がAKB好きだからかも知れません。 なので、この本をオススメする方の条件は、まずAKBを好きなこと。 そうでなければ、最後のページまで?だらけの苦行を強いられることになると思います。
0投稿日: 2014.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルもすごいのですが、たとえば「はじめに」に、「AKBの不動のセンターであったあっちゃんこと前田敦子が、この現代社会において、いかにしてキリストを超える存在たりえたかについて分析する」という文があったりします。ちょっとこれほどの文は、なかなか見ることのできないのではないかと思います。 内容は、アイドル・グループとしてのAKBの特異性を、オタクの視点から熱く語った本です。吉本隆明の『マチウ書試論』やマルクスの『資本論』などになぞらえているところもありますが、自分の好きな対象と教養を結びつける、いかにもオタクらしい語りかただと思えば、まあ受け入れられるかな、と思います。 匿名掲示板をはじめとする「アンチ」の言説に取り巻かれながら、「私のことは嫌いでも、AKBのことは嫌いにならないでください」という語った前田敦子の「利他性」に、著者は宗教的な自己犠牲に比するべきものが見られると著者は述べます。その一方で彼女たちは、握手会や劇場公演では、どこまでもファンと同じ目線に立ち、一人ひとりの呼びかけにこたえてくれる存在でもあります。ここに著者は、徹底的に世俗的な次元において聖性を宿すことに成功したAKBというアイドル・グループの特異性を見ようとしています。 ファンに近いところにいて、自分たちの呼びかけにこたえることでますます輝いていくメンバーを見ることの興奮はよく伝わってきました。ただ、本書で語られるAKBというシステムの原理は、匿名掲示板などに溢れるアンチの言説が彼女たちに向けられるという現実と背中合わせになっているようにも感じます。
0投稿日: 2014.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこの著者、AKBの追っかけしてるからじゃなく、 自著の想定読者に届く言葉かどうかを全く斟酌せずに専門用語を轟々と語りまくる、その一人よがりっぷりが 正真正銘の「オタク」なんだと思った。 AKBというシステムを宗教と対比させた視点は面白い。 資本主義社会の中では、こ~ゆ~カタチでしか純愛は成立しないのかも…とも考えた。 でも、これって決して新しいシステムでもなんでもなく、郭や茶屋の女たちだって、古くは白拍子だって、同じように「女」を売って―いや売られて、商売道具にされてたんだよね。 人気があれば着飾った絵姿なんかも出回った訳でしょ? ぶっちゃけ水商売って普遍の商売なんだろぉな…。 ただ昔は買えたのは富がある者ってだけで。それが庶民まで下りてきたって事か。 貴賤貧富の差・男女の性差別が無くなった今、実際の性交渉が除外されたってだけだよね…とも思った。
0投稿日: 2014.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこじつけだなんだという意見が多そうなのだけど、アイドルとキリスト教を並べて語って共通性を見出だしていくならば、文化レベルの違いからこじつけざるを得ないだろうと思う。 というかこの話題はどう書いてもこじつけと言われるんじゃないか? 個人的にAKBについては「まぁ知ってる」くらいのスタンスで読んだのだけれど、AKBがキリスト教を越える存在になるかどうかは別として、現代社会の新しい宗教として見てみるのは非常に面白いアプローチだった。
0投稿日: 2014.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者のAKB好きがわかる1冊。というか、それ以外の感想はよくわからない。変に哲学的な表現が多くて、わざと難しく言っているのではないか?と思うほど。ただ作者が単純にAKBにはまっている。というのはよくわかる。
0投稿日: 2014.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログAKB48の魅力とは何か? なぜ前田敦子はセンターだったのか?後に『不動のセンター』と称せられた前田敦子ちゃんを徹底的に分析することによってAKB48の持つ「宗教性」をあぶりだしていきます。 『前田敦子はキリストを超えた』 このセンセーショナルなタイトルは筆者の友人であり評論家の宇野常寛氏のツイートがきっかけとなっているのですが、時代と場所が違えば恐らくこれは轟々たる批判を浴びていたであろうなぁと思いながら本書を手にとって見ました。 内容はというと、自らもまたAKB48の『ヲタ』を自認する筆者があっちゃんこと前田敦子(性格には元メンバー)と筆者自身が『推しメン』として大ファンであるぱるること島崎遥香を中心にしてとしてのAKB48を新書一冊分丸々使って語りつくすと言うものです。それにしても『識者』と呼ばれる人間に思い入れ100%の本を何冊も書かせるAKBグループはいまや巨大な『モンスター』となってしまった感が否めません。 僕は半ば距離感を置いて本書を半分ほど読み終えた頃、好きな作家の佐藤優氏がラジオでここに書かれていることとほぼそのままの見解を話しているのを聞いて、やっぱりキリスト者(佐藤氏はプロテスタント神学)からAKB48を見ても、彼女たちにはそういった側面を持っているものだったんだなと思い、改めてここに書かれている内容を読み通してみたのでした。 「私のことは嫌いでも、AKBのことは嫌いにならないでください」 前田敦子ちゃんが第三回選抜総選挙で1位を取った際、壇上で彼女が話したスピーチの内容は有名で、この中には『利他性』というものが存在すると筆者は説いております。この『利他性』というある種の『自己犠牲』はAKBメンバー1人1人の中に刻み込まれており、ついでにいうなれば第五回選抜総選挙で1位となった「さしこ」こと指原莉乃ちゃんの中にも確実にそれらが存在すると思うのです。 僕はこの辺のことをまったくわかっていないのですが、『アンチ』という存在がいて、1つはAKBそのものに対して否定的な、もしくはまったく興味の無い『AKBアンチ』もう1つはAKBの『ヲタ』のなかに存在する『AKBヲタ内アンチ』というものがあるそうで、これは昔日の会社の中にあった『派閥』のようなものだなと思っております。日ごろは『○○アンチ』や『××アンチ』といったようにメンバーやそのファンたちを非難していても、外から彼女たちの悪口を言われればガッチリと結束する。そういう風に捉えております。 しかし、彼ら彼女らがネット上に膨大な量で排出する匿名の批判。場合によっては誹謗中傷とも取れる発言の数々になぜああも耐えうることができるのか?その疑問に対しても筆者は、握手会や劇場公演などのナマで彼女たちを見る機会、さらに直接ファンとメンバーが直接交流できる機会を通じて、『ヲタ』が『メン』に大して語りかける励ましの言葉によってであるという分析は『あぁ、なるほどなぁ』と感じ入ってしまいました。 さらには、AKBグループ独特のシステムである『推し』について、第三章の『なぜ人は人を「推す」のか』で徹底的に語られており、AKBの運営は「偶然性」というものに彩られているということや、「擬似恋愛」としての側面を挙げて、彼女たちへの『ヲタ』の想いは恋愛でも性愛でもなく『恋→政=愛』という形態をシステム化させたということや、古典的なロマンチックラブの甦り、さらには彼女たちが成長していくのを「見守る」という「喜び」そして「商品」でありながら人間でもあるというアイドルのある種不思議な存在にぱるること島崎遥香ちゃんの例を用いて解説されており、その『熱さ』に思わず打ちのめされそうになってしまいました。 最後になる第四章の『AKBは世界宗教たりうるか』では 「たかがアイドル、されどアイドル」 で本当に世界宗教になるのか否かということはさておいても、ここまでのシステムを「偶然」とはいえ作ってしまった秋元康氏とわずか7人という観客からスタートし、今やその一挙手一投足までもが衆人にさらされるようになり、その中でも『傷つきながら、夢を見る』彼女たちを『推し』たくなるという『ヲタ』たちの内在的論理や行動原理は少しだけわかったような気がいたしました。
0投稿日: 2013.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
いい意味でも悪い意味でも「狂気の書」であると思った。AKBと宗教との対比、アーキテクチャとしてのAKB、といった論については、ただただ舌を巻くばかり。確かにAKBというシステムは、オウム・エヴァンゲリオン後の社会やコミュニケーションのかたちの縮図である。 しかし「たかがアイドル」――しかも、資本主義におけるモンスターよろしく大規模な搾取を続けている商品に対して、この国を代表する批評家が評価を与えている理由について、私が納得いくような回答は得られなかった。 筆者は日本のサブカルチャーやアーキテクチャの専門家であり、アイドルという卑俗なモチーフを扱いながらも有名な学者の言を引用しながら論を進めたり、自らの専門分野から鋭い指摘をしたりと、内容のおよそ半分は冷静な態度であった。しかしAKB自体に論が移ると、意図的かどうか分からないが明らかに冷静さを欠く。そして最も肝心な、「人はなぜAKBにハマるのか」という点については、偶然性によって出会った(一目惚れした)「推しメン」との疑似恋愛でしかないと言う。 ただただ納得するしかないが、じゃあ「普通に恋人を見つければ?」というツッコミ一つでこの本の価値は裸の王様になってしまうであろう。 もちろん恋人や配偶者がいてAKBにハマっている人もいるだろうから一概には言えないが、少なくともAKBを「恋愛弱者」の側から語るのか、そうでない側から語るのか、そのことで何か変わるのか、ということはかなり大きな問題であると思うので死生観云々よりもそっちを重要視してほしかった。 大体、偶然性によるつながりを量産するシステムってそんなに新しいのだろうか?濱野氏には、世界の中でも安全かつ多様に発達した、日本の性風俗産業にハマってもらい、同様の規模・視点から一冊書いていただきたい。皮肉でもアンチでもなく期待を込めて「マジ」で。
0投稿日: 2013.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログあるWebニュースで次のような見出しが躍った。 「『宗教上の理由』で休日出勤が免除されるなら『アニメ』『アイドル』イベントも認められるべき?」 この議論は既存の宗教界に波紋を投げ掛けている。一方は「神」への信仰、もう一方は「ネ申」への信仰である。そんなイベントが宗教的理由と同等とされるはずがない、というのは宗教界側の理論であり、オタ側の理論とは真っ向から対立する。 書評子は決してAKB48なるものが好きなわけではないが、しかし若者たちを虜にし熱狂させるあの“現象”が、どのようなシステムによって成り立つのかという意味において大変興味深く捉えている。オタにとってアイドルは趣味の領域を超える存在である。もし彼らが「生きるにも死ぬにも唯一の慰めがAKBである」と公言するなら、その者たちにとってAKBはある種の宗教となる。 本書の著者 濱野智史はNHK NEWSWEBのコメンテーターなどを務める若手の社会学者である。要点をまとめるとこうだ。メンバーの前田敦子は最も人気があったがアンチも多く、匿名からの激しいバッシングと口汚い罵りに曝された。しかし彼女は、AKB総選挙で1位を獲ったにもかかわらず「私のことは嫌いでも、AKBのことは嫌いにならないでください!」とアンチに向かって懇願したのであった。 著者はこれを「自らを犠牲にしてでも利他性に生きようとする超越的行為である」と受け止め、ここにキリストを垣間見たと述べる。著者は「キリストが背負った原罪に比べれば前田敦子の方は人類史的に見てはるかに軽い」という前提で論じており、全体的にいうならば、題名のインパクトとは異なり冷静な分析をしているといえるだろう。 書名を見て眉をひそめる必要はない。Amazonの古本だと300円程度なので、興味があれば是非。筆者は250円で購入した。(C・M)
0投稿日: 2013.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ【動機】AKB0048の参考資料として。 【内容】社会全体を語るためにシステムの外(アーキテクチャ)に注目し、AKB48のアークテクチャや宗教としての側面をレポを交えて解説している。 【感想】「近接性」を重視する論調が「在宅」の身としては共感しづらく、興味深かった。
0投稿日: 2013.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ今までもいろいろな出版をうぃている著者だから、新書の形で出版が許されたんだろうか。同じ本を他人が書いても出版されていなかったんじゃないかなと思う本だった。だから、評価はよくないです。 近接性、偶然性、それに、アンチの迫害性をキーワードに、社会学を専門としている著者らしい著名な書物や理論などを駆使しして、AKBは世界宗教となりうり、その穴Kで前田敦子はキリスト教のキリストになるということだが、まあ、学者先生が分析するとこんな風になるのかなと感じかな。AKBヲタらしい、当時の経験談などは読みながら笑ってしまいましたが。 ちなみに、大きな物語として、マルクス主義が進歩主義に近いことを再確認したりと別な意味で社会学の理論を確認したり、キリスト教の「預言」が正しい表記なのですが、本書は「予言」と書いてあって、宗教的にはあまり強くなく、社会学者の面が強い著者だと思いました。
0投稿日: 2013.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的な経験ってのは否めない。 AKB白熱論争は対談だからただファンの会話を楽しむみたいなところがあったけど…。 なんにしろタイトルが過激すぎ。
0投稿日: 2013.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログAKBが好きで、アイドルファンだからこそ、あっちゃんは偉大で健気なセンターであることは知っているが、信者の「神をも超えた」とする過大評価は読んでてただ気持ちが悪いだけ。 読みながら「早くゴミ箱に捨てたい」という葛藤と戦っていた。 非常に稚拙で気持ちの悪い新書だった。
0投稿日: 2013.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログいままで読んできたアイドルを論じた本の中で一番肌にあわなかった。アイドル好きの私でも、ちょっと気持ち悪さを感じてしまった。 自分は基本的に認識されたくないヲタだからかもしれない。認識中毒だったら、こういう高みに登れるのかもという羨ましさもある。 「そして筆者はいま驚いている。あのぱるるに「認識」されていることが、これほどまでに自分を律しうるということに。ぱるるに知られてるのだから、正しく生きなければならなぬ。そういう思いが強く溢れでてくるのだ。」
0投稿日: 2013.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこんな本が出るねんなあと思いつつ、AKBをちょっと理解できるかなと読んでみました。 終始高いテンションで進んでいく。筆者がAKBをめちゃくちゃ好きであるのはわかった。 文章のなかでときどき、それは言い過ぎやろうというものもあった。 AKBが宗教であるゆえんは、「近接性」と「偶然性」らしい。 通読してみても、なんとなくわかったような、わからんような、というような感じ。 AKBか、まあ、自分はこれからも好きにはならないと思いますが、今後どうなるか、楽しみにしてます。
0投稿日: 2013.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルは編集者が付けた釣りだと思ったが、どうやら違ってたようだ。著者は本気でそう思っており、それについて書かれている。 著者の言いたいことはわかる。 本書の読者はアイドルはおろかAKBも名前くらいしか分かっていない人であろう。それらの人向けにはこれである程度伝わったかと思う。 だが本当の意味ではアイドルにハマったことのない人に伝わっているのかは微妙だろう。 著者は現役のAKBヲタである。 私はというと、ももクロでアイドルにハマり、そこから他のアイドルにもハマっているKSDDである(AKBにはハマっていない) 著者はAKB以外のアイドルには興味が無いように思われる。 本書に書かれているAKBにハマる理由やアンチの存在。これらについては他のアイドルにもそのまま当てはまる。(AKBファン内アンチには当てはまらないが)そのため本書の内容だけではAKBの特異性を語られているとは思えない。 AKBから他界(他のアイドルに流れたりしてファンを辞めること)した人の話しを聞いたり、他のアイドルの現場(イベントやライブ)に行ってみて、そのファンと話たりしてみて改めてAKB論を語って欲しいと思う。 また違った切り口になって面白いものになると思う。 ■この本を知ったきっかけ 本屋で見かけて。 ■読もうと思ったわけ タイトルと帯に惹かれて。 帯は「ハマれ。さらば救われる!」 そして、ちくま新書でこのタイトルだったから。
0投稿日: 2013.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ第一印象はすごいタイトルの本だなと思った。笑 良く出版社側が許したなと。キリスト教側やらAKB側から批判されるのは目に見えてるのに。 本書はAKBの宗教性を分析したものであるが、ここでいう「宗教」とは、普通の宗教とは定義が異なる。近接性と偶然性を持ち合わせていることである。普通の宗教は自分とは関われないような人たちが(超越性)、世の中の事象を捉えようとする教えという風に定義できるのかな。(死生観がないことについては、あとがきで言及) つまり、AKBメンを押すこととキリストを信仰することを同質と捉えているのが最大のポイント。 それでいて、普通の宗教とは違う、近代資本主義的な宗教としてAKBを理解している。 まあ、筆者はAKB大好きなんだなあと思った。筆者いわく、次世代センターはぱるるらしいよ(^^) ここの理論は大雑把すぎてワロタw
0投稿日: 2013.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ思想的なことは難しくてわからないが、単なるヲタとしての生き様はところどころ笑わせてくれたところは★★★。 だが、本書を読んだのはちょうど、AKB48メンバー峯岸みなみさんの丸坊主騒動後のAKBバッシング時期。 自身でAKB48の持つ「宗教」性を強調していたにも関わらず、ネットや実社会でのAKBに対する猛烈な批判やバッシング--「迫害」--に対する言論による反論--「殉教」--が見られなかった。 本書の持つ説得力も薄れるというものだ…ということで大甘で★★に減。
0投稿日: 2013.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容としては、なぜAKBファン(オタ)になるのか。AKBがファンを虜にする仕組みと関係性について書かれた内容になっている。 筆者の更なる言及と、もっと幅広いメンバーについて、新書以外で読んでみたい気もしますね。
0投稿日: 2013.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログざくざく読む用に図書館で借りて読んだ。 哲学の知識持ってたり、古典との比較をすらすら出来る人はなんでも武器に出来るんだなあと思って感心した。ウェーバーを読みたくなった。 前半は結構しっかり読み込んだ。 アンチの受け皿としてのセンター、似非贖罪の象徴、ゴルダの丘としてのセンター、のあたりの話がおもしろかった。 後半は流して読んだ。ぱるるさんはぐぐって拝見しましたが、かわいいですね。 なんか「AKBのなんとか論」みたいな本書けば出版してくれる気がしてきた。 ぼ、坊主騒動とかがある前に借りてきてたんだからね!
0投稿日: 2013.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん、途中までしか読めませんでした。 AKBファンがAKBがいかにすごいかを語っているだけ。な気がします。他のアイドルとの比較がないんですよね。なぜ嵐やももクロではキリストになれず、あっちゃんがなったのか書いていないんですよ。半分ぐらいまででですが… AKBやあっちゃんは好きだし、最後に答えはわかるかもと思うのですが、なかなか読む気になれません。
0投稿日: 2013.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしいものを読んだ。 凄く良い。 「分不相応な女の子がアイドルになれること自体が罪=罪を引き受けるアイドル=キリスト的存在」 という読み解きより、むしろその発想の自由さ、想像力の逞しさに感動を覚えた。 最近不自由でしようがないと、頭が凝り固まってしまった感が否めない人は読めばいいと思う。
0投稿日: 2013.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこの一年で最後まで読めなかった本は、石原慎太郎の「新・堕落論」と東京大学の「震災後の工学は何をめざすのか」ぐらいしか思い出せない。けれど、この本は前書きで断念してしまった。 僕はAKB信者じゃないけれど、それなりの知識はあるしカラオケで歌っちゃうこともある。そのぐらいではこの本を読む資格はなかったのか。 否。僕にとってはどうでもいいことなのに、著者にとってはどうでもよくなかったのだろう。キリストを超えた、なんて言葉は僕にはゆめゆめ使えないけれど、それを使う人の著書を読む覚悟が出来ていなかった。前田敦子か、キリストの、どっちかに、僕は立ち向かえなかった。
0投稿日: 2013.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ3年生のゼミでAKBの話しがあったので、手に取って読んでみました。とても興味深い。著者の前田敦子がキリストを超えたとする論、なるほどと思う所もあるし、ふ〜んって思う所もあったけど、もう少しこの手の本を読みたくなりました。
0投稿日: 2013.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「推し」とは何か? 絶対的なものへのコミットメント ⬇ 境界線の恣意性 ⬇ 恣意性からコミットメントへ (あえてコミットメントする) 宗教からAKBへはこういう一サイクルとなっています。 深いコミットメントを描いたここ最近の作品として 『1Q84』2009年村上春樹 『借りぐらしのアリエッティ』2010年 宮崎駿監督 しかしこの辺の作品が描く他者へのコミットメントとAKBの誰かへのコミットメントは違う気がする。 〈宗教〉としてのAKB48とは何か? 「あえてコミットメントする」から「あえて」がとれて ⬇ 「(絶対的?)なものへのコミットメント」 まで1週したということ?
0投稿日: 2013.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「キリストを超えた!」なんちゅう大袈裟なタイトルが話題になり、私もその過剰さが気になりつい手にとり、購入しちゃったw キリストとあっちゃんのとりまく状況に類似性があるのは分かったが、あっちゃんがキリストのような存在になれるのか、また超えることができるかについては結局分かんねーな。著者による「キリストを超えることができるのか」についての推測も、おもしろかったけど納得できるほど説得力はなかったかな。 それよりも読んでいて、著者が実際にAKB48にハマっていく過程を追体験できる部分の方がおもしろかった。AKBに興味がない人はなんで特別かわいくも歌もうまくない小娘におっさんがハマっていくのか理解できんだろうが、この本でファン心理が少し分かるかもしれない。また、著者がイベントで見た小さな軌跡とも言えるエピソードの数々はおもしろかった。 タイトル負けしてると思うけど、 このタイトルじゃないとオレは手にとってないと思うので、結果OK!
0投稿日: 2013.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログぜんぜんまとまってない。こじつけにも程がある。でもなんかもうAKB好きなんだろうなぁという感じはすごいする。それが面白い。それでいい。
0投稿日: 2013.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ明日から仕事だ。 この休みで結構本読めた。 その結構読めた本の中に、 『AKB48白熱論争』http://ow.ly/gvRCB と 『前田敦子はキリストを超えた』http://ow.ly/gvRVw というAKB48に関しての2冊がある。 まず、AKBという「システム」を、秋元康氏が 発明・発見・実践したことは凄いことだと思うし、 エンタメ界にとどまらず、資本主義のあり方に 風穴を開けたといっても過言ではない、 (でもやっぱり、それは言いすぎかな) とは思うけど、この2冊の議論レベルまで行ききると、 「いい大人」がくそ真面目にAKBについて あれやこれやのアプローチで語り合う、 時に政治、時に社会学的アプローチ、 これはやはり少し滑稽に見えてくる。 なるほど確かにAKBは議論に値するくらい 革命的なアイドルかもしれないが、 誰かがどこかで言っていたように、 よってたかって笑い無しで学術的アプローチを繰り出し、 論壇的に議題として語り合うよりも、 ファンの間や、ネット上や、学校や、 居酒屋や、そういった「主観」や「個人」が 偏重的に入り乱れた空間で、「楽しく」 語り合わせるモノなんじゃないか、そう思う。 だから、例えば「AKB48白熱論争」の帯にある 「なぜAKB48だけが、売れ続けるのか? 4人の論客が語り尽くした現代日本論」 ってところに、 「なんで男どもはあんな大して可愛くないよくわかんない集団に熱狂しての?マジキモい、意味わかんない」 的な論調の女性が惹かれ、 「ん?この新書の論客達は博識な大人の男達のようね。論理的にキモいやつらのことを解き明かしてくれるのかしら?どれどれ・・・」 ってな具合に本書を手に取り、 仮に読んでみたとしたら・・・ 「はぁ?なにこれ?やっぱりキモい。「AKBの運動が世界を変えていく」って何?本気でいってんの?」 という具合に、ベースとして 「引き気味で見ていたAKB現象」を さらに引きに引いて、 結果、徹底した「無関心」に、 そう、結果、AKBに対する理解が1歩も進まない、。 結果、1歩進むどころか「後退」に つながってしまうのではないか、 そう思う。想像だけど。 例えば、 俺はあっちゃんが好き。 なぜなら~だから。 このシンプルな思考を ある男子が目の色を変えて熱く語る。 ここまでは既存のアイドルと同じ、 いや、むしろアイドルじゃなくても 自分の好きな歌手(例えばミスチルだって良い)、 芸能人、スポーツ選手にも言えることだ。 これは取り立てて新しいムーブメントでは無い。 AKBの新しさはむしろここからで、 自分のなけなしの金で買ったCDに 添付された投票券で、 自分が好きなメンバーに1票を投じる。 結果、そのメンバーはメディア選抜 (簡単に言えばテレビに優先的に出れる) 入りである16位より上の順位を獲得する。 ここだ。 旧来のアイドルとの違い、 熱狂の源泉はここにある。 今までのアイドルは、 例えば、ある男子が48人いる中の一人であるA (しかもAは48人中25番目くらいの人気) のファンだったとしても、 ある男子の「Aを好きだ」という気持ちだけでは、 Aをテレビなどの表舞台に引っ張り上げる、 「グループ内における一構成員でしか無い子」 を活躍させる直接的要因には ある男子はなることが出来なかった。 だが、AKBではなり得るのだ。 「自分の1票」が確実に、Aをスターに出来る 可能性を秘めているのだ。 なぜならその票数が選抜につながるからだ。 さらに、好きなAに「握手会」で、 本当の意味で「直接」会うことが出来て、 なんなら「握手」で「触れる」こともできるし、 リアルな「会話」も出来る。 「いつも来てくれてありがとう」 「○○くん、今日も来てくれたんだね」 なんて言われた日には、ある男子は狂喜乱舞、 1枚しか買わなかったCDを5枚買うことになるかもしれない、 5票投じて、もっともっとAにスポットライトを当てたい と思うかもしれない。 このシステムを開発したことが新しかった。 一歩踏み込めば、そこから段階的に 「AKBにハマる人間」を作り出すシステム。 くらいでAKBをまじめに語るのはやめておいて良いと思う。 「あとは個々で自分がタイプの子探してみなよ。一人くらいいるはずだよ?」 くらいの紹介で良いと思う。 そこでもし、 「じゃあ俺はこの島崎って子可愛いと思うわ」 って思ったら、 次の総選挙で「島崎って子」を、 少しだけ応援する気持ちになっていることに気がつく。 そしてさらに、 ここからが男の性で、どうせ俺が応援したなら 上の順位に!って自然と思いながら中継を見つめ、 「はぁ?こいつ島崎って子よりぶすなのになんで上なの?」 とか少しずつ島崎って子を 応援している自分に気づく。 って位の楽しみ方で良いと思う。 これ以上は、 ハマる奴はCD買って投票すれば良いし、 劇場行けば良いし、ライブ行けば良い。 そうやって増殖し続けているのがAKB。 それで十分。 楽しむ奴は楽しめば良い。 長くなったけど、 別にこのシステムをくそ真面目に 学術的アプローチしてどうとかいらないと思う。 逆に気味悪さが増すだけだ。 この本を読んで思ったのは、それ。 長くなったけど言いたかったのは、それ。
0投稿日: 2013.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログキリストを超えた、というインパクトのあるタイトルはやはり大きい。 ここまではまるんだ→何でそこまで→それはこれこれ、こういう感じで、という、自分のような初心者にも一応納得できるアイドル・AKBへのハマり方を提示してくれている。 そこの表現が、かなり大袈裟(いい意味です)。 「大してかわいくない子たちが・・」と思っている人は劇場に行っていないからだそうで、間近で見ると声援を受けて輝く彼女たちの姿に、人はここまで変われるのか、と愕然とし、これはまさに宗教的奇跡とまで言い切ってしまう。 こういうところで興ざめして、拒否する読者もいるでしょうね。 AKBと宗教の類似性を論じた箇所に、役だつところあり。 会いに行けるアイドルという”近接性”がポイント。 現代の資本主義は人々を「疎外」するが、CDを買うなりすることで「近接性」を感じることができ、そこが”救済”としての意味を持つという部分。 何かにひかれる、というあまり意識していない部分も、これからはこの「近接性」が重要なキーワードとなる時代になっていくと思った。
0投稿日: 2012.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ[とりあえず要約] 「ここではないどこかに、はっきり存在するとは言い切れないが、いるとしか言えない」という否定神学が生む超越性でしか持ち得ない「贈与」を、ネットにおける匿名性が生み出す集合的無意識(アンチ)に曝されるネット身体とリアルの身体とを、絶対的「近接性」によって結束させることで得た「超越性」でもって(近接によって得た「関係の絶対性」を用いて結束させる)、マルクス資本主義における「搾取による疎外」を「搾取による贈与」に置き換えられる。贈与を可能にした近接性による超越性は宗教としか言えないのではないか。
0投稿日: 2012.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログAKBがわからない人にとっては何を書いているのかさっぱり理解ができない。 それでも10代の女の子たちが、自分よりも年上のおじさんたちのアンチに叩かれるのは精神的に辛いだろうな。まあ、それが仕事なんだからね。 私には正直さっぱり理解できない本でした。
0投稿日: 2012.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログAKB48のシステムが宗教として機能している側面を分析。 内容はタイトルほど刺激的なものではないが、無理からに吉本隆明のマチウ書試論を引いたり、いちいち面白い。 後半どんどん語り口が熱くなり、AKBのために本気で著したことが伝わってくるのもまた好し。
0投稿日: 2012.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題の書帙を読了.AKBのセンターとして超越した存在である彼女,そして彼女達,そのシステムを,著者なりの視点で,宗教,政治,社会の一部と照し合わせ論理的に思考する良書.何よりその情熱が強く伝わってくる.読み物として面白い.ちなみに,僕はあっちゃんもぱるるもわかってない.
0投稿日: 2012.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋にて立ち読みでパラパラ読みでサラリと読了 我が神、我が神、なぜわたしをお見捨てになったのですか というキリストの言葉と 私のことは嫌いになっても、AKBのことは嫌いにならないでください という前田敦子の言葉を重ね 2人に自分を犠牲にして他者を活かす「利他性」を見出したり オタクホイホイと呼ばれる握手会でのメンバーを 人間を釣る(漁をする)漁師 と評したり キリスト教ネタを知ってる奴には楽しめるムダに熱い本 でもおもろかった! 古本で半値以下になったらじっくり読もうかな…ただその頃にはAKB終わってるかも(´・ω・`)
0投稿日: 2012.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ何回震撼するねん!と思いつつも共感はできる。この本を読む数日前にNHKで深夜に放送していたAKBのドキュメンタリーを見てしまったからだ。アイドルにはまる理由がわからない、という拒絶の姿勢だとたぶん何の面白みも感じられないとは思うが、そこに共感できるなら面白く読めるだろう。でも、深みはあんまり感じなかったな。
2投稿日: 2012.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
宗教社会学専攻(修士一年)からの視点で。 宗教の構成要素とされるものは脇本平也『宗教学入門』(1997,講談社学術文庫)によれば、教義・儀礼・教団・体験の四つに大きく大別されます。とはいえ、たとえば神道など教義が存在しない宗教も存在するため、必ずしもこれがなければ宗教とは呼べないというものではないですが、AKBにおいて、存在するものの、濱野さんが語っていない部分、つまり『前キリ』を宗教学のテキストとして読んだときに大きく欠けているのが教団(ファンコミュニティ)への言及だと思います。そしてこの本は体験の記述が多い点から宗教学ではなく、神学によっているテキストとも言えます。 いったん宗教学のほうの話をすると『宗教学入門』で、宗教の機能とされているものは「補償」と呼ばれるものであります。一言で言えば、コンフリクトの解消を担うものです。なんらかのコンフリクトを抱えた人間がその解消を求めて、参拝などの宗教行動(受験の合格祈願をしに行くなど)をとる、あるいは入信を果たす。AKBには一見その機能はない、と思うと思いますが、それは早計であると思います。説明のための例としては、創価学会における座談会がよいでしょうか。これは簡単に言えば、教団員の間で悩みを語り合う場とされています(玉野和志『創価学会の研究』(2008,講談社現代新書))。語り合う場、というのはそれだけではありますが、存外に重要な場であり、社会から孤立している存在(アノミー)を生み出さない、という点で非常に重要な場であると思います。その場ははっきり言ってなんでもいい。宗教団体でも、AKBでも、家族、地域なんでも良いと思います。しかし特殊的宗教集団に入信する人々は家族や、地域といった生れ落ちたコミュニティから阻害されている場合が多いと思われます(創価学会が躍進したのは、都市部に流入し、田舎との繋がりが断絶した若年層を取り込んだことだと言われています)。生得的に得られる宗教でないもの、"わざわざ"入信をする宗教のことを特殊的宗教と呼称しますが、AKBを宗教とみた時にこれにあたることになるかと思います。AKBをこれとして話を進めますが、いわゆるカルト、と異なりAKB有効性が認められる点は市場に乗っかることにより、開かれているため、反社会的行動には移行しにくい、という点であると考えます。じゃあAKBじゃなくてもいいよね!とされると思いますが、まったくそのとおりで、つまりはAKBであることの必然性などありません(あるいはキリスト教、仏教、イスラムである必然性もまったくないと考えます)。 話が変わって、『前キリ』を神学として読んだ場合ですが、我らの神はあなたがたの神より優れている、と述べるのは自らの宗教の正当性を主張する際によく取られる手法だと思います。また書かれている内容、特に体験(レス)の記述が多いことも神学的だと言えるのかもしれません。私は神学テキストを研究したことはあまりないので、確定的なことは言えませんが、体験の記述が多く、また自らの神(ぱるる)をセンターである!と述べる濱野さんの態度は神学のそれであるといえるのかもしれません。 宗教学専攻のぼくとしては『前田敦子はキリストを超えた』かどうかではなく、AKBに宗教的な機能がある、とするならばそれはどんな部分で、また宗教にある機能でAKB(やその他コミュニティ)にない部分があるのであれば、それは宗教の独自性であり、定義である(もしくはそんなものはなくて、「宗教」とはまやかしなのかもしれない)、と最終的には述べたい。前提として『前キリ』を宗教学、あるいは神学のテキストとして読んでしまっている点は否めませんが、もし、構造的に神学テキストとして読めるのであれば、逆説的にAKBは宗教である!(「宗教」とされるものだけが宗教ではない!)という結論が導きだせるのかもしれない、という意味では興味深く読まさせて頂きました。
2投稿日: 2012.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ『AKB48白熱論争』がすごく面白かったからあれより面白かったっていうイメージじゃないんだよなあ、あとメルマガプラネッツで少し読んでたから新鮮味があんまりない。
2投稿日: 2012.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ授業でアイドルへのファン心理も信仰心と通底するとか僕も言ってるけど、宗教をカッコ付きのキリスト教でしかとらえてない本書とは、まったく立場が違うという話を今度しないと。
1投稿日: 2012.12.09
