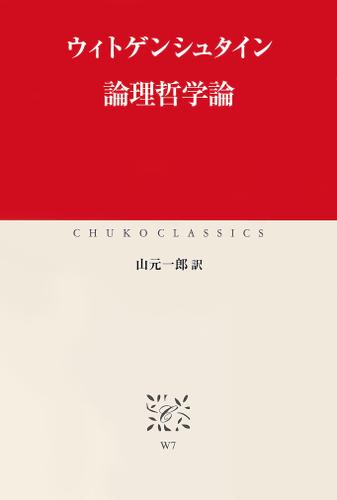
総合評価
(4件)| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
死ぬまでには読んでおきたいっていうより、読んでおかなければいけないと思ってた本。 ざっくり言えば、世界を表すのに論理学(論理学的記述)が必要で、そうして示した外側に「語られえないもの」があるってことですかね。超越的っていうか、いわゆる「神様」ではないんだけど、なんだほら、今まで哲学で問題にしてきたような、主観客観の話だとか、神の存在論だとか、生死に関するものだとか、倫理的なものだとか。 内側を語ることで、その境界を示して、そういう仕方でしか「外側」を知ることができない。その「内側の語り方」について延々と説明している感じですか? とりあえずウィトゲンシュタイン先生、6節の図は分かりづれぇわ。 この系統で一文だけ抜粋してもあんまり意味はないんだけど好きだなと思ったとこ。 6・1251 それゆえに、論理学には、驚きはありえない。
0投稿日: 2015.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「私の言語の境界が、私の世界の境界を意味する」「世界はどのようにあるか、ということが神秘的なのではない。世界がある、ということが神秘的なのである」 ウィトゲンシュタインは論理主義者であり、それゆえに神秘主義者なのでしょう。 また表現形式(連番になっている)が面白い。 「語りえぬことについては、沈黙しなくてはならない」 この最後の箇所で鳥肌がたちました。
0投稿日: 2012.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2005.10.26読了)(2005.01.29購入) 最初に30頁ほどの解説が載っている。(「二十世紀の天才哲学者 野家啓一」) ウィトゲンシュタインは、20歳ぐらいまでは、機械の構造に興味を持ち、航空工学を学んでいた。友人からラッセルの「数学原理」を紹介され、数理哲学へと移った。 「数学原理」を書き上げたばかりのラッセルの下で、学び「論理哲学論」を書き上げた。 出版された「論理哲学論」には30頁ほどのバートランド・ラッセルの序文が付いている。その冒頭で「ウィトゲンシュタイン氏の「論理哲学論」は、そこで取り扱われている諸問題について最終的真理を提供しているといえるかどうかは別としても、その幅の広さ・有効範囲・深さなどの点で、やはり哲学界における一つの重大事件とみなすべき値打ちがあります」と述べている。 論理学は、紀元前4世紀にアリストテレスにより体系化された。この体系は19世紀末まで、原型を保ってきた。論理学を前進させたのはドイツの数学者フレーゲであった。1879年の「概念記法」においてこれまでの「述語論理」に代えて「命題論理」を提起した。フレーゲの記号法は、特異で複雑であったため、理解するものはほとんどいなかった。 ラッセルは、フレーゲの真意を理解し、その真価を認めた。らっするはホワイトヘッドとともに「数学原理」(1910~13年)全三巻を書き上げ、フレーゲのアイディアを全面的に体系化することに成功した。これが現在の「記号論理学」ないし「数理論理学」の基礎となった。 ウィトゲンシュタインの「真理関数の理論」は、命題論理の体系に相当する。 「論理哲学論」では7つの命題が述べられている。 1.世界とは、その場に起こることのすべてである。 2.その場に起こること、すなわち事実とは、諸事態が成立するということである。 3.事実の論理絵とは、思考のことである。 4.思考とは、有意義的な命題のことである。 5.命題は、諸要素命題の真理関数である。 6.真理関数の一般形式は、次の通りである。(一般形式は省略) 7.語りえぬことについては、沈黙しなくてはならない。 1.~6.へことばを辿ってゆくと「世界」⇒「その場に起こること」⇒「事実」⇒「思考」⇒「命題」⇒「真理関数」と段々細かいところに分解されていくことに気付く。したがって、これを逆に真理関数から積み上げて行けば、世界にたどり着くことになる。 1.~6.が語りえることであり、7.でこれ以外のことには、沈黙しなくてはならないと結んでいる。 論理記号が使われているところは、記号論理学を勉強してから読んだほうがいいかもしれないけれど、読み飛ばしても分かりにくさは変わらないとは思う。ウィトゲンシュタインは、この本で述べていることこそ哲学であると言っている。したがって、現代哲学を学ぼうとする人は、この本を読んだほうが言いということになる。 論理学は、哲学の一分野にしか過ぎないというのであれば、論理学として読んでもいいのかもしれない。 ●関連図書 「ウィトゲンシュタイン」ノーマン・マルコム著・板坂元訳、講談社現代新書、1974.03.28 「ウィトゲンシュタイン入門」永井均著、ちくま新書、1995.01.20 「数理論理学序説」前原昭二著、共立全書、1966.06.05 「論理学概論」末木剛博著、東京大学出版会、1969.04.25 ☆関連図書(既読) 「ヒューマニズムについて」ハイデガー著・桑木務訳、角川文庫、1958.07.05 「新訳哲学入門」B.ラッセル著・中村秀吉訳、現代教養文庫、1964.02.28 「子どものための哲学対話」永井均著・内田かずひろ絵、講談社、1997.07.25 著者 ルートヴィヒ・ヨーゼフ・ヨハン・ウィトゲンシュタイン 1889年4月26日 ウィーン生まれ 19906年 ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学入学(機械工学) 1911年10月 ケンブリッジ大学のラッセルのもとで学ぶ 1914年8月 オーストリア軍に志願兵として入隊 1918年 「論理哲学論」完成 1922年11月 「論理哲学論」刊行 1939年2月 ケンブリッジ大学教授に就任 1939年4月 イギリス国籍を取得 1951年4月29日 死去、享年62歳。 (「BOOK」データベースより)amazon 20世紀前半の哲学地図を一変させた偶像破壊的な書。
0投稿日: 2010.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ野矢や黒田の翻訳は分かりやすく読みやすくしている意訳であるが この訳は厳密にしようという素晴しき意志がある。 私はこの本に出会って哲学への道へと進んだ。
0投稿日: 2008.11.03
