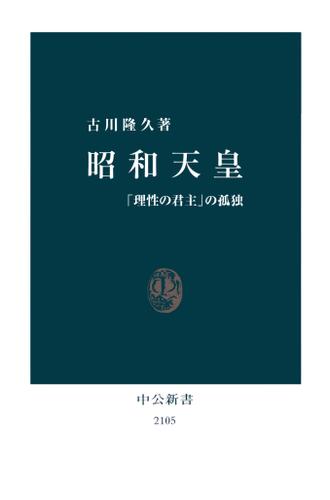
総合評価
(35件)| 11 | ||
| 15 | ||
| 6 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ旧憲法下、昭和天皇は国家統治の最終責任を負う実権ある君主として政治に関わり続けた。ときには、それなりの成果を得られることもあったが、太平洋戦争開戦を食い止めることができず、結果的に多大な犠牲を出してしまった。しかし、巨大化した近代国家では、指導者が一人で長期間適切に業務をすることは不可能である。近代国家では、君主は象徴的な存在にとどめることが、結果として君主に政治的責任を負わせることを回避させ、君主制度を生きながらえさせることにつながるのである。
1投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和天皇の、主に戦前期の生涯と戦争責任にどう向き合って来たかを題材にした本。「昭和天皇拝謁記」出版前のものでは(もちろん一般に出回っている書籍レベルの話ではあるが)一番詳細な研究がされているものではないだろうか。個人的には升味準之輔「昭和天皇とその時代」がそれまでで最も詳細かつ中立的に書かれたものと考えていたが、そこからさらに一歩踏み込んだものとなっている。 他の書籍や「拝謁記」なども読んでいるため、既知の知識も多かったが、この本で得た知見の中で大きなものが3つある。 1つは張作霖爆殺事件によって天皇の不興を買い退陣したとされる田中義一が、事件前からかなり問題のある行動を繰り返していたことである。選挙を有利に進めるためのかなり強引な人事や、政治経験がなくかつ思想的に偏りのある人物を閣内に引き入れたことについて昭和天皇はかなりの懸念を示していたし、その点について侍従や内大臣などに相談を投げかけていた。その背景を知ると単に「立憲君主として軽率な発言」とも言いづらくなってくる。個人的には満州事変以降の陸軍軍人よりこの田中義一の方が遥かに問題的な行動をしているように思う。 第二に、「拝謁記」の執筆者である田島道治が当初「天皇退位論者」として同じく天皇制継続に消極的であった芦田均によって送り込まれた人物であったことだ。「拝謁記」自体は就任約1年後の昭和24年からのものなので特に田島が退位論をぶち上げるようなことがなく、これは意外だった。本書には天皇と田島が面会し、引き続き在位することについての意見交換があった、とある。その理由については本書にも書かれているため省略するが、田島がどのような心境で意見を改めたかについては興味がある。 最後に、昭和天皇が最後まで戦争責任を重く受け止めていたことである。マスコミなどが責任転嫁の言質を度々取ろうとするも最後までその隙を見せず、自身の責任を負ってきた。簡単なようで中々できないものだ。また前述した「なぜ退位しなかったのか」についても昭和天皇が自己の責任の重大さ故に敢えてその選択肢を選ばなかったことがわかる。昭和天皇の人間性の本質がここに見えるような思いがした。 昭和天皇ほど時代にインパクトを与えた天皇は今後まず現れないだろう。立憲君主・象徴天皇としての思いや苦悩が垣間見える良書だと思う。
1投稿日: 2024.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ古川隆久『昭和天皇』中公新書 読了。立憲主義と国際協調を政治信念に持ちながらも(それゆえに)、太平洋戦争に向かうに連れて思想的に孤立していく昭和天皇。本書では、思想形成の過程に着目し、その人物像を探る。戦争責任は免れないにしろ、優れたリーダーの資質を有していたことは想像に難くない。
1投稿日: 2023.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ陸軍の暴走を苦々しく思いながらも、権限が曖昧のまま進む無理ゲー感をすごく感じました。 この時この決断をしていたらとか全くできないことが、物凄く切ない。
2投稿日: 2023.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ想像以上にリベラルな、英米協調主義な姿。最初の帝王教育の成果。戦前は、その姿勢故に日本と孤立し、苦しい立場に追い込まれる。 戦争直前は、厭世的に見え、それが後に戦争責任を問われる原因の一つになってしまったか。
3投稿日: 2019.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ古川隆久 「 昭和天皇 」戦前から戦後の昭和史を 昭和天皇の聖断(天皇の決断)とともに見渡せる本。凄い本だと思う。 昭和天皇の聖断 *張作霖事件の不手際に対する田中義一内閣の退陣→天皇の政治責任 *ポツダム宣言の受諾→国体論的な国家体制から訣別 昭和天皇の思想は 昭和の意味に込められている 昭和の意味=百姓昭明、協和万邦=世界平和、君民一致 天皇を絶対化する国体論という政治思想
0投稿日: 2018.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ原武史『昭和天皇』と併読 烏兎の庭 第五部 書評 8.31.15 http://www5e.biglobe.ne.jp/~utouto/uto05/bunsho/Hara_Ten.html
0投稿日: 2015.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ“昭和天皇”を題材にした本で、「実証的“研究”に依拠して、客観的に綴った一般向けの本」というものは、実は然程多くないのかもしれない…そんなことも思ったが、興味深く読了した。 本書は、昭和天皇の皇太子時代、青少年の頃に学んだことや経験したことにスポットライトを当てる序盤で御本人の「思想的基礎」と見受けられるものを考察した上で、昭和史の色々な事件の際の伝えられる言動を考えるという体裁の労作だ。最終的には“戦後”のこと、崩御の直前のことにまで筆が及んでいる。 本書の初登場は2011年だというが、数年を経た現在でも価値は損なわれていない。寧ろ、“昭和90年”で「戦後70年」の今年だからこそ、「昭和天皇の視点も加えた“昭和史”」という本書は価値を増すのかもしれない。広く薦めたい一冊だ…
0投稿日: 2015.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書は、多くの先行研究の結果をその性格を明らかにしつつ批判を加えていくという「史料批判」の手法により昭和天皇の実像を描こうとするもの。 これでもかと言わんばかりに羅列される種々の引用からは、天皇の絶対性を前提とする明治憲法の精神の本で、多様化する利害関係の調整を図ることの困難さが浮かび上がってくる。天皇に強大な統帥権を付与しておきながら、いざ利害衝突の段になると天皇に政治責任が生じたり権威に傷がつくことを恐れて、為政者や側近達が天皇にディシジョンメイキングをさせまいと根回しに奔走するのだ(天皇が「聖断」を下すのは田中義一首相叱責事件や日米開戦時のように、これ以上放置すると却って政治責任が生ずる、という消極的事由が存する場合のみ)。だから満州国建設の是非を巡り御前会議が検討された際など、「決定を現地軍が無視した場合天皇の権威が損なわれる」という理由で開催が見送られるなどという事態が起こる。 また、(民間科学者としての天皇の考えと決して相容れるわけではない)「国体」という鵺のような概念を天皇より実質的に上位に置いているため、その解釈如何では天皇の意向に沿わぬことも可能、という理屈がいくらでも導き出せる。畢竟、昭和天皇には実質的に追認機能しかないことになり、これでは末端が中央を等閑視するのも当然、寧ろ暴走したのが陸軍のみだったのが僥倖とも思えてしまう。 面白いと思ったのは、自然科学、特に生物学に造詣が深い天皇が、理論や理屈で割り切れぬ部分が自然界にあることを認めるのと軌を一にし、表面上は信念や不屈の意思という体裁を纏う軍部の理不尽な要求に寛容的であったとする下り。こうなると本書の帯にある「理性の君主」というよりは寧ろ、「物分りの良すぎる上司」といった通俗的なイメージが浮かび上がる。また即位時にメディアにより国民に植えつけられた大衆的でリベラルな天皇像が、戦後の平和主義的な天皇のイメージ構築に一役買ったとする指摘も興味深い。 本書の主眼は極力特定のイデオロギーの介在を排することだが、それでも昭和天皇自身の追想や側近達の手記が予め著者の描く昭和天皇像に引き寄せられて引用されている疑いは残る。しかし天皇の思想のルーツを青年期に受けた教育や外遊に求める書き振りは周到で説得力があり、またサンフランシスコ講和条約締結交渉の際の天皇の逸脱的行動の指摘など新奇性に満ちた部分も多く、総じて興味深く読めた。
0投稿日: 2015.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ平坂書房で購入する。興味深い本でした。また、非常に読みやすい文章でした。政治的介入を恐れない人物でした。これは意外でした。消極的関与ではなかったんですね。英米協調路線は明確でした。人事の面、行動ともにです。でも、うまくいきませんでした。天皇と言えでも、一つの政治的パワーに過ぎない。軍は天皇の意向を平気で無視した。つまり、軍は天皇を機関とみていたのです。これは皮肉です。また、資料は要注意だらけのようです。創作も多いようです。でも、新書を真面目に一冊読むのは久しぶりです。古本の場合、全部読むことはないもんな。新刊は全部読むよな。そんなところです。
0投稿日: 2014.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み通すのが本当に難しい本だった。長生きしたので、長い話になるのは当然だろうが、事実の羅列的で、正しくなくても、物語性(主題と変奏というか)がないと読んでいくのがつらかった。でも、日本人として、いま一度考えるのに良い本だと思う。靖国神社参拝は中止したということが印象に残る。
0投稿日: 2014.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和天皇の生い立ちから逝去までを側近の日記等を用いて実証的に整理し、その人物像を克明に著した評伝。 特に太平洋戦争前後の昭和天皇の政治的な関与に関しては天皇ご自身の発言から史実がどこにあったのか理解することができ興味深い。 皇太子時代からの英才教育を通じて形成された人格、思想が戦中、戦後も貫かれていることがよく著されている。 大正天皇の健康状態もあり、若い時分から想像以上に多面的な教育を受けていたことに驚きこと感じる。 (当時の側近の見識の高さなのだろう) 昭和天皇の政治信条は、儒教的な徳治主義と、西欧諸国、特にイギリスを模範とした民主的な立憲君主制。 また生物学にも関心を持たれていたことは神格性を自ら否定的に捉えていたことがよく理解できる。 戦中に現人神と奉られながら、陸軍と対立関係にあった事実は皮肉としかいいようがない。ある意味では大日本帝国憲法も含めた国家の制度の問題が顕在化したに過ぎないのかもしれない。 また昭和天皇すら孤立する状況を考えると世論、マスコミの怖さも改めて感じた。 以下引用~ ・杉浦重剛は、天皇が統治するという日本の国の在り方は、個々の天皇の努力によって、国民を感化し、かつ国民からの支持を得てこなければ続くことはなかったと教えた。これは当時政府が認めていた天皇観・国家観とは全く異なっている。 当時の政府の公式の天皇観・国家観とは、天皇の地位は絶対不変というものである。 ・「聖断」まで時間がかかったことは問題を残した。太平洋戦争における日本の戦死者約175万人の過半数と民間人約80万人のほとんどがサイパン陥落以後であることを考えればなおさらである。 ・しかし、国制が、薩長閥指導者たちの自由民権運動への不信感、すなわち一般国民の政治的能力への根強い不信感から、天皇の絶対性(狭義の国体論)を前提とした作られていたことは、致命的な悪影響を残した。
0投稿日: 2013.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界で皇室(王室)のある国は少ない。皇室が政治的な判断に関与すれば、責任が問われ、クーデターによって失脚し、永続しえない。「君臨すれど統治せず」は、皇室永続の条件だ。ロシアやドイツ、フランスの歴史が物語っている。日本も、6世紀に遡って世界で最も古いといわれる皇室を失いかけた。 若い頃は考えなかったが、王室のある国というのはいい。 イギリス、オランダは勿論、アジアでも王室のあるタイやブータンにも独特のナショナルアイデンティティがある。
0投稿日: 2013.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ大変読み応えがありました。自分がこれまで思っていたのは違う新しい歴史観を感じました。著者は昭和天皇の徳治主義的な政治姿勢に否定的ではないもののその限界についていくつか指摘しています。終始平和外交を目指した昭和天皇が強行的な世論から乖離し、世論により近い軍部の勢力が増長していったといいます。昭和天皇は徐々に孤立化していき、戦争への道を止めることはできませんでした。その時代の民主主義は一応機能していいたけれど、結局悪い結果しか産まなかったのです。 本書は一次資料をもとに客観的に書かれており、読み物としての「盛り上がり」はないですが、この時代の歴史に興味がある人なら必読といえるでしょう。現代を生きる私達に教訓を与えてもくれるでしょう。
0投稿日: 2013.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和天皇の伝記。 幼年期からの教育内容やその方針による人格形成など、 昭和天皇自身の人となりが何に立脚しているものかを解説しつつ、 天皇自身の発言を頻繁に引用することでわかりやすく、 かつ深く理解できる一冊となっている。 特に聖断に至る経緯はそれまでの積み重ねもあり 説得力を持って受け止められる。 個人的には最後の元老、西園寺の影響力に驚かされた。 昭和史を読み解く上でぜひオススメしたい。
0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ今でこそ違うが、かつては神格化されていた天皇を生身の人間として見ることができて新鮮に感じた。 怒る天皇、悲しむ天皇、喜ぶ天皇・・・ 国民想いで、平和主義であった昭和天皇が、時代の流れに抗いながらも避けられず第二次世界大戦に突入してしまう悲しさ。 一次資料が多いため、文面は少々読みにくいが、読む価値あり。面白い。 --- Memo i 昭和天皇ほど評価が分かれる著名人は少ない。国民のことを思い、平和を希求した偉大な人物か、それとも自分・皇室・国家の存続のために国民の命を顧みなかった無責任な権力者か。 24 (皇太子時代の)講義を通じて天皇が神の子孫ではないことを知ったこと、天皇機関説を受け入れる素地ができたことは確かである。 43 当時、日本ではダーウィンの進化論が普及しつつあった。こうしたなか、裕仁皇太子は、天孫降臨神話を否定した。 52 天皇をいただくという国のあり方(国体)は、長年の歴史の結果国民がそのように確信したから定まったのだ 55 天皇機関説によって「君臨すれども統治せず」を実現することが皇室永続につながるとしており、 75 182 儒教の徳治主義、イギリスの立憲君主制と協調外交を理想とした 184 道徳的な政治を求める昭和天皇にとって、ナチスの行動はおよそ理解し難かった 205 陸軍内の皇道派青年将校たちが決起した。日本近代史上最大規模のクーデター事件たる二・二六事件の勃発である。 304 狭義の国体論:天皇を絶対視する考え方 広義の国体論:皇室が維持されていくこと 308 昭和天皇はもともと狭義の国体論を信じておらず、国体護持のために国民を犠牲にするとまでは考えなかったのである。 311〜312 終戦への流れ 315 「戦争責任者を自分一人引き受けて退位でもして収める訳には行かないだろうか」と述べたように、昭和天皇は、最終的な責任が自分にあることを認識しており、責任の取り方として退位も視野に入れていた。 321 マッカーサーは昭和天皇に好意的な態度をとったことが外務省の記録からわかる。 394 昭和天皇は、戦後の後半生において、戦争責任という問題に向き合わざるをえなくなった。
0投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
新書大賞2012 2位。 中立~昭和天皇寄り(?) とっつきにくそうなテーマとボリュームだけど、すごく良かった。 天皇とその周囲の人たちがどのような国を目指していたのか、なぜ戦争に向かっていったのか。侍従官たちの日記に記載された天皇の発言を通して結構リアルに近い(?)気持ちがよみとれて感情移入してしまう。 結局昭和天皇の人生の一番の時期が、皇太子時代のヨーロッパ巡りであった。そこで感銘をうけた民主主義の実現を目指したが孤立し上手くいかず・・・というのが切ない。 原稿が紛失したという、昭和天皇本人による自叙伝が見つからないかな・・・
0投稿日: 2013.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和天皇の戦争責任がテーマとしてあがるたびに、開戦前・終戦の決断等、実際にはどんな思想とご意見を持った方なのかわからないし、憲法上、国際法上、戦争責任があるのかないのかも、とわからないのが正直なところである。 本書は、一次資料に基づき、実証的な著述スタンスを崩さず、特定のバイアスがかかっていない点に非常に好感が持てる。 冷静に、陛下の軌跡を追うことができる。そこから浮かび上がってくる昭和天皇像は様々であろう。(だからこそ評価の分かれる天皇なのかもしれない) 良くも悪くも、すらすらとは読めない一次資料の引用が多いので、読みこなすには時間と根気がいるが、良書であると思う。
0投稿日: 2012.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまでの昭和天皇評伝・伝記のなかでは一番実証的。学界における最新の研究成果が網羅されていると思います。
0投稿日: 2012.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ平和的に道徳的に日本を導こうとして、結局理想に導けなかった昭和天皇像が描かれている。軍部や閣僚の暴走と、自身の政治理念に挟まれながら、最終決断の責任を負う立憲君主って大変だわ。 昭和天皇の責任といえば、太平洋戦争の開戦や終戦時期について追及されるが、開戦時には既に昭和天皇は政治的に孤立しており、陸軍の暴走を止められない状態であったとされる。おそらく誰も止められなかったかも知れない。とすると、その原因となった日中戦争勃発時の処理の誤り、もしくは、その戦中の判断について責任追及されるべきなのかな? 親英とされる昭和天皇だが、中国、朝鮮等、対アジアに対する考え方がもう少し異なっていたら、もしかして、歴史は違うものになってたかも?と思ってしまいました。
0投稿日: 2012.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ【69冊目】新書大賞2012第2位受賞作。サントリー学芸賞も受賞したそうです。 その副題のとおり、戦争の終わった今から見ると、協調外交だとか政党政治の支持のような、非常に理想的な思想をもった君主だった昭和天皇像が浮かびあがってきます。 けれども、そういった思想の持ち主であったがゆえに、当時の状況や世論からは浮いてしまい、軍との信頼関係も築くことが出来ず、孤立してしまったことが分かります。 それだけではなく、日本が大戦にどのように巻き込まれていったのかという状況の勉強にもなります。たとえば、ドイツの快進撃に幻惑されてしまっただとか。 本書を読んで思うのは2点 ① 昭和天皇の戦争責任は、戦争を遂行したことにあるのではなく、戦争の開始を容認し、かつ、一撃講和論に見られるように戦争の終結を遅延させてしまったことだろう、ということ(ただし、戦争中の国の指導者としては、一撃講和論は必ずしも不合理な選択ではないように思える。)。ヒロヒトの責任は、ヒトラーやムッソリーニのそれと同列に語ることはできないように思う。 ② 民主主義は手段にしかすぎず、目指すべきなのは自由主義なのだろう。 時代が時代ならば、かなり優れた君主として評価されていたのではないのかな。 昭和天皇という重要人物について、手軽に読める本として、かなりオススメ。
0投稿日: 2012.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ主として、青年期から太平洋戦争の終わるまでの、昭和天皇の思想。 そのとき、何を考えて、どのような行動をしたのか。側近の方々の記録などをもとに、それに出来るだけ近づこうと書かれています。 自分がしたいことではなく、自分はどうすべきかを考えていた方なのだなと読んで感じました。それは大切なことですが、好きか嫌いかの判断のほうが決断はやはり早い。それが無いことで決断できず遅きに失した点、言葉では皆簡単に言うことの、実行の難しさを読後改めて感じました。
0投稿日: 2012.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史とは人の生き方である、とは誰から聞いた言葉だっただろうか。平和な世に住む(大震災やテロに被られている現在ではあるが)私たちにとって激動の「昭和」時代はなかなか創造が難しい。その最高位であった人物、昭和天皇の理想、挫折、そして責任。単なる年号や出来事ではわからぬ深さが「人」を読むことで身にしみてきた。
0投稿日: 2012.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ古川隆久『昭和天皇 「理性の君主」の孤独』(中公新書、2011年3月)税別1,000円 【構成】 第1章 思想形成 1 東宮御学問所 2 訪欧旅行 3 摂政就任 第2章 天皇となる 1 田中内閣への不信 2 首相叱責事件 3 ロンドン海軍軍縮条約問題 第3章 理想の挫折 1 満洲事変 2 五・一五事件 3 天皇機関説事件と二・二六事件 第4章 苦悩の「政談」 1 日中戦争 2 防共協定強化問題 3 太平洋戦争開戦 4 終戦の「聖断」 第5章 戦後 1 退位問題 2 講和問題と内奏 3 「拝聴録」への道 日本大学文理学部教授・古川隆久(1962-)による昭和天皇の政治史である。2011年度のサントリー学芸賞(政治・経済部門)受賞作である。http://www.suntory.co.jp/sfnd/prize_ssah/detail/2011sk2.html 昭和天皇にまつわる書物は山のようにある。本書でも指摘されているように平成に入ってからの史料公開の進展により、研究水準も著しく向上している。 評者のごく主観的な印象では、井上清を源流にする「戦争責任論」、つまり戦前の国策決定に昭和天皇がいかに携わってきたのかという点が強調されてきたように感じる。 昭和天皇は、立憲君主として、憲法の規定する輔弼者の決定には従うという姿勢を大原則として自らを強く律していた。しかし、その一方で、その輔弼者が自らが求める「理想」と大きく乖離した内容の裁可を求めた場合に、それに対して「不満」「否定」の意を表明する。 批判論は、大原則よりも、大原則からはみ出た意見表明、国策決定への関与を取り上げて、それが不十分、誤りであったと指摘する。評者自身、そのような批判論にあまり共感ができなかった。 本書はそのような批判的評伝とは明らかに一線を画している。 本書は、昭和天皇が求める理想的な政治、つまり内政にあっては徳治主義、外交にあっては国際協調主義をどれだけ強く求めていたかという点が強調される。その上で、現実の政治過程の中でその理想が挫折していく様が繰り返されていく。 政治の表舞台に現れない御下問と内奏のやり取りを拾っていくことで、戦間期の協調外交路線が衰退し、帝国陸軍のごり押しによる大陸政策や三国同盟がぐいぐいと進められていく様子が浮き彫りにされる。 昭和天皇は、摂政時代から繰り返しテロの脅威にさらされ、軍部の青年将校や右翼からは「軟弱」「平和主義者」として強い批判を受けてきた。昭和天皇が信頼を寄せていた側近や政治家も次々とテロの標的となり、天皇の側から離れていった。 政治思想も、側近人事も孤立化していった非常に困難な状況下にあってもなお、昭和天皇が陸軍に対してブレーキをかけんとしていた姿勢は十分に評価する必要があるのではないだろうか。 軍人勅諭を奉じ、軍旗を掲げ、皇軍を名乗る帝国陸軍が、現職の天皇位にある大元帥・昭和天皇の意図を汲もうとしないどころか、強く抗弁し、時には虚偽の答弁までする。まして、天皇以外の組織・個人に対しては天皇直隷・統帥権の独立を盾に反対意見を封殺するのである。吐き気を催すほど不愉快な組織である。 最終的には太平洋戦争という全く無謀な戦争を仕掛けるという異常な時代にあって、国制の最高位者が「理性的で」「正常な平和」を求める姿勢を持ち、帝国陸軍や排外主義にたける国民世論と対峙しなければならなかった。昭和天皇の苦悩はいかばかりであったろうか。 本書を読み、太平洋戦争開戦前の戦争回避指示や、「開戦の詔勅」に込められた「豈に朕が志ならんや」の言葉の重みが大きく変わった。もっと大げさに言えば、昭和戦前期の見方が変わった。 この時期の歴史については、山ほど文献が出ているが、本書はその中でもまず最初に読むべき一冊に数えられるだろう。このような研究が、学者向けの専門書ではなく、新書という一般の人が広く読める媒体で出版されたことは本当に幸運なことだと思う。
0投稿日: 2012.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ根底にあったのは東宮御学問所で授けられた徳治政治、 理想としたのは「君臨すれども統治せず」の大英帝国、 目指したのは政党政治と協調外交。 しかし、先の大戦前夜、昭和天皇が思っているようにはこの国は 進まなかった。 昭和天皇に関してはその死後、側近たちの日記などの一次資料や 多くの研究所が世に出た。その膨大な量の資料や報道等を綿密に すり合わせて、その時々で昭和天皇が何を思い、どのように行動し たのかを浮き彫りにしている。 理想と現実の乖離に苛立ったり、側近に不満をぶつけたり、無力感に 苛まれたり。磁極の判断を誤った個所も歪曲することなく書かれている。 また、自身の戦争責任についての発言もあり、考えさせられる部分も 多い。 終戦後、昭和天皇には退位論もあった。もし、あの時、退位していれば 戦後に事あるごとに持ち出された戦争責任論も違ったものになったの かも知れぬ。 責任を取って退位していたのなら、戦後のヨーロッパ訪問で各国の 厳しい世論に晒されることもなかったのだろう。亡くなって以降もこの 問題には繰り返し持ち出されることを考えると、在位し続けることが 昭和天皇の責任の取り方だったのだろうか。 記者会見で「これまでで一番の思い出は?」と聞かれると、皇太子 時代のヨーロッパ訪問であったと答えていた昭和天皇。死後、 宮内庁の職員が机を整理すると引き出しからパリの地下鉄の 切符が出て来たという。 即位から崩御まで、辛いこと・苦しいことの多かったのだろうな。 本書はバランスの取れた良書だ。巻末には多くの参考文献が掲載されて いるので、折を見て読みたいものを探そう。 客観性に徹した良質な研究書である。
0投稿日: 2011.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ終戦の聖断を下した時、昭和天皇は44歳だったという書評を何処かで読んで、自分の生きた昭和を体現する昭和天皇に関心が出てこの本を読んで見た。流石にサントリー学芸賞を受賞するだけのしっかりとした内容。読みごたえあり。
0投稿日: 2011.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、昭和史をより深く解明した良書であると思った。1989年(昭和64年)の昭和天皇の死去を契機とし、昭和天皇の側近や深く関わった人々の日記や書簡が明らかになってくることにより、昭和史の政策決定に関わる奥の院の様子がだんだんと解明されてきたことは興味深い。 本書は「昭和天皇ほど評価が分かれる歴史上の著名人は少ない」と語る。最近まで宮内庁は、発信する情報量の少なさからマスコミから[菊のカーテン]と揶揄されてきた。昭和史の大きなエポックである日中戦争とそれに続く太平洋戦争についても、その開戰に至る詳細な政治的過程が全てわかっているわけではない。今に至るまで「なぜ、負ける戦争に突入したのか?」という疑問は誰しもが抱いていると思う。太平洋戦争においては、日本人だけでも310万人の死者、アジア全域では1000万人とも2000万人ともいわれる死者を出し、現在でも総理や天皇がアジアの戦争関連国に行くと、「お詫び」の言葉からはじまらざるを得ない。戦争への道は、大きな誤った政策であったことは明らかであるのに、それについての統一した国民的認識はいまだに成立していないように思える。昭和の戦争についての名称さえ「太平洋戦争」「大東亜戦争」とバラバラである。成熟した歴史認識が成立していない理由の一つに、政策決定の詳細が明らかにされていないことがあるのではないかと思われる。本書は、その貴重な奥の院をより明らかにしていると思った。 本書によると、昭和天皇は一貫して英明な君主であるように描かれている。「思想形成」では「神格化とは無縁の大正デモクラシーの空気をたっぷりと吸収した青年君主」の姿が描かれ、1921年(大正10年)の摂政就任においては「意欲的な皇室改革に邁進」する姿がみえる。日本が戦争に傾斜していく過程では、昭和天皇は親英米で協調外交路線をもちつつも、強硬な陸軍に引きずられる姿が描かれている。1929年(昭和4年)の張作霖爆殺事件や1931年(昭和6年)の満州事変においては、「決定を現地軍が実行しない場合に天皇の権威が損なわれる」という理由で陸軍に譲歩する姿が描かれ、「昭和天皇の協調外交路線はすっかり時流から外れた考え方になってしまった」と昭和天皇をかばうかのように本書では評価する。そしてだんだんと軍部の発言力が強化されていき、「昭和天皇が国政を掌握するのが困難に」なったとみる。1937年(昭和12年)の盧溝橋事件、その後の三国同盟締結そして日米開戦においては、昭和天皇が努力しつつも、状況に流される姿が詳細に検証されている。 本書は、歴史的事実を昭和天皇に目一杯好意的に解釈した本であると感じた。側近の日記等を数多く引用した解釈には一定の説得力はあるが、ここまで昭和天皇が無謀な戦争政策に抵抗している姿が真実ならば、なぜ陸軍が従わなかったのかと疑問を持つ。ましてや時代は絶対天皇制の時代である。ちょっと違和感がつきまとう。 もしこれが事実だったとしても、現在では一般的には上司と部下の意見が違った時に、部下の意見に迎合して大失敗した場合は、上司の意見を無視した部下が悪いのか、指導力がない上司が悪いのか。部下の人事権は上司が握っている以上、上司に全ての責任があるのは当たり前のことである。まだまだ昭和天皇については歴史の検証が必要であると思った。 本書によると1976年~1985年にかけて作成された「拝聴録」や「大東亜戦争御回顧録原稿」(独白録)等、計14袋の関係資料が行方不明だという。宮内庁の管理下で重要文書が行方不明などありえないとしか思えず、意図的な隠蔽と言われても仕方がないのではないかと感じた。1945年(昭和21年)の敗戦時に公文書の焼却を命じた閣議決定もそうだが、歴史の記録は国家と国民の共有財産であるという認識が欠けているのではないかと感じた。 本書を昭和の時代を解明するために高く評価すると共に、この時代は、まだまだ解明が必要であると思うものである。
1投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ実証史学の手続きに忠実に,昭和天皇の実像に迫る,とても良い本だった。ただ,新書なのにかなり重たくて,読了までに8時間ほど要した。夏休みのサイパンで半分,帰国して残りの半分。あとからふりかえってみてびっくり。 昭和天皇の側近が遺した日記などの一次資料から,様々な回顧録までを適切に史料批判しつつ論を組み立てており,信頼に足る評伝といえる。かつては史料が乏しく,またイデオロギーの時代だったので,昭和天皇の伝記は書く者の政治的立場が強烈に出ていたそうだが,本書は極めて中立的。 昭和天皇は,1901年生れで,思想形成を大正時代に終えている。大正デモクラシーと言うように,自由主義的な雰囲気の溢れた時代に教育を受けた。誰しも生れる時期は選べないが,こうして平和主義者,国際協調論者としての天皇をいただくことになったのは不幸中の幸いだったかも。 元老西園寺が健在だった昭和のはじめころまでは,天皇の考えが周りにも支持されていた感じなのだが,満州事変が起こり,日中戦争が始まってくると,だんだんと天皇の周りから人が消えていき,天皇は徐々に孤立してしまう。 陸軍は天皇を軟弱者とし,一部が暴走して政府要人や天皇の側近を狙うテロが頻発。そのような中で,戦争を回避しようとする天皇の考えはなかなか賛同を得られなくなっていった。 結局対米開戦のやむなきに至ってしまうが,一旦始まった戦争は,やりぬかなくてはならない。敗色が濃くなってくると,昭和天皇はなんとかもう一度戦果をあげて,有利な条件で終戦できないかと考えるが,それも空しく,沖縄が陥ち,二発の原発が落とされて,最後は聖断によってポツダム宣言を受諾。 最後まで徹底抗戦論者も少なくなく,クーデターや天皇に対するテロの恐れも大いにあったが,終戦の聖断は下された。良き立憲君主たろうとした天皇個人の想いがこの決断に表れたのだろう。実際に玉音を収録したレコードが,一部軍人によって強奪未遂にあっている。 終戦後は,戦争責任を背負いながら長く公務をこなした。戦争を主導したのが自身ではないとしても,開戦を決断し,厖大な犠牲を出してしまったことについては責任を痛感していたようだ。摂政時代を含めて70年もの間,苛酷な立場に立たされてきた昭和天皇。やはり偉大な人物だったと思う。 昭和天皇は,摂政宮時代からずっと趣味として生物学をやっていて,もちろん進化論などもよく知っていた。それでいて戦前には現人神とかされていたわけで,その辺,居心地の悪さもかなりあったんじゃないだろうか。 もともと生物と歴史に興味があり,どちらに取り組んだらいいか,というときに,歴史は政治的に差し障りあるよねってことで生物学を選んだそうだが,生物学もなかなか考えさせられるところがあったんじゃないかな。理系の学問をやってると,社会に対してもちゃんとした見方できるような気が。少なくともそういう素養がついてくるような気がするな。
0投稿日: 2011.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログありそうでなかった「昭和天皇の伝記」。新書で400ページを超える大作だ。 国を意のままに操れる絶対君主ではなく、立憲君主とは何とも難しい立場だ。すべてが思い通りに行くわけではないし、「やーめた」と最近の日本総理大臣のようにあっさりと地位を放り出せるわけでもない。そんな難しい立場で史上最高の天皇在位期間を全うした昭和天皇。超人的な忍耐力を持った人だ。
0投稿日: 2011.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ実証史学の手法が駆使されており、まさに「昭和天皇の実像を知りたい」という欲求にこたえてくれる良書。ことこまかに史料の出典が示されていることに信頼が持てる。昭和天皇がほんとにリベラルな平和主義者であり、それゆえ孤独に陥っていたことがよくわかる。どれだけ憲法で強大な「権力」が規定されていても、実際に「権威」が受容されていないと、いかに無力であるかということも再認識した。
0投稿日: 2011.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和天皇の普遍主義的思想がいかに形成され立憲君主制を理想としながらも、一連の戦争により思想的に孤立していったか。国体としての存在がどのように軍部に利用されたか。昭和天皇の視点から第一次世界大戦後から太平洋戦争という時代を見るのに非常に有益なものだった。
0投稿日: 2011.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ大正デモクラシーの息吹に育ち、死ぬまで戦争責任を背負った天皇。いろんな限界があったにせよ、徳治主義に生きた君主として私は評価したい。何せ60余年も在位すれば、批判される点もあろう。英国の立憲君主を目指しながら、太平洋戦争中に孤立し疲弊してしまったということを改めて知る。◆また憲法を遵守する姿勢も知り、平和憲法の改憲論を生前抑える重石になっていたという説も納得する。◆◆本来であれば自由に生きた方が楽なのになぁ。
0投稿日: 2011.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ全てを理解できたわけではなかったけど、初めてきちんと昭和天皇の生涯を追い、知ることができて良かった。
0投稿日: 2011.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
メモ 昭和天皇論。彼については賛否両論あるが、時事能力に長けた学者肌で頭脳明晰だったようだ。欧米に親近感を抱いており、国際協調を望み、平和主義者かつリベラルで国体の欺瞞を見抜き国民に近い皇室を目指した。君主としての自覚があり、戦前のみならず新憲法下でも政治的な発言をしたとされる。しかし、満州事変を経て軍部や右翼が台頭し、思想的にも孤立して戦争を抑えられなかった。戦後は戦争責任論に苦しめられた。 彼の在位期間中を中心に89年の生涯は壮絶だったし、戦争責任はないわけではないが、国体という大義名分で軍部や政治家に利用された悲劇の人ということもできると思う。 主権者としての天皇や先の大戦の賛美、一方で象徴としての天皇制を否定することはないが、そろそろ客観的に考えるべきだと思う。
0投稿日: 2011.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ勇気ある行動。実証中心との標榜であるが、まあ偏りもなく資料を客観的に用いる姿勢は好感が持てる。しかし、孤独な君主とは洋の東西古今を問わないものだ。
0投稿日: 2011.05.03
