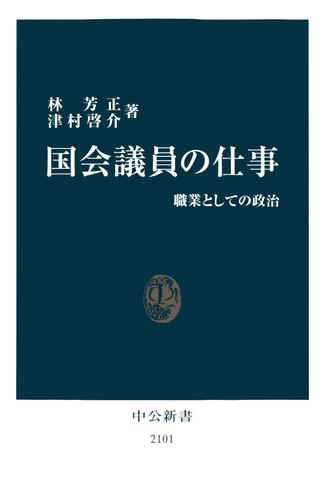
総合評価
(16件)| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ国会議員が直面する課題や、政策決定のプロセスについての具体例が豊富に挙げられており、実際の政治活動がどのように行われているかを理解する上で非常に有益な本だと思う。野党から与党になった民主党の津村さんと、与党から野党になった自民党の林さんのそれぞれの視点からみた政権交代の様子がわかったのも良かった。
0投稿日: 2024.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ国会議員は何をしているのか、気になって読んでみた。 こんなにも国会議員は熱意があるのかと驚いた。意外だった。私だったら忙しすぎて倒れてしまう。 もっと多くの国民がもっと関心を持ったら、政治家は広報にお金をかける必要はないし、もっと有効に国会議員のお金と時間を使えると思ったが、現実はまだ人気投票の側面があるから、広報は必要だよなぁ。
1投稿日: 2022.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ国会議員の仕事 / 林芳正 津村啓介 / 2011.09.29(19/71) きっかけ:永田町をより知りたかった。 官僚は基本的には嘘をつかない。けれでも本当のことも言わない。もってきたペーパーに「・・・等」とあったら、必ず具体的には何?と聞かなければならない。往々にして、羅列してある事柄の何倍ものことが、その一文字に隠されている。 法律の多くは霞が関で造られ、役所の幹部が永田町の有力議員に根回しを終えた段階で、事実上立法プロセスは終わる。国会での与野党による法案審議は、一種のアリバイ作りでしかなく、議員立法や修正協議は極めて例外。国会は議会製民主主義の象徴であり、権威の府であるが、権力の府ではない。真の立法者は別にいた。官僚だ。 政治家が脱官僚依存して、自分自身の言葉で答弁しなければ、国会審議は活性化しhない。国会改革と政治主導の確立はコインの裏表。 政治家が議員特権に見合っただけの仕事ができているか。 金帰火来 大臣にとって、次官・局長は一流の家庭教師 政権交代後の民主党は、政治主導のものとに政策決定などから官僚を排除し、閣僚、副大臣、政務官ですべてを決める方針を実行に移した。初めから、お前ら官僚のいうことは聞かない。政治家が決めるからそれに従え、といってうまくいなかない。 大臣から課長までが同じ方向を向き、胸襟を開いて語り合える関係が必要。 メールとルールに頼りすぎ、極めて官僚的。 森内閣で自民党は終わっていた。小泉が出現して救われた。森内閣で政権交代が怒っていたほうが、日本にとっては良かった。 小選挙区制は日本になじまない。アメリカには、南北戦争の歴史があり、ここは民主党、ここは共和党が強いといった風土・伝統がある。英国にもかつての階級制度の名残から、ブルジョアは保守党、労働者階級は労働党という意識が値強くある。二大政党制を可能とする社会的基盤がある。しかし日本は、一億総中流。国を二分するような歴史がない。政治とカネの問題是正の政治改革が、いつのまにか小選挙区制導入にすりかわってしまった。 マニフェストは羊頭狗肉。作り方のいいかげんさ。公開せず、少人数が秘密裏につくった。そもそも、民主党が何をめざすか、綱領がない。 財政に対するコンフィデンスが崩れれば、国債の売り圧力が高まる。現在、1.1%程度の長期国債利率が、仮に1ポイントUPしただけで、消費税の1-2%は吹き飛ぶ計算。 大臣にとっての最初の罠=官僚はその圧倒的な専門知識を駆使して、政治家をコントロールし始める。 官僚は敵対するのでなく使いこなすもの。 日本は選挙が多すぎる。参院選が3年に一回、衆議院解散も3年に一回程度。自民は3年に一度、民主は2年に一度、党首選挙。日本の総理大臣は毎年にように選挙のハードルを越えないと、居続けられない。アメリカは4年の任期保障、英国、下院は5年で、4年では運用上解散なし。信任投票にエネルギーが割かれ、内閣支持率が気になり、短いスパンでしか判断できなくなり、中長期での国家戦略がゆがめられる。 任期が短く選挙が多い状態のまま、小選挙区制を導入した結果、総理大臣を使い捨てる国になった。 行政も立法も官僚がやっていて、国会議員は社外取締役というのが官僚の意識。
0投稿日: 2014.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ境遇の異なる2人の男性が、いかにして政治家となり 現在国会議員として職務を果たしているかを書いた半自伝的な一書。 細かな政策には触れられていないためか、何といっても読みやすい。 ただし国会議員としての職務は雰囲気が感じ取れる程度に過ぎず あまり頭に残らなかったのも正直なところ。 政治家を志し、選挙活動を行う前半は非常に面白く こういう人たちが政治家になるのかとひとつのケースを知ることができた。
0投稿日: 2012.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料ID : 11100085 所在 : 展示架 請求記号 : 314.18||H48||2101
0投稿日: 2012.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
当選した政治家は具体的にどんな仕事をしているのだろうと思って読んだ。でも本書の内容の3分の1は選挙について。1期生の仕事は「次の選挙に勝つ事」といわれているそうだ。内容の薄い(無い)選挙運動にそんなに時間を取られたら政治活動なんかできるのだろうか。ただの多数決要因なら定数は半分でいいような気がした。
0投稿日: 2012.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ全般を通して、林さんはどっしり、津村さんはあたふたという印象を受ける。その理由は主に①選挙に地盤・鞄があるかないか②政権で仕事した実績の2つだろう。 特に津村さんは全く縁故も何もなく政治家になり、お金や仲間や地盤の問題を常に抱えている。このことが政党交付金など党に感謝せざるを得ない状況を生んでいるのも事実で、ここは本来であれば政治家個人の歳費は削減してもスタッフはもっと登用できるような国からの資金サポートが必要だろう。ただしこれも現状では議員立法、もしくは党内の政調がちゃんと機能してこそである。 また②の政権の実績のなさは、テレビなどでもよく報道されていることではあるが、政権をとって仕事をしてみたらそれは自民党が来た道であったというものである。自民党を批判していたものは実は与党にはつきものの批判も多く含んでしまっていた。 また津村さんが主張するインプットをたくさんしなければアウトプットは出来ないというのはその通りで、政治家がやるべきマーケティングとはメディアを通してのものと直接ヒアリングするものであろう。ただ選挙を意識しなければならない立場なので、開会中に週に2回も地元に帰るのはやりすぎではないか。普通のビジネスマン感覚でそれで仕事をする時間が確保出来るとは到底思えない。また例として表示されている「岡山での1日」の日曜日のスケジュールは朝から晩まで、冠婚葬祭や地域イベントの出席でこれをインプットと読んでいる感覚は正直疑問だ。 ただ一番の問題は、国政の仕事が多岐にわたりすぎているが、それをこなす人材がおらず、官僚と正しく議論も出来ないところにある。そもそも大臣のかけもちや、会議がめちゃくちゃ多い事自体がおかしくそれで仕事ができないのは当たり前なので、それは改善しないとダメでしょう。
0投稿日: 2012.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ自民党、民主党両議員の「政治家になるまで~現在」がそれぞれ書かれている。 読んでいても知識が無いので分かりづらく、なかなか読み進められなかった。 色々感じたことを順不同に書いていく。 *政治家の扱う範囲が広すぎて、1人の政治家に任される分野が多岐に渡りすぎる *政治家の組織態勢が旧体制のままで、要は「グローバル化できない日本の大企業」のように、古い態勢にしがみついて新しいものを受け入れない化石状態になっている *国民はもっと勉強すべき。お前らの国だぞ! *政治家は頭が良すぎて言ってること意味不明。政治家同士では通じるかもしれないけど、国民に伝えるようにもっと簡単な言葉で話してくれ。 *メディアは何のために政治家をいちいち叩くのか こんな感じですかね。 国民はもっと勉強しないとダメです。 何も自分自身が分かってないのに「日本の政治はダメ」って、赤ちゃんみたいだからやめましょう。国民の協力なしに政治はできません。 政治家の方は、確かにお金もらいすぎです。 それをまっとうに公開して使われてるという津村議員は誠実。 政治とカネ問題起こしちゃってる人達は、言い訳しても無駄。 政治家が政治家のイメージ悪くして自分たちの首絞めて後輩に迷惑かけて、早く古株は引退すべきでは。 こんな感じです。 引き続き政治関係の本は読んで行きたいです。 ちなみに。 重要なこと書き忘れてた。 政治家の方、すげぇ頑張ってます。(本の内容が真実ならば) こんなに日本のこと真剣に考えて、国民のこと真剣に考えて動いてるんだって思います。確かにそれ相応のお金は貰ってるけども。 政治の行方は私たち国民の肩にも掛かってるので、私たちもアクションしていかないとね。
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ現役の政治家2人によるもの。 自民党的な考え方はある種の合理性を感じ取れる一方で、民主党議員がいかに「官僚化」しているのかがなんとなくわかる。 次官会議の廃止ですべて解決すると思っていた短絡さには笑う。 今後、政権交代をくり返す中で理想的な政と官の在り方を模索していくべきという主張は同感。
0投稿日: 2011.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ別の本を買いに行ったときに「学術書ばかりじゃなくて新書も買っておくか。」と思って寄ったジュンク堂の新書コーナーで目に留まっただけで買った数冊の中の一冊で、忙しくて時間もなかったのでずっと積読になっていた。 読もう、と思ったのは、これまた自分の本棚で目に留まって、買った時には気付かなかったんだが、著者のお二人が林芳正氏と津村啓介氏、という自分が勝手に近いと思っているお二人だったから。(この時まで気付いていなかった!) 林氏は同郷で、キャリアパスはすごく参考にしたいものだし、津村氏は今の自分の研究領域の科学技術政策を担当していらっしゃる。(文献などで頻繁に名前を見る。) で、あまり余裕もないにもかかわらず1日で読み切ってしまった。 立場も環境も違う2人の若手政治家が、どういう経緯で政治家になり、政治家として仕事をしてきたのかを綴っている。 お二人がとても優秀な方なのはよくわかった。 でも一方で、彼らが何がしたくて政治家になったのか、はあまり見えなかった。(そもそも、「これがやりたい」から政治家になる、政治家になるしか実現する方法がないから、という人はもしかすると少ないのかもしれない、と思い始めた。。) 林氏が対談で引いている、徳富蘇峰「大きな改革を成し遂げるためには、三種類の人間が必要だ。思想家と、破壊者と、創造者だ。」について。これは似たようなことを前に言われて、自分もなるほどそうだ、と思う。ところで、1人で複数の役をやりたい場合はどうしたらいいのか。。と思う今日この頃でもある。
0投稿日: 2011.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログまだあがっていない油乗り切る前の 議員の本だけに日々のディティールが 大変おもしろかった。 事務所運営、官僚との距離間などなど。
0投稿日: 2011.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ政治の世界では日本という国全体をステージにして、おおがかりな”茶番”劇が今なお繰り広げられている。6月2日には、管総理に対する不信任決議案が否決された。 「政治家って何なんだろう?」 「みんな何をやりたくて政治家になったのかな?」 「こんなんで良いんだったら、自分でもできるよな」 色々な疑問が沸いてくる。そんな疑問に答えてくれる本があった。それがこの本だ。 (続きは、こちら↓) http://ryosuke-katsumata.blogspot.com/2011/06/blog-post_05.html
0投稿日: 2011.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ私を国会議員にしたいとしている思っているらしい議員秘書さんからのご紹介。国会議員の仕事がコンパクトまとまっている良著。
0投稿日: 2011.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2011-061。 どちらかといえば若手議員の、今までとこれから。 対談での、相手の意見を尊重する部分、歩み寄り部分が興味深い。
0投稿日: 2011.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読書】2名の現役国家議員が語る国会議員の仕事を語った本。現在この2名は与党民主党議員、野党自民党議員であるが、政治地盤等の置かれた環境も全く違う。その中で、これまで与野党として対峙していたのが、政権交代を挟み、立場は逆転し、大きく環境が変化した。特に津村議員の政権交代後の国家戦略室草創期の状況等の試行錯誤の取組は、政府内部でもなかなか見えないところであり、非常に興味深かった。
0投稿日: 2011.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ菅や与謝野は秘書かスタッフが書いているっぽい??が、これはなんとなく直筆みたいで感じが良い。といっても印象だけだが。よく見返してみると林のパートも津村のパートも文体が似ていて区別がつかないな・・。 とはいえ、政治家を志すというのがどういうことか、ある程度等身大でわかる。この世界に興味のある若い人は読んでみるとよかろ。
0投稿日: 2011.03.24
