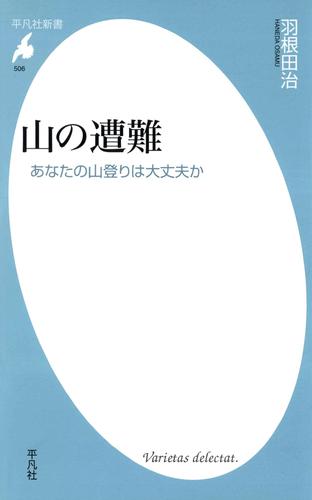
総合評価
(6件)| 0 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体的な遭難の事例がいくつも紹介されていて、参考になる。 国内における山岳遭難事故の統計は、毎年7月上旬に警察庁生活安全局地域課によって公表されている。遭難者数は1990年代半ばからうなぎ上りに増加しており、年齢層別では、60〜70歳代が多い。
0投稿日: 2024.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の羽根田氏と言えば、これまでにも気象遭難・道迷い遭難に関する本やロープワークのハンドブック、それに「雪山100のリスク」(編集サポート)などを読ませてもらっている“山の遭難の専門家”。 この本は新書で手軽だけど、山の遭難の小史から現状、内包される社会的な問題点などを手際よくまとめた、とても読み応えのある本です。 まず、1980年前後を境に、山岳会や学校山岳部を中心とした「自分の心技体を鍛えて挑む山」の時代から、特に中高年層(若者が、つまり3K環境である山からいなくなってしまったので)を中心とした「散策の延長として文字通り物見遊山で行く山」の時代へとフェイズの大変化があったとする指摘が面白い。 面白いと言いつつ、その過程で本来山は危険な場所であるという基本認識が置き去りにされている、という指摘なんですね。 一方面白いで済まない(どころか、胸が悪くなる)のが、後半にさまざま紹介されている遭難者たちの実態なんです。 スリ傷程度で救助を要請するやつ。「民間のヘリは金がかかるから警察のヘリを飛ばしてくれ」と言い放つやつ。足が痙攣したことを「夕べ遅くまで仕事してたんだから仕方ないだろう」と開き直るやつ。救助されたあとに「頼んだ覚えはない」というやつ…。 自分の愉しみ、あるいは自分の過誤に他人を巻き込んでいる自覚もなければ陳謝・感謝もない勘違い野郎たちのオンパレードと来たもんだ。こんなところにも、例のモンスターペアレントやモンスターペイシェントに通じる「モンスター遭難者」がいるわけです。これ、日本社会をあまねく覆う病理なんじゃないだろうか。 ほかにも、遭難の類型(大した装備も持たずに北海道の嵐の山をパーティ分断の上突き進むとかね)、遭難したら人はどのようになるか、報われにくい救助隊の仕事…などなどと続く話題には、ひとつひとつ身につまされるものがあります。 山に行く人はぜひ、こうした本を精読したいものなんですが(読めばいいっちゅーもんでもないが)、本当に読んだ方がいい人って読まないんだよね、きっとね…。
1投稿日: 2019.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
山岳遭難の歴史から現代の遭難の形態、そして対処法。山岳遭難の現在がきっちりとコンパクトに詰め込まれた一冊です。
0投稿日: 2012.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] ひんぱんに報じられる山の遭難事故。 厳冬期の北アルプスだろうと、ハイキングで行く山だろうと、遭難事故は、いつ、誰に起きても不思議ではない。 「自分だけは大丈夫」「私は危険な山には行かない」―そんなふうに考えているとしたら、あなたも“遭難者予備軍”だ。 “明日はわが身”にならないために、今こそ、「山でのリスクマネジメント」を考える。 [ 目次 ] 第1章 山の遭難小史 第2章 統計が語る現代の遭難事情 第3章 救助活動の現場から 第4章 遭難事故のリアリティ 第5章 なぜ増える安易な救助要請 第6章 ツアー登山とガイド登山 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦後の登山ブーム以降の遭難史がコンパクトにまとまっており概観できます。無自覚・身勝手な登山者に対する辛口な論評に好感が持てます。何も考えず人まかせに登っている登山者にぜひ読んでいただきたい。
0投稿日: 2011.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ羽根田さんの新書が出たので、読んでみた。 これまで、山岳遭難を追ってこられた著者ならではの視点で時にはキツク遭難について切り込む。 山の遭難史や統計情報などは、安全な登山を行うリスクマネジメントの観点からも非常に参考になる。 また、救助する側の視点や安易な遭難救助が増える現実については、山を登る人は是非、一読し一考すべき事項だ。 山を歩いていると、「この人大丈夫?」と思う人を見かけるが、登山を志す人は一読の書です。
0投稿日: 2010.03.27
