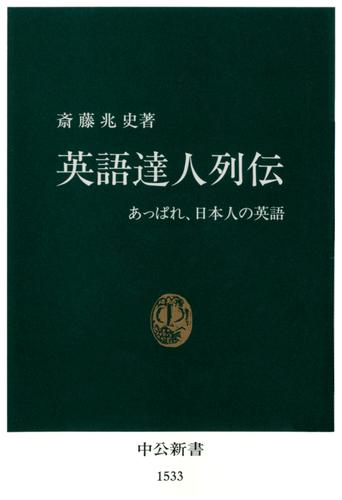
総合評価
(44件)| 7 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ今のように、様々な音源もなく、ネットで調べられる環境、条件がない中、先達は、どういう風に語学を習得したのか 不思議人思っていました。 ストレートには書かれていませんが、皆並外れた鍛錬、時間を費やしているのがわかります。そもそも図書館のが本を全部読む目標、 全集を読む、教本丸ごと暗唱、暗記など、凄すぎる。 そして、その鍛錬が好きだからなのかもしれませんが、全く苦にしていない。 習得方法等のいう観点からは期待とは違いましたが、達人の凄み伝わりました。
0投稿日: 2025.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治から昭和時代における、日本史上に誇る英語使い達の伝記集。 著者は人選の基準として、留学経験のないことを挙げているが、皆、天才すぎて全く勉強法の参考にならない。
2投稿日: 2024.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ2000年の刊行なのに、(著者の一人ノリツッコミを除けば)古臭さを感じない。完全ド正論の英語学習本と言える。 帰国子女でもないのに、英語ネイティブも舌を巻くほどの英語力を身に付けた、近現代の偉人たちを特集。英語教師でもある著者の学習論も交えており、今回沢山メモを取らせていただいた。 思えば教材が満足に揃っていなかった時代。原書を必死に読み込んだり自ら師匠を探したりと、今以上に苦労が絶えなかったのは確かだ。しかしその分、10名とも質の良い英語をものにしたと自分は見ている。 著者曰く、ネイティブから「貴方の英語は上手だ」と言われているうちはまだ初歩の段階にあって、上達するにつれて何も言われなくなるらしい…。 今まで逆だと思っていたし、その理論でいくと偉人たちは、最終的に何も言われなくなっていることになる。 刊行時以来、実用英会話(いわゆる「生きた英語」)がもてはやされる風潮は変わっていない。しかし英語の成り立ちや構成・文法といった土台を外しても、英語を使いこなせていると言えるのだろうか。 この問いに少しでも引っかかった方は、彼らの英語人生で答えを見出していただきたい。 新渡戸稲造(国際連盟事務局次長)、岡倉天心(美術思想家)、斉藤秀三郎(英学者)、鈴木大拙(仏教学者)、幣原喜重郎(第44代 内閣総理大臣)、野口英世(細菌学者)、斎藤博(外交官)、岩崎民平(英学者)、西脇順三郎(詩人)、白州次郎(実業家)。 こうやって書き出してみると、職業に結構なバラつきが見られる。でも忘れてはならないのが、全員英語の達人であること。誰がどう凄いのか、素人目線では全然見分けがつかないというのが正直な感想である。 英語とは縁のなさそうな鈴木大拙は禅を世界に広めた立役者だし、斉藤秀三郎は一度も日本を出た事がないのに、立派な英辞書や文法書を編纂している。 そして、白州次郎のラスボス感…!笑 前の9名と比べてガリ勉の印象はなかったものの、人間関係でキングズ・イングリッシュを磨き上げ、戦後GHQと渡り合った。GHQ(アメリカ英語)への手紙に、堂々と英詩の表現を挟んでいたのにはゾクっとしたなー…。 「ああしろ、こうしろと口やかましく言わず、相手がそのまま模倣してよいような生活をする。これは、語学の学習にそのまま通ずる心掛けと言えましょう」(第7章 岩崎民平) 英語はコミュニケーション・ツールの一つに過ぎないが、それを極めるというのは、自分と一体化することに等しいのかなと思う。 斉藤秀三郎には、特に感銘を受けた。ある時は「てめえたちの英語はなっちゃいねえ」と、イギリス人役者に英語で一喝した。またある時は、「あなたのシステムで英語を研究すればどんな本が読めるようになるのか」という質問に対して、「あなたはどんな本を読みたいのか」と返した。 日本語の時と変わらず自分の言葉で訴えたい内容を伝え、難易度よりも自分が読みたいかどうかを優先する。 土台から学んできた英語が、自分と一体化していく…。これぞまさに、「生きた英語」ではないか?
43投稿日: 2024.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『英語達人塾』が面白かったので、英語達人たちの偉業・面白話に興味を持ち、本書を読んだ。 本書は、勉強法云々よりもむしろ偉人伝として抜群に面白い。それは著者が英語学者でありながら日本語の文章がとても上手いからである。ユーモアと修辞に富んでいながら、筆が滑りすぎたり文章がうるさかったりすることは一切ない。岡倉天心の件にもあったが、英語に限らず言語一般に対する高い興味・解像度が英語達人たちには共通しているのだろう。 達人の裏には尋常じゃない努力がある。わたしも地道な努力を弛まず続けなければ、達人はおろか中級者にもなれない——ということを思い知らされた。 勇気づけられるエピソードがあった。第Ⅴ章で幣原喜重郎がイギリスで御者に英語が通じず、「これは英語をやり直さなければならんと考えるようになった」という件だ。というのも私はカフェでバイトしているのだが、外国人のお客さまに簡単な英語の文言(”anything else?”など)が全然聞き取ってもらえないのである。これには自尊心が傷つけられる。だが、そこでしょげかえるのではなく、「やり直そう」という気概を持って発奮した人がいるという事実にわたしは救われる思いがした。わたしも彼と同じように一から発音を学び直そうと思う。ちょうど手元に、関正夫『世界一わかりやすい最後の発音の授業』がある。これが良い教師がわりになることを信じる。
2投稿日: 2024.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ第86回アワヒニビブリオバトル「【2日目】おうち時間DEビブリオバトル」3時間目 英語で紹介された本です。 オンライン開催。 2022.05.04
0投稿日: 2023.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログまえがき 新渡戸稲造 岡倉天心 斎藤秀三郎 鈴木大拙 幣原喜重郎 野口英世 斎藤博 岩崎民平 西脇順三郎 白洲次郎 クロノロジカル・チャート 参考文献 あとがき
0投稿日: 2023.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人の英語教育の問題は良く指摘されるが、その中から天才的な英語の達人が時に現れる。10人の達人たちの生涯は英語学習のヒントになるか。 新渡戸稲造、岡倉天心、齋藤秀三郎、鈴木大拙、幣原喜重郎、野口英世、斎藤博、岩崎民平、西脇順三郎、白洲次郎。 留学しないと語学は身につかないような印象があるが、本書に紹介される人物の多くはほぼ独学で英語を修得している。学習法や環境より才能が求められるのかもしれない。 だがネイティブを前にひけをとらない態度ひ痛快。 中央公論に連載されたもの。
1投稿日: 2022.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治〜戦前、英語の学習教材もロクにない時代に、欧米人に遜色無い、もしくはそれを上回るまでの英語力を身につけた達人たちのエピソードを興味深く読む。 語学の才能の差もあるが、少なくとも彼らほどの猛烈な努力は出来ていないことから、自分に語学力が身に付いていない理由を再確認し、改めて学習意欲を持った。 新渡戸稲造の『武士道』、岡倉天心の「茶の本』、鈴木大拙の『禅と日本文化』は、原文で読めるようになって彼らの格調高い英文を感じてみたいと思った。
1投稿日: 2021.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔の人の泥臭い努力エピソード読んでやる気出そおもたけど、どっちかというと泥臭さより天才みが深すぎてウザかった。いや、そんなん無理やん。
2投稿日: 2020.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ偉人達のなす技であり到底我々凡人には真似できる芸当ではない。その上で彼等の姿勢、気概には学ぶべきところが多く定期的に自戒の意味で読み返している。
3投稿日: 2020.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログもう昔から英語習得の方法は確立していたのだと、改めて思い知らされます。 音読やるべし! 達人はその勉強量が常人には想像も出来ないくらいですが、方法はマネできます! ヤル気でる本です!
1投稿日: 2019.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ英語を道具として活用して世界で活躍した日本人を紹介した本。語るべき哲学がないと、英語ができても意味はない。さぁ自分は何を語れるか??まぁ英語もできないけど。。
0投稿日: 2018.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人でありながら、英語が母語の国の人よりも堪能な日本人を紹介。 彼らの背景は一人ひとり異なる。しかし、誰もが英語に対して目的意識を持って臨んでいたように思う。「英語が楽しいから」とか。あとは、個々人の言語能力が大きい。 英語という観点で、歴史上の人物を掘り下げてみるのは面白いと感じた。 その時代会計と相まって、その人の息遣いも聞こえてきそうだ。
1投稿日: 2017.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログあとがきにあるように、英語を通じて日本近現代史を読み直す内容。 達人たちの英語力に圧倒されるのはもとより、驚くほど読みやすい文章でグイグイ引き込まれた。 そして日本のために奔走する偉人の姿に憧れを覚えた。
1投稿日: 2017.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ英語が切り口だが、人生への真剣さがひしひしと感じられた好著。自分も自分の道を極めようと思えた。まだまだ甘い。
1投稿日: 2017.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治から昭和にかけての英語の達人から英語との付き合い方を学ぼう、というのがコンセプト。 新渡戸稲造から白洲次郎まで、10人の達人たちがどのように英語を身につけ、どのように英語と向き合ったのかが、様々なエピソードとともに語られる。 読み物として気楽に読め、英語学習のモチベーションアップになる。 もっとも、もとより非凡な才能(努力の才も含めてではあるが)の持ち主たちの話である上、彼らの具体的な勉強法が紹介されているわけでもないことには注意が必要。
0投稿日: 2017.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ新渡戸稲造、岡倉天心、斎藤秀三郎、鈴木大拙、幣原喜重郎、野口英世、斎藤博、岩崎民平、西脇順三郎、白洲次郎
0投稿日: 2015.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ第140回 英語を使って、したいことは何?...(2012.5.18) 英語を使って、したいことは何? 明治から昭和にかけ、日本を出ることもなく「意思の固さと努力の才」とでネイティブも驚く英語力を身に付けた人たちがいました。 それを道具に彼らが政治・外交の世界で、あるいはそれぞれの学術分野で、何をなしたか? 知れば勇気がわいてきて、高い目標を掲げたくなること間違いなし。多分。
0投稿日: 2015.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ岡倉天心 ・美術思想家 ・「東洋の思想」「日本の目覚め」「茶の本」 斉藤秀三郎 ・英学者 ・仙台生まれ、正則英語学(神田)創設 ・学生時代に図書館の英書や百科辞典を読み尽くす 幣原喜重郎 ・外交官 ・ワシントン会議中の山東問題会議などで活躍、協調外交 斎藤博 ・外務省、駐英参事官、駐米臨時大使など ・「しゃべったままが立派な文章になるのは、語学自慢の霞が関の中でも斎藤博一人」 岩崎民平 ・辞書の偉大なる男(西脇順三郎) ・研究社新英和大辞典、研究社新英和中大辞典、ポケット英和辞典など
0投稿日: 2014.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人でありながら優れた英語能力を身に着けた、10人の人びとを紹介した本です。取り上げられているのは、新渡戸稲造、岡倉天心、斎藤秀三郎、鈴木大拙、幣原喜重郎、野口英世、齋藤博、岩崎民平、西脇順三郎、白洲次郎です。 國定正雄や松本亨といった英語の達人が時々取り上げられているのを目にしますが、本書で扱われているのは、英語を通じて世界と渡り合った、さらにスケールの大きな人物像です。もはやこのレヴェルになると、「英語の達人」という枠では語りきれないのですが、英語という面から見ても、常人離れしたエピソードばかりで、ひたすら驚き呆れながら読みました。 彼らがもし、今の英語学習者を目にしたら、英語教材もDVDもあふれているのに「ゆとり」にもほどがあると叱られるかもしれません。
0投稿日: 2014.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治から昭和前期の、日本を代表する英語の使い手たちの英語力の特質を、生い立ちや学習歴の紹介を交えつつ解説した本。 天才の勉強のしかたを凡人たる自分が学んでどうなるのか、とも思わないでもないけれど、やっぱりすさまじい勉強振り。 天才って、何もしなくて出来る人の事ではない! むしろ、努力を努力とも思わず成し遂げてしまう人のことなんだと、改めて認識した。 新渡戸稲造や岡倉天心、白洲次郎といった人たちについては、これまで他のところでも知る機会はあった。 英語教育会の巨人、齋藤秀三郎や岩崎民平といった、知らなかった人のことを知ることが出来たのもよかった。 でも、一番強烈だったのは、「知っているはず」の野口英世の章。 英語の達人というイメージさえなかったのだけれど・・・強烈な出世欲と自己アピールという側面もあったのね。 苦学して、偏見にも耐えて偉業をなした、立派な人格者―というイメージで語れる人ではなかったのだな、と。
0投稿日: 2014.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「日本人は英語が苦手だ」という通念など信じるに足らない。日本には素晴らしい英語の達能家たちがいます。洋行帰りの若者たちがペラペラ喋る英語ではなく、内容のある知的な英語の修得について10名の先輩たちが語っている。新渡戸稲造、白州次郎たちが、今の私たちと異なるのはただ1つ。彼らの意志の固さと努力の才だけである。 北九州市立大学:名誉教授 乘口眞一郎
0投稿日: 2013.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ気分転換の一冊。 英語の「達人」のエピソード集です。 目次を見るとびっくりするのが、 達人1名につき、1章という大胆な構成です。 「英語」を切り口にした伝記集ともいえるでしょう。 それぞれの達人が、 ・「どんな達人だったのか」 ・「どのようにして達人になったのか」 いろいろなエピソードで語られていきます。 最近英語をやる気がおきない… そんなときの気分転換におすすめです。
3投稿日: 2013.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治から戦後にかけて活躍した国際人たちが、いかにして英語を習得したかという本。新書だから仕方ないけど、もうちょっと掘り下げたものが読みたかったです。
0投稿日: 2013.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログNHK テレビ3か月トピック英会話「聴く読むわかる!英文学の名作名場面」の講師をしていた斎藤兆史さんの書いた本.明治時代から終戦直後にかけて活躍した英語の達人を10人選んで,その人たちの英語史が語られている.外国で育って英語を学んだのではなく,日本で英語を学んで達人になった人を選んで,日本で英語を学ぶことの意義までを考えさせる仕掛けになっている. これが非常におもしろい.みんな個性的な人ばかりだ.英語という側面に話をしぼることによって,これまで知っていた人の知らなかった部分が見えたり,私がこれまで知らなかった外交官,斎藤博や英文学者,岩崎民平といった人たちを知ることができてとてもよかった.先に読んだ「女の旅」と一人,一人に割いているページ数は同じながらも,こちらはかなり充実感がある. 取り上げられている人の中で,特に印象に残ったのは岡倉天心,西脇順三郎. またときどきはさまれる英語の先生の悩みとか,英語教育に関する考えなども興味深く読んだ.
0投稿日: 2013.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ札幌での研修会で名前が出てきたことから、その後立ち寄った本屋で氏の名前に触れて衝動的に購入。帰りの汽車で読むことができた。近代日本をつくりあげた歴史上の人々と英語の関係について、詳細簡潔に述べられている。また、昨今の英語教育に関する氏の危惧がところどころにちりばめられているのも興味深く、取り上げた達人たちに対する、また英語学習・英語教育への氏の想いを感じながら読むことができる。英語道は遠く険しいが、同時にやはり面白いものであることを再確認できる良書であった。
0投稿日: 2012.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ英語の化け物の偉人達の伝記。 取り上げているのは基本的に幼少時に海外生活をしていないもの。つまり、帰国子女っぽい人は外している。英語の基礎は日本国内で学んだ人たちばかりである。多くは学習後に海外でも研鑽を積んでいるが、海外に渡った時点でのレベルも相当のものというか、異常なレベルの高さ。 英語の達人、英語を一つの学問としてそれを研究するというばかりでなく、何らかの手段として英語を学び自分の目的を達するために英語を学ぶのだけど、道具としての英語がそれはもう一流である。彼らは日本人の中では最高クラス、それどころか英語圏の人たちの中でもトップレベルの英語力を備えている。 自分の研究対象が専門的であればあるほど、それに対応する英語も高度になってくる。 面白い人物が挙げられている。 野口英世 新渡戸稲造 岡倉天心 幣原喜重郎 白州次郎 岡倉天心のエピソードは特に面白い。 英語学習の何らかの学ぶ本としてはあまり期待できない。とても真似できない。
0投稿日: 2012.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ▼日本で生まれ、日本に生きる日本人なのだから、日本人に合った英語の習得法があるはずである――筆者は言う核心は、ここにある。留学経験はないけれど、英語でコミュニケーションがはかれるようになりたい!そんな自分を励ますように、と、この本を手にとった。 ▼「来た球を打つだけだ」と言えるのは、実は、彼らが天才だから(だけ)でなく、それまでの過程を、努力によって知らずもがな身につけていたからである。だとすれば、彼らの努力の方法を尋ねようとするのは、愚行でしかないのかもしれない。結局、彼らの生まれた環境が……と、思わなかったと言えばウソになるが、まだ頑張る余地はありそうだ、と思い直すいいきっかけにもなった。 ▼ちなみに、「英語」に捉われるこなく、単にエッセイとして楽しむことも(もちろん)可能で、最後に収録されている白洲次郎の章を読むだけでも、充分に、本書を手にとる価値があると思う。
0投稿日: 2012.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
非常に面白かった。 過去の偉人たちがどう英語を学び、どう英語に対処してきたか 英語の学び方というだけでなく、歴史の勉強にもなる。 また、日本人としてどうあるべきかを考えさせてもくれる。 幣原喜重郎の章に出てくるデニソン氏をはじめ 表舞台に立つことがなかったが、素晴らしい人たちの言動を 知ることができるだけでも素晴らしい本だし なにより筆者が英語至上主義であることもなく 分野が違うことには自分は門外漢であると潔く言い 自分の目で見たことや経験したことを交えてわかりやすく きっぱりと書いてくれており、筆者の魅力も感じられる本。 英語を話す日本人は、英語を話しているとき普段と人格まで変わる という話を聞いたことがあるが 英語を話していても普段と態度が変わらない人こそ 本当の意味で英語を習得した人なのだろうと思った。 日本国内で日本人なのにも関わらず 英語をもてはやしたり、社内の公用語にしたり 「日本人の男はだらしない」などと言う女がいる昨今、 『西洋かぶれになることなく、またその反動として偏狭な国粋主義に陥ることなく』 『日本人として英語を使うことの意味』 を踏まえた上で英語を操れる人間になりたいと思った。 そうなれた暁には是非、着物を来て外国旅行に行きたいものだ。
0投稿日: 2012.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. 新渡戸稲造 2. 岡倉天心 3. 斎藤秀三郎 4. 鈴木大拙 5. 幣原喜重郎 6. 野口英世 7. 斎藤博 8. 岩崎民平 9. 西脇順三郎 10. 白洲次郎
0投稿日: 2011.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ使える英語とかオーラルコミュニケーションじゃない。これからの日本に必要のなのは、"英語道"だと感じた。 徹底した修行に裏打ちされた英語を武器に世界に出て行く。 日本の夜明けには、現代の英語達人が必要だろう。 残念なのは、自分には到底その資質がない事だ。 日本のことをあまりに知らない自分に驚く。 恥ずかしながら、「武士道」が英語で最初に書かれたことなんてはじめて知った。
0投稿日: 2011.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・茂木健一郎のツイートを見て読むことにした ・「言葉そのものに対する感受性が語学力を左右するように思われる」それほど語学力はないが、感受性についてはそれなりにある方だと自負している。ほんの少しやる気が出た。・・・とか書いてはみたものの、後半まで読み進めると、自分の言語感覚など大したものではないと思い知らされた。嫌になる。 ・多読の重要性を感じた
0投稿日: 2011.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 「日本人は英語が苦手だ」という通念など、信じるに足らない。 かつての日本には、驚嘆すべき英語の使い手がいた。 日本にいながらにして、英米人も舌を巻くほどの英語力を身につけた「達人」たちは、西洋かぶれになることなく、外国文化との真の交流を実践した。 岡倉天心、斎藤秀三郎、野口英世、岩崎民平、白洲次郎ら、十人の「英語マスター法」をヴィヴィッドに紹介する本書は、英語受容をめぐる日本近代文化史を描きだす。 [ 目次 ] 第1章 新渡戸稲造 第2章 岡倉天心 第3章 斎藤秀三郎 第4章 鈴木大拙 第5章 幣原喜重郎 第6章 野口英世 第7章 斎藤博 第8章 岩崎民平 第9章 西脇順三郎 第10章 白洲次郎 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ近年の文法軽視、会話重視の英語学習に疑問を感じる人は読んでおきたい一冊。歴史に名を残すような偉人の努力量はすさまじい。日本人として英語を使うことの意味を考えていきたい。
0投稿日: 2011.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ新渡戸稲造にはじまり、白州次郎に終わる日本の英語達人の英語熟達度とその方法を紹介した本。洒脱な文章でとても読みやすい。また、日本人が本質的に英語がだめ、という誤謬を正し、また僕らが英語ができないあれやこれやの言い訳を一刀両断してくれる。外国人に「英語が上手」と「貶められる」意味も教えてくれる。
2投稿日: 2011.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ過去の偉人達がどうやって英語と向き合ってきたのかがわかります。こういう人たちがいたからこそ、今の日本があるのだと思います。
0投稿日: 2011.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ札幌農学校に学んだ新渡戸稲造からスタート。日本国内で英語をマスターした達人を列挙。十分な教材もないままとにかく英語の文章を読むことから始めたような印象を受けました。国内にいてはあたれる原典が限られているせいか、シェイクスピアすら読むという。オーラルコミュニケーションの授業が人気であったりする昨今、やはり自学自習の基本は読む、これにつきると思った次第です。それと達人それぞれに外交の仕事、研究者としての仕事があり、英語修得のその先に日本の明治から昭和を形作る人材で、日本の仕事をしているという高い志しがありました。今だったらお金や時間のことさえ解決すれば簡単に留学できてしまうところなのに。これを読んだら英語の勉強ができない言い訳ができない。
0投稿日: 2011.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ岡倉天心が弟子の横山大観とボストンの街を歩いていて、人種差別的発言をされたが、見事に英語でやり返したエピソードがある。 著者も気に入っているのか、白洲次郎の項目でも、彼が占領軍に対し機転を利かせて応えたエピソードに、これを引き合いに出している。 アマゾンのレビューに、この本の中の10人の内8人までもが英語以外の分野で高名であることに留意しないといけない、彼らにとって英語とは手段でしかなく、目的ではなかった、という評があったが、まさに正鵠を射るものである。 達人たちの英語勉強法が皆目紹介されていないという事実が、逆説的にそれだけ膨大な時間と努力を費やしたからこそ達人たりえた、ということを雄弁に語っている。 唯一気になったのが、著者は野口英世をあまり好ましく思っていないのではないか、ということ。 戦前の木口小平よろしく、戦後教育において野口の神格化を苦々しく思っているのかもしれないが、それにしても「だが、彼の生き方には、後輩たちが真似をしてはいけない部分がある。人として守るべき礼節の規範に適わぬ部分がある。」とまで言うからには、我々の知らないどんな背徳のエピソードがあったのかと思ったが、彼の遊興や浪費を「人生の汚点」としていた。そんなことで汚点と言うのであれば、私などは汚れに汚れきった人生であると言わなければいけないし、現代の学生を見てもそんなにストイックなまでに学問一筋で脇目もふらず、という人はいないのではないか。 ということで、野口英世にだけ異様に厳しいのがバランスを欠くように感じたので星四つ。
0投稿日: 2010.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログwhat sort of "nese" are you people ? are you chinese, or japanese, or jvanese ? we are japanese gentlemen. but waht kind of "key" are you ? are you a yankee, or a donkey, or a monkey? 岡倉天心がカッコイイ
0投稿日: 2009.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログどなたかもご指摘されていますが、斎藤先生の一連の著作のルーツとなるのがこの本。 現在のコミュニケーション偏重・文法軽視の日本の英語教育に警鐘を鳴らし続ける斎藤先生は、英語受容期からの昭和までの「英語達人」らの驚くべき学習法を示しながら、本当に英語の力を付けるためにはどうすれば良いのかを説く。図書館の洋書を片っ端から読んでいった者から、辞書を暗記しては食べて!?いたという者まで、達人たちはやはりタダモノではないが、彼らの学習法に共通している学習法は何かと考えるのは、現代のわたしたちにとっても有益だと思う。
0投稿日: 2009.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ斎藤先生と言えば、一般向けには、『英語達人塾』、『日本人に一番合った英語学習法』、『これが正しい!英語学習法』など一連の英語学習法の指南書の中で、一貫して素読、多読、精読などのやり方で地道に、確実に英語を読みながら、英語の上級者を目指すための方法や心構えを紹介し、昨今の会話重視・文法軽視の英語教育を批判するという著作が多いが、それらの本の根本にあるのはこの本(というかこの本の元ネタとなった雑誌の連載)にあると思う。明治期から昭和期にかけて活躍した英語の「達人」10人の英語学習、英語にまつわるエピソードを、当時の日本の状況や昨今の英語教育への批判を交えながら紹介するというスタイル。個人的には「巨人」斎藤秀三郎や、辞書の岩崎民平なんかが興味深かったが、日本の戦後政策に関わった幣原喜重郎、白洲次郎なんかも面白い。野口英世の人柄が評価されていなくてショックだった。(07/07/02)
0投稿日: 2008.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ訳あって、斎藤先生から直接頂戴しました。 雑談気味に、日本の英語教育の問題点が盛り込まれているところも、実は読みどころ。
0投稿日: 2007.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書としては軽いものだが、なかなか面白い。 英語の達人(この達人というのは著者の基準に基づいているが)の半端ない勉強法がさまざまなエピソードを交えつつ書かれている。大いに刺激を受けることは間違いない。 同時に今まで半端な勉強しかしていなかったのかもしれないと内心忸怩たる思いであった。
0投稿日: 2006.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ過去の偉人の努力は並大抵じゃぁないね。 全員意外と初等から外国人の先生に教えてもらっていることをのぞいて、各自の努力の量が半端ではなくて、本当に語学習得はスポーツだ!といわれる齋藤さんの意見に賛同したくなる内容です。
0投稿日: 2005.04.23
