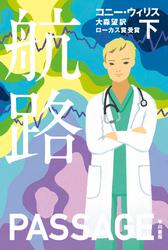
総合評価
(23件)| 10 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
え〜、まだ下巻のこんなにページが残っている段階で、主人公がこんな事になってしまって、いったい作者はどうオチをつけるのだろう…(だからといって、ハイテンポでどんどん事態が進んで、どんでん返しのまたどんでん返し、などという展開では全くありません)
0投稿日: 2024.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨死体験を科学的に解き明かすSF。 ”科学的であること”に対する深い信頼と、それ自体がエンターテイメントになりうるという確信。 まさにSFとしか呼びようのない傑作小説でした。 本を読んでいるとたまに自分の読む速度が遅いのが悔やまれることがある。もっと読みたい、もっと先を知りたい!それなのにどうして私の読書スピードはこんなにも遅いのか!! そんな憤りすら感じられるほど面白い。 面白すぎて、脳みそが蕩けてしまいそうなほど。
0投稿日: 2022.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
220519*読了 ちょっと、ちょっと、ちょっと! 上巻の感想に書いてたヨミが当たり、下巻は最強だった。 もし、上巻でめげそうになり、読むのをやめようとする人がいるなら全力で止めたい。 下巻を読み出したら、止まらないから、と教えたい。 ジョアンナ…まさかすぎる。衝撃すぎて、カフェで読みながら声が出たと思う。 こんな展開になるとは思ってもみなかった。 ただNDEの謎を解明するストーリーじゃなかった。 ありきたりな言葉になってしまうけれど、愛と感動のストーリーと表現するにふさわしい。 ジョアンナの願いが思いが届き、メイジーが救われるラストのシーンは鳥肌。 こんなにも感動する小説だったなんて、本当に予想していなかった。 読めてよかった。この小説をつまらないという人はいないんじゃないの?もしくは上巻で諦めた人だけなんじゃないの? それぐらい、黙って下巻まで読んで!と言いたいです。 ジョアンナが必死に解き明かし、残そうとしてくれたメッセージを受け取って、彼らは前を向いて、まだ先の長い航路を進むのでしょう。 タイトルも秀逸。航路って。そう、航路ですね、って読み終えたら感じられます。 たくさんの人におすすめしまくりたい小説。 いい小説に出会えました。
1投稿日: 2022.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨死体験をめぐる医学SF。読み終えた直後の率直な感想は、「あ〜長かった」のひとことにつきるかな。医学、文学、映画、そして遭難事故などに関する情報量とディティールはすごいが、それが面白さにつながっているのかは微妙。とにかくすべてが冗長に感じられる長ったらしい文体、これを楽しめるかどうか。第二部のラストで仰天させられ、ようやく面白くなってきた時点で残り4分の1。医学的にどこまでが実在の話なのかはわからないが、ミステリの謎解きのようになるほどと納得のできる着地はする。その過程を楽しめるかどうか。正直自分にはいまひとつ、合わなかったようだ。 キャラクターは魅力的だが、臨死というテーマの深刻さをユーモアとコミカルさで緩和している感じ。ギャグもそれほど笑えない。これはこの作家の作風なのか。もう少しロマンス色が濃いほうが好みなので、そのあたりも不満が残る。 初めてのコニー・ウィリス、圧倒的に評価の高い作家なのでこれにこりずに、もう何作か読んでみようと思う。
0投稿日: 2021.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ完ぺきなどんでん返し 驚いた。タイタニックもヒロインの大活躍もありふれたラブストーリーもなく、シンプルこの上ない真実が下巻中盤で解き明かされる。 で、このあとどうなるの? 全体から見て残り1/4は謎ときが終わってからのエピローグかと思った。でも、ここからが本題だったのかもしれない。かなり長すぎる気がするけど、ヒロインの存在感が一気に浮上する第4四半期だな。文庫1,200ベージ読了だ。
0投稿日: 2020.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半の、ユーモアも交えつつ、あっちへ行ったりこっちで隠れたり、みたいなドタバタ劇も楽しかったけど、本下巻では、結構展開がスリリングになってくる。物語の核心に近付いていきつつ、でも本巻の中盤でまさかの主人公死亡事態が発生して、どうなるのかと思いきや、そこからは謎解きの面白さも加味しながら、感動の結末へ突き進む。主人公亡き後とはいえ、二章に一章は死後の世界における主人公の活躍が描かれるから喪失感はさほど無く、悲しみのカラーってよりは、むしろ次の世代に託された希望のカラーのイメージの方が強い。かなりの長編だったけど、翻訳の妙もあって、どんどん読み進められる良品でした。
0投稿日: 2018.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻は第一部のスローな日常の反復描写のために、かなり時間がかかった。しかし第二部から、もっといえば下巻からはもう止まることはできなかった。もう、止まれるわけがなかった。そして着地、なんと見事か。
1投稿日: 2018.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻が一週間くらいかかったので、下巻も時間かかるかなと思ったら、どんどん読んでしまって2日で読んでしまった。生きているもの、死んでいるもの、その全てが繋がっていてどちらも遠くから手を振っているような。すごいな。すごい本。SFは得意ではないけどこんな本があるならたまには読まないと損をするなと感じた。とにかくすごい本だった。
0投稿日: 2017.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨死体験がテーマのSF。認知心理学者ジョアンナは自ら臨死体験の研究プロジェクトの被験者となり、すこしずつ臨死体験の謎を解明していく。 上下巻でそれぞれ650ページずつくらいの大長編だけど、ジョアンナが「潜り」はじめてからは、一歩一歩着実に真相に近づいていき、どんどん先が気になってくる。臨死体験の謎が、予想もしてないようなことにつながっていき、展開がよめない。真相にたどりつきそうでなかなかたどりつかない様子が、舞台の病院が改装工事や通行止めばかりだったり、登場人物たちが留守電やポケベルの行き違いなどでなかなか連絡がとれなかったりする描写と重なり、いろんな意味でこちらももどかしい。 第2部の終わりでまさかの展開で、下巻はもう一気に読めてしまう。衝撃も大きく、最後までよめば展開に納得するものの、やっぱりショック。医学的な研究がテーマだけれど、映画や文学が多く登場し、高校時代の英語の先生がキーパーソン。主人公たちの臨死体験の研究も、そういったものからヒントを得る。象徴的なラストまで読みきると、もう一度最初から読み返し、すべてをひろって考えたくなる。冗長だった部分にも意味があり、物語のいたるところで暗示されていたもの、メタファー……振り返ってみるととても文学的なSFだった。感動号泣、というより、凪がおわった海みたいに心がゆれるような感覚。 ジョアンナとリチャードをはじめ、ジョアンナの親友ヴィエルも、心臓病の幼い入院患者メイジー、敵役のミスター・マンドレイクなど登場人物はみんなわりと典型的なのに魅力的。典型的だからこそかな。ころころと映画をみているよう。文庫のカバー、上巻がメイジーで下巻がリチャードかな。上巻、なんでジョアンナじゃないんだろうと思ってたけど、読んだらちょっとわかった。
0投稿日: 2017.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
無意識下って不思議。 いつ誰が何に対して何を思って、それが様々なメタファーになってあらわれるか 本人にもわからない。 人それぞれにNDEのビジョンがあるなら楽しいな。 登場人物、物語に流れる空気感が心地よかった。 病院で職務に従事する人たち、すごく素敵でした。 あとやっぱり、ドクター・ライトがチャーミング。すき。
0投稿日: 2017.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ジョアンナは薄皮を1枚1枚剥がすみたいに臨死体験の真相に近付いていく。迷路のような病院の構造に伝言ゲームみたいな留守電とポケベルでのやり取りが、あと少しで真相に手が届きそうで届かない状態と相まって読んでいるこちらも非常にもどかしい。そして、二部の終わりでの驚きの出来事の後は、結末が気になり読書をやめることができなくなりました。海外の作品は苦手という人も多いし、上下巻合わせると1300ページという長編なので誰にでもお勧めという訳には行きませんが、どちらも平気という方には是非読んでみて!と勧めたい作品です。
1投稿日: 2016.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログまさかこんな展開?!びっくりしたけれど、最後まで読み進めて納得。 さて、私の若き読書仲間はこの長さに耐えられるか?!
0投稿日: 2016.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなことになるなんて… どうしてウィリス作品の登場人物たちは人の話を聞かないんだろうか どんでん返しがいつくるかないつくるかなと淡い期待をして辛いけど最期まで読んだ 喪失感 はあ…
2投稿日: 2014.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かに第2部終盤には驚かされた。 そして、そこから始まる並行の物語は (現実では並行ではないけど) 本当に静かな余韻を漂わせるラストへ。 帯にあるような「魂を揺さぶる感動巨編」とまでは 思わないが臨死体験を通して生と死に向き合う。
0投稿日: 2014.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ既読の本の中のどこかで(もしかしたら解説かも)紹介されていて、 たしか傑作と表されていた気がしたので、ボリューム満点だけど読んでみた。 文字通り“象徴的”なラストだった・・・。 臨死の中で人は何を見て、何を体験するのか。 それは統一されたイメージなのか、それともメタファーか。 はたまたもうひとつのリアル(現実)なのか・・・。 日本で言えば三途の川のあっち側とこっち側ってのが有名(?)だけど、 本書ではちょっと違った切り口で医学的にドラマチックに解説されて興味深い。 雰囲気はアメリカのテレビドラマ、『グレイズ・アナトミー』みたいな感じ。 序盤はあんまり進展しないんだけど、なんだかんだでいつの間にかめくったページがたくさん。 正直こんなに長くなくてもいいんじゃなかろうかと思いながら読んでいたけど、 先述のラストを体験した今、途中もっとちゃんと読み込めばよかったな・・・ と、意味もなく反省。
0投稿日: 2014.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログヴィレッジブックスにて読みました。 ハヤカワから復刊とのこと、喜ばしい。買います。 人生のベスト3です。 しばらく他の本読めませんでした。 圧倒的な読後感。 人に面白いよ、って話すのですが、内容全く伝わらない。もどかしい。
1投稿日: 2014.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 二日がかりで一気に読みました。 臨死体験が薬によって再現できる、という設定の元に認知心理学者の主人公が擬似臨死体験のプロジェクトに参加することになるのですが、そのうち自身がその被験者となり、そこで行った先は何とあの歴史上有名なアノ場所だった!と分かるところで第一部が終了します。この辺りで上巻の半分強、ここまでは多少冗長な展開なところもありましたが、そこから先の上巻の終わり、そして衝撃的な第二部のくくりを経て最後へと続くところはまさにノンストップノベルという感じ!訳者があとがきで作者コニー・ウィリスは常々日本の宮部みゆきだと言っているのだが、と書いてますが、まったく同感です。衝撃的な展開が第二部で来るのでその後どうなるのか、とても気になって気になって読み進めて、最後も裏切られませんでした。(最後に「え〜?」という展開の小説もありますしねえ) 医学ミステリやドラマぐらいの医薬品の名前や作用、アメリカのERの物騒さなど背景に忌避感がないのなら、読んできっと楽しめると思いますよ。久しぶりに海外翻訳物でアタリを引いた感じです。
1投稿日: 2014.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二部の終了後、驚愕と衝撃と、これが夢オチなら三文小説だ!と思った。 でも三部で粛々と話が進み、混乱と新たな謎に立ち向かって行く。 メイジーには何度も涙腺を攻撃されました。 ラストの58章は特にがつんとやられました。58章って!58!!
1投稿日: 2013.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログもうずいぶん前に読んだ気がするけど登場する映画タイトルとかみると十年ちょっとしか経っていないのか。 再読しても面白さと感動は変わらず❗️。 表紙の変わった「ドゥームズデイ・ブック」も買いなおしたい。前の表紙担当の方には申し訳ないけど、大嫌いでした。あれで読む気を削がれましたもの。
0投稿日: 2013.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外小説の中でも1,2位を争うほど好きな小説。 新たに文庫で読めるようになってとても嬉しい。 今回再読して初めてこんなにメタファーが重ねられていることに気づいた。 すごい構築力。
0投稿日: 2013.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨死体験がテーマのSF大作……の、下巻。 まさかああいうことになるとは思ってもみなかったが、最後まで読むとやっぱりああするのが一番いいと納得が出来る。 上巻はやや冗長さを感じたが、下巻は長さを感じなかった。
0投稿日: 2013.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨死体験という現象に科学的なアプローチをし、その成果を描いてこの小説は終わるのだけど。こんなにも涙腺を刺激されるのは、それでもやはりどこかで願っているからだ。繋がっていると思いたいからだ。作中の人々も、それを読むわたしも、誰もが。それはもちろん、思いたいだけなのだけれど。 読み終えた…。以前図書館で貸りて読んだ時には読み切れなかったんでしたorz… 上巻後半から下巻3分の1くらいまでとにかく延々と「思い出せそうで思い出せない」が繰り返されるので、読み続けるのがかなりしんどい。プロジェクトの難航と併せて、とにかくフラストレーションが溜まる。主人公にイラついてきたりもする(~"~;) …しかしとにかくがまんして読み進めるがいいのです。そして泣くがいいのです。
0投稿日: 2013.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直,上巻の方は微妙な感じだったけど下巻に入ってからがすごい.あと,しんみりと怖い.この感じはだいぶ久しぶり.
0投稿日: 2013.08.09
