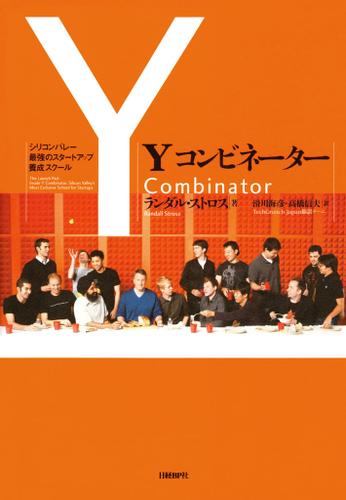
総合評価
(43件)| 10 | ||
| 21 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ●2025年10月1日、メルカリで「ファスト&スロー」を上下1,000円で仕入れたところから、袋もなんもなく箱に入って届いてびっくりしたからその人の評価を確認しにのぞいた。そしたらまた本が出てたのでチェックしてて、これを見つけた。
1投稿日: 2025.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログアクセラレーター、インキュベーターの様子がよくわかる本。この本読んでポール・グレアムのTwitterをフォローするとオモロい。ピーター・ティールのゼロワン本も読むといいかも。
1投稿日: 2021.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログスタートアップがどんな感じが体験できます。 創業者になるには五つの資質が必要。 この素質は25歳が最適。 スタミナ 貧乏 根無し草性 同僚、 無知。
0投稿日: 2021.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログベンチャーキャピタルに興味があり、どのような人たちが参画しているのか知りたく、読んでみました。 起業を目指す若者を集めて、アイデアを出し、数か月間導く、資金もつける、卒業後は横のつながりも含めてサポートしていくという流れでした。 予想以上に、仕組みとして確立していることを感じます。 少し古い本ですが、ご興味あれば。
0投稿日: 2020.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ有名なベンチャー企業育成組織であるYコンビネータに密着取材したドキュメンタリー。ベンチャー企業の卵たちはどういうマインドセットで日々を過ごしているのかが分かりました。
0投稿日: 2020.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログAirbnbの本を読んでいたらYコンビネーターの事がよく出てきたので、それで調べていたらこの本を見つけて読んだ。 スタートアップの環境がシリコンバレーにはある。 そんなに目新しい事を、ここでしか真似出来ないことをやってるいる訳ではないので結局のところそれしかない。
0投稿日: 2020.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業家の熱を感じられる書。 スタートアップで働くひとは読むとシリコンバレーの感覚を味わえるかもしれません。
0投稿日: 2019.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログYコンビネータ (wikipedia) が行っているベンチャー企業投資プログラムと、参加ベンチャー達の3ヶ月間の奮闘の様子を描いた本。 Yコンビネータの投資方法が面白く、 - 同時に数十社のソフトウェアスタートアップに対して、スタートアップの株式7%を引き換えに約100-200万円ほど出資する。 - 投資を受けたチームは、3ヶ月間、Yコンビネータがあるシリコンバレーに引っ越してきて、プロダクトを作り続ける。 - いつでもYコンビネータの役員(多くはスタートアップ成功者)の助言を受けられる。(成功の確率が上がる。) - 最終日にある デモ・デー(数多くの有力な投資家の前でピッチする日) があり、更に多くの資金を得るチャンスが得られる。 - Yコンビネータに出資を受けたスタートアップは成功率が高いので、投資家にとっても魅力的に映る。 というもので、成功例としては、Dropbox, Airbnb, Heroku などがあるよう。 印象に残ったトピックは、 - スケールしないビジネスは「スモールビジネスの開業」、スケールするビジネスは「スタートアップの開業」。スケールしないの例は、webサイトのデザインを助言するコンサル会社、など。一社一社人手で回らないと成果が出ない。スケールするの例は、webサイトの構築の自動化をし、作成を用意にできるソフトを販売する会社、など。ソフトを作れば爆発的な速度で広まる。 - リーン・スタートアップの考え方をかなり取り入れている。「できるだけ早くプロダクトを作り上げて、即刻リリースし、ユーザからフィードバックを集めて、改良する」を繰り返す。 - 忙しく間違ったことをして過ごさない(正解は顧客の声) 本の中では、20数社ほどのスタートアップの試行錯誤の様子が具体的に描かれており、とてもエネルギッシュでパワーが得られた。「どんな人たちが挑戦しているのか」、「どんなことを思いついたのか」、「その思いついたことをブラッシュアップしていく過程はどんなものなのか」、「それぞれの局面でYコンビネータの役員達はどんな助言をするのか」などが詳細に書かれており、参考になった。
0投稿日: 2019.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業家の熱気を感じ取れる本。実際に企業をはじめようと考えるか、始めたときに、とっても励みになる内容と思う。同じような苦労、苦しみ、高揚感を感じることができそう。これらがあれば、くじけそうになる気持ちの支えになると思う。実際にくじける必要はなく、だめでも、また再チャレンジすれば良いという割り切りの獲得もできる思う。実際にフリーになったとき、再読したい一冊。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ『Yコンビネーター』読んだ。2011年時点の密着ドキュメントだが、今読んでも新鮮な内容と学び。グレアムが『ハッカーと画家』で披瀝している類稀なる知性と思考を、ここまで見事に社会実装していることに賞賛するほかない。
1投稿日: 2018.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログとある学生起業家育成のプログラムに携わっており、場をつくるところでYCのあり方を改めて参考にしてみたくて読みました。ポール・グレアム氏は、他の国に欠けているのは起業家精神ではなく、多くの創業者が集中する場所だと言います。熱量が集中し、トライ&エラーが共有され、独立心を損なわれない場所づくりを考え抜いて進化していくのがYCであり、やはり引力とフィルタの両方が働くというのが大事なんだなぁと言うのが見てとれました。
0投稿日: 2017.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログあるタームのyコンビネータの取り組み方を時系列に、第三者の立場から運営、参加者の内容をまとめてあり、スタートアップ企業を始めるノウハウが詰まっていた。ひたすらブラッシュアップする、相談する、プレゼンの見せ方、プロトでの進め方など、なるほどと思うことばかりだった。ノンフィクションみたいで、成長の様子も気になった。 改めてDropboxはすごいと感じた。
0投稿日: 2016.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログスタートアップが生まれるYコンビネーターを取材してまとめたもの。 スタートアップが生まれる環境を理解できる一冊
0投稿日: 2016.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書はYコンビネータ−(以下「YC」)の門を叩いた創業者の卵たち(けれども金のがちょうの可能性が高い)のドキュメンタリーだ。グレアムのカリスマ性や鋭さが感じ取れる。 「ユーザーと向き合え」「コードを書け」「週次で目標を達成しろ」「右肩上がりは素晴らしい」、YCの掲げる標榜は極めてシンプルだ。 YCの特に取り組みの素晴らしい点はシリコンバレーの生態系を箱庭的かつ人為的に生み出そうとしている点だ。シリーズAにも満たないアイデアに少額を張って尻を叩いて成長させる。このYCの仕組みであれば全世界でシリコンバレーの生態系を生み出せるかもしれない。
0投稿日: 2016.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ本文と関係ないけどIggy PopのSearch and Destroyを朝から爆音で鳴らしても怒らないむしろ高まるようなハッカーチームでcodeを書き始めることが日常のような環境で、あわよくば住み込みでニュープロダクトを創りたい気持ちが高まった。
0投稿日: 2016.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログYCのドキュメンタリー本。読んでいる自分までYCでデモ・デーに向けてあくせくしていくような気分になる。自分もいつかここで!
0投稿日: 2015.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ【老舗シードVCのYCに迫る!】 創業者ポール・グレアムが「アクセラレーションプログラム」と言われるのを嫌がっているので、シードVCと記述するが、このYCの登竜門をくぐり抜けた卒業生のエリートさは半端ない。 ドロップボックスやAirbnbなどのユニコーン企業が生まれているのである。一方で、ポール・グレアムが言っているように必ずしも成功するわけではないということで、実際YCの通った人の話を直に聞いたことあるが、やはりビジネスとは一筋縄にはいかないというのが見て取れる。 ある意味、ネット上で拾ってこられる情報ばかりではあるが、YCの流れやYCが求めているチームなどがわかるので、YCに応募しようと考えているのであれば、一読することをおすすめする。
0投稿日: 2015.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログスタートアップとは、単なるベンチャー起業じゃない。急速に成長する市場を開拓する企業なのである。 そんなスタートアップを育成するシリコンバレーにあるスクールが”Yコンビネーター”である。 これはある学期の始まりから終わりまでの様子を密着取材したものである。 これを読めば少しはシリコンバレーのスタートアップがどのようなことを経験しているのか分かるかもしれない。 しかし、焦点をあてているスタートアップも多く、感情移入したりはできなかった。また、どんなことをしているのかについても情報に乏しい気がします。 まあ、冒頭にも書いているようにハッカーの仕事あパソコンの前でコードを書くことなので、見てても面白いものではないからなのかもしれませんが・・・。
0投稿日: 2015.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログシリコンバレー最強のスタートアップ養成スクール「Yコンビネーター」。ハッカーと金持ちの世界、大変刺激的な内容でした。特に指導者でもあるポール・グレアム氏に興味を持ちました。
0投稿日: 2014.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログカリフォルニア、シリコンバレーにあるシード投資集団Yコンビネーター(以下YC)。ITベンチャーに関わる人であれば一度くらいは名前を聞いた事のある有名な投資集団、その創設者は、IT業界関係者であれば名前を知らない事が恥ずかしいとも言える有名人、「ハッカーと画家」の著者ポール・グレアムだ。 そのYCだが、実態は秘密にされる事が多く、具体的にどこに投資されたのかすら明かされない場合も多かった。しかし本書では実際にYCの1スパンに密着し、多くのインタビューやミートアップへの参加により細かい描写がされ自分もそこにいるかのような臨場感に溢れる一冊となっている。既にITスタートアップに勤務しているのなら必読、ITスタートアップに興味がある人にとってもかなりオススメの一冊と言えるだろう。 さて、自分はITスタートアップに勤務している立場だ。そうすると勿論周りのITスタートアップも普通の企業に所属しているよりは気にしているという立場でもある。 そのような立場でもって読んだ感想は、月並みではあるがシリコンバレーと東京の環境があまりにも違うという事だ。 細かい違いは本書を読めば嫌でも分かると思うので割愛するが、ざっくりと書くとシリコンバレーでは超優秀なハッカー達が伝説的なハッカーポールグレアムのアドバイスを受けて合宿し、文字通り「死に物狂い」でベンチャーキャピタルへ売り込む為のデモ作成とプレゼンを行うのである。 その合宿で興味を惹かれるのが ・とりあえずシリコンバレーに住む事(シリコンバレーは世界でも有数の生活費がかかる事で有名) ・リクルートされたパートナーには「24時間」という勤務時間以外ありえない ・合宿期間中は家族や恋人、友人等とは連絡を取らない事が推奨される。むしろYC参加中と言えば簡単に断れるだろうから好都合だよね!と言った具合である。 これが良いか悪いかは判断が分かれるところだが、少なくともスタートアップを成功させたいのならば、大事な時期にこういう取り組みが必要だという事は何となく理解できる。もちろん、こういった働き方への取り組みだけでなく、アイデアをどう練るかやベンチャーキャピタルへのプレゼンについても参考になる記述が散りばめられている。 最後に一つ強く印象に残るのが、シリコンバレーでこれをやってるのは凡人ではなくて超がつく程の優秀な人物達であるという事だ。このような環境でやっているシリコンバレーのスタートアップに、日本のスタートアップがまともに闘っていくというのは殆ど無理な話だろう。だが本書を読むとそこで簡単に諦める必要も無い、著者が語る様に今やソフトウェア産業は世界を食い尽くす勢いで成長している。このような産業の源泉が永遠に1地域にとどまるというのは、それはそれで考え辛い事だ。 シリコンバレーが産まれた理由にはいくつかの偶然はあるものの、基本的には人が手を加えて作られたITベンチャーの聖地だと思っている。そうであれば別の地域でも「真剣に」取り組めば作る事も可能だと思う。ただし、それを実現するにはポールグレアムも語る様にハッカーという一風変わったキャラクターを持つ集団を許容して育んで行く文化は絶対的に必要だろう、いつかは日本にもそういうフィールドが出来る事を強く願う。
0投稿日: 2014.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ# 感想 エンジニアが集まり、技術に興味のあるお金持ちが集まるシリコンバレーというのは特異な地域。 失敗に寛容でチャレンジする人にエールを送るそんなことが当たり前にカルチャーである。 日本にもシリコンバレーを作ろうという話を聞いたことがあるが、技術者は現れど金持ちや失敗に寛容なカルチャーは生まれるのだろうか。 シリコンバレーはシリコンバレー、日本は日本と思ってしまったのが悲しい所。それでもシリコンバレーのことを教えてくれるという意味ではこの本は役目を果たしている。 デモデーなんかでITスタートアップを成功させたポールグレアムやその他何かしらの成功者に見てもらい意見をもらうと言うのは大切なことだと思う。投資を見据えた行動ならなおさらこのことは大切で合理的だと思う。 失敗に寛容ではあるが、もちろん成功するに越したことはない。 成功率?いや、一つでも多く大きくするベストな方法の一つなんじゃないかと思う。
0投稿日: 2014.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログDropboxとairbnbを産んだスタートアップのアクセラレータとして有名なYコンビネータが、有望なチームを集めて開催する三ヶ月間の「学期」に著者が密着して取材を行ったドキュメント。著者が付いた学期からも先日Googleに買収されたTwitch.tvが出ている。 内容は、著者が取材した学期に参加した2011年の64のスタートアップのチームが成功を求めて奮闘する様子を描いたもの。核になるようなストーリー持つ企業がいくつかできればよかったのかなとも思うし、Yコンビネータを興したポール・グレアムにフォーカスを当ててももっと面白いものにできたのかなとも思う。ただ、少し面白くなくても(これは翻訳のせいかもしれないが)、彼らが実際に中で何をやっていたのかを記録して世に出したかったのかもしれない。その意味では有意義な本と言える。 シリコンバレーでベンチャがこれほどまでに次々と生まれるのは、周りに手本があるからだ、と言うグレアム。そしてその中で成功したものが次の手本になる。自分自身もベンチャを成功させた経験を持つ。こういう人がいるというのもシリコンバレーの強みだろう。 ---- いくつかチームを選んで3か月間の期間サポートし、最後にデモデーを設定して機関投資家に売り込む機会を作るという仕組み。KDDI∞ラボのやり方はここから来てたんだな。
0投稿日: 2014.06.23スタートアップ!
スタートアップを目指している人なら一度はYコンビネーター(YC)というベンチャーファンドの名前を聞いたことあると思います。 本書はそのYCに長期間密着取材したノンフィクションです。 実際にYCにいるようなリアリティがあり、多くのスタートアップ企業の成り立ちや成長が分かるので面白いです。 また、YCの創業者 ポール・グレアムなどの発言は勉強になります。 ・Minimum Viable Product ・コードを書け、顧客と話せ ・数字で測れるものを作れ などなど
1投稿日: 2014.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログたくさんのスタートアップ企業が登場し、その様子を窺い知ることができ、その活力によって元気がもらえる一冊。
0投稿日: 2014.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ遅ればせながらようやく読みました。Yコンビネータがどのように起業家を育てているのかが良くわかる。最近実務から随分離れてしまっているのだけども、2,3年前のシリコンバレーの様子はこんな感じなんだろうなと思う。
0投稿日: 2014.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログいまいち。ノンフィクションなスタートアップの現場の物語は面白いけど、訳の翻訳しました感が強すぎたり、アメリカアメリカしすぎたりしてすごく読みにくかった。ジョークも笑えない。
0投稿日: 2014.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体例がふんだんに書かれていて参考になりました!例えば、Day1からDemo Dayまでのダイナミックな日々の出来ごとや、Demo Day後の陥りやすいポイント、投資家との付き合い方等。 以下、個人的に気になったフレーズ等のメモ ・5年後にこのサービスが巨大化しているとしたら、それはなぜか。 ・その準備はいつ始めるのか。 ・山ほどの資金があったとして、どのくらい早く成長出来るか? ・投資判断の基準は、「私はこの創業者の下で働きたいと思うか?」 ・常に成長率に目を光らせる。
0投稿日: 2014.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログYC密着ドキュメンタリー作品。日々起こる細かな描写は起業プロセスにおいては法則やティップスなどないと言っているかの様。起業とはいかに無駄な事をやめ、本質的な所に集中させるかが重要であり、かつ何度もそれにチャレンジ出来る土壌あるか。作品全体に"How to"へ否定を感じる事が出来る傑作。
0投稿日: 2013.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ【本日の一冊(^O^)】 Yコンビネーター シリコンバレー 最強のスタートアップ養成スクール これは、スタートアップを目指す方は必読ですね! シリコンバレーの生の姿が読み取れます。 シリコンバレーが優れているところ、そのは起業家精神が他の国や地域よりも秀でているわけではなく、多くの創業者の集中だという。 「スタートアップが集積していない場所にいることは、スタートアップにとって害になる」 「他の地域では、人が大胆さに欠けるなどということではなく、手本に欠けていることが問題なのだ」 スタートアップの最終的な成功率は、0.3%くらいかもしれないと言う、創業者のグレアム氏。 ここ本を読んで、ワクワクするか、自分には無理と思うか。 シリコンバレー屈指の養成スクールへの密着取材の中から、シリコンバレーの今を知ることができる一冊です。
0投稿日: 2013.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログDropboxがこの世に生まれることを助けたことで世界的に著名なスタートアップ・ファンド、Yコンビネーターを描いたノンフィクション。 これまであまり知られることがなかったYコンビネーターの内幕を、2011年夏期を軸にした長期取材で明らかにしている。 Yコンビネーターのメンバーの中でも、やはりポール・グレアムのキャラの強さは飛び抜けていて、読めば、ポール・グレアムのファンになること間違いなし(笑)。 2011年夏期のYコンビネーター参加スタートアップには、今をときめくCode AcademyやMongoHQ、Parseなどがあって、おぉと思わせられた。オススメ。
0投稿日: 2013.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログベンチャーキャピタルに関するドキュメンタリーなのだが、エキサイティングな内容ではない。あくまでもたんたんと。 当たり前を当たり前にすることが成功なのだと思った。
0投稿日: 2013.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログYコンビネーターの参加者は一つの施設の中で、インキュベーション式に取り組んでいると思っていたのですが、実際は夕食会の時などにしか集合しないのは新しい発見でした。Dropbox, Airbnb, herokuなど活躍中の卒業生が他の卒業生の時価総額の大部分を占めているというのは、興味深かったです。codeacademyは利用しているので、さらに頑張って欲しいです。
0投稿日: 2013.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。こんな商売の仕方・教え方があるんだなぁ、と。グレアムの発言・視点もスタートアップ達の考えも勉強になる。難点は、自分が年を食ったなぁ、と少し凹む点。 。。。詳細。。。 クラウドを活かして即座にビジネスを立ち上げられるリーンスタートアップな時代になった。そんな時代の投資・インキュベーション方法。というか、本のタイトルにある通り、起業家の学校の話。 ソフトウェアが適用できる分野は、今や数限りなくある。ニーズは多すぎるので、ニーズのある人がサービスを作ればよい。リーンスタートアップなら小額でも商売を始められる。本当に必要かどうかは、ユーザに試させればよい。 出版社が著者を探して本を出すようなイメージに近い。違いはテキストを書くか、Interactive & Collaborativeコンテンツを書くか程度か。ソフトウェアの開発コスト・必要スキルは急激に下がりつつある。となると、ハッカー集積地のシリコンバレーでなくとも、YCのモデルは立ち上げやすい。お金とニーズと少数の活動家がいれば。
0投稿日: 2013.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログYコンビネーターの中にはいり、徹底取材し一冊。 Yコンビネーターは、tech crunchで登場のニュースをみていらい、注目してたのですが、秘密主義のこともありあまりわからないことが多かったのですが中のことが惜しげもなくかかれているので、スタートアップやシリコンバレーに興味のあるひとは読んだ方が良い一冊です。
0投稿日: 2013.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログスタートアップ企業だけに投資を行うYコンビネーター。Dropboxの創業期に投資をしたベンチャーキャピタルとして有名だが、その手法はユニークだ。スタートアップの卵を募集し、大学生が夏休みの3ヶ月間に、シリコンバレーで、合宿をする。本書で取り上げられている2011年は64社のスタートアップが集結し3ヶ月間学ぶ。いや、学ぶではないな。サバイバルするのだ。Yコンビネータに一律に15万ドルを投資してもらい、3ヶ月後に、たくさんの投資家を呼び、デモを行い、新たな資金調達をし、巣立っていくのだ。この3ヶ月間で、起業家は、Yコンビネータから助言や叱咤激励を受け、自らのアイディアを形にしていく。すべてのスタートアップが成功するわけではない。生物と同じように、生き残りをかけて戦い、最終的にごく僅かな起業家だけが生き残り、成功するのだ。Yコンビネータはサバイバルを仕組み化し、次々と素晴らしい企業を生み出し続けようとしていてとてもユニークだ。
0投稿日: 2013.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨場感ある独特な世界観にひきこまれ、まるで、スタートアップの創業者のような気分になり一気に読めた。また、ストーリー性のあるおもしろさとは別に、ビジネスの基本的な内容も盛り込まれており、(たとえば、プレゼンの部分だったりとか)最近まれにみる良書。時期をあけてまた読んでみたい。
0投稿日: 2013.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味あるなら、情報が新しい今のうちに読んでおいたほうがいいと思う。(Airbnbとか、数年経ったらスタートアップではなくなってるので。) オフィスを提供する場合には「インキュベータ」、そうでない場合には「アクセラレータ」 スタートアップの本質は単に新しい会社という点にはない。非常に急速に成長する新しいビジネスでなければいけない。 アイデアを生み出すための3箇条 1. 創業者自身が使いたいサービスであること 2. 創業者以外がつくり上げるのが難しいサービスであること 3. 巨大に成長する可能性を秘めていることに人が気づいていないこと。 ドメイン名を買おうとするなんて時間の無駄 なんとしても設定した目標成長率を達成しなくてはならない。努力しているうちになにをしなければいけないのかわかってくる 成功するスタートアップはミートアップに行かない セールスアニマルになる 一人だけのスタートアップには出資しない 大きすぎる数字は使わない。兆から連想されるのは政治であってビジネスではない AnyPerkはどうやって出来たのか http://jp.techcrunch.com/2012/05/25/jp20120510anyperk-and-ycombinator-2/
0投稿日: 2013.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ米国のベンチャー育成の実情を具体的に紹介した本。読み始めた当初はいろんな企業名が出てきて混乱するが、次第に引き込まれて行く。Yコンビネーターでの3か月に及ぶベンチャー育成期間の訓練方法やら、米国ベンチャーのスピード感、ベンチャーキャピタルの動きなどがわかって面白い。やっぱりフェイス2フェイスが大事だし、人が集まることでベンチャーが育って行く。かつて訪問させていただいた京都のKRPも環境が似ているような気がした。 読み進めて行くうちに加速的に面白くなってくる本。ただ、日本ではなじみのないウェブサービスも数多く登場するので、その部分を補うような日本版解説が少しあってもよかったかも。ということで、☆一つ減らしました。
0投稿日: 2013.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログシリコンバレーにあるスタートアップ養成スクールの3ヶ月を、密着して追いかけたドキュメント。本書の面白さを知るためには、「はじめに」の章で書かれているわずか10ページほどの説明を読むだけで十分だ。 このスタートアップ養成スクールを運営しているのは、ベンチャーファンド「Yコンビネーター(YC)」。その中心人物が、元起業家でプログラマーのポール・グレアムだ。 YCは数10社ものソフトウェア・スタートアップに同時に投資を行う。一方それぞれの会社は、少額の出資を受ける見返りに株式の7%をYCに与える。だが彼らが投資をする際には、一つの重要な条件が出されるという。 まずチームは、3ヶ月間にわたってシリコンバレーに引っ越して来なければならない。そしてプロダクトの開発を続けながら、グレアムをはじめとするパートナーたちの助言を受けることになる。また毎週ゲストを招いた夕食会に出席し、最後にはデモ・デーと呼ばれるイベントに参加することにもなるのだ。 このデモ・デーとは、数百人もの有力投資家の前でプレゼンテーションを行う機会が与えられることを指す。つまりYCは、スタートアップという未来のプラットフォームを生み出すためのプラットフォームなのである。 YC発のスタートアップの中には、既に大成功を収めたチームもいくつか存在する。代表的なのは、なんといってもDropbox。また、戸建・マンションの持ち主が予備の部屋を旅行者に貸し出すためのオンライン仲介サービス、AirbnbもYCの卒業生だ。 著者は2011年の夏、YC内に常駐し、応募者の選考過程からスクールの内容まで逐一記録することが許された唯一の人物である。YCの中で起きることを漏れなく観察し、興奮をそのままに伝えてくれている。 ここまで読んだら、もう後戻りはできない。頭の中で勝手に映画のオープニングムービー風の音楽が鳴り出して、物語は動き出す。シリコンバレー特有の情熱とスピード感が、あっという間にラストシーンまで誘ってくれるだろう。 今や流行語のように飛び交う「スタートアップ」という単語だが、その定義はポール・グレアムに言わせると以下のようなものになる。 ”スタートアップの本質は単に新しい会社だという点にはない。非常に急速に成長する新しいビジネスでなければいけない。スケールできるビジネスでなければスタートアップではない。” この戦場のような場所に送り込むために、スクールでは厳正なる選考を持って人材が選ばれる。その合格率や、わずか3.2%。過酷な質問によって試されるのは、スタミナ、貧乏、根無し草性、同僚、無知という5つの資質である。 彼らは、そんな資質を兼ね備えるのが25歳という年齢にあると判断している。創業者が学生だと、失敗しても学生に戻れるので真剣味も足りないのだが、25歳にもなると学校に戻るという退路が閉ざされているからだ。 また選考時に見ているのは、ビジネス・プランだけではない。実際に、創業者たちが成功に必要な資質を備えていると思えるなら、アイデアに弱点があっても大目に見ることもあるのだという。シード資金の段階での投資においては、アイデアよりも創業者の人物こそが重要なのだ。そこに、共同創業者がいること、チームの全員がハッカーであることなどの条件も付加される。 そんな厳しい選考をくぐり抜けてきた64組160人の精鋭たちが集う場とは、一体どのようなものなのか?その実態は、実にリベラルなものであった。創業者たちは個性のままに活動し、命令に絶対服従するための儀式・しごき等のブートキャンプ的要素はみじんもない。それもそのはず、ダメな創業者はYCがクビにしなくても、市場が追い出してくれるからだ。 だがそんな事態に陥らぬよう、ポール・グレアムは的確にスタートアップのポイントを指導していく。 ”いいか、アイデアを生み出すための3ヶ条だ。1.創業者自身が使いたいサービスであること 2.創業者以外が作り上げるのが難しいサービスであること 3.巨大に成長する可能性を秘めていることに人が気づいていないこと。” ”コードを書いて顧客と話せ、早く出してやり直せ、数字で測れる週間目標を決めて集中しろ。” ”ハッキングが得意で、かつ営業に積極的でなくてはだめだ。われわれが投資する相手は全員ハッキングが得意だ。それは見ればわかる!” 全員が13歳頃からプログラミングを始めたという集団内において、コードの部分ではそれほど差がつかない。コードの外側、つまりオフラインの部分において、市場を、顧客を、数字をいかにハックできるのか、それこそが試されているのだ。そんな熾烈な環境下で彼らは競い合い、そして分かち合う。 このような教えの全てに、シリコンバレーの真髄が詰まっているとも言える。おそらくこの地では、YCで教えられているようなことが、これまでにも暗黙知的に引き継がれてきたのではないかと思う。金持ちとハッカーが行き交う場所での流儀、地場に根ざした”最先端であり続ける”という伝統。それを形式化したYCという存在は、まさにシリコンバレーの中で最もシリコンバレーらしい場所とも言えるだろう。 また本書は、将来性豊かなスタートアップのサービス内容を知るための一冊としても有用である。そのいくつかを紹介してみたい。 ・rapgenius http://rapgenius.com/ ラップミュージックの歌詞を解説するサイト。ユーザーがラップ歌詞への注釈を投稿すると、ラップIQスコアがもらえる。コミュニティ機能を付けること、新分野であるロックに進出することなど、今後の展開への岐路に立たされている。 ・launchpadtoys http://launchpadtoys.com/ 子供たちがアニメ化されたお話を作れるアプリ。レゴなどの創造的遊びと子供向けTVゲームを合わせた新カテゴリー。iPad上で動くフィギュアの大きさを変えたり、歩かせたりすることができ、バイラル化することも可能。どこの親でも、自分の子供のしたことを自慢するのが好きであるという点がミソ。 ・ScienceEXCHANGE https://www.scienceexchange.com/ 科学実験のためのオンライン・マーケットプレイス。今は大学内で行われていることの多くが外注に出されているのが実情。そこに効果的なマーケットプレイスを作って、現在は不可能な全大学を横断する実験運営ができるようにするというもの。このプラットフォームの存在を知ってもらうために、ポスドクに営業をさせているという点もユニーク。 実際に公開されたサイトだけを見ていると、有能な起業家たちがクールに仕事をして出来上がったかのようにも思える。だが、その舞台裏は水面下で必死にもがく白鳥である。アイデアに行き詰まり、共同創業者に逃げられ、ピボットを余儀なくされ、プレゼンも上手くいかない。本書のもう一つの見所は、そんな失敗や試練を繰り返し、青春とビジネスとが共存した起業家たちの群像劇だ。 本書の読後感は、まるで大人になってから見る「夏の高校野球」のようなものであった。かつて年上のお兄さんたちが活躍していた甲子園では、いつの間にか年下の選手たちがグラウンドで躍動している。もはや観客席から見るしかないことを観念しながらも、その全力プレイについ心を踊らせ、胸を打たれてしまうのだ。 その一挙一動から目を離すことの出来ない、手に汗を握るビジネス書でもある。問題は、このまま観客席に座っていて良いのかということだけだ…
1投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
YCの12週間のできごとをその当時参加していたメンバーの例を交えながら、スタートアップ養成スクールの各フェーズを説明してくれている。 -引用- 間違っていてもなんらかの決断をするほうが、ずるずると決断を引き伸すよりずっといいんだ。自分が興味を持てることをやるのが重要なのははっきりしている。しかし、失敗のコストが最小であるようなアイデアを選ぶようにしなけりゃいけない。この場合のコストというのは、きみらがそれにかける時間だ。 スタートアップライフにおいて、捧げる時間の長さは一種類だけ、24時間だけだ。「我々が求めているのはフルタイム、文字通りの意味です」。
0投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ引用 単純にノンフィクションのドキュメンタリーとしても楽しめてしまう一冊。投資家を前にプレゼンをし、資金調達出来るのか否かが決定される「デモ・デー」に向けて、起業家予備軍たちがどんな特訓を受けるのか・・・? こちらはビジネス書としてではなく、読み物として超お薦め。是非。
0投稿日: 2013.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の自分に必要な内容で、また内容も非常に面白かったため、 この種の本では珍しく一息に読み切ることが出来ました。 ・なぜポール・グレアムはYコンビネーターを立ち上げたのか ・なぜYコンビネーターはエキサイティングなスタートアップを排出し続けているのか ・なぜシリコンバレーでなければいけないのか 自社サービスで一旗揚げたいと考えているエンジニアで、 Yコンビネータを知らない人はいないと思いますが、 いままでぼんやりとしか分からなかったであろう内幕を垣間見ることができる貴重な書籍です。 ポール・グレアムによるYコンビネーター立ち上げの背景から入り、 2011年夏期生64組の3ヶ月の悪戦苦闘から、 投資家へのプレゼンを行うデモ・デーまでを通して、 「なぜYコンビネーターはエキサイティングなスタートアップを排出し続けているのか」 「スタートアップとしてどうあるべきなのか」 を知ることが出来る、とてもエキサイティングな読み物になっています。 Heorku, Parse, airbnb, MongoHQ, Codecademy など、 2012年に急成長したおなじみのWebサービス名がたくさん出てくるので、 エンジニア的にのめり込んで読み進めることができるのではないでしょうか。 ただ、会社名やサービス名が分かりやすいカタカナ表記になっているため、 「ヘロク」「エアビーアンドビー」など、ほんのりとずっこける感があります。 逆にわかりづらいので、Heroku, airbnbなどスペルを表記してくれてたらもっとよかったなと思います。 選りすぐりの天才が集まった64組のスタートアップ達ですが、 武勇伝ばかりではなく、むしろ失敗話が大半なので、 またクローズアップされ、実際に成功と呼べるのはほんの一握りであることから、 スタートアップが本当の意味で成功することが如何に難しいことかが良く分かります。 ほとんど役に立ってないながらも、 共同創業者として会社を立ち上げて1年ともうすぐ半年になる所、 腑に落ちるところがたくさんありました。 また半年後に読み直したい一冊です。
1投稿日: 2013.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログYコンビネーターという、シリコンバレーの起業支援プログラムについて書かれた本。有名な卒業生は、DropboxやAirbnb等。採択の段階では、事業の内容よりもチームメンバーの資質を重要視しているんだとか。ITとか起業に興味があれば面白い本だと思うが、起業の良い面しか書かれていないのが残念。
0投稿日: 2013.04.28
