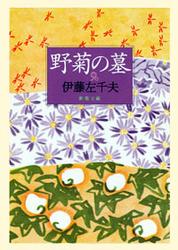
総合評価
(102件)| 21 | ||
| 28 | ||
| 33 | ||
| 6 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ20年ぶりに再読。子供心に抱いた恋慕の情と今なお燻り続ける悔恨が美しい日本語で表現されており心に染みる。(野菊の墓) "自分の都合許り考えてる人間は、学問があっても才智があっても財産があっても、あんまり尊いものではない。" (姪子)
0投稿日: 2025.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ連れても逃げず、ついても行かず、少年は学校に発ち、女性が見送る。それが生涯の別れとなる。矢切の渡しの松戸側。歩いて20分先にある文学碑。時は明治。女の方が年が上。それだけで禁断の恋になる。引き裂かれ、却って募る想い。二人歩いた道に咲いた花。採って渡して喜んで。彼女に喩えたその花が、永久の住家に繁っている。日本に野生の菊はない。よく似た花なら咲いている。幽明遥けく隔つとも1日たりとも去ることのできない心。…数えきれない映像化。時代を超えてに読み継がれてきた物語。捌けてしまう今になってこそ純な愛を求める。
0投稿日: 2025.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むきっかけは、北村薫先生の円紫さんと私シリーズで、主人公とその友人たちが『野菊の墓』の聖地である千葉に遊びに行ったのを、なんとなく覚えてたからだと思う。 作品名も学生の頃教科書などで見かけた記憶がある。 表題作の「野菊の墓」は、仕事の昼休み中だったのに涙ぐみながら読み終えた。ストーリーはよくある展開のように思われるんだけど、主人公や民子の家族の悲しさや後悔が、何度も何度も感情に訴えてくるような簡素な文章で表されているから、その悲しみが心に迫ってくる… 昔の農村の爽やかで懐かしい風景の中で、美しく健康的な姿の民子と、政夫との仲を引き裂かれてしまった後のあわれな姿の対比も切ない。 解説によると、伊藤左千夫はこの小説を読み上げながら何度もすすり泣いたそうだけど、これは自伝的な小説なんだろうか。冒頭で、今も民子とのことを思い出しては泣いている、と書いてあったけど、本当のことなんだろうなー。 「浜菊」は、かつての学友が田舎に引っ込み所帯を持ったことで向学心が失われてすっかり変わってしまい、それに落胆するという話だったけど、ちょっとこれは傲慢だよなあと思った。どっちが正しいかは誰にも判断できないし。 ただ昔から友人でも、環境や時代の変化で価値観が変わってしまい、かつてのような関係性でなくなってしまうのは、現代にも通ずることだし、悲しいけれど人生ってそういうものだよなあと思う。 近代化以降の日本でよくあることなのかと思ったけど、もっと昔はどうだったんだろう。例えば江戸時代に任地で田舎に行って戻ってきた人がすっかり人が変わってた、ということはありそう。環境が与える人間の性質への影響は大きいんだろうなあ。 「姪子」はよくわからず、最後の「守の家」は、「野菊の墓」に通ずるような、あの時代の女性の、他者に対する切なくまっすぐな思いが表されていて、印象的だった。
0投稿日: 2025.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ恋愛小説の古典である。著者は、歌人の伊藤左千夫。彼は、小説はこれぐらいしか残していないから、もしかしたら本人または知人の実話に近いのかもしれない。歌人らしい自然描写が美しく、それだけ悲劇に終わってしまう若い二人の純愛が哀しい。
0投稿日: 2024.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログあんまり覚えていない。 ありきたりの悲恋という感じ。 時代の風潮で結ばれない。 後半の二作はほとんど覚えていない。偏屈親父が、友達が変わってしまったと嘆き、批判する話だった気がする。
0投稿日: 2024.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログなんで今まで読んでこなかったのだろう。 求めていた話がここにあった。 1900年代発表なのも驚き。 似た雰囲気の作品があればそれも読みたい。
0投稿日: 2024.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
北村薫著、秋の花より。 再読するたびにいつか読もうと思っていたコチラをようやく手に取る。 普段あまり遣わない漢字や言葉が多くて、そういえば私、小説たくさん読んできたつもりだったけど、いわゆるクラッシックな名作っていうやつはあんまり読んできてなかったな、ということに思い至った。 と、いうことで読み慣れない古い言葉や漢字に悪戦苦闘…、 短編で良かった。 お話のスジは主人公政夫が、思春期の入口にいた頃、仲の良かった2つ年上の従姉妹とのその関係を周りにとやかく言われ始めたことから意識してしまい、お互いプラトニックな恋心を通わせたタイミングで親や親戚からその仲を引き裂かれ、従姉妹は望まぬ結婚をさせられ、失意のうちに若くして亡くなり…という思い出を振り返って語る、というもの。 従姉妹…民子の亡くなった理由としては嫁に行き、身重になったものの、子どもはおりてしまい後の肥立ちの悪さゆえ、ということらしい。 縁談を断る民子に、政夫の母が言い放つ言葉がなかなか厳しく、また、嫌がる彼女に強引に縁談を勧めた家族の圧も結構しんどかったことだろう。 実際、民子の死に際して政夫の母も民子の家族も大きな責任を感じている。 物語は過去の政夫の視点で進む。 民子の死を伝えた時の、母の詫び言、 墓に参った政夫を出迎えた民子の家族の詫び様に、1番感情を動かされた。 政夫に民子との仲を引き裂いたことを涙ながらに詫びる。 さらに政夫に民子の死、その一部始終を涙ながらに聞かせる。 …いやいや、皆さん、 それでその罪悪感から逃れようとしていませんか? …なんなんだ、この人たち、と。 秋の花の正ちゃんは、政夫に随分ご立腹でしたが、私は民子が亡くなった後の政夫の母や、民子の家族の詫びようになんだかとてもイライラしてしまった。 いやマジで、 民子の嫁行った先のお家の方にもめちゃくちゃ失礼だろうよ。 2人で茄子をもぐシーンや、綿の畑で過ごす時間、野菊と竜胆のやりとりなど、繊細で美しいところもあったけど、 実はイマイチ政夫や民子にも共感できなかったんだよな。 時代認識の差なのかなー…。 共感ではないが、同情するとしたら、民子の嫁ぎ先の旦那さんに1番同情した。 (おそらく待望のお子さんも亡くなってるわけだし) とは言え、読み慣れない文体にも関わらず、なんだかんだで感情を動かされる。 美しい悲恋に感動で涙が流れる…という動かされ方ではないけど、集中が途切れず一気に読めたのも良かった。 あ、ほかの3編もじわじわ面白かったです。
1投稿日: 2023.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ技巧的な面白さは ないかもしれないけど 牧歌的な昔の日本を味わえた 2歳の差が こんなに壁になるなんて 現代の人達には 分からない感覚だろうなぁ... 椙山書店にて購入
0投稿日: 2023.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ優しくて控えめな少女と、近所に住む2歳年下の少年の純粋な初恋の話。 子供の幸せを願って、2人を離れ離れにする大人たちが、結局は子供たちを不幸にしてしまう。悲劇の中にあっても、親を責めずに慰めの言葉をかけ、自分自身が強くなろうと決意する少年の強さに感動した。 大人から見ると子どもは未熟に見えるが、子どもなりに自分自身の感情を受け止めて、人生を決めていけるということを信じなければいけないタイミングがあるんだろうなと思った。
2投稿日: 2023.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ正岡子規に師事していた伊藤左千夫 酪農家でもあった 写生の人。 表現せずには生きられない 文学は道楽ではない「去年」 八女との食卓。生活と文学。
0投稿日: 2023.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度読んでも味わいのある素晴らしい名作だと改めて思いました。 最初に読んだのは、中学生の頃だったと思います。大泣きしました。何と悲しいお話なのだろうと思いました。その後も何度か読み今回。情景描写の美しさ、格調のある文章等読みつがれる理由がよくわらりました。 時を戻すことはできない。その時々を悔いなく生きなければという気持ちが、強く残りました。
0投稿日: 2023.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ十五歳の政夫と二つ年上の民子。 幼い清純な恋は、大人たちのために隔てられてしまいます。 政夫は町の中学へ、民子は心ならずも他家に嫁ぐことに。 そして間もなく病死。 今尚、可憐な恋物語として読者の共感をさそい続ける『野菊の墓』。 再読ですが、若い時とは違って、今になって分かることもあり、改めて、良い作品だなと思いました。 幽明遥けく隔つとも僕の心は一日も民子の上を去らぬ。 ー 91ページ
0投稿日: 2023.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者の情緒を身近に感じすぎて却って物語に集中できなかった。客観的に書かれている話のほうが不思議と感情移入しやすい気がする。
0投稿日: 2023.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
久々にこんなにピュアな恋愛小説読んだ…。この時代を生きたことはない筈なのになんかリアル。伊藤佐千夫の作品にぐっと興味が湧いた。 終始主人公視点で進むのだけど、民子を礼賛する言葉はほとんど内面に関するもの。外見や性愛に囚われない、イノセントな恋愛だということを示してる。主人公の愛情はヒロインが他人の元へ嫁いでも何ら変わらない。美しすぎる。ムリ。泣いた。素敵すぎる。 この時代の恋愛小説といえばひたすら女性が耐え忍ぶ精神性を尊ぶものが多い印象があって、個人的には政夫の誠意が光る作品だったかも。
0投稿日: 2023.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなにも綺麗で胸の詰まる恋ってあるのか。一度は体験してみたいけど立ち直る自信は…ねぇ…… 政夫さんの精神力には見習うべきものがあります。言葉選びも素晴らしい。相手を想う気持ちに長けてますね。
0投稿日: 2023.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ七月三十日 左千夫忌 伊藤左千夫命日ですね。懐かしい野菊の墓でも。 「野菊の墓」1906年 初小説 淡く切なく儚い、野菊の様な少女の初恋。 少年は15歳、従姉妹の民子は17歳。二人は、幼い頃から仲良く、この頃から、お互いに清純な恋心を抱き始めていた。 民子が2歳年上であること、ただそれだけで、母や義姉に二人の恋は認められず、とうとう民子は別の男性に嫁ぐことになる。民子は、精神的に肉体的に弱っていく。そして、流産の後、亡くなってしまう。 少年は、たとえ誰と結婚しようとも民子の心は自分にあると信じていたが、彼女の死は受け入れがたいものだった。彼女の墓の周りを野菊でいっぱいにする。そして、二人への仕打ちに後悔する母親をも支えようとする。成就できなかった初恋に胸が詰まる。 ストレートなストーリー。時には、心の浄化。 「浜菊」 これがなかなかの良作。 友あり遠方より来るが、それをしっくりもてなさない友人。客人は、すこぶる居心地が悪い。年賀状では遊びに来いって書いてあったのに。去年は楽しく再会を楽しんだのに。 客人の内心は謎と不安と不満でいっぱいになる。居た堪れず、翌日にはそそくさと旅立つ。 なんか、もう、いつの時代もあるよね、こんな事。 「姪子」 うーん。働き者の姪子。 「守の家」 子供のお守りの“守”。子供が5歳になり、実家へ戻った“守”の女性。お別れの寂しさ。 昭和の文庫で読んだから、収録短編が今と違うかもしれない。
41投稿日: 2022.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
情景描写の美しさや、若い二人の初々しい恋愛がとても素敵だった。 ただ、政夫は恋に恋してるだけのような感じがしてしまった。本当に民子のことを思ってるんだったら会いに行ってやれよ!まあ、15歳だったらそんなもんかなとは思うけど。 あと、民子も最後に握るのは写真と手紙は違うだろ。自分の死後にそれをみた母親達がどんな気持ちになるのか想像できない子じゃないと思うから、もしかしたら無理矢理結婚させられた腹いせとして、自分の死後に傷つけてやろうという魂胆があったのかもだけど、もしそうじゃないんだったら竜胆を握っておけばよかったのに。せっかく政夫=竜胆という2人だけの約束事があったんだから。
2投稿日: 2022.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
マックで読んでたら泣きそうになってしまって休みながら読みました。 僕はもとから野菊がだい好き 僕大好きさ わたし急にりんどうが好きになった。 民さんが野菊で僕が竜胆とは面白い对ですね。僕は悦んでりんどうになります。 キャー
0投稿日: 2022.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ『野菊の墓』 過去に幾度となく映像化されたもののいくつかを見たことあれど原作は初めて。若すぎる2人の儚い恋心が美しく切なく表現されている。嫁いでもなお政夫への思いを持ち続けた民子の健気さもさることながら、悲しい結末に追い込んだ事を後悔し泣いて謝る大人に対し、悲しみを堪えて受け止める政夫の姿が、この物語を一層切なく美しいものにしている。 明治の時代はかくもこのように恋愛には閉鎖的だったのでしょうが、世間体を気にする大人の身勝手さや醜さと言ったものはいつの時代にも当てはまるからこそ時代を超えて読み継がれ映像化もされるのでしょう。 『浜菊』 以前文学の道を志したがその道を諦め家庭を持った者が、今も文学の道を生きるかつての同志の訪問に対し、冷たいもてなしをする言うだけの短い話だが、その邪険な扱い方がちょっと面白く、そんな事あるだろうな、と思ってしまったw 妹が年賀状で、また来てくださいと書いてくれたからと言ってのこのこ訪問してしまったが招かれざる客と悟った主人公。一つの時代が終わった、と感じる瞬間は誰しも経験する事だと思うし、夢を諦め堅実な生活を選んだ人にとって、今も自分の道を生きる友人にはやりきれない複雑な思いを抱く気持ちもわかる。 『守の家』 主人公が幼い時の、子守の娘との思い出。これまたとても短い話でしたがなかなか良かったです。
1投稿日: 2022.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
兄嫁なんだアイツ絶対に許さねぇ! 幼さの残る二人が、周りから「デキてんじゃないの?」と言われた途端に意識して恋に落ちてしまうっていうのがなんともリアルで可愛くて良かった。 映画版はきっとラストが改変されてハッピーエンドだろうと信じてたんですけど、やっぱり民子は死ぬんですね。つら……
0投稿日: 2022.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
久しぶりに胸きゅん。 普段、イヤミスとかホラーとかおどろおどろしい本ばっかり読んでる自分の中にまだこんなピュアな気持ちが残っていたのかと驚かされるほど、可愛いやりとりにきゅんきゅん。 だからこそ、ラストが哀しい。
0投稿日: 2021.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供だましの様な純情話に年甲斐もなく涙がこぼれそうになった。こぼれたのでは無い。そうになったのだ。「民子は死ぬのが本望だ」民の今わのきわ
0投稿日: 2021.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ可哀想で泣きそうになった。 古典の名作はバッドエンド多い気がする。 貴方は野菊のような人だ、とか好意を直接言わないところが奥ゆかしい感じがしてよかった。
0投稿日: 2021.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログバッドエンド多し。 しかしよく考えると人生もバッドエンド(?)バッドな区切りは多い。これが正しいリアリズムかもしれない。 現代のスカッと爽快逆転ものは読んで気持ちいいが、実際はそうそう起こらない。
0投稿日: 2018.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度目だか忘れたけど、気持ちをピュアに戻したい時に好適な小品。いつまでも色褪せないでホントに古風だけれど 純粋で甘酸っぱくて もどかしくて切なくて、そうだ自分にもこんなのに近い気持ちの時が かつてあったよなぁ 等と大昔を回顧したり ね 笑。あっと言う間に読めるし。
1投稿日: 2018.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画(松田聖子の)を見たので原作も読んでみました。アララギ派らしい素朴ながらも悲しいお話。収録されていた「浜菊」の文章が好きで2回読んだ。
0投稿日: 2018.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ伊藤左千夫の『野菊の墓』はタイトルとしては知っていたし、いろいろな映画になったのも知っていたけど、読んだことはなかった。明治時代の純愛文学の代表作とのことだが、時代の違いが物語のトーンを決定しており、結局純愛って何?という疑問が離れない。まあ時代背景を学ぶということなんだろうか。 親の決めた相手と結婚するという考え方が主流の時代で、好きな人と結婚できずに病に伏せって亡くなってしまう、そんなことなら好きな人と結婚させればよかったとやっぱり親が考えて慟哭する。であれば、やっぱり親達も好きな人どうしで結婚させるべきだという考えがあったということなのか。親が決めた先というのは家と家が結びつくということもあったとは思うが、そこには違う利害関係や、それは親が何かのために良かれと思ったことなんだろうとも思うが、それはやっぱり純愛と正反対に位置するものなのだろうか。 伊藤左千夫が表現したものは、自由な文体で恋愛を扱う、ということなのか、純愛という性愛などとはかなり遠い位置にある、恋愛経験の幼い段階のことを文学にしたことが珍しいことなのか。なんだか何度も読んだり他人の書評を読むにつけ、表現の世界にとどまってしまっていないか?そんなことを感じたりもしたわけです。
0投稿日: 2018.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
表題の『野菊の墓』が一番読後感が良かった。 残りの『浜菊』『姪子』『守の家』はなんとなく消化不良というか、モヤモヤする感じ。 ただ、裏表紙の作品紹介で『野菊の墓』のネタバレしてるのはどうかと思う………。 でもこの説明を読んで、読んでみようと思ったから必要なのかな…? 主人公とヒロインに感情移入しやすくて、ハッピーエンドではないけど心があたたまる感じがした。
0投稿日: 2017.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
中学時代の読書ノートから。 「互いに手をとって後来を語ることもできずに小雨のしょぼしょぼ降る渡し場に泣きの涙も人目をはばかり、一言の言葉も交わし得ないで永久に別れをしてしまったのである。」
0投稿日: 2017.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れた純愛物語。時代の持つ理不尽さもあるけれど、声に出して読みたくなるような綺麗な日本語。伊藤左千夫は歌人だからか言葉のリズムが心地よい。
0投稿日: 2017.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生の時以来50数年ぶりの再読。政夫や民子に近い年齢で読んだその時と、その母に近い年齢で読んだ今。卵的の恋はくすぐったくもあったが、そういう気持ちはいくつになってもあるもので、いくつになっても卵的の恋はできる。中学生の時にはその母の気持ちにどれだけ思いを寄せられたか。今はその母の気持ちがとてもよくわかってせつない。 「野菊の墓」のほかに3編収録。作者の一本通った思いを感じる。朴訥としている。
0投稿日: 2017.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「野菊の墓」伊藤左千夫。1906年の小説、新潮文庫。 ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」も、真っ青な、ムズキュン恋愛ドラマです。 ま、オチは楽しくはないですし、ダンスはありませんが。 # 関東近郊の農村の、ちょいといいとこの、15歳のお坊っちゃん。 親戚の女の子で、坊っちゃんの家に下働きに住み込みで来ている、17歳の女の子。 このふたりが、子供の頃から仲良くて、だんだん初恋になっていって、両思いだったんだけど、女のほうが年上だし、周りが反対して引き裂かれ。女の子は病気で死んでしまった。 と、いうだけの話なんです。 コレが素敵な小説です。 # あまりにも有名なンだけど、読んでないなあ、というよくある小説で。特に理由もありませんが、読んでみました。 オモシロイ。 読みやすい。 もうほんと、冒頭に書いただけのお話なんです。 # 若いふたりは、毎日のように仲良くしています。 ただ、微妙に立ち位置は違います。 お坊っちゃんの政夫くんはお坊っちゃんで、東京の学校に進むことが決まって。 民子ちゃんは所詮、働きに来ている立場。家事に追われています。文章を書くこともできないんです。 ちょっと農作業に一緒に行く、とかが、言ってみれば素敵なデートなんです。 周りがだんだんと、「あのふたりはちょっと恋人みたいぢゃないの」と、心無い当てこすりを言うようになって。 そのあたりのストレス感が、「ああ、田舎ってこうだよなあ」という妙なリアル感。 民子のほうが年上だ、ということもあって。政夫が東京に進学して、帰省してみるともう民子は家にいなくなっています。 実家に帰した。そして、嫁に行くことになった、と。 そして会えないまま歳月が過ぎて、今度は連絡があって帰省してみたら。 なんと民子さんは婚家で苦労した挙句、お産がうまくいかずに病死してしまった…と。 なんともはや、なハナシなんです。 # これがまた、とっても素敵にポエムのような心情豊かな中編小説なんです。 どこまでいっても、ピュアなんです。プラトニックなんです。 政夫くんと民子ちゃんにとっては、いっしょにいて、おしゃべりして、農作業とか行って、そんな日常のひとつひとつが、「いっしょにいると楽しいね」なんです。Hとか、そんなの考えもしていません。 そして、そんな仲良しだったふたりが、恋になっていくステップというか、果実が熟すような温度が、ものすごくくっきりと心情、描かれます。ムズキュンなんてものぢゃないです(笑)。 そこから先に、ふたりの仲は熟すことなく、ポッキリ終わってしまうんです。現実としては。 でもだから、お互いに気持ちの中では、終わってないんですね。 もともと肉体的に性的にどうこう、ということぢゃない訳で。 誰と結婚しようがどうしようが、瞬間冷凍された「恋」は生きているんですねえ。 ただもちろん、嫌なことをいわれて、陰口を言われ、親大人のプレッシャーで嫁いだ民子さんは、ほんとに哀れです。 (ま、現代風に考えれば、結婚した夫のほうだって哀れなんですけれどね) そして、民子さんから、政夫さんに連絡できないんですね。文章書けないですから。携帯もメールもラインも無いし…。 # 民子さんが死んだあと、握りしめていたのが政夫くんからかつて貰った手紙だった、というラストは、思わず知らずグッと来ちゃいました。そこまでの語り口の素晴らしさ。 # 悲劇で、女々しいといえば女々しいのですが、あまりにも無垢な少年少女のお話なんですね。だからなんだか、辛いけど明るい不思議な物語。 最後は無論、涙、ナミダなんだけど、なぜだか不思議に、いじけた味わいにならない。そういう、他者攻撃とか、恨み節になっていかないポエムな読後感。 恥ずかしいと言えば実にハズカシイ小説なんですが、素敵な恋愛物語であることは間違いなく。 奇跡のようなキラキラした少年少女ストーリー。 # そして、このハナシ、伊藤左千夫さんの自伝的実話なんだそうです。 伊藤左千夫さんにとって、これは処女小説だったそうで。どこかで読んだのですが、仲間の集まりで、作者本人が朗読して発表したそうです。 そして、最後に自ら慟哭してしまったそう。 # 新潮文庫で読んだのですが、「野菊の墓」の他に「浜菊」「姪子」「守の家」の短編3つが入っていました。 かつての親友の家を訪れたけど、あまり楽しくなかったという「浜菊」。これはちょっと面白かった。 それから、野菊の墓と同じく自伝的風合いの強い「守の家」。 これは、もっと少年だった頃のお話で、子守娘と坊っちゃん子供の愛惜のお話。 10代くらいだろう、という子守娘の、男の子への愛情がこれまたピュアで、グッと来ました。 どうやら伊藤左千夫さんはこっちに持っていくと強いんですかね。 # 「野菊の墓」は何度か映画にもなっています。 なんと松田聖子さんが民子を演じたバージョンもあるはずです。それは未見。 大昔に見た、木下恵介監督の「野菊の如き君なりき」(1955)が、なんにも覚えていないんですが、かなり泣けた、という記憶だけ残っています。 またいつか、再見したいものです。
4投稿日: 2017.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ純愛物なのに、文章が情緒に欠けるなぁ…と思って読んでいたけれど、最後の三文は美しい。政夫と民子の想いを凝縮した文章。 「号泣した」という感想をよく聞くが、わたしはそこまでではなかったかな…? 「野菊の墓」「守の家」は切なく悲しく、「浜菊」は少し皮肉めいていて、「姪子」は暖かみがあったので、この一冊でいろいろな話を楽しめた。
1投稿日: 2017.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ恋愛小説をちょっと読みたいと思うなら、この切ない恋愛をおすすめしたいなと思いました。 結婚する相手が年上の女性というのが嫌われる時代の男女の話。とても柔らかい雰囲気で二人の気持ちが素直でまっすぐだということが常に伝わってくる文章です。あまりにもまっすぐのため「恋」というものを初めて知った時を思い出します。 また、見方によっては在り来たりな部分もあるかもしれませんが、素直に胸が熱くなったり、目頭が熱くなったりする場面もありました。
0投稿日: 2016.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう作品は、アラサーになってから読んじゃだめ、絶対(悲壮感)。 初恋は実らない。 なんて使い古されて手垢の付いた至言でしょうか。初恋は実らない。実を結ばないからこそ、いつまでも瑞々しく、甘酸っぱい思い出として記憶に留められる初恋………。私の初恋の木下くん、元気かな………← ですが、古典文学の世界にあっては、初恋は悲劇と切っても切り離せるものではありません。 ロミオとジュリエットしかり、ツルゲーネフしかり。 実らないからこそ、 悲劇として幕を閉じるからこそ、 一瞬の強烈な輝きを永遠に留めることのできる初恋……………。 うーーーーーーーーーん。 可哀想だね?(@綿矢りさ)以上の感想出てこない←←←←← 本作、野菊の墓の主人公・政夫と、二つ年長の従姉・民子が、世間体を気にする大人達のせいで離れ離れになり、そして取り返しのつかないあの結末にたどり着くんですが。 うん……………可哀想だね??←←←
0投稿日: 2016.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
確かに『野菊の墓』は、フレッシュな感じがしたよ。 今の年齢で言うと13歳と15歳のいとこ同士が、ちょっと仲良くしていたら「デキてんじゃないの?」って言われて、かえって意識し始めたんだけど、政夫くんの方が年下だしとかなんとかで周囲は反対。 政夫くんは寄宿制の学校へ出され、その間に民子さんは嫁に行かされ、そこで流産しちゃって、実家に帰され病死。 死の床で政夫くんの写真と手紙を握りしめていたと聞かされ、政夫くんをはじめ一族で懺悔&号泣! 政夫「民さんは野菊のような人だ。ぼくは野菊が大好き♪」 民子「政夫さんは桔梗のような方ね。」 政夫「じゃあ民さん、桔梗を好きになってよ♪」 民子「あら。うふふ!」 ってな感じで、年齢的にもまさに中二病全開の恋でした。 もうちょっと二人が大人であれば、舞台になった矢切の渡しを利用して「連れて逃げてよ~♪」と細川たかしちっくに盛り上がって、別のストーリーになったものを…。 冷静に考えると「民さんがもっと気の強い人ならば、オレ以外と結婚させられるくらいなら自殺するに決まってる!」とか、政夫くんの妄想的オレ・ナイスガイ!的要素があるお話なんだけど、ピュアな雰囲気は確かにあるように思いました。 感想文が、くどくてゴメンね。 なんか伊藤左千夫さんって人のキャラを考えると、素直に純愛としては読めなくなっちゃって…。 奥さんを晩年まで毎年のように孕ませておきながら、新潟方面他各地に愛人を作ってた人でしょ? 俺さまオトコの妄想かな…って思っちゃうんだよね。 まぁ、そんなこんなで、同じ本に収録されていた他の小説の感想は以下のとおりです。 『浜菊』 夜中に押しかけて行った柏崎の友人宅で下心を持っていた友人の妹にも会えず、友人の対応がイマイチ丁寧ではなく、翌朝寝坊して起きたらお茶も出てこないことに怒りを感じ、インテリちっくに理由をつけて悪口を羅列まくった短編。 モデルになった柘植潮音さんとは、これで絶交になったらしい。 さもあらん。 『姪子』 博打と酒でダメ男だった姪っ子の旦那が更生して、百合根を掘って餅をごちそうしてくれたことを嬉しく思い、学問や財産があっても自己中なヤツよりは、こういった粗野だけど人間性があるヤツのが良いって教訓的な結語で終わる短編。 誰かへのあてこすりっぽい。 『守(もり)の家』 5歳の頃に親しんでいた子守のお姉さん(16)が、解任されたうえでダメ男と結婚させられ、鬱になって死んじゃって哀しいですってお話。 野菊の墓の原型っぽい超短編でした。 ≪まとめとか…≫ クセのあるタヌキで牛飼いのおじさんが、澄んだ色彩を帯びた文章を書きますよってところが、伊藤左千夫さんの面白さなのかもしれないね!
0投稿日: 2016.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学時代に読んで、印象に強く残ってる作品です。僕は野菊が好きだ。民さんは野菊のようなひとだ。こんなラブコール、素朴でいいですね!(笑)
0投稿日: 2015.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログくらもちふさこの「ハリウッド・ゲーム」、岩館真理子の「ガラスの花束にして」の中でヒーローの男の子が松田聖子のファンであり、この野菊の墓について話題にするシーンがある。 それゆえ私にとっては野菊の墓=松田聖子が出演した映画、悲恋を描いた物語という認識しかなかった。 最近何の気なしに読んでみたが、予想に反して自然と涙が出た。 確かに筋を大雑把にみれば、何のことはない思春期のすれ違いののちの悲恋話である。 ただ一般的な悲恋という印象ではなく、遥かに純愛という面が強く印象に残り、胸の中に心地よい風を通してくれる。 周囲からのさりげない牽制に抗う術なく、日々は淡々と流れてゆくが、互いの間にあるゆるぎない確信のようなものが気持ちを動じさせる材料にはなり得なかったという描写にはハッとさせられた。 自分がそうであるように、相手も同じように確固たる気持ちを信じられるというのは何て単純で美しいんだろう。 物事において、理由はなくとも確信を持って信じられるということがまれにある。 そういうときは相手を信じているというよりは、確実に自分のことを信じている時だと思う。 理由もなくなんて、不明瞭で脆いものに感じられるかもしれないが、確かにそういうときがある。 政夫の台詞に思春期が言わせる、傲慢な想いだと感じなかったのはそういうところからだった。 だからこそ美しさと切なさが自分の中で一層深く印象づけられたのかもしれない。
0投稿日: 2015.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ短編四編。 表題にもなっている野菊の墓は、哀しいの一言に尽きます。 前半などはほのぼのとしていてかわいらしくもほほえましいのだけど、最後はただ哀しく、涙がこぼれそうになりました。 主人公が子供の頃を回顧するところから始まるので、おおよそどのように終わるかは想像がつくのですが、それにしてもあんまりです、と非難したくなるほど胸に迫りませした。 こんなにも短い文の中で、こんなにも入り込んでしまったのは久しぶりです。 残り三編も、情景が浮かんでくるかのようで、地味な内容でありながら記憶に残る、とでも言うのか。昔の日本の暮らしがありありと浮かび上がるよう。 とくに姪子は、宮本常一を読んでいるような錯覚を覚えました。
0投稿日: 2014.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
友人から、私と誕生日が同じ作家の作品だよ、と頂いた作品。映画化していたので名前だけは知っていたけれど、読んでいなかった。今から100年以上前に生まれた作者による舞台設定は、平成生まれの私には少し古びていて、読めない漢字や知らない単語が多かった。けれど、情景や心情描写は全く色あせること無く、現代に生きる私の胸に響いてきた。 若さゆえ、疑うことなく人を想える純粋で、ひたむきな、恋ではなく愛を感じ取れる作品。
1投稿日: 2014.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ伊藤左千夫が1905年(明治38年)に発表した"野菊の墓"他3つの短編を収録。どの作品も、作者の素朴な感性がにじみ出ていて読んでいて清々しい文章です。"野菊の墓"は、100年前に書かれたとは思えないほど、現在の鑑賞にも耐える作品です。舞台設定などは古いのですが、そこに描かれる恋愛模様は、全然色あせてないです。締めの文章がなんかドキッときた。"浜菊"、"姪子"、"守の家"の3編は、それぞれの主人公のある日を切り取った話ですが、"浜菊"だけが毛色が違うというか他にこんな話を書く人はいないのではないでしょうか。
0投稿日: 2014.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「矢切の渡し」がある松戸市の学校に通っていたので、その頃読んだような読んでないような。 描写が美しいし、登場人物に共感しやすく、とても読みやすかった。 ジブリ映画の『風立ちぬ』は見ていないけれども、なんで宮崎監督は『野菊の墓』を映画化しなかったのか。ジブリ映画でぜひ綿摘みのシーンや、丘の上からの景色を見たかった。しかたないので、脳内再生しながら読みました。ああ、残念。絶対キレイだったろうに。
0投稿日: 2013.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ超有名作なのに 全く内容を知らないので読んでみる お、思いの外、淡白な文章…! いや、都会的淡白さというより 朴訥としたあっさりさか 表題作もヨカッタが あとの三篇は全く違う舞台で エッセイかと思うほどリアリティあふれるお話だった 文章の作りが好み これで現代語なら最強かも でも星は3つ
0投稿日: 2013.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ純愛小説。作者伊藤左千夫。 中学入学直前の男子と、二歳年上の女。 ただ、母親の無理解だったり、周囲のねたみだったりで 引き裂かれてしまうよう悲しい話。回想形式。
0投稿日: 2013.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ伊藤 左千夫(いとう さちお、1864年9月18日(元治元年8月18日) - 1913年(大正2年)7月30日)は日本の歌人、小説家。本名 幸次郎。上総国武射郡殿台村(現在の千葉県山武市)の農家出身。明治法律学校(現・明治大学)中退 Whikipediaより 15歳の少年・政夫と2歳年上の従姉・民子との恋を描いた小説。今でこそ姉さん女房は珍しくない時代だけど、この小説が発表された時代(1906年)には相当な反対があったようで、二人の仲は周りの人達の手で引き離されてしい、不幸な結果となってします。 二人の恋が少しずつ育むまれていく心の様子が、とてもリアルに思われ読み進むうちに幸せになって欲しいと思われてくる。 しかしながら不幸な結果となってしまう。そこまでの二人の気持ち、特に民子の辛さが身につまされ、涙が溢れてしまった。
0投稿日: 2012.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ青空文庫で無料だったので読んでみた。 小さい頃、小学生くらいの時かな、 「短い話だけど印象的」だと感じた記憶があったんだけど、 10年くらい経っても名作は名作でした。
0投稿日: 2012.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ民子と政夫のやりとりが、初々しくて、いじらしくて、せつないところもあって、あそこはなかなか良いのだけれど。 最後、民子がしていることは恩着せがましくないだろうか。 政夫が忘れられないのは、それゆえに、愛情よりは後悔やら執着やらに思えてきてしまう。 若いときは、あんなに清新だったのに!
0投稿日: 2012.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログTami, you look like wild chrysanthemum. Masao, you are gentian. 民先生。你是象野菊一样的人。小政夫、你是龙胆。松田聖子主演で映画にもなった作。死人には勝てないけど、最後の文は現在の政夫の妻に対して、結構失礼だ。
0投稿日: 2012.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ設定があまりに旧時代的だったんでのめりこめるか疑問だったけど、案外物語の底にあるものは普遍的だった。 作者は歌人としての業績のほうが大きいので小説はやや一発屋の感が。 水を汲みに山を2つ越えなきゃならない明治時代の松戸はある意味すごい。
0投稿日: 2012.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ正岡子規自宅で開かれていた 「山会」という勉強会に参加していた 歌人 伊藤左千夫による初恋物語です。 初恋というか、恋の原風景でしょうか。 田舎の風習によって、 想い合った二人が、沿い遂げられない悲しい結末ですが、 読者が少々心が痛むほど、ひたむきな想いに心が洗われます。 (いやはや、私も大人になってしまったものだ。) そして、果たして、恋とは何なのかを考えるのです。
0投稿日: 2012.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代文の教材で問題として出てくる前にちょっと読んでみようと思って読みました。2人の初々しさというのか、いじらしさというのか、この関係が羨ましくなってしまった。
0投稿日: 2012.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ青空文庫さんにて。2人が本当に初々しくて、清らか。切なくて仕方がないけど、それがまた好き。当時の社会を如実に書き出している、ということで授業ですすめられた作品。
1投稿日: 2012.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
当時の時代性がはっきり見えるほど台詞の中のカタカナ遣いと言い回しがいいなぁとひしひし…これは当時に生きている人じゃないと絶対に書けないものだと思う。同時代研究が実に楽しそうな作品。恋だの愛だの、考えずに一緒にいられたらいいのにという二人はとても清純で美しい。それに加えてその美しさは小説の中でしか美しくなりえないのだということも教えてくれる気がする。切ないなぁ…。
1投稿日: 2012.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ1906年1月、雑誌「ホトトギス」に発表。私が生まれる遥か昔の小説である。ただ、子供の頃ドラマ化されて小説もブームになったことがある。読めば泣くと言われた。でも、私は泣けなかった。当時、男の子は恋愛小説を読んで泣いてはいけなかった。授業での反応は?韓国の有名な小説「ソナギ(夕立)」に似ていますねと言うとその主婦は昔を思い出すかのように、私も読みながらそう思いましたと言った。野に咲く花にお互いを託し愛を確かめ合う二人。若い学生たちはこんな廻りくどい男は嫌だと言う。降る雨に昭和も遠くなりにけりかな(ノ_-。)
0投稿日: 2012.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の作品の中では、あまり描かれることのないテーマ。だからこそ、ここでしか読めないという希少な雰囲気の漂う物語に、特別なものを感じてしまいます。 斉藤政夫、十五歳。戸村民子、十七歳。 政夫は或る日、幼い頃より共に育った従姉の民子との間に、まだ芽生え始めたばかりの恋を認める。民子も、その想いに気づいており、二人は言葉に出さないまでも相思相愛の関係にありました。 従姉とは言え、ごくごく身近に居すぎた二人は、これまで育ててくれた周囲の人の目を気にし始め、互いに距離を取り始めます。 次第に膨らんでいく純粋な想いと、世間体や大人の目への罪悪感。 思春期に生まれる恋心を、かくも純粋に、憐れみを込めて描いた作者・伊藤左千夫の筆力に圧倒されました。 決して大声で、この作品が好きだと言えない自分に、政夫と同じ躊躇の念を重ねて想像します。 このことは皮肉にも、自身が少しは大人になった…ということなのだろうと思うのですが。 大声で好きだと公言できないものの、とても魅力的な作品である…という意味において、『踏み絵』的な魅力に包まれた作品であると思いました。
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ悲恋。せつない、の一言にかぎります。名作だけど、著者の文章はそんなに上手ではない・・・かな・・・・・・。
0投稿日: 2011.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ受験真っ只中で読みふけっていた。読みやすく、こてこての純愛ながら心打たれた。 ------- 2017/09/19 この作品を手に取ると、鮮明に思い出す。 高校卒業間近の3階の教室の窓際。冬ながら小春日和で日差しが暖かかったこと。中庭に輝くようなハクモクレンが咲いていたこと。冬休みの静かな校舎。先生の担いでいた脚立。何を読んでるの?と聞かれて応えると、「お民さん、」と先生が言った。自分の名前を呼ばれたような気がして、頬が熱くなったこと。暮れるのが早い冬の西日が眩しかったこと。 永遠のような静かな時間が心地よかった。十年、二十年のちにこの本を読んでも、きっとまっさきにこの日を思い出す。幸福を感じたこと。人生でいちばん、美しい日だったこと。
1投稿日: 2011.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「野菊の墓」と「守の家」がとても気に入った。前者ではお互いに好きだとわかっているけれど、直接伝えることのできない初恋。二人の距離感が絶妙でとても切なく、儚いものだけれどその純粋さに心が温まった。後者も関係性は違えど、お互いに思う無邪気さには私の忘れていた感情を起こさせるものだった。両者とも当時の村社会特有の性質の悪しき部分から悲しい結末になってしまう。しかし互いが好き同士であっても集団の意思には個は抗えないという常識の元ということで二人の存在が際立って切なく美しいものになっていることは皮肉なことだと思う。
0投稿日: 2011.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログツルゲーネフの「はつ恋」みたく読むにつれ予感はするものの、いざ読み切ると、やはりはかない。これでは恋情がくすぶるままに燃えきらない生木みたいだ。
0投稿日: 2011.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ野菊のような人。竜胆のような人。 恋というのは人間である以上、皆共通の感覚。留学中の外国人の恋愛話とか思い出した。 恋愛には某かの制約がつく。世間体、年齢、将来性。本当に今好きな人が運命の人なのかは、誰にもわからない。だからこそ人は、一回一回の出会いを大切にできるのかもしれない。
0投稿日: 2011.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログあまりにもピュアで、あまりにも切ない、純愛小説の代表作。これほどまでに真っ直ぐな純愛は、もはや現代日本には存在しないかもしれませんね。明治時代に書かれた古い作品ですが、そういう意味で逆に新鮮さすら感じる、淡く素敵な恋物語です。
0投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ純朴。 たおやかな恋でした さよなら(サイハテ) 「民子さんは野菊のような人だね」 (中略) 「僕は野菊が好き」 いいなぁ
0投稿日: 2011.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学校だったか、国語の先生が進めていたのをふと思い出して購入。農村のなか歩く政夫と民子がまったく純粋で!素朴な風景描写が雰囲気をより深く喚起させて、また終盤のながれが辛いものに…。「姪子」は穏やかな気持ちになるし、「守の家」も優しくて哀しい話でなかなかよかったけど、「浜菊」はこれただの悪口だなw
0投稿日: 2011.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ政夫と民子の叶わぬ恋の物語。しかし、切ないなぁ。やり切れない気持ちになります。世間体という見えない壁、それを気にして見栄を張りたがるのは現代の人間も同じです。他にもこんな寂しい結末が無いとも限らない。そう思うとやるせないです。野菊の花のようだった民さん。幸せになって欲しかったですね。
0投稿日: 2011.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ5年前に読みましたが 野菊が道路わきに咲き始める頃 毎年、民さんを想います。 大学の授業で、この作品の アナザーストーリーを創作したこともあって 思い出深く、きゅっとなにか鼻の奥がツンとする感じ。
0投稿日: 2010.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ少女漫画にも劣らない恋愛小説で、なんだか読んでいる方が気恥ずかしくなりました。 最後は涙を誘います。
0投稿日: 2010.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ好きです。 どの話も人間臭さを感じられる。 「姪子」 ひんやりとした早朝のぴりっとした空気に朴訥な人々、美味しい空気と美味しいご飯…とても魅力的に感じた。 最後に語られる人生観、いいなと思う。 「野菊の墓」 働いた後、野で民さんと政夫さんがご飯を食べる場面、本当にご飯が美味しそうだった。
0投稿日: 2010.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ民子が今わの時に政夫の手紙と写真を持っていたのには思わず涙腺が・・・。 本筋からは逸れますが、P43の「八百屋お七は家を焼いたならば~」の件はおそらく江戸時代に起きたある火事の描写ですよね?何かそんな話を聞いたことがあった気がしたので。 これが発表されて今年でちょうど100年のようですが、ボクは、文語のリズムがあって、また生活も昔の緩やかな雰囲気が流れてて、そして話が純粋なので大好きです。ていうか民子が好きです。笑 (2006年02月10日)
0投稿日: 2010.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「民さんは野菊のような人だ。」政夫と、二さい年上の、いとこの民子は、まるできょうだいのように仲のよい間がらだった。子どものように、むじゃきに遊んでいたふたりに、やがて恋がめばえる。だが、世間体を気にする大人たちに、ふたりの恋はじゃまされて…。 まだまだ完成されていない文章な感じがするけど、すごく力がある。 特に感情表現がたどたどしい。だけどだからこそ理解できる。
0投稿日: 2010.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「民(たみ)さんは野菊のような人だ」 好意を寄せている少年から花に譬(たと)えられて、少女は摘んだ野菊の花に顔をうずめて喜んだ。 好いた女性を花に譬える男性がどれほどいるのかは分からない。しかし、実際に「○○さんは野菊のような人だ」と言うためには、かなりの心の純粋さがなければならないような気がする。しかも、相手が野菊のイメージとは限らないから、その女性の雰囲気に最も近い花を的確に伝える感性も必要である。ゴージャスなタイプなら「薔薇のような人だ」、和風美人なら「桜のような人だ」といった具合に。純な気持ちからその言葉が出て、自分のイメージに合致する花の名前が出てくるのでなければ、女は途端にしらけてしまう。 数えで十五歳の政夫には、その純粋さも細やかな感性も共に備わっていたのだろう。いや、むしろこの年頃の少年には、ひとしなみにそういった感受性が与えられているものなのか。彼は、同じく数えで十七歳のいとこの民子に「民さんは野菊のような人だ」と言ったのだ。この台詞の前に政夫は、野菊が好きだという民子に対して「僕はもとから野菊がだい好き。民さんも野菊が好き……」と言い、そしてそのあとは、こんなやりとりが続く。 「政夫さん……私野菊の様だってどうしてですか」 「さアどうしてということはないけど、民さんが何がなし野菊の様な風だからさ」 「それで政夫さんは野菊が好きだって……」 「僕大好きさ」 これは、民子イコール野菊の図を作っておいて、野菊が好きと言うことで、同様に民子に愛を告白するという技巧や駆け引きなのではない。政夫にも民子にも、そんな計算はなく、自分の好悪(こうお)の感情に素直に従って語り合っていたら、それが結果的に愛の告白になっていたということなのだ。矢切の渡(わたし)を東に渡ったところにある、穏やかな農村で始まったおおらかな淡い恋は、周囲の大人の思惑に抗し得なかった彼ら自身の純真な心と繊細な感受性によって、悲恋への道を辿っていく。 政夫と民子が恋を成就させるには、いくつかの障害があった。まず、民子が政夫よりも二つばかし年上だったこと。矢切村の内では、仲のいい二人を揶揄して、二つも年の多いのを嫁にする気なのだろうか、などと陰口が囁かれていたりもして、民子はそのことをしきりに気にしていたのだ。第二に、政夫の嫂(あによめ)や下女のお増が、二人の親密なのを勝手にうがった見方で捉え、これもこそこそと陰口を言っていたこと。第三に、その嫂の進言を受けて、政夫の母までもが政夫と民子の仲について、ふと疑念を起こしたこと。これらのことが、政夫と民子を無邪気ないとこ同士でなくさせ、想い合っていることが何とはなしに後ろめたいような、罪深いような気にさせるのであった。 そしてある日、彼らが引き裂かれる直接の原因となった出来事が起こってしまうのだ。その日、陰暦の九月十三日、政夫と民子は、母親から山畑の棉(わた)を摘み終えるようにいいつかる。村祭の直前ではあり、大人の働き手は皆それぞれ野の仕事を一段落させねばならないので、政夫と民子が棉取りにやらされることになったのである。その時点では、政夫の母はまだ、二人の関係を兄弟のようなものと考えていた。嫂からの小言が耳に入ったので、二人に釘を刺したりしたこともあったのだが、政夫が実の息子であるように、民子もまた、母にとっては心情的に娘のような存在だったのである。 しかし、彼ら二人は秋の日の短いのも忘れ、景色に見とれ、話に夢中になり、二人でいられる時間の嬉しさとは裏腹に、二人の関係について何か肝心なことを言うのもためらわれてぼんやりしているうちに、家へと帰るのが、すっかり遅くなってしまったのである。政夫と民子の間に何かあったわけではないが、とっぷりと暮れるまでに帰宅が遅れたことで、母の疑念も再び頭をもたげてきた。このために、政夫は千葉の中学に通う時期を早められ、民子と会えなくなるように仕向けられたのであった。矢切の渡から舟で市川へと出る。その別れ際に見た憔悴しきった民子の姿が、政夫の眼に焼きついた最後の姿となった。 政夫が暮から正月にかけてしか実家に戻らなくなり、一年と数ヶ月が経った頃、学校の寄宿舎に政夫宛の一通の電報が届いた。「スグカエレ」という電報の文言にしたがって実家に帰ってみると、臥せりがちの母が、身も世もなくむせび泣いている。訊けば、嫁に行った民子が死んだという。 民子は、財産家の家に求められて嫁に行ったのだが、本人は全く乗り気ではなかった。けれど、民子の家の者や親戚が、無理に話を進めているところへ、追い打ちをかけるように政夫の母がこう言ったのである。 「政夫と夫婦にすることは此(この)母が不承知だからおまえは外(よそ)に嫁に往け」 政夫を待つこともできなくなり、将来への望みのなくなった民子は、嫁入った先で身重になったが、月足らずで下りてしまい、それが原因で肥立ちも良くならず、とうとう息を引き取ったのだった。 民子の墓前に参ると、野菊の花が繁っている。 二人がもう少し大人であったなら。気弱でなく、したたかな面を持ち合わせていたら、こんな結末にはならなかったのかもしれないが、少年少女のあまりにも純真無垢な性情は、駆け引きを知らず、周りの大人の意向に逆らうことも出来ず、永遠の別れを経験することになってしまった。 『野菊の墓』は、眼に映る農村の美しい風景をそのまま写実的に全て叙述し、政夫と民子の感情の揺れ動き、その感情の移り変わりに伴う一つ一つの挙措に到るまでを、これも全て書き留めているように思えてならない。「万葉調」とでもいうのだろうか、美しいものを美しいままに、哀しいものを哀しいままに、衒(てら)いや技巧もなく、ありのままに表現しているように見えるのだ。それは考えようによっては、稚拙な文章であるのかもしれない。洗練され整った文章というのは、書きたいことの全てをベタ一面に書き連ねるのではなく、一部分はあえて秘し、適度に緩急をつけたりすることで活きてくることもあるはずだからだ。しかしながら、この『野菊の墓』は、書きたい物をそのままに書くという手法が、穏やかな農村に生活する政夫や民子の、飾り気のない、おとなしい純真な性格、平穏な農村に起こった悲恋と死、そしてその周辺のさざなみの一つ一つを描き表すのに成功していると云えるのだ。 民子のお祖母さんが、彼女のいまわの際(きわ)について語るシーンがある。シーンというよりも、くだくだしいほどの長い台詞であるが、これもまた整えられた文章ではなく、本当に田舎のお年寄りが口に上す繰言(くりごと)のようになっているのである。民子に対する懺悔や後悔が、素朴な方言を交じえてお祖母さんの口からあふれ出てくるのを読むたび、私は親戚の子が亡くなったように泣けて泣けて仕方がなくなるのである。 今度こそ泣くまいぞ、と思いつつ『野菊の墓』を手に取るのだが、民子のお祖母さんの言葉を読むうちに、やはり涙は滂沱(ぼうだ)として流れる。次に読む時にも私は泣くだろうか、泣けなくなる日が来るとしたら、それは自分にどんな変化が起こった時なのだろう、と時折考えることもある。
0投稿日: 2010.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ半世紀以上昔、純情乙女だったころ読んだ。 ゴルフの石川遼選手の父上が遼君に薦めたと書いてあったので、 改めて読んでみたが、薦めた理由が奈辺にあるのかわからない。 80歳近いおばあさんも政夫と民子の純情には胸にジーンときた。
0投稿日: 2010.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログあぁ、なんと不毛な恋。 今の自由な恋ができる時代じゃないにせよ、 こんなにも思うようにならないものなのですか 哀しすぎる。 主人公がもう少しこうだったら、あのときこうしていたら といういわゆる「たられば」ではどうにもならないところが 読んでいて、苛立たしいほどでした。 家族も、もう少し娘の気持ちに目を向けてあげてほしい 死んでしまってから後悔したって遅いんだよ
0投稿日: 2010.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログんー。あっという間に終わっちゃったっていうか。 あんまり心に残らなかった。 民さんと政夫さんの話。
0投稿日: 2010.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「野菊の墓」畑の中、二人で休んでいる時の景色が綺麗。 一度読んだ時の悲しいイメージが強かったが、このシーンは忘れていた。読み直して良かった。 「野菊」は身につまされる様でひやっとした。 「姪子」、こういう人に会ってみたいと思う。コミュニティが弱いから見た事が無い。 「守の家」お松にじゃれる坊のイメージがありありと浮かぶ。良かった。
0投稿日: 2010.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の世にえらいと言われている人たちには、意気でひとと交わるというようなことはないようだね、身勝手な了見よりほかない奴は大きい面をしていても、真に自分をしたって敬してくれる人を持てるものはおそらく少なかろう、自分の都合ばかり考えている品減は、学問があっても才智があっても財産があっても、あんまり尊いものではない。 100年前の作品にして、素晴らしい。
0投稿日: 2010.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ微妙なところに拘る私としては、表記を統一しろ! と思った場所が数箇所。 なんだかよく解らないけど、純愛物語であることは朧気に判った。 表題作より、他の短編の方が面白かった。
0投稿日: 2010.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生の頃に、薄い文庫本だったので読んだ記憶がある。いや、挫折したかな…これも2度ほど映画化されている。野菊の如く君なりき、だったのかな、聖子ちゃんが出てたのも、これだったか(どっちも観ていない)記憶の蔵書メモ・時々挫折本有り・・・
0投稿日: 2010.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログたぶん、読むのが早すぎ、「なんで好きなのに結婚しないのー?」と母親にしつこく聞いて「昔はそうだったの」という答えに納得できずにいた記憶があります。でもやっぱり今でも「なんで結婚しなかったんだ!」と思います。
0投稿日: 2010.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公の政夫が2つ年上の従姉、民子との淡い初恋を引き裂かれても、母親を気遣うところが、恋愛至上主義的な風潮の現代から観ると返って新鮮に写ります。 女の方がたった2つ年上なだけで世間体を気にしなければならない当時の風潮は今ではちょっと想像しにくいです。 他の収録作品も情景描写が美しくて良いです。
0投稿日: 2010.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ遼くんパパが恋愛論として遼くんに薦めた本。 恋愛ってうまく成就しないほうが美しく見えるものですね。
0投稿日: 2010.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルから内容が連想できるけどできても悲しい 解説が左千夫の表現は幼稚だとか言いたい放題でうけた 幼稚かどうなのか自分にはわからない
0投稿日: 2010.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ今やいろんなものが選択の自由は憚れないものになっている。 こういう時代を経てきたからだ、っていうことを忘れちゃいけないなあ。
0投稿日: 2009.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ左千夫が、子規の「写生文」という考え方を逸脱して、まったくのフィクションを書くことは考えられない。斎藤茂吉はこの作品を「全力的な涙の記録として、これほど人目をはばからぬものも世には少ないであろう」と評しており、作者に密着した作品と読み取れる。左千夫は自分の家を「野菊の宿」と呼んで庭に野菊を植え、その風情を愛してやまなかった。
0投稿日: 2009.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ二人が徐々に良い感じになってく件(くだり)の甘酸っぱさは本当良い。 けど民子の死っていう結末で一気に陳腐な悲恋モノになってしまったように思えて、すごい勿体無い。
0投稿日: 2009.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ泣けた・・・。 泣けたけど、タイトルのせいで途中で先が読めてしまってちょっとがっかり。 それでも泣けた。 最後の展開は王道だね。完全にやられました。 「野菊の墓」は十五の政夫と二つ年上の従姉民子との間に芽生えた幼い清純な恋が、世間体を気にする大人たちのために隔てられ、少年は町の中学に行き、少女は心ならずも他に嫁いでまもなく病死してしまう、という話。 やっぱり僕は人が死んだりする話はあまり好きじゃないな。そりゃあ泣けるけどさ・・・。 せっかく小説書くならハッピーエンドにして登場人物みんなを幸せにしてあげて欲しいって思ってしまう。
0投稿日: 2009.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ泣けるよね。お涙ちょうだいでいいよね。ばか。可憐。BAKA。 って意味もないこと言ってたくなるほど泣きながらわたしがいっそ恥ずかしいごめん。バ・カッ。(泣) 一時期なんかかぶれた気がする。「野菊のバカッ!」的な。(悲しくて。)はばかりながらの短期間。
0投稿日: 2009.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ叶わぬ恋をしてしまった二人のお話し。 事が起こった後に「悪かった悪かった」と必死に侘びられても……というのが感想。 今一歩踏み出せなかったお坊ちゃんな政夫くんにも、身分上何も出来なかった儚げな印象の民子さんにも、「ああ、もう、じれったいなあ」と思いながら読んでました。そこが売りなんでしょうか。 母から勧められたから読んでみたけど、うーん。美化されすぎているという印象が強すぎて私は好きじゃないです。 文体はやや難しいけれど、慣れればどうってことありません。 短いお話ですので、お時間があればどうぞ。表題作以外の短編もぜひ。
0投稿日: 2008.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ思いのほか読みやすかった 純愛小説… ただそれだけ、ってかんじで これぞ純愛なんです それだけw
0投稿日: 2008.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学の講義のために読んだ作品です。 この作品は一気に読んで、涙が止まらなかったのを覚えています。 胸がいっぱいになりました。 何日かこの作品が頭から離れませんでした。 時代のせいであり、誰も悪くなかった。 それでも、一途に焦がれる想いと思いやる想いが存在していて、それがとてもせつなかったです。
0投稿日: 2008.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前一度読んだことがあったんだけどもう一度手にとってみた。 「野菊」、ふいにグッときてしまった。 前に読んだ時はそんなことなかったのにな、こういうことってある。この違いってなんだろう? 前回から今までの数年の間に、私の何がかわったんだろう? なんだか本の感想ではないけれど、そんなことを発見した一冊。
0投稿日: 2008.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログそれは「追憶」。 人の別れやその時の物悲しさが巧く描かれているが、悲しみを引きずらない様な工夫もされている。 過去を振り返った形で描かれる感情表現の仕方は読み手にも(作中の登場人物の)感情の細やかなところが少しずつ伝わってくる。
0投稿日: 2008.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログやるせないお話でした。 古いお話は、やはり聞き・読み慣れない言葉使いのため、ちょっと世界に入り込みにくかったです。
0投稿日: 2007.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の頃に読んで、 純粋な切ない恋心に涙しました。 許されぬ恋は切なすぎる。 気になって松田聖子さん主演の 映画も見たことがあった。 夏目漱石も絶賛した作品らしいです。
0投稿日: 2007.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ家と世間体によって 一緒になることを許されなかった2人。 民の最期は大人しいながらも 彼女に今までないくらいの決意が 秘められていたと思う。
0投稿日: 2007.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代に極められる人生に絶えなきゃいけない子どもの、せいいっぱいの恋愛というか。二人で山に行ったときのやりとりが好き。
0投稿日: 2006.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこれを読んだきっかけは、大学の某教授が、「世界の中心で愛を叫ぶ」は「野菊の墓」の現代版、という主張を聞いたからです。 確かに、という感じはしました。ただ、何でも自由を叫ばれている現代よりも、昭和初期という、周りの壁のあるこの作品の方が、「純愛」という観点から見れば上でしょう。障害があるほど恋は燃える、といいます。読者を惹きつけるエンターテイメント的要素としても、「世間体」、「抑圧」という壁がこの物語りで厚い壁をつくり、読者の共感を呼ぶのではないでしょうか。「純愛」は、周りを悪にするほど引き立ちます。しかし、必ずしも悪ではない周りの大人たちを見ていると、切ない気持ちになってきます。
0投稿日: 2006.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ話の筋は要は少年が恋に落ちて死に別れなのですが、その相手が死ぬ理由が嫌いな相手のところに無理やりとつがされた心労のためというのが時代を感じさせます。 何となくセカチューより好感が持てるのは私が現代人だからでしょうか。 あぁいい時代だったのだなぁと思いました。
0投稿日: 2006.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログとても若々しい小説だった覚えがあります。でも本人はかなりの頑固者だったとか。ずいぶんと年配になってから作家になった人です。
1投稿日: 2006.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校2年生の時に初めて読んで以来、私の中で『野菊の墓』は特別、心に深く刻まれている話である。こんなにも、切なくて悲しくて、心が痛くなるような初恋の物語というのはないと思う。民子の思いが、そして政夫の思いが読む人の胸に迫ってくる。人生はたった一度しかないのに、思い通りになることは少なくて、だからこそ自分の思いや他人の思いを大切にできる人になりたいと思う。
1投稿日: 2005.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「民さんは野菊のような人だ」 「政夫さんはりんどうの様な人だ」―――表題作「野菊の墓」は、伊藤左千夫の代表作。姉弟のように育った民子と政夫の恋の行方。所々に現れる、純朴で飾らない言葉が胸に迫る。ラスト、「幽明遥けく隔つとも僕の心は一日も・・・」の一文は、あまりにも有名かつ、あまりにも、切ない。 他に「浜菊」「姪子」「守の家」収録。しかしやはり、「野菊の墓」は絶品。
0投稿日: 2005.07.17
