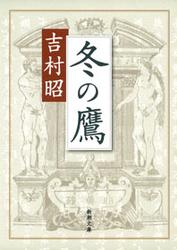
総合評価
(46件)| 15 | ||
| 22 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ人体の部位の絵の脇で、横に這っている得体の知れない文字。限られた情報源から推測し、格闘すること3年半。遂に出版にこぎつける。翻訳を行ったのは主に良沢。しかし、訳業関係者として彼の名は連なっていない。中途半端な出来には満足せず、言語を極めることに没頭する。いつの間にか人を遠ざける。誉れ高き名声と巨万の富を得た玄白とは対照的。寂しく見える晩年も、美学追求の1つの姿。…歴史の授業。江戸時代中期の必須で覚える出来事。「解体新書」。そこにも学ぶべき人生訓があった。各々がならではの道を生きて、今の医学と語学がある。
6投稿日: 2025.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉村文学の長編に挑戦した。4日で読み終えた。 オランダ語を生涯かけて追求する男。 名声を求めない、お金を稼ぐことに興味はない。 老荘思想に憧れる。学校で習った解体新書の著者は、杉田玄白ではなかった。前野良沢であったのを教えてくれた。
0投稿日: 2025.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
前野良沢、杉田玄白それぞれの特性・性格が反映された人生が描かれており興味深く読んだ。 良沢の執念、玄白の社交性と統率力。両者どちらが欠けても解体新書は世に出版されることはなかっただろうと思った。 良沢は玄白の祝いの席にも出席したのに、いくら性格が合わず、後ろめたさがあったとはいえ玄白が良沢の葬儀に行かなかったのは不義理だと感じた。 個人的に好きな場面は老いて隠棲していた良沢を娘の峰子が迎えに来た場面。冬の鷹とはまさしく前野良沢のことだと思った。
0投稿日: 2024.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ解体新書の訳者は杉田玄白ではなかった、とこの本の概略について事前情報を得ていたので、杉田玄白はとんでもないやつだった!という内容なのかと思って読んでいたが全く異なっていた。 私は良沢に共感する心と玄白に共感する心の二面性があり、どちらが自分にとっての幸せが掴める生き方なのだろうかと考えながら読んでいた。
4投稿日: 2024.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ教科書に載っている皆がしっている歴史の事実を、タイムスリップして覗き見ができた感じ。教科書ではわからない、そこに生きた人の性格や生き方に触れることができて面白かった。
0投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログターヘルアナトミアを翻訳し、解体新書を出版した前野良沢の話。良沢と杉田玄白の対比が面白かった。お互い医家ではあるがオランダ語を翻訳することに人生を捧げた良沢とオランダ医術を布教することに専念した玄白。長女、妻、長男を亡くし茫然自失となった良沢、養子玄沢や大槻ら優秀な門徒に囲まれた玄白。最後まで研究者として意固地な良沢のまっすぐさが描かれていた。 未知の文字を翻訳することの大変さ、それを成し遂げたのに名を売らなかった良沢の生真面目さがわかりやすかった。 平賀源内の印象がすごい変わった。
7投稿日: 2024.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログあなたは、「『解体新書』を翻訳したのは誰か」と聞かれたら何と答えますか? 小学六年生社会科のテストなら 『杉田玄白』 と答えていれば丸になるかな。 でも、実際の翻訳作業はほぼ全て 『前野良沢』 が手掛けたことまでは学習しません。 本書はその前野良沢と杉田玄白を中心とした歴史小説です。オランダ語の習得に全身全霊を捧げようと志す前野良沢は、ほとんど暗号解読のような状態で翻訳を成し遂げます。しかし自分の名を著作に刻むことはよしとしませんでした。一方で用意周到に出版の準備を進めた杉田玄白は、後に医家として大成し医学界の頂点を極めます。 吉村昭さんの小説は、対照的な二人を軸とするも、平賀源内や高山彦九郎といった関わりのあった同時代の人物にも多くの筆をさいていて、江戸時代末期の社会情勢を俯瞰して見つめています。それでも著書の視点は温かく、埋もれがちな前野良沢へとより多く向けられています。"どちらが正しい"と二者択一するのではなく、二人の対照的な生き方が、現代に生きる我々にも多くの示唆を与えてくれていると思います。 …それにしても、"杉田玄白はほとんどオランダ語はできなかった"っていう事実は、知っておくべきかもしれないなぁ…。
27投稿日: 2023.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉村昭さんのお蔭で、知らなかった、知っておくべき過去の有名無名の偉人の業績、人生を知ることができて本当に嬉しい。有難い。 タイムスリップして、透明人間になって、その場にいたような気になれる文章が好き。 ターヘルアナトミアを前に、絶望する前野良沢や杉田玄白の姿が見える。孤独、名声、期待、失望、怒り、悲しみ、喜び、安堵。 彼らの生きた時代の空気を感じられた気がする。 読めてよかった。
2投稿日: 2023.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ解体新書を上梓した二人の医学者を通して、当時の思想や政治体制を背景に物語が進んでいく。比喩が正しいかわからないが、理系肌で頑固一徹な前野良沢、文系肌でコミュニケーション脳力が高い杉田玄白の生き方のどちらが正しいのか? 学問を極める事とそれを世に広める事は、同じ人間には出来ないのか?を考えさせられる。 吉村昭の洞察力の深さを思い知る作品である。 前野良沢は、吉村昭の生き方に通ずるのだという事が理解できる。 同じ時代を生きた高山彦九郎を主人公にした『彦九郎山河』を同時に読まれる事をお薦めする。
1投稿日: 2022.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代後期、蘭学隆盛の端緒となった解体新書の翻訳・刊行の中心人物であった前野良沢、杉田玄白の話。技術英語の翻訳に関わることもある仕事柄、読む前から強く興味を惹かれるテーマだったが、未知の蘭語の翻訳の困難に関わる話は、解体新書の刊行に至る物語の中盤よりも前で触れられている。ここをより深く掘り下げて欲しかった気持ちがあることは否めない。しかし、辞書という概念すらほとんど知られていない時代にわずかな手掛かりから原書の記述の意味を探り出そうとする苦労は十分に伝わってきた。 物語後半は、他者に抜きんでた専門性を持ちつつも学究肌で柔軟性に欠ける良沢と、専門知識には劣るが社会性に秀でて解体新書の刊行をきっかけに活躍する玄白の境遇の対比に重点が置かれている。前者は頑迷ともいえる研究者であり、後者はビジネスセンスのある企業家というところか。学問の探求とビジネスの間のバランスの取り方の難しさは現代にも通じるところが大いにあって面白い。著者はどちらかというと良沢に肩入れした描き方をしているが、むしろ現代の研究者がビジネス面のバランス感覚を持つことの意義を知るためにも、本書に書かれた良沢、玄白の生き方の対照性は参考になるのではないかと思う。
1投稿日: 2022.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログオランダの医学書を翻訳して解体新書を書いた前野良沢の翻訳人生を描いた作品。 同じく解体新書を書いた杉田玄白とは、その後の人生、信条、キャラクターなどがまるで対照的で、この二人の対比で話が進んでいく。 杉田は外交的、前野は内向的。前野は語学の学問を追及、杉田は医学の実利を追及。前野は自分が育ちたい人、杉田は人を育てたい人。 二人に共通しているのは、好奇心のかたまりであること、あきらめが悪いこと、確固たるポリシーを感じること。 二人の歩んだ人生はまったく違うが、チャレンジ精神を称えたい一冊。
1投稿日: 2022.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログオランダの解剖書ターヘルアナトミアを翻訳した前野良沢と杉田玄白の話。 学者肌で頑固、融通が利かない良沢、学問を極めることよりも世渡りや調整力に長けた玄白の対比が面白く、現代人にもそれぞれ似たようなタイプが居ると思う。 良沢は貧しく寂しい老後を送る一方、玄白は弟子に囲まれて裕福な老後を送る。 物語にあるように、世の中で成功するのは大抵人格能力の優れた玄白タイプが多いのではないかと思う。
1投稿日: 2022.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ★★★ 今月1冊目 解体新書を出した、杉田玄白と前野良沢の本。 世の中では杉田玄白がという感じだが実際は前野良沢が翻訳。杉田玄白は弟子。 が、人生の明暗を分けたのは考え方。 おもろかった
0投稿日: 2022.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログターヘルアナトミアと、当時の辞書を手に取って、解体新書を作る過程を試してみた吉村昭さんが書いた、解体新書創造がメインストーリーとなる前野良沢物語。 世の中は、さほど動いていないように思えて、激動の時代だった江戸中期のストーリーから、現代に繋がるメッセージはとても大きいものでした。 是非、人生の挫折ではないかと、壁に突き当たっている人に読んでもらいたい一冊です。 前野良沢さん、生まれて亡くなるまで壁しかない人生。でも、その生き方にはなぜか憧れる。
1投稿日: 2022.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ杉田玄白の「解体新書」のことは、学校で習って知っていたけど、その翻訳作業がこれほど困難で、これほどドラマがあったことは初めて知りました 吉村先生らしい綿密な資料に基づく著作は、リアルに2人の生涯を追いかけさせてくれました
1投稿日: 2022.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「解体新書」を著した前野良沢と杉田玄白に関する歴史小説。 オランダ語を習得する執念とその努力は、語学を学ぶ全ての人にとって、大いに刺激になると思う。 (当時の苦学を知れば、現代人が英語学習で苦労するなんて言ってられないだろう) 同じ吉村昭著の高野長英の歴史小説も思い出した。(これも名著) 蘭学を通じて、西洋近代の知識を吸収し、延いては、それが幕末の政治的な動きにまで繋がってくる。 そう考えると、解体新書を世に出した二人の存在の意義の大きさを、改めて認識させられる。 (当時、鎖国の方針を緩めた徳川吉宗の見識の高さでもある) この小説の面白いところは、今でも、前野良沢的生き方と杉田玄白的生き方があるからだろう。 自分の場合は、世の中をうまく生きていくよりも、前野良沢のような、頑固で、不器用で、妥協を許さないプロ意識に高い人物の方が好感が持てる。
1投稿日: 2021.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ今から280年程前の江戸中期に刊行された「解体新書」に関わる人々の生涯と当時の社会情勢が記録映画ように綴られたお話し。 原本であるオランダ語で書かれた「ターヘル・アナトミア」を翻訳した前野良沢とそれを刊行した杉田玄白のその後の両極的な人生の明暗が読み進めていく内にコントラストを強め、読み手の心を捕らえていく。 個人が抱く矜持は人それぞれだが、前野良沢はそれに美しさを求め、杉田玄白は正しさを求めた。結果は歴史が証明したが、悔いのない人生であったのならば、それで良い。 「解体新書」は、西洋科学(医学)書の日本最初の翻訳書と言われている。 それまでは中国から伝わる文物が主流だったが、西洋科学の正確さに気が付いた彼らは、少ない情報を基に途方も無い苦労の末、翻訳を成し遂げる。 これは、もしかしたら西洋以外では初の試みなのかも知れない。 日本はここから西洋文明を怒涛の如く吸収し、脱亜入欧を掲げてアジアでは突出した文明国に成長していく。 これは「解体新書」が一つの切っ掛けにもなっているのではないか。 暗闇の中、手探りで翻訳を成し遂げた前野良沢を日本人は忘れてはいけないと思う。
1投稿日: 2020.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者はこういう前例のないものに挑む人間ドラマが本当に好きなんだろうな。他作品もそうだが、地道に愚直に自身の求めるものを深く掘り下げていく様は危うさが感じられるものの、まっすぐで清々しさがある。玄白や源内との対比でよりキャラが立ち、良沢が孤高の存在として際立つ。署名を固辞した後の2人の生活、人生遍歴も興味深い。
8投稿日: 2020.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ『解体新書』の舞台裏を、吉村昭がいつものごとく、緻密な取材のもと描いた作品。 『解体新書』=杉田玄白と前野良沢ら、と学生時代に習った記憶。 杉田玄白メインなイメージ。 それを根底から覆してくれた作品。 杉田玄白の明るさや要領の良さと、前野良沢の生真面目さや頑固っぷりが、一貫して描かれていたから、年を重ねるごとのその対比が読みやすかった。 平賀源内などの当時の彼らを取り巻く人々についても、仔細に描かれているのはさすが。
0投稿日: 2020.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログオランダ語で書かれた『ターヘル・アナトミア』を翻訳した前野良沢・杉田玄白、彼らの作業過程とその後の人生を詳細に描き出した作品。 教科書などでは、この二人がほぼ同列の訳者として記載されているけれど、事実は前野良沢が苦心して翻訳したものを、杉田玄白が整理し文献の形に整えたという風に役割分担がなされていた。 学究肌の良沢は訳を終え、『解体新書』として発行する話を、それはまだ不完全であるからとして喜ばなかった。そのため、『解体新書』の訳者として自分の名を載せるのを禁じた。 そのこともあって、世間の評判は玄白にのみ集中し、彼は八十を超えて大往生を迎えるまで栄華の中にあった。一方の良沢は、傑出したオランダ語の知識がありながら、自らが訳出した他の本についても出版して金儲けすることを浅ましいと考え、老齢に至るまで貧しいままであった。 オランダ語を訳せないながら、蘭医として名声を博した玄白と、オランダ語の権威でありながら貧窮の中にあり続けた良沢。二人の生き方は正反対だけれど、自分は良沢の不器用な生き方の方が好ましく感じられた。
1投稿日: 2019.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ『解体新書』といえば、杉田玄白。 しかし、前野良沢という名前を聞いたことがある人は、少ないのではないか。 自分もその1人だった。 陽の杉田玄白と陰の前野良沢。 このふたりがいたからこそ、『解体新書』が生まれた。 それならば、何故、前野良沢は『解体新書』に名を残さなかったのか。 頑固で潔癖なる性格ゆえか。 頑固で潔癖。 これが、良沢の人生を表している。 オランダ語に人生を捧げた前野良沢と名声を得るために人生を捧げた杉田玄白の対比が如実に現れている。
1投稿日: 2018.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
菊池寛「蘭学事始」の前後左右に肉付けした感じ。ところがこの肉が厚くて豊かで魅力的。玄白がちょっとフォローされてるかな。まあでも、報帖で様子見とか家治への献上とかって玄白のアイデアだし、病弱で独り者だった玄白がこの成功で妻帯できたのは良かった良かった。 良沢が中津から江戸へ戻る途中で、「大井川に渡しがない」って話が出てきた。先日、角倉了以が江戸初期に舟を通した話(岩井三四二「絢爛たる奔流」。この本の解説、偶然にもこの人)を読んだばかりだったので、あれ?っと思ったけど、よく考えたら了以のは京都の「大堰川」だったw あと、そもそもこの話、前野良沢と杉田玄白がダブル主役なんだけど、それぞれの交友範囲に平賀源内と高山彦九郎がいる。史実上、無視できないのはわかるけど、この2人、脇役には相当向かない濃いキャラw。なんで、全体のバランスが崩されちゃって、最終的に座りが悪い仕上がりに感じた。寧ろ例えば、玄白が60歳で良沢70歳の時の20年振りの再会なんかは、もうちょっと紙幅を割いて欲しかったなあ。 岩崎克巳の「前野蘭化」、挑戦したいけど、東洋文庫3分冊かあ。ハードル高いなあ〜!
1投稿日: 2017.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎のファンで、似た毛色の作家を探し求めている人には吉村昭をお勧めします。そして、いま困難なプロジェクトに四苦八苦している人にこそ、この本をお勧めします。 大河ドラマにするなら絶対この作品の方がよい!高山彦九郎・平賀源内というサブキャラも魅力的に関与していますし、なにしろ杉田玄白と前野良沢の人生と処世観の差が鮮やかに引き出されています。また、長崎・江戸・中津(大分)と取材箇所が各地に分散する点も魅力を感じます。 ちなみに、蘭学事始で著名な「鼻はフルヘッヘンドである」云々のエピソードはこの本の中に出てきていません。その理由もあとがきで吉村昭自身が言及しており、資料に丹念に向き合って小説を書く作家であることをうかがわせ、極めて好印象です。 私は初めてこの作家の著作を読みましたが、別の本も手にしたくなりました。吉村昭は戦時下の昭和日本も司馬遼太郎と違っていくつも取り上げてますしね
3投稿日: 2017.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ解体新書の訳に携わった人たちの物語。こういう風に翻訳していったのかと初めて知った。てっきり杉田玄白だけで翻訳したのかと。職人の脳みそだけだと生きづらいのが人生だけど、そちらのほうが尊いのかもしれないな。
1投稿日: 2016.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ偏狭までに学究肌の前野良沢の姿を杉田玄白と対比させて描く。生涯学ぶ姿勢にも打たれた。平賀源内の滑稽なまでの軽さも一つの生き様であろう。作者の調査の綿密さも窺える良書。2015.5.5
1投稿日: 2015.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ解体新書を訳した前野良沢を中心に、長崎でオランダ語を学ぶ苦労、杉田玄白らとの交流が描かれている。学者肌で誤りが残る翻訳を出版したくない思いや、人との交流を絶ったことで貧しく孤独な暮らしになる。その中でも凛として生きていく姿が目に浮かぶ。人の崇高なる生き様を感じられる本である。
1投稿日: 2015.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代。『ターヘル・アナトミア』の翻訳版、あの名高い『解体新書』を世に送り出した杉田玄白ではなく、その翻訳の中心人物であった前野良沢を主人公とした物語。前野良沢という人物は名前だけは知っているが、どういう人物なのかは全く知らなかった。この本によれば、まさに学者という人物で名利を求めるような人物ではなかった。だから今でも杉田玄白と比べると知名度が低い。 『ターヘル・アナトミア』の翻訳というのは実に難作業だったのだと伝わってきた。辞書もろくに無い中で、単語の意味を別の本や実際の解剖の結果から推測し導き出すという作業は根気が必要で、とても常人には成し遂げられないものだ。そのような翻訳が完璧であるわけはなく、だから前野良沢は広く世に出版する事をいやがった。しかし杉田玄白は、完璧ではなくても世に送り出し広く知らしめる事に重きを置いた。僕はこの点に関しては杉田玄白が正しいと思う。 平賀源内や高山彦九郎といった時代を彩る人物が登場し、江戸時代の雰囲気を感じる事ができた。良書である。
1投稿日: 2014.06.16解体新書の制作過程と対照的な2人
解体新書と言えば杉田玄白が思い浮かぶが、実際の翻訳はほぼ前野良沢だった。 医学と自信の発展を望む杉田玄白、対照的に出世欲は無く完璧主義で蘭学研究に没頭する前野良沢。 西洋医学を日本に紹介した当時は革新的な医学書の制作過程と2人のその後の生涯を通し、その時代、生き方を見せてもらった。 教科書での1行程度の知識がこの本を読むことでその背景が伝わってきた。
0投稿日: 2014.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ予期せぬ感動。 オランダ語の習得と翻訳業に専念し、富や名声を求めなかった前野良沢と、翻訳チームをまとめて、『解体新書』出版に尽力し、社会的成功をおさめた杉田玄白。どちらのタイプも、大事業を進めるには必要なのだろう。 だが著者は前野良沢の生き方に、つよく心を惹かれている。とにかく頑固で、清廉潔白に生きた人。それゆえ晩年は貧窮したが、おそらく良沢は、自分の人生にさほど後悔はしてないはず。 学問の厳しさ、「分かった」ときの純粋な喜び、新しい知識の広まりと反発など。史料に基づく抑制された文章の合間から、歴史上の人物の息遣いまでも伝わってくる。 『天地明察』にも通じるものを感じた。
2投稿日: 2014.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
富と名声を無視してでもオランダ語の和訳に対して昏い情熱を燃やし続けた前野良沢と、日本の医学を発展させるために賢しく世を渡って富と名声を手にした杉田玄白。対照的な生き方の二人をターヘル・アナトミアの翻訳という史実を介して、オーバーラップさせて構築した歴史小説。外面描写に徹した文体や冷徹な目線での語りを見るだけでは公平な眼差しで物語を構築しているようにも見えるが、タイトルを見れば、吉村昭氏は前野良沢に対してシンパシーを抱いていたであろうことが想像できる。そんでもって、どうせ人は死んでしまうという虚無感が、この作品の根底にも冷え冷えを横たわっている。これが心地いい。
1投稿日: 2013.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
前野良沢は杉田玄白の助手という説明でセンターを受けた。読後、この人物こそが解体新書和訳の第一人者なのではないかと感銘を受けた。杉田玄白は正義感の強い主人公ヒーロー、前野良沢は歴史の教科書に載るような生真面目な研究家、そんな印象だった。解体新書の完成過程は、様々なメディアを通して世間に知れ渡っているが、本書では医学研究家2人の憎み合い(親しみ合い)の駆け引きがとても面白かった。現代には無い江戸時代独特の威圧感が容易に想像できた。いつか大河ドラマで解体新書を巡る題材を取り上げるのであれば、本書を希望したい!絶対面白い!
1投稿日: 2013.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ解体新書を訳して出版した杉田玄白と前野良沢のお話。 合わせて、平賀源内も同時代で親交があり登場。 何もないところから専門書を訳すのは、できないことはないけど本当にものすごい根気が必要な作業で、それは熱意の成せる業。 同じ蘭学を学ぶ同士ながら、その志と辿った人生の違いが描写されています。 三者三様に良いところがあるのに、時の趨勢が彼らを取捨選択する… それでも見てる人はいるんだから、頑固に生きていいのかも。 華やかなエピソードしか聞いたことがなかった平賀源内の死に方と、あとがきのフルフェッフェンドの逸話が衝撃的でした。
1投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログひたすらに蘭語を追求した前野良沢と世間をうまく渡り歩き蘭学の権威を手にした杉田玄白。 解体新書を世に送り出した二人の対照的な生き方が鮮明に感じ取れます。
1投稿日: 2012.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ1774年(安永3年)8月、 オランダの医学書の訳本「解体新書」が出来上がった。 しかし、この本には後に我々が常識のように知っている前野良沢の名前は無い。前野良沢が訳者に自らの名を出すのを拒否したからである。杉田玄白、中川淳庵、桂川甫周との共同作業の中で1番オランダ語に通じていたのは前野良沢だった。しかし彼は「未完訳稿ともいうべきものを出版すること自体が、私の意に反する」と云う。いや、不完全でも医学の進歩のために早く出版するべきだ、と云うのが杉田玄白の考えだった。つまり、2人はたまたま志を同じくして大事業を成したが、性格は正反対だったのである。 吉村昭はあとがきで、「良沢も玄白も同時代人として生き、同じように長寿を全うしたが、その生き方は対照的であり、死の形も対照的である。そして、その両典型は、時代が移っても、私をふくめた人間たちの中に確実に生きている。」と書く。 前野良沢は学究肌で一生名誉栄達とは関係無く貧しさの中で亡くなった(しかし不幸せだとは私には思えなかった) 。杉田玄白はプロデューサー的資質に富んでいて、人当たりも良く、医者として栄達を極め、金も儲け、人々に囲まれ亡くなった(しかし決して悪辣なことはしていない)。その2人の対比が面白かった。 今回この本を読んだのは、50歳近くになって、オランダ語の学問に目覚め、つきすすんで 行ったという前野良沢になにかしら共感を覚えたからである。この本を読むと、めらめらとハングル学習欲が湧いて来た(^_^;)。 また、人嫌いの前野良沢が何故か急進的な尊皇思想家・高山彦九郎と交流があり、それとは関係無く良沢は択捉(エトロフ)の地理書を翻訳している。完全にノンポリであるにも関わらず、その90年後の激動の思想的準備をしていたことに、何かの「歴史の必然」を、私は思うのである。 その後、つくづく思うに自分は杉田玄白タイプだった。未完成でも、世に注意を喚起することの方を選ぶ。名誉や金銭欲はあまりないが、名を後世に残したい、世の中の為に成りたいという欲はある。 前野良沢は、名誉や金銭欲とは全く無縁なので、ついつい自分と重ねあわせがちではあるが、完璧主義の姿勢はやはり私とは無縁だと思う。
4投稿日: 2012.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ターヘル・アナトミア」翻訳の中心人物でありながら、自らの訳業に満足せず翻訳書上梓に反対だった前野良沢は、『解体新書』に翻訳者として名を連ねることを拒否した。代わりに翻訳者の筆頭となった杉田玄白は蘭医としての名声と富を手に入れたが、良沢は人との交際を殆ど断ち蘭学に没頭したため生活は困窮を極めた。 良沢は当時の日本で殆ど唯一蘭書を翻訳し得る語学力をもった学者であり、玄白は学究肌の良沢が効率的に翻訳を進められるよう腐心した有能な編集者であった。良沢がいなければそもそも翻訳は不可能だったが、玄白がいなければ良沢の訳業はいつ成就するとも知れなかったし、成就したとて良沢が訳稿を筐底に秘していた可能性が高い。 訳稿が玄白の手に渡ったのは、幸いだったと云わねばならない。「物に深くこだわることの少ない性格」だった玄白は、自ら翻訳した殆ど誤訳だらけの原著者序文を付して『解体新書』出版に漕ぎ着ける。そして『解体新書』の影響を受けて西洋医学を志す者たちを門下に受け容れ、優れた門人を輩出して更に名声を高めた。良沢には到底為し得ない芸当である。 それにしても、両者手を携えて蘭学の発展に尽くすという選択肢はなかったのだろうか。玄白の医家としての華麗な晩年と比べて、良沢の侘しい極貧生活は何ともやるせない。しかしそれは良沢が自ら選び取った道であり、目が霞んで文字が見えなくなっても蘭書と向かい合っていた彼にしてみれば、あるいは学問に専念し得た満足な一生だったのかも知れない。
1投稿日: 2012.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ医書『ターヘル・アナトミア』の和訳書である『解体新書』を訳出した前野良沢と杉田玄白。 しかし実態は前野良沢がほぼ独力で翻訳し、杉田玄白は翻訳作業が始まる時点ではオランダ語のABC(アルファベット)も知らなかつたといふ。蛮勇をふるふにも程があらうと言はれさうです。 ほとんど手がかりが無い中で、大いなる苦難の末、一応の訳出を果たします。しかし、どうしても分からない箇所も多くあり、そんなところは類推で無理やり翻訳してゐるので、当然誤訳もそこかしこにあるのでした。 オランダ語学者として完璧な翻訳を期す前野良沢と、医学者として医療の進歩を優先する杉田玄白。2人の対立が表面化します。結果、前野良沢は翻訳者としての名前を出さず、杉田玄白の訳書として世に問ふことになりました。 それまでの漢医学を否定する側面を持つ『解体新書』は、一大センセーションをもたらします。杉田玄白は紹介者として名声を博す一方、頑固な完全主義者・前野良沢は貧窮の境遇に陥り、私生活にも恵まれません。読者は、自然と前野良沢に感情移入してゆくのであります。 少々の瑕疵には眼をつぶり、とにかく前進する人と、足元を固めないうちは、前に進まない慎重な人。現在でも、かういふ対立はとかく生活の場、ビジネスの場などで散見されるのではないでせうか。 しかし世間的には敗者となつた前野良沢に、作者は暖かい眼を向けてゐるやうに思へます。 最後に近い場面で、視力が衰へ身体も自由が利かなくなつた良沢が独りで死を待つだけの情況に追ひ込まれます。そこで迎へに来るのが、他家に嫁いだ娘の峰子でした。一緒に暮らさうと引取りに来たのです。辞退する良沢に対し語気強く主張し、この父にうなづかせるくだりがあります。告白しますと、私はここで泣いてしまひました。小説を読んで泣くなど滅多にないのですが...やられましたねえ。おすすめです。 http://genjigawakusin.blog10.fc2.com/blog-entry-33.html
1投稿日: 2011.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「解体新書」は、杉田玄白と前野良沢が翻訳したと学校では習った。でも、「解体新書」の翻訳者のところには、前野良沢の名前がなかったことは、この本で初めて知った。しかも、この本が出てからの杉田玄白と前野良沢の歩んだ道がこれほど対称的なのも初めて知った。
1投稿日: 2011.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ解体新書と聞くと杉田玄白ぐらいしか知らなかったので、実際は翻訳のほとんどを担っていたのは前野良沢という人物であることをはじめて知りました。 読んでいると辞書の便利さを改めて感じます(笑)七百語ほどしかない乏しい語彙の中、推測や意訳も交えて翻訳していく様子は読んでいて興味深いです。それでいて大意はつかめていたらしくそれもすごい。 翻訳後、不完全な翻訳で出版することに疑問を持ち学問で名をあげることを良しとしなかった良沢と、医学の発展のために出版を急いだ玄白の人生は解体新書出版後、正反対の方に向かいます。二人の人生の対比も興味深いです。 終盤、良沢は彦九郎という人物と出会うのですが、そこの書き込みは少し物足りなかったかな?しかし全体を通して時代背景や、当時の情勢などの下調べもとても綿密で読み応えがありました。
1投稿日: 2011.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログターヘルアナトミアの翻訳にかかる前野良沢と杉田玄白を中心とする人間ドラマ。医家ながら、オランダ語の学習に異常なまでの情熱を燃やし、遂には大通詞すら凌ぐ語学力を修得するも、人嫌いでその能力の継承には関心のない前者と、医学の前進、時に名声の獲得に気を払う社交的で人の扱いに長け、次世代の育成に力を尽くした後者。更に、類い稀なる才能に恵まれながら山師と呼ばれ不幸な最期を迎える平賀源内、三大奇人と言われた尊皇家のはしりの彦九郎、など、それぞれの人となりが歴史的裏付けの下、よく描かれている。 通詞の中ですら読み書きをまともにできる者のいない中で、辞書も教科書もない時代に、たった700語を超える程度の語彙数で、仏蘭語辞書を意訳して、大意なりとも正確に訳出したことは本当にすごい成果だったと思う。本当に、融通のきかない学者肌の良沢には、玄白のような要領のよい気の利く相棒がいなければ、解体新書は成らなかったのだろうと思う。2人がその後ほとんど関係を持たなくなったことは性格の違いから自然なものだったのかもしれないが、それだけ違う2人を結びつけた翻訳への情熱が凄まじかったことの証明。 この時代の背景知識もよくまとまっており、後世に残したい一冊。
1投稿日: 2011.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ“解体新書”といえば杉田玄白が有名だが、この本は影の功労者である前野良沢にスポットを当てている。満足な辞書も無い時代に、いかにオランダ語を翻訳していったのか。解体新書が完成するまでの軌跡がこの一冊に密に詰まっている。
1投稿日: 2011.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本史上、「解体新書」の訳者は杉田玄白が有名ですが、それは前野良沢が訳者として名を連ねることを固辞したから。 彼は不完全な訳本に訳者として名を載せるのを良しとしなかった。 でも実際に血のにじむような努力をして訳したのは前野良沢ただ一人。杉田玄白は翻訳しやすい環境づくりをしただけ。 あれだけの努力をして名を載せないとは…その件を読み、心底驚いてしまった。良沢さん!載せましょうよ!と心の中で叫ぶ(笑)。 玄白は4人(だっけ?)チームの和やかな雰囲気づくりをしたり。いわゆるムードメイカー的な。 学究肌の良沢と、名声を欲した玄白とを対照的に描いている。正直ここまでキャラが対照的だったのかな?とちょっと思ったけれど。吉村氏は非常にわかりやすく描いてくれた。 この解体新書出版後の人生も、玄白は塾を開き大槻玄沢を輩出したり、後継者にも恵まれ、順風満帆(知的障害のある長男が生まれるというようなことはあったけれど)、富と名声を得た。 かたや前野良沢は、最期までオランダ語の勉強を続け、富と名声とは無縁、晩年は家を買うお金もなく借家住まい。最晩年は娘に引き取られた。 この時代のことは、みなもと太郎の「風雲児たち」で読んだ。 だから文章を読んでいるとそれぞれの漫画での顔が浮かぶ。 最後のほうでは、尊王派の高山彦九郎が登場して、彼の話になっていく(前野良沢がかわいがっていたそうな。吉村氏いわく、二人にはかたくななところなど、似たところがあるという) この方も「風雲児たち」に出てきたから興味深かった。寛永の三奇人! 中津は母の地元。 中津の描写自体はほとんどないけど(前野氏が町を歩いた、という程度の記述しかない)、中津藩は築地鉄砲洲にあったとか、奥平氏の名の由来とか、色々と興味深い。 奥平氏の名は、祖先の赤松氏(中世、鎌倉あたりにさかのぼる)が上野国の奥平というところを領地として与えられたことが由来なんだそうだ(高山氏が中津藩に親近感をもっていると話すところに記述あり)。中津と群馬なんて遠くて縁がなさそうだけど、こんなつながりがあるんだなあと興味深かった。
1投稿日: 2011.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ前野良沢と杉田玄白。 そのあまりの生き方の違いに、つい引き込まれて読んでしまう。 歴史の語り部としての作者の力量の高さに、あらためて脱帽。
1投稿日: 2011.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ駿台時代にこの本のことを知って、読みたくなってから3年越しくらいだ。前野良沢を主人公とした、『解体新書』にまつわる物語。辞書もないのに、どうやって立ち向かっていったのか、それに打ち込む情熱はどこから来たのか。その辺の試行錯誤とかが知りたくて、吉村昭なら書いてくれるだろうと期待してた。読んでみると意外な感じだ。ただ単にどうやって解体新書ができたかを書いていくだけでは、たぶん単調な話になってしまうのだろうが、色々と盛りこんであって、単に苦労話だけでなくそれぞれの生き方も丁寧に描いてあって、良い意味で期待を裏切ってくれた。『解体新書』が成るまでの話も面白いが、この本で秀逸なのは後半、良沢と玄白の交流がなくなってからだと思う。ひとまず「ターヘルアナトミア」の翻訳ができあがったとき、玄白は医学の発展のために出版しようとするが、学究肌の良沢は翻訳の不完全さを理由に訳者に名を連ねるのを拒む。こうして『解体新書』には中心人物である良沢の名前は載らず、玄白の名声ばかり高まる。良沢と玄白という対照的な2種類の人間のその後の人生が、後半に描かれている。多少の功名心をのぞかせる玄白はさらに目立ちたがりの平賀源内とも似ているが、源内が悲惨な最期を遂げるのに対し、玄白は幸福な晩年を送る。良沢は高山彦九郎との交流が描かれ、最後までオランダ語研究に情熱を注ぐが、晩年は孤独。さあどの生き方が僕にはあっているだろう。良沢の探究心には憧れるが、その成果を世に出さないのはあまり感心できない。学問は独りでやるもんじゃないと思うから、ファラディーが"Work, finish, publish."と言ったように、世に問うてみなければだめなんじゃないか。一方で源内みたいな生き方は僕も嫌いだし、彦九郎のような行動力はないし。玄白みたいな感じか? 玄白のような、集団をまとめる才覚みたいなのは絶対にないと思うけどね。とりあえずこれは座右の書にするかな。解説は上田三四二!
1投稿日: 2010.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ解体新書を翻訳したのが誰か知ってる程度の知識だったので 非常に興味深かった。同じ事業にかかわりながら、それをきっかけに 人生が真っ二つに分かれていき、対称的な晩年を送った二人。 どうしてそうなってしまったのだろう? 人生を考えさせられる一冊。
1投稿日: 2008.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「解体新書」といえば杉田玄白。学校の歴史では確かそう習った。実際、出版したのは杉田玄白だ。しかし、オランダ語の原書を翻訳したのは前野良沢だった。前野良沢という名はなんとなく聞いたことがあったが、彼が何をした人物なのは全くといっていいほど知らなかった。 この2人の人生の岐路となったのが「解体新書」の出版だったのだ。同時に、それは2人の能力というより性格、さらに言えば生き様の違いを浮き彫りにした。 いかに生きるべきか、人生に何を求めるのか。江戸時代の2人の「医者」の物語を通じて深く考えさせられる。
1投稿日: 2007.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ前野良沢と杉田玄白。このような関係と人生だったのか、と初めて知った。二人の人物の価値観の違いが読ませる。
1投稿日: 2006.12.13
