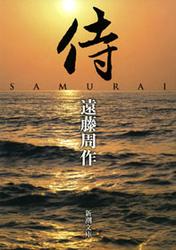
総合評価
(76件)| 29 | ||
| 32 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
こんなに悲しい悲劇的な小説もないというほど悲しいが、文句のつけようのない面白さだった。 イエスという未知の大きな存在、それらに惑わされ翻弄される人々、想像もしていなかった世界に対する戸惑い、これらが全て余す事なく表現されており、続きが気になって仕方なかった。風景や船旅の描写もとても素晴らしく、どれだけ過酷で残酷であったのかが分かりやすく伝わった。大袈裟な表現は一切ない。あれが現実なんだと心から納得させられる、だからこそ辛い感情もたくさんあった。 この作品の登場人物達に何か共感する事などとてもおこがましく感じる。日本とは狭く小さな国だと自分たちが言うのと、当時の侍が言うのでは重みが違う。 うまく感想が書けないが、この作品は長く自分の心の中に残り続けるだろう。ぜひ大人に読んでほしい作品だ。
0投稿日: 2026.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいて、日本の迫害者への怒りとか、キリスト教の偉い方々への不満などを感じましたが、「それでも信仰するの?」という感想から「それでも信仰するよね!」という気持ちが少し出てきました。
0投稿日: 2025.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログずしんときました。エゴと宗教、個人と社会、信じることと組織、結局は全て人間が作ったものなのに、それを自分で複雑にして潰しあってる。汚いところを隠さないと綺麗には見えない。。。
13投稿日: 2025.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでて辛いので★三つ! キリシタンの迫害は何度読んでも辛くなります。 毎度のことながら、数千年ものあいだ、人間の欲、政に振り回される人の多いこと。。。 今も変わらず続いてること。。 本当に人間の世界は一番辛く、分かりにくく、生きるのに難しい世の中と感じてしまいました。
0投稿日: 2024.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
貿易のため、東北からヨーロッパに派遣されることになった侍が、道中に役目のためのキリスト教の洗礼を受けた。異国の地で帰国後の約束を夢見て過ごす最中、日本の情勢はどんどん変わっていっていた。長い旅路を帰ると命令自体が無意味なものとされおり、クリスチャンとなった責任を問われることになる。 無宗教に近しい日本人が宗教に触れ、なんのために、なぜそこまで神が必要なのか、不服ながら掴んでいく。 我こそが日本にキリスト教を布教できると息巻く野心家の宣教師は、日本人の文化や生き方に紐づいたふるまいを、不気味がりながらも実は最も捉えている。 侍の道中の葛藤、役目を果たせない絶望、諦めと辛抱、宗教に触れた際の心の揺れや拒絶感、家族への想い。宣教師の傲慢な野心、宗派への考察、理解しきれの日本人への恐れ、傲慢さへの気づき、最後の無謀な行動。 どれもが唐突感がなく矛盾がなく心に落ちてくる。語りから見えてくる人物像であれば、おそらくその選択をするであろうと思える。侍が過ごす東北の生活も、その心理と合わせて目に浮かぶように描写されている。
0投稿日: 2024.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ『沈黙』を読んだ時と同じく、宣教師の「キリスト教を日本に布教することへの熱すぎる使命感」みたいなものには、やっぱりその気持ちよく分からないなぁ…という気にさせられたけど、『沈黙』よりもこの『侍』の方が私は好きだった。 主人公が日本人だったからだろうか。日本の小さな村の中の世界しか知らなかった長谷倉が、海を渡りノベスペニアやヨーロッパを知っていく過程で世界の広さを思い知っていくと同時に、やっぱり先祖代々の墓や家族がある日本への思い入れを強く感じるところ、みすぼらしくみじめに見える男の像をなぜヨーロッパ人は敬うことができるのかと不可解に思い続けていたが、日本に帰って御政道の何かを知り理不尽な扱いを受け続けた末にキリスト教を信じ続ける人の気持ちが分かったような気がするところ、結局どこの国でも宗教世界の中でも争いや駆け引きがあって人間はどこでも変わりないのだと諦めの気持ちをもつがそれをうまく言えないところ… そういう長谷倉には共感を覚えることができた。そして、彼を通して見ると、一緒に旅を続けた宣教師に対する日本政府の仕打ちのひどさにも少し同情することができる気がした。 (P447) あまたの国を歩いた。大きな海も横切った。それなのに結局、自分が戻ってきたのは土地が痩せ、貧しい村しかないここだという実感が今更のように胸にこみあげてくる。それでいいのだと侍は思う。ひろい世界、あまたの国、大きな海。だが人間はどこでも変りなかった。どこにも争いがあり、駆引きや術策が働いていた。それは殿のお城のなかでもベラスコたちの生きる宗門世界でも同じだった。侍は自分が見たのは、 あまたの土地、あまたの国、あまたの町ではなく、結局は人間のどうにもならぬ宿業だと思った。そしてその人間の宿業の上にあのやせこけた醜い男が手足を釘づけにされて首を垂れていた。「我等、悲しみの谷に泪して御身にすがり奉る」テカリの修道士はその書物の最後にそんな言葉を書いていた。このあわれな谷戸とひろい世界とはどこが違うのだろう。谷戸は世界であり、自分たちなのだと侍は与蔵に語りたかったが、うまく言えなかった。
1投稿日: 2024.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログなんというか、すごい本を読んだ。 300ページ超とそれほど分厚い本ではないのに、重苦しく読むのに10日と、とても時間がかかった。が、つまらないからでは決してない。 この本の感想を言葉で表す術がない。怒り、悲しみ、切なさ、理念、信念…少し、頭をひやしてじっくりと脳みそがことの本質を理解するのを待つことにする。いや、もしかしたら感想を書くこともできないかもしれない。私のような凡人にこの本の感想を書く資格などないのかもしれない。
3投稿日: 2024.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログまさに皆の思い浮かべるTHE SAMURAI的なやつ。もちろんハリウッド版じゃなくて三船敏郎版みたいな。 侍ってひたすらに我慢を強いられるというか、そういうイメージのもとに明治から昭和の戦時体制やらその後の昭和やら、ずっと力を持っていたわけで、しかしついに日本でもそういう人種が隅に追いやられ始めて、今この令和はまさに時代の切り替わりなんだとか思ったり。さてどうなるのか。 とは言え日本人にはこの我慢の感覚が染み付いてるわけで、ついつい心を打たれるのは昭和世代ということなんだよね。
1投稿日: 2024.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ弱い人でも強い人でも心挫かれたときに、その辛さを分かち合ってくれる理解者としてのキリスト。そして現世利益を重視する日本人にとっては富めるものよりも貧しいものがあの世で救われる考えや、実存的でないものがあまり合わない。こうした遠藤周作さんの考えるキリスト教や日本文化論を感じられる1冊でした。 過去作『沈黙』よりも運命や身分、政治といった大きい力の前で従うしかない弱い人と抗う強い人が強調されている感じでした。 とくに強い人として描写される宣教師の身勝手で欲深いために、周りに迷惑をかけてしまうところは共感を感じました。 そんな強い人が心を折られ、そのなかで自分が成すべきことを見出し最期はある意味で救われるところは感動しました。 遠藤周作さんの考えるキリストは自分にとっては本に近いとも感じました。辛いときに同じ境遇やもっと苦しく絶望に陥っても、それでも生を全うする登場人物をみて、不思議と心が安らぐ感じに近いと思います。 そして、本作の侍も宣教師も苦難ばかりの長旅と失意の底に陥ります。彼らの旅に比べれば多少の現実の困難は大したことないかもですが、それでも彼らからしたら「わかるよ、辛いよな」という気持ちになってくれるはずです。 そのうえできっと裏表なく理解してくれる。とくに仕事や人間関係で辛いときはわかりあってくれて、人生に全うできるように肩を並べてくれるような気がします。 この作品を読んでわずかでもキリストに関われたのだからきっとそうだと私は信じてしまう。そんな読後感でした。 【お気に入りフレーズ】 泣くものはおのれと共に泣く人を探します。嘆く者はおのれの嘆きに耳を傾けてくれる人を探します。世界がいかに変わろうとも、泣く者、嘆く者は、いつもあの方を求めます。あの方はそのためにおられるのでございます。
15投稿日: 2023.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ大事に少しずつ読んだ。 フィクションとはいえ 悲しい 日本 いにしえの時代の黒歴史。 なぜ日本は ラテンアメリカ諸国のように キリスト教 に征服されなかったのか ここに一つの答えがあるように思う。
2投稿日: 2023.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ策士で出世欲をにも駆られたエスパーニャ人宣教師。その宣教師と共にノベスパニアへ旅立つ四人の伊達藩使者たち。 宣教師と日本人も旅立つ目的は全く異なるもの。 現世の利益のみにだけしか宗教心を持たず、無表情で寡黙、狡猾とも表現される日本人。 侍とは、日本人とはそういう存在である事が時に哀れに表現されつつも、例え袂を分かつ仲間でさえもその強さに魅了されてしまう。 『沈黙』に続き手にした作品。 宗教とは?信じるものとは?そもそも信じるものが現実世界に必要なのか?存在するのか? 筆者の狙いは別としても、考えずにはいられない謎が浪漫を導く一冊。
0投稿日: 2023.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ慶長遣欧使節の一員としてローマにわたった支倉常長をモデルとした小説です。 宣教師のベラスコは、現世を超越したものへの関心をもたない日本人にキリスト教の信仰にみちびこうとする強い情熱をもっていました。同時に彼は、布教のためには手段をえらばない、策略家でもありました。そんな彼のもくろみが功を奏して、陸前の港からノベスパニア(メキシコ)に向けて、使節が派遣されます。使節の役目を果たすことになったのは、召出衆と呼ばれる不遇の「侍」であった長谷倉六右衛門をはじめとする四人でした。長谷倉たちは、ベラスコに不信感をいだきながらも、海外との通商の窓を開くことを決意した藩主の親書をもって海をわたります。 その後一行は、大西洋を越えてヨーロッパへわたり、さらにローマ法王に謁見することになります。しかしそのころ日本では、幕府が禁教政策の強化に動き出し、主君の命を果たそうとする長谷倉たちの思いはむなしく終わります。そしてベラスコもまた、日本人をキリスト教の信仰にみちびくという望みがついえたことを知ります。 ベラスコに対立するペテロ会のヴァレンテ神父との討論では、キリスト教がけっして根づくことなく、いつのまにかそれを伝統的な信仰に変えていってしまう日本という風土にかんする著者自身の見かたが示されています。野心的な宣教師が経験することになったの挫折と、当初は簡単にわかりあうことがないように思えた「侍」の悲劇的な運命が交わるというストーリーの運びかたが見事な作品だと感じました。
0投稿日: 2023.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
侍って作中にあえてでているのはなぜなんだろう。 安土桃山時代に主君の命とはいえ、異国に行けといわれどんな気持ちだったろ。 実話に基づく話でこんな日本人がいたことを知らなかった。時代の流れに翻弄され無念だったろう。 ローマに残るのも心残り。不本意にキリシタンになりそこの地で暮らすのも不本意。行き場のない気持ちがえがかれていた。 キリスト教にとって、インディオの村も日本も野蛮で改心させねばとおもわれていたんだな。何故ほっといてくれないのかと悲しい。
0投稿日: 2023.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ遠藤周作の圧倒的無力感・孤独感を凝縮した野間文芸賞受賞の傑作。 鎖国下での宣教師と侍という特殊な立場の対比が興味深い。 長編の中でも尺のあるボリュームだが、その前半で何となく結末が分かってしまうにも関わらず読ませてしまうエネルギーと説得力。
1投稿日: 2023.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦国時代、藩主の命令によってローマ法王への親書を携えて海を渡った東北の貧しい侍の話。侍から見た世界、キリスト教とは。4人の侍の性格の違いとたどった道筋の違い、そして太平洋から南米大陸、大西洋、ローマへの長い旅路の様子も興味深い。 忍耐強い侍の心理描写や従者との信頼関係も印象に残った。
0投稿日: 2022.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ『沈黙』と同様、読後に心に重くのしかかる1冊だった。遠藤周作の作品を読むたびに信仰とは何かを考えさせられ、カトリックである私は自己の信仰を見直すことになる。ここでは、使節団がノベスパニヤで出会った元修道士が語るように、自分は「教会や神父たちの説くイエス」は信じておらず、自分の信じるイエスは「金殿玉楼のような教会におられるのではなく、このみじめなインディオの中に生きておられる」ということ。信仰の原点を知らされた思いがした。
0投稿日: 2022.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、映画が公開された事もあり沈黙を読んだ。切支丹禁制の中の重い考えさせる話だった。この侍という本は、キリスト教から行き着いたのではなく、メキシコ、バチカンまでの航海の方からたどり着いた。この本の解説によると支倉使節団については資料が少ないらしい。支倉が書いた日記も処分されてしまったらしい。もったいない。使節団として送り出されたのに状況が変わり、帰ってからの不遇。現代のサラリーマン社会にも通じるな。可哀想。ここでも沈黙同様、運命に翻弄されるキリスト教徒の信仰についての苦悩が語られる。航海の記録というより、こうした神をどう理解するかというところに主眼が置かれている。考えさせられる一冊。しかしこの使節団が無事に日本に戻ってくるのは素晴らしいことだ。
0投稿日: 2021.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに読んだ遠藤周作。 さすがというか、やっぱり文豪。 40年たっていても、文章が生きている。 しばらく、遠藤文学を読み直してみようと思う。
0投稿日: 2020.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ沈黙に続き読了。 実際のモデルは支倉常長。 当時のキリスト教への時代背景や、日本人のキリスト教への捉え方、政治利用など様々な事が学べて面白かった。 『人間の心のどこかには、生涯、共にいてくれるもの、裏切らぬもの、離れぬものを――たとえ、それが病みほうけた犬でもいい――求める願いがあるのだな。』
4投稿日: 2020.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆☆☆2020年3月☆☆☆ 江戸時代初期、まだ大坂の陣は終わっていない頃。 徳川氏の天下が確定しつつあった頃の物語。 東北から、宣教師とともにメキシコへ、ヨーロッパへと旅した「侍」と、宣教師を中心とした物語。 「侍」=長谷倉のモデルは、明らかに支倉常長だろう。 異国との通商を求めるという親書を携え、メキシコへ、スペインへ、イタリアへ、苦難の旅。 「宣教師」=ベラスコはポーロ会という宗派の宣教師で、日本にキリスト教を広めたいという強い思い、そして自分が出世したいという秘めた野望を持っている。 長谷倉らは、使命を果たすため、やむなくキリスト教に改宗。これが帰国後彼らにとって悲惨な結果となってしまう。つらく悲しい物語だ。特に若者の西が可哀そうに感じる。異国の珍しいものに心から感動していた、好奇心の強い若武者。 「日本人は利に聡く、利用できるものなら何でも使用しようとする」ような記述が所々にあったが これは筆者の想いだろうか? これは日本人のいい面でもあり、悪い面でもあるだろう。 ベラスコは、最終的に自ら日本に赴き殉教する事になる。「信仰」のために何故そこまで?というのは、私たちにはわかりにくい。
0投稿日: 2020.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
◯昔のことなので記憶が怪しいが、「沈黙」の時に感じた日本人の現世利益的な信仰と、西洋的な信仰の関係性とは異なり、個人の信仰と、組織や政治との関係に関する小説だと読んでいて感じた。 ◯また、読みながら、歎異抄の「親鸞一人がためなりけり」という言葉を思い出した。こちらは能動的に関係を築き、この境地に至っている点を思えば、「侍」の中で日本には根付かないとされた信仰の心は確実にあったと思う。解説にもあるとおり、侍自身は受動的に始まったものだが。 ◯そう考えると、「侍」はやはり純粋に信仰に対する試論なのかなと思った。
3投稿日: 2019.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ実に丁寧に書かれている文章だと感じた。 侍が、キリスト教に関して問うている部分が、非常に共感できて、また、時代の流れも感じられた。 淡々と進むストーリーと、感情の変化、揺れが、非常におもしろかった。
0投稿日: 2019.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ転ぶ。 信仰とは何か?、ということすら、生きる上で全く考えることのない、無意味なくらいの、そんな侍の社会。 その社会で大切なのは、ただただ忠誠であり信仰とは似て非なるモノ。 その時代の人達が。 何故ヨーロッパに行くのか? キリスト教が介在したのは何故? 危険を冒す理由があったのか? という事は、史実でも、まさに本文中でも、たっぷり書かれている。 個人的に唸ったのは。 商売の利と信仰を天秤に計る人の心理 忠誠を示す為に信仰を選ぶ心のさざ波 司祭同士の出世争いの場にされた日本 功名心を信仰心で巧みに隠してく醜さ 棄教を前提に自分自身を欺くその描写 日本に戻った侍の心の描写が、その答えだった。 「侍は自分が見たのは、あまたの土地、あまたの国、あまたの町ではなく、結局は人間のどうにもならぬ宿業だと思った」 信仰と不信。 二つのテーマが、ぐるぐると廻り、巡り、描かれる一冊でした。 信仰があることがイイワルイではない。 自分がどうあればいいのか?とか、信じないといけないとか、奇跡なんて科学的じゃない、理論的じゃないとか、どうでもいい。 信仰することで救われる人がいるんだ。 ただただ、そのコトだけを知り認める心を持つだけでいいんだと、そんな読後の感想でした。
1投稿日: 2019.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「沈黙」のテーマ「神の存在の有無」に対し「侍」は「宗教とは何か」という問いかけの小説だと思います。 キリスト教のお話でありながら、日本の宗教観についても描かれていて、「なぜキリスト教は日本に向かないのか」をヴァレンテ神父が語る場面は、深く頷きながら読みました。ヴァレンテ神父の語った日本の宗教観や社会構造は現代日本に脈々と受け継がれているものがあるのを感じました。 また、江戸時代の日本社会の陰湿な部分を、政府上層部や役人の描き方や、暗く冷たい建物の描写で表してるところがすごく印象に残りました。 でも正直読みながらずっと思ってたのは「ベラスコのせいでこんな事に…!!」ということです。こいつさえいなければ…!!そして、やはり宗教の押し付けは古今東西良いことがない。 ただし、最終的には実はベラスコは自らの信仰と布教において勝利しているところがまたこの小説のすごいところです。 「侍」は最期、何を、誰を思ったのでしょうか… 残酷な現実と絶望の向こう側に真理が少しだけ見えるような描き方が素晴らしかったです。 神とは、宗教とは、日本とは…考えさせられる一冊です。
1投稿日: 2019.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ沈黙とは異なるキリスト教歴史小説。 政治の闇に弄ばれたと書くには足りない、男の生きざま。 日本人の不気味さと誇りとを外国人の目を通し語らせているのが秀逸で、著者の目線の低さを感じる。
0投稿日: 2019.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ支倉使節団として、勤めを果たすために海外へ長い旅路を経て行くが、日本に帰国したら基督教を信仰しているとして処刑されてしまう。なんとも不条理な世の中であったのだろうか?
0投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々に読み応えのある小説に出会えた。自分の力ではどうにもならぬ運命に流されていく切ない物語。「転ばない」美学
0投稿日: 2018.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「侍」は、実在した仙台藩の支倉六衛門常長をモデルとした史実に基づく小説であり、遠藤夫人が夫遠藤作周作の著作中で最も好きな作品として挙げている。 キリスト教に帰依したことを理由に処刑されることとなった「侍」に従者が伝える「ここからは……あの方が、お仕えなされます」という台詞について、遠藤は「この一行のためにこの小説を書いた」と後に語っている。 「あまりにも多くのものを見すぎたために、見なかったのと同じなのだろうか」 「日本人たちはこの海を日本を守る水の要塞にして、自分たちは土の人間として生きてきたのだ。日本人たちはこの世のはかなさを楽しみ享受する能力もあわせ持っている」
0投稿日: 2018.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ主命でメキシコ・スペインへ渡った「侍」は、役目を果たすため、キリスト教へ帰依をする。しかし、旅の途中で日本の政情が鎖国へと変わり、当初の役目を果たせなかったばかりか、偽りとはいえ受洗したことが咎となり、帰国後も潜むように生きることを強いられる
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ果たして基督教の信仰とは何なのか、苦難に対峙してもなお沈黙する神とは何なのか。時代と政に翻弄される「侍」長谷倉と烈しい信仰を持ってベラスコの眼と体験を通して日本人の宗教観が立体的に描かれる。万の神を認めて藩主を絶対的統治者とした当時の侍たちに対し、当初は使命感と意志をもって基督教布教を謀るベラスコの姿は滑稽で狡猾ともみえるが、後半になるに従って長谷倉は藩への疑義に反して信仰を問い、ベラスコは教会への不信に反して信仰を深める姿が印象的だ。 『沈黙』と比べると直接的表現も多く、理解しやすい反面文学性はやや劣るが、『侍』のほうが会社の命令に右往左往する悲哀溢れるサラリーマンに通じるものがあり感情移入する人は多いかもしれない。
0投稿日: 2018.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
藩主の命によりローマ法王への親書を携えて海を渡った一人の侍。多くのものを失い傷つき絶望し、7年もの後やっとの思いで故郷の地を踏んだ彼を待っていた運命はあまりに過酷だった。 共に旅をした宣教師ベラスコはすごく傲慢で初めは嫌いだったが、読み進めるほどに彼の人間らしさ未熟さに興味がわく。 宗教は好きではないが、最後に侍の心にその人が寄り添って少しでも楽になったのならいいなと思う。だけどラスト、ベラスコがその知らせを聞いたときの反応には正直がっかり。その思考は理解できなかった。 小説としてはすごくおもしろかった。
0投稿日: 2018.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ物凄く面白かった。キリスト教との関わりの中から、他の作品と同じように、日本人の本質をことごとく見事にあぶりだした作品だったと感じる。 30年近く日本で布教活動をしてきたヴァレンテ神父の「日本人はこの世界の中で最も我々の信仰に向かぬ者達です。彼らにとってもし、人間以上のものがあったとしても、それは人間がいつかなれるようなものです。たとえば彼らの仏とは、人間が迷いを棄てた時になれる存在です。日本人は決して1人では生きていません。彼の背後には村があり、家があり、彼の死んだ父母や祖先がいて、彼らはまるで生きた生命のように彼と強く結びついているのです。一時的にであれ改宗したはずの彼が、棄教してもとに戻ったとは、彼がその強く結びついた世界に戻ったということです。」という、研究結果の報告文書に近いような諦めの言葉にも負けず、熱と烈しさを持って挑んだベラスコ神父の心理描写が、刻々と変化していく様も実に鮮やかだった。 司教就任のためにキリスト教や切支丹、さらには母国の同胞までもを世俗的に利用していたベラスコが、終盤では政治の世界で敗れはしたものの、魂の世界においては勝利したのであり、それはイエスキリストと全く同じ状況であったとする下りからも、つまりはキリスト教全体が包括する様々な価値観から、自身の人生に意味を与えるものを抽出して当て込んでいるのだと思う。「夜と霧」にあるアウシュビッツの囚人たちと全く同じで、「自分の人生に意味を持たせる」ために、神はいるのであって、安直なオプティミズムで受難を隠すためにいるのではない。そのためには時として苦しみ、嘆き、辛苦を徹底的に味わうことで、みすぼらしく痩せて困難にまみれた生涯を生き抜いたとされるイエスキリストの人生を体現し、意味を持たせることすらできる。 言っちゃえば、人がどんな人生を歩もうと、何もかも超越した神様が見てるぞーってなればどうとでも意味づけができるんだということ。意味づけのない人生こそ、何より虚しいものだと。人生が上手く行ってれば、感謝してたらいいし、上手く行ってないなら、上手く行くために頑張る活力を与えたり、反省懺悔させて救ったり、なんだかんだで「自分はこのために生まれてきたのだ」に近いものを授けてくれる。それがキリスト教なんじゃないか。 日本人は上にもあるように、家や村や家族あってのものなので馴染むわけがない。日本人は1人で生きていないってのは名言。その点、創価学会がここまで広まった経緯は、地方から出稼ぎで出てきた、つまり家も村も祖先も棄てた人達が共同組合みたいな成り立ちで出来たと聞く。なので地方民が集められたような街で勢力を広めていけたわけで、その点キリスト教みたいに1人で生きていかなければいけない人達を救うことができているのかもしれない。 従者として苦心を共にしてきた与蔵がキリスト教を強く信仰していた理由は、村での人生に意味づけができていなかったからだし、最後の与蔵の一言に侍が大きく頷いた理由も、自身の労苦が報われず主従関係が反故にされたことで、人生の意味を失ってしまったからだ。人生の意味をもう一度見つけてくださいと、与蔵が侍に伝えたかったのだろう。
2投稿日: 2017.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者の作品、「沈黙」と双を成すキリスト教をめぐり時代に翻弄される人々の物語。あまりに無情な仕打ちを受ける主人公の侍。もう一人の主人公、野望をもったベラスコが悟りを開いていく過程をじっくり描いていて説得力があります。ベラスコが日本に再上陸することで結局は侍も残念な結果に。。侍はある程度納得しているのかもしれないが、残された家族はいたたまれないです。 キリスト教は精神の安定を目指しているのは司教の考えであって、仏教も含め多くの宗教を信仰する庶民は現世の幸せを願うものでは、と考えてしまいます。 人それぞれの価値観と尊厳を考えさせられる深い一遍です。
0投稿日: 2017.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ藩主の命によりローマ法王への親書を携えて、自分の狭い領地しか知らなかった侍は海を渡る。お役目達成のために受洗を迫られ、その後鎖国となった日本に戻ってきた侍の運命は…という内容。 日本人が絶対的なものより、親族の結びつき、現世で利益となるものしか信用しないという見方は面白かった。 宗教の受容が国、個人どのようにされたのか興味深い。
0投稿日: 2016.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまでの読本で、かなり上位にくる名作。 侍の心理が、深く心に突き刺さる。また、宣教者達の日本分析が、五百年後の今もピタリと当てはまる。いくらグローバルを叫んでも、この日本人の本質は、先般読了した原発敗戦同様、肝に命じておく必要ありだ。
0投稿日: 2016.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ支倉常長の海外渡航から死に至るまでを書いた重厚な1冊。 これは旅行記ではなく、信仰についての問いかけに満ちている。前に読んだ「沈黙」は神の存在について考えさせられるものであったが、この本は神を信じる人間についての本にだと思う。 ノベスパニヤにいた日本人が信じる神とローマで信じられている神との隔たりは強者と弱者の信仰の違いを語っているように感じ、そこに神という存在の不明瞭さからくる悲劇を思う。 最後に支倉常長に寄り添う神はローマの神ではない。 神とはなんなのだろうか。 「沈黙」の時にも感じたが、やはり人の心の中にだけ神は存在し、そこに真実があるように思う。 形に意味はなく、見えない部分こそが大切なのだ。 それにしても支倉常長、全然わかってなかったが一言でいうと悲しすぎる。
0投稿日: 2016.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ遠藤周作の作品は「痛快」という言葉がよく合う。 「沈黙」よりも動きのあるストーリーなのに、なぜだろう、すごく長く感じてしまった。きっと自分の歴史の知識が乏しいことと、総じて暗いからなんだろうけど。 遠藤周作の作品はノンフィクション風に描かれているので、まま信じてしまいそうになる。解説を見ると、船上での生活や洗礼儀式など、彼自身の体験を忠実に再現しているそう。リアリティに溢れているのも納得である。 彼の表現は正確である以上に、人が潜在的に感じている感覚的な部分まで細かに言語化されている。こちらがとらえている人間以上の人間らしさを、まったくうまく描写してるんだよな〜とやはり痛快に思った。
0投稿日: 2016.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ藩命により、日本人未踏のヨーロッパに行き、不本意のまま洗礼を受ける。苦難の末帰国した一行に待っていたのは、キリスト教禁制、鎖国した故国。支倉常長一行が長旅の末に至った信仰は、やむを得ずか、自らであろうか。2016.1.3
0投稿日: 2016.01.03侍
メキシコとの貿易を開始するため使節団としてローマにまで行かされた侍。さまざまの政治的駆け引きのある中やっとの事ローマ法王と会うことができたがその頃には日本の状況が変わりキリスト禁教令が出されていた。べラスコスの野望のために振り回された侍達。あきらめの境地。 宗教とは何なのか考えさせられた。特に政としての宗教にはどうしてという疑問がわいてくる。
0投稿日: 2014.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ『沈黙』よりももしかしたら、こちらの方が好きかもしれない。ずしーん、と心に重くのしかかってくる作品。 自分のことや、友だちのことを考える時、信仰って一体なんだろう、と思うことがよくある。 それでも信じ続ける理由? 僕はまだ、よく分かりません。
0投稿日: 2014.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代初頭、仙台藩が送った遣欧使節の話である。主人公は、長谷倉六右衛門と宣教師ベラスコ。ベラスコの持つ、驕慢と野心、日本という困難な国で布教し、征服したいという野望。一方、侍の持つ、お役目に対する真摯さ、たとえ不条理なものでも定めと受け入れる愚直さ。この二人は対照的だが、読み終えてから気づいたのは、実は表裏一体なのではないかということ。 物語は、月の浦から出航するまで、ノベスパニア、さらにエスパニア、ローマ、そして空しき帰路と展開していく。ヴァレンテ神父との対立の中、切り札である侍たちの洗礼がなされ、ベラスコの野望は成功し、使節団と国王との謁見が実現するかに見えた。ところが、江戸幕府がキリシタン禁制に舵を切ったことが発覚し、形勢は一転する。 破れた悲壮さの中で、侍は御政道の現実を知る。そして、人間が求めるものは、生涯そばにいてくれ、裏切らぬものである、それがあの男の存在意義なのかもしれないと気づくのだ。 この著作は、物語の展開や、登場人物の深さにおいて、誠に読み応えがあった。自刃で以て、自己を完結させた施設の一人田中。ベラスコは、自殺に等しい禁教となった日本への潜伏を試み、火刑に処せられる。私は生きた、という言葉を残して。それは、自殺を禁じられたキリスト教徒ベラスコの、自己完結の手段だったのだと感じる。
0投稿日: 2014.07.28忠義を尽くす事とは一体なんなのか?
慶長遣欧使節の話をベースにした小説なのですが、主人公の「侍」の運命がかつての自分と重なり思わず涙してしまいました。
1投稿日: 2014.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ務めのため異国に渡った侍の話であり、宣教者の信仰の話でもある。 長谷倉(支倉)はスペインに渡って同化するどころか、その文化とも信仰とも、交わるところはない。翻弄されても日本人であろうとする姿は、今はなき侍の矜恃である。 そこかしこに神がおり、人間以上のスーパーマンは不在の日本に、キリスト教は馴染まない。異文化を通じて日本人というものが浮かびあがってくる。
0投稿日: 2014.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ貧乏な一人の侍が突如、殿様の命令によりメキシコへ派遣される。同行者には通訳兼神父のベラスコ。旅の途中で侍はお役目の為にキリスト教に帰依する。そして日本に帰ってきて… この本の最後にある解説を読んでびっくり。実話を元にしたフィクションだそうだ。大河ドラマにしたら視聴率とれるんではないか?
0投稿日: 2013.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ徳川幕府が切支丹禁止令を出す頃の東北のある大名が遣わした遣欧使節団に関する事実。大海に出て世界を見てきた「侍」が数年後、日本に帰国して待っていた運命とは。もの悲しくもあり、人間とは?信仰とは?を問いかけられる。
0投稿日: 2013.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ『沈黙』に触発されておそらく初読、個人的には『沈黙』には及ばないかな。 こちらの作品は主人公が二人設定されており、それぞれのストーリーが紡がれているため若干冗長な感がある。 日本人にとっての自己とは何か?という考察、非常に興味深い。 ヨーロッパはキリストという絶対的な客体との関係の中で自己を捉えるが、日本は家族・地縁・上司等客体であって客体でもない人間関係の中に自己認識の基盤がある。 これは決定的な相違であり、だからこそ侍達には絶望が、パードレには(あくまでパードレ自身にとってだが)希望が最後に待ち構えている。 侍達の境遇は現代日本の何処にでもありそうな話、つまり日本人の精神性はなおも変わっていないというこれもある意味悲しい話でもあります。
0投稿日: 2013.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ重い、暗い話だ。 宗教と自分の虚栄心、また社会制度の中で揺れ動く主人公達。 真面目だ。 神なのか家なのか、自分の屋台骨となる信念を持っている人たちはすごい。現代人にはあまり無い感覚だ。
0投稿日: 2013.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ権力に翻弄された庶民の数奇な運命。。 この話は知ってましたが、ここまでだったとは…。 この作家の誠実さは、尋常ではない。
0投稿日: 2013.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログベラスコ(ルイス・ソテロ)の烈しさはどこからくるのでしょうか。支倉常長の思いと慶長遣欧使節の事実も気になります。 今年は出帆400周年なんですね。 いつか仙台&石巻に行ってみたい。
0投稿日: 2013.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ報われない道程だと知りながらも、「武士」ゆえに拒否することも、引き返すことも出来ない・・・ 宗教、伝統、階級、そして鎖国に否応なく翻弄される、宣教師と支倉常長たち一団のローマ法皇謁見までの長い長い旅路を、遠藤周作の美しい筆致で、重厚に描いた作品です。
0投稿日: 2013.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ名前は聞いたことがあるが、よく知らない支倉常長。ローマまでの道のりはどれほどの苦しみがあったのか、垣間見ることができた。キリスト教とは距離を置いていた支倉の気持ちやその葛藤についてもっと描ききってほしかった。
0投稿日: 2012.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日、慶長遣欧使節資料が世界記憶遺産に申請されたというニュースを聞いて読み返してみた。 『沈黙』と共に、キリスト教とは・日本人にとっての宗教とは…ということを考えさせられる一冊。
0投稿日: 2012.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ遠藤周作の作品に出てくる登場人物ってどうしてこんなにイメージしやすいんだろう。中でも、『侍』は使節として送られる代表3人と、彼らを繰ろうとする宣教師それぞれが全く異なる個性を持っていると認識出来て面白かった。
0投稿日: 2012.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
時代はまさに,家康が幕府直轄領に切支丹の教えを禁じだした時である。そんな時代,布教に対し,命をかけなければならないような日本に,宣教師ベラスコ(実在したルイス・ソテロ神父)がキリストの教えを広めるため,そして自分の栄達のため,策謀を張巡らせつつ,本当のキリストの教えとは何なのか悟っていくていく物語。また,そんなベラスコの熱意に対し,侍がどのようにイエス・キリストのことを考えたか。日本人の心がどのようにキリスト教を捉えているのか,日本人特有の現世利益を求める姿を例にあげつつ,侍の心とベラスコの心を交互に捉えながら話は進む。 当時,本来であれば,日本は宣教師であるベラスコを追放するべきなのだが,利用価値があるとして,通詞の役目を与え,ノベスパニヤとの通商を始めようとしていた。幕府直轄領では禁教するが,その他の国ではお咎めなしという都合のよい施策を打っていた。このため,江戸を追われた信徒は西国や東北に逃亡することも黙認していた時代だった。 フランシスコザビエルが,半世紀前に日本に上陸し,この国の伝道はすべてザビエルの創設したペテロ会が独占してきたが,十年近く前に法王のクレメンテ八世が他の修道会にも日本への布教を認め,ペテロ会と他の会との軋轢が増した時代である。ベラスコはペテロ会と対立するポーロ会の宣教師で,日本での布教が厳しくなったのは,ペテロ会が長崎に植民地に等しい土地を得ていたためだとなじった。九州を占領した秀吉は,布教に名を借りた侵略だと激怒し,禁教令を布いた事は周知の事実である。ベラスコは,自分に任せておけば,日本人をうまく操れる,日本人には利益を与え,我々には布教の自由をもらうといった取引を自分は巧みに行うことが出来ると思っていた。国家は宗教を利用し人々を支配し,宗教は国家を利用し布教を進めようとする。宗教が広まっていくのは,先進国の技術を途上国は輸入させてもらう代わりに布教の自由を与える。宗教と国策は切っても切れない縁で繋がっていた。 ベラスコも同じように,布教を許してもらう代わりに,ノベスパニヤとの通商の道を開けと藩主伊達政宗に言われる。これによりノベスパニヤ行きが決定したわけだが,それには日本の使節が必要になる。そこで選ばれたのが,本書の題名になっている”侍”こと長谷倉六右衛門(実在した支倉六右衛門のこと)だ。 船の中でベラスコは日本人がキリスト教に興味を持つだろうと思っていたが,そうはならなかった。日本人は幸福の意味とは現世の利益を得ることであり,それは富み,戦に勝ち,病気が治ることで,それらを目的とした宗教なら受け入れるが,超自然なもの,永遠に対してはまったく無感覚である。その現世利益のためだけに,使節団と共にノベべスパニアに渡った商人連中は切支丹になった。役に立つものなら,何でも取り入れるという日本人独特の考えである。薬師如来も病気平癒のため崇められる。宗教に現世利益を求める日本人は,キリスト教の言う,永遠とか魂の救いとかを求める宗教は生まれない。ましてや復活など。ペテロ会は当初はそんな日本人の特性に対し,鉄砲を売り込み,その代わりに宗教を広める許しを得てきたが,利権確保をやりすぎて失敗したのだ。 ベラスコがキリスト教を日本人にも広めようとする中,侍は,無力でみすぼらしいキリストの姿に神々しさも尊さも感じない。美しい仏像にはおのずと頭が下がる思いがするし,清らかな水の流れる社の前に立つと手を打つ気分にもなれる。日本人は本質的に人間を超えた絶対的なもの,自然を超えた存在,切支丹が超自然と呼んでいるものに対する感覚がない。反対に,この世のはかなさを感じること,はかなさを楽しみ享受する能力を合わせ持っている。持っているだけでなく,その能力があまりに深いゆえに日本人はそこに留まることの方を楽しみ,その感情から多くの詩を作る。そこからは決して飛躍しようとはせず,飛躍して更に絶対的なものを求めようとは思わない。日本人は人間と神を区分けする明確な境界がないのだ。人間はいつかは神になれる,近づける存在だと思っている。だから日本人は,人間とは次元を異にしたキリストという神を考えること,捕らえることが出来ない。 日本人は決して一人では生きていない。『彼』という一人の人間は日本にはいない。彼の背後には村があり家がある。それだけではなく,死んだ父母・祖先がいる。その村,家,父母,祖先はまるで生きた生命のように彼と強く結びついているのだ。彼とは一人の人間ではなく,村や家を背負った総体なのである。フランシスコザビエルが日本で布教を始めたときぶつかった最も大きな障碍はこれだった。日本人たちはこう言った『切支丹の教えは善いものだと思う。だが自分は自分の祖先がいない天国に行くことは祖先を裏切ることになる。死んだ父母や祖先と自分たちとは強く結びついている』と。これは単なる先祖崇拝ではなく,強い信仰といわず何と言おう。 侍をはじめ,多くの日本人は,キリストの,あのようなみすぼらしい,みじめな男を敬うことが出来ない。あのように痩せた醜い男を拝むことは出来ない。しかし,切支丹はこう言う。キリストがみすぼらしく生きられたがゆえに信じることが出来る。醜く痩せこけ,この世の哀しみをあまりに知ってしまったキリストは,人間の嘆きに眼をつぶることが出来なかった。だからキリストはあのように痩せて醜くなられた。もしキリストが自分たちの手も届かぬほど,気高く,強く生きられたなら,切支丹とはならなかったと。キリストは生涯みじめだったゆえに,みじめな者の心を知っている。みすぼらしく死なれたゆえに,みすぼらしく死ぬ者の哀しみも知っている。キリストは決して強くもなく,美しくもなかった。キリストは一度も心驕れる者,充ち足りた者の家には行かなかった。醜い者,みじめな者,みすぼらしい者,哀れな者だけを求めておられた。泣く者はおのれと共に泣く人を探す。嘆く者はおのれの嘆きに耳を傾けてくれる人を探す。世界がいかに変わろうとも,泣く者,嘆く者は,いつもキリストを求める。そのためにキリストはおられるのだと。 後段で著者はベラスコに自分の嘆きとも言える言葉を吐かせている。今はキリスト教の司教も司祭も心は富み,心は充ち足りている。今あるキリスト教は,かつてイエスキリストが考えられた姿ではないと。
0投稿日: 2012.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログおれにとって6作目となる『侍』は、これまで読んだ『沈黙』、『イエスの生涯』、『キリストの誕生』を合わせた集大成のような作品だった。遠藤周作の考える、日本人と宗教、日本人とキリスト教、無力なイエス像、ペテロとポーロ、といったテーマが織り込まれた作品。 ほんとは宗教や信仰とかいった問題について考えるべきなのかもしれないが、それよりもおれは、歴史の壮大な流れの中に生きるちっぽけな人間、どうしようもない理不尽さ、という感覚を強く味わった。この「ちっぽけな」という部分が「イエスの無力さ」という部分に通じるのだろうけど、イエスがどうのこうのと考える前に、やっぱり単純に侍の生き方に思いを寄せてしまう。ところで、松木という人物は、人や物事のすぐ裏をかいでしまう点ではおれにすごく似ている、とか思ってしまった。 あまり小説を読んだことないおれでも、その分厚さにも関わらずすぐに読めてしまうほど面白いと思えた。(11/12/22)
0投稿日: 2011.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ鎖国。この実に閉鎖的なシステムが、ある時日本に260年の長きにわたる泰平の世を築き、日本独特の美しく神秘的な文化を生み出しました。しかし、それにはどれほど残酷な犠牲があったことでしょうか。 藩命を帯びて遠くヨーロッパに渡り、やがて藩に捨てられた侍たちの物語です。
0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ宗教は万民に普遍的なものという勘違いを起こしている。 宗教は人によって全く違うものである。 日本人の宗教観が垣間見える作品 ぜひとも別の作品も読んでみようと思う。
0投稿日: 2011.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ感動の名作だと思う。侍は、藩主の命で、ローマ法皇に親書を渡すべく、メキシコ、スペイン、ローマと旅をするわけだが、その間に日本はキリシタン禁制の国に変わってしまう。政治や権力に翻弄される侍たちの心の葛藤の表現が素晴らしい。
0投稿日: 2011.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ支倉六右衛門(常長)をモデルにした小説. 慶長遣欧使節として,ドン•キホーテの時代のスペインや,バロックの都であったローマを訪れた日本人への興味があって読む. しかし,この小説では「訪れた」というよりは「無理やり行かされた」面を強調している.巻末の解説によれば,実際どのような旅であったかは,資料が少なくてはっきりしない部分が多いらしい.この小説では,ひたすら苦難の連続の旅として描かれている.静かな生活を望みながらも,政治に翻弄され,宗教に翻弄された人生である.
0投稿日: 2011.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ六年前から探していた本に似ていたため 読んでみた所、違いましたが とてもおもしろかったです。 普段はじっくり読んでいるつもりでも ぱらぱらと読んでいたり、きづいたら 飽きていますが、かなりじっくりと読んでいました。 話は、もやもやしますが 納得できる感じでした。 しかし最後の侍と西の描写はもう少し 見たかったです。 私は最後の解説に書いてあった 多くの日本人はこの小説を、魅力的な歴史冒険小説以上のものとしてはみていない というのがすごく、そうだ と思えました。
0投稿日: 2011.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ一昨日読了。丸一日かけて読んだが、そうすることができたのも、面白さ故だろう。 目の見えない存在を信仰する教徒たちの姿は、僕のような無神論者からすれば奇異に映る。いわば作中の長谷倉と似たような印象を持っており、決して彼らの事を嘲笑したりするつもりは無いが、「不思議」に思えて仕方がないのだ。 そういった意味で、日本人の無神論的考え方は江戸時代初期から今まで変わっていないのかもしれない。(仏教の問題はあるが、民間信仰はキリスト教的の信仰のそれとはまた少し違っているように思う) 長谷倉に共感しながら、とは言わぬが、理解のしやすさはあったように思う。 江戸時代初期を扱った作品であるがゆえ、やや難しい単語が羅列する。それでも、飽きるどころかページを捲る手が早まったのは、必要以上に「難しさ」を強調せず、本筋に多くの理解・想像の余地を残している描き方のお陰だろう。 エッセイを読んでいるとやや露骨に内容が重複することもあり(例えば、わたしが・棄てた・女。デパートの食堂で云々のくだりや、自己暗示など)、くどく感じることもあるが、概ね好みの文章だ。 しばしば周作の作品は、キリスト教をテーマとした云々と語られる。そういった面は確かにあるが、どちらかというと、「宗教の前における人間」あるいは、人間そのものを描くことに、彼の目的があったのではないかと考えている。宗教を扱った作品以外を併せて読むと、比較的多くの人がそう考えるのではないか。 この作品で色濃く表れていたのは、絶望だったように感じる。 文庫の裏表紙の紹介を読めばだいたいの内容は想像がつき、ある程度の先読みも可能ではあるが、それでも圧倒的なディティールを持って、迫力を生んでいる。 信じていたものに裏切られたときの虚しさと、それでも何かに縋ろうとする儚さに、煉瓦で頭を打たれたような衝撃が走った。
0投稿日: 2011.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログながい旅の物語である。 仙台の空の玄関、名取空港には支倉常長の「偉業」を称えるパネルがある。400年も前に、仙台からメキシコ、スペインを経てローマにまで渡り法王とも謁見を果たした。その彼の旅程が壁面一杯の世界地図に記されている。 「支倉焼き」なる菓子のメーカーは、製品名の由来となった彼の旅を「ロマン」と称えている。 だが、「偉業」でも「ロマン」でもありえない。 太平洋と大西洋を命懸けで越えヨーロッパにたどり着いた時、日本ではキリスト教徒の弾圧が一層激化していた。マドリードにもローマにもその知らせは届いている。そんな国と条約を結ぶほど世界の最先進国であった相手は間抜けではない。使節は決死の旅に出発した直後から、彼ら自身だけか知りえなかっただけで、失敗することがあらかじめ運命づけられていたのだ。 空しい悲劇の主人公が、苦しみ、耐え、そして裏切られ、なおも耐え忍んだ末の末、自分だけの本当の信仰に到達するまでの、長いながいこころの旅の物語に他ならない。 この物語をきっかけに、支倉常長ゆかりの場所や資料を漁った。 市立博物館には遺品が「国宝」として納められている。が、その扱い方はあまりにも粗略である。 数十億かけて建造されたと思しき、復元されたサンファン・バウテスタ号と巨大な展示場にも行った。面白くはあったが、主人公の悲劇の実相と深い苦悩は伝わりようもなかった。そもそも、この展示が根拠とする歴史の「定説」も数々の点で修正を迫られている。 史実という点においては、支倉常長と慶長遣欧使節に関する資料はあまりにも少なく、帰国後の常長の消息(彼の墓と称するものは3ヶ所もある)だとか、家康や政宗の意図がなんだったのかなど「闇」の部分が多い。 だが、背負わされた使命を全うすべく七年超にも渡る筆舌に尽くしがたい艱難のすえ彼が手にしたものは、報いどころか汚名であった。その悲劇だけは、史実としても物語のコアの部分としても揺ぎ無い真実である。 このどうしようもない空しさを理解することなしに、憧れたり称えたりしたとしても、報われることなく耐えて死んでいった六衛門常長への、鎮魂にはなりえない。 おそらくは自らも信仰の前で煩悶し、精神的艱難のすえ独自の信仰に到達された著者のみが、自らの精神史と重ね合わせたすえにのみ、物語として辿ることができた「こころの旅」の軌跡であろう。 私自身もそれなりに苦労をし、そして空しい結果に終わろうとしているこの8年間を、思わず重ね合わせてしまう。だが、遠藤先生や常長に比べたならばあまりにもちっぽけで取るに足らないものだ。 そもそも私には、私だけの「神」を見出すことはできていない。 私の旅はまだ途上、なのかも知れない。
0投稿日: 2011.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ引っ越しなんてできない。 偉い人には逆らえない。 人権なんてない。 時代の流れが人生に大きく影響する。 ありきたりだけど、なんて現在は自由なんだろう。 侍。 良い言葉。
0投稿日: 2011.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで読んだ本の中で、これが一番好きな作品です。主人公の侍が最後に老犬を比喩に出す箇所こそ、遠藤文学の集約では…と勝手に思っています。
0投稿日: 2011.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ数年前の出張時に買った本。重そうなので何となく手が出ないままでしたが、年末の帰省時に読んでみました。 「なんで俺が選ばれたの?」「こんなに頑張ったのにそれが褒美か!」「上の方針がさっぱり分からん」みたいな痛切な叫び。組織に属する者の悲哀が全編に満ちており、サラリーマン小説として秀逸な作品だと思いました。 『沈黙』はいつ読んでも面白いかもしれませんが、『侍』は社会人になって読む方がよいです。
0投稿日: 2011.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ中高とプロテスタントの学校で過ごしていて、割と身近にはあったキリスト教。しかし日本での信者は宗教の自由がある今でも1%にとどまるよう。 結局キリスト教の教えと日本に根付く価値観は相容れないのだと思う。 キリスト教・イエスこそ至上だと考え、日本での布教をすすめたい野心的な宣教師と、一藩からお役目としてスペインに渡ることになった「侍」たちが、各地の政(まつりごと)に翻弄される話。 実話がベースになっているようだ。 途中にでてくる「侍」のキリスト教に触れたときの感触や、別の宣教師による日本論など、おそらく随所に遠藤周作の意見が反映されてるように思う。 考えれば当たり前なのだが、この本を読むまで日本にキリスト教伝来 といえど、単に1つの宗教が来たわけではなく、様々な宗派が争い、前後して日本に来たという感覚を失っていた。 教皇の無謬性が失われ(弱まって?)て以降は常に政治の道具だったのだと、そして差異を示す方法のひとつであったのだと確認した。 単なる冒険物語にとどまらないストーリーはとても面白かったです。 おすすめ。 Dec 2010
0投稿日: 2010.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ宣教師はわたしみたいな人だった。 神さまのためにって歩んでるのに、それは自分の欲でしかない。 いっっっちばん印象にのこっているのは 「こんなインディアの中におられるイエスさまを信じているのです」 あの方が、一緒におられる。 イエスさまが、一緒におられる。 そのことが一番のこってる。
0投稿日: 2010.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ遠藤の小説の中でも『沈黙』とならんで衝撃的な内容だった。2000年前もその時代も、政治によって消されていく小さな人間の思い、信仰の力のなさをいたまずにいられない。しかしそれは無駄に流された血だったのか。いや、今の自分に昇るこの思いだけ、全くの無駄ではない。 09/5/29
0投稿日: 2009.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ今回もなかなかの作品。 支倉常長ってのが信長の野望にもちょろちょろ出てて、伊達政宗がスペインに使節を送り込んだ話ってのは知ってたんだけど、まさかこんな悲惨な結末を迎えていたとは…。この作品はその史実にしたがって作られた歴史小説らしい。 相変わらずの彼のキリスト教観です。沈黙で見たような、自信満ち溢れたパードレが打ちのめされてイエスにすがっていく感じと、諦めれ粛々と自らの運命を受け入れる日本人がイエスに救いを見出すってゆう、そんな感じ。それから日本と西洋の文化的背景の違いとかへの考察。
0投稿日: 2009.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログたった1冊の本の中にこんなにも壮大な世界が描かれていることに驚いた!太平洋を渡り、ローマ法王の所まで言ってしまうだなんて!
0投稿日: 2009.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ「侍」というタイトルなのだろう。 野望ある宣教師の方が目立ってしまって、侍というタイトルに最初違和感を感じた。 けれども、やはり「侍」である。 日本の侍ゆえの、イエスに対する考え。 悩み。 問い。 イエスとは、信仰とは何か、考えさせてくれる小説。
0投稿日: 2007.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が日本人であることを改めて考えさせられた。心打たれる場面がいくつもあり、最後のほうはとてもつらかった。読後はずどんと沈みこんでしばらくあがって来れなかった。 出会えてよかった本。ずっと心に残る一冊。 最近若い作家さんばかり読んでいたが、こういうのを読まないと駄目だなって思った。
0投稿日: 2007.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ日本人にキリスト教が浸透しないのか?宣教師“ベラスコ”と侍“長谷倉”を中心に、日本人の気質がものすごくリアルに客観的に書かれている作品。遠藤周作がまるで日本人じゃないかのように、日本人というものを分析しています。おもしろいよ
0投稿日: 2006.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ国を信じて異国に旅をして、ついには国に捨てられた侍の話。 最初は読みにくい…と思っていたけど、最後は涙・涙…
0投稿日: 2006.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人間の心のどこかには、生涯、共にいてくれるもの、裏切らぬもの、離れぬものを 求める願いがあるのだな」
0投稿日: 2005.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ田舎侍が、自らの運命に立ち向かうことなく、淡々と激流を流されていく姿が物悲しい。自分がないのね。遠藤周作では、海と毒薬がベスト。
0投稿日: 2004.10.15
