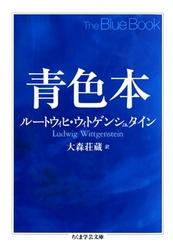
総合評価
(18件)| 1 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. ウィトゲンシュタインの哲学的アプローチ - 治療としての哲学: ウィトゲンシュタインは、哲学を理論構築ではなく、哲学的な困惑を解消するための治療として捉えている。 - 言語ゲーム: 言語は特定の活動に根ざしており、言葉の意味はそれが使われる文脈によって決まると強調されている。 2. 言語の使用と意味 - 自動詞的用法と他動詞的用法: 「期待する」などの言葉が持つ異なる用法を明確に区別し、それによって生じる哲学的困惑を解決する必要性を示している。 - 文法の重要性: 表現の文法を明確にすることで、哲学的な混乱を解消できると主張している。 3. 心的現象と表現 - 心的過程の理解: 思考や想像といった心的現象は、物理的現象と異なる独自の性質を持っているが、それを理解するためのモデルが必要である。 - 私的言語の問題: 他者とのコミュニケーションにおいて、個人的な経験や心的状態を言語化する難しさを強調している。 4. 認識と知識 - 知識の概念: 知識がどのように形成され、認識されるのかという点について、普遍的な定義を求めることの困難さを示している。 - 事実でない事態の考察: 思考対象が実現していない場合でも、事実でない事態を考える能力についての探求が行われている。 5. 哲学的困惑の解消 - 困惑の解剖: 哲学的な困惑がどのように生じるかを分析し、それを解消するためのアプローチを示唆している。 - 表現の曖昧さ: 言語の使用における曖昧さや誤解の原因を明確にし、理解を深める必要性を訴えている。 6. ウィトゲンシュタインの影響 - 哲学の変革: ウィトゲンシュタインの考え方が、哲学的な議論や言語観にどのように影響を与えているかを考察。 - 新しい哲学的方法: 「青色本」を通じて、ウィトゲンシュタインが学生に新しい哲学的アプローチを教えようとしたことが強調されている。 7. 具体的な例と応用 - 具体的な日常言語の使用: 実際のコミュニケーションにおいて、言語がどのように機能し、意味を形成するかに関する具体的な例が示されている。 - 日常的な表現の分析: 一般的な言葉の使い方が哲学的議論に与える影響についても考察されている。
0投稿日: 2025.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログわかったようなわからないようなという感じ。野矢茂樹の解説はよかった。彼の『言語哲学がはじまる』を読んでみようと思う。
0投稿日: 2024.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ冒頭で「語の意味とは何か」という問いがある通り、この本はその問いに対応する形で書かれている。また、著者はそれを示すと同時に、哲学することについて読者に示す。以下は私の理解である。 本書で繰り返し語られることに、「言葉を整備する」ことがあげられると思う。そして言葉を整備することが、語の意味とは何かを示し、哲学することなのだ。では語の意味とは何か。 語の意味とは、誰かによって与えられているものである。誰かとは、発話者のことである。そして、語の意味は厳密に示されるものではない。よって単語帳に載っている意味は、その語が蓋然的に示す意味であると考えられる。著者は、家族的類似性という概念を用いて語の意味がもつ性質を説明する。 哲学は、伝わらない言い回しで同語反復的に何らかの実体を明らかにすることではない。哲学することとは、その複雑怪奇な言い回しが何を意味しているかを明確にすることである。つまり、「意味」による微妙なすれ違いが、意味のどのような誤解によって起こっているのかを明らかにし、わからないことはわからないことを結論することである。 さらに、こうした語の意味がいくらでも可変である性質から、独我論へ展開する。独我論とは、A氏が何を示しているのかが私(B)にはわからなず、かつ私(B)が示していることも相手(A氏)にはわからない。よって見ているものは、常に私(BやA)であるという視座である。 以上が私の理解する所の一部である。日常的に感じる、話のすれ違い、また詩的表現などから、著者が言っていることはよくわかる。しかし、それを上手に説明するのはなかなか難しい。
12投稿日: 2024.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かに読みにくい本だが、ウィトゲンシュタインが事例として挙げる問題を自分なりに丹念に追いかけていくとそれらがけっして浮世離れした次元の話ではなく、むしろ私たちの住む平凡な日常とつながっていることがわかる。なぜ私の発する言葉が通じるのか。なぜ人の感覚を私たちは言葉を通したことで理解に至るのか。系統/筋道がはっきりせず、思ったことをつらつらと書きなぐっているような中身に辟易するのもわかる。しかし、別の言い方をすれば思索/思念の動きが実に生々しく捉えられる1冊でもあるとも思う。もっとゆっくり読むべき1冊なのかも
0投稿日: 2023.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ初期『論考』の「世界ー言語並行論」に基づく意味論的発想を離れ、中期の「文法」すなわち規則を重視する立場から後期『探求』の「言語ゲーム」への移行期における、ウィトゲンシュタイン(LW)の講義の口述録。ここではすでに「言語ゲーム」という言葉は表れているが、あくまで中期LWの特色である「文法」「ルール」に重きを置いた考察がなされており、後期のようにそこに我々の生活があって初めて実質が与えられる、という立場は取られていない。野矢茂樹氏の解説によれば、あくまで「文法」内での語の使用のされ方に焦点を当て「あてがわれるべきものと異なる文法を適用してしまうことにより生ずる我々の誤謬を治癒しよう」というのがここでのLWの狙いだという。 世界には数多の「文法」があり、そこでの語の使用は文法ごとに異なっており、恣意的ですらある。しかし語それ自体は共通して用いられることが多いため、我々は往々にして文法の適用を誤り混乱してしまう。LWは具体的な場面(有名な歯痛の例など)を挙げつつ、より混乱の少ない文法を提案するのだが、そもそもそのような混乱の根本にあるのは「一般名辞の意味を明確にするには全ての適用を通じて共通する要素を見つけねばならぬという考え」であるという。LWによればそのような要素は存在せず、あるのはただ語の使用によって付随的に浮かび上がってくる「家族的類似性」のみだというのだ。つまり語の意味というのは帰納的にしか把握できず、全ての語の意味を決定づける演繹の起点となるような「本質」など存在しないというのだ。確かにこの点からするとLWを論理実証主義者と呼びたくはなる。 後半はLWを論ずる上で避けて通ることのできない「独我論」。ここでもやはり基本となるのは「文法」であり、独我論的語りを可能にする(強いられる)のは「私的言語」、ただ自分の経験のみを表現することにのみ適した文法を有する言語なのだと論じられる。この私的言語は、指示対象と記号の対応関係がその発話主体にしか検証できないため、トートロジカルな無内容を必然的に含む。これが独我論的語りにまつわる違和感の正体だというのだが、どうやらその治癒方法までは本書では明らかにされないようである。
1投稿日: 2022.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ『論考』から『探求』に移行するまでの間に記されたWittgensteinの後期思想への入り口的な著作。Wittgensteinがケンブリッジ大学の少数の学生に口述した内容を元にしており、Wittgenstein自身の生々しい哲学的思考の軌跡をありありと見て取ることができる。 ここでのテーマは一貫して「語の意味とはなにか」ということであり、本は「語の意味とは何か」という文から始まる。ただ、この意味についての議論は、錯綜を極め、「望む」「期待する」「欲求する」という語を検討し始めたかと思うと、「知る」「推測する」という語について論じ始めるなど筋を追うのが難しい。本の最後は後期著作の大きなテーマとなっていた私的言語論の話題であり、「私は歯が痛い」という文を例にとり、独我論の論駁に費やされている。全体でいうと、前半は心の働きとされる諸概念にまつわる哲学的困惑について、後半は言語を通じた他我問題、独我論について論じている。 Wittgenstein自身のその解決法としては、日常言語の観察を主としている。日常での言葉の用法をつぶさに観察し、哲学的な用法での言い回しと日常言語との「文法」の相違に気付くことによって哲学的困難を解決しようとする。この本では、その実践をいやというほど目の当たりにできる。 後期の主要なテーマとなるアイデアが随所に現れており、「言語ゲーム」や「家族的類似性」「意味の使用説」(と我々が呼ぶ立場)、「意味の心像説批判」(と我々が呼ぶ立場)、規則順守のパラドックス、についてその思索の原型を眺めることができる。そして、この本では、これらの問題はすべてつながっていることを感じることができる。 ___________ ずっと読んでいると船酔いのような気持ち悪さがある。野矢茂樹の解説がなかったらちんぷんかんぷんで終わるだろう。むしろ、解説から読んだ方が良い。 だが、これをここまでの読める文章にした大森荘蔵はすごい。文中の訳者挿入にかなり助けられている。 Wittgensteinはいろいろあれがだめだ、これがだめだと言うけれども「本当にそうなのか?」という気持ちになる。これは私の理解がまだ生半可なのだろうが、「文法」が本当に異なっているのか? それを取り去ってもなお、哲学的困難は消えないのではないか? 意味については比喩や像を通すことによってしか得らず、把握できない意味があるのではないか? みたいな気持ち。何をそんなに目くじら立てて怒っているのかがよくわからない。細かいことをぐちゃぐちゃうるせえな、こいつは、みたいな気持ちにもなる。これは私に哲学をやるセンスがそもそもないかもしくは、この哲学的困難が私にとっては追求したいテーマではないのかもしれない、ということなのかもしれない。いや、「たしかにこいつの言うとおりだな」と思う箇所ももちろんあるのですが。赤色をイメージしろの話とか。規則順守の話とか。 というか、たびたび目にするWittgensteinから哲学的立場を取り出してはいけない、というのがやはりよくわからない。野矢自体は解説でそれは役に立つしありだと思う、って書いているがそもそもなぜだめなのかがよくわらかない。哲学的治療であることと哲学的立場を認定すること(表明すること?)は両立するのではないか?
0投稿日: 2020.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ巻末の野矢茂樹の解説がありがたい。まずこれを読んでから本編に挑戦。そして再度野矢の解説を読んだ。本編も何とか読み通せたし、ある程度理解できたように思う。本編を読んだことで得られた収穫は、ウィトゲンシュタインの思考の息遣いのようなものを感じ取れたことだろうか。粘り強く、というか、どちらかといえば執拗に思考実験を繰り返す。その様についていくのはなかなか大変だが、それだけに、ついていけたときには結構うれしい。内容的には、言語ゲームの序論といった感じ。
2投稿日: 2019.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログいやあ難しい! 他人の「歩み」をトレースすることは、ただでさえ難しい。 そこに「辿り手」の意思が介在する余地はなく、ただ、無心に轍を見つめ、辿るしかない。 その「轍」を付けた、先を歩む存在が、不出の天才哲学者であるのだから、ただでさえ難しいトレースは、凡人にとってほぼ困難なものであると言ってもいい。 けれど、そこについた轍の先には、なんとも言えない魅力がなみなみと湛えられている。 そこにたどり着くため、困難である道を文字通り這いずってでも辿りたいと、そう思わせてくれる。 はっきり言って、一読しただけではさっぱり解らない。 文字は目に映るだけで、脳へたどり着く前に滑り落ちていく。 理解なんて望むべくもない。 けれど、何度も繰り返して読んでいれば、きっと、いつか脳へと言葉は辿り着く。 そして、たどり着いた言葉が蓄積していけば、きっと理解する事すら出来るのだと思う。 末尾には、野矢氏による解説が掲載されている。 それは、理解へと読者を導く案内役となってくれるに違いない。 でも、ほんと難しい本だ・・・。
0投稿日: 2018.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 「語の意味とは何か」―本書はこの端的な問いかけから始まる。 ウィトゲンシュタインは、前期著作『論理哲学論考』の後、その根底においた言語観をみずから問い直す転回点を迎える。 青い表紙で綴じられていたために『青色本』と名付けられたこの講義録は、その過渡期のドラスティックな思想転回が凝縮した哲学的格闘の記録であり、後期著作『哲学探究』への序章としても読むことのできる極めて重要な著作である。 [ 目次 ] [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
0投稿日: 2014.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ文庫化の報を知って以来、気にはなっていたがやはり古書店ではそう簡単に見つからず、先日漸くブックオフにて入手した次第。大森荘蔵の訳に野矢茂樹の解説だと知っていれば、もっと早く買っていたかもしれない。ウィトゲンシュタインはかの有名な『論理哲学論考』しか読んだことがないが、時期的にも思想的にも大いなる断絶が認められるため、あまり連関はない。 ウィトゲンシュタインにとって哲学とは理論・学説の構築などではなく、哲学的困惑の解消・治療であるという点、大変に興味深かった。既に「家族的類似性」「言語ゲーム(のちの用法とは異なるらしいが)」といった後期哲学の重要タームが書かれていて、ウィトゲンシュタインが新たな"治療法"に乗り出していたことが判る。語りなくして治療なし。 あと訳文の「も少し」、これって大森先生の書き癖?
0投稿日: 2014.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人は,自分の言いたいことを,言葉で相手に伝えることは出来ない」 それが,論理哲学論考で私が読み取った(これさえも幻想かもしれないが)内容だった。 そしてこの青色本は,その理由を丁寧になぞっていくプロセスであったように思う。 私なりの理解では,人が言葉で伝えられない理由は以下の2つ。 ・スーツケースワード 単語の一つ一つの表す範囲が広く,また単語は文脈に依存するため,自分が「りんご」という単語をAという意味で使ったとしても,相手がBという意味で理解する可能性が否定出来ない。赤を赤だと認識するのは唯我であり,それを共有することは誰とも不可能である(高校生のときに同じことを考えていた)。 ・「私」の流動性 発話者である「私」の存在自体が,確固たるものではない。さっきまでりんごを食べたいと思っていたのが,すぐに「やっぱり珈琲が飲みたい」と変わることも珍しくはない。そんな流動的な自己であるならば,さっきと現在で同じ単語を発しているとしてもそれが同じ意味で使われているとは言い切れない。 禅で言う「以心伝心」「不立文字」であろう。 ”悟り”は言葉では伝えられない,という意味なのかと思っていたが,実はウィトゲンシュタインと同じく,「人は言葉で自分の言いたいことを相手に伝えられない」と言っているのかもしれない。 執着を嫌う仏教らしいといえば,いかにも仏教らしい。 それさえも,「君の論理空間では断言は出来ないことだ」とウィトゲンシュタインは嗤うだろうが。
0投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ後期ウィトゲンシュタインの思考の端緒。「語の意味とは使用である」という主張を掲げ、語の背後に何らかの実体を想定する本質探求を批判していく。語の意味は具体的実際的な語の使われ方にあるという考え方は今日様々な社会科学の基本的前提をなしているが、そうした「言語論的転回」の根源にあたる記念碑的著作。
1投稿日: 2012.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログヴィトゲンシュタインの中期作として捉えられるべき作品。 彼はあらゆる哲学的探求、会話は言葉ゲームであると云っているが、個人的には「そんなことを考えてどうするのか」と思わせるところも多い。 ただ、人であれば一度は考えることも多いし、「云われてみれば」と思わせるあたり、ヴィトゲンシュタイン哲学の魅力があるのだろう。私一個人としては、「そういう考え方を人もいる」程度のものでしかない。 彼の考え方に触れたのは、「他人の心を知ることはできるか」という箇所であるが、これは大学の講義で知ったことで、かつ彼の後期作「哲学探究」の中課から引用するものである。仮に「『リンゴ』や『歯痛』という単語が共有されている以上、どう表現しようとも、その言葉を把握している以上、他人の心を把握できているに違いない。」と。文理としては分からなくもない。 彼は語の定義に関する回答は、あらゆる例示によってのみ解消されるとする。しかしこれは、いままでのソクラテス的回答「しみじみと何かを語りつくす」ことに対する挑戦である。ただ、私も思うのは、哲学はそれによってあらゆる要素が混沌とし、難解にしてきたのも確かだ。分からなくもないが、20世紀初頭ですでにこの考えを主張する、というのも、哲学のいったんであろうけども・・・。 かのデカルトは、スコラ哲学に関して「その問い自体がなんであるかを考えないのか。」と云って修道院を抜け出したとされる。ヴィトゲンシュタインも、デカルト、ベーコン、カント...という近代哲学の系譜に対する「哲学的挑戦」をけしかけているのかもしれない。「語に対する探求」から「語を使うことによる探求」へと逆立ちさせたあたり、彼は俗的だが、云いえて妙な説を展開する。 読めば読むほど、「そんなことを云っても仕方ないだろう。話を振り出しに戻したいのか。」と云いたくなってくる。ただ、それはそう言わしめるくらい、哲学が複雑すぎることへの反発だ。
0投稿日: 2012.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画監督デレク・ジャーマンにエイズ患者の独白を青一色の画面で語り続けるという遺作『blue』は、この著作に捧げられたのだと思う。
0投稿日: 2011.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ何年もほったらかしていたウィトゲンシュタイン。久しぶりに読んでみたが、実に分かりやすくなっていたのにびっくりした。用語の使われ方の多様性。使われ方そのものが大事、、、という論旨は実にシンプルで説得力がある。なのに、なんでこういう回りくどい文章を書くの?ウィトゲンシュタイン先生。 僕も、「定義はできないけど例示はできる」という命題で文章を書いたことがあるので、しごく納得。それでよかったんだ。
1投稿日: 2011.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ腰巻きの「もっとも読みやすいウィトゲンシュタイン」というキャッチはあんまりではないかと思う。昔読んだときもそう思ったが、訳は大森荘蔵の思い入れが強すぎはしないだろうか?そしてもう一つ気になったこと。この本の冒頭に出てくる茶色本の保有者P.スラッファは、リカード全集の編者であり、経済学者として極めて著名なのだが、哲学の人たちはそのことを知っているのだろうか?ちょっと気になる。
0投稿日: 2011.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ全集版で持っているが、電車通勤の友として購入。お馴染みの議論であるが、ていねいに読むと何か発見があるかもしれない。
0投稿日: 2011.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログウィトゲンシュタインといえば懐かしい。『論理哲学論考』読んだのはもう20年位も前だったか。 で、この本を買ってみたのだが、あんまり面白くなかった・・・。 この「言語へのこだわり」が結局どこへ向かうのか、それが見えなかった。しかも、文章が体をなしていない。本の成立事情からやむをえないのだろうが、訳者が大量に補足を加えなければ意味が通じない文章。 ラッセル系の分析哲学なので、「言語」に関する省察も、ソシュールや構造言語学とはまるで関係がないように見える。 このスタンスは・・・自分には今回はちょっとなじめなかった。 ウィトゲンシュタインの『哲学探究』は抄訳しか持ってないので、完全版を読んでみたいな・・・。
1投稿日: 2010.12.01
