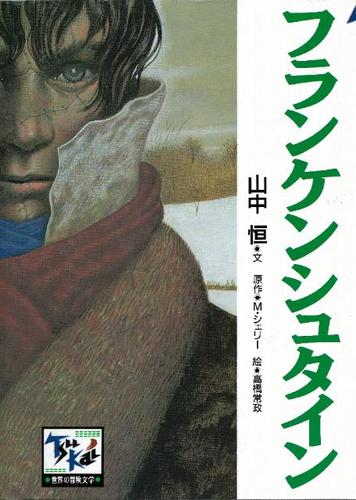
総合評価
(5件)| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
フランケンシュタイン=モンスターって思ってた でも実はフランケンシュタインはモンスターを作った博士の名前っていうのを初めて知り衝撃でした。 作った博士、作られたモンスター ある意味、親と子 切っても切れない絆 この物語の深いテーマなのかな? 博士とモンスター、似てるようで似てない、けどどこか通じ合ってる。 愛と憎しみが入り混じった関係って、すごく人間くさくて切ない。 しかも作者のメアリー・シェリーがこれを書いたのって、まだ10代だったってのも驚き… 「人はどこまで神の領域に踏み込んでいいのか」とか、「責任ってなに?」とか、めっちゃ考えさせられる作品。 クローンの羊を思い出した。 あれ、どこいった?? 作者自身の喪失と孤独、そして愛と死が入り混じった過酷な人生から生まれた作品 母(フェミニズムの先駆者メアリー・ウルストンクラフト)を出産直後に亡くし、 父とは距離があり、10代で詩人パーシー・シェリーと恋に落ちて、彼は既婚者。 世間に背を向け、駆け落ち。略奪婚。 愛を手に入れたようで、その代償はやはり重く、、、 子どもを4人産んで、3人を失うという心の砕けるような経験。 スイスのレマン湖のそばで 「誰が一番怖い物語を書けるか」というゲームから始まった、 『フランケンシュタイン』の執筆 ただのホラーじゃなく 命を生み出すとは何か?愛されなかった存在は何を思うのか?作った側の責任とは? 最終的に夫も失い、彼女は一人で息子を育てながら、作家として生きていく。 影には思い過去が詰まった話。
31投稿日: 2025.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生のミツヒロは電車の中で偶然岡村青年と知り合い、前世催眠を受けることになる。 ミツヒロが催眠中に話した前世の記憶は、何とフランケンシュタインが創造した「モンスター」だったんだよ!!な……、何だってえ~~~~~~!!! 録画テープは途中で途切れ、続きを知りたくなったミツヒロは図書館で『フランケンシュタイン』を借りてきて読む。 一日がかりで読破したミツヒロは自分の人間関係について考える。 家出した母親の本棚を見ていたミツヒロは、そこで衝撃的な事実を発見する!そこで明らかとなった前世催眠の真相とは……!!! 原作の翻訳は忠実なのですが、その前後に日本の少年の物語が入っています。 原作は ウォルトンーフランケンシュタインーモンスター という入れ子構造になっているのですが、本作品はその上にまた ミツヒロの前世催眠の語りーミツヒロの行動の同時進行(三人称体) という二つの構造が入っています。 なかなか面白い構成だと思います。 ただ、私としては最後に謎を引っ張るための語りが余りにも技巧的過ぎる・無理があるとも思うのですが、皆様はどう思われるでしょうか。 ともかく、古典文学の翻訳として面白い演出だと思います。 ところで本作には『フランケンシュタイン』の翻訳史に関して、日露戦争当時の真部鉄泉や小松原鉄泉・光次郎の話が出てきます。 彼らに関しては本作オリジナルの逸話なんでしょうか。 現実と非現実の境界があやふやで混然一体となった構造は原作『フランケンシュタイン』の構造とよく似合っています。 本書には巻末に風間賢二さんの解説が収録されています。 角川文庫(山本政喜訳版)の1994年の改版にも風間さんの解説があります。 同じ方が書いているだけあって、共通する記述も多い。 分かりやすい読みやすい文章で深い内容のことが書かれています。 児童書なのですが、本文から解説までなかなか充実した一冊ではないでしょうか。 20世紀少年少女SFクラブ 【フランケンシュタイン】の主題による変奏曲 その2 https://sfklubo.net/frankenstein2/
0投稿日: 2022.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「フランケンシュタイン」を読む日本人少年視点で展開する…って感じのシリーズ刊行ものだったらしいですね なるほど… 100分de名著でも思ったけど、フランケンシュタインて彼のことは有名?だけど、けっこう誤解があるっていうか、あんまり原作の内容は浸透してないよな…
0投稿日: 2021.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了直後はまた親・大人批判かと思い特に思うところはなかったのだが、たまたま合唱曲「怪獣のバラード」を聴いたところ、フランケンシュタインと重ね合わせ涙が出てきた。 フランケンシュタインの人造人間はただ人と交わりたい。言葉を交わし、誰かのために働き、暖かいご飯と寝床を得て、普通に生きていたい。ただそれだけ。なのに人々は彼の姿を見ただけで悲鳴をあげ出ていけと叫び暴力を振るう。暖かい笑顔を向けていた家族が彼に対しては怯える。 反してフランケンシュタイン博士の気持ちもよく分かるのだ。夢中になって人造人間を作成したものの、完成したのは醜い化け物。恐ろしく醜く、生命を弄んだ罪に今になって気付く。彼にとって人造人間は人間ではないのだ。ただ恐ろしい化け物で、畜生と同じなのだ。だから心を傷つけても罪悪感などないし、信頼もできない。できっこない。 人造人間は言う。親であるならばせめて愛を与えよ。もしくは仲間が欲しいと。人造人間にとっては本当に切実な願いだろう。彼は普通の人間と同じ生活を過ごしたいと願っており、それができないことを当たり前と思ってないのだ。それもそう、勝手に作り出されて放っておくとはどういう了見だ。 フランケンシュタイン博士にとってはそうではない。化け物を作ってしまったことは彼にとっては忘れたい過去であり、見たくない夢にまで恐怖で見るようなトラウマである。化け物が怖いという本能には逆らえない。意図して化け物を作成したのではないので、その覚悟のほどが違う。 しかして二人は鬼ごっこを続け、フランケンシュタイン博士が亡くなるまで執念は続いた。作られた化け物が人の心を持っていたから起こった悲劇なのだろう。単に人殺しをするだけであれば、フランケンシュタイン博士は人造人間と会話をすることもなかったろうし、人造人間は己について悩む必要もなかった。 思ったんだが「昔、酷い火傷を負ったので人に見られたくない」という理由で顔を隠して生きていくことはできなかったんだろうか。人造人間は自分でもぞっとすると言っているのだから、顔も受け入れてくれなきゃいやだ、ということはないのだろう。そうして必要な嘘をついて人に混じって生きていくことはできなかったのだろうか。その意味では人造人間は世の中を知らない子供だったのかな。 リーディングを挟むのは良い挑戦だった。フランケンシュタイン原作のみならずより物語を深く楽しめたと思う。 ライトノベルだとさらっと読み流すか、感情的に楽しかったあのキャラが可愛かったと思うことが多いけど、児童文学は考えさせられるね。
0投稿日: 2014.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ児童向けなようで字が大きくて読みやすいです。 第一部は著者のオリジナルストーリーが勧められており、 第二部から原作のストーリーが始まります。 ただ、フランケンシュタインのモンスターの話が 第一部で抜粋(正確には本書の主人公の台詞として出)されており、 第二部でその部分が重複するのを避けるためにか要約しかなく、 物語の最中もオリジナルストーリーの描写が入ったりと 純粋に原作を読みたい人には不向きかもしれません。 それがブレイクになって休み休み読めるのは利点かも。 オリジナルストーリーも子供が入りやすいものだと思います。
0投稿日: 2010.05.01
