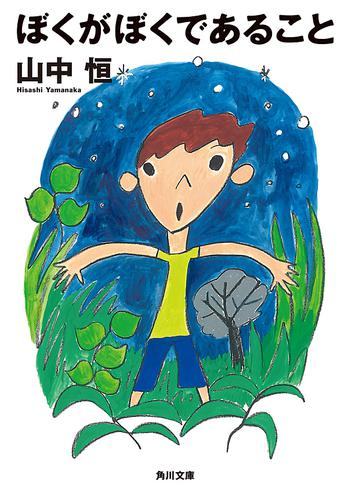
総合評価
(21件)| 8 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
小学校6年生の時に読んだ本を約25年ぶりに再読。 児童書であるが一気読み。多少は思い出補正もあるだろうが読ませる力量のある作家さんだと思った。 落ちこぼれの少年秀一が一夏の冒険で出会う少女夏代とその祖父との交流の中で成長する。 ひき逃げやら自宅全焼やら児童書にしてはなかなかショッキングな展開があるが、そんなシーンはすっかり記憶から消えており、なぜだか夏代の口から糸のようにおちるよだれと、手紙に“そして”が一か所もない夏代の文章に主人公が関心する場面だけが記憶に残っていた。妙な場面を覚えているものだ。 兄弟の中で出来が悪く落ちこぼれで母親や兄姉妹に言われるがまま、家出さえほとんど行き当たりばったりで決行してしまった秀一だが、家に戻ってからの秀一は自分の意志をしっかり持ち、自分で考え、必要な事を自ら学び、肝が据わった少年になっている。 時には社会科の知識で母親に反抗しておりなかなか小憎らしい。 一皮むけた秀一に比べ、秀一の母親初子は、事あるごとに口を出し非合理的でヒステリックに泣き喚き、どちらが子供かわからない。 しかし子が問題を起こせば寝込んでしまったり、我が子を助けようと炎の中でも果敢に飛び込もうとする。 家出から戻ってきた秀一を連れてご近所にお詫びに回るあたりも、きちんとした母親だ。 手紙を盗んだことしかり、我が子を無意識にも意識的にも支配しようとするのは、行き過ぎた心配と愛情から。 恐らくそのことに気が付いたであろう秀一が妹を許し、母親のもとへ向かうラストシーンがよかった。 本書は主人公の成長物語であるが、周囲の登場人物たちもまた主人公をきっかけにそれぞれに気付きを得ている。 子供は意思をもった個人であり、必ずしも親の思い通りにならないのだと初子が気が付くことができれば、母親として家族として成長できるのだろうと思う。 本書と『偽原始人(https://booklog.jp/item/1/4101168067 )』が小6の時のクラスの教室に置いてあった。 どちらも大人からの抑圧に抵抗する少年の物語だ。今思えば担任の先生の私物だったのだろう。 2冊とも耳にボールペンだったり煙草だったりを挟む描写が出てくるのだが、今ではすっかり見なくなった光景だとしみじみ。
0投稿日: 2025.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書は学研「小学六年の学習」で昭和42年に連載された作品がベースとなった児童文学作品です。主人公は夏休みに家出した小学6年生の成長ぶりをリアルな親子の関係性を軸に綴られていく、およそ児童文学らしくない硬派な内容が特徴です。 5人兄弟の中で唯一無気力で要領の悪い秀一は、事ある毎に母親から叱られる。2人の兄と姉は優等生で、妹は毎度母親に告げ口のご注進。そんな秀一がプチ家出をきっかけに少しづつ大人になっていき、一見平和だった家庭に亀裂が…。 解説の尾崎秀樹氏「作者は本書で、現代の家庭教育のあり方を批判すると同時に、子供が子供であることの意味を探り、その問題を読者に投げかけている」 出来れば、親子で読むべき秀作です。ヘタウマな挿し絵は永田力氏。
2投稿日: 2024.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに読んで面白かった。ゲーム機やPCやスマホが無い時代の日常を今の若い世代は想像出来るかな?と感じた。
2投稿日: 2023.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和44年の作品ということだったが、展開が始まってからは(最初の主人公がどういう少年かというくだりがやや長い)どんどん話が繰り出されていき、面白く読めた。ただ、女は家事、男は稼ぎみたいな昔のテンプレート的な設定や会話は多く、そのあたりを今の子がどう受け止めるかは不明。 五人兄弟(!)の下から二番目、小六の秀一は名前はりっぱだが、成績などイマイチ振るわず、兄弟姉妹の中でいつも駄目だと母親に言われ続けている。他の兄弟は皆、良くできる。 あまりにも怒られるので、夏休みに家出を試みる秀一。もちろん計画性もなにもない(アホなので)。このへんまでは読んでいてもあまり楽しくない。 しかし、飛び乗ったトラックがなんと交通事故を起こして、秀一は密やかな目撃者となり…。 つばさ文庫になっているのが、どの程度手を入れたのか気になる。挿絵だけでも、少し昔の感じだせばかなり読みやすいかもしれない。
2投稿日: 2022.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ眠くなるために読み始めたのに読破してしまった。大学の授業も教授も大嫌いだったけど、強制的に買わされた本がこんなにおもしろいとは思わなかった。もっとおすすめの本を聞いておけばよかったと後悔する一冊。
0投稿日: 2020.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ夏休みのある日、小学校六年生の秀一が突然家出をした。その波紋は、静かに深く広がって激しく家庭をゆさぶった。家出先で出くわしたさまざまな出来事−−−ひきにげ殺人事件の目撃、武田信玄の隠し財宝の秘密、発行の少女夏代との出会いなど−−−が微妙に絡みあって、教育ママの母親や優等生の兄妹の重圧から彼を解放する。 家庭が持つ強さともろさの二面性を児童文学の中にみごとに描き、読み物としても抜群におもしろい話題作。 ----- 夏代のキャラクター、特に最後の祖父との会話がグー。 過去ではなく今が大事(リアル)という夏代のセリフがいい。さすが山中恒、子どもにこういうことを言わせてしまうところがとてもいい。模範的な児童文学にはなかなかできない芸当である。ジェネレーションギャップがテーマ。上記の部分にもつながっている。子どもが自分たちの今を主張。その意味では「ノーライフキング」とも通じるところがある。 活き活きとしたストーリー・文体。秀一が手紙を盗まれたことを知り吐くところがよい。
0投稿日: 2018.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい迫力。権力と生きることを誠実に、またギリギリまで問うた人にしか書けない物語。20年前に一度読んでいるのだが、すっかり内容を忘れていた。情けない。しかし、私も辛苦を嘗めて、やっと本書を読めるようになったのかもしれない。子どもの視点の凄さを思い知った。
0投稿日: 2014.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ親と子達の物語。 母親を嫌うようになった子供たちの様子が描かれいるけどこんな小学生いるか?と思ったが境遇によってはいるのかもしれない。作者が子供の時に体験した事を文章にしたらこうなるのか...言葉が大人ぽっくて小学生に思えなかったが、作品の時代背景や戦国時代についてふれている関係なのかな。 家出をモチーフに親と子の関係をうまく物語りに取り込んでいました。さすが児童文学の最高傑作で考えさせられました。そして正直に面白かったです。
0投稿日: 2014.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
児童文学の最高傑作。何度でも読みたい。私が大人になってから理解した「私は私であること」がこんなにも分かるように描かれている。 5人兄弟の中で一人だけ出来が悪いと毎日小言を聞かされている秀一が、夏休みの十数日間の家出を経て「僕」の自由は誰にも侵せないことを知り、教育ママの城が崩壊するまでの話。読み始めは、母にガミガミ叱りつけられ妹に告げ口され、学校では廊下に立たされと萎縮してしまいそうな主人公・秀一に共感した。成績が悪いと言っては一時間も小言を聞かされ、隠したテストを見つけられては他の兄弟と比較され、兄弟にはバカにされ、母親の行き過ぎた教育ママぶりに友達もできない。本当に秀一を勉強ができるようにさせたいのなら、誰かが勉強を見るようにさせたり他の兄弟と比べることをやめて彼が前進したら褒めたり、秀一のペースに合わせて行動を起こすべきだろう。なのに一方的に叱りつけ感情をぶつけるだけで、これでは秀一がくさるのも当たり前だ。 そんな秀一も夏休みにどことも知れない田舎の家に泊まることで変わってくる。いや、変わったのでなく、元々の秀一の性が出てきたのだろう。嘘をつきたくない、お礼はきちんとする、これらは秀一から自然に出てきたものだ。 そうして清涼になり自宅に戻った秀一を待っていたのはいつもの母と、世界の見方の変わった自分だった。そう、母は理不尽である。誰も自分の自由を縛ることはできない。あれだけ疎ましく感じていた妹も動物園のサルのように感じる。母は哀れだ。 他の兄弟も母を疎んでいることが分かり、母の牙城は崩壊する。本当に家出から戻ってからの世界の見え方の移り変わりが見事。環境は何も変わっていない。ただひとつ、「僕が僕であること」。昔の出来事は関係ない。子供にとっては今が全てなのだ。大人だからと言って子供を好きなようにしていい訳ではない。私は私、あなたはあなた、私とあなたは違う。そんな当たり前だけどはまってしまうと抜け出すのが難しいことを秀一と夏代は知る、知っている。同じ人間ではないからしたいことも違うし、衝突するかもしれない。でもそれがごくごく当たり前のことなのだ。 本との出会いは縁である。この本に出会えて良かった。解説で紹介されていた本を次は読みたいと思う。 本当にこの本は心が洗われる。子供の頃に出会い繰り返し読みたかった。今読んでも遅いという意味ではなく、それだけ確かなものを残す本だから。
1投稿日: 2014.01.06教育ママから家出する小学6年生の冒険
山中恒、あばらはっちゃくの作者、「ビュワーンビュワーン」はしれちょうとっきゅうの作詞など有名です。 ぼくがぼくであることは、中学のころ、何度も何度も読み返した、お気に入りの一冊です。山中恒の児童よみもの作家っぽい書き口は、あまり馴染めなかったけれど、この一冊ははまりました。 教育ママとその手先の妹、優秀な兄たちのいる家を出て、たどり着いた田舎で目撃するひき逃げ事件、受け入れてくれる田舎の家。子供にとって唯一絶対な家を出て、他に行く場所があるということで、主人公秀一の気持ちや考えはすっかり変わります。 映画転校生の原作となった「おれがあいつであいつがおれで」よりも、この一冊こそが、ぼくの捨てられない百冊に含まれています。
1投稿日: 2013.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなく手にとって読んでみたら、主人公は小6の男子。 ちょっと反抗期。 うるさい母親。 なんとも自分の境遇に似ている・・・。 読めば読むほど、母親が鬱陶しい。 私が読み終わった後、小6の息子が読み始めたので、 「この母親、ママとかぶる?」と聞いてみたら、やはり「すごーくかぶる」とのことで。 普段の自分を大いに反省するきっかけとなった良い1冊でした。 すごく前の作品とは思えない今読んで共感できる本でした。
0投稿日: 2012.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
子供向けの読み物と思って油断した。 兄弟の中で、ひとり、出来が悪いと母に毎日小言を言われる主人公、秀一。兄の良一、優一、姉の稔美、妹のマユミ。ほかの兄弟は、成績もよく、母の小言を言われる事がない為、秀一だけが一人、母の小言を受ける事になる。 この本が書かれた当時の時代背景が、今とは違うから、「全学連」などという耳慣れない言葉も出てきて、少々分かりづらい部分もあるけれど、この本の世界に引き込まれる。 妹のマユミの告げ口から、母との言いあいになり、軽い気持ちでした家出が大きな事件になり…。 ここまでめちゃくちゃな母親はないだろう、と思いながらも、これに近い母親はきっといるだろうと思う。 この母親がしたこと(秀一宛ての手紙を勝手に読んだり、秀一が受け取れないような細工をしたり、秀一が出した手紙を盗んだり)は、今の時代なら子供の人権を踏みにじる行為として完全に非難されることだろうし、あんな結末にはならないんじゃないかと思う。 母親は子供から訴えられてもしょうがない行為をしているし、この本が書かれた時代だから、こんな母親でも、ある程度容認されてしまっているけど、今なら絶対に許されない。 で、最後まで読んでいった時に、もしかして私、この本を子供の頃に読んだかも知れないと思った。 たぶん、この本を読んだ時に、「親の言う事を聞く事」が正しいという考えは間違ってると思って、各家々に、法律のように決まりを作ればいいのにと考えた気がする。 そうすれば、親が間違った事をしたり言ったりしたら、親も子供に謝らなければならなくなるし、子供が親に対して、言ってる事や、やってる事に矛盾があると思った時に、はっきりと言う事が出来る。 親は親であるから正しいのではなくて、親でも間違う事はあるし、その時は、相手が子供でも謝らなくちゃダメだよな、と子供ながらに思った。 そして今、私は親になっているけど、あの頃の、子供の頃のに抱いた気持ちを、忘れずにいるかというと、忘れてはいないけれど、実行できているかというとそうでもなくて。 親でも子供に謝るべき時は謝らなくちゃならないけど、年を取ると、素直になれなくなる。変なプライドが高くなったり。でも、気をつけなくちゃ。 時代背景が違うから、今の時代ならとても考えられないほどの酷い事をした母親でも、最終的には家族から受け入れられて、家族が再生していくことを示唆したようなラストになっているけれど、今の時代に同じような設定でストーリーを書いたなら、最後は、母親は自分のした事の報いで、家族から見捨てられてもしょうがないんじゃないかと思った。 この本が書かれた時代に、ここまで酷い母親が存在したのかどうかは分からないけれど、「親の言う事は絶対」という考えの親が存在したであろうとは思う。 今は親と子が、友達のようなフレンドリーな関係になっているから、このような親子関係は考えられないし、そういう親子関係を異常と感じるけれど。 読み始めの、冒険ものかなにかかな、という軽い気持ちが、読み終わった時には、色々な思いが渦巻いていた。 親になって読むと、また子供の頃に感じた思いとは違う思いを抱く。 子供は、これを読んで何を感じるのかなぁ。
0投稿日: 2012.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ児童文学の名作といはれてゐます。 学生時代に友人から薦められて購買だけはしたのですが、私は本については頑なに自分で選ぶのが好きで、人から推薦されるのはあまり読まない。それでそのまま放つてゐました。 で、最近本棚があまりに汚いので少し整理してゐたら、本書を再発見、何気なく読み始め、そのまま最後まで読了してしまつた。 主人公の平田秀一くんは小学6年生、5人兄弟の下から2番目であります。優秀な(と母親が思う)他の姉や兄、妹に比べて、秀一は1人出来が悪いといふことでお母さんに怒られてばかり。 話の弾みで家出をする羽目になりますが、それをきつかけに、とんでもない事に巻き込まれていくのでした... 少年向けなので、登場人物の性格付けも極端にはつきりと描いてゐます。特に母親は戯画化が激しい。かと言つて有り得ない設定かといふと、発表当時の世相を考へますと、この母親はいかにも実在しさうな感じを与へます。兄弟姉妹の中でも、出来の良い子供とさうでない子供に対する対応が明らかに違ふ親は珍しくなかつた。 もちろん親のいふ「出来の良い子」は、学校の勉強が良く出来て親や先生の言うことを良く聞く子供で、その逆は悪い子なのでありました。 家族の問題を通じて、自分とは何かを探す少年を描いてゐるのですが、まあそんなことはどうでもよろしい。もしこの本を大人が子供に与へるならば、余計なことを何も言はずに渡して欲しいですね。 何しろ読み物として、まことに面白く出来てゐます。一気に物語の世界に引きずり込む力を持つてゐます。さうして『ぼくがぼくであること』を読んだ少年は、必ず自力で次の本を選ぶことでせう。 http://genjigawakusin.blog10.fc2.com/blog-entry-39.html
0投稿日: 2011.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
すごい。これが児童文学か?小6の子供が主人公なだけで、ただの児童向け読み物とは思えず。「常識や慣習といった束縛にとらわれず、自分の頭で考えてみよう。そのために、外の世界に目を向けよう」という思いがある。 ラスト、自分の家が燃えたのにも関わらず感じてしまうすがすがしさは、やはり今までの束縛が壊れだしたからだろう。結局のところ、何も問題は解決していない(解決しそうな気配はあるけれど)。それでも前向きな気持ちになるのは、自分の頭で考えだした人が行動を始め、今までの束縛から逃れだしたからだ。
1投稿日: 2011.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ親への反発、親への服従は大なり小なり皆、通ってきたことだと思います。親の子どもに対する期待や愛し方も十人十色。秀一のおふくろさんも子を愛し思う故であるのだろうが、この歯車の合わなさもよくある事で…。 一時,家を離れ生活するうちに、いろんな事々を通して客観的に自分や周りを視ることが出来たとき、「自分が自分であること」を周りにわかってもらおうと立ち返る。秀一のそんな心と身体の成長をハラハラしながら読める一冊。 ひとりひとりがかけがえのない存在。「ぼくがぼくであり」「あなたがあなたである」人と人がうまく噛み合っていく世の中である事を願う。
0投稿日: 2011.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初は文章が古臭いし、主人公の魅力ゼロで読むのをやめようかと思ったほど。でも、公園で寝ていた男のトラックの荷台に潜り込んで家出してから急に物語が生き生きと動き出した。殺人事件、世話になった家の秘密、武田信玄の財宝と、結局最後まで読んでしまった(笑)
0投稿日: 2011.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学6年の息子が読んで、よかったよというので、借りて読んだ。 この本で言っていることの趣旨は、よく分かる。 一人ひとりの人生がある、そして、にも関わらず、大人はときどき自分の勝手で何かを押しつける。 こういう永遠に思えるテーマの他に、時代背景も感じた。 戦争を経験した夏代のおじいさん。そのときは、日本が混乱していたから、心の傷を負った人もたくさんいただろう、そして、その傷はずーっと抱えたままのことが多かっただろう。 学生運動。大人の不正に立ち向かおうという機運の中で、それぞれの思いがあったようだ。 作者の山中 亘さんは、「あばれはっちゃく」も書いたそうだ。 子供のころ、テレビでやっているのを見ていた気がする。
0投稿日: 2011.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ夏休みに家出をする少6の秀一。初めは子供向けかと思っていたが、その家出がいろいろな事件に遭遇する事に。そして秀一を強くしていき、周りの事もよく見えるようになる。大人でも十分楽しめる。
0投稿日: 2011.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生の時涙流して読んだ本 たまたま文庫化されてたのを発見 改めて読んだが、いい本 泣かなかったけど
0投稿日: 2008.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ山中恒のぼくがぼくであることを読みました。私が小学生だった頃、学校で「6年の学習」というような雑誌を売っていました。私もそれを購読していたのですが、「学習」の付録に小説がついていて、それを読んでとても感動したことを記憶していました。たまたま古本屋でその小説を再度見かけたので、つい買ってきて読んでしまいましたが、やはり面白く読めました。ここで描かれている母親のイメージは確かにステレオタイプなのですが、子供の頃に見上げる形で読んだときと現在横から眺める形で読んだときでは受ける印象もちょっと違っているのかなあ、とか思いながら読んでいました。
0投稿日: 2004.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ1995/大人はクズ。子供は自分の正義に従って行動せよ!と言う、宗田理みたいなノリの作品。これ読んでも結局家出なんかしなかったからな。母親に勧められて読んでは見たが、
0投稿日: 1995.08.10
