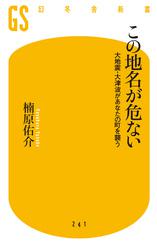
総合評価
(16件)| 0 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ地名には土地の記憶が刻まれている。「田代」は水田の端、「蛇ノ口」は洪水の流れ口。先人は自然の脅威を名に託し後の世へ警告した。しかし開発が地形を変え由来を忘れた町は看板だけを残す。津波の到達点も土砂崩れの常襲地も字名をたどれば見えてくる。古い地図と地名に耳を澄ませば未来を守る知恵がそこにある。地名が防災になり得る。
0投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ日の目を見ない老齢科学者の研究日誌。ばらーーーっと床に散らかしたこまごまとした発見を部屋の隅に寄せてまとめたような一冊。著者が置かれている現在の不遇をなじるような場面もあり、半ば厭世的にあらゆるものを批判して快感を得て自尊心を満たしている。 確かに地名から得る教訓はあるだろうし、著者の唱える説には正解も多いのだと思う。ただ「地震は活断層関係なく全国どこで起きても不思議ではない」と警鐘を鳴らしてしまっている以上、過去に全国各地で地震は起こっていたはずで、そうなれば全国のあらゆる地名は著者によって忌むべき地名にこねくり回されてしまいかねない。つまり、こじつけ臭がすごい。 研究でお金をもらって生きていこうとしたら市井の人々の為になる成果を引っ提げていかないといけないわけだけど、我々にダイレクトに訴えかけるにしてはまだまだ自我が強いと言うか、これをもっともっと噛み砕いて分かりやすくしたらまたちょっと印象が違うのかもな。あと分量が多くて読みきれない。序盤の津波のこととかいいこと言ってるのに、ボリュームの多さに辟易してしまって…
0投稿日: 2021.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ●地名というのは先人からの警告だというのは納得だが、いかんせん著者の推測も多分に含まれるところも多く、こじつけではないかという反論も少なからず湧いた。
0投稿日: 2018.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ平成の大合併という市町村合併の是非を問うようなことはおいといて。 思いがけない地名の変遷に驚きがいっぱい。 ただ、内容的に、評価はわかれるところもあるかな。
1投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔からある地名には、さまざまな意味が込められている。 中には、地震や津波など、過去の自然災害の影響を反映した地名もあるので、むやみやたらに変えるべきではない。 といった主張をしています。 推論もたくさんあるので、すべてが正しいわけではないですが、著者の論には、参考にすべきところがたくさんあります。 ちなみに、著者は、僕と同じく岡山県出身。 岡山県の地名のネタもたくさんあったので、興味をもって読み進めることができました。 地名に関する本を読んだのは、これが初めてですが、たまにはこういう本を読むのもいいですね。
0投稿日: 2017.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ○日本の地名とその由来となっている地形や災害リスクを紹介(推察)したもの。 ○結構強引な推論もあるが、総じて面白かった。
0投稿日: 2015.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ先の東日本大震災を契機に、各地の地名を過去の災害から読み解こうとしたもの。 地震や津波、洪水などの被害からネーミングされたであろう地名の紹介からその根拠など、独自の論を展開している。地名を言語学的に分析して災害の痕跡を見つけ出しているところはなかなか面白いと思った。昔の地名を分析することによって、その当時の人々が後世に何を伝えようとしたかわかるという主張には頷ける。市町村合併などで新しい名称が必要になっても、なるべく歴史的地名を残すようにすべきだという意見には賛同する。 ただ自説を主張するあまり、既存の説を頭ごなしに貶す論調はいただけないと感じた。他のレビューにもあるが、こじつけではないかと思われたり、煽動的なところがあったりで、最後まで読む意欲を失った。
1投稿日: 2014.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際の地図などを見ながら、分析している。宮城県在住の身にとっては、名取市の地名や津波浸水について、きちんと記載されていたことだけでも、この本を手にして良かったと思う。 私事だが、定年後は東京近辺に住むことも検討しているが、この本を読む限りは、埼玉県に在住したほうが地震のリスクが少ないのかもな。
0投稿日: 2013.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ【蔵書案内】坂東市の図書館:危機感を持つためにオススメするわけではありません。地名は祖先からのメッセージでもあるわけで。市町村合併などによって古くから親しまれている地名が消えていくのが、惜しい気がしました。
0投稿日: 2013.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ地理の知識が浅い私にとって、なかなか難しい本だった。最初はなるほどと思いながら読み進めていたが、後半になるにつれてこじつけ感が強くなっていくような気はした。
1投稿日: 2012.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ内地に住むようになってから「~台」と付く地名は高台にあるなど意味があるんだなと思うようになってきたので題名につられて読んでみた。「桜島」は「裂く」から、「灘」は「な(土地)がたれる(崩れる)」からという意味からとは知らなかった。最初のうちは「へぇ~そうなんだ~」と思いながら読んでいたのだが、あまりにも色々なところがとりあげられているのを読むうちにだんだんこじつけも多いんじゃ?と思うようになってしまった。これはわたしが地理、地形がよくわかってないせいかな?
0投稿日: 2012.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・桜島 裂けて溶岩と火山灰を噴き出す・裂くら あおっている割に内容が深くないようなところもあったため、流し読み。
1投稿日: 2012.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ後からなら、言えるよな、っていう気持ちと、でも、ここでちゃんと認識しておくことも大切、っていう気持ちになった一冊。合併で消えてしまった町村・地域名に意味があるかもしれません。
0投稿日: 2012.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨日(2012年3月17日)東武伊勢崎線の業平橋駅が「スカイツリー駅」になりました。地名が変わったわけではありませんが、由緒ある名前が一つ消えていくのは寂しい気持です。平成の市町村合併で名称が変わった町等も多いと思いますが、数百年にもわたって使われてきた名前には多くの歴史が刻みこまれていることでしょう。 特に何度も地震や津波、台風などの被害に遭ってきた地域には、それを示す名称がつけられていて、近くに住んでいる人たちはそれを認識して(覚悟して)住んでいたのではないでしょうか。ところが最近の宅地開発の影響で、その地名が変更されている箇所があり、昨年の大震災時に思いがけない(と思われていた)場所で液状化現象が起きたのも、その土地の昔の状態に起因していたと思います。 先日見たTV番組では、今後調査することで「ハザードマップ」を作成するとのことでしたが、昔の地図を地名入りで公開するだけでも、その目的には合うのではないでしょうか。それによって不都合を感じる人や企業もあると思いますが。この本を読んで以上のようなことを考えさせられました。 この本を読んで気づいた事実ですが、東京湾央で何度も地震が起きている事実で、関東大震災の後にもM7程度の地震が起きていることでした(p246)、道理で昨年の震災以降に何度も小規模ながら東京湾央で地震が起きていたのですね。 以下は気になったポイントです。 ・陸前・陸中・陸奥を総称した三陸と呼んだのは、明治29年(1896)6/5の、岩手県沖でM8.25で発生した地震において発生した津波が「三陸地震津波」と採用されたことに始まる(p26) ・関東大震災時には、横浜市はじめ東京湾岸から相模湾岸にかけて津波が来襲、津波の高さは熱海で12メートルを記録(p30) ・今回津波の被害を受けた浪江町一帯はかつて津波が作った潮入りの湖沼の跡だったと思われる(p44) ・蔵や倉は、動詞クルが名詞化した語で「地面がえぐられたような地形」に使われたケースが殆ど福島第二原発の立地している地籍:波倉は危険な地名(p45) ・鎌倉という地名は倉庫にも蔵屋敷にも関係ない、関東大震災の津波に何度も襲わて続けて作られた釜状の穴倉である(p48) ・鎌倉大仏は初めは木造仏として高徳院境内に建立されたが、のち大風のため破損して、1252から金銅仏として改鋳、室町時代の1498に大地震で大仏殿が倒壊、津波で流されたため今日に至る(p51) ・日本の河川名は、一級(国土交通省)、二級(都道府県)、準用(市町村)、の他に河川法適用外の普通河川に四分される(p57) ・台帳記載以外の田を「余田」という、これが公認されると加納あるいは、加納余田、加納田と呼ばれる(p66) ・宮城県女川、福島県いわき市小名浜のオナ(ヲナ)は、雄(男)波のヲ・ナミを下略して津波を「ヲナ」と呼んだ名残と思われる(p79) ・幕藩時代には市街地を守るため農村部を犠牲にする施策はいくつもある、小名木川東端の西葛西領、東葛西領等、江戸では浅草の北西、山谷堀の南西側の日本堤など(p89) ・関東大震災でも、「品川湾に海嘯、隅田川は逆流」という新聞報道あり、東京湾内でもM6.5-7クラスの地震及び津波が発生している(p91) ・寛政3年旧暦8月の地震では江戸深川一帯が津波に襲われ、洲崎弁天社周辺が水浸しになり、幕府は付近の家屋建築を禁止して、両脇に津波警告の石碑を建てた、これは関東大震災・東京大空襲で損傷したので、現在は洲崎神社内に建てられている(p93) ・芋は古くは「ウモ」と発音された、そのウモとは「地中に埋もれた」という意味に他ならない(p128) ・昭和55年(1980)8月14日、富士山近くの久須志ヶ岳から大岩が二度にわたり剥離・落下して夏富士登山で賑わう吉田口砂走り下山道を直撃して、死者12名、負傷者32名という大惨事が起きた(p162) ・江戸前期から酒造業で盛んになった「灘五郷」は、東から、今津郷・西宮郷・東郷・中郷・西郷である(p170) ・関東大震災の被害は都市の規模に比例してではなく、神奈川県下一円のほうがはるかに大きかったということが調査でわかった(p211,213) ・関東大震災の本震が起きたすぐ後に、神奈川県横須賀市沖でM6.6、東京湾央でM7の地震が起きていたことは殆ど知られていない(p246) 2012年3月18日作成
0投稿日: 2012.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現在の地名は災害の名残でつけられたものと指摘し、その土地の危険性を喚起する本。発想はいいが、軽々しく言い過ぎだと思った。 例えば「名取」は、古語で「ナ=土地、地盤」「トリ=災害で土地が削り取られた地」という。そっか、納得!と最初は思ったが、この調子であれもこれも列挙されると、日本中の地名は災害の記憶を留めるためにつけられたことになってしまい、疑いを隠せない。 地名とは、「一本松」とか「富士見ヶ丘」とか、その場所のランドマーク的なものにちなんでつけられる場合が多い気がする。第一、災害の記憶が込められているなら、もっと「死」などネガティブな名前が多い気もするのだ。 論拠も今、取っている最中の様子で、出版はまだ早かったのではと思ってしまった。論が偏っており扇動的だったので、すっと入ってこなかった。
1投稿日: 2012.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
地名の由来を地震や洪水などの被害に対する記憶と言う。 妥当性の高い話も見受けられるが、如何せん肩に力が 入りすぎているきらいがある。 著者が、「すべての地名をアイヌ語源で説くことにはおかしい」 と主張しているが、 私は、「すべての地名を地震・洪水被害で説くことはおかしい」 と言っておきたい。
0投稿日: 2012.01.14
