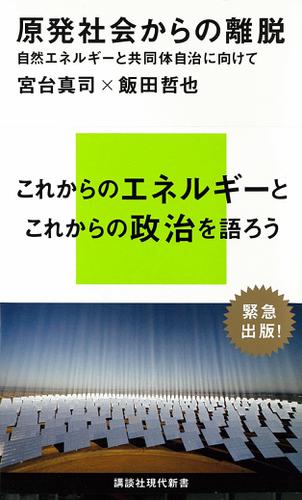
総合評価
(45件)| 11 | ||
| 21 | ||
| 6 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ日本が原発推進から軌道修正できないのか。明らかに文化的、組織的問題、国民的問題。エネルギーや技術の問題ではない。ただ、この霞ヶ関が変わらない一旦が日本の政治の問題でもあり、国民の意識と 行動の結果であることは目を背けられない。3/11の直後に流れを作りたくて発刊していることがすごい。にも関わらず、日本は変わらなかったことが悔しい…
0投稿日: 2023.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「原発を止めた裁判長」というドキュメンタリー映画を見た。 裁判長の本も読んだが、その中に登場する技術者・飯田哲也氏のことを知りたくて手に取った一冊。 https://saibancho-movie.com/
0投稿日: 2022.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ悪い心の習慣を私たちは排除できるか。 それができなければ、私たちの社会は安定化せずに、滅びていくだろう。
0投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮台さんと、飯田さんの知識が、どうやって原発に向かっていくのか、わくわくしながら読了。2人の生きてきた背景と、そこに結びつく経験と知識が、直接原発について語られなくても、浮き上がってくるのが面白い。
0投稿日: 2017.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常におもしろかった。我々が知らない画期的な自然エネルギーについての話がたくさんあってとても勉強になる。飯田さんの豊富な知識もさることながら宮台氏の鋭い考察も読んでいて唸らされる。なぜもっと早く読んでおかなかったんだろう?
0投稿日: 2015.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発社会からの具体的な離脱論の展開を期待したが、いささか内容が飛びすぎる。どちらかと言えば国策批判、官僚批判がメイン。 「貧しくならない省エネ」という考え方には同意。ただし30万円する薪ストーブを「普通の人」が買うかどうかはちょっと疑問。 「生活をいちいち反省しなくてもいいから、原発でいい」国民の心が一番変わらなければならないが、一番変われないのも国民の心では。その方法論をもっとブレストしたい。
0投稿日: 2014.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「現実」に手を突っ込む! 本著は、かって原子力ムラにもいたことがあり政界や産業界の現場でも行動するエネルギーの専門家飯田哲也氏とアクティブな社会学者宮台真司氏の3.11直後の対談録である。 「飯田:推進対反対の二項対立だと、相手の穴を狙って論破すれば勝ち、ということになります。でも勝っても現実が何も変わらないなら、そういう議論は不毛です。(略) 宮台:現実に作用する権限を持った者(政府東電等:筆者註)の側に、圧倒的に責任があることは間違いない。そうした非対称的な関係のもとで、実際に行為する側は政治的な無責任を決め込み、批判者は有効性を度外視したままひたすら反対運動をやり続けてきた。その結果、何も変えられないまま、今回の惨事にいたった。それが日本の現実です。」 <議論は単なるディベートでなく、現実をよりよく変えることにつながる議論か?反原発デモだけで社会の現実を変えられるか?> 「宮台:大前研一さんが脱原発になったのも、イデオロギーではなく、合理性の乏しさが理由でした。なので、合理性の問題を国民に丁寧に説明することを目的として、NHKも番組を作ることができると思う。イデオロギーよりも合理性の方が説明の手順が必要で、丁寧に番組を作らないと視聴者は分からない。 飯田:原子力が消えていくのも、まさに合理性です。」 <反原発は右翼でも左翼でも、保守でも革新でもなく、現実的合理性である。> 「この福島第一原発に起きた歴史に残る大事故は、いまだなお収束の見通しは立っていない。この不安定な状態は、未だ数年・数十年のオーダーで続くことは間違いない。この状況を眼の前にしてなお、この国の「旧いシステム」は変わるどころか、上で述べたような既得権益を露骨に温存する動きが見られる。(飯田)」 <この対談は3.11直後だが、指摘された問題は今も同じで変わらない。民主党から自民党へ政権交代して、原発エネルギー政策はむしろ後退悪化している。 今日のyahooニュース→ エネルギー基本計画 再生数値目標を見送り 自公合意 http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/science/alternative_energy_sources/?id=6112508 > 「この国の「旧いシステム」は、あまりに日本社会を構成する大多数の善良な人々、とりわけ最低辺層や将来世代への眼差しが欠けているだけでなく、その善良さを愚弄し、見下し、しかもそこに付け込んで「寄生」しているとしか思えない。しかし他方で、それを批判して理想論を美しい論文にまとめても、どろどろした「現実」に手を突っ込まなければ、それはエクスキューズにしかならない。(飯田)」 <国民一人一人も、エクスキューズせずに自分が出来る範囲で「現実」に手を突っ込むこと!>
0投稿日: 2014.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島直後の対談をもとにした脱原発の本。 あれから3年経過して、状況が変わっている部分も多いので、改めてお二人の話を聞いてみたい。
0投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災、福島原発事故から2年を過ぎても、 いっこうに収束の行方が見えない… 本書は、震災事故1週間めの対談をもとに編まれた一冊。 肝心で不可避な問題点が明晰に言及されていると感じた。 著者の飯田哲也は「あとがき」でこう書いている… ―この国の「旧いシステム」は、あまりにも日本社会を構成する 大多数の善良な人々、とりわけて最底辺層や将来世代への 眼差しが欠けているだけでなく、その善良さを愚弄し、 見下し、しかもそこに付け込んで「寄生」しているとしか思えない。 しかし他方で、それを批判して理想像を美しい論文にまとめても、 どろどろした「現実」に手を突っ込まなければ、 それはエクスキューズにしかならない。 「美しい国」を標榜する現首相は、このどろどろとした「現実」に どれほど手を入れようとしているのだろう… いかに美しくコーティングされようと、否応なく 泥水を飲まされるのは、ボクら国民に他ならない。 嫌なものは嫌だ! いらないものはいらない! すべてはつまびらかにされない情報を、 それでも執拗に追い続け、叫び続けるために、 ボクにとって、本書は有益な一冊となった。
0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログよきも悪きも東日本大震災後から明らかになった日本社会の歪みを、エネルギー専門家の視点と社会学的な視点とのコラボで解説されている。
0投稿日: 2013.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2012.10.17読了)(拝借) 【東日本大震災関連・その104】 副題「自然エネルギーと共同体自治に向けて」 かみさんの本棚から拝借しました。東日本大震災の後比較的早く出版された本です。 福島第一原発の事故により、原子力発電は事故が起こると実に大変な事態を引き起こすことが実感されました。そこで、原子力以外の方法で、電力を確保する方法が可能なのかについて考察した本です。 海外の事例や東京、長野での取り組みが紹介され、工夫次第で、原発社会から自然エネルギー社会への転換が可能であろうと・・・・・・。 【目次】 まえがき 「原発をどうするか」から「原発をやめられない社会をどうするか」へ 宮台真司 1章 それでも日本人は原発を選んだ 2章 変わらない社会、変わる現実 3章 八○年代日本「原子力ムラ」探訪 4章 欧州の自然エネルギー事情 5章 二○○○年と二○○四年と政権交代後に何が起こったか 6章 自然エネルギーと「共同体自治」 7章 すでにはじまっている「実践」 あとがき フクシマ後の「焼け跡」からの一歩 飯田哲也 ●無謬原則(45頁) 行政官僚制には「無謬原則」がある。官僚機構のなかでは人事と予算の力学が働くので、「それは間違っていた」とは誰も言い出せない。これは大東亜戦争中の海軍軍令部や陸軍参謀本部問題でもあります。(宮台) ●霞が関文学(70頁) 霞が関文学=官公庁の文章 「霞が関文学」の本質は「フィクションと現実を繋いでいく言葉のアクロバット」です。(飯田) ●自己の時代(76頁) 僕は『終わりなき日常を生きろ』(筑摩書房)という95年の本で、冷戦体制が終わる時代が、科学が輝く時代の終焉と重なると書いています。「未来の時代」が終わり、「自己の時代」が本格的に始まります。(宮台) ●アメリカ依存(86頁) 日本で奇妙なのは、エネルギーを外から得なければだめだという問題が安全保障に繋がってないことです。単にアメリカに依存すれば大丈夫という話ですべてスルーされるのがおかしい。普通は食料とエネルギーはいざとなったら自給できなくてはいけないという話になるはずです。(宮台) ●原子力推進派(114頁) 原子力発電所をひとつ作ると、非常に大きな波及効果がある。発電量も大きく、温暖化防止にもなる。原子力を推進すれば、技術も磨かれ、産業としてもエネルギー対策としても発展する有望な技術だ、と考えている。(飯田) ●再処理と直接処分の経済性(119頁) 福島瑞穂さんが国会で「再処理と直接処分の経済性を比較したことがあるのか」と質問して、当時の日下一正資源エネルギー庁長官が「今までは検討したことがありません。これから検討します」と答弁した。実は日下さんの後ろのキャビネットには、直接処分のほうが安くつく報告書があったのです。(飯田) ●蓄電池付き(150頁) 自動車の蓄電池を活用するより早いのは蓄電池付きの冷蔵庫やテレビかもしれません。計画停電になって冷蔵庫が止まり、みんなが困った。だから蓄電池付き冷蔵庫の発売がすぐ決まりました。技術的には簡単です。(飯田) ☆関連図書(既読) 「私たちにとって原子力は・・・」むつ市奥内小学校二股分校、朔人社、1975.08.03 「食卓にあがった死の灰」高木仁三郎・渡辺美紀子著、講談社現代新書、1990.02.20 「私のエネルギー論」池内了著、文春新書、2000.11.20 「ぼくとチェルノブイリのこどもたちの5年間」菅谷昭著、ポプラ社、2001.05. 「これから100年放射能と付き合うために」菅谷昭著、亜紀書房、2012.03.30 「原発と日本の未来」吉岡斉著、岩波ブックレット、2011.02.08 「緊急解説!福島第一原発事故と放射線」水野倫之・山崎淑行・藤原淳登著、NHK出版新書、2011.06.10 「津波と原発」佐野眞一著、講談社、2011.06.18 「福島の原発事故をめぐって」山本義隆著、みすず書房、2011.08.25 「官邸から見た原発事故の真実」田坂広志著、光文社新書、2012.01.20 「飯舘村は負けない」千葉悦子・松野光伸著、岩波新書、2012.03.22 (2012年10月28日・記)
1投稿日: 2012.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮台真司×飯田哲也(2011)『原発社会からの離脱――自然エネルギーと共同体自治に向けて』を読了。 東日本大震災・福島第一原発事故以降、世の中は明らかに脱原発ムードへとシフトした。それでも、政府は子どもの被ばく許容量を20ミリシーベルトにしたり、大飯原発再稼働や原子力規制庁長官問題など、明らかに原発推進のシフトを崩さない。 原発は燃料調達コストや核廃棄物などを合理的に考えてみれば、明らかに環境にやさしい「クリーンエネルギー」ではない。太陽光発電や風力発電は普及すればするほど、市場メカニズムに従って、発電コストは下がり総体としての発電量も増えるのだが、危険リスクを徹底的に管理・規制していかなければ、その負担コストは跳ね上がるために、市場メカニズムが働かない独占市場の中でしか機能できないものだ。しかし、両氏が問題にする「悪い心の習慣」の問題、即ち、全てを自分ではなく他者に任せるか責任を追及し、その他者が為すシステムやプラットフォームを自ら自治することをしない/できない、いわゆる思考停止状態の拘泥から抜けられずにいる社会がこの国の病理として浮かび上がってくる。 議論を通しての主張は精緻かつ明快だ。リスクなどを自ら考慮した上で合理的思考による議論を重ね、その知識の蓄積に基づいた選択と決定と直接的な共同体自治こそ、さまざまな変化に柔軟に対応できるとするものだ。決定の権限や選択肢が大きくなればなるほど、その決定は硬直化し拘泥する。だからこそ決定するためのセクターを数々増やして自治の質を高める。そこに社会としての変えるべき道があるとするものだ。 原発に関する問題や自然エネルギーに関する実践事例も紹介されているが、両者が描く社会の哲学(社会哲学・政治哲学)が非常にクリアに語られているのが特筆すべきところ。まだソーラーシステムも電気も選べない社会であることが非常にもどかしい。
0投稿日: 2012.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会学者、宮台真司さんと環境学者?の飯田哲也さんの対談形式によって原発依存社会について言及された一冊。 全体としては飯田さんが環境的、エネルギー政策としての専門的な側面から論じ、宮台さんが(どちらかといえば)読者目線で的確な疑問を投げかける、といったような構成。宮台さんのコメントについては、読んでいて気になる部分を的確かつわかりやすい表現で突っ込んでくれたり、理解を促進する言い換えをしてくれたり、さすが宮台さんって感じでした。 個人的に一番面白かったのは第二章「変わらない社会、変わる現実」で、ここではなぜ日本社会が原発依存社会から抜けだせないでいるのかを、抜けだしたスウェーデン社会との比較から、社会学的な目線で論じている。こういった内容なので宮台さんの発言も読者のサポートという立場ではなく、自身の考察をふんだんに交えているわけだが、非常にわかりやすくて納得の行く議論になっていた。
0投稿日: 2012.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログエネルギー問題についてなんも知らなかったおれには目から鱗な情報満載だった。例えば自然エネルギーが実は結構量的な意味でもいけるんじゃないかとか、北欧の例とか。原子力ムラも聞いたことあったけど実態が垣間見えたし。エネルギーの問題から日本の共同体自治についても考えたり。 ただ対談形式なんで、おれみたいな無知な人間にしたら知らないキーワードが解説なしで出てくるのが難点。
0投稿日: 2012.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログエネルギー政策を取り巻く背景と、政治のカラクリが読めた気がする。 本の趣旨とは関係ないが、薪ストーブに惹かれてしまった。 炎を眺める生活は優雅でいいなぁ。
0投稿日: 2012.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
トンデモな二人の対談 定量的な論拠に乏しいと思う 2012/03/24図書館から借用;3/28朝の通勤電車から読み始め;3/29朝の通勤電車で読了
0投稿日: 2012.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ飯田氏は東電にも出向した経験があり、福島原発の開発にも関わり20余りの特許も取得した技術者だった。その後その「原子力ムラ」を飛び出しスウェーデンに留学、自然エネルギー等を学んだ。 北欧に比べ日本の状況は30年以上遅れているという。
0投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ東電も官僚も銀行も、自分の利益を守る。強引に狡猾に、また愚直に。法律の例や前福島県知事の例などから強く感じた。 感情ではなく事実から判断しないといけないということも学んだ。二項対立で、自分の陣地から抽象しているだけではどこにも進めない。国や大手マスコミが流す大本営発表に対し、フリージャーナリストの方々が情報集めて流し、一般市民がSNSで情報を収集できる現状はだいぶよくなったと思う。次は我々が自分の問題として自分の考えを持つこと。 欧州の経過や現状との対比から、日本の問題点を洗い出している点は興味深い。正直なところ私には内容が難しく、かなりの割合で理解できていないのが残念だが、、、 エネルギー安全保障という点では、ウランの埋蔵量は少ないかもしれないが、複数に分散しておくという利点はあると思う。実用できないので意味はないが、再処理は資源に乏しい日本としては望んだ夢であり、また儚い夢であった。
0投稿日: 2012.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログありきたりな脱原発、自然エネルギー推進議論ではなく、そもそも何が問題なのか、掘り下げた議論を展開。 飯田氏の濃密な経歴も初めて知れた。
0投稿日: 2012.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ大震災の後、トータル的に自然エネルギーについて語れる人はこの人しかいないという状態になって、ずーとマスコミに出っ放しになっている飯田哲也氏の震災後初めての本になった。時間がないから対談本になっているのは仕方ない。いつかきちんと整理した自然エネルギーシフトへの啓蒙書を出して欲しいと思う。 対談相手は、私は初めてだが、社会学者の宮台真司氏。氏によっておそらく今回の対談は歴史的な広がりを持った。今回の原発問題が、何度も繰返してきた日本の社会システムの過ちをまた繰返していることが明らかになった。歴史の教訓からどのように未来デザインを描くのかをある程度は示した。 今回の原発問題が、戦前の大本営の失敗の歴史的教訓をそのまま繰返していることには気がついていたが、その問題の本質に「官僚問題」があり、それは幕末から続いていることについては、今回初めて知らされた。 またびっくりしたのは、お二人とも私と同世代の1959年生まれ。大学入学時代には、しらけ世代全盛期で、その中で違和感を感じ、(身動きが取れなかったのは私だけだろうけど)人生を模索しながら生きて来たことに共感を覚えた。 飯田氏は特に理工系の学部に進んだけど、今西錦司ゼミの学生と付き合う中でどうも鍛えられたらしい。表立っては行動に移せないけど、議論だけはする雰囲気があった。それが後々、原子力村の中枢に入っても違和感を覚えてそこをステップに次ぎに移る素地になったようだ。 以下、幾つかなるほどと思ったところをメモ。 ●【宮台】日本は、政治が主導的だった時代は明治維新以降、ほんの僅かな間しかなく、長く見積もって明治はんばぐらいまでしか続かなかった。それ以降は役人の力が巨大な官治主義が続きます。(略)大正になると政党政治つまり民治主義になるけど、政友会と民政党の政党争いの末、政友会が民政党浜口内閣のロンドン軍縮条約締結を統帥権干犯として批判したのを機に、軍官僚が総てを握る。(略)政治家と行政官僚はどこの国でも対立するわけですが、日本では圧倒的に政治家が弱く官僚が強いわけです。政治家の活動の余地は単なる利権の調整しかないので、ドブ板選挙をするしかない。政策にはほとんどタッチできません。 ●【宮台】自立に向けて舵を切ろう、アメリカに依存する国であることをやめよう。田中角栄はそう考えて、対中国外交と対中東外交でアメリカを怒らせる独自路線を走ろうとしたわけです。それが例の「ピーナツ」という暗号が書かれたものが誤配されて見つかったという発覚の仕方で五億円事件まで行く。(略)いろいろな政治家に聞いてもアメリカの関与は良く分からないのですが、「田中角栄のようなことをやってはいけないんだな」という刷り込みにはなりました。 ●【宮台】行政官僚には「無謬原則」がある。官僚機構の中では人事と予算の力学が働くので、「それは間違っていた」とは誰も言い出せない。これは大東亜戦争中の海軍軍司令部や陸軍参謀本部問題でもあります。 ●【飯田】世界では自然エネルギーへの投資額が毎年30%-60%ほど伸びています。10年後には100兆円から300兆円に達する可能性がある。20年後には数百兆円、今の石油産業に匹敵する可能性がある。 日本はこの投資の1-2%しか占めていません。日本は「グリーンエコノミー」の負け組みなのです。新しい経済を生み出す側で負けてしまっている。 一方で日本は化石燃料を年間23兆円、GDPの約5%を輸入しています(2008年)。石油、天然ガス、石炭です。(略)(石油と石炭の)二つが、今後貿易黒字を縮小させるなど日本経済の負担になっていきます。新しい経済の側でどんどんチャンスを失い、しかも日本の電力は石炭だらけですから、その石炭代と、それで増えたCO2を減らしたことにするためのクレジット代でますます電気料金が上る。原子力はコストパフォーマンスが極めてお粗末ですから、新しい原発はできず、稼働率は低く、事故だらけ。それをまた石炭で補う。という極めて暗い未来像になります。 →常識的に言えば、自然エネルギーへの転換が、日本の未来にとって、中国対策にとってでさえも、米国支配からの脱却という面でも、ベストな選択だろう。芥川の「危険思想とは、常識を実行に移そうとする思想である」という言葉が思い浮かぶ。唯一の心配は、飯田のこの試算がほんとうに正しいかどうか、ということだろう。 ●【飯田】霞ヶ関文学の本質はフィクションと現実を繋いでいく言葉のアクロバットです。 ●【宮台が飯田の半生を要約】p74
13投稿日: 2011.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで日本社会が原発にべったりと依存してきた理由は、行政官僚の暴走を政治家が止められないという<悪い共同体>の<悪い心の習慣>にある。それは、負けると知りながら、 軍部がアジア・太平洋戦争へと突っ走っていったのを誰も止められなかったのと全く同じ構造をしている。原発や六ヶ所村の再処理工場は、「現代の戦艦大和」のごときものだ。 奇妙なことに、日本においては、脱原発や自然エネルギー推進を唱えることが左翼イデオロギーと結びついて捉えられる。けれども、原発をやめられないという病理は、<原子力ムラ>と<電力幕藩体制>、そして<霞が関文学>=「フィクションと現実を繋いでいく言葉のアクロバット」によって紡ぎ出されたものにすぎない。原発は、技術的に不合理である以前に、社会的・経済的に不合理な存在なのだ、というのが本書の主張である。 こういう対談形式の本は、さながらテレビの討論会を聞いているような臨場感があって読み易いのだが、体系的な知識を得て理論武装するためには使えないという欠点がある。飯田哲也氏の本をもっと読んでみようと思った。 ともかく、日本の政策的知性は いったい、これが世界でもっとも進んだ先進国で民主主義の国だと信じられてきた日本で、チェルノブイリ事故から25年も経た21世紀にもなって、今、起きている現実なのだろうか。これは、フクシマ後に出現した「知の焼け跡」と表現せざるを得ない。(「あとがき」) というほど情けない状態であることは分かった。しかし、それでもなぜか均衡を保っているのが日本社会の不可解なところだ。
0投稿日: 2011.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログデモには最早、意味がないという宮治教授の記事を読んで、なんとなく感じていたことを形にしてもらった気がした。
1投稿日: 2011.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発の話以前に、日本社会のなんたるやが書かれた本だと思います。 私自身がそうだけれど、日本は先進国だとか、日本の教育はすごいとか、日本人ほど他国に信頼される国民はいないとか、そういうおおよそ平和ボケした神話をまんまと刷り込まれて、ある程度洗脳されつつどこかに違和感や恥ずかしさを感じながら生きてきたように思います。 日本は変わりたい。日本を変えていきたい。飯田さんが最後に書いていますが、日より見でも野次馬でもなく、どろどろになって行動したい。行動に移す方法を探っていきます。
0投稿日: 2011.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ市場をうまく導入することで、社会の流れも変わってくる可能性があるという話は、なるほどと思った。 制約を加えた上で、市場に任せることで変化は自然に起きる。エコだからお金の話が絡んじゃだめってことはないんだろうな。どうしても、一般の人間より、我慢して、無理してやっているってイメージがある。 自然エネルギーについては、真剣に考えてみようと思う。北海道に住んで、家の作りで(断熱性能で)暖房のあり方も、コストも全然違うことがよくわかったしなぁ。 もっと当事者の意識が必要なんだろう。いろんなものが拡大して、多くの人が分け前をもらえた時代は終わっちゃってるんだから。
0投稿日: 2011.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発の専門家である飯田哲也さんが、いわゆる「原子力村」が、なぜ、こんな組織構造なのか、何が行われているのか、などを解説してくれるほか、宮台真司さんが、今の社会構造などを分析していて、現代社会に何が欠けているのか、これから何を目指していかなければいけないのか、気付かせてくれる。対談形式で読みやすいので、一度、読んでみると、目からウロコなところが多々あるかも。
0投稿日: 2011.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ『We』編集長・稲邑さんがオススメだというので図書館で借りてきた。「地域生活支援のあり方を、当事者・行政・事業者・市民で考えるフォーラム」へ出かけるときに持って出て、行き帰りであらかた読んでしまう。 フォーラムでは、登壇者のひとり、役所の障害福祉課長さんが、市の総合福祉計画を「市民みんなが関係者」の話にしていけるように…というようなことを言っていた。障害のある当事者とか、その身内とか、そういう「一部の関係者」の話ではなくて、みんなの問題だという話が印象に残った。 それがあったせいか、この本の最後のところで、「誰もが関心を持てる問題から始まって、そこから道筋をたどっていく」という戦略の話は、参考になるような気がした。この本の切り口は「原発社会からの離脱」だけれど、「誰もがそのひとらしく、そのひとが望む生活ができる街」を切り口にしても、通じるものがあると思った。 著者のふたりは、1959年うまれ。ほぼ同じ頃に「いままでのやり方でいいのか?」と思い、「やってられるか」とぃう感じになったところに共通点がある。 3.11後、「原発をやめられない社会をどうするか」、ふたりが語っている。「今さらやめられない」という空気が漂うこの〈悪い共同体〉の〈悪い心の習慣〉について、その悪さを意識できない限りは、技術的にこれが可能だとか政策的にこうもできるといった「合理性」を議論したところで、稔りがないという。 だから、ふたりは、〈悪い共同体〉の〈悪い心の習慣〉を脱し、これから目指すべきは「共同体自治」、"任せる政治"ではなく”引き受ける政治”への転換だという。 共同体自治の成功を左右するひとつは、共同体の規模。 ▼宮台 …顔が見えるからこそ働くインセンティブやモチベーションが、必ずあります。…僕らが大規模なシステムにぶら下がっていれば、依存しようと思わなくても、システムは誰がどうまわしているか分からなくなるから、トータルには依存的になるわけです。分かるものに頼っているのか、分からないものに頼っているのかというのは、やっぱり大きな違いです。(p.139) そして、「人を固定して、その専門性を尊重した積み重ねを実行していた」という希有な例として、佐藤栄佐久前知事時代の福島県、そして大野輝之環境局長のいる東京都の例があげられている。 ▼飯田 …よくある地方自治体の会議は、知事どころか局長、部長も最初の挨拶だけ来て、「このあと部長は所用があります」と席をたって、後は委員だけ残されて、横にいるコンサルの作った筋書きの通り淡々と会議を回すという、ほとんど中身のない審議会が、国の二重写しのような状態でした。 ところが、福島県は佐藤前知事以下…県の組織トップが全員参加して、…自分の頭で考え、受け止めて質問する。…知事以下局長級とも、日本の地方自治体で生身の受け答えをトップクラスの人とした、これは私の最初で、今のところ最後の経験でした。佐藤前知事は、「充て職」とか「役職」ではなく、中身のある議論をさせるという文化を徹底されていた。(pp.141-142) この二人のキャラクターによるところが大であったとしても、そんな文化をつくることが可能であったことは特筆すべきことで、こうした福島県の最大の成果は、2002年にまとめられたエネルギー政策検討委員会の中間報告書。「この文書は全国民が読んだほうがいいものです」と飯田は言う。 ↓その報告書 電源立地県 福島からの問いかけ あなたはどう考えますか?~日本のエネルギー政策~(pdf) http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/energy_021200torimatome_book.pdf ▼飯田 …結局、二年に一回異動する官僚たちが、適当な評価で補助金を配り、受ける地方自治体側もやはり二年で異動する「素人」の担当者が、適当な提案書を作る。そこへ、受注して報告書やモノを納めてしまえば「あとは野となれ」というメーカーやコンサルが食い逃げする。「これでいいんじゃないか?」「ちょっと進んだ技術だ」と、無責任のトライアングルで日本中に「ガラクタ」が作られていくわけです。 …共同体自治をしようとしたら、地域の側にしっかりとした受け皿となる知恵と経験と信用、そうした社会的関係資本を重ねていける「中心」がないといけない。(p.176-177) これは、”環境の町づくり”に関わるさまざまなレベルの事業の話。でも、他の問題にも通じるなと思う。「もっとちゃんとやってくれ」という要求で、ちゃんとやることを任せているあいだは、結局は似たような別の誰かがよばれてくるだけ。 誰かに任せる政治から、自分らで引き受ける政治へ。市民としてできることは何か? ▼宮台 いきなり環境問題から入ると何も動かなくなるので、…まず自治を取りもどす。共同体自治の形を作ってから、環境の問題をそこに実装させていこうという戦略だと思う。…エネルギーを変えることから自治を再生するという方向と、自治を再生することでエネルギーを変えることの政策的な現実性を上げていく。両方の方向性があると思います。 …ある種の特殊な人が関心を持つ問題ではなく、誰もが関心を持てる問題から始まって、その問題に関心を持った以上は、次の問題に関心を持たないのは不自然でしょう、というふうに道筋をたどっていくようにしよう、という戦略です。 いきなり環境問題というと、それは環境オタクの話でしょう、と無関連化されてしまう。誰もが関心を持つ問題ならそうはならない。(p.179) たとえばどんな問題から入ったら、「自分にも関わる問題」につながるだろう? 市の総合福祉計画を「市民みんなが関係者」の話にしていくには、どんな切り口がありうるだろう?そんなことを思いながら読み終える。 この本でどうしても気になったのは「〈悪い共同体〉の〈悪い心の習慣〉の逆機能は、盲目的依存に集約される。…総じて「〈システム〉への盲目的依存」と呼べるだろう」(p.4)というところ。盲判などと同じで、ものの喩えとしての表現だとしても、具体的な盲の人を思い浮かべると、ろくに吟味もせずにとか、感情にひきずられてといった意味合いがこめられているこの言葉には、やはり引っかかる。冒頭に「盲目的」がじゃんじゃん出てくるせいで、読みはじめたときのこの本の印象はかなり悪かった。 (9/11了)
0投稿日: 2011.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログシステムに依存すれば便利で快適かもしれないが、盲目的に依存すればするほどそれが壊れたときに大変なことになる。 個人がバラバラの状態で大きなリスクを背負う状況は幸せとはいえない。そうであれば、しっかりとした「中心」を据えてそこに人々が集い、知恵と経験と信用(ソーシャルキャピタル)を積み重ね、選択肢について吟味し、互いに納得し、時には我慢をしながら進んでいくしかない。 今までは、大きなものに依存して「ちゃんとやっておいて」「もっとうまくやれよ 」だった。でもこれからは「自分たちでちゃんとやります」。要は自分たちが営んでいる社会を変える必要があるのかどうかについて、自覚的になれるかどうか。 まさに、「原発をどうするか」から「原発をやめられない社会をどうするか」へ。 http://www.miyadai.com/index.php?itemid=947
0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の政治家で、環境問題について歴史をおさえ、一定の知識人なら当然知っているべき知の体系(環境ディスコース)にもとづいて語れる人はほぼゼロ。
0投稿日: 2011.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
飯田哲也さんという半端なく頭の良い人の今までされて来られたこと、さらにはおいたち、さらに宮台真司さんという社会学者の一般人にも面白く分かり易い話で綴られた対談本。 勉強してなかった私なんかは、何かおかしいぞとまでは思うけど、それが何かがわからないでいた。今まで何だか疑問が残ったまま時が流れていたことの、答え合わせ本。自治体、個人個人がもっと勉強し責任感をもつこと。 三月の震災以降、始めて明るい未来が見えてきた。 東電をゾンビのように生かすのは、やはり変なんだ。東電や国の払うべき代償を国民に押し付けるなんてことはあってはいけない。 誰でも電気を作って都市ではそれを共有する。スエーデンの様に何発電かも選べたらすごい進歩!早くそういう社会になりますように! また読み返します。
0投稿日: 2011.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発の存否を巡っては賛否両論半々といったところだと思うが、個人的にはなくして良いと思う。経済性や危険性も両方意見があって実際よくわからないが、経済性や安全の問題でなく、安心の問題だと思う。この点小田嶋隆の日経オンラインのコラムが最も合点がいった。一度ハエのとまったケーキはたとえとまった部分を取り除いてもみんな食べたくないのだ。
0投稿日: 2011.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ実現可能性はともかく、脱原発・新しい社会への提案のひとつとして、何が考えられているかを知るには面白い。 基本的に対談形式は読みやすくて面白いものだけど。 何かヘーゲル的ってこういうことなのかとも思った。 大きな物語が必要なのだ。 問題は今後の世界に誰の物語が採用されるかなのだ。
0投稿日: 2011.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
机上のシミュレーションでは当然負けるはずだった日米開戦になぜ突き進んだのか、なぜ私たちは原発を「選んだ」のか。ショッキングな冒頭の文章から一気に読んでしまいました。小さい頃、親につきあって原発反対のデモ行進につきあったことがあります。あのときはすごくざわざわした感覚がありましたが、たしかにいつのまにか私たちは原発の現実を見ないようにしてきましたから「選んだ」といえるのでしょう。飯田哲也さんという人の本を初めて読んだけど、もっと読んでみよう。
0投稿日: 2011.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011年3月11日の大震災で福島第一原子力発電所が再起不能の大事故を起こしたのを契機として原発の存続の是非が議論されている。いまや日本の電力の2割強を閉める原子力発電が今回の事故で閉鎖もしくは縮小の道が模索され、日本全体が節電や自粛の渦中から抜け出せない。 原子力の穴を何かで埋めなくてはならない。不足する電力をいかに補うのかは焦眉の急だ。しかし、次のエネルギーをどうするかという議論にはなかなか進まない。それは我が国の構造的な問題がある。本書はまさにそうした現体制への批判書として読むことができる。 飯田哲也氏は原子力発電の技術者出身で、その内情を知り原子力の欠点と将来性のなさを悟って自然エネルギーへの転換を主張する科学者であり、実践者である。内情を知るだけにその言葉の重みはあり、関係者の名前を明記したかなり生臭い話まで登場する。それは本書が対談という形式をとっているからこその特徴だろう。 本書には大企業によるエネルギーの独占状況に関しての強い批判がある。確かに日本人にとっては電気はその地域を広域で取り仕切る電力会社から買うものというのが常識化しており、その大規模な電力事業を確保するために、供給地から遠くはなれた過疎地に発電所を造るというのが無批判に受け入れられている。福島や柏崎、さらには東通までが「東京電力」であることを知らずにいた関東の住人が大多数だろう。 今回の震災で原子力発電は現況のまま継続することはきわめて危険であることは分かった。震災がなくても核サイクルの技術的破綻でやがて行き詰ることは目に見えていたのである。反原発の動きは今までもあったが「非現実的」の名のもとに抹殺されてきた。それが逆に原発を使えず困窮する現実に結びついたのはなんとも皮肉なことであった。 本書には原発なきあとの日本のエネルギー事情についての提言が少しだけある。例えば、自然エネルギーへの転換を進めるとともに、小規模な発電設備を増やしエネルギーの自治やネットーワーク状に電気をやりとりできる方法を模索するべきだとある。しかし、この点に対する言及は極めて少なく、私のような門外漢が具体的なイメージを構築するにはいかにも物足りない。つまり本書は現状への批判の書としては一定の役割があるが、将来への提言としてはかなり物足りない。対談集という形でまとめた限界といえるのだろうか。 エネルギー問題に関するリテラシーはもっと高めなくてはならない。本書のような啓蒙書でさえ、意味不通の文言が数多く出ている。それは私の勉強不足が最大の要因ではあるのだが。
0投稿日: 2011.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会学者である宮台真司氏と、環境エネルギー政策研究所(ISEP)所長の飯田哲也氏が、3・11後の超多忙のなか、2日間をどうにか絞り出して行われた長時間にわたる対談をまとめた一冊。
0投稿日: 2011.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、冒頭から最後まで、目の覚めるような指摘、論点に満ちています。「環境・エネルギでは欧州に対して30年遅れている」、「原発推進・反対の2項対立は不毛」、「新エネルギー=コスト高、のうそ」、「中央から地方役人に権限を渡してもダメ」など。もちろん対談なので正確な理論展開はしていません。むしろ大事なのは、読者が政府発表、世の中の雰囲気、俗論に惑わされずに、「自分で確認し、考え抜くこと」態度のほうでしょう。お2人が説く「共同体自治」というのはそういう社会の姿なのだと思います。
0投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ何かに依存することで得られる安定や安心が、実は不安やリスクの裏返しであることを改めて認識。さて自分はこの先依存体質から脱却できるだろか。
1投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発事故後,より注目されている飯田哲也氏と宮台真司氏との対談本.前半は宮台真司氏の独演傾向あり(宮台真司氏がダメな人には不向き).後半になり飯田氏が前面に出てきて,私が勉強不足で知らない情報や氏の考えを示してくれる.東京都が先進的な環境政策を実行していることは初めて知った.東京電力と株主を守ろうとしていることに違和感を持っていたが,「東京電力が全ての財産を出す.次に株主で,それに融資した銀行.それでも賠償に足りなかったら,原発埋蔵金 再処理等積立金を使う」とコメントしていることには溜飲が下がった.
0投稿日: 2011.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ緊急出版!! 「環境エネルギー政策研究所ISEP」飯田哲也所長http://www.isep.or.jp/ & 宮台真司教授http://www.miyadai.com/ による共著です。 表紙やまえがきの ☆これからのエネルギーとこれからの政治を語ろう ☆「原発をどうするか」から「原発をやめられない社会をどうするか」へ に象徴☆ イデオロギーやら反社会的?やらな内容ではなくて、 東日本大震災を機に私たちが気付いた、 生活に密着した疑問や違和感に寄り添う情報だと思います。 ぜひ皆さん、一読を!
0投稿日: 2011.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮崎氏の堅苦しい話が展開すると思いきや、飯田氏の熱くクールな話で向かうべき方向性は示してもらったように思う。 あとは誰がやるかだが、一人一人が空気に流されず自覚を持って主張し行動するという、世界の中では至極当たり前のことが日本人に、私自身に求められている。
0投稿日: 2011.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。原発推進を止められなかったのは、組織とか構造の問題。原発のみならず、未来のためよりも自分の組織のため、変えることに対する許容が少ない、この考え方を変えなければならない。
0投稿日: 2011.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこういうのはタイムリーに読んでおかないと、と思って他の積読に優先して読んでみた。 こういう対談本は議論の展開が速くて、理解が浅くなっちゃうけど、キーワードはたくさん盛り込んであるから、それをもとにわからなかったことを他の本とかで調べるといいかも。 知識はたくさん仕入れることができたんだけど、なんとも救いがなく、読んでてちょっと凹んでくる内容だった。
0投稿日: 2011.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに発売日前に予約して、急ぎ読んだ本。ここでいま形にしようという意気込みもきっとあったはず。 素晴らしいのだけど、これをどう広めたらいいのかとひたすら思う。 真新しいことより既にあったことのが多い内容で、だからこそ。そうなったらいいな、こうできたらいいな、こうしたいな、は確かに頷き意気込むばかりなんだけど、じゃあさあ今日明日どうする、という課題は、わたしごとき一人じゃあんまりにも実践的でなく思いつかない。何ができる気もしない。砂漠に一滴の水。だからこそ。 南は今回の件で助かったのではなく置いていかれた結果になりはしないかという予感が日に日に強くなっている。意識や文化のレベルで。それこそ、空気が。
0投稿日: 2011.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮台真司氏の語り口はごつごつとしたものであるが、その論考は見事に核心をついている。”悪い共同体”の“悪い心の習慣”という言葉で今の社会を鮮やかに切り取っていると思う。共同体自治というユニットからの統治がこれからの日本復興をなしとげるためのキーであるとしている。我々も単に自明のシステムに依存するだけではだめなんだと反省させられます。
0投稿日: 2011.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮台真司の本を買うのなんて、たぶん20年ぶりくらい。正直、その「口調」があまりフィットしなかったのだが、この本は興味深く読んだ。 東北電力における白洲次郎のファンクションは僕には謎である。案外、言われているようなレジェンドではないのかもしれない。今後調べてみたいテーマだ。 CO2と原子力の関係や六ケ所村の問題など、いろいろと勉強になる本だった。
1投稿日: 2011.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ一筋の希望の光とともに、この先のエネルギー問題について考えたいひと必読の一冊。 ここでは「3.11以後の日本」について、社会学者の宮台真司氏と環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也氏ふたりの対話を通じて、おもに「エネルギー」面から論じている。 宮台氏はここまで原発社会をつくってきた日本人の「心性」について、「《悪い共同体》とそれに結合した《悪い心の習慣》」「知識社会」「ガジェットの集積を尺度とした豊かさ」といったキーワードから語っているが、まさに核心をついている。 一方、もともと技術者として原発開発の現場に身を置き、原発行政にも深く関わってきた飯田氏の話も生々しく興味深い。その後訪れたスウェーデンで出会った自然エネルギーについて、ヨーロッパのみならずアジア諸国の導入例や、日本における可能性や過去の失敗例まで紹介されており勉強になる。 そして、この先のヴィジョンとして提唱される「小さな統治ユニットによる共同体自治」は、エネルギー問題だけでなく、この先の日本、とりわけ東北〜北関東の早期の復興のためにもぜひ実現してもらいたいと思う。もちろん、あわせて電力の固定価格制度の早期導入もまたれるところ。なぜか福島県や新潟県に「東京電力」の原発があるという不自然を是正するためにも。
0投稿日: 2011.06.24
