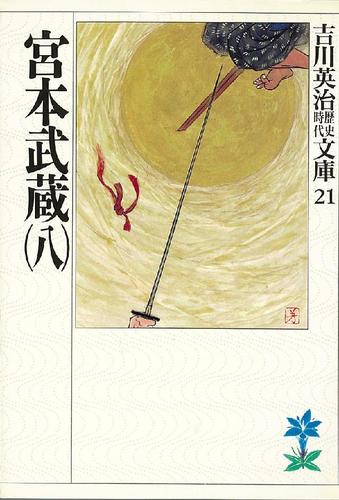
総合評価
(32件)| 15 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ魅力的なキャラクターが多く構成も含めて引き込まれる内容。新聞小説らしく、都合の良い展開や最後に急激にハッピーストーリーに向かう点などは気になるが、それも含めて楽しめた。
0投稿日: 2022.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ最終巻は、小次郎の「力と技の剣」と武蔵の「精神の剣」の闘いである巌流島の決闘が描かれる。決闘が近づくと街は騒がしくなるが、それでも武蔵の周囲に保たれている静謐さが印象的。ブレない姿とはこんな姿なんだなと思う。 虚しさや苦悩を原動力として凄まじく成長する宮本武蔵、意志が弱く堕落していく又八、この2人は1−8巻を通して対照的な人間として描かれているが、2人で1人の人間のように思える。人は様々な性質を持っており、常にせめぎ合っているものだと思う。それでも、自身の弱さを制して内面的な完成を目指そうとする大切さを、吉川英治の「宮本武蔵」から学んだ。また時間をあけて読み返したい本だ。
2投稿日: 2021.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ剣の道を磨き続けてきた武蔵。 ついに因縁の相手、佐々木小次郎との決戦が決まります。 お杉ばばとお通、又八と朱美、城太郎、伊織、夢想権之助らが、物語の最終に向かって、次々と武蔵のもとに。 お通との邂逅、お杉ばばとの和解。 全てが最後に繋がり、ついに舟島で佐々木小次郎と決戦の時を迎えます。 10年ぶりに通して再読しましたが、何度読んでも、感動します。 またどこかで、再読しようと思います。
0投稿日: 2020.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ何回読んでも、武蔵と伊織の再会の場面、武蔵とお通の別れの場面では、必ず涙が流れる。 極上の物語を生んでくれた吉川英治には、本当に感謝したい。 昭和、平成と時代を超え、次の時代にも、永遠に語り継がれる大名作。
1投稿日: 2019.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画化・ドラマ化・漫画化など、様々なかたちで紹介されてきた大人気歴史小説の最終巻。伏線回収のため、あっちへヨタヨタ、こっちへヨタヨタという印象が否めない。ラストも息切れされたのかな?と思われる中途半端さがあったのも残念。
1投稿日: 2018.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮本武蔵最終巻。 お杉婆が山姥のようであった。 初めてこの本を読んだのは、伊織や城太郎に近い年齢の頃であった。読むと言っても、当時の自分にはこの物語を読み解く力はなく、視線が文字を上滑りしただけだったらしい。どんな話だったか全然覚えていなかった。途中で挫折した可能性も十分に考えられたが、全巻にしっかりと手垢がついていたので頑張って捲ってはみていたらしい。 武蔵の年に近くなった今となっては自分も少しは成長したようで、さらさらと楽しく読むことができた。 正直、内容がどうこうではなく、しっかり話を理解しながら読めたということ自体がうれしい。 今後も過去に読んだ作品を読み返してみると一層楽しめるかもしれない。
1投稿日: 2018.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最終巻。結果的には又八、お杉婆とも和解し、お通や城太郎、伊織らとも再会して、小次郎の対決にのぞむ。そんな話の流れ。「人間宮本武蔵」がどの様な経験をし、自分の糧としていったかをメインテーマにしているので、小次郎との対決シーンもあまり文章を割いて触れられてはいない。その点はちょっと期待外れの感が否めなかった。ただ、史実に対して創作をした部分が多いと思われるけれど、全巻を通して宮本武蔵の物語を楽しませてもらったという点では満足。あとお通の気持ちを武蔵が受け入れた点についても満足。感想はこんなところです。
0投稿日: 2017.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ積ん読チャレンジ(〜'17/06/11) 19/56 ’16/10/06 了 長かった全八巻に及ぶ武蔵の物語もこれにて終幕。 宮本武蔵と佐々木小次郎による巌流島の決闘というクライマックスに向けて物語が収束していく。 お通さんと城太郎の再会、お通さんとお杉婆の関係の氷解、長い長い人生の回り道を経て夫婦となった又八と朱美…… そんな彼らが、武蔵の決闘の行方を見守ろうと、一所に集まる様は物語の最終局面を彩るものとして良かったと思う。 一方で姉弟であることが明かされてから相対していない伊織とお通さんなど、もう少し描いて欲しかった部分への言及が足りない気がしたのも事実。 小次郎と武蔵の決闘に決着がついた後、剣の実力のみで言えば小次郎の方が上だったかも知れないと言う表記があったことも良かった。 戦いの敗者に対しての賛辞が最後にあったことで、それを破った武蔵の試合巧者ぶりも窺える。 最終巻だけに色々と急にまとめに掛かっているなと感じる部分も多々あったが、その最たるものがお杉婆の改心。 急に良い人になりすぎていて、違和感しか感じなかった。 三つ子の魂百までと言う言葉がある通り、あんなに急に人の心根は変わらないだろうと思う。 1935年に一話目が新聞に掲載されたこの作品は、今から80年前の作品。 世間の持つ宮本武蔵及びそれに関わる人物への認識は全てこの作品に基づいたものであると言っても過言ではない。 「史実」を超えた認識を我々に与えている作品だ。 家中の積ん読を全て読み終えようと行動を起こして数ヶ月たつが、いつかは読まなければと思っていた作品を読み終える機会に恵まれて良かった。 -------------------- 気に入った表現、気になった単語 「「艱苦に克ったすぐ後には、艱苦以上の快味がある。苦と快と、生きてゆく人間には、朝に夕に刻々に、たえず二つの波が相搏(あいう)っている。その一方に狡く拠って、ただ安閑だけを偸(ぬす)もうとすれば、人生はない、生きてゆく快も味もない」」(P84) 「寝る間も油断のならない危険に研がれ、絶え間もなく生命を窺う敵を師として、しかも剣の道は、人をも活かし、世をも治め、自己をも菩提の安きに到って、悠久の生ける悦びを、諸人と共に汲み頒(わか)とうという願いにほかならないのである。--その至難の道の途中で、たまたま、つかれ果て、虚無に襲われ、無為に閉じ籠められる時--卒然として、撓めていた敵は、影を顕してくるものとみえた。」(P101) 「が武蔵には間髪のまに、処する方法が立っていた。兵法によらず、すべての理は、それを 理論するのは、平常のことでわ実際にあたる場合は、いつも瞬間の決断を要するのであるから、それは理論立てて考えてすることではない。ひとつの「勘」であった。 平常の理論は「勘」の繊維をなしてはいるが、その知性は緩慢であるから、事実の急場には、まにあわない知性であり、ために、敗れることが往々ある。 「勘」は、無知な動物にもあらから、無知性と霊能と混同されやすい。智と訓練に磨かれた者のそれは、理論をこえて、理論の窮地へ、一瞬に達し、当面の判断をつかみ取って過らないのである。」(P104) 「荒海(わだつみ)の潮(うしお)のような樹々の唸りに体を吹かれて佇んでいる」(P186) 「この船出に、身に纏うている黒い小袖は、光悦の母が自ら針を持って縫うてくれたものである。 手に持つ笠や草鞋。その他一物たりとも、何か 世間の人の情けの籠もった物でない物はない。 いわんや、碌々、米も作らず布も織らず、百姓の耕す粟を喰っている身は--まさしく世間の恩で生きている。 (何をもって酬いようか) 心をそこにおく時、彼は、世間に対して慎む心こそあれ、迷惑がる気もちなど起すのは勿体ないと知るのだったが--しかし、その好意が余りに、自分の真価に対して過大であり過ぎる時、彼は、世間を恐れずにいられなかった。」(P207) 「何しろ、合わせる顔もないとして、権之助はそう聞くほどさらに、伊織を尋ねることに焦心っていたのだった。 --と。その武蔵が、愈々、小倉へ向って立つということを、昨日九度山で聞いた。 (かくては何日(いつ)か) と、意を決し、面(おもて)を冒(おか)して会うつもりで、早々、道を急いできたのだったが、」(P210) 「「驕慢な天才と、凡質を孜々(しし)と研いた人と、いずれが勝つかの試合ですな」 「武蔵様も、凡質とは思われませんが」 「いや決して、天稟(てんぴん)の才質ではありますまい。その才分を自ら恃(たの)んでいる風がない。あの人は、自分の凡質を知っているから、絶えまなく、研こうとしている。人に見えない苦しみをしている。それが、何かの時、鏘 然と光って出ると、人はすぐ天稟の才能だという。--勉めない人が自ら懶惰をなぐさめてそういうのですよ」(P212) 「天にあっては比翼の鳥、地に在っては連理の枝とならん」(P234) 「お通はその時まったく、自分が病人であることは忘れていた。しかし城太郎にそう注意されても彼女の意志は肉体を超えて、はるかに高い健康な信念の中に呼吸していた。」(P240) 「岩間角兵衞にしてみれば、自分の世話した巌流が、今日かくのごとく名声を得、君寵も厚く、大きな邸(やしき)の主ともなってくれて、その邸でこうして一杯の酒の馳走にでもなるということは、世話がいがあったという気持から、人生の欣(うれ)しいことの一つを杯の一口一口に舐めているような顔つきだった。」(P253) 「あたたかい心で人の中に住め。人のあたたかさは、自分の心があたたかでいなければ分かる筈もない」(P274) 「舟が進んで行くにつれ、佐助は、ひとりでに先刻から、肌(はだえ)に粟を生じ、気は昂まり、胸は動悸してならないのである。」(P345) 「射るという眼はまだ弱いものであろう。武蔵の目は吸引する。湖のように深く、敵をして、自己の生気を危ぶませるほど吸引する。 射る眼は、巌流のものだった。双眸(そうぼう)の中を、虹が走っているようき、殺気の光彩が燃えている、相手を射竦めんとしている。 眼は窓という。思うに、ふたりの頭脳の生理的な形態が、そのまま巌流の眸(ひとみ)であったであろう、武蔵の眸であったにちがいない。」(P358) 【舂(うすづ)く】 太陽が山の端にかかる、夕日がまさに没しようとすること。 【渇しても盗泉の水はくらわず】 ひどい苦難や貧乏にあっても、不正なことには加わらないこと。
0投稿日: 2016.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ大団円の第八巻。 又八、朱美、お杉ばば、城太郎、そしてお通。 これまで武蔵と関わった人々が、 巌流島という場所に集結し、 全ての人が救済された。 まさに大団円というのに相応しい。 だが、その後佐々木小次郎との決闘という 誰もが知っている結末が残っている。 戦いの結末も、どのような方法で決着が着くかも、 誰もが知っている話ではあるが、 不要でもつまらなくもない。 ここに辿り着くための長い旅だった。 吉川先生は武蔵の精神の剣が、 小次郎の技や力の剣に勝ったのだとした。 解説も面白い。同じ国民作家の名で呼ばれる 司馬遼太郎による宮本武蔵像が書かれているが、 彼は勝つための合理主義者として描いたらしい。 戦前の精神主義と戦後の合理主義。 同じ人物を描いてこうも違うのだろうか。 元々この小説は直木三十五と菊池寛による 武蔵名人説、武蔵非名人説の論争に対し、 吉川先生が回答として書いた小説だった。 宮本武蔵という人物の実像は謎に包まれている。 私が巌流島で会ったとある人物は、 武蔵を評してつまんねー奴と言っていた。 お通との恋も、又八との友情も、 沢庵和尚を初めとする一流の人物との邂逅も、 全て吉川先生の創作だろう。 そういう意味では本当の宮本武蔵はつまらない。 だが、本当につまらない人物だったとしたら、 彼は歴史に埋もれていったことだろう。 後世の人々が宮本武蔵という男のことを考える。 それだけでも彼は偉大な人物であり、名人なのだろう。
0投稿日: 2016.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ最大の山場とも言える、手に汗握るシーンが含まれた巻だったけど、読み終えたらなんだか静かな気持ちになった。8巻あっという間だった。楽しかった。 2014/9/10
0投稿日: 2014.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ少年よ(少年でなくとも)大志をいだけ。というメッセージに感じました。 しかし、心入れ替える前のお杉さんはすごく暗黒だ。
0投稿日: 2014.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ能力や腕だけでは駄目。精神力がなければ。 特に8巻に至言多数。 登場人物の多くには共感できるのだけど,本位田のおばばにだけは共感できない。 特に改心前のおばばのような老人にはなりたくない。
0投稿日: 2013.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
よくよく考えると武蔵と小次郎の対決の必然性がお世辞にも滑らかに、自然な形で導入されていないな、これは大きな弱点。 ただそれを補ってあり余る魅力が満載、この巻の小次郎との最後の対決シーンもそうなんだが、戦いの場面の文章が凄い。 映像が浮かんでくる表現とはまさにこの作品に当てはまる。 でも詰まるところ本作の魅力は最後の文章に詰まってるんだろうな。 『波にまかせて、泳ぎ上手に、雑魚は歌い雑魚は踊る。けれど、誰か知ろう、百尺下の水の心を。水のふかさを。』
0投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮本武蔵第8段。 ついに、天の時来たり。 なんという両雄。長き旅路の果てに、物語は完結する。多くの人々の思いを受け、試合に臨む二人。希代の達人でありながら、心では苦悩する二つの命。それはあまりにも人間らしい。 天の時。地の利。人の和。勝者は、最後に時を得たか。 「鞘は、汝の天命を投げ捨てた」
0投稿日: 2013.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ試合前、武蔵が伊織に対してかける言葉が深く心に残る。「ひとたびお世話になった方のご恩を忘れないこと、武道だけでなく学問にも励み、謙虚に、人の避けることも進んでやること。肉親がいないため僻みやすくなるが、温かい人の中にすめ。人の温かさは、自分の心が温かくなければわからない。長い生涯があるが命は惜しめ。事ある時、国・武士道のため、捨てるために命を惜しめ。」 美しい師弟関係が人を育てるのだと改めて思う。 天稟の才能である小次郎の剣と努力で築いた武蔵の剣。最後は、武蔵の信じた精神の剣が小次郎の信じた技や力の剣を打ち勝ち、幕を閉じた。
0投稿日: 2013.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「『武蔵様も凡質とは思われませんが』 『いや決して、天稟の才質ではありますまい。その才分を自ら恃んでいる風がない。あの人は、自分の凡質を知っているから、絶えまなく、研こうとしている。人に見えない苦しみをしている。それが、何かの時、しょう然と光って出ると、人はすぐ天稟の才能だという。――勉めない人が自ららん惰をなぐさめてそういうのですよ』」 一人の人間のすさまじいまでの人間としての成長、道を求める苦難。それを続け抜いた生き方に感動します。三国志同様、一気に読んでしまいました。 しかも、話としても非常に面白く、最後に向かいすべての人間が収束していきます。見事でした。本って面白いなぁと改めて思います。
0投稿日: 2013.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログようやく全巻読了。 この巻の感想。クロージングにある程度強引さがあったのが残念。8巻も書いたんだがら、最後がっつり盛り上げて欲しかったが。小次郎との試合は一乗寺下り松のところみたいに書いて欲しかった。サラッと終わってしまった。 全体としての感想。前半(一乗寺下り松のところ?)で終わる予定だったのが好評だったんで、後半も書かれたんだとか?結果的に冗長だったと思うが、前半は何しろ面白かった。痛快で気持ちよかったし、哲学的でもあった。それでいて政治的じゃなくて、時代背景を理解してなくても楽しめたから、自分に合ったのかもしれない。今後好きな本はと問われたら、吉川英治の宮本武蔵、と言うかも。
0投稿日: 2013.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ全八巻の旅を完了。宮本武蔵をもっと知りたくなる良書であったと思います。全体を通して7巻の沢庵宗彭の言葉が記憶によく残った。この沢庵さん、沢庵漬けの考案者っぽい。
0投稿日: 2013.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ『宮本武蔵』では多くの決闘や多彩な登場人物との関わりが書かれています。良かれ悪かれ登場人物の「信念」に触れる中で、武蔵は人間性を磨いていきます。有名な佐々木小次郎との決闘も、勝敗を分けたのは「技や力の剣か精神の剣の差」と著者は綴っています。『宮本武蔵』は人間の成長の物語です。
1投稿日: 2012.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ武蔵と小次郎の決着 綺麗な終わり方だな、と思った 技術的なことはほとんど省かれて、精神だけが強調されている
0投稿日: 2012.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ行方の知らないあの人この人、蔭からおいで祭りや祭り、船島の決斗ぞいつぞいな。もはや馴染みに近い感覚すら持つサブストーリーの主人公たちが覚り、寄り添い武蔵を見送る時点で既に物語は大団円を迎えていると思う。 あ、やっぱり櫂なんだとか、鉢巻なんだとか。それは一つの物語を区切るアイコンでしかなかった。 愚堂和尚いみじくも記すところ、元来仏法無多子 喫飯喫茶又着衣。 宮本武蔵 全八巻了
0投稿日: 2012.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ己が主体であり、影法師が対象であるように、 己の心が主体であり、現世日常への感覚は対象なのだ。 現世日常の憂い・煩悩に煩わされ、己の心を取り乱しながら生きる人間のなんと多いことよ、 という教訓を僧侶は無言で武蔵に悟らしめた。
0投稿日: 2012.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮本武蔵という人物を中心に据えた人間形成,鍛錬の物語です. 幼馴染みの又八が心の弱さを,佐々木小次郎が強さと傲慢を,武蔵が高潔を,それぞれ担当しているように見えます. その他にも,色々な登場人物が人間の色々な性質を担当していて,作品世界が一つの人間の心の中で起こる鬩ぎ合いと重なって見えました. 一気に読むよりも,毎日少しずつ読むことで,毎日読者自身を叱咤激励できる作品であると感じました.
0投稿日: 2011.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ剣豪という言葉からイメージしていた武蔵と違い、思慮深さ、人間性、武士道を追求する姿勢は興味深い。一通り読み終わってみると、吉川英治の他の小説を読み終わった時と同じく、史実が知りたくなってしまう。史実がこの通りであって欲しいと思ってしまうあたり、小説に魅入られた証拠だと思う。
0投稿日: 2011.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦前の新聞連載小説. 水村美苗さんが「手紙,栞を添えて」の中で「宮本武蔵は,私にとっては実に懐かしい本なのです.なにしろハイスクール時代,年に一度は儀式のように読み返したのです.」と書いているのを読んで以来,いつか読もうと思っていた. これだけの長い物語が,少しも流れが滞らず,最後の船島での試合にまで導かれるのには驚くばかり.読むのが遅い私でもそれほど時間をかけずに読み終えた. しかし,この本を読んで私が興味を持った人物は,宮本武蔵ではなく,本阿弥光悦や沢庵和尚だから,私はこの本のよい読者ではないのだろう.
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ遂に最終巻、又八、もばばもお通も、色々な人々が巌流島の戦いに向かって収束してゆく。「小次郎の信じていたのは、技や力の剣であり、武蔵の信じていたものは精神の剣であった。それだけの差でしかなかった。」
0投稿日: 2011.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ長々、と八巻目。 本巻は、いよいよその展開が、速度を上げる。 正直に言うと、登場人物の名前とか、、だいぶ追いついて無い@@ 行き着くところは、やはり巌流島。 諸説あるも、吉川英治で描かれるのは、努力人間 対 天才。 結末は、果たして。 個人的には、吉川宮本武蔵は、前半がハラハラドキドキしたなぁ。 さて。本当の武蔵を知るべく、五輪書を手に取ってみようかなぁ。
0投稿日: 2011.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ宿命の二人・武蔵と小次郎は遂に船島にての決戦に臨む。今まで出会った人の恩を受け、そこにいる二人。再び彼らに会うのはいずれか―。 武蔵と小次郎の果し合いで幕を閉じます。試合に出る前の、お通との別れが特に心にきました。その後故郷に戻り、二人して幸せに暮らしたことでしょう。 又八が父親として還俗していくのも良かったです。今までさんざん不甲斐ないところばっか見ていたので(笑)、感激もひとしおでした。 長編ですが新聞小説なのでさくさく読めます。お勧めします。
0投稿日: 2010.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ一巻~八巻全部の感想 コミック「バガボンド」を二十巻ぐらい読んでから、この本を手にとりました。コミックで、ある程度人物をイメージできてたので、長いなが~い長編でしたがサクサク読めました。 武蔵、お通、又八、城太郎、吉岡、お杉婆、朱美、佐々木小次郎もろもろ、それぞれの視点からのストーリーも描かれおりよかったですね。 お通の武蔵を想う恋、武蔵に異常な執念を燃やすお杉婆、武蔵と親友であった又八の裏切り、嫉妬・・・ コミックと違い(原作だからそれはそうか(笑))、佐々木小次郎は高慢で憎らしいキャラクターでいかにも悪者という感じでした。さすが、最後のラストボス(笑)武蔵と最後の闘いは、あっさりでしたが、あっぱれな敵でしたね。 「小次郎、負けたりっ」の言葉は有名!読めば凄さがわかります!!
0投稿日: 2010.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ~内容(「BOOK」データベースより)~ 当初、二百回ぐらいの約束で新聞連載が開始されたが、作者の意気込み、読者・新聞社の熱望で、五年がかり、千余回の大作に発展した。一度スタートした構成を途中から変えることは至難だが、さすがは新聞小説の名手。ただし、構成は幾変転しようと、巌流島の対決で終局を飾ることは、不動の構想であった。作者が結びの筆をおいたとき、十二貫の痩身は、十貫台に―文字通り、鏤骨の名作。 ~~~~~~~~~~~~~~~~
0投稿日: 2009.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ最終巻。最後に集まった者達をみれば、今まで武蔵が歩んできた道に満開の花々が咲いているようである。巌流佐々木小次郎との試合。心して読むべし。宮本武蔵を読み終えた。この書物は心のバイブルだ。いかに人間が自分と戦っていくか。その苦悩を如実に描いている。この本を読む事で心の修行になるに違いない。
0投稿日: 2007.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ三国志は仲間とはを教えられ、武蔵には個人とはを教えられました。巌流島での戦いが一般的ですが、私的には武蔵の心の葛藤がたまらなくいいんです(笑) 武蔵の神様に対する「神を尊び神に頼らず」、、、 凡人にはとても言えません。 お通さんも理想の女性だったなあ。
0投稿日: 2004.10.20
