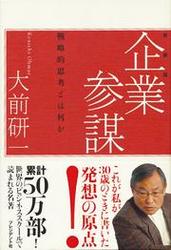
総合評価
(79件)| 23 | ||
| 27 | ||
| 18 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前研一さんが若かりし頃マッキンゼーに入社したての時期に、メモ書きしていたものをまとめたものだと冒頭に紹介されています。コンサル会社に入社してまもない社員が本を出版し、またそれがマッキンゼーの売り上げにも貢献していたようで、本国からも色々と横槍が入ったようです。内容は、ビジネスの本質を捉えるための手法などが、理路整然とわかりやすく書かれています。今ではフレームワークが構築され当たり前になっているものも、当時の大前さんの言葉で説明がされています。 私の読んだものは、2003年の第11版なので(表紙がクリーム色)、新装版とは多少違うものかもしれません。
3投稿日: 2026.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ変革しなければならないのは個人であり企業だが,個人や企業が変わるには「こうすれば変わるのだ」という「気概」が必要になる。ポイントは (1)目的地に達した場合,守り抜けるものでなくてはならない (2)己の強さと弱さを常に知り抜いていなければならない (3)リスクをあえてとる局面がなくてはならない (4)戦略に魂を吹き込むのは人であり,マネジメントのスタイルである である。経営者が備えるべき先見性の必要条件として事業領域の規定と明確なストーリーの作成だけでは不十分で,自らの経営資源の配分にムダがなく,また原則に忠実で,かつ世の中の変化に対しては原則の変更をも遅滞なくやっていくという十分条件が備わっていなければならない。 内容については素人にはちょっと難しい。
0投稿日: 2025.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ2025年2月22日、YouTubeで「本を読むこととお金持ちになること」と検索して出たショート動画「保存必須!賢くなれる本3選」のコメ欄で、皆がおすすめしてた本。 コメ欄より:lssue drivenと企業参謀はどこ? https://youtu.be/zW1jx6LS4ko?si=EpTXRbzGwUm9u9fN
0投稿日: 2025.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業参謀 (講談社文庫) 著:大前 研一 企業や公共機関には、戦略的問題解決者のグループが必要である。このグループは、問題をいかにしてとらえ、いかに解決してゆくかということに対する専門家である。問題の解決ではなく、評論家の集団に成り下がってしまった今日のスタッフ部門にたんにとって代わるだけでなく、組織の最高意思決定者のための真の戦略参謀である。 こうした機能は、ほとんどの組織に欠けている機能である。日本をとりまく客観情勢の変化は、「おみこし経営」から「コントロールタワー経営」への変革を迫っている。著者の意図は、この遷移の一助となるような戦略的思考家の像を描いてみることであった。 本書の構成は以下の5章から成る。 ①戦略的思考入門 ②企業における戦略的思考 ③戦略的思考方法の国政への応用 ④戦略的思考を阻害するもの ⑤戦略的思考グループの形成 数年前に読んだものの、非常に難解であったため、時間をおいて再読。やはり難しい。しかし、その難しさの中に本質を垣間見れ、光を感じる。 本書が記されたのは1985年。インターネットはもちろんスマホもない時代にこれだけの「知」が入り乱れ、飛び交い、著者の中で体系的に持論として展開されている。 時代は違えども、芯を食った歯に衣着せぬ物言いそのままの文体は、今でも輝き、今だからより輝いている。今の日本にない、今の日本に求められている、言い切る。そんな、力強さが文字からもその熱量として伝わってくる。 難しいがまた触れたくなる。 数年後にも再度読み直し、再度教えを請いたくなるような病みつきになりそうな一冊。
3投稿日: 2024.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ・マーケットサイズは再び増大することはないか ・当製品市場におけるシェアの決定要因は何か。当社がその決定要因を十分持っているか ・プロフィットツリー ・現状の延長線上に解がない場合の戦略的代替案 1)新規事業へ参入:多角化 2)新市場への転出:海外進出など 3)上方、下方または双方へのインテグレーション(垂直統合):石油精製から上方に行けば輸送、採掘などがあり、下方へいけば有機合成化学、ガソリンスタンド業などがある 4)合併、吸収:3)の統合の目的のためだけではなく、単に製品系列を拡充したり、マネジメント力の強化を図るために行う場合もある 5)業務提携:販売網の共有化、部品の共同購入、技術提携など 6)事業分離:別会社設立による専業化による効率経営など 7)撤退、縮小、売却:事業の切り売りから退却まで、全体のために部分を放棄する ・たとえば耐熱ガラスは、用途から見るとアルミ鍋などと競合しているし、贈答品としてみれば化学調味料や角砂糖と競合しているのである。だからこの場合には500円から1万円までの贈答品市場を関連マーケットとしてとらえなくてはならない、そして砂糖ではなく、耐熱ガラス製品を購入する決定的要因を分析し、この要因に影響を及ぼすような販売方法や製品開発をしなくてはならない ・業種の付加価値マトリックス 国内付加価値率/国内付加価値率に占める単純労働人件費の割合 ・アプローチ 第一段階:必要性の確立 第二段階:潜在力の評価 第三段階:代替案の選考 第四段階:実施計画を立案、実行 ・この業界で成功する秘訣は何か = KSF ・戦略家は頭脳の明晰さではなく、結果のみを問われる淋しい職業である。しかも将軍であれば臨機応変にアドリブで切るのであろうが、参謀は将軍のアドリブが少なくて済むように考え抜いてあげなくてはならない。将軍と、その兵の力量と判断力を評価できなくてはならない ・状況が悪くなるほど、広く見なくてはならないのに、余計狭く見て、もう選択の余地はない、と思い始めてしまう。しかし、万一、目標を「成功」から「最悪の事態を避ける」ことに置換した場合には、様々な選択が自ら出てくる ・大企業で事業部制を取っているところは、形態的に官僚組織を持っている。一方、自由体としての私企業の本来の特徴は、“組織よりは発想”が重視され、予算のうちの可変部分が著しく大きく、状況変化に迅速に対応するという特質を持っている ・戦略という言葉は、戦争における勝利に至る計画をさしているのであろうから、第一に相手がいなくてはならない。したがって企業における戦略計画においても、当然その大前提は競争相手が存在し、その競争相手に対し相対的に有利になるような、かつ、その有利になり方が最も効率的であるような方法を模索しなくてはならない。 ・お客様の要望に沿って製品系列を拡充し、少ない経営資源をさらに薄く広げてすべての前線で敗退することは極めて常識的な帰結なのである ・インスタントカメラのフィルム数を20枚から24枚に増やすことにより「なんとはなしにフジ」のイメージに対して少なくとも一瞬のためらいを注入することになった ・戦略的自由度(強化できるオプションの軸)を整理し、打ち手を実現するための費用とその効果をプロットすることで、単細胞的に一つのことばかりを考えずに、それぞれの方向に対して対策ができる ・戦略事業ユニットの究極の姿は、戦略的自由度に沿って存在している既存の組織の軸を、すべて束ねた形でくくってしまうこと。逆にいえば、戦略的自由度が最も大きくなるように事業単位を包み込んでやる必要がある ・いかなる勇者といえども、市場の構造変化を予知し、対処するためには、己の強さと弱さを常に知り抜いていなければならない ・どんなに成功している事業でも、かならずその由ってきたる理由というものがあるはずで、これを見失って経営者の欲望の赴くままに進み始めれば崩壊は疑いない。このため、先見性のある経営者なら、自分はどのような顧客のために、どのようなサービスを提供し、どのようなメカニズムで収益を上げているのか、ということを寸時も忘れることはしないだろう
0投稿日: 2024.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ・参考図書指定科目:「経営戦略論」 <OPAC> https://opac.jp.net/Opac/NZ07RHV2FVFkRq0-73eaBwfieml/cZSQplUz61n9jgUjswjXy2xFvPh/description.html
0投稿日: 2024.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ〈書評〉 戦略とは何であるか、参謀とはどうあるべきか、企業はどのような体制で企業戦略を作り実行していくべきかというテーマについて、考え方のエッセンスと、エッセンスを具体的なケーススタディに落とし込んだノウハウが書かれている。しかし、著者も言及しているように前者(エッセンス)が重要であり、後者はケースバイケースのため枠組みとしては利用できるが、紹介している型をそのまま当てはめる既製服のよう使い方は想定されていない。 本書が書かれた時代と今では社会背景などは大きく異なるものの、問題解決/戦略的思考の手引きとしては、現代でも充分に活用できるエッセンスが散りばめられていると思う。 〈メモ〉 ・「戦略的」=事象を本質的な境界線を頼りにバラバラに分離させ、自身の目的達成に有利になるように組み直し、攻めに転ずること。 →「本質的」な分解と再構築とは何かを考える ・企業戦略の立案において、自社状況などの内部に目を向けるのはもちろん、市場や競合他者などの外部にも目を向けて、分解と再構築の見通しを立てる必要がある。 ・特に、市場における「KFS」が何にであるかを掴むことが最重要事項の一つである。 ・参謀心得 →「If」を恐れない:常に代替案を探り、どんな状況にも対応できる構えを取るべき。(※日本人は古くは中国、近代では西洋などの先行事例への依存、そして言霊的なシャーマニズムに由来して、「もしも」に対する準備をする慣習が薄い) →完璧主義を捨てる:完璧な戦略は存在しない(無限の資源が必要)。競合相手より一枚上手を行くだけで充分。 →KFSには徹底的に挑戦する:二項の完璧主義を捨てるに反するように見えるが、KFS、戦争におけるセンターピンが何であるかに関しては、妥協せず試行錯誤を繰り返して探り続ける。 →制約条件に制約されない:「何ができないか」ではなく、制約条件を取り払った状態で「何ができるのか」を考えた上で、制約条件を突破するためにはどうしたら良いかを考える。 →記憶にたよらず分析をする:惰性や常識にとらわれず、本質的な分解と再構築に向き合う。
0投稿日: 2024.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ1975年出版てすごいな。32歳だったらしい。 なにかで「コンサルをセールスするための営業資料」を狙ってたのじゃないかと読んだが、そんなに胡散臭さもなく、大前健一節みたいなものも胡散臭くない程度に入っていて、とても面白かった。(料理に物を例えるケースはよく見るが、食品の腐敗を未回収投資と呼んだり、償却損と呼んだりする、異様な具体性に笑った)
0投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ基礎知識は中小企業診断士の内容と一緒だけど、実際に理論を使ってたひとの話だからわかりやすい。 冒頭のppmらへんは面白かった 後半は流し読み
0投稿日: 2023.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者として、企業戦略の定義(他社と差別化できる目的地から逆算した、競争力を活かした攻め方)を顧みたのと、改めて自社の分解とKFSの言語化をしたくなった本。
0投稿日: 2023.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログオリジナルの本は40年以上前に書かれたものであるが、それでも今なお、変わらない企業戦略の本質が描かれている。 企業がどういう戦略を取るかを考える上での考え方についてまとめられている。
0投稿日: 2023.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦略的思考とは、既存のシステムをものの本質に基づいて分解した上で、各々の持つ意味合いを自らにとって最も有利になるように再構築、攻勢に転じるやり方である 戦略の基本は、世の趨勢を見極め、うまく利用し、競争相手との差が最大になるよう自社のケイパビリティを最大限活用する そのため、製品・市場分析は肝要
0投稿日: 2022.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解できないことが多かった。印象的なことはKFS。これを考えることは今後社会人とて、ゲームとて何でも重要なことと思える。また読み直したい。次は理解できるように。
0投稿日: 2022.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ中期経営戦略の重要性 全員が会社の将来のためを考えて迷う時間 一見いい気がするが、多すぎると議論する時間無駄 各自に目標を与えるて迷いを無くす意味で重要 下記をアクションとして定めました。 ・企業活動を分解してKFSを掴む KFSには徹底的に挑戦せよ ・原価低減を考えずに、販売改善考えても効果が薄い その掛け合わせで利益が大幅に改善される https://docs.google.com/presentation/d/1OMI50zQIZlGu2FYSPOhltAq69vwhn79tURDpbUCGE5E/edit#slide=id.g1132f716a5a_0_16
0投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦略的思考家のKFS=Key Factor for Success=成功のカギ思考が、とても為になり、どのレベルのビジネスマンにも共通する必須な思考法だと感じた。
0投稿日: 2021.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・ものの本質を考えるために、設問のしかたを解決志向的に行うこと。 ×「残業を減らすにはどうすればよいか?」 →ありきたりな回答しか出てこない。 ○「当社は仕事量に対して十分な人がいるのか?」 ○「当社は仕事の量と質に対して人間の能力がマッチしているのか?」 ×「売り上げを伸ばすためにどうしたら良いか?」 →ありきたりな回答しか出てこない。 ○「シェアが伸びていないのか、マーケットサイズは増大しないのか、シェアを増やす方法ないか、シェアの決定要因は何か」 ・現象から実行計画を立案しないこと。正しくは、現象→グルーピング→抽象化→アプローチ設定→解決策と思われる仮説設定→分析により仮説の立証または反証→結論→具象化→実行計画立案→実行。 52マーケの強い会社は分析をルーチンワークで行えるよう、一定間隔で情報収集をやっている。 分析のための情報収集を断片的に、思い出したようにやっている会社はマーケティングがあまり得意ではないはずで、断片的な分析や知識では正しい経営戦略は出てこない。万一できてもそれは運。必勝を期す戦略的思考家のものではない。 183 KFSについては徹底的に挑戦する 189何ができないか?と考えるかわりに何ができるか?と最初に考えること。そして、その「できる」ことを「できなく」している制約条件を一つずつ執拗にはぎとる戦略を考えていく (まだ途中)
2投稿日: 2021.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業分析や市場分析の観点で大変勉強になる本だった。 ただ、一回では読み解ききれなかった部分も多いので、もう一回読みたい。 特に、市場の見方についてはとても構造的にまとめられている本だった。
0投稿日: 2021.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログレジェンドコンサルタント大前研一の代表作にして、コンサル界の古典とも評される本著。 著者の若手時代のメモ書きがベースになっているだけあり、内容は抽象的な思考姿勢から、実践的な理論とケーススタディまで多岐にわたり、ジャンルレスな一冊と言える。 理論自体は高度なものもあるが、図解も多く、何より非常にロジカルな論理展開なので自分は理解しやすかった。特にPIMS、PPT、戦略策定プロセスは興味深い。 また読み返して、内容を身につけたいと思える一冊だった。非常に良書。
2投稿日: 2021.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ20代で読んだが正直難しかった印象。 30代になり流し読みで再読すると今ちまたに出ている戦略やフレームワークなど 1970年の内容としては大変先駆けだったのだなと思いました。 この書をきっかけに大前さんの本を読むようになった現在です。
0投稿日: 2021.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦略コンサルティングという仕事が一体何なのかを非常に分かりやすく書いてくれてる。 しかも、かなり多くのケースを使って思考のプロセスやら可視化の手段やらを説明してくれているので、テクニック的な部分も学びが多かった。 個人的には情報収集の仕方にも結構興味があるので、その辺りに触れてる本も探してみたい。
0投稿日: 2021.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかく読みにくい、そしてとっつきにくい文章です。本当にコンサルタントが書いたのかと思うほど、読む意欲が削がれると言っても過言ではないです。 と言っても始まらないので、例示や脱線する箇所を飛ばして読み、代わりに自分の身近な話題で問題提起をするなどしてから文中の例示に戻り、自分の解釈と答え合わせしながら読みました。この本の解説者になることが目的ではないので、この本で言っていることを実践しながら読み進めたほうがより良い読書になるかもしれません。 以下紹介 I部は「非線形的思考が戦略的思考の第一歩である」「本質を捉える問題提起をする」「そのためにツリーや尺度を用いる」「これらは企業の中長期的計画や戦略の策定、政治問題へのアプローチへ応用出来る」といった企業参謀が行うべき思考プロセス(手段)の紹介。 Ⅱ部では、常に変化する状況下で「官僚的な」思考停止に陥ることなく、戦略的思考を用いてどのように問題提起し解決案を提示するのかより具体的なプロセスを紹介。
0投稿日: 2021.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。 ずいぶん歳をとってから改めて読んでみると、若い頃には読み取れなかったことがらが思いの外多く、大変勉強になった。 KFSの大切さ、それは名前自体から自明のことだが、戦略的思考家とは、常にKFSが何であるかという認識を忘れない人のことであり、その人は、全面戦争ではなく、KFSに対する限定戦争に徹底的に挑む、 という。 そして経営とは常に相対的にみた状況判断から始まるということ。市場があって、コンペティターがいて、産業があって。そういう情景を見渡せられる人が参謀たりえる資格があるということだろうか。
1投稿日: 2021.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか難しい内容だった。戦略的思考とはどう言うものか、企業·事業がどのポジションにおいて、経営·意志決定すべきかが述べられている。他にも重要なポイントは何か、留意点は何かということなども。 プロダクト·ポートフォリオ·マネジメント(PPM)についてがメインだったと思うので、たくさんの製品や事業を扱っている企業、つまり大企業向けの話っぽいなと思った。 戦略の立案や分析のプロセスについてはどの企業にも参考になるので、実践してみたいなと思う。 とにかく、一読では理解しきれない内容であるから、何度も読み返して、実践して、(出版されてから時間も経過しているので)最新のベストプラクティスを考慮しながら、思考とその実行力を身につけていきたい。
0投稿日: 2021.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ人事、文化、カルチャーに関する記述が薄いのが大企業の戦コンっぽい。 中小は当たり前のことを当たり前にする実行力で詰むのがほとんどなので、この星。 シェアのパーセントでも市場成長率でもない。 中小は自分たち知らない市場があるかどうかだし、自分たちしか取れない市場があるかどうか。
0投稿日: 2020.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書は1975,77年に出版された『正・続企業参謀』を新装版として出されたものである。大前さんの『処女作である「企業参謀」は30歳から31歳の頃に私的なメモとして書き留めたものである。~そのノートを当時のダイヤモンド・タイム社(現プレジデント社)の守岡道明編集長に見せたところ、「おもしろい」ということで出版となった。この本は出版した74年に16万部も売れ、私は32歳でベストセラーの著者となった』という背景がある。大前さんが日立を辞められて、マッキンゼーのコンサルタントとして入社してから、負けず嫌いの性格もあったのでしょうが、徹底的にいろんなコンサルタントや文献を片っ端から調べ、ノートにつづり、いつのまにかマッキンゼーの顔のコンサルタントになっていた。その駆け出しの頃のメモは実に我々にとっても理解しやすく、逆に理解しやすいがために、いっそう難しさを感じてしまう私である。 本書は企業における戦略をあらゆる角度から実例を交えて説明している。その内容については、ぜひ書をとって、ことあるごとに参照されたい。 この場では唯一、『戦略的思考家たることを妨げるものについてのきわめて観念的な(つまり一般論の!)記述を試みたい』と示している『参謀五戒』を紹介させていただきたい。 戒1=参謀たるもの「イフ」という言葉に対する本能的恐れを捨てよ 戒2=参謀たるもの完全主義を捨てよ 戒3=KFSについては徹底的に挑戦せよ (KFSとはKeyFactorSuccessの略。) 戒4=制約条件に制約されるな 戒5=記憶に頼らず分析を 何かを企画しようとする際に、あるいは企業の核として、その戦略を考える際に再びページを開いて、さまざまな角度からの分析を試みたい。 自らが「企業参謀」を目指す人にとっては必読の書である。
0投稿日: 2020.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ旅行パンフレット→移動や食事,が旅行中どれくらいの割合を示すか数字で出すと,本来の目的(レジャー)の時間がとても短かった.→それでも,そのほかの理由をつけてみんな消費する(都会を出る開放感とか.)→パッケージの中身を定量的に考えずに雰囲気でお金を出してしまう. こう言った例を他にも見つけて,本質的なものとそうでないものを切り出そうとするとそこに新たな市場がある. →短時間で髪を切るだけの理髪店,旅館etc ある問題に対する問いをどう立てるかから大事 A社は売り上げが乏しい製品を抱えている→ ×「売り上げを増やすにはどうしたら良いか」 ○(例)「売り上げが伸びないのは,シェアが低いからか?」 →Yes,Noで答えが出る, どちらに転んでも次に進める
0投稿日: 2020.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログかなりの古典にしては今読んでも納得感はある。先見の明とはこういうことかと感心するが、如何せんちと難しすぎて、というか実践に取り入れづらく、挫折。
0投稿日: 2019.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ上司オススメの一冊 【ざっと内容】 大前研一当時の経済の見方や組織運営の仕方がギュッと詰まった一冊。抽象的な考え方から具体的な指標の見方まで幅広く触れられている。初版は1999年でそれ以来29刷もされておりロングセラーとなっている。 【こんな人にオススメ】 ・組織の中心人物、特にNo.1,2の人 【感想】 正直、自分にはまだちょっと難しかった……逆に本作をしっかり理解するためには普段からもっと大観的に組織を見る必要があるなと改めて感じた。 戦略的な組織運営における考え方は参考になることが多かったので、組織のトップを目指す方々は是非一読してみては? 数年後読んだら全く違うところに線を引いてそう。
1投稿日: 2019.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ『企業参謀』は不朽の名作だと思う。通算3度目の読書だが、自分自身の戦略思考度が上がったと感じるとともに(初読では論理展開力に圧倒された「イカ漁」も今はやや強引で多少の稚拙と感じるまでになった)、本書を32歳のときに書き上げた大前研一氏の知的水準の高さに驚かされる。 『企業参謀』『続・企業参謀』は間違いなく良い本だが、特に改変もせず合体して単行本化というのは芸がない。文庫化もされているのに。ということで星は3つである。
1投稿日: 2019.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログもはや説明不要の戦略本。 とにかく内容は奥が深く、本を読みなれていないヒトが読むとおそらく最後まで読めないと思います。 難しい内容も多いです。ただ、読むべき箇所は 第3章『戦略的思考に基づいた企業戦略』 だと思う。 ・企業活動ステップと、ステップごとのKFS ・競合との相対的優位性に基づいた戦略 ・新機軸に基づいた戦略および戦略自由度 ・戦略設定時のプロテクション(守り)の必要性 この部分が一番読んで仕事に生かせると思った。 この本はたまに読み返すために手元に置いておきます。 おそらく自分が経営層になった場合は必ず役に立つと思う。
0投稿日: 2019.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代を超えて語り継がれる伝統的戦略論、という感じ。 伝統的大企業が、どのように考え、問題解決にあたるかについて説明するもの。 自分のポジションによって、読み返すごとに新しい知見が得られるのではないか。
0投稿日: 2017.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
企業参謀 経営戦略の本 戦略的思考:事象を分析し、ものの本質に基づいて分解したうえで、自分にとって有利なように組み立てていく思考方法 ・問題点の摘出と解決のプロセス ①問題点の絞り方を現象追随的に実行 ①現象→②グルーピング→③抽象化→④アプローチ設定、必要な手段 →具体的な手段に落とし込む
0投稿日: 2017.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ20170717読了 企業が取るべき戦略について、参謀の立場から論理的かつ客観的に考える方法論について書かれた本。 内容盛り沢山で、概要を知りたいだけならエッセンシャル版で十分。ただ40年前に書かれた内容について、今の世の中の状況と比較すると面白い。日本の総合機械メーカーのポートフォリオの話とか、低成長時代に対する考え方とか特に。 正直、読んだからといって明日から何か実行したり自分が変わったような気分になる本ではないが、企業参謀とは何か、戦略とは何かを知るには良い本だと思う。 ・企業が成功するための要素KFSを、業界、サプライチェーン、時代の状況ごとに徹底的に考えること。 ・分析力と概念を作り出す力を開発すること。「しょうがない」を「しょうがある」状況にするにはどうするか。なぜ?を常に考える。常識を常に疑うこと。
0投稿日: 2017.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ古い本だったが特に時代遅れではなかった 一読では全てを理解するのは難しいが、なるほどと思える所が多々あった 戦略的思考 非線型思考 設問のしかたを解決策志向的に行うこと そのためには、問題の絞り方を現象追随的に行うこと 製品系列のポートフォリオ管理(PPM) 製品・市場戦略とは、実に分析的な仕事なので最初は専門家の助けが必要 参謀五戒 戎1:参謀たるもの「イフ」という言葉に対する本能的恐れを捨てよ 戎2:参謀たるもの完全主義を捨てよ 戎3:KFS(成功のカギ)については徹底的に挑戦せよ 戎4:制約条件に制約されるな 戎5:記憶に頼らず分析を 世の中の「営みごと」はすべて、オン=オフというバイナリー系(二者択一)ではなく、灰色のアナログ系である 新機軸展開方法 1.考え方の転換 2.戦略的自由度 3.技術的ポートフォリオ 戦略的に意味のある計画は、ひとたび目的地に達した場合、守りぬけるものでなくてはならない(プロテクション) いかなる勇者といえでも、市場の構造変化を予知し、対処するために、己の強さと弱さを常に知りぬいていなければならない 真の戦略家は、リスクを避けるのではなく、リスクをあえてとる局面がなくてはならない 最後に戦略に魂を吹き込むものは人であり、マネジメントのスタイルである
0投稿日: 2016.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ【MEMO】 ■戦略的思考とは・・・ 一見、常識となってパッケージとなっているような事象を分析し、ものの本質を見極める事 「設問の仕方を解決策志向的に行うこと」 そもそもその商品はマーケットが拡大しているのか?シェアは取れるのか? 広告宣伝を一生懸命やる・・・解決にはなっていない。 問題点の抽出と解決のプロセス 問題ある事象を並べる→グルーピングする→抽象化する→対策を打つ→具体的な取り組みに落とし込む ・イシューツリー ・プロフィットツリー ■問題解決成功の尺度 ・利益ー売上高利益率、収益性 簿記会計ではなく、管理会計による攻めの会計・・・いかにアウトプットを出すか 【企業における戦略的思考】 ■中期経営戦略計画 ・3年程度が妥当 それ以上は、市場の変化を読む事は難しい。画餅になる。 ・中期経営戦略の立案プロセス 目標値の設定 ⇒ 基本ケースの確率 ⇒ 原価低減改善ケースの算定 ⇒ 市場・販売改善ケースの算定 ⇒ 戦略的ギャップの算定 ⇒戦略的代替案の摘出 ⇒ 代替案の評価選定 ⇒ 中期経営戦略実行計画 ■Product Portfolio Management (PPM) ・低成長時代においては、事業の選択が必要 ・事業マトリックス(業界の魅力度×自社の強さ ・収益を得る時期か?投資をする時期か? ■製品・市場戦略 ・市場(現市場→新市場)市場を拡げるか? ・製品(現製品→新製品)製品を拡充するか? ※現市場もしくは現有製品を軸に拡大するのが基本 1.市場性の動的把握 今後、市場はどうなるか? 2.内部経済の分析 内部資源はどうなっている? 3.競合分析 自社のシェアは今後どうなるか? 4.自社の強さ弱さの把握 顧客視点から見て選ばれるポイントは? 何が弱みとなっている? 5.改善機会の抽出 どこを改善したら、シェアを伸ばせる可能性があるか? 6.改善計画作成 ▪︎参謀五戒 1.参謀たるものイフという言葉に対する本能的恐れを捨てよ。 2.参謀たるもの完全主義を捨てよ 3.KFSについては、徹底的に挑戦せよ 4.制約条件に制約されるな 何ができるか?できない理由は何? 5.記憶に頼らず分析を ※問題解決者…内部の人々の経験と知識に、外部の人間の客観性、中立性、分析力、集中力、実践力が加わる。 これに結果を見届けるまでしつこくねばるという精神が内、外を問わず仕事にたずさわる全員に浸透すれば、百戦危うべからず。 【戦略的に考えるとは】 ・楽観的に見ない ・追い込まれた状態の時こそ俯瞰的に見る ・創造と論理のバランスが重要 ・ベクトルの向きと大きさを考える ・業績評価は、経常利益だけではない。必要な指標を用いる。 ・ミドルの重要な役割の1つはトップに対して現場の生々しい声を伝える事である。 ・PPM法(プロダクトポートフォリオ)
0投稿日: 2016.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログポートフォリオを利用した企業戦略、事業戦略に触れられている。 1975年に売られ、その時から低成長が問題に成っていたんだなって改めて思い知らされる。 戦略というのはどうやって立てていくのかといったアプローチが記載されており、一読の価値はあるように思う。 ・what if この場合どう考えるを徹底 ・完全主義を捨てる ・kfsを徹底 ・制約条件に制約されないこと ・記憶に頼らず分析すること
0投稿日: 2016.01.03名著は色褪せないですね。
名著は色褪せないですね。事例は古いですが、本筋は違和感なく読むことができました。この当時に低成長を予見して話が展開されている点、大前先生の先見の明には頭が下がります。中期経営計画の作成、製品ポートフォリオ管理の基礎を学べる良本。物事を考えるときに、「抽象化」のプロセスを通すことで、問題の本質に解決策を打つという思考は目から鱗でした。当時の勝ち組企業のいくつかが現在苦戦している点、どんな理由だったのか気になるところです。定期的に再読したいと思います。
1投稿日: 2015.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログいまから40年も前の本なのに古さがない。具体例に古さはあるが、企業が抱えている問題については不変。それもどうかという話だが。。。 ひとまず自分にできる自分の部署についての戦略的思考を始めて実践してみようと思う。
0投稿日: 2015.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本がほぼ40年前にかかれていて、かつマッキンゼーへと転職して2年目前後で、かつ大前氏が31〜32歳の時に書かれたというのだから、その本質をつく視点と思考法は、まさに圧巻としか言いようがない。 流行のビジネス書や自己啓発本を読むのも、そりゃおもしろいものだが、やはりこういった長く読み継がれているものは、きちんと手元に置いておいて間違いがない。 http://d.zeromemory.info/2015/02/20/kigyo-sanbou.html
0投稿日: 2015.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前研一30代にして、この企業分析、社会分析をしていたことに大変驚いた。世の中をよく観察し、問題点を見つけ、自分ならどうするのか?どう変革することが将来必要なのかを日々研鑽することで、大前研一にちょっとでも近づけるのかなと感じた。
0投稿日: 2014.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ書いてあることの1割も理解できなかった。財務会計、経営の基本知識を前提とする上に色んな情報がジャングルのように飛び出してくるのでついていけなかった。ただ、考え方としてはこうした戦略思考が身につけば業界といったところは飛び越えて応用できると思えるので、もう少しレベルが上がったら戻ってこようと思った。これを30歳で書いたなら、やはり大前研一はすごい。 ただ昔の本なので、例示が古く、少しイメージがしづらい。
0投稿日: 2014.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営戦略の教科書。巷にあふれる戦略系のビジネス書に書かれていることは、40年前に上梓された本書に、既に全てが書かれている。 とにかく、『現状分析から現在置かれているポジションと、進むべき方向性を導き出し、具体的な実施プランに落とし込んでいく』という戦略策定〜プランニングまでのベーシックな在り方が、これでもかという程細かく、具体的に記されている。その熱量に圧倒される。 本書は『企業参謀』と『続・企業参謀』が一冊となった本でボリュームがあるため、最後の方はちょっとお腹いっぱいになってくる。が、ビジネスマンは読んでおくべきだ。 本書とドラッガー『経営者の条件』、コヴィー博士の『7つの習慣』の3冊を読んでいれば、ビジネスマンとして基本的なマインドはセットされるように思う。
0投稿日: 2014.09.11世界のMBAスクールにて使用されている教科書
MBAコースの教科書として購入し読んでいます。 当たり前のことだから、深く分析せずに、表面だけをみて納得していることって身の回りにたくさんあると思いませんか? それはビジネスシーンにおいても多々見受けられることだと思います。 この本は、そのような問題の解決の糸口を例を挙げ分かりやすく説明しています。 世界中のMBAスクールで教科書とされているからといって、決して分かりにくく難しい本ではありません。 経営とは?戦略とは? あまりよく分かっていない私でも楽しく読めていますので、気になった方は一読をお勧めいたします。
6投稿日: 2014.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業の全社戦略に関する本。 全社戦略、中期経営戦略を考える視点が網羅されている。 今では当然のようになった考え方やフレームワークが多い。 しかし、これは今だからそう感じること。 この本が書かれたのは約20年前。 30年前からこの域に達していたことを評価すべきだと思う。 しかし逆に言うと、20年経っても変わっていない戦略手法は評価できないのでは。。。 一つの真理にたどり着いているのだろうか? 以下メモ 戦略的思考とは、物事を本質的に分解する作業と、それを別の形に組み合わせ、ソリューションを導き出す行為を指す。 本質に迫るためには、解決策的な問いを立てる必要がある。問いを立てるためには、事象を抽象化するプロセスを経る必要がある。 抽象化のプロセスを経るためのフレームワークとして ・イシューツリー ・プロフィットツリー → イシューツリーよりも収益に特化したツリー、そもそも論を展開出来る。ただし、経営に関する問題に限定される。 中期経営計画策定にあたり、登場する考え方 ・PPM ・プロダクトライフサイクル ・製品市場戦略 → かなり良いのでまた読み直す ・SWOT ・What If → もし状況がこうなったら、どの様に考え、あるいは行動、反応したら良いのか? 参謀五ヶ条 ・Ifを考える ・完璧主義を捨てるKFS(Key Factors for Success)を徹底的に ・物事に影響を与える ・制約条件に制約されない ・記憶に頼らず分析 PPMの象限、マトリックスのマス一つずつに対して標準戦略を考える必要あり。
0投稿日: 2014.04.03一段上の目線で物事を考えられる
いわれてみれば当たり前・・・ でも気が付かない という考え方がたくさん載っていてとても勉強になりました。 企業の参謀として、考え方、将来の予測、戦略がわかりやすくまとめられています。 内容に古さは感じられません。戦略の考え方は、古くならないと思いました。
2投稿日: 2014.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ特に尺度分析で財務指標をピラミッド構造でまとめている部分が使いやすい。中期経営戦略の策定プロセス、商品・市場戦略、継続的な差別化の3要因が分かりやすい。今後は、低成長下の戦略部分を読み込みたい。
0投稿日: 2014.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ旧版は読了済み。新装版がKindleで販売されていることから、再読。 ハウツーでなく、ものの考え方の記載が多く、著者が伝えたいのも後者。初版がでたのは、今から約30年前だが、使えない感は全く無し。それは、後者中心の記載故。 問題解決に臨むにあたり、制約要件に目が行きがちな自分にとって、戦略的自由度の考え方が不足していると感じる。これは柔軟性不足を意味しており、この改善が成果をあげるために必須。本年の課題の一つだ。
0投稿日: 2014.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前研一さんが30歳の頃の作品です。当時はMBA的な経営分析ツールなどはまだ一般的ではなかった中で、大前さんがマッキンゼーで自らの思考と体験を通じて身につけ、本書で紹介されている様々な考え方は、確かに深みがあります。 社会環境が大きく異なり、事例も古いのは致し方ないことですが、その分、若干読みにくいと感じました。ただ、実務に照らし合わせて考えながら読み進めることで、なるほど、と思わされる個所が多いです。
0投稿日: 2013.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ数年前に勝って内容が理解出来ず、放置していた本だが、なぜ、名著なのか少し理解出来た。 もう少し経営の知識をつけたうえで、再度トライしたい。 2013/9/23
0投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスブレイクスルー大学院に興味を持ち、学長である大前さんの代表作である本社を読んだ。実際にMBAのコースでも教科書の一つとして使われているようです。 豊富な例がありとてもわかりやすい。が、わかるとできるは大違い…30年近く前の本であるが故に大前さんの先見性の高さにも驚かされる。 また、日本の会社組織の課題に欧米の手法を単純に当てはめてもダメというスタンスにとても共感するとともに当時から変わっていないという事実にも愕然とした。
0投稿日: 2013.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ目的 中計策定に貢献する意見を出すため。 投資判断改善に活かす意見を出すため。 混然一体としたものを分析するには一度それを解きほぐし、解きほぐされた個々のものが全体に与える影響を計る。あるマーケットにおける売上が落ち込んで来た場合は、マーケット全体のパイが減少しているのか、それとも自社の売上だけが減っているのかを見極め、対応に至る。 設問の仕方を解決策志向型に行う。例えば残業を減らすにはどうしたらよいか?ではなく当社は仕事量に比して充分な人がいるのか?という風に。 計画を立案ではまず目標値を設定し次に現状のペースが続いたらどうなるのかという基本ケースを策定する。ここの前提、定量化が肝になる。その上で目標と基本ケースを埋めて行くためにコスト提言、売上の向上、利益率の改善、新規事業等の目論見を立てる。 競争に勝つには「相手よりも一枚上をいく戦略をタイミングよく実施すること」。実施を決断する上では何かを失うことを恐れず、完璧主義を捨てること。 物事には成功の主要因となるKFSが存在する。KFSが何であるかを認識し、これをうまく管理、コントロールする。
0投稿日: 2013.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業経営をやる上で、企業トップが持つべきマインドセットを教えてくれる本であり、小手先のテクニックを教授する類いのものではない。コンサルタントが根付いていなかった当時の営業的意味合いがあるのだろう。
0投稿日: 2013.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ入門編では物足りなく、本編を読んだのだが、なかなか難しく読了までにかなり時間が掛かった。 大前さんの思考法というのはとても新鮮で、70年代に書かれたものなのに全然色あせてなかった。 戦略的思考を行うフレームワークとしては有効だと思う。 ただ、表現が難しく、なかなか頭に入らなかったので、繰り返し読む必要があると思う。
0投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ1回目読み終わった。刺激は受けたが難しすぎる。戦略に至るプロセスへの考え方が大事なのは分かるがそれが難しい。勉強し直そう。何回も読む必要がある…。
0投稿日: 2012.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前研一氏と本書についてその高名をしらないものは、本書の題名「企業参謀」を見たときに、まるで小説のような題名であることから、一見自伝的書籍かと思うかもしれない。 しかし、「企業参謀」の題名の横に「戦略的思考法とはなにか」と書かれているように、これは戦略的思考というものはどういったものであるのか、もしくはどのように思考する ことが戦略家であるのかという、くしくも洋書で翻訳された題名「Mind of the Strategist」に帰結される内容である。 本書は、発行以来、数多くの言語に翻訳され著名なビジネススクールにおいても教科書的に機能している戦略的思考に関する書籍で、内容についてはあえて発行当時1975年当時 から変更を加えていない。さらに大前氏は、本書を著作したときにおいて未だ30代前半であったということであるので、如何にその戦略家たらしめるゆえんやマッキンゼーという 組織の強烈なまでの成長速度(当然、大前氏はその組織で十分に機能していたわけである)を促す環境であったかが伺い知れる。 本書は戦略的思考法について、ビジネスにおける想定や実例、または国政への利用法と多岐にわたる為、書評として網羅的なものを作成することが非常に難しい。 また、内容が安易ではないので、Amazonの書評にも多くあるように数回は読み込む必要がある。既に5回目という人物もざらにいる。 1回目を読了した上で、直観的に影響を感じざるを得ない個所をいくつか紹介して初回の書評としたい。 まず基本的なことではあるが、戦略的な思考を行うに至っては精緻で詳細な分析をもってそれのベースとしなければならないということである。他者に説明する段になって、それを 気付き考え直すようでは戦略的思考法ができていないという訳である。 また、戦略上仮説や仮定で設定した数値は、ある程度推定であっても現実の数値に近いものとする為には、その仮定とした数値をある一方向から算出するほかにもう一方から算出 することで、その仮定した数値の蓋然性を向上させ大枠の事実と近似したものを取得する必要があるという。これには、思考と分析の”しつこさ”が必要で、おそらくこれをことある ごとに実践しているのとしていないのとでは、要求水準に対する結果つまりはアウトプットの質が異なるのであろう。 こういった、実際にトップコンサルタントがどのような過程や結果をもって、サービスとしているのかを感じることが出来る事は大きいし、実務上求められる要件以上をアウトプット しようとする実務担当者には非常に有益なものであろう。 これを端的に表現しているのが、著者自身がケーススタディを自ら構想し解決策を自ら提案する部分で、そのストイックさもさることながら、実例に基づく思考経路を理解するには もってこいである。このケーススタディを聞いただけで、本書への興味関心がわくと思うのでさわりだけ紹介すると、ニュージーランド沖に日本イカ船団が大量にイカがとれるという ことで大挙したものの時間経過とともに乱獲が原因でイカが捕れなくなった。さらにはニュージーランド側から日本政府水産省へ、漁船行動に対するクレームがあがっているという。 この解決策とその導き方を戦略的な思考法で、考察しようというものである。 こういった、ケース毎に解を模索していく中で、2,3度著者が注意喚起している事にフレームワークに関する事柄がある。 課題解決や事業戦略に用いられるフレームワークは、他社の戦略で用いられていることを見た経験や実際に利用してみて間が抜けたものになった経験というのはビジネスに携わる場で は少なからずあると思われる。課題解決法には、あるパッケージ化された方法論というのは存在せず、基本的にはオーダーメイドで思考、分析されるものであることを著者は強調して いる。 BCGの考案した、PPMについてもより詳細に説明し、如何に精緻で"しつこい"分析の上に利用する事が望ましいのかGEとBCGの採用事例から紹介されている。また著者(マッキンゼー) はこのPPMを2×2の4つの分類ではなく3×3の9つの分類にわけ、ポジショニングに対してそれぞれの戦略を当てはめるということをさらに製品系列毎に実践するような多大な労力を伴う うえに非常に精緻な分析がなされているものを紹介している。 さらに、KFS(Key factor for Success:成功のカギ)というのが、新規参入や事業には存在し、多角的な視点がなくKFSを分析せずに安易な考察でもって失敗に陥った多角化における 新規事業例をタービンメーカーの事例等を用いて紹介し、KFSをつかむことが大きく事業の成り行きを左右する事を知ることができる。 最後に、本書を読んでいて非常に気付きが多い事がわかるのであるが、これをもって思考法の練習が開始されるのであって膝を叩いて終わるのではないことは言うまでもなく、それを 考えると数回読み込んで実践に移していかなければ身に付かない内容であるのは明確である。 よく大前研一氏自身がかつてメディアへの露出も多く、思想が合わないので本書を手に取ることを躊躇される方もおられるかもしれない。 実際に、大阪市長である大阪維新の会が参考にした、大前研一の平成維新の会の根源的な思想である小さな政府を論じる片鱗が本書においても見え隠れする。 企業においても、戦略的思考に基づく戦略立案集団は特に実践的で有能な集団にのみ携わらせるべきであるといった個所は、特にそうなのかもしれない。 しかしながら、大前氏は政治的な思想は別として戦略立案の側面ではプロフェッショナルであることに違いはない。 そのプロフェッショナルに触れることは、間違いなく自信を磨き上げることの手助けとなるであろう。
1投稿日: 2012.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わるまでにちょっと期間をかけてすぎたので、記憶がかなり薄れてはいるけど。とりあえず。 初めて大前研一の本を読んだ。ありがち、といえばありがちな洞察を加えているのかもしれないが、この本が書かれた年代を考えると恐ろしく先見の明があると思う。ありがち、と感じるのはむしろこの本を元にしている本が多すぎるからなのかもしれない。 自分がなんとなく読んでいた本は、この本を元にして簡単に書いてあったからわかりやすかったんだなぁ、と思う。原著?だからかやや硬い表現があったりして読みにくかったりするが、面白い。 次は、きちんと時間をとって短期間で読み直してみたい。
0投稿日: 2012.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
10年以上も前に書かれたとは思えないクオリティの大変素晴らしい本。大前研一氏の完成度と洞察力をもってして生まれた本。名著以外の何物でもないと思う。素晴らしい。 名言 ・理想を頭に描くことで、制約条件が理想に向けての障害物に変わる。 ・ラインの短期利益追求から中期的利益の追求へ。 ・スタート時点で大切なこと「設問のしかたを解決策志向的に行うこと」そもそも論を問いにしてみる。どうしたらよくなるかではなく、そもそも人は足りてるのか、そもそも仕事の量と質に人材の能力がマッチしているのかなど。 ・問題点の絞り方を現象追随的に行うこと。ブレストなどで現象摘出→同類項をまとめる。→さらにまとめ共通する問題点をさがす。(「抽象化プロセス」)これを行わないと、Q&Aの短絡した表層的な解決にしかならない。現象の問題点が何に帰属する問題であり、何に深い関わりあいがあるのか。これを理解しないと新の解決策はない。 本質的問題解決のプロセス 現象→グル―ピング→抽象化→アプローチ設定→解決策と思われる仮説設定→分析により仮説の立証・反証→結論の導出→具象化→実行計画立案→実行 ・中期経営計画戦略立案プロセス 明確な目標値の設定→基本ケースの確立(現状そのままやるとどうなるか)→原価低減改善ケースの算定(コスト改善ケース)→市場・販売改善ケースの算定→戦略的ギャップの算定(オペレーショナルな努力の限界値と目標値の差)→戦略的代替案の摘出→代替案の評価算定→中期経営戦略の実行計画 ※どんな仮定を置いているかは明確にすることが必要 →その部分のみを変更して処理できる。 ・戦略的代替案例①新規事業参入、多角化②新市場への転出、海外市場など③上方、下方へのインテグレーション(垂直統合)石油だと情報は輸送、採掘、下方は有機合成化学、ガソリンスタンド ④合併・吸収 ③のためや製品系列の拡充、マネジメント強化など ⑤業務提携 販売網共有化、部品共同購入、技術提携など ⑥事業分離 別買者設立による専業化による効率経営 ⑦撤退、縮小、売却 事業の切り売り、退却、全体のために部分を放棄する ワクを狭くすると抜本的戦略が出てこない・広げるとリスク現実性が発散する。称事業部からバラバラに出てきた寄せ集めはだめ。 ・SBU事業戦略ユニットを作る際はKFSを共通項として構成するべき。 ・多角化は多様化、新市場、地固め以上に必要な時に初めてするべき。 ・製品、市場戦略策定のためのプロセス ①市場性の動的把握(市場のサイズと動態、成長性を知ること)→②内部経済の分析(売上高、前者に占める割合、限界利益、商品別限界利益→傾向とその理由の把握。損益分岐点、付加価値分析→どの工程の付加価値が高いか。)→③競合状態の把握(商品サイズ別のシェア)→④KFSに照らしたわが方の強さ、弱さの客観的理解→⑤改善機会について仮説の抽出評価→⑥改善実施計画作成、実施→⑦モニター、必要な軌道修正 ・戦略実践時には具体的なタイムスケジュールの作成が大事。 思考力を極限まで用いて、相手の動きを予測して戦略を立案する。 ・参謀五戒 ①ifという言葉に対する本能的恐れを捨てよ。 ②完全主義を捨てよ。相手よりほんの一枚上をいく戦略をタイミングよく実施することが勝利のカギ。③KFSについては徹底的に挑戦せよ。常にKFSが何であるかという認識を忘れない。全面戦争ではなく、KFSに対する限定戦争に徹底的に挑む。④制約条件に制約されるな。理想を描くと制約が障害に変わり、どう取り除けばいいかを考えるようになる。⑤記憶に頼らず分析を。しょうがないことを週1つ取り上げて、自分ならどう「しようがある」ようするかという策(概念)を展開してみる癖をつける。 玉石混交の問題。 負け戦をしているのに、ホッケースティックで「善戦している」と通報すると誤った判断に陥ってしまう。⇒妥当性の検証が重要。善戦からの情報に常識のスクリーニングにかける。 高速道路の鹿 早く走ると視野がどんどん狭まってしまう。経営者はごめんなさいを言った後の状況の方が、破局に至った後の断頭台よりいいと考えないといけない。 日常生活における絶え間ない空想力と、論理を組み立てる訓練に裏打ちされたものでなければならない。 製造の中心が移っているのであれば、そこに資本を投入しておくべき。 低成長⇒判断ミスの融通性が失われてきた。分析を重視し、個人の情や勘の入る余地を 少なくして、分析に携わった全員の責任になるようにする。 財力が強い会社の特徴 ①安定したプラスのキャッシュフロー②外部資金調達能力が高い③自己資金比率が高い 市場競争力の強い会社の特徴 ①市場占有率が高い②コスト管理がうまい③生産体制に柔軟性がある④特殊技術や独自の販売網を有する 競争相手との相対的力関係を変化させる方法 ①経営資源配分において、相手より濃淡をつけ、シェア収益性で優位にたつ。 KFSに基づく企業戦略 ②競争条件が違うため優位に立つ 技術、販売網、収益、資産内容の相対差 相対的優位性に基づく企業戦略 ③新機軸を貫き相手に追従させないことで優位。 新機軸展開による企業戦略 新機軸を求める方法 ①考え方の転換②戦略的自由度③技術的ポートフォリオ ①常識を疑い、疑問に結び付ける。 最も本質的とされている仮定を列挙し、仮定が依然として正しいか、仮定がなければ事業が成り立たなくなるのか考えてみる。 戦略立案の底流となる思想 ①戦略的に意味のある計画はひとたび目的地に達した場合、守りぬけるものでなくてはならない (プロテクション) ②いかなる勇者といえども、市場の構造変化を予知し、対処するために己の強さと弱さを常に知りぬいていなければならない。 ③真の戦略家はリスクを避けるのではなく、リスクをあえてとる局面がなくてはならない ④最後に戦略に魂を吹き込むのは人であり、マネジメントのスタイルである。 先見性の四つの条件 ①事業領域の定義が明確 ②現状の分析から将来の方向を推察し、因果関係について、きわめて簡潔な論旨の仮説が述べられている ③選択肢のうち少数のみが採択されている。 ④基本仮定を覚え、状況が変化した場合を除き原則から外れない。 世の中の力の動きを見通し、提供すべきものを考えるヒント ①自ら定義した事業領域で対象ユーザのトータルエコノミクスを徹底的に分析する ②サービスでは時間、手間、便利さの分析 既存のものをなるべく活用。規模の経済の閾値以上に一気にもってく ③既存システムの存立要因を理解し、これを揺さぶるか活用する。 先見性のある経営者なら、自分はどのような顧客のためにどのようなサービスを提供し、 どのようなメカニズムで収益をあげているのかを忘れない。
0投稿日: 2012.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の時間を占有する業であるということ。その業を徹底することが人生の喜びにあることに違いない。 ん〜。その通りなんだろうな。大前さんすごい!
0投稿日: 2012.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
経営戦略に関する教科書的1冊 氏のコンサルティング経験を元に戦略的思考方法からPPMの実際にまで多岐に渡り企業経営の基礎を解説。 経営企画、経営戦略に関わる業務に携わる方は必読。
0投稿日: 2011.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前氏の本を後2冊読む、としていた内の1冊。 企業参謀…すなわち企業の経営戦略、ひいては人生を戦略的に生きようとする人を対象に、「戦略的に考えるってこういうことだよ、特に企業経営においてはこうだよ」とシンプルに解説している本です。「考える技術」と言ってることは変わらない。 モノを分解して考えることを基本に、市場と自社をポートフォリオにして、そこに目的を加味して経営戦略を立てる。簡単なようだけど、このポートフォリオを組むには自社の資源を隅々まで把握する必要があり、物事をボカす癖の日本人はここが弱い。 戦略の教科書といった評判のとおり、上記のような基本的なことがシンプルにわかりやすく解説されています。 といいつつ、まだまだ新米な自分には腹に落ちにくい部分もあり、飛ばし飛ばし読みました。今後、営業・マーケティングを担っていく上で、煮詰まった時に読み返したいと思います。
0投稿日: 2011.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ21世紀に残したいビジネス書にも選ばれている有名な一冊。 かなりボリュームもありましたが、今や当たり前に使われているフレームワークがここで紹介されております。 この本が最初に出たのが30年以上前。 今読んでも全く色褪せません。 世界中でベストセラーになったのも納得の一冊です。
0投稿日: 2011.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分には非常に難解で、読むのにえらい時間かかってしまった。 これを29歳(だったかな?)で書いたというのだから、大前研一はすごいと言わざるを得ない。 電車の広告を見てビジネスモデルを考えているというのも分かる。 経営者だったり、少なくともそういう人になろうとしていたり、経営企画、営業職の人にはいいかもしれないが、そうでないと日々の仕事にどう活かしていいか分からない。 やっぱり分かっていないから、と言えばそれまでだが。。。 またそのうちリベンジしよう。
0投稿日: 2011.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログもはや古典の名著の風格アリ。 古い(実際挿絵は古い)が、色あせない。 勉強会でまた(しつこく?相変わらず?)やります。
0投稿日: 2011.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は私が生まれた年に書かれている。しかし全く古さを感じない。 近年の大前研一の著書よりかなり骨太の内容となっている。 将来の仕事のことでいろいろ考えた時期がここ最近あり、 その流れでこの本を購入していた。 やっと今後の自らのスタンスと方向性が見えてきたので読み進めた。 昭和50年のときに既に当時の日本経済を、 「戦後のGNP祭り」は日和見主義と 権限移譲ではない多頭責任性が原因とズバリ指摘している。 今日でも「よりかかり的」なものの見方・考えが潜んでいることが 原因となっていることを多くの方が感じるところだろう。 それを打破するための思考法が事例を織り込んで紹介されている。 ■戦略的思考 対応しつつ考えること。 作業を分解し本質をまずつかみ、設問を解決策志向的に設ける。 内部経済の分析・管理会計を実施する。 ■参謀五戒 (1)参謀たるもの「if」という言葉に対する本能的恐れを捨てよ →手持ちの代替案を持ち続ける。 (2)参謀たるもの完全主義を捨てよ (3)KFS(key factor for success)については徹底的に挑戦せよ (4)制約条件に制約されるな (5)記憶に頼らず分析を →ただの知識ではなく、事実・データに基づく分析力を培い、 結果的に「概念」を作り出す力をつけること ■戦略的計画の核心 (1)目的地に達した場合、守り抜けるものでなくてはならない protection 計画の視野planning horizonが狭くてはいけない。 (2)市場の変化を予知し、己の強さと弱さを常に知り抜いていなければならない (3)リスクを避けるのではなく、あえてとる局面がなくてはならない (4)戦略に魂を吹き込むのは人でありマネジメントのスタイルである 謀略であってはならない 経営者が備えるべき、先見性の必要条件は、 事業領域の規定と明確なストーリーの作成とである 自らの経営資源の配分にムダがなく、 また原則に忠実でかつ世の中の変化に対しては 原則の変更をも遅滞なくやっていくという十分条件が必要。 ........... 来年は落ち着いて行動し、 飛躍の時機を得て成長したい。
0投稿日: 2010.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や聴きなれたビジネスWordだが、わかり易く並べられているのが、流石。頭を整理したい時に読み返すことにする。
0投稿日: 2010.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ2010/05/15 大前研一さんのことはつい最近知りました。 きっかけは、あるWeb siteで見た次の言葉。 『人が変わるには三つしか方法はない。 時間配分を変えるか、付き合う人を変えるか、住む場所を変えるかだ。 もっともおろかなのは決意を新たにすることだ』 決意を新たにすることの無意味さは身をもって知っているので、 この言葉にはとても共感しました。 本著は出版されてからかなりたっていますが、 まずは代表的な著書であるこの一冊を読んでみたいと思います。
0投稿日: 2010.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ1年半前、某有名コンサルティングファームにインターンに行った時、 「戦略的思考」というものを全く勉強していなかったので、恥をかいた ということで今さらながら、読んでみた とてもよくかけている本である まったくもってマッキンゼー出の人間はわかりやすい話の展開をするな、と再確認 図もとてもシンプルでわかりやすい ただずいぶん昔に書かれたものなので、例とかがちょっと古いのは仕方ない そして、自分の知識も到底及ばないので、彼が言わんとしていることを吸収しきれていない 社会に出る前にこの本と出合えてよかったが、 ドラッカー同様この先何度も読み返す必要があるようだ 一度は読無べきである
0投稿日: 2010.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログBBT(MBA)経営戦略論のメインテキスト。 経営戦略、企業戦略の基本的考え方。 30年以上も前に書かれたのに、いまだに経営戦略の基本書として各方面で読まれているすごい本。 PPM(Product Protfolio Management), KFS(Key Factor for Success), SDF(Strategic Degree of Freedom)等の考え方。
0投稿日: 2009.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ既に古典。3回目の読み直しでしょうか。 ほんと、30歳そこそこで、どうしてこんな本が書けるのか。自分には理解不能です。 ソリューションビジネスに身をおく人間として、考え方、心構えはいまでも通じるものがありますね。 著者の本は何冊か読みましたが、デビュー作であるこの本が一番読み直すことが多いです。 コンサルタントとしての基本を身につけ、そして適宜思い出すのにGood。
0投稿日: 2009.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前研一氏の著書。 1999年に出版されたと思うと、著者の頭の中には未来が描かれていたのかと思わせる内容。 戦略的思考の章で、旅行業者のパッケージの費用を中身で分析することと、床屋にかかるサービスと値段の関連は、 今でこそ旅行パックや1000円カットができたから消費者もバラエティに富んでいるのを考えることができるが、 その当時にそのような考えをしていたことに驚く。また、発想が素敵。 ‘冷蔵庫の教訓’は面白かった。一人分の食料を買いに行ったつもりが、買う物が決まっていなかったため、 やたらに多くの物を購入してしまい、多くを腐らせてしまったとのこと。かけた費用に対し、得るものが少なかった失敗例を記している。 その失敗をホッケースティック曲線で思い起こし、コンサルタントで活かしている点は面白かった。 できる人の失敗を喜ぶのはいけないが、人間味を感じる記述は感性に響く。 長かったから、全部を理解してはいない。でも、購入したからいつでも読める。 また、読もう。
0投稿日: 2009.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容 1部 戦略的思考とはなにか 戦略的思考入門 企業における戦略的思考 戦略的思考方法の国政への応用 戦略的思考を阻害するもの 戦略的思考グループの形成 2部 戦略的経営計画の実際 戦略的に考えるということ “低成長”とはなにか 戦略的思考に基づいた企業戦略 戦略的計画の核心 先見術 大前氏の中で最も好きな本で、マッキンゼーの新人時代に大前氏が書いた手記がそのまま書籍化されたものである。 フレームワークが云々という話が中心ではなく、物事の考え方について実例を挙げつつ記述している。 1975年に初版が発売されているので古すぎるという指摘があるかもしれませんが、物事の本質をどうやってとらえるかという方法に関しては古いも新しいもないと思うので★×5の評価です。 日本のイカ漁を例にしたケーススタディは骨太かつ題材もかなりユニークで面白かったです。 本来ケーススタディの回答はこのレベルにあるべきで、巷で「地頭」とか「フェルミ推定」とか言われる小手先のテクニックとは一線を画しているレベルの書であると感じました。
1投稿日: 2009.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ大先輩の方から経営の定番本を読んでおいて 損はないよーと言われたので 今、必死に時間を見つけて読んでいます。 これがそのうちの一つ。 友人が経営を科学したものと 言っていましたが、かなり正しいのでは ないかと思っています。 内容はさほど難しいものではなく 非常にわかりやすくなっています。 びっくりな事としては、これが70年代に 出版された本である事。 今まで読んできた経営に関する本の中でも トップいくつかに入るだけの 内容が含まれていると思います。 この本は後で購入決定ですね。 読んだときは図書館だったので。
0投稿日: 2008.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ惨敗。この本を読みこなすだけの能力のなさを実感。後日、再度トライします。 メモしておきたいフレーズを一つだけ:変革しなくてはいけないのは、個人であり企業である。国や地方自治体にいくら変われといっても変われない。彼らは個の集合体にすぎない。個人や企業が変わるには、実は、こうすれば変われるのだ、という「気概」がカギとなる。
0投稿日: 2008.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ開始:20070520、完了:20070520 さすがに1975年のときの本となると、目新しさがない 部分もあるが、しかし、当時30〜31歳の大前研一氏がいかに物事の 本質に迫ろうとしていたのかというのと、その膨大な体系化された知識 驚かされる。ただの焼き増しではなく自分の頭で考えているということ がよくわかる。 しかし、まさに戦略の教科書といえる。中期経営計画の立て方や、将来 の不確実性の考え方など、とてもわかりやすい。1回目に読んだときよ りも2回目に読んだときのほうが理解が深まる。 ホッケースティック曲線。 そこは願望と期待の入り混じった"明日こそは業績回復"曲線が例外なく 示されている。これはまさしく自社のことといえるのではないだろうか。 以下メモ。 企業参謀は30歳〜31歳のときのメモ。 マッキンゼーは5年で古株。 運、不運ではなく問題に取り組むときの姿勢と方法に大いに関係がある。 縮むマーケット。うまみのあるボリュームがなくなっている可能性。 練炭メーカーor冷蔵庫発達後の製氷業者。 売上高利益率。 ROA、総資産利益率。総資産に対して利益がどのくらい出ているかをみる。 この指標は経営内容の詳細がわからない他業種や他社との比較には 便利だが、一方一定の会社内での異なった製品間の比較や ビジネスそのもののうまみを絶対値としてあるいは経年的に 測るにはあまり適していいない。 使用総資本利益率(ROCE)。ROAの不備を取り除くため、分母の総資産から 短期買入債務を差し引いてある。 P&Lとバランスシートの双方を同時に正当に評価するための有料な指標 であるということができる。 個々のファクターの弾性値が定量的に把握されてしまえば、企業のトップ マネジメントは重要な武器をもつことになる。 資本投下の見返りが最も多くなるような事業は何か。 10年も15年も先のことになると戦略というよりは空想といったものに 近くなる。 しょせんは"カン"の重畳。 参謀としての頭脳グループが最も有効に力を発揮できるのは、短期でも 長期でもない、その中間の中期経営戦略である。 大体3年ぐらいを中心とした前後1,2年を中期、という。 各段階で現実性のある中期経営計画を立てる必要がある。 8つのステップがある。?目標値の設定、?基本ケースの確立(現状 のままだったらどうなるか、住宅着工件数など)、?原価低減改善 ケースの算定、?市場・販売改善ケースの算定、?戦略的ギャップの 算定、?戦略的代替案の摘出、?代替案の評価・選定、?中期 経営戦略実行計画。 創造力を駆使した思考と分析を重ねれば、必ず非常に実現性の高い中期経営 戦略が立案できる。 業種の成長曲線、高成長持続型、低成長型。低成長が基本的には持続すること。 プロダクトライフサイクル、成長期、成熟期、衰退期。 製品・市場戦略策定のためのプロセス、?市場性の動的把握、?内部経済の 分析、?競合状態の把握、?KFSに照らしたわがほうの強さ弱さの客観的理解、 ?改善機会について仮説の抽出・評価、?改善実施計画作成・実施、?モニター/ 必要な軌道修正。振り幅を正しくつかむ。 ニュージーランド沖の日本イカ船団。事業のうまみは少なくとも銀行の 長期預入金利よりも大きくなくてはならない。 自然の再生そのものを毎年の漁獲量とする。 経済性と実行可能性。 参謀五戒。 ?参謀たるもの「イフ」という言葉に対する本能的な恐れを捨てよ。 代替案を探るときには「What, If....?」という設問のしかたを するのが普通である。すなわち「もし状況がこうなったらどのように考え (あるいは行動反応し)たらよいか?」ということ。 ?参謀たるもの完全主義を捨てよ。 ?KFSについては徹底的に挑戦せよ。 「この業界で成功する秘訣は何ですか?」 ?制約条件に制約されるな。 「今何もできない、と思うに至った制約事項とは具体的には何と何ですか」 「これらの制約条件が一切ないとしたらどんな可能性が出てきますか?」 意外にも実はそれほど大きな制約条件ではなかった。 ?記憶に頼らず分析を。 2つの重要な能力「分析力」と「概念をつくり出す力」。 「道場破り」の促進。 二律背反につきあたる。 料理名がないと意外と材料の買物ができない。 ホッケースティック曲線。 そこは願望と期待の入り混じった"明日こそは業績回復"曲線が例外なく 示されている。 すべてが強気の計画。 "明日こそは"のカーブゆえにもう少し待ってみようかという気になってしまい、 低業績、不採算事業から抜け出せないという羽目になってしまう。 本来成熟し硬直化した市場においてなんらかのドラスティックな アクションを伴わないで業績が急展開して回復することはそれこそ奇跡に等しい。 猛烈社員の常として計画と努力目標とが識別されていなかったり、一度低位 に計画を設定すれば努力をしなくなるのではないかという恐怖感から、 できないと理性で知りつつも、情熱が"明日こそは"のカーブを描かせてしまう。 拡大思考は確かに社員にやる気を起こさせ、トップに立つものにとっては 逆に指導もしやすいが、ラッパや太鼓でしか社員を陶酔させることができない 人は一見勇壮ではあっても危なくて見ていられない時代になっている。 経営者が追い込まれていくと、似たような挙動を示すこともよくしられていく。 状況が悪くなるほど、広く見なくてはならないのに、よけい狭く見て、 もう選択の余地はない、と思いはじめてしまう。 世の中の「営みごと」はすべてオン=オフという二者択一ではなくグレーの アナログ系である。「つき」は呼び込むもので、与えられるものではない。 誤りは「制御」できるもの、最悪事態は避けられるものである。 経営は真剣勝負ではあるが一命を落とす前なら敗者復活もありうる。 勢いにのっている会社は"そこに至る道"を考え、勢いの落ちた破局に向かっている 会社の場合は最悪事態を想定し、"そこに至らない方策"を考える。 多少不利な講和条約でも結んでしまったほうが、ヒロシマに原爆を落とされ、 東京が焦土と化すよりもよいのだ、という発想が出てこない。 PPMの公害で、自分の参入市場をなるべく狭義に定義し、シェアを高めに 計算する癖のある会社もある。 「味の素」ではなく「クリスタル」を買わせるにはどうしたらよいか、という 問いに対する答えになっていることが必要。 国レベルでのポートフォリオ管理。 人と資金の有効循環。 日本の3つのエポック。 ?徳川幕府の創設、?明治維新、?終戦。 柔軟な思考法。 白か黒かでないと、考えられないというような硬直した頭ではなく、 どのくらいの灰色までなら妥協してもよいかを判断できる人物が戦略的 思考家である。 「最悪の事態」を避けるための施策。 基幹事業の成熟化と生活水準の向上に関係している。 原価低減の圧力を部下にかける以外にアイデアの浮かばないトップマネジメント は企業家とはいえない。 日本、「恥の文化圏」。 市場成長が鈍化または停止し成熟期になると通常はシェアも硬直化してくる。 常識に徹底的に挑戦する。 経営資源として、人・資本・原材料・技術の少なくとも4つを考える必要がある。 「どの」技術かということ。 余裕のある今のうちに部分的にでもよいから企業内にとにかく戦略的計画法 の実績をつくってしまっておくことがいざというときの何よりの強みとなるに 違いない。 ホワイトカラーも含めた生産性はアメリカに負けてしまう業種が多い。 低成長への対応。?需要変動型、?国際競争力型、?新価格体系型、?ライフサイクル の短命化。 世の中は全て相対的。相対的戦力。 軍事戦略における人的部分とは能力・組織・士気の3点。心情が官僚的になってしまうと 企業は硬直化してしまう。 官僚的心情の克服。 事業機会というものは見つけたら一挙に掘り起こしてしまう必要があり、 よほどの冒険家か金持でないと成功しにくい理由はまさにそこにある。 冒険家の成功話(カシオ、ダスキン)はたくさんきく。企業活動のステップ 、原料確保→生産設備→設計→生産技術・技術特許→品揃え→ アプリケーション→販売力→販売網→サービス。 電気メーカーは事業のバランスが問題。"電気"と名のつくものを片っ端 からやっていればわが国のGNPの1/3に匹敵する事業領域に経営資源を 分散することになる。 家電関係の研究員にとってはアパートの主婦の立ち話のほうが、学会の 発表よりも実り多い場合があるだろうけれども、ともすれば自分の住む 空間を完全にユーザーから離れた独自の振動、独自の宇宙としてしまう。 新機軸を求める方法、?考え方の転換、?戦略的自由度、?技術的 ポートフォリオ。 最も素朴な「なぜ」という質問を担当者に嫌われるほどしつこく発する やり方。 東芝の敷き毛布。誰も曲げたり乗ったりしてはいけないという既成 概念にチャレンジしなかった。 戦略軸、フィルム、レンズ、付属装置。 市場を考えない製品が研究室から自然発生したり、衰退市場に新製品 を注ぎ込んだりしてしまう。 技術ポートフォリオ。 新規事業に次々と参入し、売上高は伸ばしたけれども、市場地位は 伸び悩んでいるというような事業部をたくさんかかえた大企業が多い。 地位が他人にまねのできない何かによって守られているとき。 リスクをあえてとる局面がなくてはならない。 成功した経営者の話を聞くとその意思決定がいかに預言者的であるかという点。 後から考えると全く論理的。 成功のパターン、?事業領域の定義が明確、?将来の予言ではなく現状の分析から 将来の方向を推察して因果関係についてきわめて簡潔な論旨の仮説が述べられている。 ?自分のとるべき方向についていくつかの可能な選択しのうち、比較的少数の もののみが採択されている。 ?基本家庭を覚え続けており状況が全く変化した場合を除いて原則から外れない。 ヤマハの川上源一さん。 ピアノからエレクトーン、エレクトーンからオーディオ。 ピアノの木工技術から家具。 洗剤のいらない洗濯機。ポリバケツにつけておくだけできれいになる洗剤。 電気屋の洗濯機事業そのものを崩壊させることを狙うかもしれない。 日本の組み立て産業がつよいのは部品メーカーが強いということ。 コストダウンをしたり、改良設計を行っていることだけが事業計画と 思っているような人はもはや形骸化した大企業の一完了にすぎない。 このような考え方をいくら積み重ねても、世の中をリードするような先見的 製品や事業というものは出てこない。
0投稿日: 2008.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦略論の名著としていまだに読まれている本書。個人的にもかねてから読んでみたかった一冊。がしかし、まだ自分には早かった。レベルは結構高めなので、もうすこし力をつけてから再度トライしたい。
0投稿日: 2007.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログブックオフで購入。 昔の本だけども今に続くロジカルシンキングとかの流れを作った本で中身はそこまで古さを感じさせない。結構良書
0投稿日: 2006.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ初版の企業参謀から数十年後に読んでも古さを感じない.それだけ企業が変わって(変われて)いない現実を知る...
0投稿日: 2006.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログテーマ:戦略論 お勧めの人:大前の名著を読みたい人。3Cって聞いたことあるけど。。何か知りたいという人。戦略論の古典を勉強したいという方 ポイント:僕はすっと読めましたが、分厚く量も多いので、難しい本ということで星三つにしました。内容は☆5つです。特に理系で、コンサルに興味があったり、理系からビジネスへ転身したい人には、面白いと思います。彼が原子炉エンジニアからマッキンゼーに移り、学んだ事を30歳くらいの時にまとめたノートなので。 世界中で読まれている本です。
0投稿日: 2006.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦略的思考と言うよりも、 経営的な焦点のようなものが学べる。 利益を上げるとはどんなことか? 業績を上げるとはどんなことか? 最善解を見つけ出すマッキンゼー式ロジックがここに!
0投稿日: 2005.06.12
