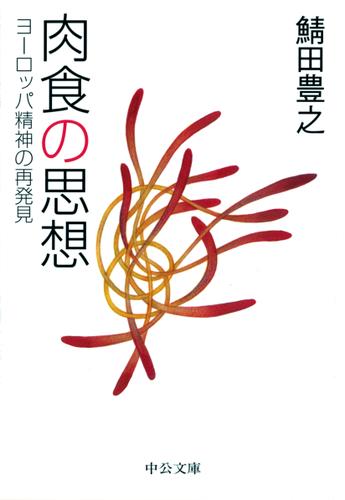
総合評価
(11件)| 1 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
わりと大味
肉食から始まり社会論、文化論に展開。 初版が今から半世紀ほど前なので、現在の研究水準からするとかなり一面的だったり、間違っていたりという点も目に付きます。「ではあるまいか」という推測が多く、推測に推測を重ねたあげく、なぜかインドのカーストに飛んだりして、落ち着いて読んでみるとかなり強引です。半世紀以上も前の本なので、そういう時代だったのかなぁ、という大らかな気持ちで読むのがよいかと思います。 また本書は文庫版ですが、中公新書版も電子化されており、そちらの方が表が大きく見やすいかと思います。
0投稿日: 2021.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこの人も、基本的には保守系の歴史家だと思うけれど、煽るところがないのが上品でよい。 ブログに書きました。 https://plaza.rakuten.co.jp/simakumakun/diary/201906140000/
1投稿日: 2019.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 欧米人は、なぜ動物をと畜して食う一方、動物を愛護するのか? 本書は、ヨーロッパ思想の原型を、歴史的・地理的条件に由来する食生活の伝統に求め、それに基づき形成された思想的伝統を明らかにし、日本とも比較しながら平易に説く。 食という新しい視点で西洋の歴史を見直す、西洋史学究の問題作。 [ 目次 ] 1 ヨーロッパ人の肉食 2 牧畜的世界ヨーロッパ 3 人間中心のキリスト教 4 ヨーロッパの階層意識 5 ヨーロッパの社会意識 6 ヨーロッパ近代化の背景 [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
0投稿日: 2014.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。 【購入本】 肉食の思想“ヨーロッパ精神の再発見” / 鯖田豊之 これはたいへん面白い。 ヨーロッパ人の肉食。 からの ヨーロッパ人の宗教思想 からの ヨーロッパ人の社会思想 からの ヨーロッパ人の近代思想 牧畜と農業におけるヨーロッパと日本の違いが実興味深く、なんでこんなに興味もってるの?俺みたいな感じです。 気候や土壌的に牧畜に向き農業に向かないヨーロッパと 気候や土壌的に農業に向き牧畜に向かない日本。 小規模で手間をかけてたくさんの実をとる方式の日本。 大規模で手間をかけずに少量の実をとる方式の欧米。 日本農業もアメリカみたいに大規模化しないと世界から完全に遅れをとるんじゃないかと、そう思っていた時期が僕にもありました…。 なるほどー。って感じです。 ガッテンガッテンガッテン。って感じです。 後半の思想はだいぶん肉食からはずれて行きますが、起点はなにせ肉食です。 食用家畜と動物愛護を完全に分離してる宗教観とか。 パンを食すことができるできない身分の違いの社会観とかね。 だからなのかー。そうなのかー。って感じですね。 最後の太平洋戦争への流れのムード的多数意思に関していえば、今の政治でもなんら変わってないわね。 この本あれなんですね。 1966年なんですね。 たいへんおもしろい本でございました。 いやーすごいわ。
0投稿日: 2013.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、日本人の立場で、ヨーロッパの思想的伝統を解明する試みです。食という尺度を用い、深い知識と洞察力で著された比較文化論となっています。日本のリーダたる人に読んで欲しい名著です。
0投稿日: 2012.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
昔書かれた本なのに、おもしろい、のか、昔書かれた本だから、おもしろいのか。 とにかくそこら辺にある本とは視点が全然違って、すごくおもしろかった。 抜粋: ・パンの役割は日本の米とは違い、主食・副食ではない WW1, ドイツに攻められて、パリの孤立に備えて、お隣ブルゴーニュの森に、牛、豚、羊の群が籠城の用意に集められた。 日本で籠城と言えば、昔から混め・塩・水でしょ。いくら肉好きだからって、危急存亡の時にまで、小麦じゃなかったのか? 日本では、米は文字通り主食であって、副食がどんなに贅沢になっても、米は食べるし、足りなければ、塩でもかけて、米を詰め込む。つまりパリでは、パンの役割は日本の米とは違い、主食・副食ではない。 ・日本では、肉食はある意味贅沢 高い肉食率を維持するには、広い農用地がなければいけないが、日本にはそんなスーペースがないから。 日本は暑い時期と湿度の高い時期が重なっているが、パリなどヨーロッパでは、米を食べる地域を除いて、重なっていない。この時期には、なんでも食物が育つので、無駄な雑草も育つ。それが育つと、食用の作物や家畜のえさになる草が駆逐されてしまう。でもパリなどでは、この時期がないので、雑草は育たない。日本で放牧しようとしたら、雑草を抜いて回らなければならないが、パリでは、放っておいて生えてた草をそのまま家畜が食べられるので、何にも面倒がない。という意味で、肉食など日本ではできなかった。 し、パリでは米は育たない。水稲の栽培には、3ヶ月以上20度を越す気温と、年間1000ミリを越す降雨量が必要だが、ヨーロッパでこの条件を満たすところはほんのわずかである。 ・キリスト教では、恋愛と婚姻は別。 一時期はコートリー・ラブ(コートニーじゃない)といって、宮廷内で、若い騎士と主君の奥方の恋が流行った。姦通まで言ってしまった例も多いが、本来は、決して肉体交渉を持たない。12、13世紀頃の本では、「恋愛はその権利を夫婦の間に及ぼすことが出来ない。恋人達は、なんらの義務に酔って強いられるものではない。夫婦は反対に、双方の意志に従うべき、またお互いが決して拒絶するべかざる、義務によってしばられているのであり、夫婦間に真の恋愛があるはずがない。」とまで言っている。この宮廷愛では、なによりも洗練された恋愛技巧がものをいい、気の利いた会話や討論によって、相手の気を引いたり、自分の思いを訴える。ときには相手にわざとヤキモチを焼かせたり、気持ちを確かめるためにわざ2難題を出す。一種の頭脳プレイであったという。欧米人が、婚前であろうと結婚後であろうと、日本人よりはるかに愛の技巧に長じているのは、このためである、とまで作者の鯖田さんは書いている。面白い話である。 ・キリスト教では、動物に留まらず、白人以外も人間だと思っていない 1537年、ローマ法王が、インド人や黒人、インディアンも「ほんものの人間である」と、厳かに宣言したそうである。宣言してもらわなくとも、彼らも僕らも人間である。この宣言まで、ヨーロッパ人は、僕らを何だと思っていたんだろうか?すごい優越意識である。ついでにこれは非キリスト教にも当てはまり、未だに根強く残っている(と、思う)。だからムスリムにあそこまで言えるのではないかな。少し戻れば、ヨーロッパの国々に昔から住んでいたキリスト教でないユダヤ人たちは、だからこそ常に迫害され続けて来た。迫害の理由は、彼らが金貸しをよくやっていたからだという説もあるらしいが、金貸しじゃなくても、貧乏であっても、迫害されまくったのは、自明の事実である。近代ではどの国でも、政教分離だと言われているが、目に見えない差別待遇は、隠れたところでは依然として、冷たい一線があるらしい。今もだろうと思う。 ・インドのカースト制では、上の階級になるほど口に出来る肉が減る 貧乏だと、肉天国。最高位のバラモンになると、絶対に何の肉も口に出来ないらしい。なんてかわいそう。その分、牛乳(羊かも)を飲みまくるらしいけど。 ・インドの、夫が死んだら妻は生きたまま焼かれる、というのは、本当 サティーと言って、50年前は日本でも有名だったらしい。日本や欧米と違って、ヒンドゥー教では、死後も婚姻を解消することは出来ない。これは輪廻思想によるからで、輪廻流転の中で、死はほんの一区切りでしかないので、そんな理由で婚姻を終了させるわけにはいかない。 ・パン屋はあるが、ご飯屋はない。欧米は元々外注家事だった。 パンはもと2買ってくるものだった。家で焼こうにも、パンの釜などは公共の物で、シェアしていた。すでに加工してあるものだから、切るくらいしか手間はかからない。これに比べて、米は精米してしまえば、後は家で各家庭でつくれる。これは食品加工業が欧米にはとても多いが、日本に少ないというくだりで書いてあるのだが、ある意味、それによって欧米よりも家庭で手がかかっていたとも言える。これを、電気釜の登場と女性の解放運動と結びつける人が居る、と書いてあった。なんともすっかり忘れ去った話だが、昔はとても大変だったらしいから、そういえばそうかも。 ・ヨーロッパ人は先祖崇拝が理解できない。 米は、毎年同じ田で作る。その方が、上手くできるというか、その土地の手入れによって豊作度が決まるから、田は固定で、家単位で守るものだった。 これに比べて、ヨーロッパの麦は、同じ場所で翌年作ることができない。何年か、放牧などにまわして土地を休ませる必要がある。放牧にはたくさんの土地が必要だから、隣近所と土地を併せて広くし、元誰の土地であったかは関係なしに、共同体として農畜産業をする。にわかには信じがたいのだけど、元々は、村社会で、とても共同体意識が高かったのだという。 日本では、高い穀物生産高は、毎年、昔から耕作を欠かさずにきた「ご先祖様」のおかげだが、ヨーロッパでは、毎年穀物生産が続けられるのは、ご近所が土地をまわしてくれているおかげだ。だからヨーロッパでは死んだ先祖より、生きている村の仲間の方がよっぽど大切で、中々日本人の先祖との一体感は理解できない。 今、先祖との一体感があるかはちょっと謎だけど。 ・腑に落ちないというか、そうだったのかもしれないが、今では陰もない、もしくは逆転しているものもいくつかある。 ①本来、欧米人こそ他人が気になるおせっかい。 昔は同じキリスト教内でも、細かい派閥で争い、最たる例は魔女狩り。地球は回るとか、人間はサルから進化したとか言えば殺される。 信仰の自由は額面だけの者で、イギリスやイタリアでは、少なくとも50年くらい前までは、アングリカン(白人?)とキリスト教は優遇うされている。西ドイツでは協会税が徴収され、カトリックとプロテスタントに分配される。確かドイツは今も、協会税あったね。無宗教を表明すると免税になるが、目に見えない不利益があるのだそうだ。店主と宗派が違うから雇ってもらえないとか。 ヨーロッパの建造物や外観に決まりがあるのも、ここでは全体の調和を乱さないように、という配慮、ではなく、他人のことを気にする病気、とされている。 ②今も残る、強く長い階層意識に反発してのすさまじい個人主義 支配階級を武士とすれば、日本には商人より貧乏な武士もいたし、階級は曖昧、さらに、武士の割合は、貴族の割合より一桁多かった。ヨーロッパでは本当に一部の特権階級が、王様が殺されるくらい恨まれるまで、優雅な生活を送って来た。ので、フツウの人は、伝統的に、強制、抑圧され続けて来た。だから、その反動もものすごい。その反動が個人主義であり、平等であり、自由である。 だから、欧米では、義務教育を受ける「権利を有する」であり、予防接種を受ける「権利を有する」わけで、何人たりとも強制されない。 ついでに、武器を有する権利も有するし、強盗を撃ち殺す権利も有する。アメリカでは武器を持つ権利が憲法に明記されているし、ヨーロッパでも全面的な禁止になっているのは、武器を持ってで歩くことで、自宅での武器の保有については、せいぜい武器の種類に制限があるくらいらしい。例えばフランスは、ピストルは許可制で、刀は全くの自由だとか。50年前だけど。 ③自由と平等は、海外では大義名分 自由で平等な人間などというものは、どこにもありはしない。あくまでフィクションである。 だから、民主主義は、そういうフィクションに立脚した、1つの幻想である。実際政治の上ではいい役割を果たしたが、言っても伝統思想の衣替えをしただけである。 例えば多数決。昔はヨーロッパでは全て満場一致制だったから、反対すると、兵糧攻めされたり、いじめられたりした。少数派はつぶされた。多数決では、少数派にも一応そこに居るのだと言う主張や、意見を述べる権利が認められた、そういう意味で、衣替え。 ④日本は自由・平等・多数決を、まっすぐに輸入してしまった 近代思想の核である自由と平等を、以上を知らずに、もと2階層意識の曖昧な国に輸入してしまったから、かろうじてあった階層意識はくずれ、みんな平等になった。おかげで、優秀な支配者は産まれないし、多数決の平均みたいな人がトップにつくことになる。これでは物事を押し進められない。 ⑤1964年にサイエンスに、「キリスト教の、人間が自身のために自然を搾取することが神の意志である、という教えが環境問題の根源である」という論文が載った。キリスト教圏では騒動になったらしいが、ほんとにその通りである。その後も、「自然において人間が特殊な地位にあるという思想では環境問題を解決することはできず、あらゆる生物は対等の関係にあるという平等主義を人間が受諾しないかぎり、環境は維持できない」と主張したり(ノルウェー)、およそ、日本ではほぼ当たり前のことが、繰り返し述べられているらしい。 なにせ、おもしろい本でした。あっぱれ!
0投稿日: 2012.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ・流し読み ・人間が動物より上、というキリスト教の影響 ・日本の主食は米だが、ヨーロッパ人は主食と副食の境界がない →穀物が十分に育たない(効率でいったら日本の1/10) →天気の影響で動物が放牧して食べれるレベルの草が生える →結果、肉を食す ・ヨーロッパ人の断絶論理 →支配者/被支配者 →貴族/一般人 →ヨーロッパ人/ユダヤ人/アフリカ系 →人間/動物 確かに、ヨーロッパではこれが主食!と言ったものはなかった気がしたけど…極端過ぎる気がする。
0投稿日: 2012.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ食べ物の面からヨーロッパをみるという視点が斬新で興味深かった。 身近で必要不可欠な食べ物という視点から考察を進めていて、読みやすかったし理解もしやすかった。
0投稿日: 2011.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、世界史ブームなのと、日高敏隆さんがオススメしていたので。 一気に読んで面白かったことは面白かったけれど、なにせ書かれた年代が古いので、現在どうなっているのか、齟齬はないのかを気にしながら読んだ。 日本と西洋(アメリカを含むヨーロッパ)の違いを、穀物中心・コメを主食にしてきた日本文化と、肉食中心・主食と副食の区別のないヨーロッパ文化を比較してきた文化論で、切り口も新鮮。 ただ、肉食文化には人と動物の間に一線を画すことを根本に置く「断絶論理」があって、だから「人間=ヨーロッパ人種でキリスト教」からハミ出す相手に対して排除する方向に向かったが、日本人はそうではない……というところにはどうにも頷けなかった。思ったよりは読んでもスッキリしなかったのが残念。 日本人のキリスト教受容あたりの話は十分頷けたんだけども。
0投稿日: 2010.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログヨーロッパの精神、思想を「肉食」という観点から見直す。肉食が生理的に及ぼす影響ということではない。家畜の生殖や屠殺が日常生活の中にあふれていたことが、人間と動物を厳密に区別する必要性を生じさせた。そこにヨーロッパ思想の特徴のひとつがあるというのだ。ここから導かれる洞察には説得力があり、とても面白い本だ。
0投稿日: 2009.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本に宣教に来るのは、日本の食生活の面から厳しい公卿だった。 ヨーロッパ人はキリスト教徒以外は差別していた。ヨーロッパ人が非ヨーロッパ人と恒常的に付き合うようになったのは近代以降のこと。 カースト制度の場合はもっぱら差別意識だけが先送りし、たいした意味もなしに階層は細分化する一方である。ヨーロッパ社会の意識は他人が自分と同じでないと我慢できない一種のおせっかい精神である。だから異教徒を殺す、日本人は相手を気にしないから赦す、というか相手にしない。
0投稿日: 2009.09.27
