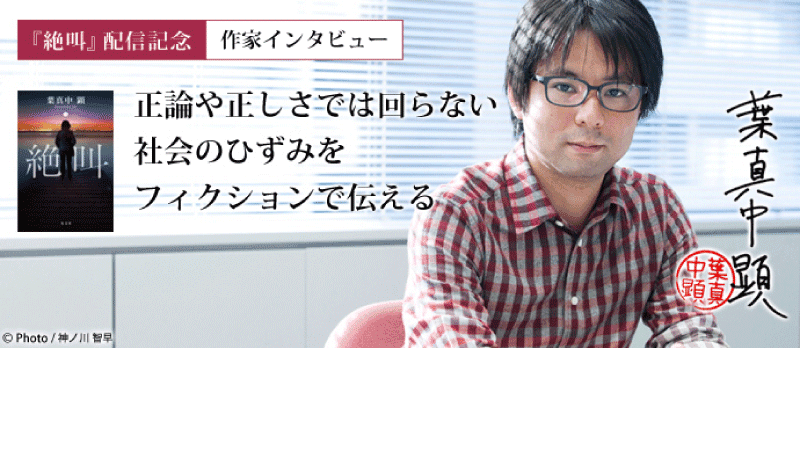
『絶叫』配信記念 作家:葉真中顕 インタビュー
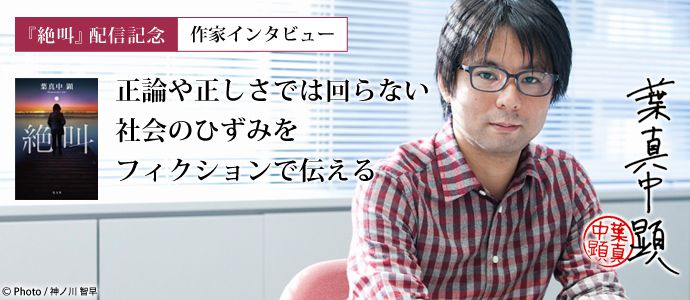

2012年、介護現場で起きる連続死事件を描いた『ロスト・ケア』で、第16回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞。現代社会の闇に迫るスケール感と緻密な構成で恐るべき新人と評された葉真中顕さんの、受賞後第一作『絶叫』が上梓された。
『絶叫』は昭和から平成へと移り変わる時代を背景に、運命に抗うひとりの女の人生を、さまざまな社会問題を織り交ぜながら紡いだ物語。葉真中さんがこの作品に込めた思いについて、うかがいました。
葉真中顕インタビュー
──デビュー作『ロスト・ケア』から1年半を経て、待望の新作ですね。今の心境から聞かせてください。

葉真中: 前作は、自分が書きたくて書いていたものですが、今回は職業作家として、出版社から依頼を受けて書いた初めての作品。新人賞がまぐれだったといわれないように、前作以上のクオリティのものを書かなければという危機感や、これから作家としてやっていけるかどうかの試金石になるというプレッシャーもあり、執筆に1年以上かかってしまって……。なので今は、完走できてほっとした気持ちです。
──『絶叫』は、平凡な家庭に生まれたひとりの女が、時代に翻弄されるように転落していくストーリーです。この着想はどのように得られたものなのでしょう?
葉真中: 『ロスト・ケア』では介護問題をテーマにしましたが、本作では、もうちょっと広い視点から現代を描きたい、という思いがまずありました。今、クローズアップされている格差や貧困などの社会問題って、バブル経済が崩壊し、そこから長い不況が続く中で出てきたもので、私が子どもの頃からその素地はあったと思うんですね。私は76年生まれ、いわゆる団塊ジュニア世代なんですが、この世代はそうした社会の変遷が人生と重なってくる。つまり、現代の語り手として一番適した世代なんじゃないかと思いまして。そこで、自分が見てきた時代を、自分とは違う視点で書いてみたいと思い、同世代の女性を主人公にした物語を書くことにしたんです。
──前作とはまた違ったアプローチで、「貧困」「無縁社会」「ブラック企業」といった現代のさまざまな社会問題が織り込まれています。
葉真中: こうした社会問題がニュースなどで取り上げられるときって、わかりやすい構図が語られるだけで、その背景や翻弄される人々の人生にまでは踏み込んでいかないんですよね。それをもっと掘り下げていく手法のひとつが、ノンフィクションとして具体的な事実を追い客観的なデータとエビデンスで語っていく方法で、もうひとつが、フィクションの中でありえたかもしれない人生として描く方法です。私はフィクションを書く立場なので、こうした報道に接したとき、そこに描かれなかった「if」を考えます。自分の力ではどうにもならない大きなものに翻弄される人生をひとつの「if」として描くことで、現代を逆照射するように、時代を語ることができると考えているんです。
──メディアで語られる社会問題と、葉真中さんがご自身で感じる社会問題のズレみたいなものを感じることはあるのでしょうか?
葉真中: たとえば、若者の草食化やコミュニケーション能力の低下が話題になるときって、心の問題に還元しがちじゃないですか。特に最近は、「人の心が劣化してきた」といった言説がとても多い。でも、私はこれには大きな声で異議申し立てをしたくて。人間の心は、100年やそこらで変わらない。何かが変わったとしたら、それは社会なんです。個人の心がけや善意だけでは対抗しえない大きな時代の流れ、社会環境の変化によって、人々の行動様式に変化が起きているだけなのだと思っています。
──主人公「陽子」が転落していくさまが説得力を持って描かれていて、読み進めているうちに「他人事ではない」という切実さを感じました。
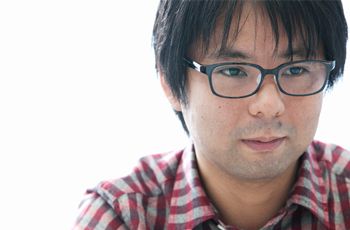
葉真中: 私は基本的なスタンスとして、世の中に絶対的に正しいものも悪いものもないと思っているんです。それで、この小説を書く上でも、わかりやすく「悪」となる登場人物は、なるべく作らないようにしました。犯罪に手を染めてしまう人が、みんな邪悪な心で動いているかというと、そうではない。たとえば娘を抑圧する母親も、娘が憎いわけではなく、自分の大切なものを守ろうとするなかで、どうしようもなく娘を傷つけてしまったりするわけです。世の中の悲劇って、そういう状況から生まれてくるのだと思います。そしてそれは、誰にとっても他人事じゃないんですよね。
──葉真中さんの作品には、「悪」もですが「正」も登場しませんね。たとえば陽子を追う刑事・綾乃の元夫は優しく教養のある人物ですが、その正論で綾乃を苦しめます。
葉真中: 綾乃の元夫は、私自身が正しいと思うことを代弁しているキャラクターなんですが、こういう人物にも限界はあるんですよね。「正しさ」は常に正しくないものを「間違い」として抑圧します。たとえば、「これからは女性は自立して、ひとりで生きていくべき」と言うのも、逆に「女性は結婚して子どもを産むべき」と言うのも、「べき」で語ろうとした瞬間、ただの一般論ではなく抑圧になって誰かを追い詰めてしまう。ときには言葉にしていなくても、時代が空気として要請してしまうこともあります。そもそも、こういう本を読もうなんていう人は、文化的で理性を重んじる人がほとんどだと思うんですよ。でも、そういう人だって、なんの悪気もないのに誰かを抑圧してしまうかもしれない。正しさだけでは、世の中はまわっていかないんです。
──最近ではインターネット上でも、自分の信じる正義を説く人が増えてきたように思います。
葉真中: 私も昔、インターネットで批判記事を書いていたこともあるんですが、やっぱり気持ちいいんですよね。正義の側に立って、なにかを批判することって。そこには、発言するだけで自分が偉くなったような気持ちにさせる魔力がある。もちろん批判精神は、社会を健全にまわすために必要なものだし、発言する場が増えることは悪いことではないと思います。でもそういう発言は、言ってる瞬間は気持ちいいけど、物事をなにも解決させないことが多い。それに、みんな建前では「それぞれの生き方を尊重して」とか言うけれど、そういう正論ではどうしても割り切れないものが、社会のあちこちに濃厚に漂っている。そのことは、意識的に書いていきたいと思っています。
──葉真中さんが小説を書く上で心がけていること、大切にしてることとは?

葉真中: どうしたら読者が、小説世界で起きることを他人事だと思わず、当事者性を失わないまま最後まで読めるかというのは、非常に気を遣っているところです。たとえば、もし自分がこの時代に生まれていたらとか、男性でも「もし自分が女の人だったら」というふうに、自分にとっての「if」として読み進めて欲しいですね。それで、説得力をもたせようとしたところ、主人公の子ども時代から書くことになり、結果としてこんなに分厚くなってしまったんですけどね(笑)。でも、そうして自分のこととして読み進めていくと、最後に、現実世界では決して見えない景色が見えてくるはずなんですね。そういう小説がいい小説だと私は思っているので、少し長くなってもいいと思い、じっくり書くことにしたんです。
──ラストは事件としてだけでなく、ひとりの女性の人生としても意外性があり、ずしりとした読後感が残りました。
葉真中: ありがとうございます。そう言っていただけると、うれしいですね。私は今まで誰も思い付かなかった密室殺人のトリックとかを書くタイプのミステリー作家ではないので、話の筋運びと構成で勝負していくしかないと思ってます。この小説は、書くのには随分苦労しましたが、わりと早い段階でラストは決まっていたので、ここにうまく着地できれば勝算はあると思い、書き進めていきました。ミステリーって、結末を読めば、「ああ、そういうことだったのね」で終わる形式ですよね。でも、そこで終わらせず、なにか爪痕を読者に残したい。そのためには、ただ謎を解くだけではなく、その背景にある人間ドラマに魅力を感じてもらわないといけない。それは今回、私の中でひとつの挑戦だったのですが、なんとか納得のいく形で出せたかなと思っています。
──児童文学や漫画シナリオも手がけるなどライターとしても活躍されていますが、表現の場にフィクション、中でも「ミステリー」というジャンルを選ばれたのはなぜですか?
葉真中: まずは、一読者としてミステリーが好きということ。それと、読者を物語世界に引き込む効率のよい形式がミステリーだと私は思っているんですね。やはり小説の中に謎があると、読者を引っぱっていけるので。その上で、文学性といったら口幅ったいのですが、小説でしか表現しえないものを意識して書いていきたいと思っています。小説のキモは、リアルの追求じゃなくて、リアリティの追求なんですよね。リアリティを追求することで、読者の心を動かしたり、現実とは違う世界を描き出すことができる。たとえば、大江健三郎の『死者の奢り』に出てくる大学病院での死体洗いのエピソードは、いかにもありそうな話なので、本当にそういうアルバイトがあるらしいという都市伝説になりました。そんなふうに、小説のリアリティがリアルを超えることがある。私も小説を通して、リアルより濃いリアリティを読者に与えたくて。それが、フィクションの価値だと思うんです。
──最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。
葉真中: この小説は女性を主人公に書いた小説ですが、私自身、男性作家ですし、男性にとっても他人事ではなく読んでいただけると思います。また、1970年代から現代までの一代記になっていて、30代以上の方にとっては懐かしい事件やトピックもふんだんに盛りこんであります。なかには、あえて固有名詞を書かずに描写しているものもあるので、「これはあのドラマだな」とか「このライブハウスはあそこのことかな」と読みとって、ニヤリとしていただく楽しみ方もあると思います。そうして読み進めていくと、ラストには小説を読まなければ見えない景色、味わえない感情がきっとある。ですので、長い小説ではありますが、最後のページまでぜひお付き合いいただければと思います。
葉真中顕(はまなか・あき) プロフィール

1976年東京生まれ。
2009年、児童向け小説『ライバル』で角川学芸児童文学賞優秀賞受賞。2011年より週刊少年サンデー連載漫画『犬部! ボクらのしっぽ戦記』にてシナリオ協力。2012年『ロスト・ケア』にて第16回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、ミステリー作家としてデビュー。


