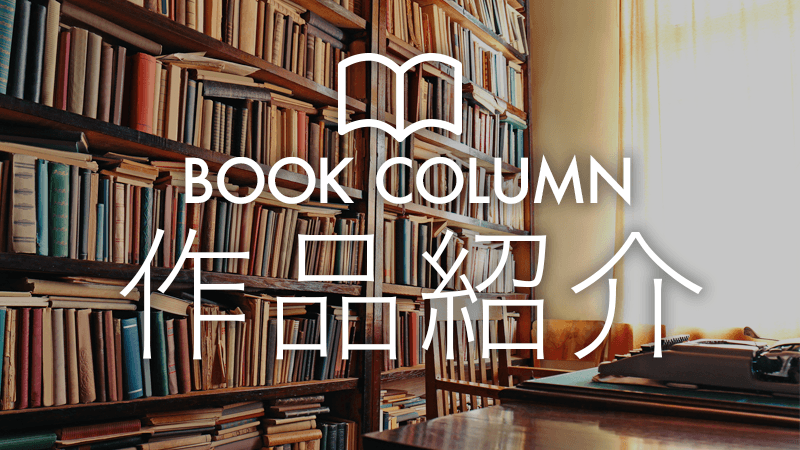
「地に足の着いた」宇宙SF(オービタル・クラウド)
「地に足の着いた」宇宙SF
【日本SF大賞受賞】2020年、流れ星の発生を予測するWebサイト〈メテオ・ニュース〉を運営する木村和海は、イランが打ち上げたロケットブースターの2段目〈サフィール3〉が、大気圏内に落下することなく、逆に高度を上げていることに気づく。シェアオフィス仲間である天才的ITエンジニア沼田明利の協力を得て、〈サフィール3〉のデータを解析する和海は、世界を揺るがすスペーステロ計画に巻き込まれて――
なるほど、こうすればよいのか。それが読後の第一印象だった。ここまで地に足の着いた宇宙小説もないのではないだろうか。ちょっと矛盾した表現ではあるが。それがまず驚きだった。大抵は現実からある程度の飛躍を設定しなければ、宇宙小説は成立しない。近未来とかパラレルワールドとか、そういう現実をいじる仕掛けなしに、宇宙を舞台にした小説を書くことは不可能だと思っていた。それほどまでに、私たちの世界は宇宙から遠ざかってしまっている。なにしろ宇宙開発は金食い虫で、先頭を走ってきたアメリカでさえ、有人宇宙飛行を大きく削減せざるを得ない現状だ。
ならば、宇宙から遠ざけられた人々の鬱屈が宇宙を目指すエネルギーになるのではないか。そうした逆転の発想が本書の仕掛けだ。もちろん、国家が頼れないなら、資産家や技術者が結集して民間でロケットを打ち上げてしまおうぜ、などという安易な話ではない。
本書に特権的な主人公はおらず、スーパーマン的な活躍は誰ひとりとして、なし得ていない。地球軌道上で着々と進行する陰謀を巡って、それぞれの場所で地味に活動してきた技術者や専門家たちが、それぞれの思惑と関心をもって活動を続けていくうちに、バラバラだった視点が徐々に束ねられ、ひとつの方向へと導かれていく。彼らは有能ではあるが、天才でも超人でもなく、自分の環境で得られる情報を最大限に生かして、事態を打開しようと奮闘する。
本書が第35回日本SF大賞を受賞したのもきわめて当然のことだろう。まさにこれまでとまったく異なる切り口の宇宙SFだと言っていい。だがその一方で、まったくSF小説になじみのない読者が手にしたとしても、それほど違和感なく読めてしまうことだろう。大仕掛けのサスペンス小説として読むことも十分に可能だ。そこが本書の間口の広さで、急速に支持を拡大している理由のひとつでもある。
アクションはほとんどなく、ロマンスも皆無。物語の大半は、登場人物たちがパソコンの前に座って何か計算したり分析したりしているだけだ。それなのにここまで読ませてしまう筆力が何よりもすごいし、新しい。
ネットの世界を描いた小説は、これまで、多かれ少なかれ「サイバーパンク」であろうとしてきた。パソコンの前にただ座っているだけでは物語にならないし、動きも発生しない。そんな話を誰が読むだろう。現代を描くためには、ネットに触れざるを得ず、そのための有効な方法論は、これまで「サイバーパンク」しかなかった。
だが藤井は、そんな背伸びをした飛躍はしなくてもいいことを示してしまった。ネット空間が面白いのは、きらびやかなCGでも氾濫する情報でもない。遠く離れた人々の思考が瞬時にやり取りされるという点なのだ。しかもそれは完璧ではなくて、うまく届かないこともあるし、意志に反して覗いたり覗かれたり、ということもある。そこにサスペンスが生まれる余地があるわけだ。藤井は活字表現の長所を最大限に生かし、登場人物の行動よりは意識にスポットを当てて、思考の流れとキャッチボール、駆け引きを、ダイナミズムに溢れた物語として描いてみせた。
もちろんこのやり方にも弱点はあって、キャラクターの印象が薄く区別がつきにくい。物語が本格的に立ち上がるまでは、なかなか没入しづらい。だが、それは今後の作品の中で解消されていくだろう。本書においても、何よりも敵方に立つ人物たちが魅力的で、強く印象に残る。いわゆる書き割り的な悪党ではなく、血の通った人間として、敬意をもって描かれているのがすばらしい。
地に足がついたまま、大いに結構だ。多くの登場人物は、宇宙空間を直接見ることなく、地球の表面に張り付いたまま、それでも宇宙を夢見る。それこそが本書ならではの魅力なのである。(高槻 真樹)


