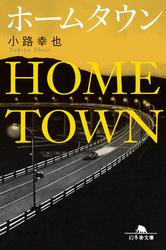小路さんの「フック」と「カコーン」と「モテ話」

『東京バンドワゴン』や『東京公園』など、青春小説や家族小説、ミステリーからSFまで、極上のエンターテインメント小説を次から次へと発表する、小路幸也さん。その尽きることない創作の源は一体なんなのでしょうか?小路さん流・物語の書き方から、プライベート秘話まで、大胆に語っていただきました。
小路幸也の作品
『東京バンドワゴン』の作家・小路幸也のインタビュー
小路さんの「フック」と「カコーン」と「モテ話」
――多彩な作品群を、次々と生み出す小路さんの「頭の中」はどうなっているのでしょうか?

どんな風に物語を作っていくのかというと、まず僕が<フック>と呼んでいるものが浮かびます。フックとはアイディアのようなもので、あるキーワードやアイディアが文字通り「カコーン!」とフックに引っかかって釣り上げられた瞬間、主人公の設定やエピソード、脇役たちのキャラクターや背景までが、全部一緒に「カコッ!」と浮かび上がるんです。それらを整合性を考えながら選び取り、「カコカコカコッ!」と組み合わせていって、オープニングと着地点が見えたらすぐに書き始めます。どういう道筋を通ってどんな風に最後までもっていくかは割とぼんやりとしたままなんですが、書きながらラストへのルートを探していく。それが僕の書き方です。
――カコーン、カコッ、カコカコカコッというのは…、小路さんならではの感覚でしょうか(笑)? 今回、新たに電子書籍化された4冊の「カコーン!」な瞬間をそれぞれ教えてください。

カコーンとかカコカコッは……そうですねぇ、かなり感覚的なものかもしれません(笑)。 では『21 twenty one』から。これは、僕にとって初めての連載小説なんです。デビューして3、4年目くらいだったかな。書き下ろしの依頼ばかりの中で、初の連載依頼はものすごくうれしくて。だって、連載だと書いたらその月に原稿料がもらえるわけで…、そういう意味でもとても印象深い1冊です(笑)。 僕の場合、執筆の依頼があると、まずは編集者とどんな話にするか打合せをするんですが、この連載依頼のときは「若者の話にしよう」ということだけが決まっていました。そこで、当時僕がたまたまもっていた「21世紀に21歳になる」というキーワードをお話したら、いいね!と盛り上がり、そこから「21世紀に21歳になる21人」というのが決まりました。これこそが僕の言う<フック>です。そこから、21人ならちょうど1クラス分だからクラスメイトの話にしよう、もしその中の1人がいなくなったらどうなるかな、など同時に浮かび上がってきた設定をカコカコカコッと整理して着地点を決め、書いたものなんです。
――「当時もっていたキーワード」とおっしゃいましたが、いつもキーワードもしくはアイディアをたくさんお持ちなんですか?
たくさんではないですけれど、“お、なんか面白そうじゃん!”と何の気なしにふと思いついた言葉やアイディアは、できるだけメモ帳に書き留めるようにしています。それを小説に書きたい、というではなくて単純にキーワードとして持っているだけ。僕の場合、それらに点火するのは、フックのときだけなので。(小路さん、メモ帳をパラパラめくりながら)たとえば、「UFOばっかりみてる主婦」「僕だけが見た戦争」とか。ね、面白そうでしょ?あ、「ファーザーとマザー」ってのもある。よくわからない、なんだろ、これ(笑)!
――『ホームタウン』はどうですか?
中学生のときに読んだ海外のミステリー小説で、百貨店に常駐している探偵が出てくる話があって、当時はアメリカの百貨店には探偵がいると信じていたんですよ(笑)。たぶん、今思えば警備員みたいな感じなんでしょうけれど、それ以来ずっと僕の中には「百貨店の探偵」というキーワードがありました。これがフックです。しかも広告業界で働いていたとき、僕は百貨店の広告を担当していたから、舞台裏はなんとなくわかってる。百貨店の中で探偵のような仕事をする人。そこからスタートした物語です。
――『探偵ザンティピーシリーズ』の主人公もまた、かなり変わった設定で…(笑)

主人公の探偵ザンティピーは僕のお気に入り。1冊目の『探偵ザンティピーの休暇』は初めての文庫書き下ろし小説でした。「軽いミステリーの書き下ろしを文庫で」という前提以外はすべておまかせということだったので、まず「探偵もの」だなと。と考えたときに、大好きなニューヨーク・マンハッタンにいる探偵がいいな、しかもその探偵が、日本人なら誰もが知っている映画の主人公みたいなキャラクターで事件を解決したら面白いかも、と思いついてしまって。思いついたらもう、どうしようもない(笑)!それがフック。しかも2冊目の『探偵ザンティピーの仏心』では“湯けむり探偵旅情編”の要素まで盛り込みました。このシリーズはかなり自由に楽しく書かせてもらってます。
――ネタ帳に書かれたアイディアを次々と小説という形でアウトプットされていますが、「しまった、ネタがない。インプットしなくては!」と焦ることはありますか?
ないと思います。小さいころから読んだり観たりしてきた小説や漫画、映画、ドラマ、すべての何百何千という物語が溶け合って“ニュアンス”みたいなものになって、僕の中に染み込み、蓄積されています。それをフックで上手く引っかけられるかどうか。一度引っかかったものでも組み合わせを変えれば、フックは無限大です。それに、今こうやってインタビューを受けている最中もインプットしています。へえ、こんな部屋があるんだ、こんな会社にこんな人がいるんだ、家族はどんな人かな、顔つきやしぐさ、つけている指輪など、すべてを取り込んでいます。もう、生きていること自体、インプットと言えますよね。だから、枯渇することはないと思っています。
僕は“感覚”で書いていくタイプなんですが、何か僕に優れている点があるとすれば、「感覚をつかむ感覚」かもしれません。今、北海道に住んでいますが、東京を物語の舞台にしたとしても、東京の感覚、雰囲気は描けます。映画化された『東京公園』も、東京の公園をたくさん書いていますが、実際に行ったことがあるのは1、2箇所です。後は資料を見ながら書いているので、ひょっとしたらそういった感覚は優れているのかなぁと思います。
――その感覚は、小さいころから優れていると認識していたんですか?

うすうす、感づいていたような…(笑)。たぶん、僕はものすごく“ナルシスト”なんです。作家やアーティストって基本、みんなそうだと思いますよ。「俺が一番カッコイイ、一番カワイイのは自分、俺は人より優れている!」という気持ちがないと小説は書けないと思います。そういう部分は、多かれ少なかれあるはずで…。ただ、僕の場合、会社員としての生活も長かった分、そのナルシストな部分と普通の感覚のバランスの取り方が上手いというか、悪く言えば上手く立ち回るみたいなところがあって、僕のことを昔からよく知る人々は僕のことを「悪党」と呼んでます(笑)。お前ほど悪い奴はいねえな、と。
――小路さんは、一体どんな子供だったんでしょうか…?
これがまたいやらしいことに優等生でね(笑)。勉強もスポーツもできて弁も立ち、先生のウケもいい。イヤな感じでしょ?! しかも4月生まれだからクラスの中で一番お兄さん。さらに、姉が2人いる末っ子でいろいろと鍛えられて育っているから、立ち回りが上手い。何でもみんなよりできちゃうんです。
――もっとも女子ウケしそうな小学生です(笑)。
はい、正直モテました(笑)。小学4年生からは放送委員で、当時からいい声だったんですよ。中学校に入ったらすぐギターを始めてバンドを組んで、高校でも音楽活動に夢中でした。19歳のとき喫茶店でバイトをしていたんですが、週末はバイトの男子を目当てに女の子が大行列するんです。喫茶店文化が背景として残っていた時代とは言え、それはもうすごい人気でした。僕らバイトは、お揃いのジーンズとTシャツ、バンダナを巻いたりしてね。バレンタインデーには、僕ひとりで82個チョコレートをもらいました。ハイ、自慢です(笑)。ただ、なぜだか僕が好きになって交際を申し込んだ人には必ず振られていたんですよねぇ…。
――そんな小路さん、実はまだ恋愛小説をお書きになったことがないですよね?
そうですね。それは意図したことではなくて、たまたまです。ご要望があればいつでも書きます。ぜひ(笑)!
Text / Miho Tanaka(staffon)
Profile
小路幸也 しょうじ ゆきや 作家

1961年北海道旭川市生まれ。1985年、札幌の広告会社に就職し、地元百貨店を担当。エディター、ライター、プランナーとして勤務する。1991年、「30歳を機に作家になる」と志し、新人賞へ投稿開始。38歳で退社、フリーとなり、ゲーム制作会社でシナリオライターを務めながら、専門学校でゲームシナリオ講師も。2003年、『空を見上げる古い歌を口ずさむ』で講談社メフィスト賞を受賞、作家デビュー。『東京バンドワゴン』シリーズをはじめ、著書多数。幅広い層から支持を得ている。