
作家インタビュー:貴志祐介
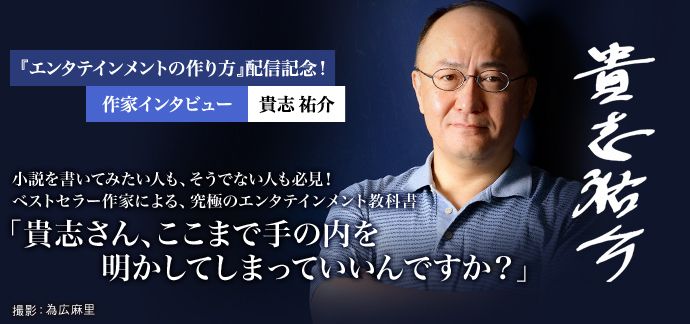
ホラー、ミステリ、SFで文芸賞を受賞し、
『黒い家』『青の炎』『悪の教典』とミリオンセラーを出し続ける作家・貴志祐介さん。
年代を超えて愛され、読者を魅了する作品はどのようにして生まれるのでしょうか?
アイディアの膨らませ方からプロットの立て方、キャラクター作りなど、
エンタメ・キングの「頭の中」を初公開した本が、このほど発売!
その真意を、じっくりとお伺いしました。
「売れる小説」はどうやったら書けるのか、書くべきなのか・・・・・・アイデア、プロット、キャラクターなど、小説を書くための必須テクニックをベストセラー作家・貴志祐介が惜しみなく伝授する、唯一無二の創作論。
貴志祐介インタビュー
―小説以外、しかも「エンタテインメントの作り方」。こういったノウハウ本は初めてですか?

初めてです。といっても、私自身がこういった本を出したいと思っていたわけではなくて…(笑)、編集者の方から出してみませんか、というお話をいただいたのがきっかけです。ただ、今までさまざまなインタビューを受けてきた中で、一番聞かれたのは「どういうふうに作品がつくられたのか」、物語ができるまでとその背景についてでした。ですから、細切れになったそれらの回答を、まとまった形で残しておくのは意味があることかもしれないと思っています。
デビューしてちょうど20年。新人のときは「書く」ことに気負いや照れがあったんですが、歳をとるとそんなことどうでもよくなってきて、ある意味、肩の力が抜けたというか…。この年齢になったからこそ、正直になんでもオープンにしてしまおう、と思えたのかもしれません。実際、自分自身が今までやってきたことを振り返る意味でも、とてもよい機会だったと思います。
―それにしても、『黒い家』や『悪の教典』といったべストセラー作品の裏側をはじめ、ここまで手のうちを明かしてしまっていいのでしょうか…?
小説は工業製品ではないですから、製法を明かしたからといって同じものが書けるわけではないんです。ただ、あんまり底の浅いことを書いてしまうと、「なんだ、この程度だったのか」と読者に見透かされてしまう怖さはあります。だからといってカッコつけると逆にボロが出そうだし…(笑)。ですから、アイディアのヒントやその磨き方、プロットの立て方やタイトルのつけ方といった小説を書く際のノウハウはもちろん、キャラクターの命名法や、漢字とひらがなのバランス、改行の仕方についてまで、かなりオープンに、細かく言及しました。気恥ずかしさはもちろんありますが、どうせなら全部内幕を見せてしまえ、と腹をくくった感じです。
―どんな人に読んでもらいたいですか?

やはりまず、一番読んで欲しいのは、<小説を書きたいと思っている人>です。昨日、ある新人賞の選考会があったのですが、何度か最終選考に残ったことはあるけれど、最後、どこか壁を突き破れないという方が多いんですね。そんな方々に何かしらヒントになれば…という思いはあります。
今は、昔と比べて「書くこと」自体のハードルは下がったと思います。昔、私が小説を応募していた当初は原稿用紙に手書きをしていました。100枚以上書くと手や腕が痛くなってきて、清書するだけでもひと苦労。だから原稿用紙に向かうときは、“居合い”をやるような気持ち、つまり真剣勝負で刀を構えるような、そんな気持ちで書いていました。ちょっと精神論になってしまいますけれど、それくらい神聖な部分だったんですね。
パソコンが普及した今は、手書きのころと比べて書く(打つ)スピードは格段に速くなったし、何より、無制限に直せるようになりました。これはこれで、ものすごく大きなメリットです。本書の中でも書きましたが、小説というものは「水墨画」よりも「油絵」に近いと思っています。つまりどんどん塗り重ねて直していくうちに、見えてくるものがある。小説も直せば直すほど質が上がる。ですから、私に関していえば、パソコンのおかげで、確実に書くもののクオリティは上がったと思っています。
それからもうひとつ、「書く」ハードルが下がった理由として、インターネットの存在も大きい。今や、SNSやブログなど誰もが気軽に発信できる時代です。携帯小説や、小説サイトなどで発表された作品からベストセラーが生まれることもまれにありますよね。
プロとアマチュアの違いについて、よく言われるのは、プロは消費者からなんらかの対価をいただいて生計を立てているという点。もちろん、書く側の執念や信念は、プロにもアマにも共通してあると思います。ですが、編集者や校閲といった、第三者の目、プロの手を経ているものとそうでないものとは、決定的に質が違う。お金を払って読んでもらうものかどうか、そこへの“責任”が違うんです。
私自身、プロの書き手となった今でも、編集者からさまざまな指摘をうけます。新人のころは、せっかく書き上げた原稿を、削ったり変更したりするのはとても辛かった…。ですが、編集者の指示に従うことで、もとのものより格段によくなるということを経験から学びました。本書では、そんなふうに、テクニック的な視点に加え、エンタテインメントとは何か、プロの書き手になることへの心構えなども盛り込みました。
―では、プロの書き手になるために、もっとも必要なことはなんですか?

ひとつは、本をたくさん読むこと。小説、とくにエンタテインメント小説は“読みやすさ”が命です。そのためには、豊富なボキャブラリーが必要で、ボキャブラリーを増やすには、本をたくさん読むことが一番のトレーニングです。私は昔から、読むものがなければチラシも熟読するほどの本の虫で、子供のころはお気に入りの本を何度も何度も暗記するくらい読んでいました。それらが今、私の血肉になっていると思っています。
それから、書きたいものがあるかどうか。書くことは、本当にエネルギーが必要です。まずは自分の中に「誰がなんと言おうと私はこれが好きなんだ、書かなきゃいけないんだ」という思いがあるかどうか。そして、その非常に個人的な思いに、いかにして一般性をもたせられるか。つまり、共感ですね。最終的に本というものは、読者があって完結するものです。書いただけでは意味がない。誰かが読んで、その人の頭の中で化学反応がおきて初めて、書いた意味がある。それをめざすにはどうすればいいかという道筋をこの本では書いているんです。
ですから、すでに何かを書いている人、書きたいと思っている人は、この本で書いていることをぜひ実践してください。実践してみて初めて、こういうことだったのかと腑に落ちると思います。
―ところで、貴志さんが小説を書いていて、一番楽しいのはどんなときですか?
ところがいざ書き始めると、一瞬にして現実に引き戻されます(笑)。思ったとおりに書けず、自分の力のなさを思い知る。ですから、プロット作りのときに感じた「これは面白い!」という燃え上がるような思いの“炎”に、薪をくべて少しずつ燃やしていくこと、つまりペース配分も大切になってきます。加えて、肉体的な体力と脳の体力。最後までめげずに、面白いと思ったものを小説という形にまできちんと書き上げること。執念と体力が必要なんです。
―「書く」体力を鍛えるために、貴志さんがしていらっしゃることはありますか?

んー、どうやったら鍛えられるんでしょう? 逆に私が知りたいくらいです(笑)。ただ、執筆に欠かせないもの、脳を強制的に「書く」モードにもっていくものはあります。まずはコーヒー。執筆前には必ずコーヒーを入れます。モカ系統、ブルーマウンテンが一番好きですね。書き続けているときはずっと飲んでいますから、「コーヒーは体によくない」なんていうニュースが流れても信じません(笑)。本当に稀ですが、夜も更けてくるとワインを飲みながら書いたりすることも…。プロにあるまじき行為だという先輩作家も大勢いらっしゃって、それはその通りだと思います。後で読み返すとほとんどがダメですからね。
もうひとつは、BGMです。『悪の教典』は、タイトルにもかかわってきますが、ELP(エマーソン・レイク・アンド・パーマー)のアルバム『Brain Salad Surgery』をかけていました。『ダークゾーン』もそうですが、殺りく系の作品は、ハードロックを大きめの音量で。『新世界より』は、ドヴォルザークの交響曲ですね。作品ごとにBGMを変えているんですが、これは私にとって非常に効果的です。自分の中でイメージを掻き立てる一因になりますから。
―最後に、貴志さんからメッセージをお願いします!
読書の楽しみは、好きな本を読んで楽しい時間を過ごすことに尽きますが、たとえば書き手が何を考え、どういうふうに作っているのかを知ると、理解が深まって、もっと楽しくなると思うんです。旅行先で美しい街並みに感動したとする。そのとき、そこにある建築物の知識やその歴史を知っていると、また違った角度でその街並みを楽しめる。そんなふうに、この本を通して、小説の違う楽しみ方を知ってもらえたらと思います。さらに、読み終わった後、「書くつもりはなかったけど、なにか書いてみたいなぁ」と思ってもらえたらこんなうれしいことはないですね。
取材・文/田中美保(スタッフ・オン)
貴志祐介(きし ゆうすけ) プロフィール

1959年 大阪生まれ。京都大学卒。96年 『十三番目の人格(ペ ルソナ) ISOLA』 でデビュー。翌年『黒い家』で日本ホラー小説大賞を受賞、ベストセラーとなる。2005年 『硝子のハンマー』で日本推理作家協会賞、08年 『新世界より』で日本SF大 賞、10年 『悪の教典』で山田風太郎賞を受賞。

















