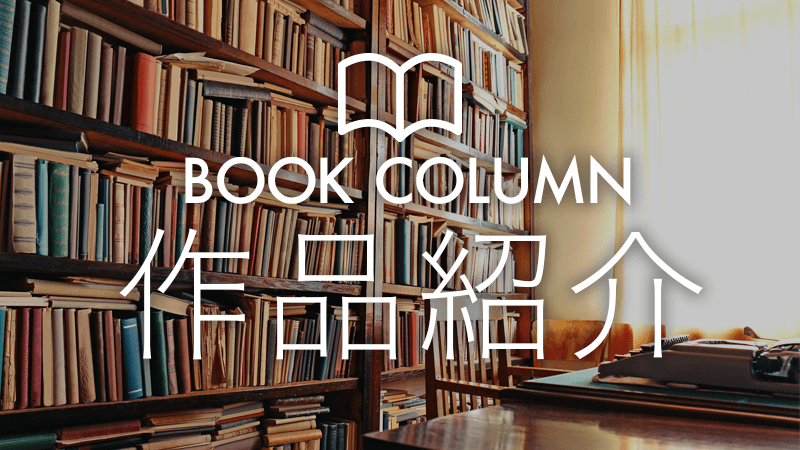
何が一番「ぼっけえ、きょうてえ」かと言えば…(ぼっけえ、きょうてえ)
何が一番「ぼっけえ、きょうてえ」かと言えば…
「教えたら旦那さんほんまに寝られんよになる。・・・・・・この先ずっとな」時は明治、岡山の遊郭で醜い女郎が寝つかれぬ客にぽつり、ぽつりと語り始めた身の上話。残酷で孤独な彼女の人生には、ある秘密が隠されていた・・・・・・。岡山地方の方言で「とても、怖い」という意の表題作ほか三篇。文学界に新境地を切り拓き、日本ホラー小説大賞、山本周五郎賞を受賞した怪奇文学の新古典。
遊郭の女が語りだす身の上話を、彼女の客だろうか、黙って聞いている。私たち読者は、その客に同一化して、じっと、女の語りを聞いていなければならない。この身動きの取れない感覚が、まずもって怖い。まるで、見つかったら捕えられてしまう状態で、息をひそめてなければならないような場所に、私たちは置かれるのだ。
微に入り細に入り、観察し、くまなく描写されるのではなく、余白を残すようにさりげなく語られる異常さ。
確かに妾は目や鼻が、左のこめかみに向けて吊りあがっとるよな。醜女とからかうお客だけじゃのうて、怯えるお客も結構おりますわ。
どう吊り上っているのか、なぜ吊り上っているのか、おそらくは、暗闇に近い空間なのだろうし、女の語りだけが、空中に舞い、やがて消えてゆくだけ。私の意志が働く余地はどこにもない。
恐怖とは、自由意思の制限から生じてくる身体的感覚ではなかろうか。
しばしば私たちは、怖い話を語りを通して聞かされる。放課後の怪談、キャンプ中の車座での怪談、ドライブの最中の怪談。暗い夜道をドライブしているときに怪談などを話しているカップルには、たいてい惨殺フラグが立つわけだが、そんな拘束的状況こそ怪談のリアリティがいや増す刻なのだ。
そのような拘束的状況を、冒頭の数ページで本書は、つくりあげてしまうのだ。
山間部の寒村の貧しさから生じる悲惨は、日本全国どこにでもあるはずだ。遊郭の女が体験した悲惨もまた、複合的に組み合わされているから残酷というわけでもない。何が怖いのかと言えば、この世の中とその悲惨が地続きゆえに、怖いのである。もちろん遊郭の女が、どこまで嘘を盛っているのかは定かではない。全ては、怖がらせるための空想に過ぎないかもしれない。虚実皮膜の間、という言葉を思わせる。ただ、そこに、観てきたかのようなリアリティのある言葉が挿まれると、より怖さが増すのである。
赤子を引きずり出す前に、まず糞を出させる。血と糞の匂いが家中にしみついて、夏はかなわんかったで。まぁ、屎糞地獄に堕ちる準備と思やええんか。
全体的な真偽の不確定さと、細部に宿るリアリティ。荒唐無稽だと思いつつも、細かい部分で本当らしさが積み重ねられると、私たちはダブルバインド状況に陥り、思考を放棄したくなる。そんなおり、浸潤してくる怖さの記号がある。
言葉は、非日常的な場面も、日常と連結して描ける便利なメディアだ。黒い白猫も、三本足のユニコーンも、たやすく召喚することができる。だからこそ、ホラーのメディアとして、小説は何かを持ちえるのではないだろうか。
おっ母より、その後ろの痩せた稲穂が目に焼き付いとるな。立ち枯れた山には水子とも烏ともつかん泣き声がこだまして、あねぇに空は青いのに川の水は泥色で。おっ母の後ろには、死んだおっ父が立っとった。肩すぼめて、立ち枯れた木みてぇじゃった。なんでか目玉がぽっかり空洞になっとってな。何も見とらんかった。
淡々と、このような語りを、書き記すことのできる作者の方が「ぼっけぇ、きょうてぇ」と思った読者は、私だけではあるまい。(田中里尚)


