
LGBTを読みとく ──クィア・スタディーズ入門
森山至貴
ちくま新書
結構真剣に読まないと、筋(=論理)を十分には追えないかも。
この本を手に取る人は、と著者に挑発されて、若干慎重に読み進めました。基本的知識のない私には違和感をもたらす部分があるのですが、そのあとにそこに至る論理が示されていて、(多分)理解できました。理解と同意は違うのですが、多分、概ね同意できたように思います。この論理を組み立てて、一見正しいことを本当にそうなのかと検証する学問の営みが、性自認、性志向のみならず、全ての私たちが「なんとなく」正しいと感じていることに対して、必要なのでしょう。それが、日本の社会から欠落し始めているような気がしてなりません。「LGBT」についての学問を知りたい人のみならず、今日本を覆っている短絡的な思考(とも言えないもの)に違和感を持つ人は、ぜひ頭の体操に、この本を。
0投稿日: 2018.06.25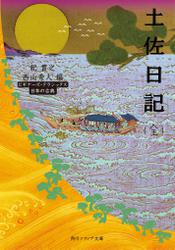
土佐日記(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典
紀貫之,西山秀人
角川ソフィア文庫
有益な、フォーマットでした。
学校時代、古文をほとんどパスして、最小限の資源で単位を取った私には、最適のフォーマットです。 飛ばしたくなるのを我慢して、本文(古文の部分)も読みました。私にも我慢して読める程度の長さにまとめられています。 そして、ここに記載されている人と人の関わり・交わりを(解説に助けられながら)味わいつつ、確かに人は1000年前と同じと人だと、嬉しいやら悲しいやら。 このシリーズ、読破してしまうかも。
1投稿日: 2017.03.02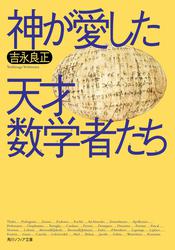
神が愛した天才数学者たち
吉永良正
角川ソフィア文庫
数学に興味を持つことと、数学者に興味を持つことは、同じではないのでしょう。
私は、数学に興味はあるけれども、十分には理解できない方です。人間には興味があるけれども、それは数学者である必要はない。 ということで、どちらの観点からも、少し中途半端な感じでした。もう数を少し絞って、詳しく書いてもらったら、嬉しかったかも。 筆者の意図とは違うかもしれないけど、数学に興味を持っている若者が、数学と格闘している合間に、これを読んで気分転換するのには、いいかも。
2投稿日: 2017.03.02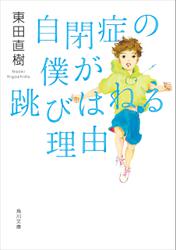
自閉症の僕が跳びはねる理由
東田直樹
角川文庫
全体が、一つの詩です。
なぜ自閉症という特徴を持った個人が、なぜその行動をするのか、なぜその行動しないのかを、深い自己への洞察に基づいて記載していて、一つ一つ、その内容が納得できます。そして、その多くが、自閉症という特徴を持たない個人にも、共通する部分があると気付かされます。 自閉症という特徴を持つ人を理解したいと感じる人にとって、本当にありがたい、貴重な本となるでしょう。と同時に、自閉症という特徴を持つ人々に、敬意を持つことでしょう。 言語的なコミュニケーションの障がいにより、自己の内面と他者との間の障壁を持つが故の、その深い自己及び他者の探求によるものでしょうか、全体が詩のような美しさを有しています。
2投稿日: 2017.01.24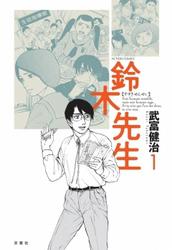
鈴木先生 1巻
武富健治
漫画アクション
これは、脅威です。教師になりたいと、思わされました。
1〜2巻目(くらいまで)を読み、いい本だな。。。と感じながら、次に手を出すのを止めてしまった人々には、是非、続きに手を伸ばし、それなりの時間を割いて、読んでみてください。 ただ、異質な表現で、慣れるまで、少し苦労するかも。どこかの巻のあとがきにもあるように、最初のうちは、笑うべきところなのか、深刻なところなのか、分からなかったりして。 本題です。言葉の力と、ティーンエイジャーの思考力、他者に共感する能力に絶大な信頼をおき、言葉の山塊をもって、個々の人間とそれを取り巻く「社会」の多様性とその多様性の貴さ、その貴きものを理解できるために、われわれが自ずからを鍛えなければいけないこと、を滔々と、ときに訥々と、紡いでいます 世の中の、決めることのできる指導者、強い指導者などと自称する独裁的な(=複雑な事象を鑑みることをできず決定できてしまう)指導者とは対局の、人類の哲学的思索の到達点の一つ、でしょう。 この言葉の山塊を伝え、その意味を理解し、他者の立場に思いを致す時間を、授業では到底、持ち得ないんでしょうね。 やっぱり、漫画家の方がいいか。 無学なものでスペイン語を解さないのですが、鈴木先生第6巻の表紙にある横文字は、「大衆」を身分ではなく、「他の人々と同じあることに安心し、あるがままの自分に満足する人々」と規定し、「選ばれし人々」とは「孤独に耐え、成長を求める人々」である、としたオルテガの言葉だそうです。
1投稿日: 2016.11.17
スポーツ遺伝子は勝者を決めるか? アスリートの科学
デイヴィッド エプスタイン,福 典之,川又 政治
ハヤカワ文庫NF
読み応えのある、面白い本です。
驚嘆するほどのデータを駆使して、説得力をもって、”事実”を示していき、どんどんと引き込まれて行きます。 但し、みんなが既に、「知っていること」を、ではあるのですが。。。 陸上をかじったことがあれば、なじみの名前の裏にある物語りに、スリルを感じるでしょう。 また、ここで示される事実は、トリビアとしても強力なものに。。。え? 陸上のトリビアでは盛り上がらないって? まあ、そういわずに。面白いですよ。
0投稿日: 2016.11.07
イン・ザ・プール
奥田英朗
文春文庫
不覚にも、電車の中で、ブファッっと。
ばかばかしくも、面白い、か、面白いけど、ばかばかしい、か。貴重な電車の中の時間を、有意義に過ごしたい方には、お勧めしません。 ばかばかしくも、面白い時間を欲している方には、選択肢の一つです。 現代社会の病理を記載していまですが、解答は呈示していないことをご了解ください。
0投稿日: 2016.09.16
大人のいない国
鷲田清一,内田樹
文春文庫
子どもたちだけでも回せるシステムができた。
そこまで、日本が進歩したため、日本から大人がいなくなったと。そうかも知れない。。。私も、55歳になったけど、子どもっぽいよね。。。 愛国心についての論証は、興味深いものでした。以下、若干の抜粋 「同胞たちを糾合することには熱心だが、自分と意見を異にする人々をも包括しうる水準を探り当てることには不熱心な人間を「愛国者」と呼ぶことは私にはできない。」 「集団が維持されるための必須の、唯一の条件は「同胞については、おのれ一個の好悪や正否や利害得失と行った主観的判断を停止させること」」 「「不快な隣人たち」を国民国家のフルメンバーとして受け入れること。それが現代に残された唯一の愛国心の形」 ものを考えることはしんどい。でも、考えることが、大人の責任。大人の責任を果たしていない人たちに、公的な組織を率いる資格は無い。でも、一見できちゃっているのが、進化した日本、ということでしょうか。 読んでいて楽しくはないけど、でも、大人になるため、読んどいた方がよさそうね。
0投稿日: 2016.09.16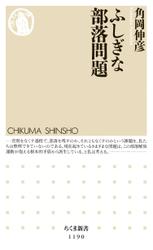
ふしぎな部落問題
角岡伸彦
ちくま新書
にほんに、期待を持てる本です。それに加えて、攻撃的なところがなく、バランスがとれていて、読みやすい。
大阪に生まれ育ち、意識することなく同和教育の存在を感じ、政党との対立に生臭いものを嗅ぎつつ、でも放置してきた欠損した知識のパズルが、それなりにはまって、視界がだいぶ良くなりました。 日本の部落差別が、人種差別とは違う要素を含んでいて、それが問題の構造を複雑化しているという呈示は、呈示されるまで、気がついていませんでした。きちんと問題意識を持っている人たちには、自明だったのかもしれませんが。。不勉強を反省。 橋下氏にはまったく感心せず、仲間内の与太話では同窓会から追い出すべきだ、などとくだをまいてますが、ここに記載されている件については、橋下氏に悪意をもつ人物の、もしくは自分をpromoteしたい人物の、質にあきれ果てました。 最後の章、主人公たちの、さり気ない、だけどまさに「正しい」行動に、久しぶりに心の明るくなる、にほんの将来に希望をもてる思いをしました。 一言、おすすめです。
0投稿日: 2016.08.23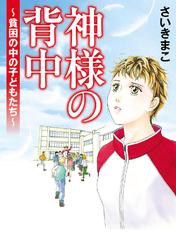
神様の背中~貧困の中の子どもたち~
さいきまこ
フォアミセス
神様の目が届かない子どもがいるんじゃない、"子どもたちに背を向けているのは神様なんかじゃない 私たち大人だ"
戦慄を感じる、phraseです。 社会のシステム、の問題なのでしょうが、私たち一人一人の心の問題、であるべき、という問いかけなのでしょうか。 本当に偶然、読み始める直前にポプラ新書の「貧困の中の子ども、希望って何ですか」を読み終えたところだったので、この物語の真実性が迫ってきました。 現在のにっぽんで、自助と自己責任を唱える人たちには、対極にある考えで、共感困難でしょうか。 でも、そうではないと感じている人たちには、是非読んでもらいたいと思います。そうすれば、にほんが、より優しく、素晴らしい国になるような気がします。 ところで、ポプラ新書の「貧困の中の子ども、希望って何ですか」の7章、英国の挑戦で触れられていますが、英国の労働党のトニー・ブレアが、"Education!, education!!, education!!!"と叫んで総選挙を戦ったときに、ちょうどロンドンに住んでいました。 ブレアの労働党は、メイジャーの保守党に圧勝しました。それはそれは、英国全体が高揚に包まれていました。日本でも、そのような日が来ればいいですね。
0投稿日: 2016.08.12
間 文理さんのレビュー
いいね!された数20
