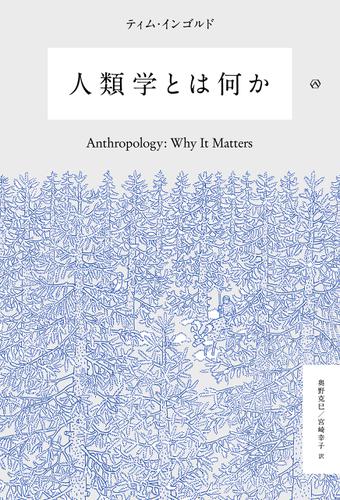
総合評価
(17件)| 4 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ他の方も書かれている通り、「人類学とは何か」というタイトルではあるが、入門書的な内容ではないと感じた。人類学に全く明るくない私には難解であり、翻訳書ということもあってか、言い回しが回りくどく難解であると感じる箇所があった。 「人類学とは何か」というよりかは、「人類学再考」というようなものだろう。人類学についてある程度知識があるものならば本書の内容を理解し、より議論を深めることが出来るのかもしれない。
0投稿日: 2025.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこういうガチ賢い系の本初めて読んだけど 理解できることとできないとこがあってすごく楽しかった。自分には良い難易度だった。 人類学とはっていう題名だけど「学問とは何か」についても新たな視点を得られた。科学をみんな信じてるけど、実験室でデータを集めて良い感じに解釈してるのをそれって真実として信じきってしまっていいのか、みたいな。(やばい語彙力無い) 筆者は元理系だけど、そういう科学で正しいと言われてることは全て正しいとも限らないという脆弱性を感じて、より真髄の当たり前から疑う人類学というものに入り込んでいったそう。人類学は哲学とも社会学とも似てるけど違って、(どう違うかの詳細はしっくりきたけどちょっと忘れた、読み直そ。)人々に教わる。何か重要なデータを得ようという関わり方ではなく、フィールドワーク先の人達を先生だと思って、人間が生きる上で大切なことを全て学びとる。そのフィールドワークで必ずしも実用的な結果や、人類の新たな発見が得れるとも限らない。けど、それでも良い。人類学は思いやりの学問だ。この激動の時代、人類がこの先どうなるべきかを考える上で大切な学問だ。なんか他の学問と全然目的とかが違う、ゆるい?ぼんやりだなと思った こんな理解で合ってるかなー?!人類学とは何か知れると思って読む人が多いと思うけど、一言でパッと表せないのが人類学だなーってことがわかった。人類学の本初めて読んだけど、この本を読んだあと、なんだかワクワクするぼんやりした輪郭が見えてきた。もっと人類学の本読みたい。 自分は生まれた時から出来るだけ自分と違う種類の人間と関わって、人を観察しまくって、その人が何を大事に生きてるのか、自分との違い、その違いはどこから来るのか、つまり生きていく上でどの要素が必要でどの要素が必要ないのか、悪とは、善とは、人それぞれ違うのだな、真理はどれなんだ、そもそもあるのか、ないのか、自分はどの価値観のスタイルで生きていこう、どう生きるべき?と常に問うてきた。ある意味、既に文化人類学者かも。私が、できるだけ偏らないように無造作に様々なコミュニティに飛び込んでいたのは、フィールドワークということかな。遠くの村の自分が持っている価値観とできるだけ違うものを持っている人達と会い、相違点、共通点を探して普遍的なものを見つける。という営み。好き。文化人類学者になろっかな。♪ めちゃ拡大解釈してるかもしないし 理解できないところも多々あったからまたぜっっったい読み直したい!
0投稿日: 2025.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ150ページほどの短い文章ながら、読めば思索が深まる体験を得られる、そんな素晴らしい本に出会いました。 本書は、ティム・インゴルドの研究領域である「人類学」を改めて問うてみた内容となっています。 インゴルドの本は、アート・芸術・建築関係から邦訳された経緯がありますが、本書はそれらとはまた違った学問について語られています。 では、人類学とはなんなのか?そして、インゴルドのいう人類学とはどんなものなのか? 第一のポイントは、他者を真剣に受け取ること、です。そのことが本書の第一章で語られています。今までの人類学は、他者を研究の対象とすることでした。フィールドワークにおいてもそれはあり、観察する側と観察される側という線引きで、いわゆる先住民を「対象」にしてきたそうです。 でも、インゴルド人類学のポイントは、他者を対象化して観察するのではなく、他者とともに研究するそうです。このやり方を「参与観察」と呼ぶとインゴルドは語っています。 これは、例えば医療の現場などにおいても言えることだと私は思います。治療する側と治療される側というふうに、病気をもった人を「対象」にすることと近いと思ったからです。でも、そこに本当のケアはあるのでしょうか。 それはともかく、最初に私が書いたように、思索が深まる体験としては、「知識と知恵」の考察や、「知るとある」の考察や「類似と差異」の考察が、本書を読むことによってダイレクトにインゴルドの思索を流し込めるので面白い体験でした。 また、近代西洋人は空想上の生きものであった、という内容の指摘はスリリングかつドキドキしながら読み進めました。こちらも非常に面白い考察でした。 インゴルドの学究人生を辿る半自伝的な内容でもある書で、人類学の史歴や学会界隈の激震と分派などまで綴られています。 読み終えて、私は、人類学のほうが、哲学よりも哲学的で面白そうだなという感じがいまはしています。 向き不向きもあるでしょうけれど、哲学や人文科学に興味のある方や、思索を深めたい方は読まれることをオススメいたします。
15投稿日: 2025.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ総合学(学とすらも呼ばないものか)としての人類学。 人は皆、最高の人類学者だ!と呼べるような社会に暮らせたら。
0投稿日: 2025.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1章:人類学とは「他者を真剣に受け取る」哲学―生への問いと参与観察 本書『人類学とは何か』は、ティム・インゴルド氏が人類学の本質を問い直す論考集です。第一章では、人類学を単に異文化を研究する学問ではなく、「私たちはどのように生きるべきか?」という根源的な哲学的問いに対し、世界中の人々の知恵と経験を結集して取り組む、「世界に入り込み、人々と共に行う哲学」であると定義します。地球環境の悪化や格差拡大といった現代社会の危機的状況において、人類学は情報や知識を増やすことではなく、他者の生き方から学び、人間の生の可能性について想像力を豊かにすることを目指します。そのため、知識(物事を固定化し説明しようとする)よりも知恵(世界に飛び込み他者に注意を払い気にかける)を重視し、対象を客観視するのではなく注意を払いよく見て聞く「参与観察」を不可欠とします。これは単なるデータ収集ではなく、他者と共に学び教育されるプロセスであり、人類学の第一原則「他者を真剣に受け取ること」―すなわち、他者の行動や言葉、そしてそれが私たちの世界観に提起する挑戦に向き合うこと―に繋がります。カナダ先住民オジブワの「石も生きている」という考えを例に、認識論から存在論への移行を示唆し、アニミズムを「生の詩学」として捉え直すことを提案しています。 第2章:「自然/文化」の二分法を超えて―関係論的思考で捉える人間の類似と差異 第二章では、人間理解の軸となる「類似」と「差異」をめぐり、伝統的な「自然」(普遍的・本源的)と「文化」(後天的・変化するもの)の二分法が抱える問題点を批判的に検討します。インゴルド氏は、この二分法が特殊性と普遍性、精神と物質といった対立を整理しきれていないと指摘し、ジョルジョ・アガンベンの「人類学的機械」(人間を他の生き物から切り離し文化と生物学を分断する近代的人間観)の解体を人類学の任務とします。「自然か文化か」という原因論の罠を警告し、甘いものへの嗜好や蛇への恐怖といった生得的とされる特性も、特定の環境における成長と成熟の過程(個体発生)を通じて発達するものであり、人間の差異は共通の土台に後から加えられるのではなく、差異化は最初の時点から存在すると論じます。私たちは絶えず自身を創造し合う集団的自己形成の過程(歴史)の中にあり、自己同一性も固定的なものではなく他者との関係性の中で流動的に形成される「関係論的」なものであると捉え、「西洋/非西洋」といった二項対立を超え、差異を通じて結びつき他者へと開かれる「私たち」という概念を提示します。 第3章:人類学の誕生と分裂の軌跡―啓蒙主義から三領域体制、そして現代へ 第三章では、人類学が成立した歴史的経緯と、その過程で「自然科学」と「人文学」の枠組みの中で経験してきた位置づけと内部的分裂が詳述されます。インゴルド氏は自身の学生時代の経験を交え、両者を統合しうる学問として人類学に惹かれたと述べます。人類学は啓蒙主義の思潮の中で育まれ、理性、寛容、自由を掲げ人間性を解放することを目指しましたが、「文明化」の物語は「未開」という概念を必然的に生み出しました。チャールズ・ダーウィンの進化論は大きな衝撃を与え、『人間の由来』で精神の進化が描かれ、自然選択の概念は社会進化論へと繋がり、19世紀後半には形質人類学(人体の進化)、考古学(人工物の進化)、社会・文化人類学(制度・慣習・信念の進化)という「三つの領域」が確立されました。しかし、頭蓋計測などに基づく人種分類や人種間の優劣を論じる偏見も生まれました。第二次世界大戦後、ホロコーストの反省から人類の平等の原則が確立され、現生人類は単一の亜種として再分類されます。社会人類学では機能主義が台頭し進化論的アプローチから離れ、生物学的遺伝(人種)と伝統の継承(文化)の分離が進み、アメリカではフランツ・ボアズらにより文化的多様性に注目する文化人類学が発展しました。しかし、これらの学問領域は現代においてもなお分断された状態にあるとインゴルド氏は指摘しています。 第4章:「社会的なるもの」の再定義―構造からプロセス、生物社会的存在としての人間 第四章では、20世紀の社会人類学における主要な理論的変遷を辿りながら、「社会的なるもの」とは何かという問いが深掘りされます。アルフレッド・ラドクリフ=ブラウンの構造機能主義(社会生活の形式の比較研究)から、クロード・レヴィ=ストロースの構造主義(社会生活を記号や象徴の交換=コミュニケーションとして捉える)、フレデリック・バルトらのトランザクショナリズム(個人の価値交換の相互作用として社会組織を捉える)へと理論は展開しました。1970年代には構造主義的マルクス主義(生産活動と社会構造の関係性)や文化生態学(環境適応における文化の役割)が登場しますが、インゴルド氏は人間を生態系システムと社会システムの二元論で捉えることに限界を感じ、「社会関係をもつことと有機体であることは、人間存在の二つの面なのではなく、同じ一つのものだ」という認識に至ります。E.O.ウィルソンの社会生物学論争(利他的行動の遺伝子レベルでの説明)や、遺伝的つながりと社会的カテゴリーをめぐる親族関係論争を経て、インゴルド氏は、遺伝的傾向と社会的意味づけを組み合わせる「相補理論」をも批判し、親族関係をケアの実践の中で実現される生物学的かつ社会的なものと主張。人間を「生物社会的な存在」として、他者との関係が自己を構成し、相互作用ではなく内側で働きかけるダイナミックなプロセスとして社会関係を捉え直し、有機体を他者との関係において構成されるものと見なす、プロセス的、発達的、関係論的な新たな生物学の必要性を結論づけています。 第5章①:現代社会と人類学の距離―公的役割の不在と「文化」という専門性の隘路 最終第五章では、現代社会における人類学の意義を改めて問い直し、未来に向けたあるべき姿が提示されます。インゴルド氏は、人類学が「どうすれば生きるのにふさわしい世界をつくり上げられるのか」という問いに、人間経験の重みを結集する唯一無二の学問であると再確認しつつも、重要な問題に関する公的な議論において人類学者の声がほとんど聞かれないという現状を指摘します。この原因として、人類学が明確な専門知識や体系的な知識を提供するのではなく、むしろ既存の前提を揺るがす傾向があること、そして「文化」を専門とすることが資本主義体制下では周縁化を招く危険性を分析します。他の学問が文化概念を取り入れ始めている一方で、人類学がそれを捨てようとしている皮肉な状況や、科学的知識が唯一の真理であるとする「科学主義」への批判的スタンスも、人類学の公的役割の不在に影響していると考えられます。 第5章②:相対主義の壁と民族誌の限界―ステレオタイプを超えた対話のために 人類学が未来に向けて乗り越えるべき課題として、まず「文化相対主義」の問題が挙げられます。文化相対主義は、あらゆる行動が「文化の一部」として許容されうると解釈され、人類学が倫理的な羅針盤を持たない学問と見なされる危険性があります。インゴルド氏は、強硬な相対主義ではなく、寛大かつ批判的な精神で他者との対話に参加することが求められると主張します。次に、「民族誌中心主義」が批判されます。民族誌を参与観察と同一視し、他者の生の記述に終始することは、人類学者の独自の声を封じ込め、異文化に関するデータ提供者の役割に矮小化してしまうと警告。人類学の真の目的は民族誌作成ではなく、他者との教育的経験から生の可能性を思索することにあるとし、アートやデザインなど、民族誌以外の多様な方法で対話に参加する可能性も示唆されています。さらに、化石探索者やマヌケな人類学者といった大衆的ステレオタイプや、それらが依拠する起源や真正性の神話を取り除く必要性も訴えられています。 第5章③:未来の人類学―生を変容させる「気づかいの倫理」と実践への展望 未来の人類学の再構築に向けて、インゴルド氏は三つの課題を提示します。第一に、人類学を個々の下位領域の寄せ集めではなく、経験の統合を目指す単一の学として再確立すること。これは、特定の知的領分を主張するのではなく、人間経験の連続的な風景の中で問いを追跡する「反学問」的な性格を持つとされます。第二に、人類学を分裂させてきた社会文化的な傾向と生物物理学的な傾向の間で新たな調停を打ち立て、人種と文化という負の遺産を克服し、歴史の中で自らの生を生産する存在として人間性を捉え直すこと。第三に、記述的・分析的であると同時に思弁的・実験的でもある未来の人類学が、いかに生を変容させる力を持つかを示すことです。未来の人類学は、伝統的な科学よりもアートに近く、パウル・クレーの言うように世界を写し取るのではなく、関係とプロセスの中で物事を気づきのフィールドへと生成させる役割を担うと示唆されます。その真の貢献は文献の蓄積ではなく「生を変容させる力」にあり、最終的に人類学者を駆り立てるのは知識への希求ではなく「気づかいの倫理」であると結論づけ、他者との対話を通じてすべての人にとって居場所のある世界を共に築いていくことを目指す、実践的な学問としての未来像が提示されています。
0投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログたまに人類学に分類される本を読むが、人類学ってなんだろ?と思ってしまうので、読んでしまったのだが、 本書は人類学についての入門書とかではけっしてなかったと思う。 むしろ、著者が自身の経験などから、人類学が歩んできた道のりとこれからどうあるべきかを章ごとにテーマを設けて書いているような本だと思うので、 もっと人類学を学んできて、改めて人類学ってなんだろ?となってから読むべき本だったかもしれない。
9投稿日: 2025.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ→https://x.com/nobushiromasaki/status/1833990328959074642
0投稿日: 2024.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しい。。 解説にも書いてあるように意見があっちこっちに散らばっていて一貫性を持って読むのがなかなか困難 また、本書全体を通して主張されている人のある面を切り出してみるのではなく一つのものとして捉えるという考え方もなんなく納得できる気はするものの理解は難しい
3投稿日: 2024.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類はどう生きるべきか?を人類学の問いとするというのが面白い。生を開いていく過程として捉えるのはフランス哲学と繋がるように思う。とりわけ、人種主義の問題を取り除くために、生物学的形質と文化的形質を相互に影響し合うものとして、新しい生物学と新しい人類学を打ち立てる箇所に進化論哲学的な可能性を感じた。
2投稿日: 2024.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ『人類学とは何か』 薄い本だがティム・インゴルドの思想を受け取れる重厚さがある。我々は他者との関わりの中で人間となるんだな。 あと自分は世界を測ることのできる研究対象として考えていたんだなと感じる。どのように生きるかを他者とともに学び、人間の生を考えていきたい #読了 #君羅文庫
1投稿日: 2022.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ他者「を」学ぶのではなく、 他者「と」学ぶ。 分けられたものを統合する。 偏見や常識と抗う。 生そのものを観察して思索する。 知識ではなく、思索が許されている。
1投稿日: 2022.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いと思うし、咀嚼できたらとても有益と思えるので星4つ。が、ところどころ「?」が頭の中に浮かんでしまう箇所がまだまた多いのも事実。インゴルドの他の本を読んでみてまた戻ってこようと思う。
1投稿日: 2022.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログうーむ、残念ながら現在、私個人的にはこういう方面へあんまり食指が動かないらしい。 機会があったら再度チャレンジするかも〜。
1投稿日: 2021.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログインゴルドの著した本編は、簡単には理解が難しい。詩的な表現も多いが、印象深い言葉が多いのも事実。訳者の丁寧な解説が読後の頭の整理に役立った。
1投稿日: 2021.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに反して人類学の素養がなければなかなか読み解けない部分が多いけれども、思いもよらない分野にまで話題が波及し、人類学の巨大さの一端を知ることができた。
2投稿日: 2021.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類学を始め、人文科学、自然科学に一定の素養がないと、著者が、これまでの人類学の、どのような点に問題があると考えているのか、どうすべきと考えているのかについて、なかなか理解が難しいだろうと思う。 著者は言うー私の定義では、人類学とは、世界に入っていき、人々とともにする哲学である。 実に魅力的な言辞であり、著者は、それがどのようなものであるか、なぜそうした捉え方が必要とされるのかを、幅広く、深く考察していく。 訳文のおかげもあるのだろうが、著者の論旨自体は明晰であるし、論点も明確に示して叙述されているのであるが、いかんせん、当方の読みがついて行けないのが残念。是非再チャレンジしてみたい。
2投稿日: 2020.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか頭に入ってこない箇所もあった。 そもそもの素養が無い。 たまに分かりかける(気がする)。そうすると急にドライブがかかったみたいになる。 こういう読書もたまにはいい。
2投稿日: 2020.05.14
