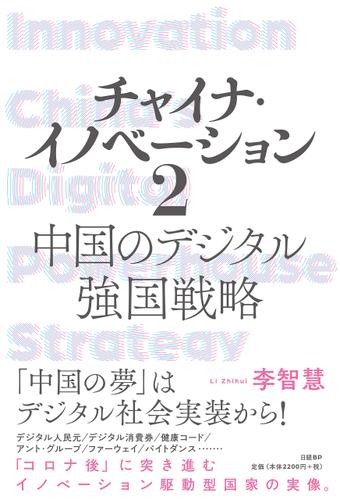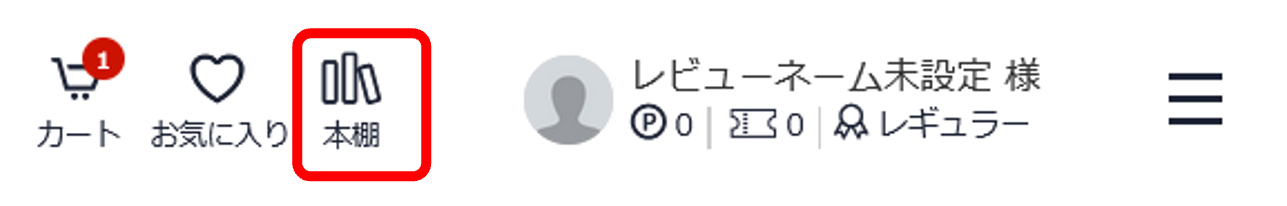チャイナ・イノベーション2 中国のデジタル強国戦略
李 智慧(著)
/日経BP
作品情報
デジタル人民元、デジタル消費券、健康コード、アント・グループ、ファーウェイ、バイトダンス――「コロナ後」に突き進むイノベーション駆動型国家の実像を第一人者が描く。「いち早くコロナを抑え込んで経済成長がプラスに転じた中国は同年11月、「第14次5カ年計画と2035年までの長期目標」を発表した。この計画には『製造強国』『品質強国』『デジタル中国』といったキーワードが並び、『デジタル中国』建設を国家戦略として位置づける意欲的な内容が盛り込まれていた。」(本書「はじめに」から)
もっとみる
商品情報
以下の製品には非対応です
この作品のレビュー
平均 3.4 (5件のレビュー)
-
新型コロナの影響で世界経済が低迷する中、デジタル技術により早々にコロナを抑え込み、経済を回復させた中国。着々と進むこの国の“デジタル強国戦略”を明らかにする書籍。
新型コロナの影響が今後4、5年で収…束した場合、名目国内総生産(GDP)で、2028年にも中国は米国を上回る。鄧小平の改革開放から、わずか40数年。経済やテクノロジーで、中国が大きく変貌した背景には、「デジタル経済」の成長がある。
中国はデジタル技術を駆使し、官民一体で新型コロナの蔓延を防いだ。例えば以下のようなもの。
・テック企業のAI技術等を用いて、感染者の情報を公開した。
・ブロックチェーン技術を活用して、支援物資のマッチングプラットフォームを開設し、物資の確実な配分を支援した。
中国政府はメガテック企業のモバイル決済プラットフォームと組み「デジタル消費券」を発行した。消費金額に応じて割引ができる電子クーポン券のようなもので、これによって
国民の消費が喚起され、経済回復につながった。
デジタル消費券のような施策を迅速に打てた背景には、コロナ以前に整備された国民IDによる認証基盤、モバイル・インターネットをはじめとしたデジタル基盤の存在などがある。
中国は、トップダウン方式で、着実にデジタル戦略を進めてきた。その歩みは、次の通り。
①情報化インフラの整備(1978~1990年)
②インターネット化への転換(1990~2000年)
③情報化と工業化の融合を促進(2000~2005年)
④デジタル国家戦略の形成初期(2006~2013年)
⑤ネット強国へ(2014~2016年)
⑥デジタル国家戦略の確立(2017年~)続きを読む投稿日:2021.12.26
デジタル社会においても中国の台頭は目覚ましい。本書では、コロナ危機における中国の素早く効果的な対応に国内テック企業のデジタル技術が大きく貢献したことをはじめに指摘し、次いで中国政府のデジタル政策の歴史…をまとめたあと、テンセントやアリババ、ファーウェイなどの企業について詳細に説明する。そしてデジタル人民元の検討の動向について説明し、日本への提言で締めくくる。
私は日本企業が中国企業と比べて圧倒的に力不足というわけではないと感じているが、中国政府の施策についての説明を読んで、それを政治が活かしきれていない情けなさを感じた。発展途上国から脱しようとしてきた中国は、その経済成長の柱としてデジタル技術の発展を推し進めているのであり、その力の入れようは凄まじい。熱意だけでなく、多数の専門家を動員して具体的計画を幾度も練り上げ、その多くを達成する行動力がある。
なお本書において、日本との簡単な比較もされてはいたが、より詳細に統治構造の差や数字の上での規模の差について説明されていればよりよい内容になると感じた。
各企業の説明は技術的な部分も含めてかなり詳細に書かれており、知らないことも多く大変参考になった。特にファーウェイについて書いた第4章は、創業者について伝記のように仰々しく叙情的に書かれた部分が多くを占め面白かったが、人柄や過去の苦労、現在の強さをよく物語っていた。米国の対中制裁の影響や結果についてもよく書かれており参考になったが、一方で肝心のバックドア疑惑については全く触れられておらず、筆者の意見を聞きたいと感じた。(その後のバイトダンスの章では筆者の批判的な受け止めが書かれている。)
中国人民元の動向についても十分に説明されており勉強になった。今後が注目されるところである。
本書は中国のデジタル政策と主要デジタル企業について総じて詳しく記述しており、有意義な一冊である。政府の規制のあり方についてもところどころで述べられており参考になった。ただし、中国の発展を語るにおいて避けては通れないはずの非民主的な政治体制について意見どころか説明もないなど、(筆者の立場上やむをえないのであろうが) 批判的な記述がほとんどみられない点に注意し念頭に置いて読む必要はある。とはいえ本書で説明された中国の強みに偽りはなく、日本も大いに参考にすべきであると感じる。続きを読む投稿日:2021.12.05
新刊自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。
- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!
- ・買い逃すことがありません!
- ・いつでも解約ができるから安心!
※新刊自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新号を含め、既刊の号は含まれません。ご契約はページ右の「新刊自動購入を始める」からお手続きください。
※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。
不定期に刊行される「増刊号」「特別号」等も、自動購入の対象に含まれますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)
※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。
※My Sony IDを削除すると新刊自動購入は解約となります。
お支払方法:クレジットカードのみ
解約方法:マイページの「予約・新刊自動購入設定」より、随時解約可能です続巻自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。
- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!
- ・買い逃すことがありません!
- ・いつでも解約ができるから安心!
- ・優待ポイントが2倍になるおトクなキャンペーン実施中!
※続巻自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新巻を含め、既刊の巻は含まれません。ご契約はページ右の「続巻自動購入を始める」からお手続きください。
※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。
不定期に刊行される特別号等も自動購入の対象に含まれる場合がありますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)
※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。
※My Sony IDを削除すると続巻自動購入は解約となります。
お支払方法:クレジットカードのみ
解約方法:マイページの「予約自動購入設定」より、随時解約可能ですReader Store BOOK GIFT とは
ご家族、ご友人などに電子書籍をギフトとしてプレゼントすることができる機能です。
贈りたい本を「プレゼントする」のボタンからご購入頂き、お受け取り用のリンクをメールなどでお知らせするだけでOK!
ぜひお誕生日のお祝いや、おすすめしたい本をプレゼントしてみてください。※ギフトのお受け取り期限はご購入後6ヶ月となります。お受け取りされないまま期限を過ぎた場合、お受け取りや払い戻しはできませんのでご注意ください。
※お受け取りになる方がすでに同じ本をお持ちの場合でも払い戻しはできません。
※ギフトのお受け取りにはサインアップ(無料)が必要です。
※ご自身の本棚の本を贈ることはできません。
※ポイント、クーポンの利用はできません。クーポンコード登録
Reader Storeをご利用のお客様へ
ご利用ありがとうございます!
エラー(エラーコード: )
ご協力ありがとうございました
参考にさせていただきます。